体外離脱体験2

学生の頃、ひょんなことから、体外離脱を体験した私は、体外離脱を意図的に行えないかと、体外離脱について書かれた本を参考に、何度か挑戦をしました。
どういう時に体外離脱が、起こるのかと言うと、眠りと覚醒の中間状態です。
体は眠っているけれど、意識はまだ、目覚めている状態の時です。
金縛りの状態に似ていますが、金縛りの時は、緊張してしまうせいでしょうか、体を抜け出すことはできません。
意識ははっきりしているのに、肉体は動かせませんし、意識の体も動きません。
これは自分の意図に反して、そんな状態になってしまうため、驚いてしまうのでしょうね。
自分で体を抜け出そうとしている時は、わかってやっていますので、似たような状態になっても、気持ちは落ち着いています。

どんな風になるのかと言うと、最初は足の辺りが、軽くビリビリと、痺れたような感じになるのです。
でも、長時間正座をして痺れるのとは、違います。
そんな苦痛な感じはありません。
ただ、軽くビリビリした感じがするだけです。
正確に言えば、痺れているというよりも、細かく振動しているような、感じかも知れません。
その振動している部分は、通常の感覚が、麻痺した感じです。
そこで驚いたり、慌てたりすると、我に返ると言いますか、ビリビリ感は消えてしまい、普通の状態に戻ってしまいます。
それは、野生の動物や鳥たちが、安全かどうか確かめながら、少しずつ近づいて来るような感じです。
ちょっとでも動いて、驚かせてしまうと、さっと逃げ出して、姿を消してしまいます。
とにかく、ビリビリした感じが起こったら、そのまま放置して、様子を見ておきます。
すると、ビリビリ感は次第に、上の方へ広がって来ます。
足から太もも、腰からお腹、胸から背中と、ビリビリした感じが広がるのです。
ここで体を、抜け出そうとしてはいけません。
まだ機が熟していないのに、体を抜け出そうとすると、意識の体ではなく、本物の体が動いてしまいます。
肉体の体が少しでも動いたら、ビリビリ感は瞬時にして、消えてしまいます。
一度消えてしまったビリビリ感が、もう一度戻って来るのは、むずかしいのです。
慣れている人なら、そんなことはないかも知れません。
でも、素人の場合、そこで完全に目が覚めてしまうか、再挑戦しているうちに、眠ってしまうことの方が、多いと思います。
とにかく、ビリビリ感が首の辺りまで広がって来ても、知らんふりをして、放っておきます。
すると、ビリビリ感は頭の先まで広がります。
足先から頭のてっぺんまで、すっぽりとビリビリ感に包まれた感じになるのです。
この時も、まだ動いてはいけません。
早く体外離脱を経験したくて、動いてしまうと失敗してしまいます。
この時に抜け出そうとすると、一瞬、体を抜け出せたような、感じにはなるのです。
でも、意識のどこかが肉体に癒着していて、完全に抜け出すことはできません。
背中に強力なゴムでもつけられているみたいに、すぐに引き戻されておしまいです。
肉体と意識がビリビリ感に完全に馴染んで、熟した状態になるまでは、ピクリとも動いてはいけないのです。
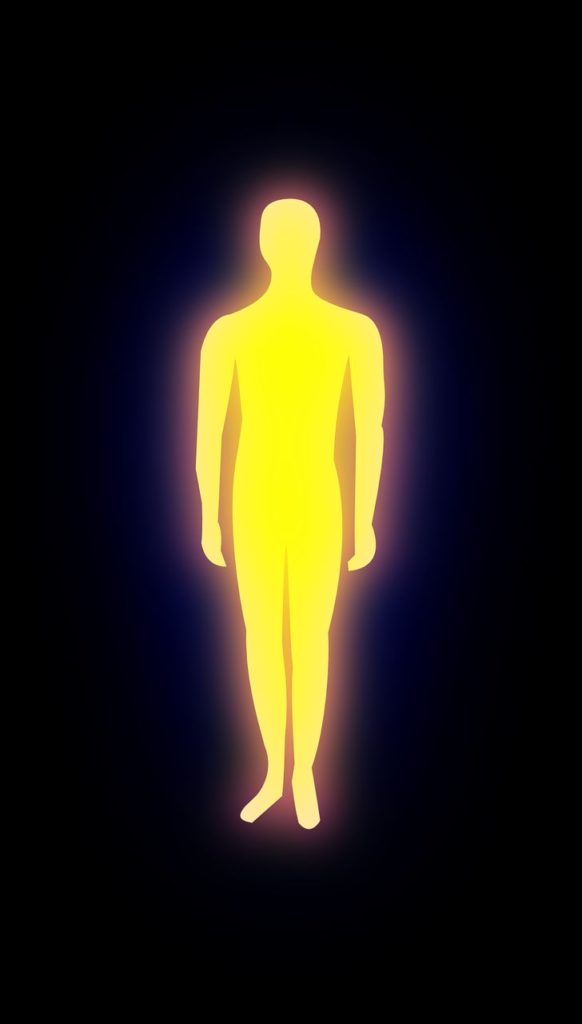
何度も同じような失敗を繰り返しながら、私は完全に肉体から、意識を離脱させることに成功しました。
その時の感覚は、初めて離脱した時と比べると、もっとリアルな感じでした。
本当に離脱したのか、疑わしくなるほどです。
部屋にはスチールの机があるのですが、その机に触れることができました。
幽霊のような存在になっているのであれば、手が突き抜けるはずです。
でも、手は突き抜けず、机に触れてその形状を、確かめることができたのです。
しかも触った感触が、肉体の手で触れるのと、全く同じでした。
机は硬くてツルッとしていて、冷たいのです。
おかしいなと思いながら、机を押してみましたが、硬くて手は突き抜けません。
私は窓から、外へ出てみようとしました。
でも、やはり窓が邪魔です。
それでも、意識の体だから、必ず突き抜けて行けるはずだと、私は思いました。
そこで、水の膜を抜けるような、イメージで挑戦してみました。
すると、あららという感じで、体は窓を通り抜けました。
その時は明け方で、外は明るくなっていました。
体外離脱の練習を、私はよく寝入りばなにしていました。
でも、そのまま眠ってしまうことが、ほとんどでした。
一方で、明け方にふと目が覚めた時は、チャンスでした。
そのまま動かないでじっとしていると、あのビリビリ感が現れることが、あったのです。
そして、この時もそんな明け方でした。

私は窓の外にある、一階の屋根瓦の上に、裸足で立っていました。
普段見るのと同じ景色が、目の前に広がっています。
外には、まだ誰もいませんでした。
そよ風が気持ちよく、本当に肉体で、そこに立っているかのようです。
感覚的には、普段の世界と何一つ変わりません。
本当に体外離脱をしているのか、疑うほどでした。
その時に、ふと私は視線を落とし、そこに立っている、自分の姿を見たのです。
瓦の上に立つ足は、裸足です。
その上には、寝る時に来ていたはずの、パジャマがありません。
私は何と、パンツ一枚の姿で、屋根の上に立っていたのです。
感覚は肉体の時と、何も変わりません。
体外離脱をしないで、そこに立っているかのようでした。
私は焦りました。
自分では、体外離脱をしたつもりでした。
でも、もしかしたら体外離脱を、していないのかも知れない、と思ったのです。
窓を突き抜けて、外へ出たはずなのです。
だけど、本当はそれは妄想で、実は普通に窓から、外へ出ただけかも知れません。
そう考えると、どうしようとパニックになりました。
だって、そうでしょう?
パンツ一枚で、早朝の屋根の上に、立っているわけですよ。
もし誰かに見られたら、完全に頭がいかれていると、思われてしまいますよね。
下手をすれば、そこに住めなくなってしまいます。
これは大変だ、早く部屋に戻らないと、と焦っているうちに、はっと気がつくと、私は蒲団の中にいました。
私はちゃんと蒲団を、かぶって寝ていました。
蒲団を剥いでみると、パジャマもちゃんと着ています。
しまった、やっぱり体外離脱ができていたんだと、後悔したけど、後の祭りでした。
もう完全に目が覚めてしまったので、どうにもできませんでした。
体外離脱体験
体外離脱という言葉を、聞かれたことがあるでしょうか。
以前は、幽体離脱という表現もされていましたが、幽体という表現が、よくなかったのでしょうか。
今では、体外離脱という言い方が普通になっているみたいです。
とは言っても、体外離脱が何なのかを知らない人には、幽体離脱でも体外離脱でも、同じですよね。
体外離脱とは、意識が体から、抜け出ることを言うのです。
この時、体は眠った状態ですが、意識はしっかりと目覚めています。
よっこらしょっと起き上がった時に、何だか体が、ふわふわしたような感じがあるのです。
後ろを振り返ると、そこに自分が横になって、寝ているのを目にするわけです。
あるいは、知らない間に、意識だけが天井近くへ、浮き上がっているということも、あるようです。
この場合、下を見下ろすと、そこに眠っている自分の姿があるのです。
この状態というのは、生きたまま幽霊に、なったようなものでしょうか。
体から抜け出す時の状況は、人によって異なると思います。
でも、大体みんな、こんな感じなのではないでしょうか。
どうして、そんな事が言えるのかというと、私も体外離脱を何度か、体験しているからです。

初めて体外離脱を体験したのは、大学生の頃でした。
当時は、一軒家の形のアパートに、同じ大学の学生四人で、暮らしていました。
四畳半の部屋が一階と二階に、それぞれ二部屋ずつあり、私は二階の西側の部屋にいました。
その時は夕方で、私は万年床の蒲団を二つに折りたたみ、それを背もたれにして座ったまま、うたた寝をしていました。
ふと目が覚めたので、私は背もたれの蒲団から体を起こし、そのまま立ち上がりました。
でも、何だかふわふわして、妙な感じでした。
高熱で寝込んだ後で、立ち上がった時に、重心が定まらないのに似ていました。
その時の部屋の空気も、変な感じでした。
水の中に潜っているような感じで、部屋の中に水が詰まっているかのようでした。
でも、体を動かすのに、水のような抵抗は感じません。
逆に、ちょっと動いたつもりが、動き過ぎてしまい、体のバランスを取るのが、大変でした。
どうも、おかしいなと思って、後ろを振り返ると、蒲団を背もたれにして座っている、自分が見えました。
私は驚きました。
でも、体外離脱のことは知っていたので、これが体外離脱なのかと、感動しました。
一階の部屋は、学生たちの溜まり場になっていて、この時も集まった友人たちが、麻雀をして遊んでいました。
その楽しげな騒ぎ声が、二階の部屋にまで聞こえていました。
私はこのままこっそり下へ行き、みんなの様子を眺めてみようと考えました。
みんなからは、私の姿は見えないはずです。
何故なら、私は幽霊みたいな状態ですから。
でも、実際はその状態の自分の姿が、他人から見えるかどうかは、わかりませんでした。
もしかしたら、いつもと同じように見えて、声をかけられるかも知れません。
どっちにしても、それは一つのデータであり、私はわくわくしました。
その時の私の部屋の扉は、閉まっていました。
でも、この状態だったら幽霊みたいに、扉を通り抜けられるかも知れない、と思いました。
ふわふわする体の体勢を整えながら、私は扉の前に移動しました。
扉は引き戸です。

扉に手を伸ばした時、私の頭を、ふと不安がよぎりました。
もしかしたら、これは罠ではないのかと。
何者かが私の意識を、私の体から引き出したのではないかと、疑ったのです。
そうであれば、私がこの場を離れている間に、その何者かに私の体を、乗っ取られてしまうかも知れません。
一度疑うと、その疑いは急速に膨らみました。
私は居ても立ってもいられなくなり、急いで体に戻ろうと思いました。
でも、どうやったら戻れるのかが、わかりません。
それで、余計にパニックになってしまいました。
私は漫画みたいに、自分の体の中に飛び込めば、元に戻れるかも知れないと考えました。
それで、私は跳び上がったのです。
重力が働けば、その後、私の体はすぐに下へ落ち、その勢いで体に、飛び込めるはずでした。
しかし、そうはならず、私の体は部屋の天井まで浮かび上がり、そこから下へ降りられなくなったのです。
私は天井のそばで、手足をばたばたさせながら、宙を泳ぐようにして、何とか体の中へ入ろうと、藻掻きました。
それでも、体は浮いたまま下がりません。
私は藻掻き続けました。
もう必死です。
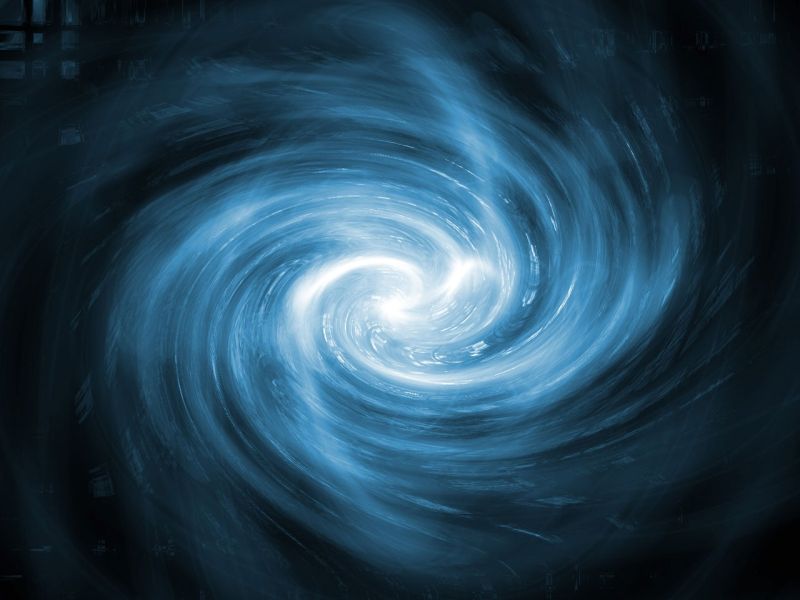
自分が回転したのか、周囲が回転したのかはわかりません。
私は渦に巻き込まれたみたいに、ぐるぐる回転し、うわーっと心の中で叫びました。
そして、はっとすると、蒲団を背もたれにして座っていたのです。
私は自分が体と一つになっていることを、確かめました。
自分が動かしている手や足は、間違いなく自分の肉体の手足です。
触ってみると、いつもどおりの体でした。
立ち上がってみると、全然ふらふらしません。
部屋の中もいつもと同じで、水の中のような感覚はありません。
下からは、友人たちの声が、聞こえています。
私はしばらく部屋の中を歩き回り、自分が体に戻れたのだと、確信しました。
途端に、何て馬鹿なことをしてしまったのだろうと、とても後悔しました。
二度とないかも知れない、貴重な体験を、不安が台無しにしてしまったのです。
下の部屋へ行って、みんなが遊んでいる様子を、こっそり確かめていれば、自分が体外離脱をした証明ができたのです。
それはまさに、千載一遇のチャンスでした。
私は悔しがりながら、もう一度蒲団を背もたれにして、眠ろうとしました。
でも、すっかり目が冴えてしまって、眠ることができません。
体外離脱を体験したのは事実です。
でも、そんな体験をした喜びよりも、下の部屋へ行けなかったことの後悔で、その日の私の頭は一杯でした。
それから私は、意図的に体を抜け出す、練習を繰り返したのです。
国境をなくすには2

今の社会は、一番上に位置する権力者たちが、自分たちの地位や権利を守るために、作ったものです。
権力者たちは、自分に忠実な者たちを引き上げて、自分の周囲を固めます。
引き上げてもらった者たちも、同じように、自分に従う者を引き上げて、味方にします。
同様のことが繰り返され、上の者の言葉に従うことが、当たり前という考え方が、ピラミッド社会の、裾野まで広がっています。
これは一種の洗脳なのです。
権力者は、お金で人を動かそうとします。
そのため、お金に困る人が必要です。
つまり、貧困者です。
貧困者がいなくなれば、誰もお金では言うことを、聞かなくなってしまいます。
貧困をなくそうと、きれい事を口にする、権力者はいます。
でも本気で、貧困をなくすつもりはありません。

今の世の中は、他人と比較され、他人との競争を強いられます。
競争に負ければ悲惨な目に遭うのだと、信じ込まされます。
子供の頃から、受験戦争という形で、そういう考え方を、植え付けられるのです。
やりたい事をするために、勉強するのではありません。
いい会社に入れるように、勉強をするのです。
いい会社は多くないので、競争です。
そういう事をさせながら、それがこの社会のルールなのだと、子供たちに教え込むわけです。
特技や能力がある者は、こんな社会でも、それなりに上に、上がることができます。
でも、それができない者もいるわけです。
そういう人たちの中で、自分は無能なのだと、信じてしまう人もいます。
そんな人は、自分の立場を高くするために、誰かを蹴落とそうとする事があります。
自分よりも立場の弱い者がいることで、安心するのですね。
その結果が、いじめや差別なのです。
それは貧困にも、つながります。
そんな中で、絶望して病気になったり、自殺をする人が出て来ます。
悪い事をしてでも、生き延びようと考える者も、現れます。
あるいは社会への憎しみを、無差別にぶつけたくなる者も、現れるでしょう。
つまり、貧困や差別を生み、さらには多くの犯罪を生んでいるのは、今の世の中なのです。
全ての原因は、かさぶたのように地球全体を覆う、歪んだ社会にあるのです。

競争というものは、本人たちが楽しめるのであれば、問題はありません。
互いに相手を尊敬し、褒め称えられるような、競争であればいいのです。
問題なのは、権力者のために、無益な競争を強いられることです。
そして、それによって歪んだ価値観を、すり込まれてしまうことなのです。
そういう価値観は、人間が本来持つべき価値観とは、大きくかけ離れています。
つまり、その価値観を植え付けられることで、人間としての可能性を、見失ってしまうわけです。
みんな、権力者の利益のために、騙されて利用されているのです。
これは世界中の人々に、言えることです。
みんながそのことに気がつけば、今の社会構造は、大きく変化するでしょう。
人が人として生きる喜びを、感じられる社会になるのです。
見た目はこれまでと、それほど変わっていないように、見えるかも知れません。
しかし、働く人々の心の中が、以前とは全然違うものになっているでしょう。
他人と競争しながら、お金を稼ぐというのではなく、自分がやりたい事をすることで、他の人にも喜んでもらう。
そこに生き甲斐を感じて、働くような社会です。
そんな社会が、世界中の国で作られるようになれば、自然と国境は意味を失って行くでしょう。
かつて多くの国が集まっていた日本は、平和な一つの国になりました。
それと同じように、世界は国境を越えて、地球という一つの世界を、築くことになるのです。

国境をなくすには1
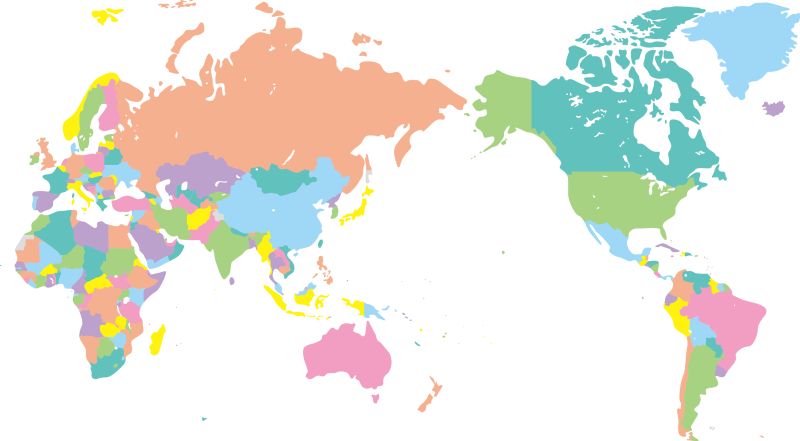
国と国の間には、国境があります。
それは、それぞれの国の主権を、守るためのものです。
言い換えれば、他国からの侵入を許さない、意思表示であります。
でも、世界が本当の意味で一つになるには、国境はない方がいいのです。
日本も戦国時代と呼ばれた頃、多くの戦国大名たちが、領土の拡張、奪い合いを繰り返し、せめぎ合っていました。
江戸時代になると、徳川幕府が全国を支配しました。
しかし、各地域はそれぞれの大名が治め、領地と領地の間は、国境として関所が置かれて、人々の出入りを管理していました。
明治時代になると、大名ではなく知事がその地域を、治めることになりました。
国境は県境となり、人々は日本中どこにでも、自由に移動をすることが、できるようになったのです。
その延長に、今の日本があります。

今の日本は、各地域の独自の文化が、残されています。
地域の人は、自分たちの暮らしや文化を、大切にしています。
一方で、国民の誰もが、自分は日本人だという、意識を持っています。
どこへ行っても日本ですから、どこの県へ行くにも、抵抗感は全くありません。
現在の世界の国々も、これと同じように、国境というものをなくすか、あるいは無意味なものにすればどうかと、私は思うのです。
別に国境などなくても、それぞれの地域に暮らす人々が、平和に暮らせるのであれば、何も問題はないでしょう。
EUは加盟国同士で国境を開放しています。
でも、それはあくまで経済圏という概念であって、一つの国になったわけではありません。
経済格差も大きく、これからと言ったところでしょう。
でも、方向性は間違っていないと思います。
他の国々も、一つの国のようになれればいいのですが、まずはお互いを理解し、尊敬し合えるようになる、必要があるでしょう。
それに、いきなり国境をなくしたりすると、悪い企みを持った者たちが、自由に行き来するようにもなります。
平和のための国境開放ですから、それは防がねばなりません。
ですから、そういう者がいないような、世の中にしながら、国境をなくしていくというのが、いいと思います。
これはEUでも、考えねばならないことでしょう。
では、どうやって悪い企みを持つ者を、なくすのでしょうか。

誰も悪いことをするために、産まれて来てはいません。
産まれた時は、誰もが可愛い赤ちゃんです。
それなのに、成長の段階で、悪いことをするようになる人が、出て来るのです。
でも、それにはそうなるだけの理由があるはずです。
そして、その多くの原因は、貧困や差別にあると、私は考えています。
つまり、世界中の貧困や差別をなくせば、いいのです。
そうすれば、自ずと犯罪は減って行くでしょう。
また、貧困がなくなれば、国の経済格差も埋まって行くでしょう。
犯罪が減り、経済格差もなくなれば、国境を厳格に考える理由が、なくなるのです。
では、貧困や差別は、どうすればなくなるのでしょうか。
貧困や差別が生まれる原因を、探ればいいのです。
これらの原因は同じです。
それは、エゴイズムです。
自分だけがいい思いをしたい、自分だけが優位でいたい、という思いです。

砥部焼(とべやき)

今日は家内と義母、私の三人で、砥部焼のイベントへ行って来ました。
松山から国道33号線を南へ進むと、久万高原の山があります。
その山の麓辺りが砥部の町で、古くから焼き物が作られていたと言います。
砥部焼の特徴は、厚ぼったくてぽってりした感じです。
とても丈夫で、他の食器と喧嘩をしても、まず負ける事はなさそうです。
伝統的な柄は、白地に紺の唐草模様ですが、最近は若い作家が増えて、いろんな模様や絵柄のものがあります。
特に女性作家が増えているそうです。
伝統的な模様は、力強くて男性的です。
それに対し、現代風の図柄や模様は、柔らかく温もりのある、女性的なものが多いようです。
今回は義母や家内が気に入った、お皿やカップが見つかったので、みんな大満足でした。
ところで、砥部焼の歴史を調べてみると、とても面白いのです。
砥部は、元は砥石で有名な土地だったそうです。
その砥石を切り出す時に出て来る、砥石の屑の処理がかなりの重労働で、村人たちから苦情が出るほどだったと言います。
江戸時代には、砥部は松山ではなく、大洲の殿さまの領地でした。
当時の大洲は経済的に、かなり大変だったそうです。
それで、砥石の屑で磁器ができる、という話を聞いた殿さまが、1775年 (安永4年) に、家臣に磁器を作るよう、命じたそうです。
しかし、初めての事なので、作業は順調に進まず、何度も失敗が繰り返されました。
そして、2 年半後の1777年 (安永6年)、ようやく白い磁器が誕生しました。
これが砥部焼の始まりです。
この頃の白というのは、少し灰色がかった白だったと言います。
しかし 1818年 (文政元年) には、新たな陶石が発見され、より白い磁器が作られるようになったそうです。

砥部焼が厚手に作られているのは、実用的であるためです。
砥部焼は壊れにくく、手に持っても料理の熱さを、感じにくいのです。
逆に言えば、料理が冷めにくいわけです。
値段も手頃で、庶民が購入しやすいというのも、特徴だそうです。
そうは言いましても、最近の砥部焼の中には、そんなに厚みがない物もあります。
まあまあいいお値段の物も、結構あります。
単なる実用品ではなく、芸術性も備えた実用品という物ですね。
その値段を高いと見るか、高くないと見るかは、買い手の価値観によるでしょう。
芸術性やオリジナリティを、評価しない人にとっては、何でそんな値段なのと、憤慨したくなるかも知れません。
しかし、その作品をとても気に入った人は、全然高くないと思うでしょう。
また、作家あるいは職人たちが、その作品を作るために、どれだけの努力と工夫、そして忍耐を続けて来たのかと、考えられる人は、妥当な値段だと思うに違いありません。
食器に限った話ではありませんが、どんな物でも、それを作った人がいるわけです。
そして、それをどんな想いで作ったのかを考えると、安い値段で買うのは、申し訳ない気持ちになってしまうでしょう。
自分が作品を作る側だったら、これより安い値段を言われたら、どう思うだろうと考えると、この値段は高過ぎるとは、なかなか言えないと思います。
とは言っても、現実の話として、手持ちのお金がそこまでなければ、いくら妥当な値段だと思っても、それを購入する事はできません。
作家の方にしても、作品を評価してもらえても、買ってもらえなければ意味がありません。
ここの所のさじ加減が、むずかしいのでしょうね。
しかし、毎日使う物であれば、見た目は高くても、高いとは思えなくなってしまいます。
少し無理をしたら買えなくはない、というような値段であれば、私なら絶対に買ってしまいます。
何故なら、それで毎日の暮らしが楽しくなるのであれば、逆に安いと思うからです。
同じ物を食べるにしても、食器が違うだけで、美味しさが変わって来ると思います。
生活に彩りを添えてくれる物は、有り難い物です。
実際に購入するかどうかは別にして、そういう物の価値というものを、確かめて楽しめば、それだけでも人生は、豊かなものになるでしょう。
作用・反作用の法則
作用・反作用の法則って、聞いたことがありますよね。
中学校の理科で習った、物理法則です。
どんな法則かと言うと、二つの物体が互いに力を及ぼし合う時、それぞれの力は向きが反対で、大きさが等しいというものです。
文章で説明すると、わかりにくいですよね。
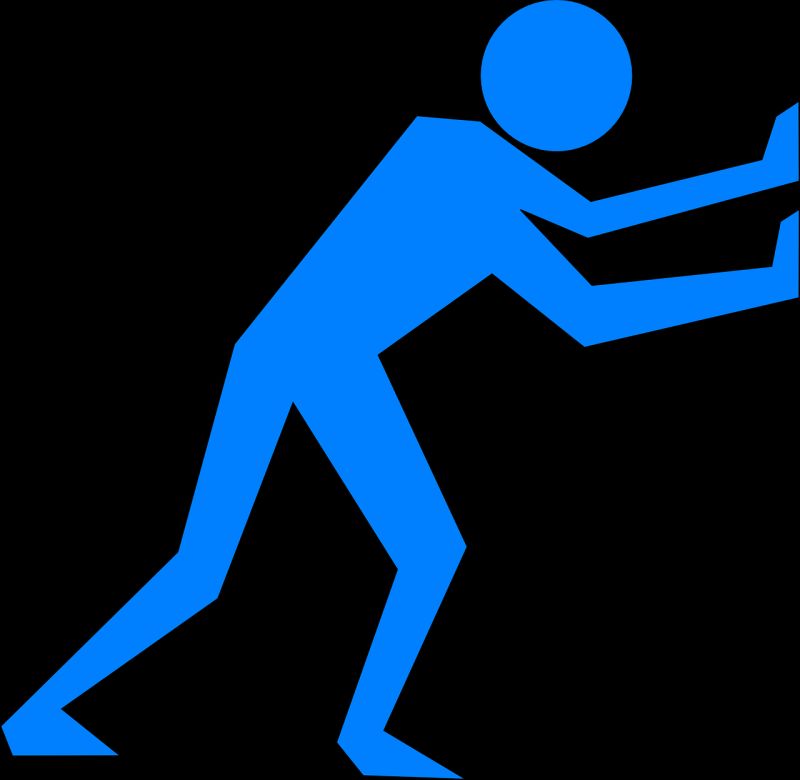
簡単に言えば、壁を押したとします。
その時の力は、どのくらいでもいいのですが、たとえば3の力で、押したとしましょう。
すると、その時に自分は、壁から3の力で、押し返されているのです。
杭に縛ったロープを、4の力で、引っ張ったとしましょう。
その時、自分はロープから、4の力で、引っ張られているわけです。
これって、何だか鏡に自分の姿を、映しているみたいですね。

さて、この作用・反作用の法則ですが、物理的な事柄だけでなく、人生にも同じことが、言えるのではないかと思うのです。
たとえば、あなたが誰かに親切にして、その人が喜んでくれたとしましょう。
その時の相手の喜び具合で、あなたが感じる喜びも、変わると思います。
相手がとても喜んでくれたら、あなたもすごく嬉しいでしょう。
ちょっとしか喜んでくれなかったら、嬉しいけど、ちょっと残念という感じですよね。

もし、あなたが誰かと喧嘩をして、その人のことを嫌ったとします。
当然、相手の方も、あなたのことを嫌うでしょう。
あなたが相手をとことん嫌って、顔を見ても、挨拶すらしないとしましょう。
きっと、相手も同じような態度を、見せるでしょうね。

あなたが大人の対応で、喧嘩はしたけれど、挨拶ぐらいはちゃんとしたとします。
すると、相手もそれに応じた態度を、見せるでしょう。
あなたが相手に、働きかける時だけでなく、逆に働きかけられた時にも、同じ事が言えます。
何かをしてもらった時、あなたの喜び具合が、相手の反応につながります。
嫌な事をされた時の、反応も同じです。
あなたが淡々としていれば、大きな騒ぎにはなりません。
個人と個人の関係だけでなく、あなたが置かれた環境にも、言えることす。
あなたが仕事の都合などで、暮らすことになった町が、あるとしましょう。
しかし、そこは不便な所で、欲しい物を手に入れるのも、大変です。
その町に対する、あなたの気持ちは最悪です。
そんな時には、町の人々のあなたを見る目も、嫌悪に満ちているように感じます。
でも、誰かに声をかけられ、喋っているうちに、あなたの気持ちは変わります。
気がつけば、自分の方から町の人に、挨拶をするようになりました。
不便だと思っていた町も、自然が多くて、癒やされる感じです。
また、手に入らない物は、自分たちで作るという人たちを見て、面白いと思いました。
あなたはいつの間にか、この町が大好きになっていました。
このまま、ここに住みついても、いいかなとまで、思うようになりました。

どうですか。
こんなのも、作用・反作用の法則でしょ?
この世界は、右と言えば、左があります。
前と言えば、後ろがあります。
上と言えば、下があります。
光と言えば、闇があります。
闇とは、光がない状態のことです。
あなたと言えば、あなたでないもの全てがあります。
そこには、人間も動物も家も自然も、あなた以外の何でも含まれます。
この世界は何かを選ぶと、同時に、それに反するものが決まります。
何かを指定することで、その何かと、そうでないものとの関係が、勝手にできてしまうのです。
あなたという存在があれば、必ずあなた以外のものが、あるわけです。
そして、両者の間には関係が生まれます。
そこには常に、作用・反作用の法則が働くのです。
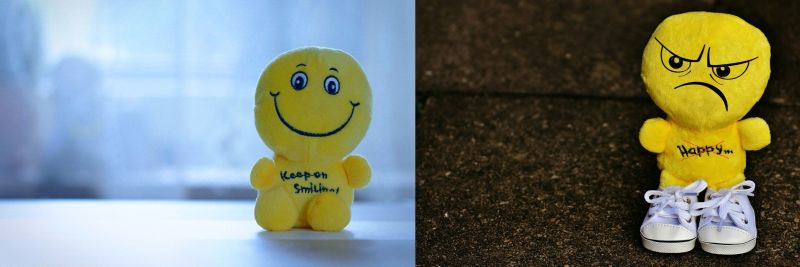
あなたが微笑みを向ければ、微笑みが返って来ます。
あなたが怒りをぶつければ、怒りが投げ返されるでしょう。
ポジティブな思いも、ネガティブな思いも、それぞれが作用・反作用の法則で、自分に見合ったものを、引き寄せるのだと考えて下さい。
人はポジティブな思いも、ネガティブな思いも、両方持っています。
ですから、人生はいい事もあれば、悪い事もあるのです。
できるだけ、ネガティブな思いを手放して、心の中をポジティブな思いで、一杯にしましょう。
そうすれば、あなたの人生は、喜びに満ちたものになるでしょう。
作用・反作用の法則です。
忘れないで下さい。
祈りと決意2
本気で何かをやりたいと思った時、その想いは無意識から来ています。
つまり、本当にやりたい事に、熱中するという事は、無意識に従って、行動しているという事なのです。
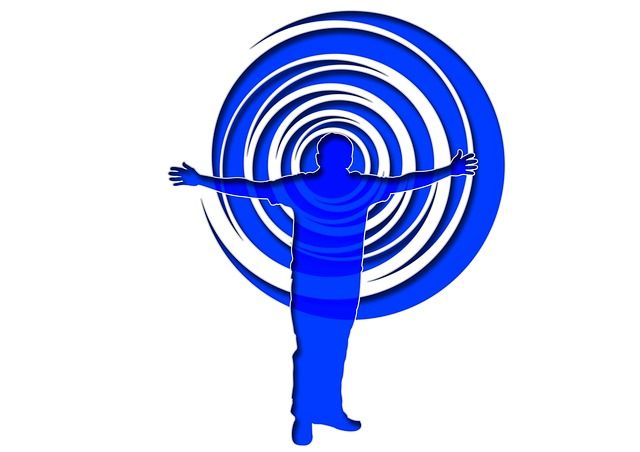
通常の意識は、今という瞬間しかわかりません。
しかし無意識は、時空を超えた情報を、持っています。
それは人類全体の意識の中で、無意識がネットワークを作っているからです。
道が左右に分かれていた場合、通常の意識では、どちらの道が望みにつながっているのか、わかりません。
でも、無意識はそれがわかるのです。
普段なら見落としてしまうような情報も、無意識に従っていれば、見落とす事はありません。
そうやって、望みを叶えるための情報が、自然に集まって来ます。
また、世界には自分一人が、いるわけではありません。
多くの人がいて、その人たちとの関わりにおいて、社会が構築されているのです。
当然、どんな人とどのように関わるのかが、望みが叶う世界に、関係して来ます。
本気で何かをやろうとしていると、その想いは無意識のネットワークを通じて、他の人たちの無意識へと、伝わります。
その中で、関わりを持てる人たちが、意識的あるいは無意識的に、様々な手助けをしてくれるようになるのです。
たとえば、困難に直面した時に、全く関係がないはずの人から、思いがけないヒントを、もらう事があります。
生活が大変な状況になっても、思わぬ所から食べ物や、お金などの支援を、受ける事があります。
この時に、相手の方はこちらの状況を、全く知らないという事もあるわけです。
こちらを助けたつもりなど、全然ないのに、結果的には助けてくれていると、いう事があるのです。

ただ、自分の望みが本物なのかどうかは、確かめる必要があるでしょう。
単に注目を集めたいとか、お金を稼ぎたいとかいうのは、無意識が望んでいる事では、ないかも知れません。
世間一般の価値観に染まった望みは、叶わないことの方が、多いと思います。
それに叶ったように見えても、それで満足感を得られるとは限りません。
でも、本音に従った望みが叶った時は、とても幸せな気持ちになれます。
もし幸せを感じられないのであれば、叶ったように見えても、それは本物の望みではなかったのだと思います。
また、本物の望みを持っていたとしても、いろんな理由が、その望みを邪魔することがあります。
たとえば、本当は自然の中で暮らしたいのに、田舎では仕事が見つからないから、諦めるというものです。
これはまず、田舎には仕事がないという、先入観かも知れません。
実際、本気で探しもしないで、決めつけている可能性があります。
誰かから、そんなのは無理だと、強く言われても、気持ちが萎えてしまいます。
いずれにしても、本音より先入観の方を、重視しているという事ですね。
本当に自然の中で暮らしたいのであれば、先入観を捨て、無意識の指示に従って、暮らす場所を探し回る事です。
と言うか、先入観を捨ててしまえば、自然に本音の動きが、現れるでしょう。
その結果、必ず自分に合った場所が、見つかります。

祈るということは、他の人、あるいは他の存在と、心をつなげるという事です。
誰かのために祈るというのは、とても高貴な行為です。
同時にそれは、他の人とのつながりを感じる事で、自分自身の心を、拡張させる事でもあります。
心が拡張すれば、安心感も広がります。
自分の事で祈りたくなるのも、安心感を得たいからでしょう。
しかし、何もしなくても大丈夫という、安心感はいけません。
自分で行動を示さなければ、周囲の状況が、勝手に動くことはありません。
それは電動式自転車の、モーターと同じです。
乗り手がペダルを漕がなければ、補助のモーターは動きません。

祈ることによって得られる安心感は、自分でペダルを漕いでもいいんだ、という意味に受け止めるのです。
つまり、自分の人生を、自分が思ったとおりにして、構わないという意味です。
そうすれば、自然に支援の力が、集まって来ます。
好きな事、やりたい事があれば、誰に遠慮することなく、それをやればいいのです。
誰かの迷惑になるようであれば、迷惑にならないように、工夫すればいいだけです。
人生を諦めている人。
人生を投げやりに考えている人。
自分なんか、何をやってもだめだと、決めつけている人。
まずは自分のために、祈りましょう。
そして、大丈夫だよという、無意識からの声を、受け止めて下さい。
不安な気持ちで祈っては、無意識の声が、聞こえなくなってしまいます。
無意識を信頼する気持ちで、祈って下さい。
そして、安心が得られたならば、好きな人生を送ると、決意しましょう。
無意識を信頼し、本音で生きれば、必ず喜びを得られます。

祈りと決意1

人は大切な人のために、祈ります。
試験に合格しますように。
無事に戻って来ますように。
病気が治りますように。
成仏できますように。
宗教があろうがなかろうが、祈りには関係ありません。
本当にその人のことを思う時、自然に胸の前に両手を組んで、その人のために祈ります。
神さまという、具体的な祈りの対象がある人は、神さまにお願いする形で、祈るでしょう。
しかし、神さまをイメージしない人でも、とにかく祈ると思います。
これは一種の本能的な行動なのだと、私は考えています。
どういう事かと言いますと、私たちの意識領域のうち、無意識と呼ばれる部分が、祈るということの意味を、理解しているからでしょう。

全ての人の心は、一つにつながって、人類の意識を形成しています。
祈りはそのつながりを通して、無意識から無意識へと伝わるのです。
無意識はその事が、わかっているのでしょう。
それで誰かの事を想う時に、それが祈るという行為に、なるのだと思います。
そして、その祈りは必ず、相手の無意識へ届くのです。
ただ、祈れば必ず、そのとおりになるのかと言うと、そういうわけではありません。
他人の運命を決めることは、どんなに祈ってもできません。
その人の人生を決められるのは、その人自身だけです。
その人が本気で動くかどうかで、その人の将来が決まるのです。
祈りはその人が本気で動くための、働きかけになるでしょう。
それでも結果は、その人の気持ち次第というところです。

祈りの対象が、自分自身である事も、ありますよね。
でも、この場合の祈りというのは、大抵の場合、自信のなさや不安な気持ちの、表れに過ぎません。
つまり、上手く行かなかった時の事を、悪いものと受け止めている事の、裏返しが祈りなのです。
一方で、自分に絶対的な自信がある人は、祈ったりしません。
この人たちは、自分の望みは、絶対に叶うものだと確信しています。
問題はそこへどうやって、アプローチするかという事だけです。
上手く行かない場合も、それを失敗だとは見なさず、別の道を探るよう示されたと、考えるのです。
失敗したと考えるのは、だめかも知れないという意味です。
失敗が続くと、絶対にだめだと思って、諦めてしまいます。

でも、失敗したと思わなければ、まだ途中であって、終わってはいないのです。
自信がある人は、何度上手く行かなかったとしても、だめだとは思っていませんから、さらに何度でも、挑戦を続けます。
彼らは祈る代わりに、必ず成し遂げるという、決意をしているのです。
そんな想いで行動すれば、必ず結果はついて来ます。
それには、ちゃんとわけがあるのです。
他の記事で書きましたが、人は一人一人が、独自の世界を体験しています。
他の人たちと同じ世界にいるように見えますが、実際は一人一人が、違う世界を体験しているのです。
その世界を構成しているのは、体からの感覚情報と、それに対する感情反応です。
自分の望みが叶うという事は、望みが叶った世界を、体験するという事です。
体験している世界は、どこでどんな情報を集めるかによって、全然違うものになります。
望みが叶った世界にするためには、それに見合った情報を集めて、世界を構築する必要があるのです。
では、どうすればいいのでしょうか。
それを教えてくれるのは、無意識です。
子供の教育2
今の学校は、決められた授業数をこなすことで、先生たちは頭が一杯になっています。
しかし、上の学校へ行くためには、それだけでは足りません。
学校とは別に、塾へ通わなければならないのです。
これでは何のための学校なのか、わからなくなります。
私が子供の頃は、塾なんかほとんどありませんでした。
塾なんかへ行けば、馬鹿にされたものです。
今の学校教育はこれまでの流れを、誰も止めることができないまま、ずるずると流されるように、毎年同じことを、繰り返しているだけです。
流れについて来られない子供がいても、目をつぶって見ないふりを、するしかありません。
目的は授業をこなすことです。
これでは先生たちも、嫌気が差してしまうでしょう。
そんな仕事がしたくて、先生になることを目指した人は、いないと思います。
今の学校教育は、子供たちだけでなく、先生方にも納得が行かないような、負担を強いるものなのです。

こうなってしまった原因は、企業にあります。
多くの企業は、大卒を採用条件にしています。
大学を出ていなければ、面接すらしてもらえないのです。
高卒の人が採用してもらえる所もありますが、同じ仕事をしていても、高卒と大卒で基本給が違ったりします。
中卒の人の就職が、さらに困難なのは、言うまでもありません。
しかし、実際は大卒であれば、高卒の人以上に仕事ができるのかと言えば、そんなことはありません。
また、大学で学んだことを、活かせる職場で働ける人は、ほとんどいないと思います。
大学の学生たちは、いくつもの企業の面接を受け、とにかく内定をもらえた所に、飛び込むのです。
でも、その仕事に就くために、大学で勉強をしたわけではありません。
一方、企業の現場としては、教えたことがわかる理解力は、絶対に欲しいところです。
あとは、本人の素直さと、やる気です。
そこに大卒の資格は、関係ありません。
現場で働く者にとって、雇われる人の学歴など、関係がないのです。

しかし企業は多くの所が、大卒を採用条件にしています。
理由は恐らく、面接だけで全ては、わからないからでしょう。
わからない分を、学歴を参考にして、判断しているつもりなのです。
職業差別がなく、大学に行かなくても、働ける所がたくさんあれば、どうでしょうか。
研究に興味がない人は、大学に行かずに働くでしょう。
嫌な勉強に、しばられる必要がなくなるからです。
大学へ行く人は、研究がしたいから行くだけのことです。
大学へ行かない人よりも、大学へ行く人が優秀ということにはなりません。
大卒であろうとなかろうと、立場は全く対等です。
大学へ行った人は、自分の研究を活かせる所で、働きます。
今のように、研究に関係のない職場を、必死に探し回る必要はありません。
問題が出るとすれば、大学でしょう。
入学生が減って、経営が成り立たなくなるからです。
しかし、大学は研究機関です。
本当に必要な研究機関であれば、国はお金を出し惜しみすることなく、ちゃんと支援するべきなのです。
お金が儲かるかどうかで、研究を評価するのは愚の骨頂です。
本当に研究をしたい者だけを入学させれば、授業は活発な議論の場になるでしょう。
また先生たちは、本来の仕事である研究に、もっと没頭できるようになります。
結果的に、研究の質は上がり、大学は今以上に、社会に貢献できるでしょう。
大学は社会人予備校の役目を終え、本来の価値を取り戻せるのです。

受験競争がなくなれば、子供たちは進学を、唯一の目標にする必要がありません。
それぞれが将来の夢を、大きく膨らませることができるでしょう。
授業も今よりも少ない時間で、子供たちの興味に合わせた、意味も内容もある授業を、行うことができます。
先生の目標も、子供たちがいい点をとることではなく、勉強の面白さを教えることになるでしょう。
特に専門の科目を、受け持っている先生は、自分が好きな科目の面白さを、どうやって子供たちにわかってもらおうかと、楽しく考えることができるでしょう。
試験の成績が悪ければ、それは子供が悪いのではなく、教え方が悪かったということになります。
だからと言って、先生が責められることはありません。
その子が理解できるような、もっと面白い授業をしてみようと、先生は自分で情熱に燃えるからです。

学校の授業が、これまでと同じようにできなくなった今、子供にも大人にも、本当に喜ばれるような教育というものを、社会全体で見直せたらいいなと思います。
子供の教育1

コロナ騒ぎの影響で生じた、授業の遅れを取り戻そうと、学校は必死でしょう。
受験が迫っている子供たちも、授業が進まないことで、不安を抱えていると思います。
それでも今は、これまでの学校教育が、本当によかったのかを、見直すチャンスでもあります。
一時、詰め込み教育が批判されて、ゆとり教育が推奨された時期がありました。
しかし、子供の学力が低下したという理由で、ゆとり教育は見直され、再び授業時間数が増えました。
その状態が、今に続いているのですが、結局は詰め込み教育に、戻っているのではないのか、検証するべきでしょう。
そもそも、子供たちに受けさせている授業が、どうして必要なのか、本当に必要なのかを、きちんと答えられる大人が、いるのでしょうか。

勉強をしておかないと、社会に出ても仕事がない。
成績が悪ければ、いい学校へ入れない。
頭が悪いと、国際競争に勝てない。
勉強が必要な理由を、大人が説明するとしたら、こんな感じではないでしょうか。
そのくせ大人が、今の子供たちが受ける試験で、どの科目でも100点を取れるのかと言うと、まず無理でしょう。
学校の先生でも、自分の担当の教科でなければ、50点も採れないかも知れません。
親なんか、さっぱりわからないから、子供の勉強は、学校や塾にお任せです。
それでも大人は、それなりに生きているのです。
それなのに、どうして子供たちに、いろんな勉強を、むりやり押しつけようとするのでしょうか。
子供の頃に受けた授業なんか、私は何も覚えていません。
覚えているのは、授業の途中で、先生が話してくれた雑談だけです。
面白いと思ったことしか、頭に残っていません。
勉強に関して、大人になっても、まだ理解できるのは、自分が興味を持ってやった事だけです。
そういう事は、大人になってからも、個人的に役立つことがあるからです。
しかし、他の授業は何の役に立っているのか、未だにわかりません。
大人になってから思うのは、勉強が必要なのは、大人も同じだということです。
社会に出て働くようになると、あれはどうなっているのか、こんな場合はどうするべきか、など自分でいろいろ考えます。
そして、必要に応じて本を読んだり、インターネットで調べたりして、知識を増やします。
私が社会人になった頃は、パソコンすら一般的ではありませんでした。
ですから調べるのは、もっぱら書物でした。
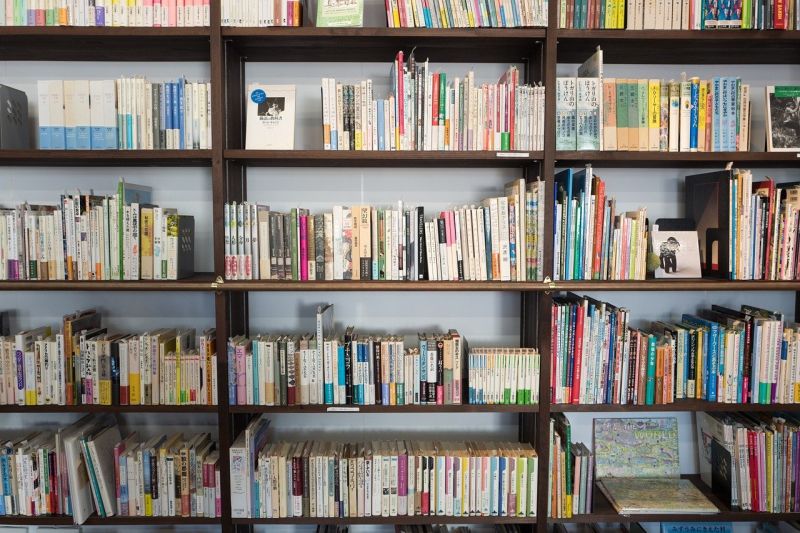
必要性に応じて調べていたはずが、読んでいるうちに、そちらの内容が面白くなることがあります。
それで同じような本を、何冊も読んだりしました。
同じような経験をされた方は、少なくないと思います。
本当の勉強というものは、大抵は大人になってから、行うものなのです。
それも自発的にです。
それは大変かも知れませんが、楽しいことでもあります。
嫌になったらやめてもいいという、主導権が自分にありますから、全然苦痛になりません。
それなのに、日本では勉強は、子供のうちにするものだと、思い込んでいる人が、多いように思います。
それも義務だから仕方なくするのだと、認識している人が、ほとんどでしょう。
その結果、勉強という言葉の響きが、アレルギーを起こしそうになるほど、嫌なものになってしまうのです。
学校教育が如何にまずいのかという、証拠だと思います。

子供の勉強というものは、生活に直接役立つようなこと、最低限必要なことを、年齢に応じて教えればいいのです。
子供のうちは、何でも覚えやすいからと言って、あれもこれもと教えるべきではありません。
子供に必要なのは、自分で考える力を養うことと、勉強が楽しいことだと理解することです。
そして何より大切なのは、自分が楽しいと思うことを追求することと、他の人が喜んでくれることで、自分も嬉しいと思えるようにすることです。
それ以外のことは、必要ありません。
外国の子供と学力を比較したところで、何の意味もないのです。
しかも評価される科目が、偏っているのも問題です。
その科目が苦手でも、他の科目が優秀な子供もいるのです。
しかし、その子たちは自分の得意分野では評価されず、一般的な評価で低く見られてしまいます。
それは、その子の自信を奪うことになり、人生を諦めさせることにもなるのです。


