責任より思いやり 期待より感謝2

親は子供に、期待をかけます。
それは大抵の場合、子供の幸せを願ってのことです。
将来、立派になって、人から信頼される人間になって欲しい。
世の中が不景気になっても、上手く立ち回る力を、身に着けて欲しい。
子供が選んだ世界で、トップになれるよう頑張って欲しい。
これらの期待は、そうなる事が子供自身の、幸せに結びつくと考えてのものです。
でも、中には歪んだ期待を、子供に押しつける親もいるようです。
自分たちの、老後の面倒を見てもらおう。
子供が立派になれば、自分たちも鼻が高い。
早く結婚して、孫を産んでもらえば、家も安泰だ。
こんな考え方は時代遅れであり、こんな風に考える親は、少なくなっているとは思います。
しかし、一部の親たちは、未だにこのような古い考え方を、抱いているようです。
こんな期待は親の自分勝手であり、子供を自分の道具のように、考えたものです。
期待をかけられた子供にしたら、迷惑とは言わないまでも、プレッシャー以外の何物でもないでしょう。

親に反発できる人は、まだいいです。
親元を離れて、親から自立することで、自分を保つことができるからです。
親の世話になりながら、反発だけする人は、いずれ大きな問題を起こすでしょう。
真面目で親に逆らわないタイプの人は、親の期待に応えられないと、自分を情けない人間だと、思い込むかも知れません。
自分を追い詰めて、自殺を図る人もいるでしょう。
あるいは、ずっと従順だった親に対して、ある日突然、大爆発をする人もいます。
自分勝手ではなく、純粋に子供を想っての期待でさえも、子供の状況によっては、大きな負担になる可能性があります。
順調に行っている時には、いいのですが、壁にぶち当たったような時に、下手に期待をかけられると、パニックになるかも知れません。
とにかく期待はほどほどにして、どんな結果になろうとも、子供を温かく見守ってやるように、するのが大切だと思います。

そもそも期待するという事は、期待の先にある状況をいいものとし、そこから外れる状況を悪いものとする、価値観が絡んでいます。
でも、何がよくて何が悪いのかは、絶対的な意味では言えません。
どんな状況であっても、見る立場によっては、いいか悪いかが逆転する事もあるのです。
つまり、どんな結果になろうとも、それがいいか悪いかの判断をするのは、本人なのです。
また、悪いと思えることを、よかったと見られるようになることは、人間としての成長です。
そう考えると、期待すべきは結果ではなく、人間として成長することだと言えます。
そして、そんな姿を見せてもらえる事に、親は感謝をすればいいのです。
我が子に巡り会えた事。
我が子の成長を、見せてもらえた事。
我が子の笑顔が見られた事。
その事への感謝です。

これは学校の先生たちも、同じでしょう。
自分が産んだわけでもないのに、多くの子供たちと出会えるのです。
その喜びを、感謝の気持ちに変えれば、素晴らしい教育ができるでしょう。
企業を経営する人たちも、従業員を家族としてみれば、その対応の仕方も、また違ったものになると思います。
雇ってやっているのではなく、働いてもらっているのだという、気持ちを持たねばなりません。
どんなに威厳を示した所で、従業員が全員やめると言えば、どんな企業であっても、たちまち潰れてしまうでしょう。
会社が潰れるだけでなく、経営者たちの個人的な暮らしさえもが、崩れ去ってしまいます。
自分がいい暮らしができるのも、みんなが働いてくれているからだという、感謝の気持ちを忘れてはいけないのです。
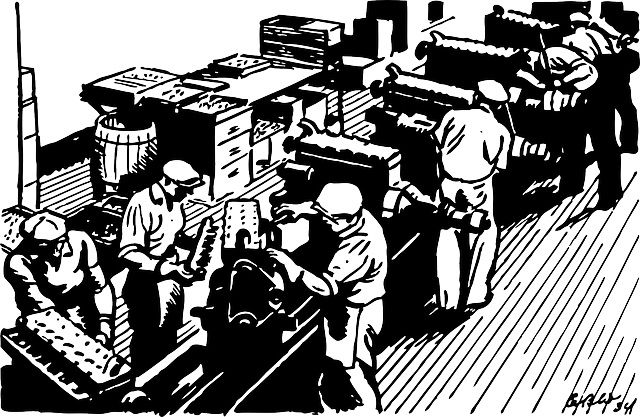
一方で、従業員の方も、会社への期待ばかり持つのではなく、感謝の気持ちを持つようにしないとだめです。
子供も親に甘えてばかりいるのではなく、親への感謝を忘れないよう、心がけねばなりません。
雇用主と従業員、親と子、そして教師と生徒。
双方の間で、互いへの思いやりと感謝の気持ちを、持つようにしていれば、どれほど素晴らしい世の中が、築けることでしょうか。
責任より思いやり 期待より感謝1

今の世の中は、管理社会です。
学校でも職場でも、こういう人間であるべきとばかりに、決められた枠にはまる事を、求められます。
枠にはまろうとしない者や、はまろうと努力はしても、どうしてもはまらない者は、役立たずだとか、協調性がないやつという風に、見られてしまいます。
本当は優れた感性を持っていたり、他人にはない面白さを、持っていても、枠にはまる事の方が、優先されがちです。
先生や上司など、上に立つ人が理解のある人で、枠からはみ出ていても、本人のよさを伸ばそうとしてくれたならば、その人はラッキーです。
でも、大半の場合、枠にはまらないと、悪く見られてしまいます。

下手をすれば家庭でさえも、躾の名の下に、子供たちが厳しい管理下に、置かれることもあります。
その躾が本当に社会的に、要求されている事柄であればともかく、大概の場合は、親の勝手な考え方や、ただの虐待である事も、多いと思います。
しかし、その親もまた、同様の管理下で育てられていたという事も、少なくないようです。
まともに子供を育てている家庭でも、幼い兄弟の上の子に、下の子の面倒を頼む場面が、あると思います。
ところが、上の子と言っても、幼い子供ですから、言われたようには、面倒が見られないこともあります。
その時に、その子を叱ってしまうのは、幼い子供に頼まれた事への、責任を求めているわけです。
でも、幼い子供に責任なんてことは、なかなか理解できないでしょう。
そういう事は、成長していく過程で、少しずつ覚えて行くことです。
親である自分も、子供の頃には同じ状況だったはずです。
しかし、大人になってしまうと、子供の頃の事なんて、忘れがちになってしまいます。
その結果、自分の都合で子供たちを、利用しようとしてしまうわけです。
相手の都合や状態など、考慮していないのですから、学校や会社が人を管理しようとするのと、同じですね。
つまり、誰かを管理しようとする時には、自分の都合を優先させて、相手の都合を考慮していないのです。
逆に言えば、相手の都合を考慮する時は、その人を管理するとは言いません。

話を初めに戻しますと、この世の中は管理社会ですが、それは社会が一人一人の都合など、考慮しないという事なのです。
みんな、それが当たり前だと、受け止めていると思います。
管理社会という言葉だけを聞いて、わかったつもりでいるのです。
でも、管理社会の本当の意味を理解したならば、どれだけ暮らしにくい環境に、自分たちが置かれているかがわかるでしょう。
企業や世の中への、奉仕ばかりが求められ、自分たちは誰にも、気に留めてもらえません。
これでは、頑張ろうという気持ちも、萎えてしまいます。
逆に、誰かにねぎらってもらったり、具体的な支援を受けることがあれば、感謝の気持ちが生まれ、それが新たな動きの原動力となります。
普段でもそうなのですが、今のように大変な時は特に、上に立つ者は、自分の事ばかり考えずに、下にいる者たちをねぎらう気持ちを、持ってもらいたいものです。
それは他人に対する、思いやりを持つということです。

学校の勉強も同じです。
子供たちは勉強を強いられ、試験でいい点を取ることを、求められます。
それが将来のためだと言われても、どうして将来のためになるのかを、ちゃんと説明してくれる先生はいません。
説明するとすれば、就職の時に有利になるからだとしか、言えないでしょう。
その子にどんな仕事に向いているかなんて、まだわかっていないのに、就職の話を持ち出しても、意味がありません。
でも、就職の話以外に、好成績を収めなければならない理由を、誰が説明できるでしょうか。
それに、学校で求められているように、全員が好成績を収めたとしましょう。
みんなが好成績になれば、差がつきませんから、誰も有利になりません。
ほとんど違いがないのに、一方は認められて、他方は認められなかったとなると、それこそ何のための勉強だったのかと、いう事になるでしょう。
学校の勉強は、本来子供の好奇心を、伸ばしてやるためのものなのです。
就職のためなどではなく、人間としての成長を、促すためにあるのです。
競争は楽しむものであり、科目による得手不得手は、その子の個性に過ぎません。
競争に勝っても天狗にならず、負けても腐らない。
自分も楽しみながら、他の子も楽しめる気遣いを覚える。
他の子の喜びや悲しみを、自分のものとできるようにする。
自分と他の子の違いを認め、それが楽しい事なのだと理解する。
世界の不思議を見つけ、それを探求する心を養う。
自分を表現する方法が、一つではない事を知る。
こういった事を、子供たちに学ばせる事が、学校の役割でしょう。
その子の成長具合や理解の度合い、好奇心の方向などを考慮し、その子に本当に必要な事を、その子のペースに合わせて教える。
それが学校に求められる、教育の姿勢だと思います。
それは社会の宝である、子供たちへの思いやりです。

仕事を頑張ってくれている人々や、懸命に成長しようとしている子供たち。
彼らに対する、思いやりの心こそが、今の世の中に、求められているのだと思います。
大人になってから読んだ本
中学生の頃からは、読むとなったらマンガでした。
小説などの本は、ほとんど読んだ記憶がありません。
大学生になると、不思議な事が書かれた本は読みました。
でも、物語のような本は、やはり読まなかったですね。
たまに本屋さんで、話題になっているような本を、手に取ることはありました。
でも少し読むと、自分には向いていないと思って、元に戻しました。
何度かそんな経験をすると、大人が読む本なんて、面白くないものばかりだと、勝手に決めつけるようになりました。
それで、社会人になってからも、小説を読むことはありませんでした。
しかし、三十代に入ってから、何となく古本屋で、手に取った本を読んだ時、私は衝撃を受けました。
冒頭に記述された、物語の舞台の情景が、本当にそこにいるかのように、目に浮かんだのです。
思わず読み進めて行くと、主人公が登場するのですが、その暮らし様が、また目に浮かびます。
これは絶対に買うべきだと思い、すぐさまその本を購入しました。
それは藤沢周平氏が書いた、「蝉しぐれ」という時代小説です。
文庫本でしたが、他の文庫本と比べると、かなり分厚い本でした。
それでも話の展開が面白くて、二日かけて読み切りました。
その後も、藤沢氏の他の作品も読みたくなって、次々に購入しました。
むさぼるようにして読んだ本は、全部当たりでした。
私は、どうしてこの人の本は、こんなに心に響くのだろうと考えました。
そして、わかったのが、どの作品にも、著者の人柄が滲み出ているという事でした。
藤沢氏の作品に共通しているのは、一生懸命に生きている人の姿を、一生懸命に書き表している事です。
それは、懸命に生きる人々への、共感と励ましなのです。
藤沢氏は、ご自身が大変な苦労をされた方で、とても優しい人なのだなと思いました。
また、ユーモアもあって、読む者の心の緊張を、ふっと解いてくれるような、話し上手な方です。
作家は誰もが話し上手だと、思われるかも知れませんが、そうではありません。
作家によって、文章の文体は違いますが、そこには作家の人柄が表れています。
わかりにくい文体を、特徴とする作家もいるのです。
藤沢周平氏が登場人物たちを見る眼差しは、とても優しいのです。
また、この藤沢氏は山形の方なのですが、山形をとても愛しているのだという事も、読んでいて伝わって来ます。
作品に描かれた登場人物も舞台も、全て藤沢氏の心の中にあるもので、どの作品も藤沢氏自身の分身だと言えるでしょう。
だからこそ、藤沢氏の作品は心に響き、夕日が沈んだ後も紅く染まったままの空のように、読み終わってからも、心の中に深い余韻を残すのだと思います。
そんなわけで藤沢氏の作品は、私に読書の面白さを、思い出させてくれました。
それから藤沢氏以外の作品も、いろいろ読むようになりました。
しかし、読後に感動が胸に残る作品は、案外少ないと感じました。
藤沢氏以外で、私が心を惹かれた作家は、浅田次郎氏です。
とても有名な方ですが、とにかく泣かせるような物語を作るのが、得意な方です。
男とは、人とは、こういうものなのだと、訴えているような作品が、多いような気がします。
今の人たちは、本よりもネットゲームやネット動画に、夢中になっているようですが、何かのきっかけで読書も面白いと、思うようになるかも知れません。
ぜひ、そうなってもらいたいと思います。
全ての本が面白いとは、私は思いません。
自分に合う作家とは、滅多に巡り会えないかも知れません。
それでも、もし素敵な作家と出会えたなら、必ずや人生観が大きく広がるに違いありません。
本なんかつまらないやと、頭から決めてかからずに、機会があれば、本を手に取ってみるのも、いいと思います。
子供の頃に読んだ本
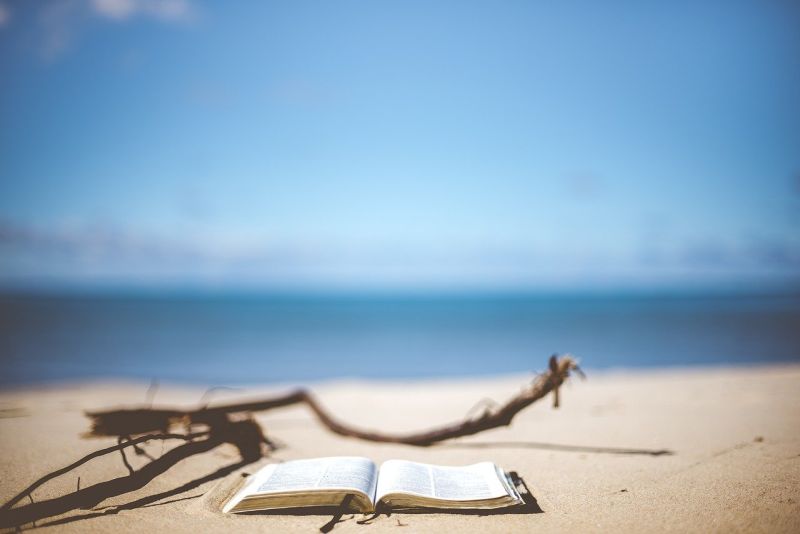
若者の読書離れが言われ始めて、もう30年になるそうです。
紙の本を読む人は、加速度的に減っていますし、電子書籍もその穴埋めをするには、至っていないようです。
今の人たちは、本を読むよりも、ネットゲームやネット動画の方が、面白いと言います。
私も若い頃は、読書をするよりも、マンガの方が面白いと思いました。
その理由を考えますと、マンガですから絵が描かれているので、わかりやすくて目を惹かれたのでしょうね。
子供用のマンガは、子供が喜ぶようなストーリーになっています。
それに本の話と違って、いきなり面白い展開が、始まったりします。
登場するキャラクターたちも、性格が一目瞭然で、すぐに好き嫌いの判断ができます。
本の場合は、しばらく読まないと、話の状況がわかりません。
登場人物についても、そうですし、ストーリーそのものも、読み進めて行かないと、気に入るかどうかの判断ができません。
よくわからないまま読み続けると、読むのに疲れて、もういいやとなってしまいます。
私が小学生の頃、小学館が出版した「世界の名作文学全集」というものがありました。
一冊が百科事典のように分厚い本で、一冊の中にいくつかの話が収録されています。
そんな本が、全50巻もあるシリーズで、それを私の父が購入しました。
もちろん、自分の子供に読ませるためです。
その子供とは、私と兄と弟の三人です。
しかし、兄も弟も読みません。
それで私が、読むしかありませんでした。
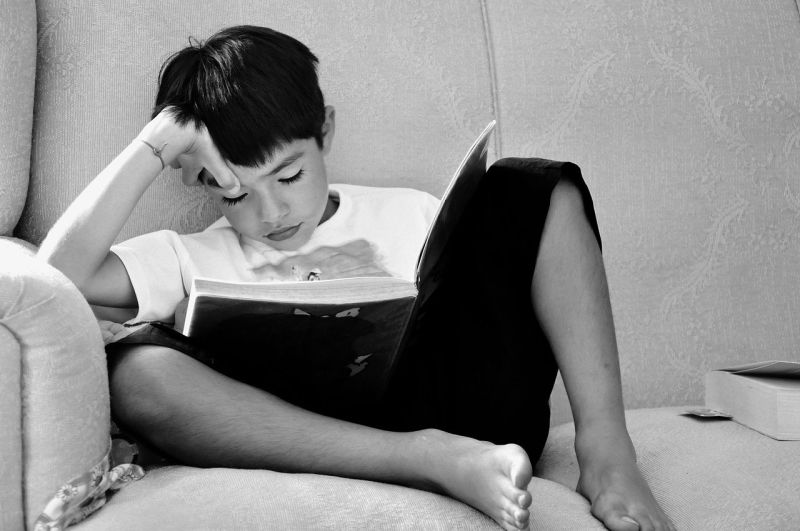
一冊を全部読んだと言えば、親に喜んでもらえるし、読まなければ、がっかりされてしまいます。
親の期待に応えるために、私は本を必死に読みました。
それでも一冊全部を読むのは、かなり骨が折れました。
子供向きの面白い話は、すいすい読めました。
でも、ちょっとむずかしい話だと、読んだというより、文章を目で追ったという感じでした。
ただ、あとでどんな話だったのかと聞かれるので、物語の要所要所は、押さえるようにしていました。
そうやって、五十巻全部を読み切ったのに、頭に残っている話は、ほとんどありません。
ただ、読んだというだけです。
この話はよかったなとか、また読みたいなと思ったものは、一つもありませんでした。
でも、学校の図書館で、自分で選んで読んだ本は、とても気に入り、何度も同じ本を借りて、読みました。
それは「うりんこの山」という、三匹のイノシシの子供たちの話でした。
やいば、いぶき、すずか、という名の三匹のうり坊たちが、成長して行く話です。
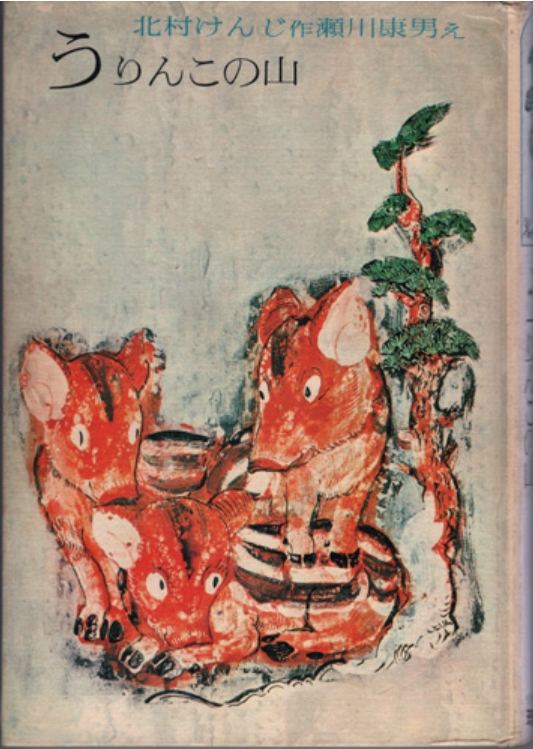
子供の本なので、挿絵がありました。
この絵も、何だかとても魅力的でした。
私は次男だったので、同じく二番目のうり坊、いぶきがお気に入りでした。
懐かしく思って、インターネットで調べてみると、すでに廃刊となっているようで、古本屋でも手に入らないみたいです。
私と同じように、子供の頃にこの本を読んで感動し、大人になってから探し求めている人が、何人かいらっしゃるようなので、何だか嬉しい気持ちになりました。
そうそう、思い出しました。
「世界の名作文学全集」の中にも、一つだけ印象の強かった話がありました。
それは「子鹿物語」です。
話の内容は、ここには書きませんが、有名な話なので、ご存知の方も多いと思います。
私はこの本を読んで、人間がとても嫌いになりました。
人間が自分の都合で、生き物の命を奪うのです。
それが生きる事だと、作者は伝えたかったのかも知れません。
でも、それこそ大人の勝手な考えでしょう。
その怒りは今でも、胸の奥に残っています。
ですから、この物語は繰り返して読んだりしていません。
ただ、「うりんこの山」にしても、「子鹿物語」にしても、子供だった私の心に、強い印象を残した点では、同じです。
そういう意味で、二つの物語は、どちらも優れた話なのだと思います。
そして本とは、そういうものでなければならないと、思うのです。
世界は変わるもの2

足下の地面、あるいは波が揺れ動くならば、それに合わせて動きます。
揺れに逆らうのではなく、揺れに合わせるのです。
転んだら、もう一度起き上がって、動く地面や波をつかまえます。
つまり、どんな状況になろうとも、その状況に応じた動きを、するように心掛けるのです。
これまでと同じ安定を、求めてはいけません。
同じ事を求めるから、上手く行かず落胆するのです。
安定など初めからないと思って、いろんな事に固執するのをやめましょう。
せっかくの仕事を、やめる事になるかも知れません。
苦労して購入した家を、手放す事もあるでしょう。
家族が離れて暮らす事を、余儀なくされる場合もあります。
それでも、その事自体には抗わず、新たな暮らしを模索するのです。
こうでないといけないとか、自分が情けないとか、本当はこんなはずではなかった、などという考えは捨てましょう。
絶望的に見える事にも、新たな展開のチャンスが、潜んでいるものです。
要は絶望的な事を、単に絶望的だと受け止めるかどうかの、問題なのです。
つまづいて転んだ石に、腹を立てる人もいれば、その石が金塊だと気づく人もいるのです。

どうしていいかわからない時には、誰かの助言を仰ぎましょう。
一度や二度、助言が得られなくても、諦めてはいけません。
本当に次のステップへ進みたいのであれば、歩みを止めてはいけないのです。
また、どちらへ進んでいいのかわからない時は、自分が行きたいと思った方へ、進めばいいのです。
どうせ何をやってもだめであるなら、自分がやりたいと思っていた事、興味が持てる事に向かって、進んでみるべきでしょう。
すると、そこから新たな道が、見つかるものなのです。
諦めて動くのをやめたり、どうせだめだと思いながら動いていたのでは、絶対に上手く行きません。
どんな状況の中でも、楽しさを追い求めて動く事が、肝要なのです。

楽しさがあると、まず自分の気分が、よくなります。
また、楽しさは人を呼び、自然に人とのつながりが生まれます。
初めは小さなつながりでしょうが、そのつながりが、やがては大きなつながりに、なるのです。
嘘だと思う人もいるでしょう。
でも、どうせ上手く行かないのであれば、楽しさを追い求めてみても、損はないと思います。
落ち込んでいると、嫌な事ばかり考えてしまいます。
その気分を解消できるだけでも、やってみる価値はあるでしょう。
とにかく、自然も世の中も、変化するものなのです。
変化を嘆いても、仕方がありません。
どんな変化が起ころうと、その中にチャンスを見つける気持ちを、持つ事が大事だと思います。
ポイントは、感謝と思いやりです。
人々を喜びに導く事であれば、それがどんな事であっても、上手く行きます。
自分だけが生き延びようとか、自分だけが儲けよう、などという思いがあると、必ず失敗するでしょう。
変化の中で生きて行くためには、楽しい気持ちが欠かせません。
でも絶対に、他の人たちとの絆を、忘れてはいけないのです。
世界は変わるもの1

人は安定を好みます。
何かに挑戦しようという、気持ちを持ちながらも、足下は安定していて欲しいのです。
足下が安定していないと、ふらついて何かに挑戦どころではないからです。
そこで、何かに挑戦する前に、先に足下の安定を図ろうとします。
具体的に言えば、経済的な安定ですね。
経済的な安定は、衣食住の安定につながります。
結婚して家庭を持ち、子供を産み育てるにも、経済的安定は必要です。
それで結局は、ずっと経済的安定のために働き続け、何かに挑戦する余裕を、持たずに過ごしがちになります。
場合によっては、挑戦する事すら、思い浮かばなくなっているかも知れません。
そこまでして頑張っているのに、世の中が突然、それまでとは違った姿を見せると、途端に足下は不安定になってしまいます。
かろうじて立ち続けられる人は、まだいいですが、中には立っていられずに、倒れてしまう人もいるでしょう。
お金や資産を、たくさん持っている人であれば、少々足下が揺れたところで、びくともしません。
しかし、予想以上の大きな揺れが来ると、どんなに構えていたとしても、ガラガラと足下が崩壊するのです。

最近になって時折見られる、自然の猛威は、どれも人間にとっては、想定外のものばかりです。
逆に言えば、想定が甘いわけです。
長い地球の歴史の中で、人間が知っている自然など、ほんの一瞬の姿でしょう。
その一瞬の姿を見て、全体がわかったつもりでいるから、痛い目に遭うのです。
それと同じで、経済状態や国同士の関係も、私たちが直接知っているのは、歴史の中のほんの一瞬なのです。
その一瞬の安定の中で、世の中が永遠に今の状態にあると、信じてしまうのが間違いです。
自然もそうですし、世の中も常に変化をしています。
小さな変化を繰り返しながら、それが突然大きな揺れになるという事は、別に不思議な事ではありません。
私たちがそこに着目しようと、しなかっただけの事です。
大きな企業に勤めている人も、中小企業に勤めている人も、自分たちが働く環境が、ずっと同じ状態で続くと、考えてはいけません。
正規雇用でない、契約社員や派遣社員の人たちも、死ぬまで今のまま行けるとは、考えない方がいいでしょう。
しかし、これは不安を煽っているわけではありません。
足下が不安定になる事を、恐れるなと言いたいのです。
無意識とのつながり その2
先日、行きつけのカフェで、素敵なショールが、目に留まりました。
青空のような爽やかな青色で、手に取ってみると、生地が厚手で、これから寒くなるのに、肩掛けや膝掛けとして、使えると思いました。

もちろん、私が使うのではありません。
初めは家内に、どうだろうかと思ったのです。
このショールはカフェを経営している方の、お姉さんの手作りだそうでした。
自分で布を藍染めして、作られたそうです。
一点物で、他では売っていません。
しかし、値段を見ると、結構な値がついていました。
そこで、いったんは席に戻って、買うのを諦めようかと思いました。
それでも、どうしてもそのショールに、目が向いてしまうのです。
普段の私は、着る物には全くの無頓着で、穴が開いている物でも、平気で着る人間です。
ファションには、少しも関心がありません。
家内が服を買う時に、どれが似合うかの判定を、手伝う事はありますが、そうでない時には、衣類への関心は、全然湧かないのです。
それなのに、どうしてこのショールに惹かれてしまうのか、自分でも不思議な気がしていました。
食事をしながら、家内と喋っている間も、心の半分は、棚にある青いショールに、向いていました。
とうとう我慢ができなくなって、私はそのショールを持って、家内に感想を聞いてみました。
別に家内の誕生日ではありませんし、家内は別のショールを持っています。
それでも家内に感想を尋ねてみると、家内はそのショールが、素敵だと言いました。
でも、欲しいかと聞くと、今はいらないという返事。
それなのに、私はそのショールを、諦められませんでした。
気持ちは、ほとんど購入するつもりだったようです。
そこで、ふと思いついたのが、お義母さんにどうだろうか、という事でした。
お義母さんは冷えが原因で、神経痛が出るようでしたので、肩掛けや膝掛けにどうかと思ったのです。
その話をすると、家内は母親はきっと、喜ぶだろうと言いました。
ただ、値段の事を気にしていました。
それでも私は、お義母さんが喜んでくれるならと、購入を決めました。
翌日、家内はそのショールを、お義母さんに届けに行きました。
実は、ショールを買った翌日が、お義母さんの誕生日だったのです。
でも私は、その事を忘れていたので、結果的にショールは、誕生日プレゼントになりました。

家内の話によれば、ショールを目にしたお義母さんは、一目でそのショールが、高価な物だとわかったそうです。
実はお義母さんも、そこのカフェがお気に入りで、前に訪れた時に、この青いショールを見て、素敵だと思ったらしいのです。
でも値段を見て、とても買えないと思って、諦めたそうでした。
だから、そのショールを誕生日プレゼントとして、受け取れたことで、お義母さんはとても喜んでくれたようでした。
私はそのショールが、ずっとそこの棚に置かれてあった事を、その話で初めて知りました。
これまで何度も、そのカフェを訪れていたのに、これまでは一度も、そのショールに惹かれた事はなかったですし、ショールの存在自体に、気がつかなかったのです。
それなのに、その日は店に入った時から、どういうわけか、目がそのショールに、釘付けになっていたのです。
全く不思議な事だと思いました。
きっとあの時、私の無意識がそのショールを購入するようにと、私に囁き続けていたのでしょう。
そして、それに従った結果、思いがけない喜びに、巡り会えたわけです。
ですから、普段から常に、無意識の言葉に耳を傾けていれば、幸せな人生を送れるはずだと、私は思いました。
では、どうすれば無意識に、自分の心をつなぐ事ができるのか。
私はショールに心を惹かれていた時の事を、思い浮かべました。

あの時の感覚。
それは頭の中の感覚だけでなく、空間の感じも、普段とは違っていたように思います。
恐らく体を包む、気のエネルギーの状態が、いつもと違っていたのでしょう。
とにかく、自分を信じて行動を起こすんだと、体の中からも外からも、後押しされているような感覚です。
その感覚を思い出していると、今も心が無意識と、つながっているような気がします。
無意識とつながった感じがしていると、とても安心な気持ちになります。
今は世界中が、いろんな問題で大変な状態にありますが、そんなものとは無縁の世界に、いるような気になります。
みなさんも、誰かを想う気持ちから、思いがけない喜びにつながった時が、あると思います。
その時の感覚を、ぜひ忘れないようにして下さい。
世の中に不安が一杯あふれていても、あなたの周りには、きっと喜びが広がるでしょう。
無意識とのつながり その1

人間は覚醒時は、通常の意識で活動しています。
覚醒時には、無意識も活動しています。
しかし、通常の意識の方が、表に立ってしまうので、その存在にほとんどの人が、気がつきません。
ですから「無意識」という、得体の知れないもののような、名前を付けられているのです。
通常の意識は言語的・論理的思考で、活動します。
言語も論理も、人間社会におけるものですから、行動の基盤となる価値観も、人間社会に沿ったものである事が、ほとんどでしょう。
一方で、無意識は言語的・論理的思考は、用いません。
無意識の活動は、インスピレーション的なものです。
はっとした瞬間に、全てがわかるという感じです。
通常の意識が、何かで思い悩んでいる時、ふとした時に、そうだと答えを思いつく事があります。
それは通常の意識が、無意識とつながったからなのです。
無意識は常に、通常の意識に働きかけています。
しかし、通常の意識は日常の事で、手が一杯になっていて、とても無意識に耳を貸している、余裕がありません。
それがお風呂に浸かって、ぼーっとしている時とか、雄大な大自然に引き込まれている時など、通常の意識が普段の活動を止めていると、無意識の囁きが届くのです。

通常の意識は、今という一瞬しか把握できません。
でも、無意識は今だけでなく、過去も未来も含めて、まるごと把握しているように思えます。
また、無意識からの情報というものは、他人の立場や想いまでが、含まれているようです。
つまり、自分の視点だけでなく、他人の視点も含めて、全体を把握しているように、見えるのです。
この事から考えると、無意識というものは、他人の無意識ともつながっている、と言えるでしょう。
そうでなければ、他人を思いやる気持ちなど、出て来ないと思います。
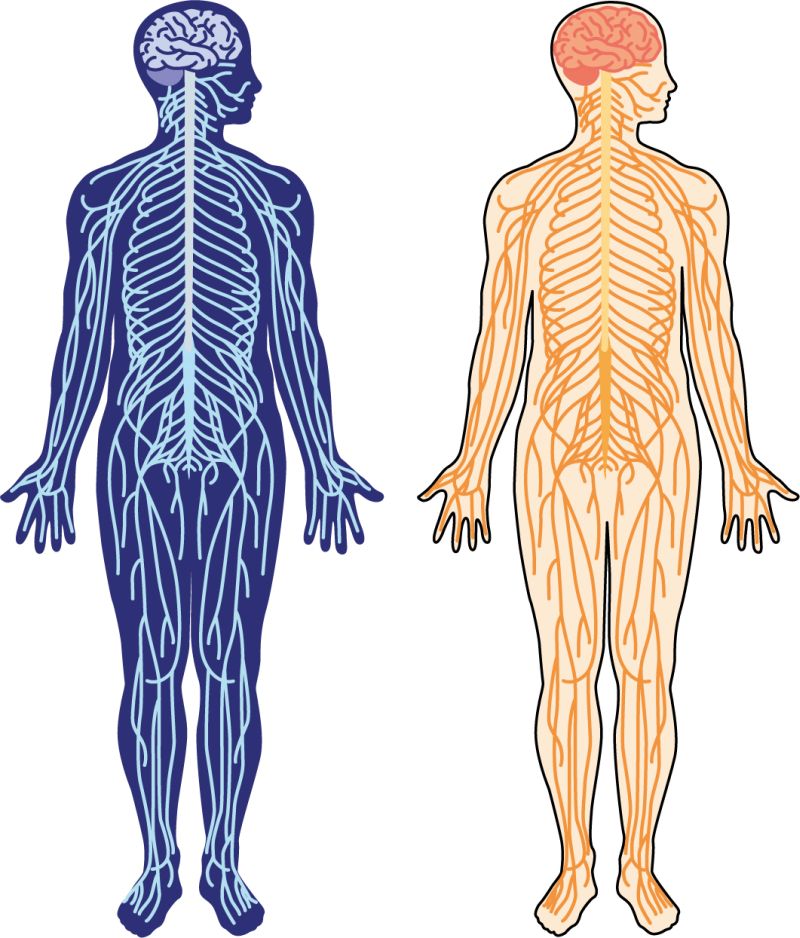
私たちの体には、無数の神経が広がっていて、身体中のあらゆる部分に、その末端を伸ばしています。
一つ一つの神経細胞は、自分の担当領域の刺激を、感じているだけです。
その感覚情報は、上位の神経へと伝達され、さらに上位では神経細胞同士が、網の目のような、ネットワークを構築して、集められた情報の解析をします。
たとえば、眼球の網膜にある視細胞は、色や明るさを感じています。
一つ一つの細胞は、全体的な像の事は、わかりません。
色と明るさを感じているだけなのです。
しかし、網膜全体の視細胞の情報が、脳に集められて解析されると、そこに一つの画像が創られます。
これが視覚です。
そこに嗅覚や味覚、聴覚や触覚から送られた、情報が加えられ、全体的にそれがどんなものなのかという事が、脳の中で理解されるのです。
でも、それぞれの感覚情報を、送っている神経細胞たちは、全体的な事については、何一つ理解できません。
わかっているのは、自分が感じた感覚情報だけなのです。
それと同じように、私たち一人一人の人間も、直接理解できるのは、自分に関わる身の回りの事だけです。
もし、人類全体の無意識が、ネットワークを作ってつながっていたならば、どうでしょうか。

恐らく、個人では理解できないような、物事の理解像というものが、人類全体の意識の中では、生じているのでしょう。
ですから、無意識は常に、全体的な事を把握しているのです。
そして、全体の中の一人として、通常の意識がどのように、活動するべきかも知っているのです。
個々の存在として別々にいる者同士が、互いに惹かれ合い、相手を自分以上に大切に想ったり、相手から同様の想いを、受け取ったりする。
そんな状態を、私たちは「愛」という言葉で、表現します。
男女の愛、家族愛、友情、絆、人類愛。
いろんな愛の表現がありますが、元は全部同じです。
そこに人間関係による、人間的な制限が加えられ、歪められた事で、様々な種類の愛が、生まれたのです。
でも、人間が作った勝手な基準を外してしまえば、全部同じ愛だとわかるでしょう。
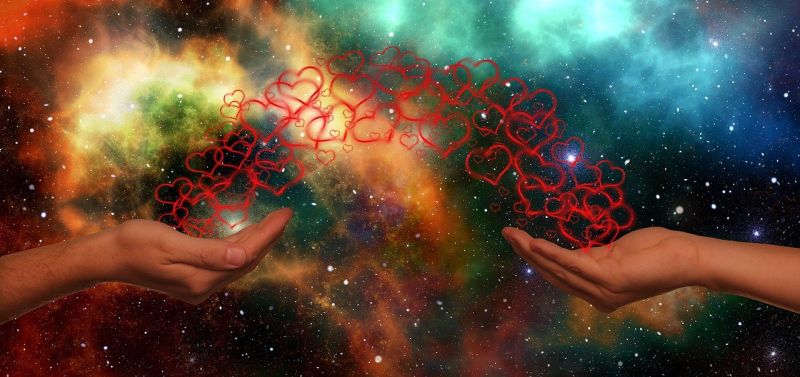
互いにつながりを持つ無意識は、自分たちが別々の存在ではなく、一つの存在である事を、理解していると思います。
通常の意識同士が、いがみ合っていたとしても、無意識の領域では、お互いはしっかりと、つながり合っているのです。
相手も自分も、同じ大切な存在であると理解し合う。
この関係は、愛と言えるでしょう。
すなわち、無意識は愛に基づいて、活動しているのです。
そして、無意識から届く情報は、愛を表現したものなのです。
日本人は、愛という言葉を使うのに、気恥ずかしさを感じてしまいます。
でも大事なのは、「愛」という言葉ではなく、この言葉が表現しようとしているものです。
英語では Love と表現され、日本語では愛と表現されるもの。
Love と愛とでは、言葉から受け取るニュアンスが、微妙に違うような気がします。
しかし、双方の言葉が伝えようとしている、オリジナルのものは同じなのです。
そのオリジナルのものは、本来感じるものであって、言葉で伝えられるものではありません。
ですから、恥ずかしがり屋の日本人は、愛という言葉ではなく、オリジナルのものをイメージする事に、意識を向けたらいいと思います。

日常の物事を判断する基準は、大抵が自分の経験や、他人から聞かされたものが、元になっています。
しかし、無意識からの声を元に、判断するようになれば、世の中の見え方が、変わると思います。
ぎすぎすして、暮らしにくいように見えていた世界が、温かく居心地のいい世界に、見えるようになるでしょう。
食べるということ

植物は根から水やミネラルを吸収し、光合成によってでんぷんを作ります。
動物は植物のように、自らエネルギーを作れませんから、植物を食したり、他の動物を食することで、エネルギーを取り込みます。
植物は大地、水、大気からエネルギーを取り込んでいます。
それを、大地、水、大気を食していると、見る事はできるでしょう。
しかし、食べるという言葉のイメージからすると、食すると言うより、エネルギーを取り込んでいるという、表現の方が適切のように思えます。

一方、動物が植物や、他の動物を食べる場合、これも実はエネルギーを、取り込んでいるだけなのですが、こちらは食べるという表現が、しっくり来るでしょう。
それは、昔からそういう表現をしているから、というのはあるでしょう。
でも、それだけではなく、食べると言った場合、他の生き物の命を、奪い取るという意味合いが、含まれているのだと思います。
人は大地や水、大気を生物とは見なしていません。
ですから、そこからエネルギーを取り込んでも、大地や水、大気を食べているとは考えないのです。
人間も含めた動物は、大気から酸素を取り込んでいますが、酸素を食べるとは言わず、呼吸をしていると表現します。
魚は水中の酸素を、鰓から取り込みますが、これもやはり呼吸です。
酸素を食べるとは言いません。
とにかく、食べるという言葉は、他の生き物の命を奪い、その体の成分を、消化器から吸収するという意味になるのです。
しかし、植物を食べる場合、その植物の命を奪っているというという、イメージが少しぼやけてしまいます。
何故なら、植物は動物のように一つの個体を、限定する事がむずかしいからです。
動物は手足や首をもがれると、死んでしまいます。
しかし、植物は枝を切られても、死にません。
草は土から上の部分を食べられても、下から新しい芽が伸びて来ます。
樹木の幹を切ると、その切り口からも、新しい芽が出て来ます。
切った枝を地面に挿しておけば、枝から根が出て生長します。

植物は動物と構造が違いますから、個体の判別や、死の定義が違うのです。
動物は一つの個体に、一つの意識があるとみなせます。
でも、植物の場合は、全体で一つの意識を持つと、考えるのが適切のように思えます。
一本一本の草木は、全体の一部であり、生長したり枯れたりするのは、全体の一部が変化しただけとみなせます。
ですから、動物が植物を食べた所で、植物を殺したとか、植物の命を奪ったという表現は、正しくないでしょう。
植物を食べる場合は、植物から養分を分けてもらっていると、受け止めるのがしっくり来ます。
別の言い方をすれば、植物から自然の恵みをもらっている、という表現になるでしょうか。
同じ食べるでも、植物を食べるのと、動物を食べるのでは、受け止め方が違うのです。
動物が、植物や他の動物を食する場合、相手に命があるなどとは、考えていないでしょう。
生まれ育った間に、相手を餌だと学習したので、食べているだけです。
しかし、人間は違います。
植物が生物である事を理解していますし、肉となった動物が、生きていた時の姿を知っています。
ただ、食べる事に夢中の人は、食材は食材としか見ないでしょう。
知識としては、それらが生物であった事を知っていても、そこに目を向けたりはしません。

でも、目を向ける人は、次第に肉を食べるのが、嫌になるかも知れません。
それは、動物が自分と同じ生き物なのだと、認識したという事でしょう。
生き物だと認識しても、肉の味を堪能し続ける人は、当然いると思います。
しかし、そんな人でも、命について深く考える機会があると、肉を避けるようになるかも知れません。
肉を食べないのであれば、自然と植物中心の食事になるでしょう。
初めは仕方なく始めた菜食でも、いつかは植物というものについて、考えるようになると思います。
そうなると、これは自然からの恵みなのだと、理解するようになります。
みんな同じ生き物であり、自然からの恵みで、命を紡いでいる。
その事を、初めは頭で理解するでしょう。
でも、やがて体でそれを感じるようになり、自分が世界の全てと、つながっているような感覚を、覚えるようになると思います。
それは超能力のような、派手さはありません。
静かで控えめで、別にどうって事ないようなものでしょう。
それでもそれは神秘的な経験です。
他のものとのつながりを、理屈で理解するのではなく、感覚で知るのです。
淡い感覚かも知れませんが、そのインパクトはとても大きいと思います。
それは世界や自分というものを、深く考えるきっかけになるでしょう。
親子関係 その2

高齢者が増えている世の中です。
子供が年老いた親の、世話をする機会が、増えていると思います。
誰にも面倒を見てもらえない、お年寄りもいます。
我が子に世話をしてもらえる人は、恵まれていて幸せだと、見られるでしょう。
でも、実際には本人が、そう感じているとは限りません。
かつては自分が、世話を焼いてやった子供です。
その子供に、親の方が子供扱いされるのです。
親としてのプライドは、大きく傷つけられるでしょう。
子供からすれば、いくら年を取ったと言っても、自分の親です。
親なら親らしく、しゃきっとしていて欲しいと、願うものです。
それに健康の話など、話せば理解してもらえると、思っています。
それなのに、何度同じ話をしても、全然理解していないとなると、だんだん腹が立って来ます。
忙しい中を、せっかくお世話を、しに来てあげているのに。
自分がいなければ、何もできないくせに、偉そうな事ばかり。
そんな不満が、出て来る事もあるでしょう。
それでも親ですから、放って置くわけにもいきません。
腹を立てながらも、世話を続けるのです。
また、自分の記憶に残っている親の姿と、目の前にいる親の姿が、あまりにも違い過ぎると、悲しいやら情けないやらで、涙が出そうになるでしょう。
感謝を求めているわけではないけれど、子供の自分をもっと認めて欲しい。
こちらの働きかけに、もっと反応してもらいたい。
そう思う事も多いと思います。

でも、親には親の言い分があるでしょう。
子供は自我が育つと、あれこれうるさい親に、反発します。
それと同じ理屈です。
親は子供が自我を持つより、ずっと前に自我を持ち、その自我で生きて来たのです。
その自我が尊重されていないと感じると、当然反発します。
あからさまに嫌な態度を、取る事もあります。
ニコニコして、ハイハイと言いながら、全然違う事をしたりもします。
また、子供に素直に感謝できない、親もいると思います。
ありがたいとは思っていても、それを態度に見せる習慣がなくて、あまり反応を示さないのかも知れません。
誰もが自分の基準で、物事を判断しようとします。
自分だったら、絶対こうするのに。
こうするのが普通でしょ。
何でこんな事が、わからないんだろう。
こんな風に、考えるのではないでしょうか。
しかし誰かが、何らかの態度を見せる時、そこにはその人なりの、理由があるのです。
それを探るには、その人の生い立ちを、知る必要があります。

本人に語ってもらうのもいいですが、人に喋りたくない事もあるでしょう。
そういう所は、その時代や状況を知っている人に、話を聞いて補完するのです。
どういう時代に生まれたのか、どんな境遇で育ったのか、どんな人たちと一緒にいたのか。
そういう要素が、その人の性格や物の考え方を、作って行くのです。
無愛想で、何をしてあげても、喜ばない人。
話を聞いているようで、全然聞く気がなさそうに見える人。
すぐに偉そうに、上から物を言う人。
みんな一見すると、勝手にしたらと言いたくなるような、人たちです。
でも、その人たちが生まれ育った背景を知ると、全然違う人物に見えて来ます。
今表に出している態度は、心の奥底の本音とは、全然違うものである事も、多いのです。
その人の本当の気持ち、本当の想いに触れてみて下さい。
その気持ちを隠そうとして、反発されるかも知れません。
だけど、誰にも言えない気持ちに、気づいてもらえるのは、とても嬉しい事なのです。
子育てに厳しかった親。
全然、子供に関心を向けなかった親。
子供を自分の手元から、離そうとしない親。
子供からすれば、とんでもない親も、世の中にはいます。
でも、親はこうあるべきなのに、とは考えないで、親の境遇を調べてみて下さい。
目の前にある性格や姿は、外から加えられた要素で、作られたものなのです。
外見の下に隠された、親の本当の姿を、見てあげて下さい。
それは、親を低く見ることではありません。
親に同情する必要もありません。
ただ、そのままの姿を、受け入れてあげるだけです。

親との関係が上手く行かない人は、自立した後でも、自分は親から愛されなかった、という思いで、苦しむ事があると思います。
でも、親の本当の姿を理解することで、自分が愛されてなかったわけではないと、知る事ができるでしょう。
それは、その人の心の傷を癒やすばかりでなく、その人を本来の輝きに満ちた存在に、導いてくれます。
年老いた人とは、単に世話が必要な人なのではありません。
その人なりの生き方を、貫いて来た人なのです。
価値観の違いなどはありますが、長い人生を生きて来られたというだけでも、尊敬に値すると思います。
ただ、その中で自分の本当の想いを、ひた隠しにして来た方は、誰かがその想いに触れて、表に出してあげると、いいと思います。
そこには、お世話や介護という言葉は、不適当なものとなるでしょう。
隠していた思いを出せた人も、それをお手伝いした人も、どちらも光輝く時なのですから。


