仕事の価値

仕事の価値は、何で決まるのでしょうか。
一般的には、得られる報酬や名声によって、決まると言えるでしょう。
お金をたくさんもらえたら、贅沢な暮らしや、気ままな暮らしができるので、多くの人が報酬の多い仕事を求めます。
場合によっては、やってはいけないような事まで、やってしまう人もいます。
同じ仕事でも、報酬が少ないと、人はやりたがりません。
ところが、災害などでひどい目に遭った人が、困っているのを知ると、普通は誰もがやりたがらないような作業を、無償でするのです。
つまり、普段は金銭的価値観に基づいて、仕事の価値を決めているものの、災害などの時には、金銭的価値観は脇に置いて、別の価値観で仕事をするということです。
災害時のボランティアの仕事は、仕事をする方にも、される側にも、とても価値ある作業です。
しかし、金銭的価値観に基づくと、まったく価値のない仕事となるでしょう。
このように、仕事の価値とは、その時の状況、その人の価値観によって、大きく異なるものなのです。
世間の全ての人にとって、絶対的に価値がある仕事なんて、存在しないということですね。
誰かにとって価値があるからと言って、その仕事が自分にも価値があるとは、限らないのです。

ところで、何故ボランティアの仕事は、報酬がないのに価値があるのでしょうか。
それは誰かの役に立つことができたという、人としての満足感があるからでしょう。
これは、とても重要なことです。
人としての満足感が得られなければ、どんなに報酬が高くても、どれほど名声がもらえても、得られる喜びは一時的であり、また深いものではありません。
ともすれば、当たり前になってしまって、喜びすら感じなくなるかもしれません。
一方、人としての満足感が得られたら、それは何にも代えがたいものとなるでしょう。
その喜びは継続され、普段から誰かのことを、考えるようにしてくれると思います。
経済的暮らしのことを考えれば、金銭的価値観に基づいた仕事が、選ばれるのは当然でしょう。
しかし、人として生きることを忘れないのであれば、人としての満足感が得られる仕事を、選ぶべきだと思います。
今の世の中は、お金がないと暮らせない、仕組みになっていますから、ある程度、報酬のことは考えねばならないでしょう。
でも、人としての満足感を捨ててまで、報酬を追い求めたのでは、かえって喜びの薄い人生となってしまいます。
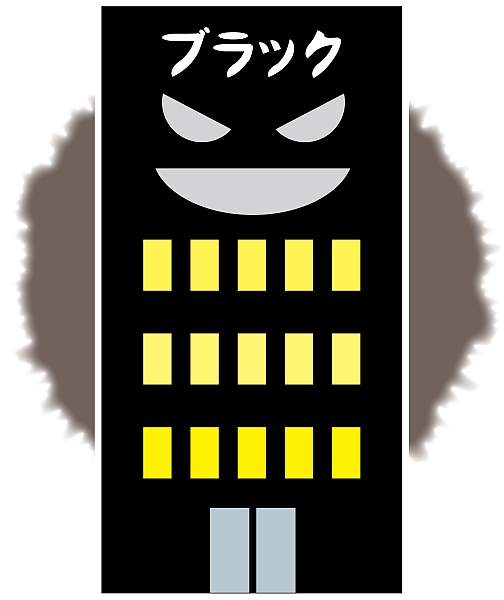
ブラック企業では、口でうまいことを言って、従業員をこき使ったり、頭ごなしに人格を否定するような、脅しをかけたりして、むりやり仕事をさせるようです。
働く人の存在や人間性を、軽視あるいは無視するような職場環境では、人としての満足感など、得られるはずがありません。
こういう企業では仕事そのものが、社会のためにという発想が、ないものだと思われます。
客でも従業員でも、利用できるものは全て利用して、金儲けをするということが、目的なのでしょう。
どれだけの報酬をもらえるのは知りませんが、こういう所は働くに値しないと思います。
人は誰もが、誰かに利用されるために、生まれて来るのではありません。
利用されているだけだと感じたならば、そんな所は、さっさと離れるべきでしょう。
どうせ仕事をするならば、自分にとって、本当に価値のある仕事をするのが、いいに決まっています。
そんな仕事を探すのは、なかなか大変かもしれません。
それでも探していれば、いつかは必ず見つかります。
見つからない場合は、この地域でないとだめだとか、こういう街でないとだめだとか、何か自分で制限や条件を、つけているのではないでしょうか。
一切の制限をつけずに、希望の仕事を探したならば、必ずその仕事に、たどり着けると思います。
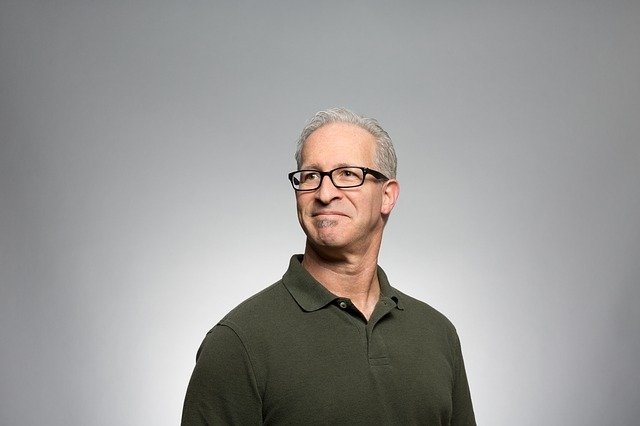
ただ自分を表現する

人は誰かに認めてもらいたいものです。
認めてもらえれば、とても嬉しく思いますし、認めてもらえなければ、とても寂しく感じます。
認めてもらえるかどうかは、人間社会を生きて行く上で、重要なことです。
定年後に、年賀状が来なくなったことに、愕然としたり、付き合う人が少なくなったことで、落ち込む人も少なくないと聞きます。
インターネットに記事や動画を投稿して、多くの人に同意をもらうというのも、認めてもらいたいという、気持ちがあるからでしょう。
せっかく投稿しても、誰にも見向きもしてもらえなければ、がっかりするに違いありません。
それは他人に認めてもらえなければ、価値がないという、判断基準が働いているからです。
誰かに喜んでもらえれば、それはとても素敵なことでしょう。
それを、自分が認めてもらえたと、受け止める人もいると思います。
でも、誰かに喜んでもらうのと、自分が認めてもらうとでは、ちょっと意味が異なります。
同じことのように思うかもしれませんが、両者は視点が違うのです。
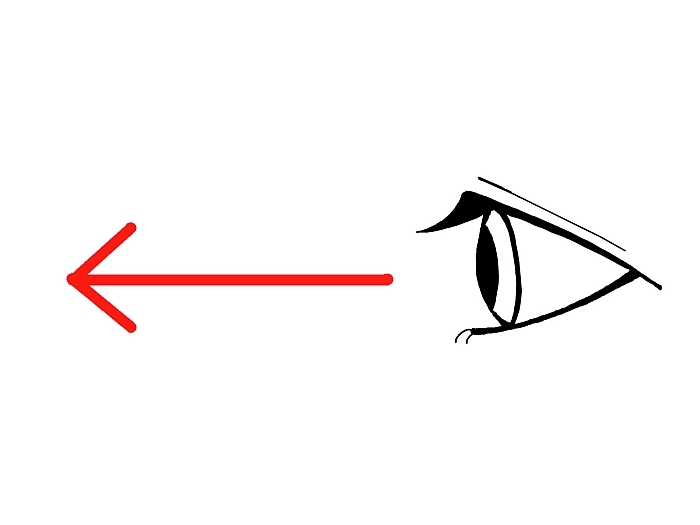
喜んでもらうという気持ちには、自分のことは含まれません。
何故なら、自分に視点があるからです。
認めてもらうという気持ちには、相手のことは含まれません。
何故なら、相手に視点があるからです。
同じ状況を眺めてはいるのですが、その受け止め方が正反対なのです。
喜んでもらうという視点は、自分の視点ですから、人生の舵取りを自分でしています。
一方、認めてもらうという視点は、他人の視点です。
この場合、人生の舵取りを他人に任せているわけで、相手の状態次第で、こちらの人生は振り回されてしまいます。
こういう人の人生は、常に受け身であり、世の中に流された状態にあります。
自分のことを自分で決められず、これから先どうなるのだろうと、常に不安を抱き続けます。
でも、自分視点で生きている人は、自分の足で人生を歩みますから、世間がどうであろうと、その時の状況に応じた、生き方ができるのです。

他人に認めてもらおうとすると、自分の生き方を、抑えないといけないこともあります。
生きているのに、生きている実感が、湧かなくなるのです。
認めてもらうための生き方は、義務的であり、堅苦しくて息が詰まるようなものです。
そこまでして頑張っているのに、認めてもらえなければ、絶望するしかありません。
しかし、認めてもらおうと思わなければ、人生の主導権を自分の手で握れます。
生きている実感も、湧いて来ます。
自分の生き方を抑える必要はなく、思ったとおりに生きることができます。
それは、のびのびとした、躍動感あふれるものになるでしょう。
その生き方は、ただ自分を表現する、というものになるのです。
結果なんて考えなくても、活き活きとしていれば、必ず受け入れてくれる人が現れます。
その人たちとは、心が通い合うようになり、一体感を持つようになるでしょう。
その人たちの喜ぶ顔が見たいという気持ち。
それを表現することが、自分を表現することとなり、自分も他の人も共に喜ぶということに、つながって行くのです。
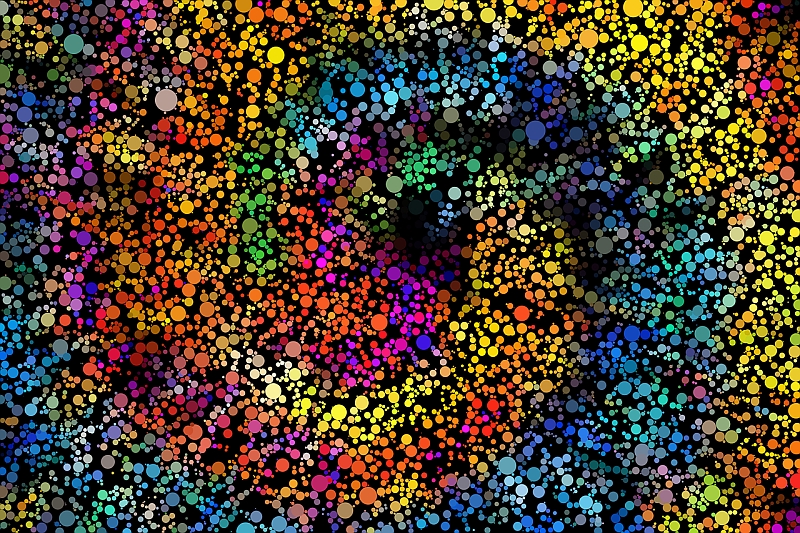
また個人レベルでは、わかりにくいかもしれませんが、人類全体の意識で考えると、全体の一部である個人の意識が、どのようなものであるかは、とても重要なことなのです。
ただ自分を表現するというのは、素直に自分らしさを出す、という意味です。
本来の自分らしく生きる、ということなのです。
それができる人の心は、とても美しく輝いています。
誰かがその人を認めようと認めまいと、その人の心が輝くことには、関係ありません。
人類全体の意識にとっては、この輝く心こそが大切なのであり、この世界で認められるか否かは、どうでもいいことなのです。
認められれば嬉しいでしょうが、そこにこだわる必要はありません。
ましてや、認められることを、人生の目的に据えてしまうと、苦労ばかりが多くて、実りの少ない人生になるでしょう。
自然に咲く花たちは、自分を認めてもらおうとして、咲いているのではありません。
それが自分の本来の姿だから、咲いているだけなのです。
どうすればいいのか迷った時には、野に咲く花たちを、眺めてみるといいでしょう。
彼らの姿を見ていると、自分がどうすればいいのかを、感じ取れると思います。
他の人が何を言おうと、世間からどう評価されようと、自分らしく生きることに、そんなことは関係ないのです。
自分は自分の花を、咲かせるのだと思い、そのような生き方をして下さい。

何故 夕日は美しいのか

夕日は美しいですよね。
夕日と言っても、見る場所や条件によって、様々な見え方をします。
それぞれの見え方に対する、好みはあると思いますが、いずれの夕日も、美しいのは間違いなでしょう。
では何故、人は夕日を見て、美しいと思うのでしょうか。
いろいろ説明はあると思います。
でも、私はこう思うのです。
夕日を見て美しいと思うのは、それはその人の心が、美しいからだと。
これは何も、自分の心は美しいのだと、言っているわけではありません。

テレビやラジオの番組を視聴するためには、情報を送信する側と、情報を受信する側の、波長が合う必要があります。
それと同じで、送信された美しさを受信するためには、その美しさと同じ波長が必要なのです。
美を理解するということは、その人の心に、美が存在しているということです。
幸せが何かを知らない人は、他人を幸せにできないのと同じで、心に美を持たない人は、美を見せられても、理解できないでしょう。
どんなに悪い人間だと思われている人でも、あるいは、自分なんて何もいい所がないと、考えている人でも、夕日を見てきれいだなと感じられるのであれば、その心の本当の姿は、とても美しいのだと言えるのです。
そのことに気づかないか、そんなはずがないと否定しているために、自分は歪んだ人間なのだと、半ば投げやりな気持ちで、人生を送る人はいると思います。
でも、そんな人に対して、私は言いたい。
あなたの本当の姿は、夕日のように、とても美しいのだと。

美しく感じられるのは、何も夕日に限ったことではありません。
花だって美しいですし、山や海などの風景も、美しいです。
それらを美しいと思えるのであれば、やはりその人の心は、美しいのです。
また、美しいばかりでなく、そこに生命を感じたり、神々しさを感じたり、素晴らしさを感じたりすることもあるでしょう。
それは、自分自身の生命を感じ、自分自身の神々しさを感じ、自分自身の素晴らしさを感じているのです。
だからこそ、頑張っている人の姿を見ると、自分も頑張れる気持ちになれるのです。
また、逆に好きなことをしている人は、他の人が好きなことを、やりたいという気持ちが、理解できます。
誰かの中に、愛を見た時、その人の心は、愛そのものになっています。
人は自分を否定しがちです。
自信を失い、不安を抱えることが、多いと思います。
でも、夕日を見たり、花を見たり、じゃれ合う子犬を見たり、小さな子供の笑顔を見たりして、胸に温かいものを感じたならば、そこに感じているものこそが、本当の自分なのだと理解して下さい。

日本人だと口にするのが、恥ずかしいと思うかもしれませんが、あえて言わせてもらうと、そんなあなたは、愛そのものであり、光そのものなのです。
何も不安に思う必要はありませんし、自分を小さく見る理由がありません。
あなたは、自分が感じたとおりに、生きることができますし、生きればいいのです。
願いが叶うとき

自分一人の力で、何かを行える時、それを願いが叶ったとは言いません。
目玉焼きが食べたいと思い、自分で卵を焼いて、目玉焼きを作ったとしても、目玉焼きが食べたいという、願いが叶ったとは言わないでしょう。
何かを願うというのは、自分の力量を超えたところでの、望みや期待を持つということです。
目玉焼きが食べたいと思っても、家に卵がなく、卵を買うお金もなかったら、目玉焼きを作ることができません。
それでも、どうしても目玉焼きが食べたいと思った時、遊びに来た友だちが、差し入れだと言って、卵をくれたらどうでしょうか。
その卵で友だちが、目玉焼きを作ってくれれば、間違いなく願いが叶ったと言えるでしょう。
たとえ自分で目玉焼きを作ったとしても、やはり願いが叶ったと言っていいと思います。

願いが叶うとは、自分の力を超えた所で、自分の望みを叶えるような、思いがけない外部の動きが、あることを言うのです。
この目玉焼きの例では、自分の願いに、友だちの心が反応してくれた、ということです。
つまり、願いが叶う時には、誰かの心が反応を示し、願いが叶うように動いてくれるのです。
もちろん、動いてくれる人たちは、願いのことなど知りません。
何となく動いているだけです。
でも、それが結果的に、願いを叶えることに、つながっているのです。
人の心を無意識の領域で考えると、それぞれの人の無意識が、つながりを持っていると考えられます。
個人意識が、人類の意識の一部であるならば、人類の意識を通して、個人と個人の無意識が、つながりを持つのは、自然なことだと思います。
誰かの願いが、その人自身の無意識に届いた時、その願いは人類意識を介して、他の人たちの無意識へと、伝わるのです。
ただ、願いと言っても、表面的な願いと本音の願いでは、中身が異なる場合があります。

宝くじを当てたい、と願ったとします。
その理由は、宝くじの賞金で、苦労した親に家を買ってあげたい、というものです。
結果として、宝くじが当たらなければ、願いは叶わなかったことになります。
しかし、借家ではあるけれど、便利で居心地のいい家が見つかり、親もその家をとても気に入ったとすれば、願いは叶ったと言えるでしょう。
この場合、本音の願いは、親にとって居心地のいい住処を、見つけたいということです。
そして、その願いを叶えるために、家を提供する人や、それを伝える人などが、自分では意図しないまま、動いたというわけです。

願いが叶う場合、恐らく、その願いの規模に応じただけの、複数の人々の無意識が、関わっていると考えられます。
しかし、願いはしたけれど、やっぱり願いが叶うはずがないな、と考えていると、それは願いが外れた状況を、望んでいるのと同じになります。
それが本音として無意識に伝わると、願いが叶わないようにせよと、他の無意識たちに伝わります。
それで、誰も願いを叶えるための、動きを見せず、願いは叶わないこととなるのです。
また、自分が無意識とのつながりを否定していたり、他の人々との間に壁を作って、つながりを拒絶していると、やはり、その願いが叶うことはないでしょう。

願いが叶うというのは、少なくとも自分自身の無意識と、つながっている必要があると思います。
つまり、無意識の声に耳を傾け、自分の本音を知るということです。
こういう人の願いは、自分の本音とつながっています。
それは無意識の指示に従っているのと、同じ事です。
通常の意識の願いと、無意識の本音が一致しているのです。
通常の意識の願いと、無意識の本音が一致していないと、願いは無意識に伝わらないかもしれません。
無意識を通して、願いを叶えるために、他の人たちの協力を得るには、無意識の本音と願いの方向が、同じであることが、重要だと思われます。
両者が一致すると、無意識は願いを実現するため、他の人たちの無意識に、情報を伝達します。
そして、思いがけない形で、願いが叶うという仕組みなのだと、私は考えています。

ただ、他の人を拒絶する習慣があると、せっかく自分の願いに従って、動いてくれる人がいても、その人たちを無視したり、拒絶するかもしれません。
そうなると、本来なら叶っているはずの願いを、自ら捨ててしまうことになるでしょう。
逆に考えれば、他の人たちのことも認め、その存在を受け入れるという姿勢が、願いを叶えるためには大切なのです。
繰り返しますと、まずは自分の心の声を聴き、自分の本音を知るということ。
それから、他の人たちとの間に、壁を作ったりしないで、その人たちの存在を受け入れ、感謝や思いやりの気持ちを、持つということです。
体で言えば、ある部分が痒みの信号を、発したとしましょう。
その信号は、全身に広がる神経ネットワークを通じ、痒みを解消してくれる部分の、動きを促します。
つまり、突然手が現れて、その部分の痒みを解消してくれるのです。

それと同じで、私たちの意識は、人類の意識という、巨大な一つの意識を形成しています。
一人一人の無意識が、大きなネットワークを構築しているのです。
そのネットワークを通じて、個人意識の望みは、全体の意識へ伝わり、その望みに必要な者たちが、望みを叶える行動を取るのです。
痒い部分を掻く手は、自分の動きの意味は、わかりません。
そうしたくなったから、その部分を掻いただけなのです。
それと同じように、願いを叶えてくれた人たちは、個人的には自分の行動の意味を、理解していません。
無意識レベルでは理解しているでしょうが、通常の意識では、わからないのです。
そんな感じで、願いというものは、叶えられるのだと思います。
そのためには、自分を大切にし、他の人のことも大事に思うことが、必要なのです。
一番いいのは、全ての人が、本当は一つの存在なのだと、心から理解することでしょう。
自分たちは一つだと理解するほど、願い全体の無意識に伝わりやすくなり、叶えられる可能性が、高くなるに違いありません。
自己犠牲

自分の気持ちを抑えて、他の人のために動く。
そんな話は、よく美談として伝えられます。
本当はやりたいことがあるのに、辛抱して仕事をする。
本当は買いたい物があるのに、我慢してお金を他へ回す。
外国の事は、よく知りませんが、日本では自己犠牲が尊ばれる傾向が、あると思います。
大切な人を守るため、自らの命を犠牲にする。
こういう話は、多くの人の涙を誘います。
そして、自分を犠牲にした人は、人間の鏡とされます。

確かに、自分のことよりも、他人のことを考えて行動できる人は、素晴らしい感性を持っていると思います。
でも本人が、他人のために自分を犠牲にしたと、思ったかどうかは、本人に確かめてみなければ、わからないでしょう。
こういう方たちをお手本にして、人間とはこうでなくてはいけないと、思い込んでしまった人は、我が身を犠牲にして、他人を助けようとするかもしれません。
一方で、他人のために動くことが、自らの喜びだと感じる人は、咄嗟の場面で反射的に動いてしまいます。
その結果、自らの命を落としてしまうことも、有り得ますが、本人はそれを犠牲だとは、考えないに違いありません。
命を落とすのは結果であって、命を捨てたわけではないのです。
その行動の原動力は、ポジティブなエネルギーであり、その行動は、本人の意思に従ったものです。
それに対して、いい人間は自分を犠牲にするものだと、思い込んでいる人のエネルギーは、ネガティブです。
見た目は同じような行動であっても、エネルギー的には全然別物です。

親が子供に、人としての生き方を教える時、誰かのために行動する人を、お手本にすることは、よくあることです。
でも、そのお手本となる人が、他人のために自分を犠牲にしていると説明し、自己犠牲を美化してはいけません。
子供がそれを真に受けると、その子は将来、とても窮屈な人生を送ることになるでしょう。
場合によっては、悲惨な結末を迎えるかもしれません。
教えるのであれば、他人を助けることが自分の喜びであることの、素晴らしさを教えるべきなのです。
自分の喜びと、他人の喜びが一致する時が、最高の喜びであることを、教えないといけません。

自分が喜ぶことは大切です。
そこに加えて、他人が喜んでくれれば、喜びは何倍にも膨らみます。
その経験は、自分の喜びは誰かの笑顔だ、という思いを創るでしょう。
誰かにつくすために、犠牲は必要ないのです。
犠牲を求める風潮は、ブラック企業をはびこらせます。
誰かを利用して、自分が得をしようという、ずる賢い者たちに、力を与えることになるのです。
自己犠牲が当然のものとして強いられ、それを拒絶できない人には、悲劇が待っています。
自己犠牲を称賛したくなる時、自分はブラック企業や、ずる賢い者たちを応援しているのだと、考えて下さい。
自己犠牲はいらないのです。
まず、自分を大切にする。
自分を大切にできない人に、他人を大切にすることはできません。
そのためにも、まず自分を大切にするのです。
それを維持しながら、他人へも気持ちを向けると、自分を犠牲にしなくても、他人のために動けるようになります。
自分が満足し、世の中が喜びに満ちたものになるためにも、自分を大切にしなければなりません。
権利と義務
権利とは何か。
辞書によると、「ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力」とありました。
また、「一定の利益を自分のために主張し、また、これを享受することができる法律上の能力」とも書かれていました。
これに対して、義務の意味は次のとおりです。
「人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め」
「倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと」
「法律によって人に課せられる拘束」
要するに、権利とは、やりたいことを自由気ままに行うことを、当然のものとして認めてもらうことですね。
一方で、義務とは、やらなければならないことです。
権利にしても義務にしても、自分以外の存在が必要です。
権利を行使するにも、義務を果たすにも、相手がいなくては、どうにもしようがありません。
山に向かって、土地の所有権を叫んだところで、土砂崩れで埋もれてしまえば、おしまいの話です。
絶滅に瀕している生物がいた時に、その生物を救うか、その生物の遺伝子情報を残すのは、人間の義務であると、考える人がいるかもしれません。
でも、それは義務ではなく、その人が勝手に信じている、使命感でしょう。

権利にしても義務にしても、人間が安心して暮らして行くために、人間によって作られた決まり事です。
それが通用するのは、人間社会の中だけです。
それも、共通の理念を持った者で、構成された社会の中だけです。
国や民族、宗教によって、理念が異なる場合、互いが主張する権利や義務は、噛み合わないことがあります。
その場合、大抵相手が間違っているという結論になり、相手を非難するか、時には暴力的な争いが生じます。
つまり、権利にしても義務にしても、その効能があるのは、地域限定の社会の中においてだけなのです。
それを他の地域に行って、そこで自分の権利を主張すると、トラブルになるのは当然です。
また、その地域における義務を、不本意だと憤慨するのも、間違っています。
こういう問題には、時々いろんな所で遭遇します。
トラブルを避けたいのであれば、あらかじめその地域の風習や、慣習などを調べておき、自分に合う場所か、確かめておけばいいのです。
しかし、元々いる地域でも、差別や無関心が絡んで来ると、権利が平等でなく、一部の者に偏っていたり、その人の事情に関係なく、これは義務だからと言って、無理難題を押しつけるということが、あるでしょう。
結局、社会を安定させるための権利や義務は、力の強い者にとって、有利な内容になってしまうのです。
そもそも、権利や義務という言葉が存在するのは、そういうものがなければ、社会がまとまらないという事情があるからでしょう。
権利や義務が、しっかりしている所は、進んだ社会であるように思われがちです。
しかし、裏を返せば、そんなことを明記しなければ、成り立たない貧弱な社会だとも、言えるでしょう。
無益な争いや、虐げられた者が存在するから、権利や義務という言葉が、生まれるのです。

たとえば、育児放棄をする親がいます。
こんな親には、子供を育てるのは、親の義務だと説教が必要になります。
でも、本当は子供は義務で育てるのではなく、愛情で育てるものでしょう。
子供に対する愛情を、感じられないというところが問題なのです。
義務だからと言って、無理に育児をさせようとしても、こういう親は、他の人が見ていない所で、何をするかはわかりません。
そして、それは子供の心に、深い傷を負わせることになるのです。
子供の立場から言えば、ちゃんと育ててもらう権利が、自分にはあるということでしょう。
でも、そんな事を訴えられる、子供なんていません。
訴える力があったとしても、子供が求めるのは権利ではなく、愛情のはずです。
相手への思いやりや配慮が、十分になされる社会であれば、権利や義務について、一々明記しなくても、何も問題は起こらないでしょう。
逆に明記するから、これは書かれていないぞ、という論法で、好き勝手をする者が出てくるのです。

これだけ人間の数が増え、様々な主義主張が、飛び交う世の中ですから、権利や義務を規定しないといけない事情は、理解できます。
しかし、権利や義務という言葉があるうちは、人間はまだまだなのです。
現に、起こらなくてもいいはずの争いが、様々な場面で起こっています。
自分の権利を主張するがあまり、憎まなくてもいい人のことまでも、憎むようになっています。
自分が何かを主張したい時は、必ず相手の事情を、考慮するという、思いやりを持つべきでしょう。
主張するにも言葉を選び、相手の気持ちも考えて、どうすればいいのかを、共に考えて行くという社会を、作らなくてはなりません。
義務と言われることも、自ら進んで行えば、義務とはなりません。
互いを思いやり、みんなでやろうという思いがあれば、義務など必要ないでしょう。
そんな中でも、参加できない人には、それなりの事情があるはずです。
それを強制的に参加させるのは、思いやりがあるとは言えません。
今の世の中は、自分の権利を守ろうと固執する人が、とても目立ちます。
自分勝手と思えるほどの、権利への固執は、人々を不快な思いにさせるかもしれません。
でも、権利への固執にも理由があるのです。
恐らく、権利を失えば、大きな損失により、不便かつ不愉快な人生を、強いられるという不安があるのでしょう。
でも、損失と思えるものよりも、よくなったと思えるものの方が、大きいと理解できれば、権利に固執する必要はなくなります。
互いを思いやれる世の中になり、何かを失うことを、恐れる必要がなくなれば、権利に固執することはなくなるでしょう。

人は誰もが自由です。
自分が自由でいるためには、他の人の自由も、尊重しなければなりません。
自由の多様性と協調を、楽しめるようになれるのが、一番いいのです。
権利も義務も、あとから作られたものであって、最初からあったわけではありません。
権利や義務は、社会を安定させるための、一つの方策ではあります。
しかし、もっと優れた安定方法を、人類は求めて行かなくてはならないと思います。
意識と時間

意識と時間は、切っても切れない関係にあります。
意識の活動には、必ず時間という要素が、必要となります。
時間が凍りついた状態では、意識も凍りついて、活動ができません。
時間の変化なしに、何かを思考できるか、確かめてみて下さい。
あなたが何かを考えたり、何かを感じたりしている間、時間は必ず過ぎて行きます。
この時間とは、時計の針の動きのことではありません。
心の中にある時間です。
たとえば、ほんのわずかな時間、うたた寝をした時に見た夢で、1時間以上の時間が経ったと思っていたのに、目座覚めてみると、5分ほどしか経っていないということが、あると思います。

嫌な仕事をしている時は、時間がなかなか流れないような気がします。
でも、好きな仕事をしている時は、知らない間にかなりの時間が、経っているということがあります。
心の外の世界と、心の中の世界とでは、時間の流れ方が、異なることがあるのです。
私がここで述べている時間とは、意識の活動が関わる時間です。
覚醒している時には、基本的に外の世界と同じ、時間の流れになります。
外の世界の時間に、心の時間を同調させるのですね。
しかし、ぼんやりしていたり、夢を見ている時など、意識が外の世界から遮断されている状態では、意識は外の世界とは、違う時間の流れにいるのです。
いずれにしても意識の活動に、時間の流れはつきものです。
時間の流れがなければ、意識は活動できません。
でも、これは意識と時間を、別物と考えての話です。
実は、時間というものは、意識の一つの側面なのです。
意識と時間とは別々にあるのではなく、意識の変化を時間という言葉で、表現しているだけなす。
意識は変化がなければ、存在していないのと同じです。
何らかの変化が生じるからこそ、それを活動と呼ぶことができるのです。
そして、その変化は時間に応じて起こるのではなく、変化する状態を、時間の流れという言葉で、表現しているのです。
意識がなければ、時間も存在しません。
でも、私がこの世を去ったとしても、この世界は残り続け、この世界の時間は流れ続けるでしょう。
それは、この世界自体が、大きな意識だからだと言えます。

世界の意識は、私たち人間がイメージするような、意識ではないでしょう。
でも、世界の本質は精神エネルギーだと理解すると、時の流れが存在していることに、納得が行くと思います。
私たちの意識は、直接この物質世界に、存在しているのではありません。
物質で構成された肉体を介して、この世界を体験しているだけであり、この世界に直接関わっているわけではないのです。
目覚めている間は、肉体を通して認識する、この世界独特の時間の流れに、自分の意識を合わせています。
しかし、ぼんやりしたり眠ったりして、この世界とのつながりがなくなると、本来の自分の意識の持つ、時間の流れで思考するのです。
それは、私たちの意識が、直接には物質世界に、関わっていないからなのです。
意識と時間は、別物ではありません。
意識のあるところに、時間は存在します。
また、時間が存在しているところには、意識が存在しているのです。
子供たちの心
とても素敵な記事がありました。
難病で視力を失った男性を、小学生の子供たちが、助け続けていたという話です。
和歌山市職員の山崎浩敬さんは、網膜色素変性症のため視力を失い、2005年から白杖を使いながら、通勤するようになったと言います。
初めは家族が付き添ってくれていましたが、2008年からは一人でのバス通勤になりました。
しかし、目が見えないため、バスの乗り口を探すのも、大変苦労されたようです。
ところが、一人でのバス通勤を始めて、一年ほど過ぎた頃、「バスが来ましたよ」と女の子の声がしたそうです。
「乗り口は右です。階段があります」と言いながら、山崎さんを座席に案内してくれた女の子は、それから毎日、学校を卒業するまで、山崎さんを助けてくれました。
女の子は、和歌山大付属小学校の児童で、山崎さんと同じバスで通学し、降りる停留所も同じだったそうです。
女の子が学校を卒業したあとも、別の女の子が山崎さんを助けてくれるようになり、その子が卒業しても、また別の子が助けてくれました。
子供たちの間で、山崎さんの力になるということが受け継がれ、また、子供たちとのお喋りが、山崎さんの楽しみとなりました。
それは、誰かに助けてもらったということ以上の、大きな喜びとなったでしょう。
その喜びは山崎さんにとって、思いがけない贈り物になったと思います。
喜びは相手にも広がります。
そのことは子供たちにとっても、思いもしなかった、お返しとなったに違いありません。
山崎さんは、自分を助けてくれた女の子たちが、全部で四人だと思っていました。
しかし、和歌山大付属小学校で、女の子たちに再会した時に、山崎さんが知らされた話では、他にも山崎さんを、助けてくれていた子供たちが、いたということでした。
そのことに山崎さんが、気がつかなかったのは、その子供たちが、そっと山崎さんを助けていたからでしょう。
自分が知らないところで、たくさんの子供たちが、助けてくれていたのだと知り、山崎さんはとても感激した様子でした。
思い切って行動を示す優しさもあれば、目立たないところで、そっと向けられた優しさもあります。
どちらも本当に素敵なことです。
そのような優しさを示すことができたのは、子供の心が素直で、純真だからなのかもしれません。
こういう子供たちに恥じないように、大人である私たちも、人に優しい気持ちを、持ち続けたいと思います。
そして、目に見える優しさ、目に見えない優しさの双方に、これからもしっかりと、目を向けて行きましょう。
未来を思い出そう

過去を懐かしんで、思い出すことって、ありますよね。
あるいは、思い出したくもない過去も、あるかもしれません。
過去とは文字通り、過ぎ去ったことで、自分が経験あるいは認識したものです。
それは記憶として残り、私たちは記憶を探ることで、過去を思い出すことができます。
それに対して、未来というものは、これも文字通り、未だ来ないことであり、まだ経験も認識もできていないものです。
一寸先は闇という言葉があるように、次の瞬間のことでさえ、私たちは何が起こるのかがわかりません。
わからないから、ただ世の中の流れに流されたり、手探り状態で身動きが取れなくなったり、するのでしょう。
でも、過去と同じく、未来もすでに存在していて、それがどんなものかを、知ることができればどうでしょうか。
私たちは、未来はまだ未確定で、確かなものは何も存在していないと、受け止めがちです。
しかし、過去に対する記憶障害のように、未来についての情報を、すっかり忘れているとすれば、どうでしょうか。
人は何かを学ぶために、この世界に生まれて来るのだと、私は理解しています。
それが何であるのかを、今を生きる私たちは、覚えていません。
しかし、目的を持って生まれて来るということは、どういう未来に向かって進むべきなのかということが、すでに決められていると言えるでしょう。
それがわからないというのは、未来に対する記憶喪失ということになります。

でも、何かを学ぶためには、記憶がない方が好ましいのかもしれません。
何も知らないまま、ある状況において、どのような選択をするのか。
そこが重要なのだと思います。
ただ、本当に何も知らないというのではなく、大切な情報は無意識領域にあります。
ですから、目の前で起こっている状況に振り回されず、心の声を聞き取ることができれば、自分が進むべき道が、見えて来るでしょう。
過去のことを思い出す時と同じように、未来の記憶も、初めのうちはぼんやりした感じだと思います。
何となく、こっちかな、という具合でしょう。
しかし次第に、こっちだこっちだと、はっきり自分の進む道が見えて来ると、それは自分の道を、思い出して来たということです。

将来、どのような自分であるのか、どんな所で、どのような事をしているのか。
そういうヴィジョンが、具体的に目に映るようになって来た時、それを単なる想像や妄想だと、受け止めるかもしれません。
でも、本当はそうではなく、目指すべき未来像の記憶が、蘇ったと見た方がいいでしょう。
ああ、こうなる予定だったんだなと、未来の記憶を思い出したということです。
ただの妄想だととらえていると、せっかくヴィジョンが見えても、それを役立てることができません。
せいぜい、こうなれたらいいのになと、考えるにとどまってしまうでしょう。
でも、未来の記憶を思い出したと、受け止めるならば、そうだったと言いながら、すでにその未来像の自分になったつもりで、行動を取るに違いありません。

自分が何に興味を持っているのか、何を大切に思っているのか。
そういう想いは、未来の記憶を思い出していなくても、ぼんやりと進むべき方向を、示してくれます。
逆に、こんな事は絶対に嫌だ、こんなのは自分に合わない、と感じることは、進むべき道はそちらではないと、教えてくれます。
初めはこれらの方向指示器に従って、人生を進むことになりますが、そうしているうちに、自分が何を求めているのかが、明確に見えて来るようになります。
それが、未来の記憶が蘇って来た、ということなのです。
過去の記憶と同じように、思い出そうとして思い出せるものではありません。
でも、何かの瞬間、何かをきっかけにして、過去の記憶が蘇るように、ある瞬間、何かがきっかけとなって、未来の記憶も蘇ります。
何かが思い浮かんだ時、それが自分の未来の記憶かもしれないと、感じたならば、疑うことなく、その方向へ進むことをお勧めします。
それは必ずしも、現代社会で憧れとされるようなものでは、ないかもしれません。
でも、自分の未来の価値は、自分にしかわかりません。
自分がそこに心惹かれたなら、そこを目指して進むことが、あなたの取るべき行動なのだと思います。
自分の中の自分 その2
バルーンアートで使う長い風船の、端っこの部分をひねって、小さく区切ります。
その区切られた部分が、今の自分だと考えて下さい。
この時、長い風船の残った部分は、無意識と呼ばれる意識領域です。
何故、無意識と呼ばれるのかと言うと、通常の意識活動のように、表に出て来ない意識だからです。
しかし無意識こそが、心の本体なのです。
私たちが何かを思いついたりするのも、無意識からの情報が、具現化されるからです。
私たちの通常の暮らしの中では、その名の通り、無意識がその存在を認識されることは、まずありません。
本当は存在しているのですが、完全に無視された状態です。
でも、私たちが眠りにつくか、あるいは死んでこの世界を離れた時、風船のひねられた部分は元に戻され、私たちの意識は無意識と一体化します。
夢から目覚めた時に、夢の中の人格が保持されるように、私たちの個人意識も、無意識と一体化した後でも、保持されます。
しかし、どちらが本当の自分かと考えると、やはり全体の方を、本当の自分だと言わざるを得ないでしょう。
つまり、初めに述べたように、無意識こそが本当の自分であり、私たちが考えている自分というものは、あくまでも仮の自分なのです。

元の意識である長い風船の中に、区切られた部分が、一ヶ所ではなく複数あったとしましょう。
すると、今の自分と同じような、元の自分の分身が、多く存在していることになります。
私たちは一度に多くのキャラクターを、イメージすることができます。
実生活の中においても、子供の頃の自分や、親としての自分、職業人としての自分や、男あるいは女としての自分など、多くの自分が入り交じっています。
それと同じように、私たちの本体である無意識の領域にも、私たち以外の分身が、多く存在していたと考えても、矛盾はないでしょう。
私たちには、自分の兄弟のような分身が、多く存在しているのです。
それぞれの自分たちは、違うパラレルワールドに、いるのかもしれません。
でも、今のこの世界を、別の立場から体験している、可能性もあるでしょう。
とにかく、いろんな自分の存在がいるということは、十分に考えられることです。
ここで、また違う状況を、想定してみましょう。
私たちの本体、本当の自分である長い風船が、実はもっと大きく長い風船の、一部が区切られたものだったとします。
また、そこには同じように区切られた部分が、たくさんあるのです。
そこの区切りがなくなると、私たちの無意識領域、つまり本当の自分は、さらに大きな存在である自分の一部であると、気がつくのです。
他の区切りの存在たちも同様で、区切りをなくすと、それだけ多くの存在が、互いに兄弟であることを、理解するのです。
そして、この大きく長い風船もまた、さらに大きな風船の一部であり、それが延々と繰り返されて行くのです。
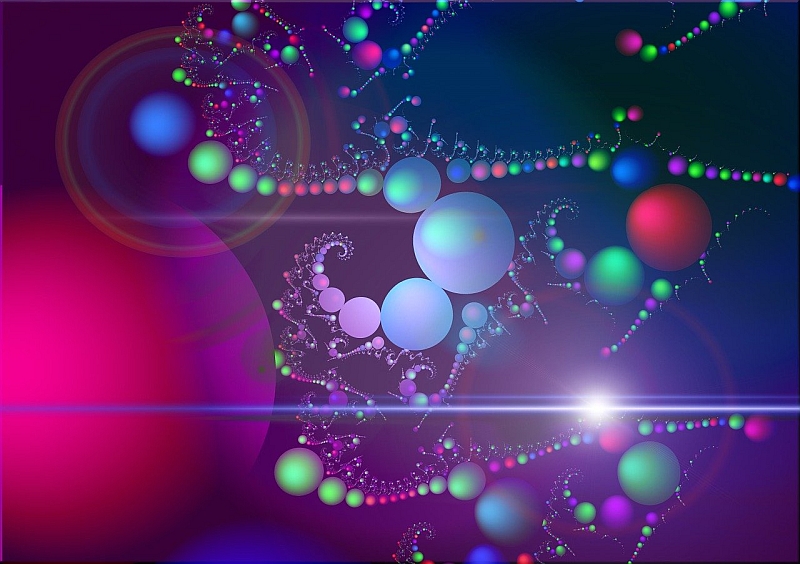
これが意味するところは、どんなに見た目が違っていても、全ての存在は兄弟であり、分身なのだということです。
考えると、頭がおかしくなりそうに、なるかもしれませんね。
だけど、少なくとも私たち人間は、性別や民族の違いを超えて、一つの存在であり、同じ存在の分身なのだということだけは、理解して欲しいと思います。
知識として知るのも大切ですが、感覚的に理解することが、最も重要です。
そして、その感覚こそが、愛と呼ばれるものなのです。

