甲賀忍者

滋賀県の甲賀市では、毎年2月22日を「ニンニンニン」で、忍者の日と規定しているそうです。
この日、市役所の職員は、何と忍者の姿で仕事をしていらっしゃいました。
今は新型コロナの影響で、みなさんマスク姿ではありましたが、それでも忍者姿でお仕事に励んでおられました。
この日、県下の小中学校では、年に一度の特別メニュー「忍者給食」が登場し、子供たちを喜ばせていました。
その内容は、地域ブランドの古代もち米「黒影米」や、手裏剣柄の「なると」が入った「忍者鍋」、忍者キャラクターの絵柄の入ったコロッケなどです。
ご馳走さまをする子供たちも、両手を合わせるのではなく、印を結ぶポーズでした。
市のPRの一環だそうですが、真面目に取り組みながら、その仕事を楽しんでいらっしゃる姿が、とても印象的でした。
特に、不安になりがちな今のご時世には、打ってつけのイベントだったと思います。
コロナウィルス感染や、生活不安に対しては、具体的に対応する必要はありますが、気分だけでも明るく前向きで、ありたいものですね。
甲賀忍者のみなさんは、そのお手本を示してくれていました。
これからも頑張っていただきたいと思います。
ポジティブエネルギーとネガティブエネルギー
ネガティブエネルギーは、反発する性質があります。
これに対して、ポジティブエネルギーは、一つになろうとする性質があります。
反発力と引力。
これは電磁力と同じですね。
電極のプラス同士、あるいはマイナス同士は、反発し合います。
これに対して、プラスとマイナスは引き合います。
磁極の N極と S極は引き合いますが、N極同士、S極同士は反発し合います。
この電磁場における引力や反発力も、実はポジティブとネガティブのエネルギーが、介在しているのかもしれません。
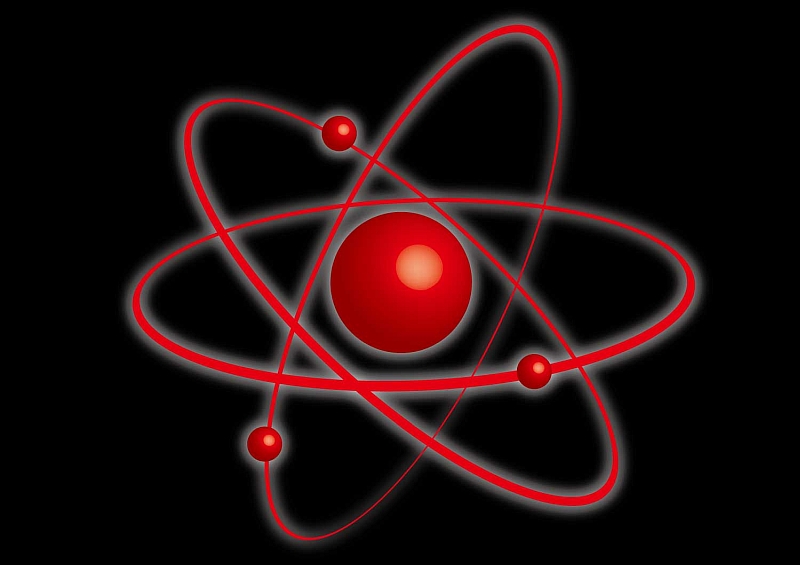
原子はプラスの原子核と、マイナスの電子で構成されていますが、上手い具合に引力と反発力のバランスが取れていて、それで原子という形が構成されています。
このバランスが崩れていれば、原子は一つの点に集約されるか、あるいはバラバラになっているでしょう。
また原子同士の引力や反発力によって、形のある物体が作られます。
これもポジティブとネガティブのエネルギーバランスが、上手く取れているからでしょう。
こう考えると、ポジティブは引力、ネガティブは反発力というだけのことで、いいも悪いもないのがわかります。
プラスとマイナスの電極があるとしましょう。
マイナスに電荷が集まり、マイナス電子がたくさんあります。
両極の間に電流が流れる時、マイナス電子はプラスの電極へ移動します。
この電子の動きは、マイナスの電極からすれば、ネガティブな動きに見えるでしょう。
一方、プラスの電極からすれば、ポジティブな動きに見えるのです。
同じ電子の動きが、電極によって、ネガティブに見えたり、ポジティブに見えたりするのですね。
でも、電子の動きそのものは、ポジティブもネガティブもないわけです。
これと同じで、何か物事が起きた時、そのこと自体は、ニュートラルの状態です。
ポジティブでもネガティブでもありません。
それをどの立ち位置で見るかによって、同じ物事が、ポジティブに見えるのか、ネガティブに見えるのかが決まるのです。

たとえば、誰かが亡くなったとします。
普通に考えれば、ネガティブなことのように思えるでしょう。
しかし、死後も魂が残り、人生は単なる学び場所に過ぎない、と考えている人は、必ずしもネガティブには受け止めません。
人生を途中で投げ出すような、亡くなり方であれば、やはりネガティブにとらえるかもしれません。
しかし、学び終えて世を去ったのだと見れば、ポジティブにとらえるでしょう。
さらに広い視野を持っている人の場合、人生を途中で投げ出したように見えても、それも一つの経験であり、いずれ学ぶべきことは、学ぶはずだと考えます。
こう考えるならば、どのような亡くなり方をしたとしても、それをポジティブにとらえることになるわけです。
結局、ネガティブかポジティブかというのは、自分の立ち位置、自分の価値観で決まるわけです。
世の中がネガティブに見えるのであれば、それは自分の立ち位置が、そのような所にあるということです。
ちなみに、ポジティブにとらえるのと、大切な人がいなくなったことを、どう感じるかは別の話です。
大切な人が突然いなくなれば、それはやはり悲しいことでしょう。
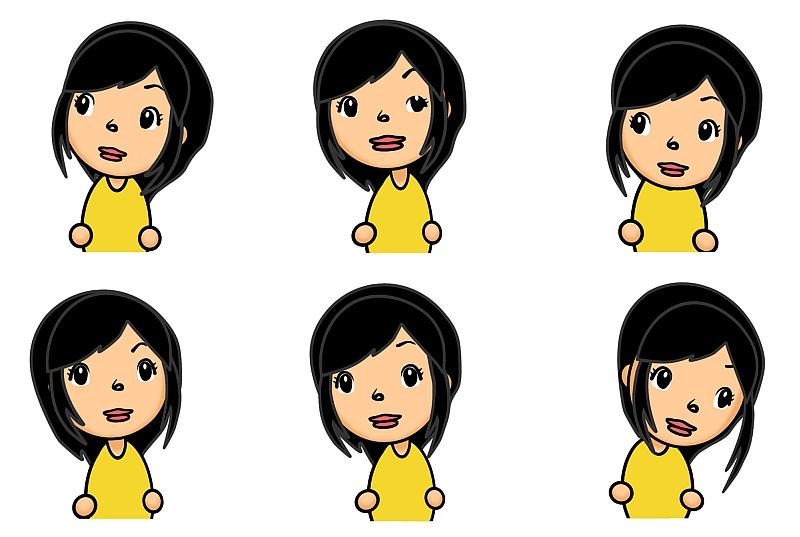
ネガティブなものを、裏から見れば、そこには必ずポジティブがあります。
物事を一方向だけから見るのではなく、いろんな角度から眺めてみるのがいいでしょう。
その上で、自分はネガティブがいいと思うのであれば、ネガティブな位置に、ポジティブがいいと思う人は、ポジティブな位置にいればいいのです。
大切なのは、両方の見方ができるというのを、知っておくことです。
電流が流れる時には、プラスの電極とマイナスの電極があるのだと、理解しておくのと同じです。
両方を知っていれば、あとは自分がどちらに立つのか、好みの問題ですね。
ポジティブを知った人が、みんなネガティブを拒絶するわけではありません。

たとえば、スポーツなどのライバルを、敵と見るのか、同じ仲間と見るかは、その競技の質や、試合の雰囲気、対戦前の約束事などで、変わって来るでしょう。
お互いに真剣勝負を望むのであれば、ゲームの間だけ、お互いを敵と見なして争うことになります。
しかし、相手を傷つけたり、殺したりするような争いにはなりません。
またゲーム以外では、互いを認め合うよき友ですし、対戦中でも、相手に対する畏敬の念は、忘れません。
こんな感じで、ネガティブとポジティブのバランスを調節しながら、楽しむのがいいでしょう。
他人の人生

他人の人生を、背負うことはできません。
もちろん、変えることもできません。
たとえ、それが自分にとって大切な人であっても、自分ではない人の人生を、背負うことはできません。
その人の世話をすることはできます。
その人を支えることはできます。
それでも、それでその人がどのように決断し、どのように行動するのかは、その人の自由です。
その人の人生を歩むのは、その人自身なのです。
こちらから見て、それがどう見えたとしても、それがその人の選んだ結果であれば、どうすることもできません。
怒ったり泣いたり、がっかりしても、どうにもならないことなのです。
できることは、それがその人の選択であるならば、それを受け止めて、認めてあげることでしょう。
否定すれば、その人の存在を否定するのと同じです。
その人が大切であるのならば、自分の感情は脇に置き、その人の選択を受け入れましょう。

選択した結果は、全て本人に戻って来ます。
人はそうすることで学び、成長するものなのです。
たとえ、それが痛みや苦しみにつながるものだとしても、その中に、その人の学びがあるのならば、他人がとやかく言うものではありません。
その人が必要とするものが、その中にあるのであれば、それを引き止めることはできないのです。
私たちにできることは、その人が必ず、そこから何かを学びとり、成長することを信じて、見守るだけです。
また、その人がどんな選択をして、どのような結論に至ったとしても、それに対して、他人は責任を感じる必要はありません。
感じたところで、仕方がありません。
もっとこうすればよかったのではないかとか、ああしてやればどうだっただろう、と考えてしまうかもしれません。
しかし、それを言い出すときりがありません。
それに、相手がこうだと決めてかかっているものは、どうにもしようがないのです。
その時に自分ができることをして、あとは、やはり見守るだけです。

もう一つ大切なことは、自分自身が自分の人生を歩むのを、忘れないということです。
学びと成長は、自分にも必要なものです。
他人の人生に振り回されて、自身の人生に目を向けることができないのは、苦しい思いをするばかりで、少しもいいことはありません。
ただ、それも一つの学びでありますから、そこから自分の人生の大切さを知る、ということになるのかもしれません。
いずれにしても、それぞれの人生の選択権や決定権、そして責任は、その人自身にあります。
その人の人生は、その人のものなのです。
自分にできること、あるいは自分がするべきこと、それは自分の人生を生きるということです。
孤高の人

出る杭は打たれると言いますが、それでも伸びる杭もあるのです。
ところが、伸びた杭は周りの杭と比べると、一本だけ高く伸びますので、周りから浮いてしまっているようにも見えます。
これが、いわゆる孤高の人です。
何かに懸命に打ち込む人。
大きな夢を抱いて、その夢に向かって進む人。
未知の世界に果敢に挑戦する人。
常識に囚われず、信念を貫く人。
こういう方たちは、みんな孤高の人です。

周囲にいる普通の人たちには、自分が考えていることや、やろうとしていることを、なかなか理解してもらえません。
場合によって、ただの変わり者とか、頭がおかしい人と、思われかねません。
でも、自分が信じた道を諦めて、他の人たちに合わせて生きると、自分が生きている実感が湧きません。
かと言って、自分が思ったとおりに生きると、孤独感を味わうのです。
進む道に壁があっても、それを乗り越えるための苦労を、誰も分かち合ってくれません。
新しい発見があっても、誰もそれを喜んでくれません。
そんな自分を悲劇の主人公のように、受け止めてしまうと、その人は挫折したり、自らの命を絶ったりするでしょう。
しかし、どんな苦労にもめげずに、己の道を突き進んで行けば、周囲より飛び出た杭は、どんどん高く伸びて行きます。
高くなればなるほど、周囲がよく見通せるようになるのです。
そうすると、すぐ近くには自分と同じような者が、一人もいなくても、離れた所には、自分と似たような高く伸びた杭が、見えて来ます。

その状況は、向こうの杭でも同じです。
互いの存在に気がついた杭同士は、自分の仲間がいることを喜び、それを励みにするでしょう。
この場合、必ずしも杭の種類が、同じである必要はありません。
つまり、相手が自分がやっていることと、全然違うことに打ち込んでいても、構わないのです。
周囲の無理解や多くの困難にもめげずに、目指すもののために打ち込む姿が、強い親近感を持たせてくれるのです。
やっていることが違っても、そういう人は仲間だと思うでしょう。
孤高とは、初めは孤独との戦いです。
それでも、自分の道を進み続けると、必ず本当の仲間、信頼できる仲間と、巡り合うことができます。
孤高における孤独とは、人生観や世界観が、周囲の人よりも高い位置から、眺めることなのです。
それは一般の人が登れないような、大きな山に一人で立ち向かい、とても高い所から、下界を見下ろしているようなものです。

当然、それは孤独です。
しかし、とても高貴で神聖な孤独です。
山頂はまだまだ先にあっても、その山頂を目指して登り続ける、他の仲間たちの姿が見えると、力が湧いて来るでしょう。
孤高とは、そういうものなのです。
人と違う何かを、追い求めている人は、それなりの苦労をされると思います。
大変な孤独を味わうかもしれません。
それでも、その孤独は勲章です。
他の人が知らない世界へと、突き進んでいる証です。
その孤独を胸に飾って、さらに上を目指して下さい。
必ずや、仲間たちと巡り会い、喜びを感じる日が訪れますから。

ハイブリッド その3
ハイブリッドが新しい存在であるのなら、それは人類の進化と関係していると、言えるかもしれません。
それは新しい特徴を持つ人間の、登場を意味するだけではありません。
ハイブリッドの人たちを通じて、全ての人が互いを認め合い、心を一つにできれば、精神をも含めた、人類の大進化となり得るでしょう。
それは恐らく、個の意識を保ちながら、同時に全体の意識も併せ持つような、そんな存在になるのだと思います。
互いの違いで、争うことはありません。
多様性はハーモニーとして、受け止められるでしょう。
誰か一人が取り残されて、悲しむことはなくなります。
誰かの喜びは、全体の喜びになるのです。
人類が大進化すれば、そんな社会が訪れるのだと思います。

ところで、類人猿から人類への進化には、異星人が関わっているという話があります。
異星人が類人猿の遺伝子操作を行い、自らの遺伝子を混ぜることで、人類が創られたというのです。
そうであるならば、元々人類は地球の類人猿と、異星人との間に生まれた、ハイブリッドの存在と言えるでしょう。
また、そうやって誕生した人類と、異星人が直接性交渉を行えば、新たなハイブリッドが生まれるのです。
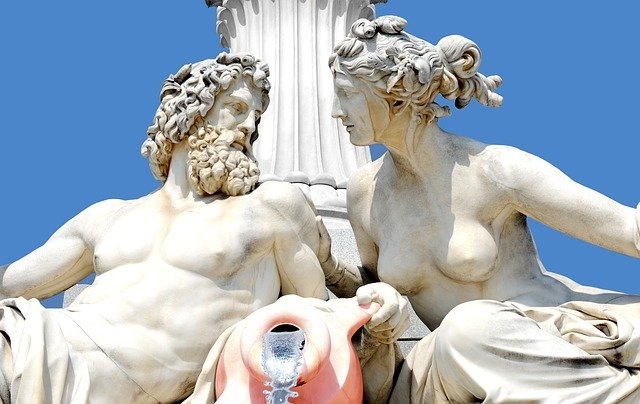
神話を読むと、神さまが人間の女性を孕ませるような話が、ありますよね。
あれは単なる作り話ではなく、異星人が人間の女性との間に、ハイブリッドの子供をもうけていたところを、表したものかもしれません。
そうだとすれば、これまでにも異星人との間に生まれた、数多くのハイブリッドが存在していた可能性もあるでしょう。
異星人が人間の姿を装っていたならば、生まれて来た子供は、自分がハイブリッドだとは、知る由もありません。
きっと、自分はみんなと同じ、普通の人間だと思っていることでしょう。
しかし、何となく他の子供たちとは、興味の対象や、物事の考え方が違っていると、感じているかも知れません。
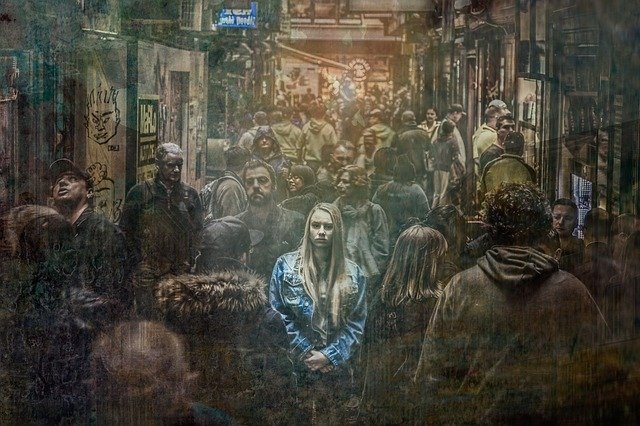
場合によれば、強い疎外感を感じて、孤立してしまうこともあるでしょう。
でも、世の中を変革へ導いて行くのは、このような人たちなのかもしれません。
実際のところはわかりませんが、異星人との間に生まれた、ハイブリッドが存在していることは、十分可能性のあることだと思います。
また、地球に数多く存在している、人種や民族の違いを乗り越えて、人類が一つになることができれば、目の前に異星人が現れたとしても、さほどショックを受けないかもしれません。
自分たちとは違う姿をしている異星人を見ると、それだけで怪物だと判断し、パニックに陥る人もいるでしょう。
人類に対して、友好的な気持ちを持っている異星人でも、面と向かって、そのような態度を見せられたら、とても悲しくなるに違いありません。
時たま UFO が目撃されることはあっても、異星人が堂々と姿を見せないのは、そういう事情があるからでしょう。
現在、地球上に存在しているハイブリッドの人たちは、自分たちでは意図していなくても、人類を大進化へと導き、異星人との交流を実現させてくれる鍵なのだと思います。
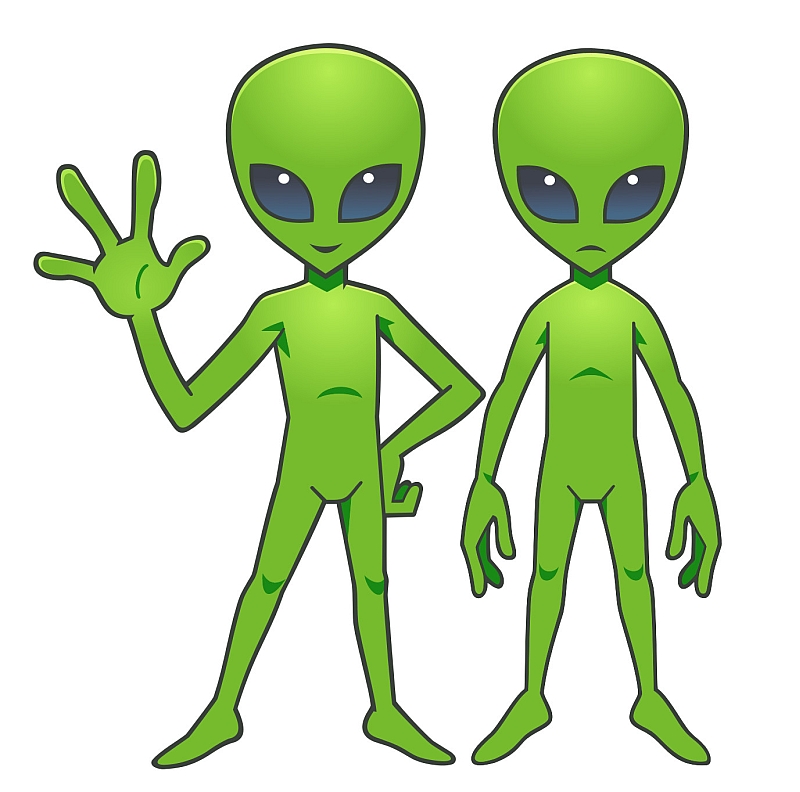
ハイブリッド その2
国籍や民族というものを考える時、そこには血の濃さというイメージが、つきまといます。
家族かどうかというのも、基本的には血がつながっているかどうかが、重視されます。
しかし、子供が受け継ぐ親の遺伝子は、父親と母親の半分ずつです。
孫になると、そのさらに半分ですから、四分の一になります。
ひ孫になると、さらにその半分で、八分の一です。
こうして代を重ねるごとに、血の濃さは半減して行きますので、百年も二百年も昔の祖先の血は、とても薄まっているのです。
でも、この場合の祖先というのは、通常は父方の祖先です。
母方も含めて考えると、私たちの持つ遺伝子は、数多くの祖先から受け継がれたものが、入り交じっているという事が、わかるでしょう。
私たちは全員が、実に多様な遺伝子を持っており、血の濃さという発想は、全く無意味なのです。
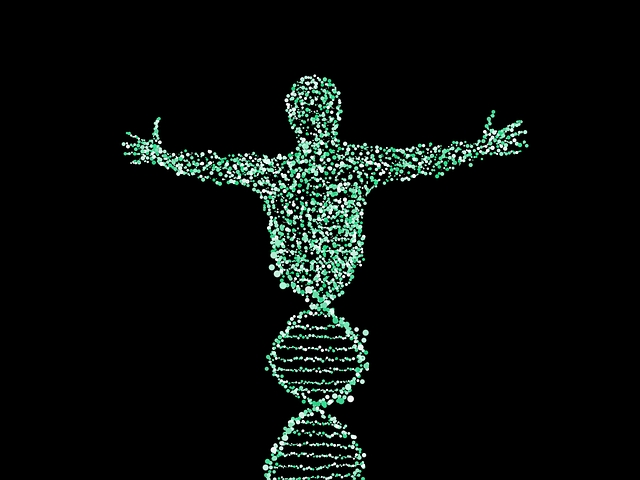
ハイブリッドの人が、多く存在するかどうかは、国や地域によって異なります。
多く存在する所は、文化的に開放的で、少ない所は閉鎖的だと、見ることができます。
小さな地域では、単に交通手段が少ないとか、外の者に関心を持たれていないなどの、事情があるでしょう。
しかし、行き来もしやすいし、たくさんの人から人気がある所なのに、ハイブリッドの人が少ないのであれば、よそ者を受け入れない、土地柄なのかもしれません。
かつて日本は、とても閉鎖的な国でした。
異国の人を見かけると、ガイジンと呼んで、特別視をしていました。
でも、最近は異国の人を見かけても、全然珍しさがなく、じろじろ見る人もいなくなったと思います。
テレビの番組を見ていても、ニュース番組からバラエティ番組まで、至る所にハイブリッドの人たちが、映っています。
また、自分の近所に、何人もハイブリッドの人たちがいる、という状況ではありませんが、いずれそうなる日が、やって来るものと思われます。
そうなると、肌の色や見かけだけで、日本人かどうかを決めるようなことは、なくなるでしょう。
外から来た人間か、日本で暮らしている者なのか、見ただけでは区別ができなくなりますし、いちいち国籍を尋ねるような、野暮で面倒臭いことも、しなくなると思います。
重視されるのは、その人と仲間意識を共有できるかどうかの、一点だけでしょう。

仲間と言っても、とても近い仲間もあれば、ゆるい関係の仲間もあります。
それでも、みんな自分の仲間だと、感じられるようになるのです。
そういうことが、どこの国でも当たり前になって来ると、国境を決める意味が、なくなります。
何故なら、どこの国も同じような状況になるからです。
各地域の文化は尊重されながら、全体は一つという感覚を、みんなが持つようになり、誰もが自分の所属を聞かれた時に、自分は地球人だと答えるでしょう。
これは実に素晴らしいことです。
そして、ハイブリッドの人たちは、そんな世界を引き寄せるための、先駆けとなってくれているのです。
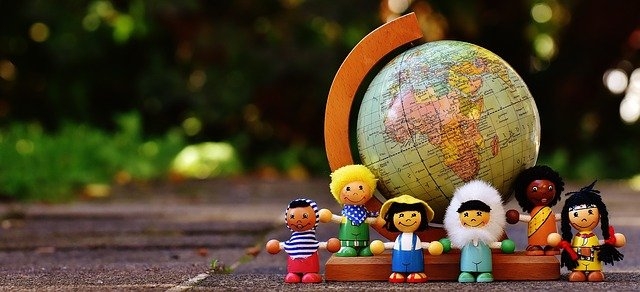
ハイブリッド その1

女子テニスの全豪オープンで、大坂なおみ選手が2度目のベスト4進出を果たしました。
日本人選手としてプレイしてくれているので、彼女の活躍ぶりに、多くの日本人が感激していることと思います。
しかし、当の本人が自分のことを、どれだけ日本人だと意識しているのかは、わかりません。
恐らく、日本人が期待しているほどには、自分を日本人だとは考えていないような気がします。
そもそも国籍なんて、国境と同じで、人間が勝手に作ったものです。
どこで誰の子供として生まれるのかとは、全く関係のないことなのです。
それなのに、生まれてしまえば、どこの国の人間だとか、どこの民族だとか、自分の知らない所で分類がなされてしまいます。
先祖代々、ずっと同じ土地で生まれ育つ者ばかりだと、わかりやすいのでしょう。
でも、他の地域の者と結婚したり、それまでとは全然違う場所で暮らしたりすると、生まれた子供は自分がどこの人間なのかが、わからなくなってしまいます。
大坂なおみ選手もそうでしょうし、彼女のように両親の国籍が違った人は、みんな似たような苦労をして来たはずです。

国籍がどこかということだけであれば、単なる事務的な話に過ぎません。
しかし、大抵の場合、子供の時に、お前はどこの人間だというような、いじめに遭っていると聞きます。
その根底には、見慣れないものへの不安や、憧れの裏返しのようなものが、入り交じっているのだと思います。
ほとんどの人が、両親の国籍や民族が違っていたとしたら、このような問題は起こらないはずです。
起こるとすれば、自分は優れた人間だと認められたい、信じたいという、自分に自信のないことによる、意図的な偏見や差別が原因です。
単に見た目が自分とは違うということで、生じる問題とは次元が異なります。

話を戻しますと、国籍や民族が異なる、両親の元に生まれた人たちは、自分がどこの国の人間なのか、わからなくて当惑すると思います。
でも、逆に考えれば、こういう方たちは、人間社会に蔓延している、分類や仕分けの慣習を、打ち破るための存在だと、見ることができるでしょう。
かつては、こういう方たちの事を、日本では混血だとかハーフなどと、呼んでいました。
しかし、この表現には、珍しさや変わり者、あるいは明らかに自分たちとは異なる、異端児のようなニュアンスが含まれています。
これに対して、ハイブリッドという言葉は、二つのものを掛け合わせて生まれた、新しいものという意味合いで使います。
日本でハイブリッドと言えば、トヨタの自動車が頭に浮かびますが、あの車は状況に応じて、バッテリーとガソリンエンジンを、使い分けることができます。
つまり、二つの能力を活かしているわけですね。
それと同じように、人間も両親から受け継いだ特性を、うまく利用できれば、それまでにない能力を、発揮できる可能性があるのです。
ですから、二つの異なる血を受け継いだ場合、ハイブリッドという表現の方が、相応しいと思います。
大腸癌の治療
ニュースで、進行性大腸癌の治療成績についての、報告がありました。
それによれば、進行性大腸癌の治療で、手術をして抗がん剤を使用した人と、手術をせずに抗がん剤のみで治療した人では、治療成績に大きな差がなかったとのことです。
また、抗がん剤の副作用では、手術をした人の方が、苦しむ人が多かったそうです。
どちらも生存率は2年2ヶ月ほどだったので、今後の治療方針としては、出血などの合併症がない限り、手術はせずに化学療法中心の治療に、なるだろうということでした。
かつては癌と言えば、不治の病の代表で、映画やドラマでも、悲劇のヒロインが癌に罹っているという話が、よくありました。
今では不治の病という印象がなくなったのと、似たような話ばかりになると、飽きられるからでしょうか、こういうストーリーの映画やドラマは、少なくなったように思います。
そうは言っても、癌が治ると言われるのは、早期発見と早期治療の結果でしょう。
見つかるのが遅かった場合や、本人の体力がない場合などは、癌は不治の病になってしまいます。
ところで、昔はこれと言った治療法がなかったため、手術できるものは切除してしまえという風潮が、医療界にはあったようです。
癌と診断がつくと、内科はお手上げ状態で、外科だけが頼みの綱という感じでした。
また、患部を切り取ってしまえば、それで治ったことにするという、暗黙の了解があったように思います。
しかし、たとえば胃癌で胃を切除してしまうと、癌はなくなるかもしれませんが、胃もなくなってしまいます。
それでも生きることができるのだから、それでよし、とされていたのですが、やはり、それまであった胃がなくなると、その方の生活にも影響が出て来ます。
食事の仕方を工夫しないといけませんし、胃を取ったせいで貧血になることもありますから、それを予防する薬も、必要になって来ます。
胃がないと、食べた物がいきなり腸に流れ込みますから、血糖値が急激に上昇することもあります。
このように、癌を切除しても、元の健全な状態に、戻るわけではありません。
それができるのは、ごく早期の癌で、本当にその部分だけを、プチッと取れる場合だけです。
そうでない場合は、癌がある状態を、体の一部(胃癌の場合は胃)が欠如した状態に、置き換えるのです。
癌だと死ぬけれど、体の一部が欠如しても、死なないのだからいいだろう、という感覚ですね。
当然、失われた部分が担っていた役割は、果たす者がいなくなるのですから、その分は何らかの、体の不調という形で現れます。
今回、発表がありました、大腸を切除する場合と、切除しない場合では、切除しない方が、抗がん剤の副作用が少なかったとありました。
と言うことは、癌と一緒に切除されてしまう大腸には、抗がん剤の副作用を抑える、何らかの影響力があったと、考えられるのです。
もしかしたら、大腸を失ったことによる、体力低下が関係しているかもしれません。
しかし、大腸には消化機能以外の、隠された役割があるのかもしれないのです。
いずれにしても、今後は薬による癌治療が、飛躍的に発展して行くでしょう。
その結果、手術による切除というものは、どんどん減って行くことと思います。
ただ、知っておいて欲しいのは、病院は私たちの体について、何でもわかっているように見えますが、実はわかっていないことが、まだまだ、たくさんあるということなのです。
また、寿命や遺伝的なものでない限り、基本的に体は病気にならないように、できています。
病気になる場合は、体の機能を損ねるようなことを、本人が気づかずにしているのです。
これからの癌治療は、自然免疫力を高める方向へ、進んで行くでしょう。
コロナウィルスやインフルエンザなどの感染症についても、やはり自然免疫力が、大きく物を言います。
こういう免疫力を高めるのに、いちいち病院に相談する必要はありません。
自分の生活を見直せば、健全な体を取り戻す、あるいは維持することができるのです。
深刻な病気というものは、表面から見えない所で、徐々に進んで行くものです。
今は元気であっても、知らないところで、病気が進んでいるかもしれません。
それがどんな病気かと、不安になって検査を重ねるより、病気になりそうな状況を、自分が作っていないか確かめて、それを改善することが、手っ取り早くて効果的です。
ただ、歪んだ環境に慣れ親しんでいる場合、それを改善するのは一苦労です。
歪んでいたとしても、その環境が心地よいというのであれば、それなりの理由があるはずです。
環境を整えることは大切ですが、何故歪んだ環境が心地よいのかを、確かめることも重要です。
そこに対処しなければ、いくらいい環境にしても、すぐに歪んだ環境に戻ってしまうでしょう。
うまく対処して、心も体も本当に居心地の良い環境を、作って行きましょう。
大地震
また東北で大きな地震がありました。
あの震災から、ちょうど10年になりますが、そこでまた大きな地震があったので、以前に被災された方たちは、前の震災を思い出したのではないでしょうか。
あれだけの大被害を及ぼした震災も、10年という年月の間に、人々の記憶から次第に、忘れられそうになっているような気がします。
あの津波の映像を見た人は、被災地の者でなくても、とても強いインパクトを受けたはずです。
ですから、東北で震災があったこと自体は、忘れることはないと思います。
しかし、直接被災したわけでなければ、どうしても日々の暮らしに追われ、目の前の問題や、新たな事件などのニュースに、目を奪われてしまいます。
その結果、震災は遠い過去の存在、あるいは他人事のような気持ちに、なりがちでしょう。
そうならないように、今でも声に出して、被災地を応援しようとしている方たちは、少なくありません。
それでも、やはり忘れて行く人の方が、多いような気がします。
あの時は、被災地の人も、そうでない人も、恐ろしさと悲しさを共有していたと思います。
でも今は、被災地とそれ以外の所では、心が離れているのではないでしょうか。
それは仕方のないことかもしれません。
阪神大震災にしても、熊本大地震にしても、さらには大正時代の関東大震災にしても、それが大変な事だというのは、理解しているでしょう。
でも、感覚的には他の世界の出来事のように、感じているのではないかと思います。
しかし、地域が違っても、心を共有できなければ、いい世の中にはなりません。
新型コロナが教えてくれているのは、そのことなのです。
そして、東北の震災からちょうど10年になる今、今回の大地震が起こったのは、偶然ではないように思います。
忘れるな。
地震は、このことを伝える、地球からのメッセージだったような気がします。
誰のせい 自分のせい その2

運転する車が、道に落ちていた釘を踏み、タイヤがパンクした時、直接的な原因を考えると、それは釘だと言えます。
でも、何故そこに釘があったのかと考えて行くと、様々な原因につながって行き、どれが本当の原因なのか、わからなくなってしまいます。
さらに言えば、どうして自分が釘を踏んでしまったのかと考えると、今のとはまた別の、原因探しが始まります。
たとえば、タイヤが釘が落ちていない所を通っていれば、釘を踏みませんから、パンクもしません。
前を走る車が、ゆっくり走っていたから、いらいらしてその車を、追い越したとしましょう。
その結果がパンクであれば、追い越していなければ、ゆっくり走っていた車が、釘を踏んでいたかもしれません。
家を出た時に、右の道から行くか、左の道から行くか考えて、右の道を選んだ結果が、パンクだったとも言えるでしょう。
これらは全て、自分自身の選択の結果です。
たとえ、釘が落ちていたとしても、自分がそれを踏むような選択をしなければ、タイヤがパンクすることはなかったわけです。
となると、悪いのは自分だったのか、ということになるのですが、こんなことでお前が悪いと言われたら、納得がいかないでしょうね。
そうは言っても、タイヤがパンクしたことには、がっくりします。
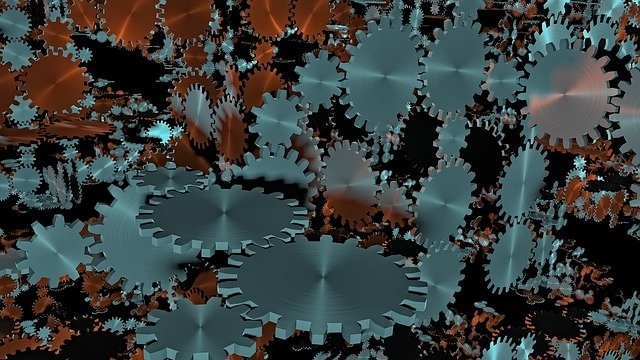
いずれにしても、ある物事が起こる場合、そこには多くの事柄が絡んでいます。
そのどれか一つだけを取り上げて、これが本当の原因だと、決めつけることはできないのです。
その物事に自分自身が関わっているならば、自分の決断や行動も、結果を生んだ原因の一つになります。
その場合、何が問題だったのかと考えると、さらにややこしくなるでしょう。
それに、まだ問題が何も起きていない時に、右を行けばいいのか、左を行けばいいのか、そんなことを決めることはできません。
それでも、どちらかを選ぶしかない場合、その先に何があろうと、覚悟を決めて選ぶしかありません。

覚悟を決めるということは、何か問題が起きた時、そこに自分も関わっているという事実を、認めるということです。
それは問題を誰かのせい、何かのせいにするのではなく、自分が選択した結果として、受け入れるということでもあります。
悲惨な結果に、誰かを呪いたくなるでしょうし、自分を責めたくもなるでしょう。
しかし、そんな事をしたところで、起こってしまった事が、元に戻るわけではありません。
そこにあるのは、起こったことを通じて経験した、いろんな思いと様々な思考だけです。
その思いや思考によって、その出来事から何を理解し、物事をどのように受け止めるのか。
そこにこそポイントがあるのです。
その結果次第で、その後の人生が変わるでしょう。
つまり、何かが起こった時、そこから何を学び取るのかということが、何より大切なのです。
原因や責任の追及も、大事だとは思います。
でも、そこにだけ目を向けていたのでは、人としての進歩はありません。
何かのせいにしたくなる時、それは今の自分の現状を、守ろうとする意思が働いています。
しかし、人間として成長するためには、現状から抜け出して、もっと広い視野で世界を眺める必要があります。
何が悪いのかと考えるよりも、ここから自分は何を学ぶのか、という視点を持つことに、重点を置いて欲しいと思います。

