新聞記事 その3

私たちが何かを、本音で選ぶ時、そこには喜びがありますし、選んだ結果に対する、覚悟もあります。
しかし、自分の本音ではなく、誰かに唆されたとか、周りに合わせたとか、流れに従って仕方なく、という理由で選んだ場合、そこに本当の喜びはありません。
もちろん、楽しいことはあるでしょう。
でも、それは心の底から湧き出るような、喜びにはつながりません。
表面的な楽しさです。
また、状況がまずくなっても、それを受け止める覚悟がありません。
ですから、文句や不満ばかりが出て来ます。
将来に対しても、自信も覚悟もありませんから、不安や心配がつきまといます。
自分が観ている、人生という名の映画も、大概の人が、自分が選んで観ているという、感覚はないと思います。

生まれた時から、こうだったからしょうがない。
自分の家は、こんな感じだから、どうしようもない。
自分は特別な人間じゃないから、状況を変える力などない。
こんな風に考えている人が、多いでしょう。
これは要するに、自分の人生に対して、あきらめているわけです。
実際の映画であれば、嫌な映画を断ることはできても、人生という映画については、断れないと決め込んでいます。
あるいは、映画を変更しようにも、どうすれば変更できるのか、わからないと考えているでしょう。
もう、すでに起こってしまったことは、変えられないのだから、自分の人生を、変えることなどできない、と思う人もいるかもしれませんね。
でも、映画館で観る映画でも、ホラー映画だと思っていたら、コメディだったということが、あるでしょう。
不幸と悲しみを背負った主人公が、最後には幸せに巡り会う、という結末のものもありますよね。
映画は制作者が、好きなように作れるのです。
また、どんでん返しの結末を迎える映画は、多くの人に好まれます。
これまでの記憶や、現在の状況から、この先もうまくいかないと、決めてかかるのは、映画監督としては失格でしょうね。

自分の人生をどうするのか。
それを決めるのは、自分です。
新聞記事や映画館の映画を、好きなように選ぶのであれば、自分の人生も、好きなように選べます。
途中で変えることも可能です。
新聞記事も深読みをすれば、その記事を書いた人が、その記事を通して、読者に何を伝えたいのか、ということが見えて来ます。
単に自分の文章を売り込みたいだけなのか、読者に希望を届けようとしているのか、あるいは不安を煽りたいのか。
同じ出来事を伝えるにも、伝える人によって、選ぶ言葉や表現が変わって来ます。
どこに視点を向け、何を強調しようとしているのかで、伝わるものが違います。
それと同じように、自分の過去の経験や、今の状況についても、深読みをすれば、今考えているのとは、違った面が見えて来るでしょう。
不幸に見えることでも、その中に必ず、喜びにつながるものが、隠れています。
それを見つけるようにすれば、自分は不幸ではない、自分だけが取りこぼされているのではない、と気づけると思います。
ここは、とても重要なポイントで、自分の記憶の中にある、人生という映画を、自分で編集して、それまでとは別物にしてしまうのです。
平凡でつまらない人生が、実は驚きと面白さにあふれていたと知れば、どうでしょうか。
その面白さは、リアルタイムで知らなくてもいいのです。
思い返した時にわかる面白さというのは、いくらでもありますから。

大事なのは、自分の人生の色づけは、自分自身がしているのだと、知ることなのです。
それができれば、これから訪れる未来についても、自由に色づけしていけますし、初めから自分が好む色の人生を、選ぶということも、できるようになるでしょう。
それは、自分が本当に観たかったものに、人生という映画を作り変える作業なのです。
新聞記事 その2
私たちの世界は、文字でできているわけではありません。
目に見えたり、耳に聞こえたりする世界です。
新聞記事は文字の集まりですから、記事が何が言いたいのかを成立させるためには、一文字一文字をつなぎ合わせた、文章にする必要があります。
そうすることで、そこに記事の内容が、浮かび上がってきます。
文字でない私たちの世界は、どうでしょうか。

私たちの世界は、映画のフィルムに喩えられます。
一コマ一コマの映像や、それに付随した音声の情報をとらえても、そこに世界は存在しません。
しかし、全てのコマを連続して流して行くと、世界が生まれ、その中で人々が動き出します。
その人たちには、ちゃんと意思があり、何かを考えたり感じたりもするのです。
あたかも、それは実在しているように思えますが、流れを止めてしまうと、世界は消えます。
そこにあった世界は潜在的なものとなり、再び誰かが鑑賞してくれるまで、姿を見せることはありません。
そして、私たちが認識している世界も、また自分だと信じているものも、全てはこの映画のフィルの中のものと、同じだと考えることができるでしょう。
本質的な私たちというものは、この世界、今の自分を超えた、別の所に存在しています。
そこで私たちが現実と呼ぶ世界を、映画を観るように体験しているのです。
映画館の観客のようなものですね。

ところで、新聞を読む時、どの記事を見るかは、大抵の場合、自分が興味があるものを、見るでしょう。
映画館で観る映画も、自分が観たいものを選びます。
でも、新聞を読む時に、自分が読みたくて読んでいるわけでは、ないということもあると思います。
たとえば、株は儲かると言われて、何となく株を買ってしまったために、毎日株価を気にするように、なることがあるでしょう。
スポーツには興味がないのに、仲間や顧客との話題のために、無理に記事に目を通すということも、あるのではないでしょうか。
営業マンなら、経済新聞ぐらい読んでおくのが常識だと言われ、仕方なく読む人もいると思います。
好きで読んでいるのなら、何も問題はありません。
しかし、読みたいわけではないのに、読んでいるという人にとっては、苦痛でしょう。
どうせ読むなら、雑誌の方がいいと、思うかもしれません。
そう思って、読みたくもない記事から、離れられる人は、素晴らしいと思います。
離れられない人は、お気の毒ですね。
映画にしても、同じです。
自分が観たい映画を観るならいいのですが、他の人に合わせて、興味のない映画を観るはめになると、退屈で仕方がないでしょう。

場合によっては、とても苦痛になったり、嫌な気分になることも、あると思います。
この場合でも、自分は観たい映画を観ると言って、その場を離れられる人は、素晴らしいと思います。
それができない人は、やはりお気の毒ですね。
新聞記事や映画は、その気になれば、自分の我を通して、変更することが可能です。
決してむずかしいことでは、ありません。
しかし、私たちの人生については、どうでしょうか。
先に述べたように、私たちの人生も、一コマ一コマのフィルムをつなげた、映画のようなものです。
本当は、こんなはずではなかったとか、自分はもっと違う人生を、歩みたかったんだ、と思うことはありませんか。
そう思うのは、あなたが間違った人生映画を、観ているからです。
新聞記事 その1

新聞には、様々な記事が載せられています。
新聞を読むにも、人それぞれ好みがあって、真っ先に自分が関心のある所から、読む人もいれば、初めから順番に読んで行く人もいます。
興味がある所しか読まない人もいれば、小さな記事まで全てを読む人もいます。
ところで、私たちが記事を読む時、そこに書かれてある文面を、一文字一文字順番に目を通して行きますよね。
そうして、一つの文を読むことで、その文に何が書かれているのかを、理解します。
文の意味はわかっても、それだけでは、記事が何を言いたいのかは、わかりません。
記事の内容を知りたければ、文の塊である文章を読まないといけませんし、いくつもの文章が書かれていれば、それら全てを読まなくてはなりません。
また、関連記事というものが別にあれば、そちらにも目を通す必要があるでしょう。
そうしなければ、その記事が何を伝えようとしているのか、詳細はわかりません。
ただ、いずれにしても、私たちは一文字一文字を根気よく読んで行き、そうやって全部を読み終えることで、記事の内容を理解するわけです。

これは、私たちの普段の暮らし、私たちがいる世界の流れと、よく似ています。
私たちは瞬間瞬間しかわかりません。
私たちにとっての現実と言うものは、実は今という瞬間だけなのです。
一文字一文字順番に読むことで、一つの文、一つの文章を理解するのと同じで、一瞬一瞬の現実が、つなぎ合わされることで、人生というものが築かれて行くのです。
それが時の流れであり、私たちの経験も思考も、全てがこの流れによって、構築されるものなのです。
どこかの一瞬だけをとらえても、そこには何の経験もなければ、何の思考もありません。
つまり、私たちが自分と認識しているものも、存在していると信じている世界も、ないのです。
そこにあるのは、一瞬一瞬をとらえて、つなぎ合わせようとする意思です。
この意思は、私たちが通常理解している、自分という概念ではありません。
私たちが理解している自分というものは、瞬間瞬間をつなぎ合わせることによって、創られたものなのです。
つまり、普段認識している自分というものは、一種の幻想であり、錯覚のようなものなのです。
そういうものを超えた別の所にこそ、本質的な自分というものが、存在しているのです。
それは、どこなのでしょうか。
それは、私たちが無意識と呼んでいる領域です。
植物の生長

植物が育つには、日光と水、それに養分が必要です。
日陰を好む植物もありますが、真っ暗闇の中では、育たないでしょう。
強い光を好むのか、弱い光で十分なのかの、違いだと思います。
植物に光は必要なのです。
光を求めるのは、光合成を行うためでしょう。
光のエネルギーを使って、二酸化炭素から炭水化物を合成するのです。
光を求めるということは、光が植物の生長の方向を、決めていると言えるでしょう。

ところで、植物も人間も同じ地球の生物です。
地球の歴史の中に生まれて来た、兄弟であり、全く別個の存在ということではありません。
植物に光と水と養分が必要なように、人間も同じ物を求めます。
そして、それは人間の体だけでなく、心にも言えることでしょう。
心は光を求めます。
光を見つけられない心は、モヤシのように萎えた状態になってしまいます。
養分がなければ、やはり植物は生長ができず、病気になります。
心も成長するための、養分が必要です。
それは様々な経験や知識によって、もたらされる智慧や理解です。
水がないと、植物は枯れてしまいます。
人間もそうですが、植物もその大半は、水分なのです。
心にとっての水というものは、精神エネルギーそのものでしょう。

全体から隔離されたエネルギーは、循環もできずに淀んだ状態です。
養分を運んでくれるのは、水です。
心も精神エネルギーの循環がなければ、智慧や理解は得られません。
それは、経験や知識を得られない状態です。
部屋の中に、引き籠もっている人は、そのような状態にあると言えるでしょう。
外に出ている人でも、同じことの繰り返しである、日常生活だけを送っていると、やはり経験や知識が得られていない状態です。
心の成長という視点で見ると、引き籠もっていても、外に出ていても、同じなのです。
植物が水を得るというのは、周囲とつながっているということです。
心も周囲とのつながりを、必要としています。
それは人同士のつながりであったり、他の生き物とのつながりであったり、地球や宇宙とのつながりであったりします。
そんなつながりを通して、人は知恵や理解を得ることができるのです。
また、どんなつながりを選ぶのか。
それは、光が指し示してくれています。
心にとっての光とは、この地上では、愛と呼ばれているものです。

地球の子供たち その3
人間は特別ではありません。
個性的なだけです。
他の存在と自分は、見た目が違うだけで、同じ所から出て来た、兄弟なのだと考えてみて下さい。
全ては、同じものの一部であり、同じものの数ある表現の一つに過ぎないのです。
周囲にあるもの、自分がいる世界を、そのような目で見てみて下さい。
見た目は別のように見えるけれど、エネルギー的にはつながっていると、考えて下さい。
そして、普段は無視してしまいがちな、自分がここに存在しているという感覚に、意識を向けてみて下さい。
自分の存在と言っても、体の五感ではありません。
静かな所で目を閉じて、ただ自分を感じてみるのです。

意識としての自分しか、わからなくなった時、自分の形や大きさも、わからなくなるでしょう。
それは、海とつながった水滴の状態です。
つまり、世界とつながっている、エネルギーの自分です。
その時の感覚を、普段の時にも思い出せたなら、日常生活の中でも、自分が世界とつながっていると、感じることができるでしょう。
自分は世界とつながっていて、独りぼっちではないと、理解できると、無意識からの情報を、どんどん受け取ることが、できるようになります。
そうなると、何をすべきかではなく、何をしたいのか、ということを重視するようになります。
他人の目も気にならなくなりますし、他の人と自分を比べることも、関心がなくなって来ます。
他人の評価など気になりません。
自分を評価できるのは、自分だけだとわかるからです。
その評価も、これはだめだという評価ではなく、もっとこうした方がいいぞ、という評価です。
他の存在とのつながりを、感じるようになれば、どんなことにでも感謝の気持ちが生まれます。
それは人生の喜びの証であり、自分が生きて存在していることの、意味と価値を示すものなのです。

地球の子供たち その2
何をしたらいいのか、悩んでしまう。
みんなと同じでないと、不安だ。
大きなことをする人が、うらやましい。
生きている意味が、わからない。
こんな風に思っている人は、とても多いと思います。
こんな風に考えてしまう原因は、視覚情報への頼り過ぎです。
表面的な情報だけで、物事を判断する癖がついているので、本当のところは、よくわからないのです。
だから、間違った情報や、良くない情報でも、すぐに飛びついてしまうのです。
その間違った情報の最たるものが、人間は特別な存在だ、というものです。
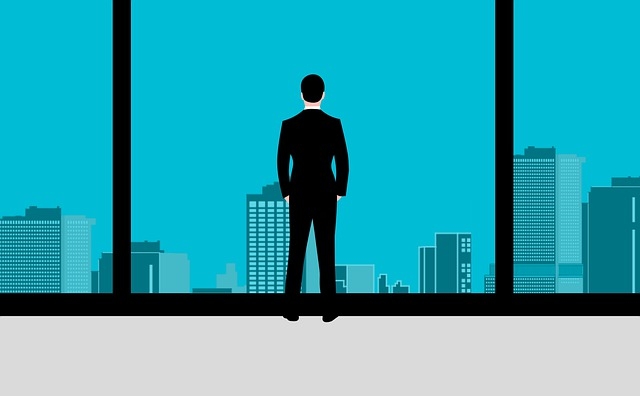
特別ということは、特権があると受け止められます。
それは他のものに対して、何をしても許されるという考え方に、結びつきます。
この、人間は特別だという発想は、個人的にも、自分は特別でありたいという願いに、つながるのです。
しかし、正しく言うと、人間は特別なのではなく、個性的なのです。
他の生き物、他の存在と異なるのは、人間が特別なのではなく、人間という個性を表現しているだけです。
他の生き物、他の存在たちも、それぞれの個性を表現しています。
どれが特別ということはありません。
立場的には、全ての存在が同等であり、同価値です。
人間社会においても、個性を尊重しようという動きが、加速されているように思います。
お金や地位、権力などで優劣を決めるのではなく、全ての人が同等であると考えることは、人間の知性がアップしたことを、意味します。
それは人間社会が、ユートピアになるということです。
でも、まだまだその動きは、強いとは言えません。

権力者たちは、自らの立場を維持しようと、躍起になっていますし、多くの人が、権力者たちた掲げている、経済や軍備の理屈を、鵜呑みにしています。
それはやはり、視覚的な情報に頼り過ぎているからでしょう。
本当の自分の価値、自分が存在している意味が、理解できていないのです。
私たちは、エネルギー的に地球とつながっています。
それは宇宙とつながっているとも言えますし、世界とつながっているとも言えます。
私たちは常に全体の一部であり、全体から切り離すことは、不可能です。
なのに、自分は世界から切り離されている、独立した存在だと、自らを欺いてしまうから、おかしなことになるのです。
全体から切り離されていると、信じている人間は、その潜在的な能力の大半が、使えないままになります。
思考しているようで、思考がストップした状態です。
私たちが何かを思いついたり、深く物事を理解できるのは、心が全体とつながっている時です。
そうでない時は、誰も操作していない、ゲームのキャラクターが、自動的に動き回っているのと、同じ状態です。
毎日毎日同じことの繰り返しで、何の変化もありません。
何か大きな出来事が起こっても、その意味を理解することもできないし、どうすればいいのかもわかりません。
みんなと同じでなければ安心できず、自分なんかに何ができると、常に自信のなさが根底にあります。
そんな風に感じて悩むのは、本物の思考が止まっているからです。

地球の子供たち その1
私たちは地球の分身です。
地球と名付けられた、巨大なエネルギーの一部です。

どんなに自分と自然や環境、他の生き物たちを区別しても、私たちの本質は、地球とつながっているのです。
それは、お釈迦様に悪態をついていた孫悟空が、所詮はお釈迦様の手のひらの上に、いるのだという話と同じです。
私たちは、どんなに自分たちを特別視したところで、地球の一部であるという事実は、変わらないのです。
そうは言われても、実感が湧かないでしょうね。
それは、私たちが視覚的な情報に、頼り過ぎているからです。
どうしても、自分の体と、そうでないものを、きっちり区別したくなってしまうでしょう。
でも、人間も他のものも、全てはエネルギー体です。
はっきりとした形があって、互いの境界があると思うのは、感覚による幻想なのです。
全てをエネルギーとして見ると、形というものはぼやけてしまいますし、互いの境界もはっきりしなくなります。

私たちは川と海を区別しています。
でも、どこからが本当の川で、どこからが本当の海なのかは、はっきり線引きすることは、できないでしょう。
地図上では、河口の両側にある海岸線を、結んだ線を境に、川と海を分けることはできます。
これは視覚的に、私たちが肉体としての自分と、他のものを区別するのと同じです。
でも、川が淡水の流れ、海が塩水が貯まったもの、と理解すれば、その大まかな区別はできても、きっちりとした線引きはできません。
淡水である川の水は、地図上の川と海の境界線を越えて、海側へ流れ込みます。
境界線近くの水は、ほとんど淡水と言えるでしょう。
また、そこを少し離れた所では、汽水と言って、淡水と海水が混ざり合ったものになります。
つまり、どっちつかずの状態ですね。
それから先が海水になりますが、この汽水と海水の境目も曖昧です。
また、大潮や高潮と言った、海の状態によっては、川を海水が逆流する場合もあります。
地理上は川でも、中身は海水です。
この川を人間、海を地球と考えてみて下さい。
水はそれぞれのエネルギーです。
淡水の流れが、川を形作るように、人間のエネルギーが、人の姿形を作っています。
川の水は、海の水が蒸発して、雨となって山に降り注いだものが、海に向かって流れるものです。
人間のエネルギーも、元々は地球のエネルギーから、創られたものです。
そして、川が海とつながっているように、私たちも地球としっかりつながっているのです。

食べることの意味 その2

食べることで、食べられる側のことを、気の毒に思うのは、そこに心の存在を認めるからです。
つまり、心を持つ自分と同じ存在だと理解して、相手に親近感を抱くからです。
親近感が強くなると、同じ地球に暮らす仲間だと、思うようになるでしょう。
そんな相手を食べることなどできません。
私たちが食べ物を食べることができるのは、そこに心の存在を認めないからです。
食べる対象となるものは、人間が自由に扱っていいものだと、認識しているのです。
でも、心があるとみなした相手を、理由もなく食べることはできません。
他に食べ物がないのであればともかく、代わりの食べ物があるのであれば、心がある生き物を、無理に食べる必要はないと、思うようになるに違いありません。
そうなると、人は次第に肉を食べたいと思わなくなり、魚や卵も食べなくなるでしょう。

では、植物は食べてもいいのでしょうか。
動物には心はあっても、植物には心がないと言えるのでしょうか。
そんなことはありません。
植物にだって、心はあります。
それどころか、土や水、空気にだって心はあるのです。
心と考えると、わかりにくいでしょうから、エネルギーととらえて下さい。
全てのエネルギーが、精神エネルギーと同じだと考えれば、土や水、空気にも心があると、理解できるでしょう。
つまり、地球にも心があり、宇宙にも心があるということです。
私たちは、その心を持つ空気を吸い込み、心を持つ水を飲みます。
でも、相手に害を及ぼしているという感覚はありません。
実際、私たちが息をしたって、水を飲んだって、相手は何も変わりません。
私たちは空気や水の、一部を利用させてもらっているだけなのです。
植物についても、同じように見ることができます。
植物も一つの苗や、一本の樹木を、一つの命、一つの心と見るのではなく、全体が一つの存在だと考えれば、その一部を分けてもらっているわけです。
だから、動物と比べると、植物を食べることには、抵抗感が少ないのです。
それでも、人間が植物を好きなようにできると見るのは、植物に対して失礼でしょう。
やはり感謝の気持ちを持つ必要があると思います。

食べるということは、体に必要な栄養を摂取するということだけでなく、その人が抱いている世界観が、表現されたものでもあります。
それは、いいとか悪いとか言うものではありませんし、こういう食事をするべきだと、いうことでもありません。
その人が自分や世界を、どのように理解しているのか、というだけのことです。
その人の理解度に応じて、食事内容や食事方法が、変わって来るわけです。
理解度が異なる相手に、食事とはこうだと言うのは、考えの押しつけであり、間違いです。
私が言いたいのは、世界観の変化に伴い、食事も変わって来るだろう、ということです。
世界観が変わるということは、その人の精神エネルギーの状態が、変わるということだと思います。
心とリンクしている体もエネルギーですから、心のエネルギー状態が変われば、体のエネルギー状態も、変化すると思われます。
そうなると、無理に肉食をやめなくても、自然に体が、肉を必要としなくなるかもしれません。
さらに人のエネルギー状態が変化すると、植物すら食べなくなっても、エネルギーの補給ができるようになる可能性も、あると思います。
と言うのは、幽霊は物質的な食べ物を、必要としないからです。
体を構成するエネルギーの状態が、幽霊のエネルギーに似てくれば、空間からエネルギーを補給するように、なるでしょう。
昔、仙人は霞(かすみ)を食べて生きていると、言われていました。
この霞とは、空間のエネルギーではないかと思うのです。
食べることの意味 その1

食事は人間にとって、体を維持するための行為であるとともに、人生の大きな楽しみの一つでもあります。
病気や怪我などで、思ったとおりに食事ができなくなると、人生がとても味気ないものに、なってしまいます。
偏った食事は脳の働きにも害を及ぼし、精神の不安定を招きます。
逆に、美味しい食事は、落ち込んだり腹を立てている人の、心を癒やしてくれます。
普段は当たり前のように思っている食事が、何かの事情で採れなくなると、食事の有り難みが身に染みることでしょう。
食事は生きるための力であり、生きることの喜びです。
しかし、最近は栄養のバランスよりも、見た目や値段の安さ、手軽さなどが重視され、様々な添加物の入った、ファーストフードがもてはやされています。
腹に入る物であれば、何でも同じだろうという感覚なのでしょう。
また、濃い味や調味料の味が癖になり、素材を生かした薄味というものは、物足りなく思われてしまいます。
流行り物であったり、経済的な事情から、ということもあるのでしょうが、やはり体に取り込む栄養分ですから、若いうちから食事には、気を配る習慣をつけた方が、いいと思います。

食べるということは、基本的には他の生き物の、生命をいただいているということです。
昔の人は、そのことを理解していましたから、食べるということに、感謝を示していました。
日本人が食事の前に手を合わせて、いただきますと言うのは、その名残です。
西洋の人が、食事の前に手を合わせて、神に感謝する場面は、テレビや映画でも観ることがありますね。
でも、日本人はあらゆるものに、魂が宿ると考えますから、神に感謝と言うよりも、食材を提供してくれることになった、魂に感謝しているのではないかと思います。
いずれにしても、食べるということを、当たり前に考えるのではなく、食べる機会を得られることに、感謝するという気持ちは、忘れたくないですね。
その感謝には、食材を提供してくれた魂だけでなく、食事の場を作ってくれた人への感謝も、含まれています。
家で食事を作ってくれる人、お店で食事を用意してくれる人、また、その食材を作ってくれる人や、運んで来てくれる人。
そういった人たちへの、感謝を忘れてはなりません。

さて、食べるということは、他の生き物の生命をいただいていると、言いました。
このことは、昔から言われていることです。
人間から見ると、植物は心を感じにくいので、食べることに抵抗はないでしょう。
でも、動物となると、違いますよね。
しつければ言うことを聞きますし、遊んで楽しむということも、知っています。
その動物を殺して食べるということには、抵抗を感じる人が少なくないと思います。
私たちが肉を食べられるのは、誰かが動物を殺して解体し、食材の肉という形に処理してくれているからです。
それを自分でやらなければ、肉は食べられないとなると、恐らく大半の人が、肉を食べなくなってしまうでしょう。
生活環境の関係で、その地域にいる動物を狩り、殺して肉を食べなければ、生きて行けない人たちは、自らの手で全てを行います。
彼らは動物に生命があることを知っていますし、心があることも知っています。
それがわかった上で、生きるために食べるので、肉になる動物への感謝の念を持っていますし、無益な殺生はしません。

一方で、消費者と呼ばれる多くの人々は、食べる物を単なる食材としか、見ていません。
その食材が、かつては生命活動を営んでいたものの、一部であるとは考えないのです。
そんなことを考えていたら、何も食べられなくなると、思う人はいるでしょう。
しかし、ちゃんと事実を知った上で、食べるべきだと思います。
子供たちにも、そのことをきちんと教えるべきでしょう。
そうすることで、食べることの意味や、生きることの有り難さを、知ることができるからです。
この世界は、何かを食べることによって、生命をつなぐようになっています。
ですから、それによって他の生き物の命が奪われても、仕方がないことではあるのです。
それでも、人はそういう場面を目にするたびに、可哀想だとか、何とかならないものだろうかと、考えます。
そうは言っても、結局、考えるだけで終わってしまうことが、ほとんどではあるのですが、 そこで終わらせないで、ずっと考え続け て欲しいと思います。
他の生命を奪わずに生きることを、真剣に模索するということは、人間と他の生き物の生命を、同等にとらえるということです。
それは世界を知る、大きな一歩となるでしょう。
そして、それは人が知性体として進化することに、つながるに違いありません。
分離思考 その2
自分を全体から分離すると、どうなるのか。
それは、私たちの日常でも、よく見られることです。
たとえば、嫌なことをされたとか、馴染めないということで、学校や職場から孤立する人がいます。
何故そうなったのかという、具体的な原因や理由、あるいは善悪の判断は、脇に置きます。
ここで問題にするのは、孤立してしまった人の状態と、どんどん人が孤立して行く、組織の状態です。
孤立してしまった人は、糸が切れた凧のような感じでしょう。
自分ではどうすることもできない状況で、孤独と不安を味わうのです。
糸が切れているので、ずっと同じ状態が続くのだと、考えてしまいます。
一方、組織の方はと言いますと、人がどんどん孤立して行くと、辞めてしまう人が増えるでしょう。
そうなると、組織が成り立たなくなってしまいます。
無理やり、人をつなぎとめたところで、その人の心が離れていたのでは、ただ、そこにいるというだけのことになります。
組織としての活動は、停滞してしまうでしょう。
ところで、このような組織の上に立つ者も、実は、糸が切れた凧 なのです。
自分自身が糸が切れているため、周囲とのつながりを、どうすればいいのか理解ができません。
また、本当は孤独で不安なのに、地位や権力を持つことで、その気持ちをごまかしてしまうのです。
彼らは何から分離しているのでしょうか。
それは、人間という存在からです。
人は一人では生きられないと、理解している人たちは、他の人たちとの間に、つながりを感じています。
離れていたとしても、そのつながりが切れることはありません。
組織の中で孤立した人も、人間としてのつながりを、誰かとの間に持っていれば、切れたはずの凧の糸が、実は切れていなかったことに、気がつきます。
そうなれば、孤独から抜け出して、安心することができるのです。
しかし、そのつながりを持てない人は、不安に押し潰されそうになります。
そこで誰かを、自分の思い通りに動かすことで、あるいは相手の無理難題に、自分を合わせることで、自分にはつながりがあるのだと、自分を安心させようとするのです。
それは子供の虐待や、ろくでもない相手からの洗脳などの形で、知られています。
お金や地位や権力を持てる位置にいる者は、そういうものを使って、他人を思い通りに動かそうとするでしょう。
傲慢な経営者や議員などが、その典型です。
彼らは、世の中で困っている人がいても、何も感じません。
そんなことより、自らの保身に力を注ぎます。
また、そんな人物に従うことで、安心感を得ようとする者も、少なくありません。
そういう状況が、社会の様々な問題を引き起こし、大きな混乱をもたらします。
その実例は、世界中の至る所で見られます。
人間という存在から、自分を分離するということは、簡単に言えば、無知なのです。
人間が何かということを、理解していませんから、自分がどうあるべきかがわかりません。
人間として、自分はどうしたいのか、という気持ちさえも、押し潰されて見えなくなっています。
ところが、自分が人間であるのは事実ですから、人とのつながりがなければ、安らぎは得られません。
それをごまかすために、人はお金や力を求め続け、それらを十分に得たあとでも、さらに強欲に求め続けようとするのです。
自分が人であることを忘れた、哀れな人ほど、お金や力に執着します。
そういう者たちが、自分たちの地位の安定を図り、資本主義信仰を世の中に広げたのです。
でも所詮は、世界を牛耳っている多くの権力者たちも、糸の切れた孤独な凧なのです。
彼らの愚かな指示に、従う理由はありません。
今どうすればいいのか。
その答えは、人間である自分の心の中にあるのです。

