インターネットの功罪

今や、あって当たり前のインターネット。
でも、ほんの 20数年前までは、一般的なものではありませんでした。
インターネットがこれだけ普及したのは、パソコン人気のお陰です。
中でも、1995年に発売されたWiondows95は、パソコンの売り上げに大きく寄与したと言えるでしょう。
それまでは、情報というものは書籍や新聞、テレビやラジオのニュースに頼っていました。
人々は、真偽を確かめることはおろか、疑うことすらせずに、それらの情報を正しいものと信じて、受け止めていました。
しかし、今は当時とは全く異なる状況で、マスメディアと呼ばれるものは、かつての信用を失い、インターネットで個人が配信しているものより、人気度が落ちているのが現状です。
人々は情報を与えられるだけの状況から、自ら情報を発信するという、新たな環境を楽しんでいます。
また、インターネットは地球の裏側の人たちとも、瞬時につながることができます。
しかも、国際電話のように料金を気にする必要もありません。
このことは、人々の距離に対する感覚や、世界観にも大きな影響を与えたと言えるでしょう。
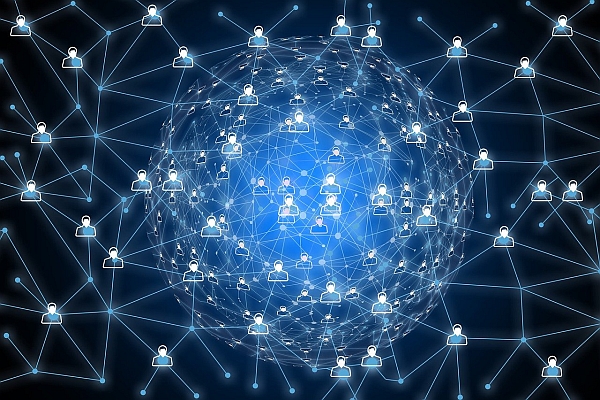
江戸時代までは、庶民の世界は村でした。
他の国でも、同じようなものでしょう。
村人が村の外へ出ることは、かなりの冒険だったと思います。
ですから、一生に一度は、お伊勢参りや金比羅参り、四国遍路をしてみたいと思ったのは、当然のことでしょうね。
それが、今では地球規模で動くようになり、国や民族、宗教を超えた交流が行われています。
中には、まだ昔の村意識のような、閉鎖的な考えを持つ人もいますが、かなりの人、特に若い人たちには、国境などの境界線は、意味をなさなくなって来ているように思えます。
インターネットにより、個人が自由な発信ができるようになると、世の中から注目されたいという思いや、世間を騒がせてみたいという考えを持つ人が、思いのままに活動し始めました。
そのことだけを見ると、インターネットのせいで、どんどん悪質な犯罪が増えていると、嘆きたくなってしまいます。
しかし、一方では遠く離れた人たちが、連絡を取り合い、互いの情報を交換し合いながら、楽しい世界を築こうとしています。
インターネットはただの連絡手段に過ぎず、いいも悪いもありません。
それをどう利用するかは、私たち人間の問題なのですね。
いい情報、悪い情報が、権力によるコントロールを回避して広がりますが、そこからどんな情報を拾い上げるのか、そこが今、私たちに求められているのでしょう。

インターネットで私たちは、世界観を広げることができました。
また、多くの人と思いを共有するという、経験をすることもできました。
あとは、その中身の問題です。
今は、いい情報と悪い情報が入り交じった状態ですが、いずれはいい情報が、悪い情報を陵駕するでしょう。
何故なら、いい情報に基づいた社会の方が、居心地がいいからです。
悪い情報を流す人たちの多くは、居心地が悪いからこそ、そのようなことをして、鬱憤を晴らそうとしているのです。
その人たちをも巻き込んで、居心地のいい社会が築かれて行けば、悪い情報が流れることは、少なくなって行くでしょう。
インターネットの功罪は、私たちが何を選択するかによって、決まります。
どこかの偉い人たちが、選択するのではありません。
私たち一人一人の庶民が、普段の生活の中で、何を選択して行くのかということです。
しっかりした足場

何か作業をする時、足場がしっかりしていないと、不安定で作業ができません。
それは心の思いも、同じことです。
あれがしたい、これもしたい、と思っても、その思いが薄っぺらい衝動的なものだと、きちんとしたことはできません。
すること自体がむずかしいですし、やったとしても中途半端で、好い加減なものになるでしょう。
やりたいことを実現するためには、本当にそれがやりたいという気持ちを、しっかり持っていることが大切です。
つまり、口先だけでなく、本気で思うことですね。

思いと行動は一つのものです。
思っていることが、行動として表現されるのです。
ですから、やりたいと言いながら、何の準備もしないのは、本気ではなく口先だけということになります。
本気であれば、自然にそのような行動を取りますし、その結果が、夢の実現へとつながって行くのです。
時間がないとか、お金がないとか、言い訳をしているうちは、本気ではないということですね。
足場がしっかりした思いではありませんから、実現できないのは当然なのです。
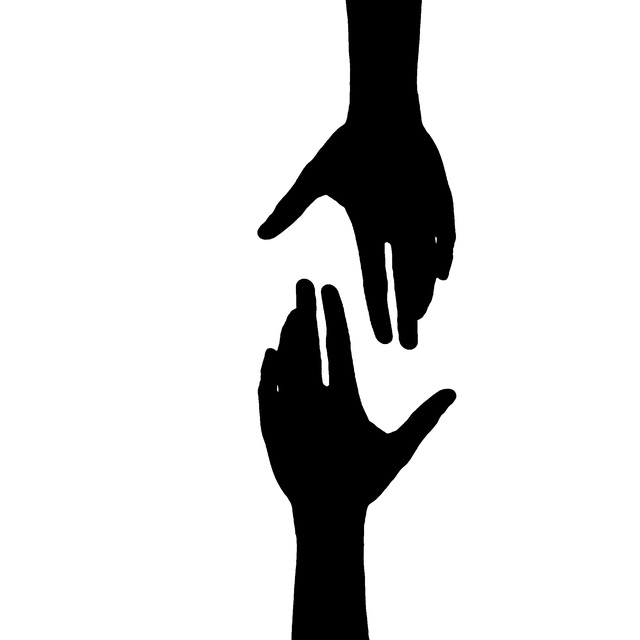
誰かを助けたいと思っても、自分が助けてもらっている立場なら、他人に手を貸すことなど、できるわけがありません。
自分がしっかり独り立ちしてこそ、他の人を助けることができるのです。
また、誰かを幸せにしようと思っても、自分が幸せでなければ、無理な話です。
幸せになるとは、幸せに気づくことです。
幸せでないということは、幸せに気づけないということです。
幸せでないと感じている人は、幸せに気づくことができないのです。
ですから、他の人に、どうすれば幸せに気づけるのかを、教えることはできません。
何をするにも、足場が大切です。
本気で思うこと。
独り立ちできていること。
幸せに気づけること。
この三つは、それぞれが足場です。
三つの足場がしっかりしてこそ、思ったような人生を送ることができるのです。
はらぺこあおむしと風刺画
「はらぺこあおむし」は、子どもたちに大人気の絵本です。
著者のエリック・カール氏は、つい先月91歳で亡くなられました。
この「はらぺこあおむし」が、毎日新聞の風刺画に利用されたことで、波紋が広がっています。
風刺画の内容は、絵本の表紙に描かれた「はらぺこあおむし」の顔の部分を、IOCのバッハ会長に換え、放映権と書かれたリンゴの実ならぬ、ゴリンの実(恐らくは五輪の実)を、仲間が食べている絵が描かれています。
風刺画の左上には、「エリック・カールさんを偲んで…」と書かれ、タイトルは「はらぺこIOC(あいおーしー)とありました。
「あおむし」と「あいおーしー」が似ていると思ったのでしょうね。
この風刺画に対して、「はらぺこあおむし」を日本で出版している、偕成社の社長から毎日新聞に対して、痛烈な抗議文が寄せられました。
その抗議に対して、全くそのとおりだと怒りを顕わにする人もいれば、IOCのしていることは、まさにこのようなことだと、風刺画を受け入れている人もいて、賛否両論のようです。
また、テレビのコメンテーターの中には、著者が文句を言うならともかく、何故出版社が著者に代わって文句を言うのかと、言う人もいましたが、出版社には出版権があるから、文句を言えるのだと言う人もいました。
このことに限りませんが、何かがあると、とにかくいろんな意見が出るものです。
それは、それだけ多くの視点や立場の違いが、あるということなのですね。
確かに、著者であるエリック氏が生きていたとして、この風刺画を見た時に、これを問題視したかどうかはわかりません。
外国の方なので、日本人よりは風刺に寛容であるかもしれません。
ただ、絵本というものは、著者だけのものとは言えません。
それは絵本に限らず、多くの文芸書もそうだと思いますが、公にされた絵本や本などの作品は、それを気に入って愛する人たちのものでもあるのです。
それらは、その人たちの心の一部になっているのです。
偕成社の社長は、著作権とか出版権ということではなく、「はらぺこあおむし」を愛する者の一人として、この絵本を愛している人たちを代表し、抗議したのでしょう。
それなのに、法律的な権利や罰則の話に固執したり、風刺なのだから少々のことは多めに見ろよ、というような考えがあるのは、ちょっと違うのではと思います。
もちろん、いろんな立場がありますので、誰がどのように考えるかは、その人たちの自由です。
でも、いい世の中を作りたいと思うのであれば、法律でどう書かれているかに関係なく、他の人たちの心を、傷つけないような言動を、常に模索するべきでしょう。
風刺と言えば、何でも許されるという考えは、オリンピックと言えば、何でも許されるという考えと、同じことです。
一般の人たちの気持ちを尊重しようとせず、自分たちがやりたいようにする、IOCを批判する風刺画が、「はらぺこあおむし」を愛する人たちの気持ちを尊重しないのは、皮肉なことです。
私から見れば、どちらも同じ穴のむじなですね。
自分の目的を達成するために、誰かを犠牲にするというやり方は、絶対にやめないといけません。
いい世の中を作りたいのであれば、という前提つきですが。
これは新聞の風刺画という、人々の目が集まる事例なので、問題とされました。
しかし似たようなことは、私たちの日常の一コマでも、よく見られるのではないでしょうか。
タバコや空き缶などのポイ捨てや、人が寝静まっている所での大騒ぎ、客だから何をしても許されるという誤解、迷惑を考えない路上駐車。
挙げればきりがありませんが、こういうことも、今回の風刺画と同じことです。
いい世の中を作りたいのであれば、そういう所から見直して行く必要があるでしょう。
今回の風刺画の問題は、そういうことを教えてくれた事例だと思います。
諱(いみな)
江戸時代まで、武士は元服をすると、本当の名前として、諱(いみな)というものを、親や主君からもらったそうです。
本当の名前を他人に知られると、呪われたりするので、他人には秘密の名前だったようです。
諱を呼んでいいのは、その人物の上になる者、つまり親や主君だけです。
他の人たちは、諱の代わりに、字(あざな)という、いわゆる通名で呼んだり、その人物の役職などで呼んだようです。
明治時代になってからは、諱と字という名前の使い分けはなくなり、誰もが本名で呼べるようになりました。
それが今に続いているのですが、呼び方がいくつもあるのは、複雑で面倒なように思えます。
でも、今だって会社の社長や部長などのことを、名前では呼ばずに、「社長(さん)」「部長(さん)」と役職名で呼んだりしますよね。
教師や医師のことも、名前で呼ばずに、「先生」と呼びますが、身内や親しい知人などは、名前やあだ名で呼ぶでしょう。
芸名やペンネームを持っている人は、そちらの名前で呼ばれることが、多いと思います。
呼び方がいくつもあるというのは、こんな感じだったのでしょう。
ただ、その人の本名は、本人が隠そうとしない限り、別に秘密ではありません。
ですから、「先生の名前は、風野陽二って言うんですか、ふーん」なんて言っても、怒られることはありません。
でも、江戸時代の侍に対して、庶民が同じようなことを言ったら、大変だったでしょうね。
ところで、諱のように本名を隠した状態というのは、本当の自分を隠しているのと、同じ意味合いになるでしょう。
相手の呪いを受けないために、本名を隠すというのは、そういうことだと思います。
本当の自分を隠したまま、周囲の人々と付き合うというのは、どこか醒めた気持ちで、人々を眺めている自分がいるということです。
スパイなんかは、そうですね。
自分の正体を悟られないよう、普通の人物を装いながら、自分の任務を遂行するのです。
どんなに周囲が笑ったり泣いたり怒ったりしても、それに引き込まれてはいけないのです。
引き込まれてしまうと、自分の使命を忘れてしまい、任務を果たせなくなるでしょう。
でも逆に、いろんなことに巻き込まれたり、影響を受けてしまい、他人に振り回される人生を送っている人は、生活現場から一歩離れた所から、自分が置かれた現状を、客観的に眺めてみる必要があります。
他人に共感することはあっても、振り回されないようにすることは大切です。
そもそも、自分は何のために、この世界に生まれて来たのだろうと考えると、今の自分を、これでいいのかという視点で、見ることができます。
この時の、見られている自分ではなく、見ている方の自分というのは、この世界の外から、この世界へやって来たという、自覚がある自分です。
ロールプレイングゲームを楽しむ時に、ゲームに参加したという意識を持っている自分ですね。
普段の自分は、人生というゲームにはまり込み過ぎて、ゲームに参加する前の自分のことなんか、すっかり忘れている自分です。
この人生に夢中になっている、自分が使っている名前が、いわゆる実名になるわけですが、この名前はこの世界でつけられた、この世界で暮らすための名前です。
この名前が本当の自分だと認識していると、人生ゲームにどっぷり浸かって、自分が置かれた状況を、冷静に見ることが難しくなります。
自分は外の世界から、この世界の人生を、体験しに来ているのだと考えられれば、物事を冷静に見ることができるはずです。
こんな時には、自分で自分に諱をつけてみましょう。
諱ですから、他人には一切秘密です。
親にも上司にも教える必要はありません。
知っているのは、自分だけです。
他人から呼ばれることのない諱をつけるのは、この世界ではない、外の世界の自分という認識を持つためです。
つまり、外の世界の自分を表す名前なのです。
この世界を客観的に見るためには、この世界から離れた視点が必要です。
そのために諱を利用するのです。
この世界の実名は、仮の名前であり、その名前で活動している自分は、仮の自分だと思えば、今の自分がこれでいいのかと、冷静に判断できるようになるでしょう。
他人の価値観と自分の価値観を、きちんと区別することもできると思います。
どうにもならない状況に、自分が置かれていると感じる人は、自分に諱を付けてみましょう。
本当の名前、秘密の名前です。
恐らく、その名前には、自分の本当の姿や、本当の望みが反映されているでしょう。
その名前こそが、本当の自分を表しているのだと受け止め、その名前のとおりの生き方を、探って行けば、行き詰まった状況から、抜け出せると思います。
この世界での経験は、とても大切なのですが、その大切さを理解するためにも、この世界から離れた視点が必要になるのです。
愛と自由と責任
自由と言えば、責任という言葉が、セットになって付いて来ます。
自由に責任は付きものであり、責任のない自由とは、本当の自由とは認められません。
では、責任とは何でしょうか。
それは、自分の言動によって、周囲に与える影響や結果を、きちんと認識し、その事実を受け入れることです。
特に、誰かに被害を与えるようなことになれば、それを償うということで、責任という言葉は使われます。
ただ、この責任という言葉は、今の人間社会においてのみ通用する概念であり、自然界においては無意味です。
生物は自分が生きられる所があれば、どこでも生きようとします。
そのために、他の生物が居場所をなくそうが、命を落とそうが、知ったことではありません。
お前のせいでひどい目に遭ったと、訴える生物もいませんから、そこに責任という概念は生じません。
つまり、責任というものは絶対的なものではなく、人間が創り出した概念です。
では、責任を軽視していいのかと言うと、そうではありません。
みんなが責任を放棄すれば、社会は崩壊してしまい、人間は野生の動物のような暮らしを、強いられることになるからです。
しかし、責任という概念を前面に打ち出して、自由を定義づけるのも、自由の意味を考えると、違和感を覚えます。

自由というのは、自分自身を愛するということと、同じ意味です。
自分を認め、自分の思いの通りに行動する。
それが、自由です。
どうせ自分なんて、と考えて、やりたいことがあっても、我慢するのは、自由ではありません。
誰に制限されることもなく、拘束されているわけでなくても、自分に価値がないと見なして、自分で自分を抑制する人は、不自由なのです。
多くの人は、自由か自由でないかを、他人による制限や障害というイメージで、考えがちですが、自分自身が制限しているということに、気がつかなくてはなりません。
自分を愛し、自分を大切にできる人が、自由でいられるのです。
自分を大切に考える時、初めは自分のことしか、目に入らないかもしれません。
子どもがそうですよね。
子どもは自分が思ったとおりに動きます。
それで、誰かにぶつかろうと、お構いなしです。
でも、周囲との関係における、自身の居心地のよさを、考慮に入れるようになると、自然に他の人の気持ちを、考えるようになります。

そして、感情や思いを共有するようになると、相手と自分の区別をしなくなって来ます。
つまり、相手のことを自分のことのように、考えるようになるのですね。
そうなると、自由な行動というものが、責任という言葉を使わなくても、初めから他の人たちのことを、考えたものになりますから、問題は起きにくくなります。
何か問題が起こったとしても、相手の側もこちらに対して、我が事のような思いを持っていれば、大きなトラブルにはなりません。
事件や犯罪と呼ばれるような行動は、本人にとっては自由な行動です。
それを法律的、社会的に見れば、無責任な行動ということになります。
でも、別の見方をすれば、その人物は他の人々と、気持ちを共有する経験を、持つことができなかったのだと、考えることができるでしょう。
もしかしたら、自分自身をも愛することができず、自由と言うよりは、自暴自棄になっているのかもしれません。
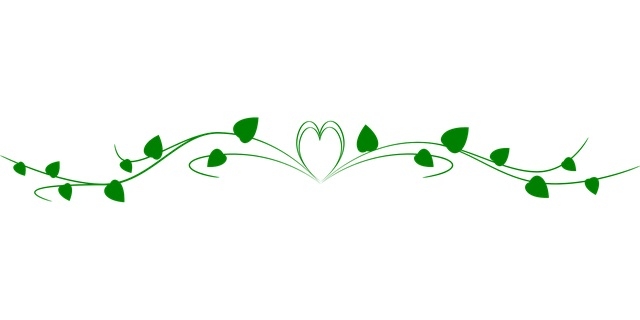
本当の自由を実現するためには、責任よりも愛を重視するべきでしょう。
まずは、自分を愛するということ。
そして、その愛が周囲へと広がるような、環境を整えることです。
この周囲とは、人間とは限りません。
他の生き物や、自然環境、地球や宇宙などにも、広げることは可能です。
いろんな人が、それぞれ自由に暮らし、それでも調和が取れている社会を、想像してみて下さい。
自然とも共存し、他の生き物たちも、活き活きと暮らしている社会です。
それは、愛に満ちた社会です。
そんな社会を考えたなら、愛と自由が同じ意味であることが、理解できると思います。
結婚願望

独身の人が、いい人を見つけて、結婚したいと思うのは、自然なことです。
しかし、結婚を通して、自分が何を求めているのか、確かめてみることは大事です。
これは、これから結婚しようと考えている人はもちろんですが、すでに結婚している人も、自分の気持ちを、見つめ直して欲しいと思います。
結婚は、赤の他人だった二人が、一緒になって暮らすことです。
役所に届け出をしているかどうかに関係なく、好きになった者同士が、一緒になるという状況での話です。
結婚について思うところは、人様々だと思います。
結婚をどう考えようと、その人の自由ですから、良いも悪いもありません。
ただ、結婚を通して幸せを感じたいのであれば、気をつけないといけないことがあります。
それは、相手に何も求めないということです。
結婚して、独身生活とおさらばすることで、自分も人並みになるとか、いろいろ尽くしてもらえるなどと期待していると、実際の結婚生活に落胆するかもしれません。
相手に何かをしてあげたいという気持ちで、一緒になるのであれば、基本的には問題はありません。
ただ、相手の気持ちや習慣を無視して、自分の思いを押しつけるようなことをしてしまうと、トラブルになることはあります。
大事なのは、相手に敬意を払い、相手の気持ちを尊重するということでしょう。

また、自分を殺して相手に尽くすというのも、お勧めできません。
自分というものをさらけ出して、相手に理解してもらうことも大切です。
こういう事は、できれば結婚前に、お互いに見せ合うのがいいですね。
それで合わないのであれば、結婚しなければいいことですから。
相手に何かを求めて結婚するというのは、破綻する可能性が高いと思います。
求めているものが満たされないと、相手の存在価値がなくなるからです。
自分ばっかり頑張っているのに、何もしてくれないという気持ちになると、途端に気持ちは冷めてしまいます。
結婚は形ばかりになって、互いの心は離ればなれになるでしょう。

相手に何かを求めたり、すがったりする気持ちがあるのなら、どうしてそう考えてしまうのかを、理解する必要があります。
それは恐らく、自分に自信がないからでしょう。
自分には何もできない、何をして生きていけばいいのかわからない、自分一人だと不安だ。
こんな気持ちがあると、誰か自分を助けてくれる人、力になってくれる人が、欲しくなります。
しかし、自分は何でもできる、やりたいことが見つかった、一人でいても全然問題ない、となると、何も無理に結婚しなくてもいいかな、と思うようになるでしょう。
結婚する時は、本当に気持ちが合った人とするのだと、考えるようになるのです。
結婚をしたくなった時、どうして結婚したいのか、考えてみて下さい。
すでに結婚している人も、自分はどんな結婚生活を考えていたのかを、振り返ってみるといいと思います。
萬翠荘
前回に続いて、松山の見所を紹介します。
松山城がそびえる勝山の南側に、大正時代に建築された洋館があります。
それが萬翠荘(ばんすいそう)です。

萬翠荘は、旧松山藩主の跡を継いだ、久松家当主の久松 定謨(ひさまつ さだこと)伯爵が、大正11年(1922年)に別邸として建設したものです。
フランス生活が長かった伯爵の好みで、萬翠荘はフランス風に造られています。
しかし、西洋建築は左右対称が多いのに対し、萬翠荘は左右非対称です。
右側には尖塔の屋根がありますが、左側にはありません。
これは左右非対称が多い日本建築の要素を、フランス建築と融合させたものと言われています。

萬翠荘の建築の話が進められていた頃、大正11年11月に四国で陸軍の特別大演習が、行われる予定となり、天皇陛下が来られるという話になりました。
当時、大正天皇は病気ということで、皇太子の裕仁親王(ひろひとしんのう)が、天皇代理の摂政宮(せっしょうのみや)として四国を訪れ、大演習のあとに各地を視察することとなりました。
しかし、松山には摂政宮の宿泊所がなく、萬翠荘をその宿泊所として、ふさわしいものとして建てるということになったそうです。
萬翠荘は、愛媛県で初めての鉄筋コンクリートで造られた建物で、当時は全国的にも、鉄筋コンクリート製法が、まだ普及していませんでした。
また、トイレも西洋式便器を用いた水洗トイレです。
大正時代に水洗トイレがあったなんて、驚きですね。
各部屋には、やはり当時珍しい、電気による連絡ボタンが付いています。
用事がある相手によって、押すボタンを分けていて、ボタンを押すと、相手の部屋のベルが鳴るという仕組みです。
暖炉も各部屋に備え付けですが、薪を燃やすのではなく、当時の最新式であるガス式の暖炉です。
部屋や廊下、階段には絨毯が敷き詰められ、階段の踊り場には、大きなステンドグラスが飾られています。


二階には、伯爵と伯爵夫人の部屋の他、来賓の部屋などもあります。
摂政宮(のちの昭和天皇)が泊まられた部屋や、食事をされた部屋も見学できます。

前回紹介しました庚申庵(こうしんあん)と同じく、萬翠荘も戦災を免れました。
これだけ立派で大きな建物が、無事だったことは、まさに奇跡と言えるでしょう。
当時、萬翠荘は最高の社交の場として、各界名士が集まったと言います。
また、皇族方がご来県の際は、必ず立ち寄られたそうです。
今は誰でも気軽に訪ねることができますので、大正時代を感じてみたい方は、ぜひご来館下さい。



庚申庵

松山市の街中に、周囲とは異なる時空間があります。
それは、庚申庵(こうしんあん)史跡庭園です。
庚申庵というのは、寛政12年(1800年)に伊予の俳人・栗田樗堂(くりた ちょどう)が、残された人生を俳句一筋で生きようと思って、建てた庵です。
栗田樗堂 52歳の時のことです。
庚申庵という名前の由来は、寛政12年が干支でいう庚申(かのえさる)であったことと、古庚申と呼ぶ青面金剛の祠が、近くにあったのに因んだとされています。
栗田樗堂は俳人であると同時に、酒造業を営み、町役の大年寄も担っていた、町の有力者でもあったようです。

仲間を集めて俳句を楽しむ庵は、とても簡素です。
やたら物が多い現代の人間に比べ、本当に必要な物だけを携える、当時の人々の暮らしが窺えて、とても新鮮な気持ちになれます。
生活環境や住まいの様子は、その人の心の表れでもあります。
多くの物に囲まれる私たちは、それだけ多くのことに興味が引かれ、訳がわからなくなっているように思えます。

庚申庵には何もないのに貧相でなく、心が落ち着き和むのは、この空間にいることで、自分自身の心も無駄な部分が削ぎ落とされ、すっきりするからでしょう。
温泉に浸かって、体をきれいにしたような感じですね。

庵の前には藤棚があり、その向こうには樹木に囲まれた、小さな池があります。
藤の木は庵の建設当時に植えられたもので、樹齢200年以上になるものです。
外に出ると、すぐ横を伊予鉄道が走り、近くには大きなスーパーがあります。
それなのに、縁側に座って庭を眺めていると、自分が松山の街中にいるのを、忘れてしまいます。
私が訪れた時には、多くの蝶々が飛び交っていましたが、人を恐れる様子もなく、すぐそばまで飛んで来るのが、嬉しかったですね。

松山は戦災に遭って、町の大半が焼かれてしまいましたが、庚申庵は奇跡的に被害を免れたそうです。
昭和24年に愛媛県史跡に指定され、平成13年に解体調査と修復工事を行ったのち、平成15年に史跡公園として開園されました。
機会のある方は、ぜひお訪ね下さい。
特に、心が疲れている方には、お勧めです。
支配欲

誰かを支配したいという気持ちは、誰にでもあります。
それは自分の世界を、自分の思い通りにしたいという、願望に基づいたものです。
自分が認識しているものは、全て自分が関わっている世界の一部ですから、それが人であれ動物であれ、あるいは自然であれ、自由に動かしたいのです。
逆に言えば、そういう気持ちが強い人は、普段、不自由を感じることが多いのでしょう。
その結果、ストレスを抱えて、心が潰れそうになっているのだと思います。
恋人や配偶者、子ども、ペット。
可愛がったり愛しているように見えながら、実は相手を支配しようとしていることは、よくあることです。
この人のため、この子のため、という聞こえのいい言葉を使いながら、相手を自分の思い通りにしようとしてしまうのです。
自由に生きている人は、他人を縛りつけようとは思いません。
そんな発想が出て来ないのです。
自分が縛られて生きていると、誰かを縛ることを当たり前だと思います。
それで自分が不自由な思いをしていても、同じことをしてしまうのですね。
自分が不自由だから、誰かを支配することで、バランスを取ろうとするわけです。
それが、不自由の悪循環を招きます。

会社の経営陣や、政府の人々は、労働者あるいは国民を支配しようとします。
また、他の会社を傘下に置いたり、貧しい国を支援を餌にして、自分の味方につけることも、相手を支配しているわけです。
こうすることが起こるのは、個人レベルが不自由の連鎖をするのと同じで、今の経済システムが、誰かを支配するという形態で成り立っているからです。
つまり、自分以外のものを支配して、コントロールしなければ、自分たちが中心になって生きていけないという、不安や焦りがあるわけです。
世界は弱肉強食で成り立っているから、強くなければ食われてしまうという、恐れがあるのですね。
また、会社や国の上に立つ人々の、個人的な意識で考えると、いかに多くの人間を、自分が支配しているかということで、大きな安心感を得ようとしているわけです。
自分が世の中を動かしているのだという、満足感が欲しいのですね。

言い換えれば、こういう人たちほど、世の中のことを、一方踏み間違えれば、奈落の底へ落ちてしまう、危なっかしくて怖い所だと、考えているのだと思います。
世界全体を自分が支配しなければ、安心して生きていけないと、考えるのでしょう。
自由に生きるということを、本当に理解している人たちが、世界をリードできるようになれば、世の中は今とは全然異なるものになるでしょう。
ここで言う自由とは、他人への迷惑を顧みない、という意味ではありません。
本当に自由を愛している人は、他人の自由を尊重しますし、他人の自由を邪魔するようなことは、望みません。
それは、他の生き物に対しても、同じです。
つまり、本当の自由を知る者は、他人に対しても、自然の生き物に対しても、思いやりの心を持っているということです。
誰かをコントロールしているなと感じたら、あるいは、自分は思いやりの心に欠けているなと感じたら、自分は自由に生きているのだろうかと、振り返ってみて下さい。
不自由な生き方をしていると気づいたなら、思い切って自由に生きてみましょう。

不安かもしれませんが、プールの水に飛び込むようなものです。
やってみれば、全然問題がないことが、わかるでしょう。
そして、清々しい気持ちになっていること、気づくはずです。
チョキチョキで気分転換

嫌なこと、腹が立つことって、ありますよね。
世の中には、いろんな人がいますし、いろんなことがありますから、自分と波長が合わない人に出会ったり、波長が合わない出来事を目にすることは、避けられません。
でも、それが一時的なものであり、すぐに忘れるのであれば問題ありません。
食べ物で言えば、口にした物に苦味があっても、それを呑み込んで、甘い物を食べれば、苦味のことは忘れてしまいます。
料理によっては、その苦味を味のアクセントに使って、料理全体の味を引き立てることもできます。
これは、嫌な人や嫌なことの存在意義を認め、それがあるから、こちらの素晴らしさが理解できるようになった、という見方ができるようになるのと同じでしょう。
人生、いろんなことがあるからこそ、味わい深く面白いのだと受け取れるようになれば、一番ですね。
そうは言っても、今、嫌な目に遭っているのに、そんな風には思えないということは、あるでしょう。
それも、一時的なものではなく、継続的な場合です。
でも、物理的に継続的であるのなら、そこから離れればいいのです。
離れられないと、いろいろ理由を挙げるかもしれませんが、それはその人の勝手です。
そこを離れるか、離れないか、それを決定しているのは、その人自身です。
その結果、嫌だと思っても、それは自分が選んでいることなので、仕方がありません。
人間社会における常識や価値観が、自分の行動を制限し、離れたいけど離れられないという場合、問題は自分が常識や価値観に、縛られているということです。
実は、それこそが本当の問題だと気がつけば、その人は自由になって、行きたい所へ行けるし、離れたい所から離れられるようになるのです。
嫌なことが物理的に継続しているわけではなくても、どうしても頭に浮かんでしまい、別の場所にいるはずなのに、気分が滅入ってしまうこともあるでしょう。
楽しいことをしようと思っても、嫌なことを思い出してしまって、楽しい気分になれません。
そんな時には、その嫌な思いをチョキチョキと切り捨てましょう。
自分で自分の髪を、散髪するようなつもりで、じゃんけんのチョキを作って、手のハサミで頭のぎりぎりの所を、チョキチョキっとするのです。

何となく、この辺りに嫌な思いがあるなと感じる部分で、チョキチョキっとして、切った思いを、パッパッと払い除けて下さい。
髪を切った時に、切った髪を払い落とすような感じです。
嫌なことを思い出したら、うるさいよ、お前なんかいらないよ、と言いながら、チョキチョキしてみて下さい。
散髪すると頭がすっきりしますが、それと同じように、頭の中がすっきりしますよ。
嫌な思いが軽ければ、ちょこっとチョキチョキするだけで済みますが、結構大きなものであれば、頭全体をチョキチョキする必要があります。
それに、嫌な思いが頭の中に食い込んでいれば、チョキチョキしてすっきりしたつもりでも、すぐにニョキニョキっと、頭の中から生えて来ます。
そんな時は、またチョキチョキして下さい。
何度生えて来たとしても、限界があります。
最後には生えて来なくなりますから、何度でも楽しむように、チョキチョキを繰り返します。
チョキチョキしてすっきりすれば、すぐに楽しいことに取り組みましょう。
楽しいことをブロックしていた、嫌な思いをチョキチョキすれば、楽しいことがどっと頭や心に、流れ込んで来ます。
楽しさが心の中に芽生えると、嫌な思いを追い出す手伝いをしてくれます。
チョキチョキは外から嫌な思いを取り除き、楽しさは中から嫌な思いを、外へ押し出します。
チョキチョキと楽しさのダブル効果で、頭から離れない嫌な思いも、きれいに取り除いて、すっきりできますよ。
では、どうして、チョキチョキに効果があるのでしょうか。
嫌な思いが頭を離れない時、意識が嫌な思いと一体化しています。
一体化しているので、引き離そうとしても、引き離すことができません。
だけど、チョキチョキしている時の自分は、嫌な思いと意識が離れているわけです。
チョキチョキしようと考えた時点で、かなりいい状態になっています。
そして、実際にチョキチョキすることで、嫌な思いを客観的にとらえて、切り捨てたという状態に、意識を変化させられます。
楽しい気持ちも、当然意識を変化させるものです。
それによって、頭の中がすっきりするのです。
また、頭の中がすっきりすれば、いろんなことを冷静に考えられるようになりますから、自分が嫌だと思っていたものの、本当の正体を見極めることが、できるようになります。
何で自分がこんなくだらないことで、悩んでいたんだろうと思えるようになるのです。
うそみたいですけど、嫌な思いで悩んでいる人は、試しにチョキチョキしてみてください。
ラジオ体操を面倒くさそうにしても、何の効果もないのと同じで、チョキチョキも真剣にしないと、効果はありません。
本当に嫌な思いを切り捨てているイメージで、お試し下さい。

