感情と波長 その2

音叉ってご存知ですよね?
学校の理科の実験で使った、U字型の金属で、それぞれが固有の振動数を持っているのです。
一つの音叉を叩いて音を鳴らすと、その音叉と同じ振動数を持つ別の音叉も、共鳴して勝手に音が鳴るんですね。
でも、振動数が異なる音叉は、鳴りません。
これと同じで、振動数が低い感情、たとえば、いらいらしてたり、暗く落ち込んでいたりしている人のそばに、同じような人がいると、互いの雰囲気が共鳴し合って、余計にいらいらや落ち込みが、強くなるわけです。
何かでみんなが不安になっている時に、誰かがパニックになって騒ぎ出すと、次々に他の人たちも騒ぎ出すのも、これと同じです。
振動数が高い感情、喜びや楽しさも、やはり共鳴し合って、より大きな喜びや楽しさを生み出します。
いらいらしている人が、喜びや楽しさに共鳴できないかと言うと、そうではありません。
自分の中の、喜びや楽しさに共鳴する部分に、意識の焦点を合わせればいいのです。
言い換えれば、心の中に様々な感情の音叉があると考えるのです。
それぞれの音叉は、それぞれの振動数と同じものに、共鳴します。
そして、どの音叉に意識を合わせるかで、その人の気分が決まるわけです。

こんな時に喜べるものか。
何が楽しいんだ、まったく。
人の気持ちも知らないで、不謹慎な。
こんな風に考えてしまうと、意識の焦点をいらいらの音叉から、外すことができません。
余計なことは考えず、ただ自分の楽しさの音叉 に、意識の焦点を合わせてやると、さっきまでいらいらしていたことなど忘れて、腹の底から笑えるのです。
別に、いらいらや落ち込みが悪いとは言いませんが、その状態は居心地が悪いと思います。
そうであるなら、意識の焦点を変えることで、別の音叉を選び、落ち込んだ気分を楽しい気分にすればいいでしょう。
このように、どの音叉に意識を向けるかで、気持ちや感情が変わります。
いつも楽しくできる人は、心の中に気分を落ち込ませる音叉が、全然ないということではありません。
あるのだけれど、そこに焦点を当てていないということですね。
つまり、常に楽しい音叉に、焦点を当て続けているのです。
いらいらしている人に、楽しさの音叉がなければ、この人は一生いらいらしたままです。
でも、そんなことは有り得ません。
いらいらしている人も、楽しさの音叉を見つけて、そこの意識を向けていれば、どんどん楽しくなるのです。

また、どんなに明るい人でも、落ち込みの音叉を共鳴させるような、強い刺激があると、やはり暗い気持ちになります。
それでも、共鳴する刺激から遠ざかり、喜びの音叉を振動させるようにしていると、落ち込みは過去の記憶となり、今に影響しなくなります。
いらいらや落ち込みが続く人は、いらいらや落ち込みの音叉を、共鳴させる刺激から離れないのだと思います。
離れない理由は、人それぞれでしょうが、わざわざ暗くなる音叉を、刺激し続けていることは、どの人も同じでしょう。
落ち込み気分を、楽しんでいるのならいいのですが、そうでないのなら、まずは落ち込み音叉を刺激するものから離れないといけません。
似たような人で集まるのは、お勧めしません。
落ち込みの刺激から離れたあとは、楽しさを刺激するものに、触れることですね。
何の遠慮もいらないし、躊躇する必要もありません。
素直な気持ちで、積極的に楽しいことに触れれば、心の振動数はすぐに高くなるでしょう。
自分が何かの感情を持った時、心の中で、どんな音叉が振動しているのか、想像してみて下さい。
苦しくてつらい時には、苦しみやつらさの音叉が、キーンと鳴っているのです。
その音叉を鎮めるイメージをするだけでも、苦しさやつらさを和らげる効果を、かなり期待できると思います。
感情と波長 その1
私たちの意識には、波長があると言われています。
ですから、気が合わない相手とのことを、波長が合わないと言うのですね。
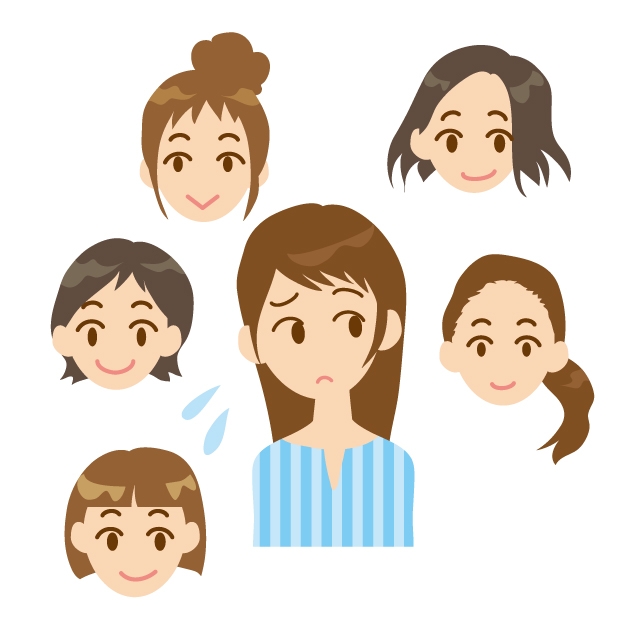
波長とは何かと言うと、振動する波の長さのことです。
一分間にいくつの波があるかを、振動数と言います。
たとえば、一分間に10回振動すると、振動数が10ヘルツだと表現します。
100回振動すれば、振動数は100ヘルツです。
波長や振動数という言葉は、電波の性質を表す時によく使います。
電波と光は同じものですから、その速度は同じです。
つまり、一秒間に進む距離は約30万kmで、地球を7周半回るだけの長さです。
その距離の中に、10ヘルツの振動数の電波であれば、一つの波の長さである波長は、約3万kmになります。
100ヘルツの電波であれば、波長はその10分の1であり、約3千kmとなります。

水面の波紋は、光や電波と違って、目に見えるのでわかりやすいと思います。
お風呂に入った時に、お湯に指をつけて動かすと、その周囲に波紋が広がりますよね。
指を一定の間隔で動かすと、それに応じた波紋が生まれます。
指を細かく動かすと、幅の狭い波紋がたくさんできるでしょう。
指をゆっくり動かすと、幅の広い波紋ができます。
この指の動きが振動数で、できた波紋の感覚が波長です。
ところで、意識に波長や振動数があると言われても、よくわからないかもしれませんね。
意識は光や水面の波のように、動いてはいません。
ずっと同じ体に固定されています。
ですから、振動しているという概念は受け入れられても、波長と言われると、ピンと来ないかもしれません。
でも、波長という言葉は、振動数を表現しているのと同じことですので、波長が違うということは、振動数が違うと考えればいいのです。
実際、意識が振動しているのかどうか、私たちにはわかりません。
心が科学の対象になっていないため、意識を直接測定するような機器がないのです。
しかし、個人的にはその時の気分で、心がどよんとしていたり、テンションが高くなっていたりは、わかります。
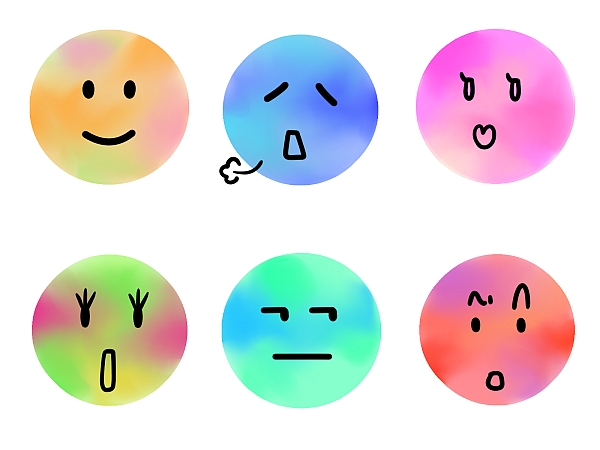
どよんとしている時には、心の活動が鈍っていると考えられますから、振動数が低いと見ることができるでしょう。
テンションが高くなっている時には、心の活動は活発になっていると見られますから、振動数は高いと考えられます。
つまり、自分の感情を確かめることによって、自分の心の振動数もしくは波長を、知ることができるわけです。
地方への移住

今、地方へ移住する人が増えているようです。
以前から、都会での暮らしに疲れたり、定年後の静かな暮らしを求めて、田舎へ移住する人はいました。
でも、今は田舎の魅力に惹かれて、移住をする若い人が多くなったように思います。
地方も過疎化を防ぐため、新しい住人を増やそうと、いろいろ工夫や努力をしています。
それでも、やはり働くなら都会というイメージが、先行している中では、思ったようには移住者は来てくれなかったでしょう。
しかし、コロナ騒ぎの影響で、テレワークを推進する職場が増え、住居を会社がある都会に構える必要がなくなりました。
それは、若者を地方へ移住させる、大きなきっかけとなっています。
また、コロナ騒ぎが起こる前から、食の大切さを知ったり、大切な食に関わることへの、生き甲斐を感じる若者が、増えていました。
彼らはフロンティアであり、都会で仕事を失い、行き場所を見失った若者たちにとって、灯台の役目を果たしています。
これまで何となく都会で暮らし続けていた人たちが、その暮らしが困難になった時、都会にいる必要があるのかと、自問するようになっていると思います。
そんな人たちが、田舎で活き活きと暮らしている、同世代の者たちの存在を知れば、自分もやってみようと思う気持ちになるでしょう。
地方にとっては、願ってもないことですから、これまで以上に手厚いサポートをしてくれるでしょう。
地方では、地元の人々との交流は、何より大切なことですが、都会の人には、馴染みにくいところがあるかもしれません。
それでも、そこで楽しく暮らしたいという思いがあれば、地元の人たちとの交流が、それまで知らなかった楽しさであると、気がつくことでしょう。
地方に元々住む人たちも、どんどん外から人が来れば、新しい力に刺激され、それまでの保守性も弱まって行きます。
そうして、都会から来る人も、地方の人も、お互いに刺激し合い、助け合いながら、新しい地域社会を築いていくのです。
それは、これまでの経済社会の理屈から離れた、新しい独自の社会になるでしょう。
一つ一つの地域は、小さく限られていますが、日本中にそれらの地域が、数多く生まれ、それらの地域同士で連携し合うと、日本そのものが新しい日本に、生まれ変わることになるのです。
それは夢物語ではなく、必ずそうなると私は思います。
コロナ騒ぎは確かに大変ですが、その大変さがあるからこそ、既存の日本の政治、日本の社会は崩壊し、新たな生き方が生まれ出るのです。
今の日本の状況は、芋虫が美しい蝶々に変わろうとしているように、見えませんか。
サナギの中で、体の構成が大きく変わって行くように、人間社会も大きく変わろうとしているのです。
その変化の一つが、若い人たちの地方への移住です。
彼らの持つ価値観は、もやはかつての日本人が掲げていた価値観とは、全然異なるものです。
一人だけ見ていると、個人が勝手に動いているように、見えるかもしれません。
しかし、全体を眺めてみると、明らかに社会全体が変化しようと、蠢いているのがわかるでしょう。
そして、私やあなたも変化を始めている社会の一部です。
サナギの中では、芋虫の体で不要になった部分は、溶けてなくなります。
必要な部分は残りますし、足らない部分は新たに構成されて行きます。
あなたは、溶けてなくなる方に属していたいでしょうか。
新たな社会でも残る部分、あるいは新たに構成される部分に、属していたいでしょうか。
社会の変化を、不安な気持ちで眺めているだけの人は、溶けてなくなる方に属しているのだと思います。
それが嫌ならば、自分も新たな社会に、何等かの形で参加したいと思いましょう。
そして、自分に何ができるのか、自分は何をすれば楽しめるのかを、真剣に考えたらいいと思います。
新たな社会は、喜びに満ちたものとなるでしょう。
それは言い換えれば、喜びを見つけ、喜びを表現し、喜びを与えられる人々の社会ということです。
つまり、自分がみんなと一緒に楽しめればいいのです。
あんなこと、できるわけがないとか、こんなことはしないよな、なんてことは考えず、自分の素直な気持ちに従うことです。
自分が何がしたいのか。
自分はどんなことに興味があるのか。
自分は何に喜びを感じるのか。
そういうことを考え、すでに行動を起こしている人がいるのです。
何の遠慮もいりません。
今こそ、あなたも自由に動くべき時なのだと思います。
聞く耳を持つ その3

とても苦しい状況に置かれているのに、どうしたらわからない場合、誰かの助言を仰ぐといいでしょう。
自分の考えだけで、うまく行くのであれば、そもそも苦しい状況に、陥ったりすることはありません。
自分では気がついていない、何かに問題があったからこそ、苦しい状況に陥るわけです。
自分で気がつかないということは、視点を変えて考える必要があります。
たとえば、天井から雨漏りがするのを、下から見上げていただけでは、わかりませんよね。
屋根に登ったり、天井裏を調べてみたりしないと、どこから雨が侵入しているのかを、見極めることはできません。
意固地になって、雨漏りを下から眺め、ぶつぶつ文句を言ったところで、雨漏りは止まりません。
放って置くと、どんどんひどくなるばかりです。

物事はこの雨漏りと同じで、おかしくなり始めたら、すぐに対処するのが、一番なのです。
放置すればするほど、手に負えなくなってしまいます。
それでも、誰かに助けを求められない人がいます。
そういう事に、慣れていないだけのこともあるでしょう。
でも、思い込みのために、助けを求められない人もいると思います。
そんな人の心には、助けてもらうのは情けない事だ、という考えが、どこかに潜んでいます。
それは言い換えれば、何でも自分一人でできることが、一人前の人間だという、思い込みなのです。
でも、自分が生まれて来る前から、人間は存在しているわけです。
あとから生まれて来た者が、一人前の人間とはこうなのだと決めつけることは、とても傲慢なことです。
自分の人生経験で得た知識など、たかが知れています。
それだけを元にして、人生とはこうだ、人間とはこうなんだ、と決めつけるのは間違っています。
間違っているからこそ、その考えが自分自身を、苦しめることになるわけです。

人の数だけ、いろんな視点があります。
いろんな違う視点の意見を聞くことは、とても勉強になります。
何か言われたからと言って、そのとおりにする必要はありません。
最終的にどうするかを決定するのは、本人です。
また、言われたとおりにしたからと言って、その人に従ったという事にもなりません。
その人の意見を納得し、自分も同じ考えを持っただけであり、あくまでも自分の考えで決めているのです。
逆に言えば、あとから、あの人がこう言ったから、という言い訳は通用しません。
自分で納得して決めた以上は、それは自分の考えであり、自分の決定だからです。
とにかく、人生の主導権は常に自分にあります。
人の意見を聞いたところで、自分の価値に何も変わりません。
それどころか視野が広がり、人生を一段高い所から眺めることが、できるようになるでしょう。
そして、これまで自分の自由を、自分自身で奪っていたことに、気がつくのです。
聞く耳を持つ その2
我が道を行くという人は、自分の本質を理解している人です。
我が道というのは、職業ということではありません。
同じ仕事を続ける人もいれば、いろんな仕事をこなす人もいます。
それでも、その人は同じ我が道を進んでいるのです。
それは、その人の本質そのものであり、時や場所が変わっても、そこで自分の本質を表すということなのです。

流行や、いろんなルールに従って、生きているわけではありません。
だからと言って、そういうものを否定したり、逆らったりはしません。
どんな状況でも、自分の本質をそこに合わせて、表現するだけなのです。
ただ、どうしても表現を妨げるルールがあったなら、そのルールが適応されない所へ、移動するでしょう。
移動が許されず、ルールか自分の考えか、どちらかを選べと言われたら、自分の考えを選びます。
それが、我が道を行くということなのです。

一方、我が道を進んでいるつもりの頑固な人は、移動することに敗北感を感じるでしょう。
自分は間違っていないのに、何で自分が移動しないといけないのか、と考えるからです。
自分がこれと決めれば、それを変更することは、受け入れられません。
長く続けていた仕事を、何等かの理由で辞めざるを得ないと、何をしていいのかわからなくなり、精神的に落ち着かなくなります。
他の可能性を追求するなど、考えることがありません。
それは、自分には他に何もできないという、決めつけた自信のなさが原因です。
自分を過小評価し、否定し、愛そうとしていません。
我が道を進む人とは、真逆の状態なんですね。
人の言葉に耳を貸せないのは、心に余裕がないことの裏返しです。
誰かの言葉に耳を傾けることは、決して自分を否定することにはならないのだと、理解することが大切です。
聞く耳を持つ その1

人の話を聞こうとしない。
そんな人、いますよね。
何を言っても、我が道を進む頑固者。
こうだと言い出したら、譲らない。
こういう時、本人は自分は間違っていないと、思い込んでいるんですね。
自分が間違っていない以上、悪いのは相手であったり、環境であるわけです。
自分の考えを見直すのは、自分にも間違ったところがあると、認めるようなものですから、そんなことは断固として否定します。
それを、あえて考え直すよう強いると、自分を否定されたと受け止めて、ひどく傷つくのです。
人はそれぞれ自分の考えがあり、その考えに従って生きています。
ですから、頑固であろうとなかろうと、それはその人の自由であり、他人がとやかく言うことではありません。
ただ、それは他の人にも言えることですから、他の人が話の通じない相手と、距離を置いたとしても、それも責めることはできないわけです。
自分だけが正しいと考える人は、たとえ本当に正しかったとしても、その正しさは他の人に、受け入れてもらえないでしょう。

態度や雰囲気は、言葉と同じように、自分の思いを表現するものです。
それが相手を否定したり拒絶するようなものだと、誰も寄りつこうとしないでしょう。
寄りつくとすれば、その人の鼻っ柱をへし折ってやろうと、考える人たちだけです。
そんな状況をよしとして、自分の姿勢を貫くのであれば、それはそれで立派だと思います。
誰が何と言おうと、これが自分なんだと納得し、満足するのであれば、それでいいでしょう。
でも、みんなから避けられたり、喧嘩を吹っかけられたりすることに、居心地が悪いと感じるならば、自分の路線を見直してみる必要があると思います。
何で自分が考えを改めないといけないんだ、と腹立たしく思うかもしれません。
しかし、世界のルールを自分が創ったわけでないのなら、もう少し謙虚にならないといけないでしょう。
結局、こういう人はとても傷つきやすく、不安がいっぱいなのです。
ですから、自分を肯定し、守るために、他人に対して攻撃的になったり、聞く耳を持とうとしなかったりするんですね。
自分に自信がありながら、謙虚な心を持っている人は、絶対に攻撃的になりません。
自分が正しいと思っても、それは絶対的なものではないと、理解していますから、他人の話にも耳を傾けようとします。
我が道を行くということと、人の話に耳を貸さないというのは、実は全然違うことなのです。
頑固な人は、そこのところを誤解しているのかもしれませんね。
死について考える その3

死んで人生を終えても、それで終わりではありません。
私たちの多くは、精神場にある世界へ移行したあと、再びこの世界へ生まれ変わって来るようです。
しかし、それは何故でしょうか。
何故、何度も死んでは生まれ変わるということを、繰り返す必要があるのでしょう。
この世界は、それほど面白く魅力的なのでしょうか。
あるいは、前の人生では体験できなかったことを、今度こそ体験しようとしているのでしょうか。

向こうの世界の話を聞くと、向こうの方が自由だし、超能力と呼べるような力が、使えるようです。
望んだことは、何でも実現されますし、死を恐れることもありません。
それなのに、わざわざ不自由なこの世界に、舞い戻って来るのは何故なのでしょう。
その理由がわからなくても、何かこの世界に秘密があるのだと、いうことはわかると思います。
向こうの世界にいたのでは、体験できないような何かが、この世界にはあるのです。
また、そんな秘密があるこの世界には、何故死という人生の締めくくりがあるのでしょう。
不老不死を求める人がいるように、死なないで生き続けることは、多くの人にとって魅了です。
不老不死であれば、いろんなことができるでしょうに、どうして生きるものは、死を迎えるのでしょうか。

向こうの世界から、こちらの世界に生まれて来るのは、この世界で何かを体験するためでしょう。
人生に死があって、その人生に区切りをつけるのは、同じ人生を長く続けても、得られない体験があるからではないでしょうか。
たとえば、不老不死の男性に生まれたとしましょう。
不老不死ですから、この人はずっと男性です。
女性の体験はできませんから、女性がどんなものかを、主観的に理解することはできません。
やはり死んで男性の人生に終止符を打ち、女性に生まれ変わる必要がありますね。
同じように、様々な人生を体験するためには、一つの人生を長く続けても、仕方がないのです。
ですから、死があるのでしょう。
思いがけない死、突然の死、あまりにも短い人生、何のために生まれて来たのか、わからないような悲惨な人生。
そんなのも全部、一つの体験です。
また、同じような体験をしても、そこでどのように反応するかは、人それぞれです。
ある体験の中で、どんな判断をし、どのような行動を取るのか。
それもまた、それぞれが一つの体験なのです。
人間社会の中にある善悪の価値観では、わからない価値観が、向こうの世界にはあるのでしょう。

死について考えることが、生きることにつながり、今度はこの世界を超えた、向こうの世界にまで、視点が広がりました。
私たちは、そのような壮大な世界の中に存在し、生きているのです。
ですから、人間社会で作られた規則や、価値観で生きるのではなく、もっと大きな自分なりの考えで、生きる道を進めばいいのです。
普通は、死は不吉の象徴です。
しかし、その死についてよく考えれば、こうした世界観を手に入れられるのです。
そして、この新たな世界観を得られたならば、もはや死は不吉の象徴では、なくなっているはずです。
死について考える その2
死を理解するためには、生きるということを、理解しなくてはなりません。
生きるということは、存在しているということです。
私たちの存在について考えると、私たちの本質は心なのだとわかるでしょう。
つまり、死を理解するためには、心というものについて、考える必要があるのです。
科学の世界では、心は物質エネルギーではないと、考えています。
科学は物質エネルギーを対象としているため、心は対象外になるわけです。
そのため、心について考えるとなると、宗教か哲学、心理学、病院の精神科や心療内科などが、専門と見られるのですが、すっきりした答えは出せないようです。
それでも、私たちは存在しています。
学者が何と言おうと、私たちの心は実在しているのです。
そもそも心がなければ、学問もへったくれもないでしょう。

心が物質エネルギーに属さないのであれば、世界には物質エネルギーとは別の側面があるということです。
つまり、心が属するエネルギー形態が、あるはずなのです。
物質の世界では、電磁力の力によって成立しています。
そのため、空間に広がる電磁力の影響を、電磁場と呼んでいます。
原子の中心にある原子核は、プラスの電荷を帯びており、その周囲にある電子は、マイナスの電荷を帯びています。
原子の構成には電磁場が作用しており、世界は電磁場によって造られていると言えるでしょう。
同じように、心を構成する場があるはずで、私はそれを精神場と呼んでいます。
人間や他の生き物たちは、電磁場と精神場の双方が干渉し合うことによって、物質的肉体を伴って生きているのだと思います。
死ぬということは、肉体から意識が消えることです。
これは電磁場と精神場との干渉が、終了したということです。
死後の肉体は、腐敗して崩壊してしまいます。
では、死後の意識は、やはり崩壊してしまうのでしょうか。
崩壊するのであれば、その人の心は失われ、その人の存在は消え去ったと言えます。
崩壊しないのであれば、その人は肉体の死後も、精神場の世界で存在し続けると考えられます。
ここで、幽霊の存在がポイントになります。

幽霊は肉体が失われたのに、その人の意識が存在している証です。
死んでも、心が失われるわけではないということですね。
しかし、全ての人が幽霊になるわけではありません。
幽霊として現れる人は、大体が未練があったり、恨みや悲しみを抱えて、この世界にしがみついているように思えます。
幽霊にならなかった人たちは、この世界を離れ、精神場の中にある、別の世界へ移行するのでしょう。
体外離脱の体験や、前世の記憶というものが報告されています。
そういうものも心と体が別物で、肉体の死後も心が存続するということを、示しています。
肉体は目で見えますが、心は見ることができません。
そのため、死について考える時、目で見ることができる肉体を基準にして、理解しようとします。
しかし、心を基準にして死を考えると、死についてのイメージが、大きく変わると思います。
死とは、一つの肉体を介した人生体験を、終了するということです。
今の人生を終えたとしても、それで自分が終わるわけではないのです。
肉体の死後も、私たちの存在そのものは、ずっと残っているのです。
それを理解すれば、自分が消滅するという、恐怖はなくなるでしょう。
でも、死後に体験するであろう、死後の世界を考えると、やはり怖くなるかもしれませんね。
死について考える その1

あなたは「死」をどのように、とらえているのでしょうか。
怖いけど、考えてもわからないから、考えませんか?
そう言わないで、考えてみて下さい。
「死」とは何でしょう?
自分が消滅してしまうこと?
魂が肉体を離れて、あの世へ行くことですか?
脳が活動できなくなることでしょうか?

死ぬと言うと、死神が迎えに来るという、イメージがありますよね。
これは魂が肉体を離れて、あの世へ行くという考え方に基づいています。
死神というのは、大概が骸骨か、あるいは頭巾を被った闇として、描かれています。
それは不吉という意味を象徴しているのでしょう。
つまり、死とは不吉なものという認識なのです。
魂があると考えるかどうかに関わらず、人生がそこで終わってしまいますから、不吉なものととらえてしまうのでしょうね。
でも、このような死神は西洋的です。
日本人の場合、先に亡くなった家族や親戚、知人などが迎えに来るという、イメージが多いような気がします。
この場合は、死は不吉ではありません。
残された者にとっては、悲しいことですが、亡くなる人にとっては、喜びなのです。
この世が嫌になって、自ら命を絶ってしまう人たちにとって、死とはどんなものなのでしょうか。
恐ろしいものや、不吉なものと見なしていれば、わざわざ自分から、そんな所に飛び込むようなことはしないでしょう。
でも、喜びの場所として、死を見ているわけではなさそうです。
自ら死を選ぶ人たちにとって、この世界こそが恐ろしい所であり、不吉な所なのでしょう。
ただ、死というものがわかった上で、死ぬとは思えません。
恐らく、この世界から逃げ出したい、この世界から逃れられるのであれば、自分が消滅しても構わないという気持ちで、死んでしまうのだと思います。
このように、人によって「死」というものの、とらえ方は様々です。
でも、死ぬということを、本当に理解あるいは納得している人は、それほど多くないのではないでしょうか。

死というものについて考えていなくても、 穏やかな死を迎える人はいらっしゃいます。
そういう方は、自分の人生を受け入れているのだと思います。
死は人生の終末ですから、人生の一部でもあるわけです。
ですから、自分の人生を受け入れられる人は、自分の死も受け入れられるのです。
でも、こういう方が元気でいる間から、自分の人生を納得して、受け入れていたかはわかりません。
ずっと、死ぬことを恐れ続けていたのが、もう死ぬのは避けられないと悟ってから、受け入れられるようになる、ということも少なくないと思います。
また、本人は死を受け入れているのに、家族や病院が死を否定して拒むために、無益な治療を続けて、本人が苦しみ続けるということもあるでしょう。
死というものについて考えることは、自分だけの問題ではなく、他の人の人生に、どう向き合うかということにも、関係するのです。
死を受け入れるということは、人生を受け入れるということです。
それは自分の人生だけでなく、他人の人生についても、言えるのです。
誰かが亡くなった時、その人の死を悲しむだけでは、その人の人生を受け入れていない、ということになります。
つまり、その人の人生を否定することになるのですね。
どんな人生でも、ちゃんと意味がある、価値があると受け止めていれば、悲しいことばかりでなく、楽しいことや、よかったことも思い出すでしょう。
別れを悲しむことと、その人の人生をどう受け止めるかということを、きちんと分けることができるのです。

死について考える時、二つの見方があると思います。
一つは、その人がどういう人生を送ったのか、ということです。
死とは人生の終わりであり、人生の一部 です。
死を、人生から切り離して考えることはできません。
死は、人生という学校を離れることであり、本人にしても周囲の人々にしても、その人の人生を振り返る時なのですね。
もう一つの見方は、素朴な疑問として、死とは何なのか、ということです。
生きている者が存在しなくなる、ということが、生きている者には、想像しがたいのです。
また、そんな死が、いつか必ず誰にでも訪れる、という事実が怖いのですね。
しかし、死が何かと考えても、よくわからないというのが実情でしょう。
わかっているのは、死というものが、生きられなくなるということです。
と言うことは、生きるということを理解すれば、死というものの正体が、見えて来るわけです。
生きているということは、存在しているということですね。
自分という存在を考えた時、初めに浮かぶのは、自分の体でしょう。
でも、深く考えると、自分というのは、体ではなく心なのだと理解できると思います。

私たちの本質は心であり、心は物質では説明ができません。
脳の活動に伴う現象だと述べる学者もいますが、それでは説明になっていません。
美しい夕日は、太陽の光と地球の大気が、織りなす現象です。
夕日は光であり、光は物質エネルギーの一部です。
しかし、心は物質エネルギーの範疇には入っていません。
心が脳細胞の活動によって生じる、微弱な電流だと言うのであれば、説明していることになります。
でも、心と電流は別物と見なされていますから、心を脳活動による現象とは言えないのです。
この科学でもよくわかっていない、心について考えることが、生きるということについて、考えることなのです。
そして、それは間接的ではありますが、死について考えることにもなるのです。
ちょっと不思議なこと
昨日、ちょっと不思議な体験をしました。
義母のガラケー携帯をスマホに変える手続きのため、私と家内が義母に連れ添って、携帯電話の店へ行ったのですが、その時の話です。
身分証明として、お店の人に見せた義母の健康保険証が、どこかへ消えてしまったのです。
ついさっき手にしていたのに、どこにもありません。
カウンターの上も鞄の中も、全部調べたのに、どこにも見つからないのです。
その時に、家内が手に持った、小さく折りたたんだ買い物袋が、ポロリと下に落ちたのです。
家内がそれを拾おうとして、椅子の下に手を伸ばしたら……
あったのです。
そこに健康保険証が、落ちていたのです。
私も家内も、その袋が健康保険証の場所を教えるために、手から落ちたように思いました。
そんなのは、ただの偶然だとか、こじつけだと思われる人はいるでしょう。
でも、逆に言えば、普段身の回りで起きている些細な不思議を、不思議として受け入れない習慣が、身についている人が多いのではないでしょうか。
こういうことは、案外起きているものだと思うのですが、ほとんどの人が、その不思議さを無視しているような気がします。
義父母のために動いている時には、こんなことが時々あるのです。
山の中の温泉に行った時、風呂から上がると、外は土砂降りの雨。
空は分厚い雲に覆われて、日が差す兆しはまったくなし。
義父母は足腰が悪いため、早くは動けません。
建物を出て、車に乗るまでの間に、絶対に濡れてしまう状況でした。
でも、いつまでもそこにいるわけには行かず、意を決して車へ移動しようとしたら、不思議なことに建物の外に出た途端、雨が止んだのですね。
青空が出たわけではありません。
どんよりした雲は、そのままです。
それなのに、雨がぴたりとやんだのです。
喜んでみんなが車に乗り込み、移動を始めると、再び大雨になりました。
何とも、不思議なことがあるものだと、その時にも思ったものです。
また、こんなこともありました。
今年の春先に、義父母が使っていたホットカーペットが、壊れて使えなくなったのです。
まだ寒い日が続くので、ホットカーペットは必要だったのですが、もう春が来る頃だったので、電気店にはホットカーペットなんか置いていません。
春に向けての商品の入れ替えだったので、どの店にも在庫がなかったのです。
それでも、あきらめずにあちこちの店を回っていると、あったのです。
それも、私たちが考えていたような、希望の品が。
絶対にないと思っていたのですが、たった一つだけ残っており、在庫処分で定価よりも安くなっていました。
その値段が五万円。
安いとは言っても、臨時の出費ですから、かなりの痛手です。
でも、どうしても必要なものでしたから、五万円を出して購入しました。
ないと思っていた物が手に入ったので、私たちも嬉しかったし、義父母も喜んでくれました。
翌日、銀行の通帳を記帳してみると、正体不明の五万円が、会社から振り込まれていたのです。
これには驚き、何かの間違いだと思って、会社で確かめてみると、コロナの影響で従業員の暮らしが大変だろうからと、みんなに一律五万円を配ったと言うではありませんか。
そんなこと、これまで一度もしてもらったことは、ありませんでした。
何といい会社だろうと、会社に感謝しながらも、このタイミングには、やはりとても驚きました。
こんな感じで、義父母のために動いていると、ちょっとした不思議なことがあるのですね。
そのこと自体が、不思議なのですが、みなさんにも同じようなことが、あるのではないでしょうか。
何かいいことがあった時、単にラッキーと言って済ませるのではなく、それが不思議なことでないのか、確かめてみるといいと思います。

