ロボット義足
足がない人のために、義足というものがあります。
しかし、義足は本物の足の代替品であり、決して本物にはなり得ません。
パラリンピック選手が、義足で走る姿を見ていると、まるで本物の足で走っているように見えます。
選手があのように走れるのは、義足の質の向上はもちろんですが、一番は選手の努力の結果でしょう。
一般の方が通常の義足を、本物の足のように使いこなすのは、それほど簡単なものではないと思います。
本物の足のような感覚は、義足からは伝わって来ません。
義足を装着した人は、体の欠損していない部分の感覚や、筋肉の動きで、義足を操作しないといけないのです。
恐らく、これは大変な労力であると思われます。
また、生まれつき両足が欠損している人は、歩いたことがありませんから、義足をつけて歩くというのは、相当大変なことでしょう。
今回記事に出ていたのは、五体不満足で有名な乙武洋匡さんが、被験者となったロボット義足です。
義足にAIと軽量モーターが装備されており、乙武さんの動きに合わせて、自動的に義足が動くというものです。
乙武さんは生まれつき、両腕両脚が欠損した状態なので、自分の足で歩くという経験がありません。
その乙武さんがこのロボット義足を使って、66.2メートルを歩くことができました。
これは実にすごいことで、乙武さんも胸が一杯ですと、感激していました。
ロボット義足を研究されている遠藤さんは、「究極は障害がなくなるくらいの技術が、世の中にいっぱいあふれていればいいな」と述べられています。
本当に素晴らしい発想です。
このような考えが、技術の向上の基盤となることは、よりよい社会の発展には欠かせません。
同じ技術の向上を目指すのでも、いかに自分は傷つかずに、相手を大量に殺傷できる、兵器を開発するのか、という人たちとは真逆のものです。
彼らとは別世界、別次元の存在とさえ言えるでしょう。
ただ、遠藤さんのような方たちを、見習わなければならない、これからの社会は、こうでなければならない、と考えてしまってはいけません。
物事を義務的に考えてしまうと、せっかくいいことをしていても、心の籠もったことはできません。
そうではなく、誰かの笑顔を喜びとして行動する、ということが大切です。
お金を稼ぐことや、人々に注目されること、などを目的にするのではなく、自分が本当に興味を持てることに、夢中になることが一番です。
そこに、自分がしていることで、誰かが喜んでくれれば嬉しい、という気持ちを加えるのです。
実際に誰が喜んでくれているのか、わからなくても構いません。
絶対に誰かが喜んでくれるという、確信を持って、自分が目指すものに没頭するのです。
みんながそうすることで、何の偽りもない、互いを思いやれる楽しい社会が、実現するのです。
分身ロボ
分身ロボという記事を見つけました。
どういうものかと言うと、自分では自由に動けない人が、遠隔操作で自分の代わりのロボットを、動かすというものです。
記事で紹介されていたのは、「お笑い芸人界で初の寝たきり障害者」を名乗る、熊本県在住のあそどっぐさんです。
あそどっぐさんは脊髄性筋萎縮症により、顔と左手親指以外は動かせない状態だそうですが、お笑い芸人の道を歩んでいるという、とてもパワフルな方です。
それだけでも、人々を熱くさせているあそどっぐさんですが、生まれて初めてのアルバイトを、分身ロボを使って体験しました。
熊本に暮らすあそどっぐさんは、この分身ロボを使って、東京のカフェで働いています。
分身ロボの名は「Orihime(オリヒメ)」。
身長は約120cmで、カメラとスピーカーが内蔵されており、あそどっぐさんのパソコンの画面には、オリヒメのカメラの映像が映し出されます。
仕事はお客が注文した品を、テーブルへ届けることですが、お客と談笑することもできます。
このカフェはオリヒメを開発した、オリィ研究所が常設の実験店として、今年6月にオープンしたと言います。
カフェの名は「分身ロボットカフェDAWN ver.β(ドーン バージョンベータ)」だそうです。
重度障害で寝たきりの人や、子育てや介護で外出が難しい人など、約60人がオリヒメの操作者として働いているそうです。
オリヒメを利用している人たちからの評判もよく、体の自由が制限されている人たちの、新たな活動手段として、大きく脚光を浴びています。
いずれ分身ロボの動きや機能は、もっと優れたものになり、今以上のことが、苦もなく行えるようになるでしょう。
動けない人が分身ロボを使って、山登りをしたり、スポーツを楽しんだり、旅行にでかけたりできるようになると思います。
オリィ研究所の吉藤オリィ所長は、自身の不登校の経験から、孤独の解消を開発目標に掲げておられるそうです。
テクノロジーによって社会とのつながりを創り、分身ロボを使って、離れていても一緒に何かできる仕組みを増やしたいというのが、吉藤オリィ所長の考えです。
動けなくても、自分の意思でロボットを動かし、人や社会の役に立つことが、生きる理由になると、所長は語ります
実際、多くの人が分身ロボにより、生き甲斐を見つけていらっしゃいます。
自分では動けないことを苦にして、自殺を望む方がいます。
その自殺をどう見るのか、また、その自殺をほう助することが罪なのか、などという議論もあります。
でも、そういうことの是非を問うのではなく、オリィ所長のような発想で、本当の問題の解決へ手を差し伸べることが、求められるべきでしょう。
寝たきり障害者を自認するあそどっぐさん、分身ロボを考案した吉藤オリィ所長、そして彼らに賛同して支えようとする人々や、分身ロボを活用して新たな道を切り開く人たち。
一見、ばらばらにいる人たちが、分身ロボを介して集まっているように見えます。
しかし本当は、今の人間社会を変えるために、それぞれが役目を分担しながら、チームとしてこの世界に産まれて来たのではないかと、見えてしまいます。
記事を読んでいると、胸が熱くなり、社会が大きく変化しようとしているのが、ひしひしと伝わって来るように感じます。
みんな、自分のことを一生懸命しているだけなのでしょうが、自分が知らないところで、目に見えない糸で、つながっているのでしょう。
それは彼らだけでなく、あなたや私にも言えることだと思います。
自分が一人で活動しているようでも、きっと見えないつながりを持った人たちが、あちこちで自分でも気づかないまま、互いを支え合って、人々の意識を変えようとしているのです。
空一面に広がっていた、どんよりした雲に、小さな切れ間ができて、そこから一条の光が差し込んでいるイメージです。
やがて、全体の雲は薄くなり、あちこちに同じような切れ間ができて、そこら中に光が差し込んで行く。
いずれ雲は全てなくなり、清々しい青空が一杯に広がるのが、はっきりとわかっている。
そんな情景が目に浮かびます。
いいですね。
本当に素敵な記事でした。
伊予の狸話 その2
神通力を持つ狸の中に、有名な刑部狸(ぎょうぶだぬき)がいます。
ゲゲゲの鬼太郎にも登場する、とても強い妖怪です。
私が愛媛で暮らすようになってから、その刑部狸が愛媛県にいたと知り、私はとても驚きました。
愛媛県って、そんなにすごい所だったんだ、と思うほど、私にとって刑部狸の印象は、とても強いものでした。
刑部狸の始まりは、江戸時代に実際にあった、松山のお家騒動だそうです。
それは奥平貞継と奥平久兵衛の、二人の家老の権力争いだったのですが、まずは貞継が勝利して、久兵衛が隠居を命じられました。
しかし、西日本一帯を襲った享保の大飢饉で、松山は最多の3500人という死者を出し、責任を問われた貞継は久万山に蟄居を命じられ、隠居していた久兵衛が家老に復活します。
実験を握ったはずの久兵衛ですが、今度は久万山騒動という、百姓の大規模な逃散が起こりました。
その原因は、飢饉による痛手が回復していない、百姓への厳しい年貢の取り立てなどが原因でした。
そして、久兵衛はその責任を問われて、再び権力を失い、蟄居していた貞継が復活します。
こんなどっちもどっちと言うようなドタバタ騒ぎに、刑部狸や妖怪退治の豪傑が絡めた、松山騒動八百八狸物語という講談話が創られました。
これが刑部狸の始まりで、松山騒動八百八狸物語では、久兵衛が悪役として描かれています。
話では、刑部狸は元々お城を守る立場の狸だったのですが、悪役の久兵衛にうまく味方に引き込まれ、悪役を手助けする役目を負ってしまいます。
その結果、正義の忠義侍が味方につけた、豪傑稲生武太夫に負けてしまい、久万山の狭い洞窟の中に、封じ込められてしまうのです。
ちなみに、この稲生武太夫とは、広島に実在した人物で、若い頃に数多くの妖怪を相手にしても、ひるむことがなかったという話が伝わっています。
さて、この講談話に出て来た刑部狸ですが、久万山の麓に、本当に刑部狸を祀った所があるんですね。

これは山口霊神という、実は刑部狸とは関係のない神さまの祠なのですが、何故かここに刑部狸が祀られているのです。
そもそも山口霊神が何の神さまなのかはわからないそうで、今では刑部狸の祠という印象の方が、強いみたいですね。
元々地元にあった話でもないのに、いつの間にか物語の狸が、ここで祀られているなんて、面白いですよね。
実際は空想の物語が、あたかも本当にあったかのように思わせる光景ですが、恐らく講談話を聞いた昔の人で、それが本当の話だと信じた人が、いたのかもしれません。
その人にとっては、空想話も現実となり、その人は空想と現実が入り交じった世界を、生きていたということなのでしょう。
でも、それは今の世の中でも、同じことが言えるかもしれません。
資本主義経済が絶対であるというのも、一種の空想に過ぎません。
現実は夢とは違うというのも、一種の空想でしょう。
違うという根拠は、どこにもないのです。
空想する中身は、今と昔で違っても、やっていることは案外同じなのかもしれませんね。
伊予の狸話 その1
四国には狐が見られず、一方で狸はよく見かけます。
そのため、四国には狸にまつわる話が多いです。
今日は、その中の一つ、松山のお袖ダヌキをご紹介します。
松山市の街の中心部には、松山城のお堀があります。
そのお堀の東側と南側の角の部分に、大きな榎が生えていて、その根元には狸を祀った祠があります。
ここに祀られている狸が、お袖ダヌキです。
その場所は、松山市役所の目の前で、路面電車や多くの車が往来する騒々しい所です。
そんな所にひっそりと、ほとんどの人に気づかれないまま、お袖ダヌキの祠はあるのです。



さて、このお袖ダヌキですが、江戸時代にお城がそびえる山から、この場所に移住して来たそうです。
昔、この辺りは榎が多く茂っていたそうで、今の市役所前の通りは榎町通りと呼ばれていました。
榎を住処をしたお袖ダヌキは、榎の上から通行人を眺めるのが、楽しみだったと言います。
また、道祖神に成りすまして、神通力で人々の願いを叶えたことから、多くの人に崇拝されるようになったとか。
このお袖ダヌキが棲む大榎は、これまでに何度か切られたり、植え替えられたりして、今の榎は明治の初めから数えて、四代目の榎だそうです。
住処である榎を切られるたびに、お袖ダヌキは他の地へ引っ越しをし、またいつの間にか元の所へ戻って来るということを、繰り返していたようです。


とても目立つ場所にありながら、案外知る人が少ない、お袖ダヌキ。
松山の隠れた観光スポットと言えるでしょう。
でも、これは人間の才能にも、似ていますよね。
すごい才能があるのに、本人も含めて周囲の人が気がつかない。
しかし、知っている人は知っている、ですね。
見る人が見れば、その才能がどれだけすごいのかは、一目瞭然です。
きっと、あなたにもお袖ダヌキのような、隠れた才能がありますよ。
終活と断捨離

終活という言葉をご存知でしょうか。
人生の終わりのための活動ということだそうですが、発音だけを聞いていると、就職活動の就活と間違えそうですね。
最近は〇〇活という言葉が流行で、終活もその流れでできた言葉です。
こんな言葉は、昔は聞いたことがありませんでした。
こうした流行言葉を使われると、やろうとしていることの内容に関係なく、とても軽くて希薄な印象を持ってしまいます。
とは言っても、いつ自分が死ぬかわからないので、身辺整理をしておくというのは、悪いことではありません。
身内が亡くなる時、葬儀だけで済めばいいのですが、財産や遺品整理、お墓のこと、保険の手続き、クレジットカードの解約など、やることは山積みです。
それらをするのは亡くなった本人ではなく、残された遺族ですから、遺族に負担をかけないと考えれば、自分が生きているうちに、身辺整理をという考えに至るのでしょう。
ただ、身辺整理をしたところで、自分がすぐに死ぬとは限りません。
きれいさっぱりした所で、思わぬ新たな人生を、踏み出すことになるかもしれないのです。

いろんな物を整理したことで、自分を抑えていた、様々なしがらみが一掃されれば、自由な気分になると思います。
そうなると、それまでとは全く違う、自分というものが見えて来るでしょう。
それは素直な自分、本当の自分です。
本当はこんなことがしたかった。
本当はこんな自分でいたかった。
そんな自分が表に出て来やすくなるでしょうから、終活も悪いことではないと思います。
ただ、せっかく出て来た素の自分を、そんなこと言ったってねぇ、と抑えてしまうと、終活はただの儀式になってしまいます。
重い病気にかかっていて、この世を離れる日が遠くない人の場合は、仕方がありません。
また次の人生で、がんばりましょうという話です。
でも、まだ元気なのに身辺整理をした人が、自分の気持ちを抑え込んだのでは、却って全てを捨ててしまったという後悔の下で、生き続けることになるかもしれません。

終活というのは一種の断捨離で、今後の自分にとって、余計な物を整理するということだと思います。
その先に死が待ち受けていようと、生が続こうと同じことです。
さらに言えば、普段から断捨離や終活を行わなくてもいいような、すっきりした暮らしを心掛けるのがいいと思います。
長く生きていると、いろんなものが付着して来ます。
その時は、それが大事なことのように、感じてしまうのですが、本来の自分に立ち返って見てみると、別に大切でないと気がつくのです。
断捨離や終活で、様々な物を手放す時に、何が捨てられて、何が捨てられないのか、自分の心の整理ができるでしょう。
自分が何を大切にしているのかが、はっきりして来ると、自分の人生がどれだけ残されているのかに関係なく、自分のあり方がわかるでしょう。
元気なうちに行う断捨離は、ある意味、それまでの自分に別れを告げる、終活だとみることができます。
つまり、終活とは新しいステージへ向かうための、準備ということですね。

無駄な物を捨てる断捨離と、次のステージへ向かうための終活。
この二つを人生にうまく取り込めば、自分が望んでいた人生に、進んで行けると思います。
他人は教師

ご存知のように、人間はいろいろです。
いい人もいれば、悪い人もいます。
神経質な人もいれば、大雑把な人もいます。
気遣いができる人もいれば、気遣いができない人もいます。
性別の違い、趣向の違い、宗教の違い、民族の違い。
いろんな違いがあり、それがそれぞれの個性になっています。
双子と言えども別人です。
同じ人間というものは、存在しません。
人生は人間の数だけあるわけで、自分一人の人生では、とても体験できないことや、理解できないことを、他の人々が代わりに、体験してくれていると見て下さい。

楽しい人生、苦しい人生、いろいろありますね。
楽しい人生を送っている人は、どうして楽しく過ごせるのか、本当に楽しいのか。
苦しい人生を送っている人は、どうして苦しんでいるのか、本当に苦しみしかないのか。
本人ではわからないかもしれないことを、他人の目で見るからこそ、わかるということはあります。
人生は学びですが、他人の人生からも、多くのことが学べます。
他人は身を持って様々なことを、教えてくれている教師なのです。
人の生き様から何かを学んだなら、それを自分の人生に適応させることができます。
逆に言えば、適応させられない学びは、学びとは言えません。
せっかく多くの人が、いろんな人生を示してくれているのに、そこから何も学べないのであれば、もったいない話です。

悲惨な状況から立ち上がる人を見れば、困難な状況に陥った時に、これしきのことでへこたれるもんかと、強い気持ちを持てるでしょう。
一人では上手く行かないことも、チームで立ち向かえば、上手く行くという経験を見せられれば、自分も仲間が欲しくなるでしょう。
お金よりも大切なものがあると教えてもらえば、生きる目的が見えて来るでしょう。
何故、争いや苦しみから逃げられないのかを、考えさせられれば、自分はそのような状況にならないよう、気をつけることができるでしょう。
死ぬことを恐れるのではなく、いかに生きるかが大切だと示されれば、それまでとは生き方が変わるでしょう。
みんな、自分が他人への教師になっているとは、思っていません。
自分の人生を一所懸命に生きているだけです。
しかし、だからこそ他人への教師になるのです。
それは、あなたにも言えることです。
あなたもまた、自分で意識をしないまま、誰かにとっての教師になっているのです。
こんなことをすれば大変だぞ、と教える教師も必要ですから、あなたの人生が上手く行っていなくても、そこから学びを与えることはできます。
しかし、こうすれば上手く行くぞ、と教えられる教師になる方が、教師の質としては高まるでしょうし、あなた自身が楽しく過ごせます。
そのためにも、他の人たちから学ばせてもらったことを、自分の人生に活かして下さい。
困難な時こそ
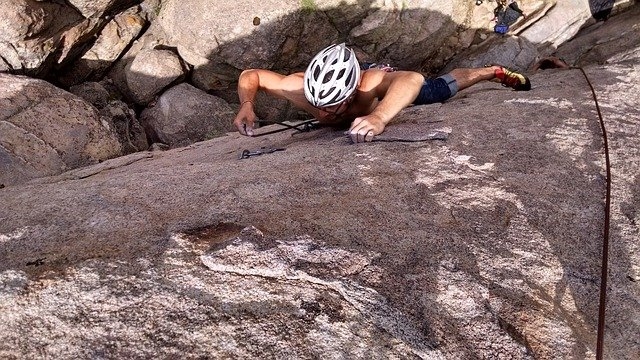
人生に困難はつきものです。
突然起こった出来事によって、それまでとは全く違う暮らしを、強いられる。
慢性的に動きにくい状況にあり、将来に希望を持てない。
困難な状況の起こり方は、さまざまですが、それを乗り越えて行かねばならないのは、いずれも同じです。
困難を乗り越えるのは大変です。
大変でなければ、困難とは言いません。
でも、困難は必ず乗り越えることができます。
それができないと感じる時、その原因は思い込みです。
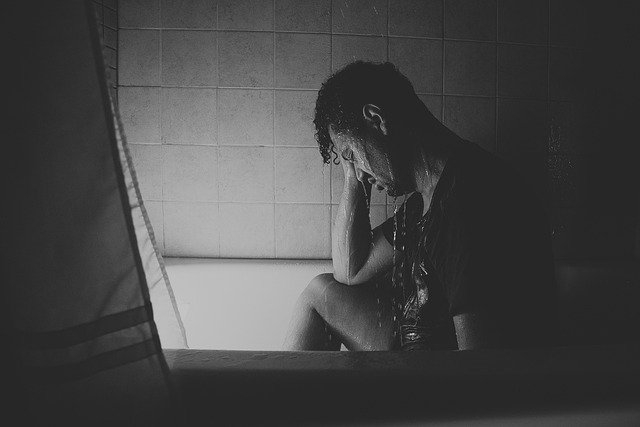
自分には何もできない。
自分はこのまま終わるんだ。
自分なんか、この程度の人間だ。
こんな風に思い込んでいると、それこそ何もできません。
自分が動きを止めたら、本当にそこまでになってしまいます。
だって、自分はこれだけいろいろやったのに、それでもだめだった。
何人にも相談したけど、誰も助けてくれない。
世の中なんて、こんなものだから、何をしたって無駄だ。
こんな言い訳が聞こえて来そうですが、はっきり言って、こういう言葉を使う人は、傲慢だと思います。
自分はいろいろやったつもりかもしれませんが、世の中の全てを、知っているわけではありません。
それなのに、まるで全てを知っているような言い草は、傲慢そのものです。
それは、自分が敗者だと認める代わりに、悟りの境地を手に入れたという、気分なのでしょう。
でも、それでは何の解決にもなりませんし、不満だらけの暮らしが続くだけです。
嫌な暮らしから抜け出したいのであれば、どんなに上手く行かない状況にあっても、自分は全ての道を探ったわけではないと、謙虚な気持ちにならなければいけません。
それと、できないことへの不満よりも、こんな状況の中でも、こんなことはできるんだと、ポジティブな気持ちを持つことが大切です。
それは発見であり、感謝です。
この気持ちこそが、新しい道を見つけるための鍵なのです。

文句ばかり言っている人には、目の前に道があっても見えません。
また、そもそも自分が何をしたいのか、何を求めているのかを、はっきりさせましょう。
そうでなければ、本当の不満が何なのかが、よくわかりません。
単に、人がやっていることを、自分もしたいだけであれば、上手く行かないかもしれません。
それは本気の思いではないからです。
他人の真似、他人の価値観を、追い求めていたのでは、道は開けません。
本当に自分がそれをやりたいのだという、強い思いがあってこそ、道は開かれます。
本当に自分が何をやりたいのか、それを見極めるためにも、ちょっとしたことへの発見と感謝の気持ちが、やはり鍵になります。
発見と感謝は、心に喜びを生みます。
本当に自分がやりたいことは、心を喜びで満たしてくれます。
ですから、発見と感謝によって、何が自分の心に喜びを満たしてくれるのかが、明らかになって来るのです。
感謝の気持ちを忘れ、文句ばかりを口にしていても、困難を乗り越えることはできません。
体の声を聴こう
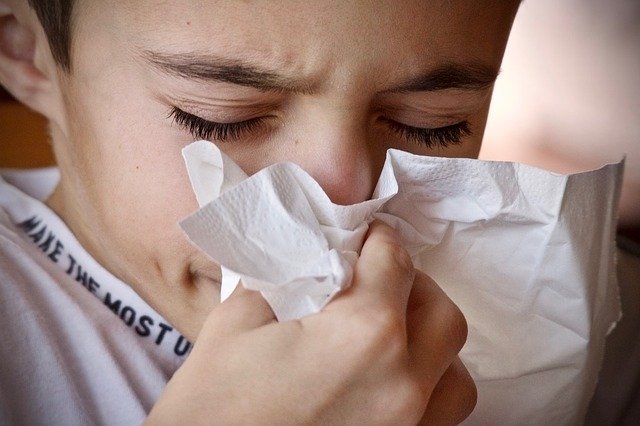
体の不調を感じることは、誰でもあります。
体は病気になるためにあるのでは、ありません。
体が本来あるべき姿であるのなら、病気になどなりません。
体に不調を感じるということは、体の本来の働きを、邪魔するものがあるということなのです。
体は、ここが悪いから、こうして欲しいと、言葉で訴えたりはしません。
その代わり、痛いとか、だるいとか、熱があるとか、咳が出るとか、湿疹が出るとか、症状という形で、不調を訴えます。
ところが、大抵の場合、体の声である症状にばかり、気を取られて、体が本当に求めていることには、気がつきません。
症状を抑える薬を飲んで、体を黙らせようとするのです。

具合が悪い時は、じっとしていることが多いので、それが体調を整えるために、プラスに働きます。
でも、それで何とか体調が戻ると、また元の状態に戻って、同じ生活パターンを繰り返すのです。
体にとってよくない環境でも、体も次第に慣れて来て、余程のことでなければ、悲鳴を上げなくなります。
でも、それは体が強くなったわけではありません。
悲鳴を上げなくなっただけのことです。
体がこの次に悲鳴を上げる時には、体のダメージがかなり進んだ状態でしょう。
でも、体が悲鳴を上げずに、がんばっていたから、何がダメージの原因なのかが、わかりません。

何も悪いことはしていないのに、普通に暮らしていただけなのに、どうして自分だけが、こんな病気になってしまうのか。
そんな風に怒りを覚えることでしょう。
でも、原因なく体は病気になったりはしません。
自分の日常生活の中に、本当に体に悪いことはなかったのか、検証してみる必要があるでしょう。
それは、睡眠や運動、食事の問題かもしれませんが、精神的ストレスも、体の機能を大きく損なう原因です。
特別嫌なことがなかったとしても、活き活きした暮らしをしていなければ、それがストレスになっている可能性があります。
心身ともに、活気ある健全な暮らしができているのか。
充実した日々を送れているのか。
何ともないように思っているけど、本当に体は不調を感じていないのか。
少々疲れても、若いから平気だとか、こんなのいつものことだから、という感じで、体の声を聞き逃していると、あとで大変なことになるかもしれません。
今、何をしてますか

今、あなたは何をしているでしょうか。
仕事ですか。
それとも家事?
年老いた親の世話でしょうか。
あるいは、小さな子供の面倒を見ていますか。
どれもが自分にとって、やらなくてはいけない事のように思えますよね。
でも、もし明日、自分が死ぬとわかっていたら、同じことをするのでしょうか。
自分が死ぬとわかっていても、それでもやろうとするのであれば、それは本当に大切なことなのでしょう。
しかし、明日死ぬというのに、こんなことしていられるか、と思うようなことであれば、それほど大切ではないということです。
また、自分の命が明日までだとなった時、ああしておけばよかったとか、こんなことがやりたかったと、いろいろ後悔の念がよぎると思います。

まさか、明日死ぬとは思っていなかった。
まだ、あとでも大丈夫だと思っていた。
こんな感じで、ずるずるとやりたい事を、後回しにしてしまうことは、結構あるのではないでしょうか。
実際、人の死なんてわからないものです。
大病を患った人を気の毒がっていた人が、交通事故で先に死ぬかもしれません。
いつもと同じように、家を出た人が、戻って来た時には、物言わぬ姿になっているかもしれないのです。
未来予知ができないのであれば、突然の死がいつ自分に訪れるかもしれないと、常に覚悟をしておく必要があるでしょう。
その覚悟ができていれば、何を先にするべきなのか、という優先順位がはっきりします。
いつ自分が死ぬことになっても、後悔しないでいいように、日常の暮らしを考えるでしょう。
今、自分がしていることは、本当に自分に必要なことなのか。
それは自分が、やりたいと思っていることなのか。
それは自分が、大切に思っていることなのか。
誰かを大切に思うのであれば、喧嘩をしたまま突然の別れにならないよう、普段の言葉遣いや、接し方を考えると思います。
感謝をしているのに、その気持ちを伝えないまま、死ぬことにならないよう、日頃から感謝の言葉を、素直に口にするようになるでしょう。
自分がまだ生きている、今という瞬間は、とても貴重です。
その今をどう使うのか。
一度、じっくり考えてみて下さい。
不思議な夢
先日、古い知人が大きな車でやって来て、私に40万円をくれる夢を見ました。
何年も会っておらず、今どうしているのかさえ、わからない人です。
それなのに突然現れて、ぽんと札束をくれたのです。
こんなものは受け取れないと言ったのですが、私に世話になったからと言うんですね。
それで、結局もらうことにしたのですが、目が覚めたあとで、あれは何の夢だったのだろうかと、考えました。
いわゆる正夢として、その知人が現れて、お金をくれるという状況が、訪れるとは思えません。
その人は私の家を知りませんし、お金をもらう理由がないからです。
そこで、自分なりに夢を解釈したのですが、その知人の登場は、思いがけない人物が、思いがけない時に、思いがけないことをする、という意味だと考えました。
もちろん、思いがけないことをするというのは、私に対して好意的なもので、夢が示すように、金銭的なことが起こる、ということかもしれません。
それにしても、突然お金が手に入るという状況は、宝くじに当たりでもしなければ、有り得ない話です。
もちろん、宝くじなど買っていませんし、今は買おうかとも思っていません。
それに、何故40万円なのか。
切りがいい数字で考えれば、100万円でもいいのに、何故40万円なのでしょうか。
何だか中途半端な金額ですが、それにしても大金です。
普段の収入以外で、私が手に入れられるお金と言うと、今月の給料に加算される、半年ごとの交通費ぐらいです。
それが10万円ほどなのですが、あと30万円足りません。
結局、よくわからないまま、何日かが過ぎたところ、急にまとまったお金が入り用になりました。
余分に使えるお金と言えば、その交通費の10万円ぐらいですが、それでは全然足りません。
困ったぁなと思っていると、家内がこれをと言って、封筒を私に手渡しました。
中を確かめると、30万円入っています。
どうしたのかと尋ねると、少しずつ貯めたへそくりだと言います。
これには驚きました。
交通費10万円と合わせると、夢で見たのと同じ40万円です。
しかも、家内がこんなお金を貯めていたなど、思いもしませんでした。
思いがけない時に、思いがけない人から、思いがけないことをしてもらったのです。
家内にも夢の話をして、二人で不思議がったり面白がったりしたのですが、本当にこの世界は、そんな所なのだと思いました。
それに、女性のへそくりというものに、本当に感心させられました。
感謝感謝です。

