それぞれがするべきこと その3
自分はいったい何がしたいのだろう。
どうすることが自分にとって幸せなのだろう。
そんなことを考えても、答えは見つかりません。
何故なら、その答えはぼんやりしたものであって、具体的な形を持ったものではないからです。
何がしたいのか、何が幸せなのか。
それは具体的にこうですよ、と決めつけたものではありません。
決めつけてしまうと、それ以外のことに喜びを見つけられなくなります。
また、決めつけたことができなくなれば、人生は終わりになってしまいます。
具体的な形は、その時の状況に応じて、臨機応変に決めればいいのです。
それが都合が悪ければ、別の形に変えるだけのことです。
見た目が変わっても、中身は同じです。
それが自分が求めているものが、ぼんやりとしている理由です。
ですから、こうじゃないといけないという決めつけた考え方は、一切棄てたほうがいいでしょう。
たとえば、大学を出ないとだめだ、お金を稼がなければだめだ、英語が話せなければだめだ、資格がなければだめだ、仲間がいなければだめだ、注目がなければだめだ、若くなければだめだ、などと言っているうちは、それこそだめです。
何をやってもいいのです。
お金があるならお金を使えばいいし、お金がなければ、お金がいらない方法を探せばいいのです。
大変に見える作業が必要であったとしても、その先に自分が望んでいるものがあるとわかっていれば、疲れはしても苦にはならないでしょう。
誰かに褒めてもらおうと思う必要はありません。
自分が満足することを、追い求めればいいのです。
他人と自分は価値観も基準も違います。
そうでなければ、自分が自分である意味がなくなってしまいます。
それでも、他人を思いやり、他人に感謝する気持ちを持っていれば、自ずと周囲が認めてくれるようになるでしょう。
そんなつもりがなかったとしても、みんなが目を向けてくれることになるのです。
自分がいいなと思ったことを、とことん楽しんで没頭するようになれば、自分に本当に必要なものが何であるのかが、わかるでしょう。
それはお金や物質的な豊かさではないはずです。
みんな見た目に違うものを、追い求めるようになるでしょうが、共通しているものがあります。
それは自由と喜びと愛です。
それぞれがするべきこと その2
周りに振り回されず、自分が信じたとおりに進むんだ。
こう言われたところで、それは容易なことではないでしょう。
身の回りで何かが起これば、どうしてもその影響を受けてしまいます。
今のように、世界が大きく動いている中では、ちっぽけな自分なんかは、濁流に押し流される、一枚の葉っぱのようなものに思えます。
それでも、流れに呑まれて沈んでしまう葉っぱもあれば、最終的に無事に岸辺にたどり着く葉っぱもあるのです。
どうなるのかは偶然によって決められるのであって、自分の力ではどうにもならない、と思うでしょう。
でも事実は、さにあらずです。
確かに自分で動けない葉っぱは、濁流に逆らって動けるものではありません。
激しい濁流には、泳ぎが上手な生き物だって、押し流されてしまうでしょう。
それでも、入り乱れた流れの中を縫うようにして、無事に岸辺にたどり着けたなら、それは流れと戦った結果とは言えません。
結果的に岸辺にたどり着ける流れの位置に、身を置くことができたから、その葉っぱは沈むことなく、岸辺に漂着できたのです。
これは頭で考えてできることでもなく、波と戦ってできることもありません。
葉っぱが沈まないルートを通るために、どんな力が働きかけていたのか。
それがわからない人は、それを偶然という言葉で表現します。
しかし、そこには目に見えない力が働きかけていると、理解している人は少なくありません。
この木の葉のように、人間が自分を安全な所に置くためには、この目に見えない力と、結びつく必要があります。
そのための力が直感です。
どこが安全なのか。
どう進めばいいのか。
何をすればいいのか。
これらを直感で判断し、そのように行動できた者が、無事に残ることができるのです。
近くで誰かがどうにかなった。
だから自分もそうなると思うことは、わざわざ自分を沈める流れに、自らを任せてしまうことに他なりません。
同じように見える流れの中で、直感は無事へつながる流れを、見つけ出してくれます。
人は人、自分は自分と考えられる人は、この流れを見つける可能性が高いと言えます。
それでも理屈で考えて判断していると、自分は自分と考えていたとしても、やはり無事へと続く流れを、見つけることはできないでしょう。
正しい判断は、思いがけないところからやって来ます。
混乱している時こそ、混乱している思考を止めて、頭を無の状態にして、どうするべきなのかという答えを求めるのです。
考えるのではなく、ただ求めるのです。
こうなったらどうするのか、ああなったら困るぞ、なんて言うことは一切考えません。
とにかく頭の中を空っぽにして、リラックスした状態を作り、ただ答えを求めていると、ふと答えが頭に浮かぶでしょう。
それに従って動けばいいのです。
それぞれがするべきこと その1
今の混乱した世界情勢の中で、これから世の中はどうなるのだろう、自分はどうなってしまうのか、と不安に思う人は少なくないでしょう。
でも、こういう不安は、受け身の体勢で成り立っています。
この混乱の中でどう対処しようかと、積極的に動かないでいるがための不安です。
いやいや、自分はちゃんと動いているよ、と言う人もいるでしょう。
それでも不安を感じるのであれば、自分がやろうとしていることに、うまく行かないかもしれないという心配を抱えているはずです。
あるいは心配とうより、絶対にそうなるに違いないという想いが、あるのだと思います。
だめかもしれないと思いながらやると、必ずだめになります。
スポーツのトップを競う人たちと同じです。
明らかな力量差があるならば別ですが、トップを競う人たちの間に、大きな差はありません。
何が勝敗を決めるのかと言うと、己との戦いに勝つということでしょう。
自分の不安に打ち勝って、思うがままの力を出し切れた者が、勝利を手にできるのです。
いわば自分を信じ切れた者が、勝利という結果を導けるのです。
スポーツと仕事は別だと思うかもしれませんが、同じことです。
何をもって仕事というのか。
それは人間が勝手に考えた定義に基づいてのことです。
定義を変えて、みんながしていることが、ただのお金稼ぎのお遊びだと決めれば、そうなります。
命を懸けたスポーツのような勝負こそが、本当の仕事であると定義すれば、スポーツが仕事になるのです。
こんなのは単なる言葉遊びに過ぎません。
この時空間の中で、人間が行っている行為であるという点において、スポーツも日常の仕事も同じことなのです。
そして、スポーツで己を信じた者がうまく行くのであれば、日常の仕事や暮らしでも、己を信じた者がうまく行くのです。
失敗した人を見て、自分もああなるに違いないと思えば、そのとおりになるでしょう。
人が失敗するのには、それなりの理由があるわけで、自分には関係のないことだと思うことができれば、自分の道を進むことができるでしょう。
また失敗したように見えても、それを落ち込むべきことだと決めつけるのか、単に次の方向を示してくれているサインだと見るのかも、人によって違って来ます。
何をどうとらえるかは、その人の自由であり勝手ですが、それに応じた結果というものが、必ずついて来ます。
うまく行きたいのであれば、そうなるような物事の捉え方をすればいいのですし、それに従って動けばいいのです。
どうして戦争が起こるのか その3
支配者が人々を支配するために、最も有効な手段は、教育しないことです。
教育しているようにみせかけて、自分では考えられないようにするのも、同じことです。
とにかく、人々から思考能力を奪い、表面的な物事の流れにだけ、意識が向くようにするのです。
どうしてこうなんだろう。
何故こんなことをしているの。
こうしたんじゃいけないのかな。
こんなことをみんなが考え出すと、一つにまとめるのが困難になります。
これがルールだから、これに従いなさいと言って、みんながそれに従えば、支配は簡単です。
いろいろ考えられては困るのです。
また、支配者に対する人々の尊敬や、支配者への人々の支持は、支配する者にとっては絶対に必要です。
そのためには、支配者は人々にとって頼りがいがないといけません。
でも、頼ってもらうためには、まず人々の生活を不安定にして、苦しんでもらわなければなりません。
これは大変だどうしよう。
誰が自分たちを助けてくれるのか。
こう思わせておいて、人々に甘い言葉をかけたり、少しばかりの支援をすれば、支配者は絶大な人気を得ることができるのです。
人々は支配者の言うことを何でも信じるようになり、どんなことにでも従うようになります。
それが人間としてどうなのか、と思うようなことでも、悪びれることなくやってしまいます。
これは支配者による洗脳だと見ることもできます。
でも、同じ状況に置かれながらも、自分で物事を考え、支配者の言いなりにならない人もいるわけです。
つまり、こうなるのは支配者からの、一方的な洗脳が原因というわけではないということです。
元々その人が持っていた無責任さや、面倒臭がりなところ、周囲への無関心というものが、大きな理由なのです。
意識してようがしていまいが、自分の人生がどうなるのかは、自分自身が決めています。
自分の思考能力や価値観が、人生がどのように展開して行くのかを、決めているからです。
いつも不安ばかり抱えている人は、決して明るい人生を送ることはありません。
人を頼ってばかりいる人が、自分で何かを成し遂げることもありません。
責任感のない人が、人々から認められることはありません。
自分で物事を決められない人は、不自由から逃れることはできません。
戦争の本当の原因を探ろうとしない人は、戦争の脅威から隠れることはできません。
どうして自分はこの世界に生まれて来たのか。
人を傷つけるため?
自分が苦しむため?
別に理由はないから、自分の価値というものもない?
そんなことを真剣に考え、自分なりの答えを追い求めて下さい。
親や先生や偉い人が言ったことなど、無視してください。
自分自身で考えるのです。
そして、自分が生まれて来た意味や、自分が送るべき人生について、考えて下さい。
そうすれば、あなたは自由になります。
誰にも支配されなくなります。
自分の人生を生きることが、できるようになります。
その時、きっと戦争が起こる理由が見えて来るでしょう。
どうして戦争が起こるのか その2

抑圧と不安の中で暮らしている人は、自分の人生を生きているとは言えません。
自分の人生を生きられないからこそ、抑圧を感じたり不安になったりするのです。
自分の人生を生きている人は、喜びと充実を感じることができます。
大変なことがあっても、それを抑圧や不安という形には受け止めません。
困難はチャレンジであり、その先に喜びが待っていることを理解しています。
そんな人たちは他人と争ったりはしません。
そんな暇があれば、自分がやりたいことに没頭するでしょう。
世界中の人が、自分の人生を生きることができれば、戦争はなくなります。

自分の人生を生きるということは、自分勝手に生きるとういことではありません。
人間として、人間らしい人生を生きるということです。
人間らしい人生を生きれば、他人を思いやったり、感謝の気持ちを持つようになります。
好きなことをするにしても、それで他人に迷惑をかけることはありません。
自分も喜び、他の人たちも喜ぶということを望むのが、人間らしい人生です。
それが人間本来の自然な姿です。
不安になったり、争ったり、苦しんだりというのは、本来の姿をゆがめられた、不自然な状態なのです。

人間の自然な姿を見せてくれるいい例は、幼い子供たちでしょう。
彼らは喜びを追い求めることに夢中です。
他人との関係がわからなくて、他の子供と衝突することもありますが、そんな時にどうすれば喜びにつながるかを学べば、あとはそのようにします。
それが学べなくて、嫌な想いばかりをさせられてしまうと、次第に心がゆがんでしまって、不自然な状態になるのです。
話を戻しますが、戦争が繰り返されるということは、人々が自分の人生を生きていないからです。
では、どうして自分の人生を生きられないのでしょうか。
答えは簡単です。
そんなことになれば、支配者は人々を支配できないからです。
どうして戦争が起こるのか その1
今、ロシアとウクライナの戦いが、世界中の注目を集めています。
しかし、これまでにも人間は、世界の至る所で争いを繰り広げ、何度も戦争を繰り返して来ました。
戦争と言うと、国同士の争いになってしまいますが、内戦と呼ばれる国内の争いも、一種の戦争でしょう。
集団と集団が互いを否定し、殺し合うものは、規模に関係なく戦争と見ていいと思います。
それにしても、どうして戦争は起こるのでしょうか。
また、人間はどうして同じ愚かなことを、繰り返してしまうのでしょうか。

歴史から学ぶという言葉がありますが、歴史は繰り返すという言葉もあります。
学んでいるはずなのに繰り返すということは、実は学べていないとういことですね。
これはタバコやお酒が体に悪いと知りながら、それをやめられないのに似ていると思います。
全然違うと思われるかもしれませんが、同じ理屈です。
タバコやお酒をやめようと思うのは、頭で考えているわけです。
体に悪いことはやめておこうと考えるのですね。
でも実際にやめられないのは、タバコやお酒をやりたいと思う、感覚的な欲求があるのです。
それは肉体的な欲求のこともありますし、精神的な欲求のこともあります。
いずれにしても、それらの欲求がどうして起こるのか、という点について考慮しない限り、本当の禁煙や禁酒はむずかしいのです。

それと同じように、戦争は愚かなことであり、悲惨なことだというのは、誰にでもわかります。
勝っても負けても、そこには悲しみと憎しみしか残らないと、誰もが学ぶことはできます。
それで二度と戦争なんかしないぞ、と考えるのです。
でも、実際には戦争を繰り返してしまいます。
それはタバコやお酒を求めてしまう欲求があるように、戦争をするしかないと考えてしまう理由があるわけです。
その理由を無視した状態では、いくら戦争がよくないことだとわかっていても、また戦争をしてしまうのです。
戦争は選択肢に入れるべきではないのですが、選択肢の一つに数えてしまうのですね。
それは何故でしょうか。
それは暮らしの不満を、相手のせいだと考えたり、相手から抑圧されたり、襲って来られるかもしれないと、不安になったりするのが原因です。
また、相手への恐れや憎しみを抱いてしまうと、相手が自分と同じ人間だということを、忘れてしまうのです。

同じ人間を傷つけるのは気が引けますが、人間でないと見なせば、殺すことだって平気になります。
戦争は嫌であっても、その嫌な戦争をさせているのは、あいつらだと決めつけます。
自分は悪くないという立場で、自分を守ることや、自分が得することばかりを考えます。
相手への思いやりなど微塵もありません。
こういう人たちは、ちょっと誰かがそそのかすと、すぐにその気になって、相手を徹底的に痛めつけようとします。
支配欲や征服欲の強い者が現れると、自分たちの救世主だとばかりに支持をして、言われたとおりに動きます。
自分がしたことの責任なんて考えません。
思考能力なんかないのです。
こんな状況が続いていることが、いつまで経っても戦争がなくならない理由です。
他人を思いやれない自分勝手な考え。
正しい答えを自分で導き出す思考力の停止。
強い者になびけば安全と思う自信のなさと責任感の欠如。
個人的ないじめや差別の問題などを、振り返ってみて下さい。
問題を起こしている者たちは、必ず上に述べたような人間です。
そして戦争という愚かなことを繰り返す人たちも、これと同じ人々なのです。

いくら指導者が命令をしたところで、誰も従わなければ戦争にはなりません。
指導者に言われたから、相手を殺したと言い訳をしたところで、自分が犯した罪が消えるわけではありません。
指導者に責任を押しつけようとしても、その指導者に従った、その指導者を支持したという責任が、なくなることはないのです。
全てのことは自分で決めている。
この事実を受け入れない限り、無責任な人たちは、支配欲の強い指導者に利用されて、戦争を引き起こします。
他人を思いやり、自分の人生は自分で決める力を持ち、その結果の責任を受け止める勇気があれば、戦争は起こらないでしょう。
狂った者が指導者の立場に立つこともなく、人々は対立ではなく、助け合うことを選びます。
そもそも指導者なんて必要なくなるでしょう。
戦争を繰り返さないために、戦争の悲惨さを学ぶことは大切です。
でも、本当に戦争をなくそうと言うのであれば、普段から人々が互いを信頼し合い、尊敬し合い、助け合うという環境が必要なのです。
犬寄峠の黄色い丘
伊予市の山に入って行くと、犬寄峠という所があります。
そこには伊予市の名所、黄色い丘があります。
ここはその名の通り、黄色い菜の花に包まれた小高い丘、と言いますか、この場所がすでに山の上なので、本当は丘という名称は正しくないかもしれません。
元々はみかん山だった所を、松浦さんという方が地域おこしのために、2012年から黄色い花で一杯にする取り組みを始められたのです。

何故黄色なのかというと、黄色は幸せの色なんだそうです。
テレビで紹介されていたので、家内と二人で訪ねてみましたが、小山が全部菜の花で埋め尽くされている景観は、まさに壮観で素晴らしいものでした。
平地の菜の花畑と比べると、立体的で迫力があります。
それに花の香りが一杯で、寒くなければ蝶々や蜂が、たくさん飛んで来ると思います。
黄色い花ということで、ミモザの木も植えられていますが、これもまた立派できれいです。
春の訪れを感じさせてくれるこの丘を、ぜひ一度は見て下さい。
いつまでいても飽きませんよ。







夢を現実に その3

そもそも夢が現実になるなんて、誰にでも起こるはずがないだろう。
そう考える人もいるのではないでしょうか。
やっぱり夢が叶う人と、そうでない人との間には、超えられない壁が存在していると、疑わない人もいるでしょうね。
でも、本当にそうなのでしょうか。
自分ができないと信じているから、できないのだという考えを、絶対的に否定できる根拠は、どこにあるのでしょう。
では、できるという根拠はあるのでしょうか。
それを確かめるためには、夢と現実について、深く考えてみる必要があります。

夢が現実になるという表現ですが、これは夢と現実が別のものであり、本来同じにはなり得ないという発想が、基盤になっています。
水が氷になったり、空に浮かぶ雲になると言っても、それを否定する人はいないでしょう。
水も氷も雲も、その本質は同じだからです。
夢と現実が別物だと考える場合、それぞれの本質が異なっていると、理解しているのですね。
でも、本当にそうなのでしょうか。

夢にしても現実にしても、私たちが体験している世界は、全て私たちの意識の中にあります。
感覚や感情という情報を元にして、自分自身の中に構成しているのです。
もちろん他の人や他の生き物、あるいは海や大地や宇宙などの存在は、自分とは別にあります。
でも、それは本質としての存在であって、私たちが見たり聞いたり触れたりしているものは、全て私たちの意識の中にあるのです。
わかりにくいでしょうか。
インターネットでモニター画面を通して、遠く離れた人とお喋りをしたりできますよね。
この場合、画面に映っている相手の姿は、あくまでもモニター画面上の映像であって、その人自身ではありません。
それと同じことなのです。
たとえ相手が目の前にいたとしても、それは相手の本質を見ているのではなく、相手が発している情報を感覚的にとらえて、心の中のモニター画面に映し出しているだけなのです。

眠っている間に見る夢の世界も、同じことです。
つまり、夢も現実も本質的には同じなのです。
夢を見ている時に、それを夢だと自覚していなければ、現実世界にいる時と同じように、そこでの出来事に翻弄されます。
でも、これは夢なんだとわかっていると、夢を自分の好きなように変えることが可能となります。
何を自分の心のモニターに映し出すのかを、決めるのは自分自身だからです。
現実世界は自分が見ている夢ではないと、反論したくなるでしょう。
でも、夢が個人の意識が創る世界であるように、現実世界は人間の集団意識が見ている、夢だと思えばどうでしょうか。
それが夢だと自覚できなければ、翻弄されるのは個人の夢と同じです。
集団意識を構成している多くの人が、夢である現実世界の出来事に振り回されています。
でも、自分たちが世界を創り出しているのだと、一人一人が自覚するようになれば、いずれは現実世界も夢の世界のようになるはずです。
集団意識が自由に目覚めた時、自らの夢である現実世界を、コントロールできるようになるでしょう。

個人レベルでも、自分の好きなように生きる人たちは、他の人とは異なる、自分の世界を体験していますし、その世界を自分で創っているという自覚があります。
他の人の世界を変えることはできませんが、自分の世界はどうにでもできるのです。
それは、その人の意志が強いと見ることができますが、夢と現実の本質が同じだからこそ、できることなのです。
そうでなければ、どんなに意志が強くても、思ったとおりには生きられないでしょう。
大切なことは、夢と現実は違うんだと、自分を諦めさせるのではなく、余計なことは考えずに、自分が生きたいように生きる、ということなのです。
そうすれば、夢も現実も同じなのだと、気がつくと思います。
夢を現実に その2

一見、夢を叶えたように見えても、そのあと、うまく行かなくなることがあります。
叶えたはずの夢が、つまらなく思えるようになるかもしれません。
うまく行かなくなった場合、実は、それはまだ夢が本当に叶う前だと考えられます。
夢を叶えるためには、いろいろ試しながら、失敗を繰り返していたはずです。
夢を叶えたあとに、それがだめになってしまうと、すごく落ち込んでしまいますが、それは夢が叶ったと思っているからです。
実は、まだ夢は完全に叶ったわけでなく、まだ途中だったと考えれば、うまく行かなくなった状況も、それまでの失敗と同じものだと、気がつくでしょう。
夢に対する思いが強いのであれば、そこであきらめることはないと思います。
どんなに苦境に思える状況でも、じゃあどうすればいいのだろうかと、さらなる一手を考えるはずです。
そして、そこから復活することができたなら、前に夢を叶えたと思っていたものが、実はまだ完成形ではなかったのだと、知ることになるでしょう。

夢を叶えたつもりが、何か違うなと思う場合、それは元の企画書や設計図を、細かい所まできちんと見ていなかったということでしょう。
料理で言えば、スパイスや隠し味を入れるのを、忘れているようなものです。
本当はそこにこそ醍醐味があるはずなのに、その部分を見落としていて、表面的な完成にだけ、目を向けているのだと思います。
夢のマイホームを手に入れて、大喜びはしたものの、そのローンの支払いのために、朝から晩まで働き通し。
体は壊すし、家族との時間も取れません。
せかっくのマイホームも、くたくたになって寝るだけの場所です。
家族からは不満をぶつけられ、誰のために働いているのかと、大喧嘩になることもあるでしょう。
こうなっては、何のためにマイホームを購入したのか、わかりませんよね。
マイホームにばかり目が行ってしまい、マイホームによって何を得ようとしていたのかを、忘れているのです。

初めの頃とは、いつの間にか求めるものが違っていた、ということもあると思います。
実は、それまでとは違う夢を見るようになっていた、ということですね。
そのことを素直に認めていれば、今の状況に変化が訪れても、あまり問題にならないでしょう。
しかし、そこに自分が気づいていなければ、これまでやっていたことが、続けられなくなったら落ち込むでしょう。
また、続けられたとしても、何だか居心地が悪いと思います。
いずれにしても、自分の本音と、自分が置かれている状況が一致していないと、うまく行かなくなるものです。
自分が本当に望んでいるものは何なのか。
そこのところをよく確かめて、決して忘れないようにして下さい。
見かけ上、願いが叶っていないように見えていても、実は願いは叶っていた、ということもあると思います。
夢を現実に その1
夢と現実は、よく対比に使われる言葉です。
現実は本当にあることだけれど、夢は幻のようなもので、本当のことではないというイメージです。
自分はこうなりたいとか、こうあって欲しいなどという望みも、まだ確定していない不確実なものなので、夢という言葉で表現されます。

夢に憧れる。
夢を追い求める。
夢を叶える。
これらは曖昧だったものを、現実のものにしたい、現実のものにしようとしている、現実の物にするという意味です。
実際、そのようにしている人もいますが、夢は夢だからと、憧れのままにしている人の方が、多いと思います。
でも、夢を叶える人がいるのであれば、同じ人間なのですから、他の人が夢を叶えられないはずがありません。
自分には無理だという思い込みが、邪魔になっているからできないのです。
あるいは、口では夢だと言いながら、本当はそこまで思い入れがないかもしれません。
本気で思っていなければ、夢が叶うわけがないのです。
この世界では、想いは行動という形で表現されます。
こんなことがしたいんだよね、と言いながら、それに向かって一歩も動こうとしないのは、本当はそれほどには思ってないんだよ、ということなのです。
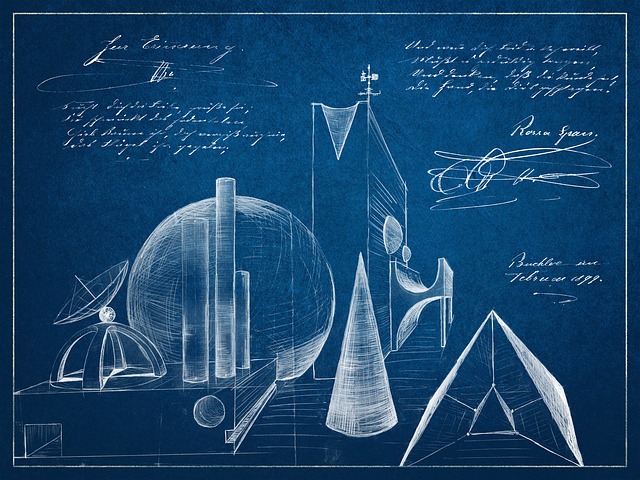
何かを創る時、そのための企画あるいは設計図やイメージが、一番先に出て来ます。
そして、それらに従って、必要な情報を集めたり、必要なものを揃えて、具体的な実現へと動きます。
それでも、すぐに思ったものが実現できるとは限らず、何度も失敗を繰り返しながら、試行錯誤することが多いでしょう。
そうすることで一番いい方法を見つけ出して、最終的には思ったとおりのものを、創り上げるのです。
夢を叶えるというのは、これと同じことです。
夢に憧れるというのは、企画や設計図やイメージを眺めて、いいなぁと思っている状態です。
いいなぁと思うのであれば、その企画を実現するべく動けばいいのですが、ほとんどの人がイメージなどを眺めながら、動こうとしないのです。
どうしてでしょうか。
それは夢を実現できる者は、特別な存在だという思い込みがあるからです。
また、自分にはお金もないし、能力も資格も才能もないと、考えています。
失敗して恥をかくことを恐れています。

しかし、自分がやりたいことをやらないで、ずっと生き続けることは、苦痛以外の何物でもないでしょう。
どんなに見かけ上は安定した暮らしをしていたとしても、それは退屈でつまらないものに思えてしまいます。
いろんなことに無関心になり、死ぬことを恐れるくせに、生きることについては、どうでもいいやと投げやりになるのです。
でも、自分が夢に向かって進むことに、何が問題なのかを、もう一度考えてみてください。
何がその道を阻むのでしょうか。
お金がないなら、ないなりの動きをすればいいのです。
動いていれば、必ずそれに呼応するような状況が、生まれて来ます。
本来ならばお金が必要とされる状況でも、お金なしに必要なものが与えられるでしょう。
もちろん本気で動かないとだめですよ。
見せかけだけの動きをしても、何も起こりません。
本気で動いていれば、必ずその動きを後押ししてくれる、そんな状況に巡り会えるでしょう。

