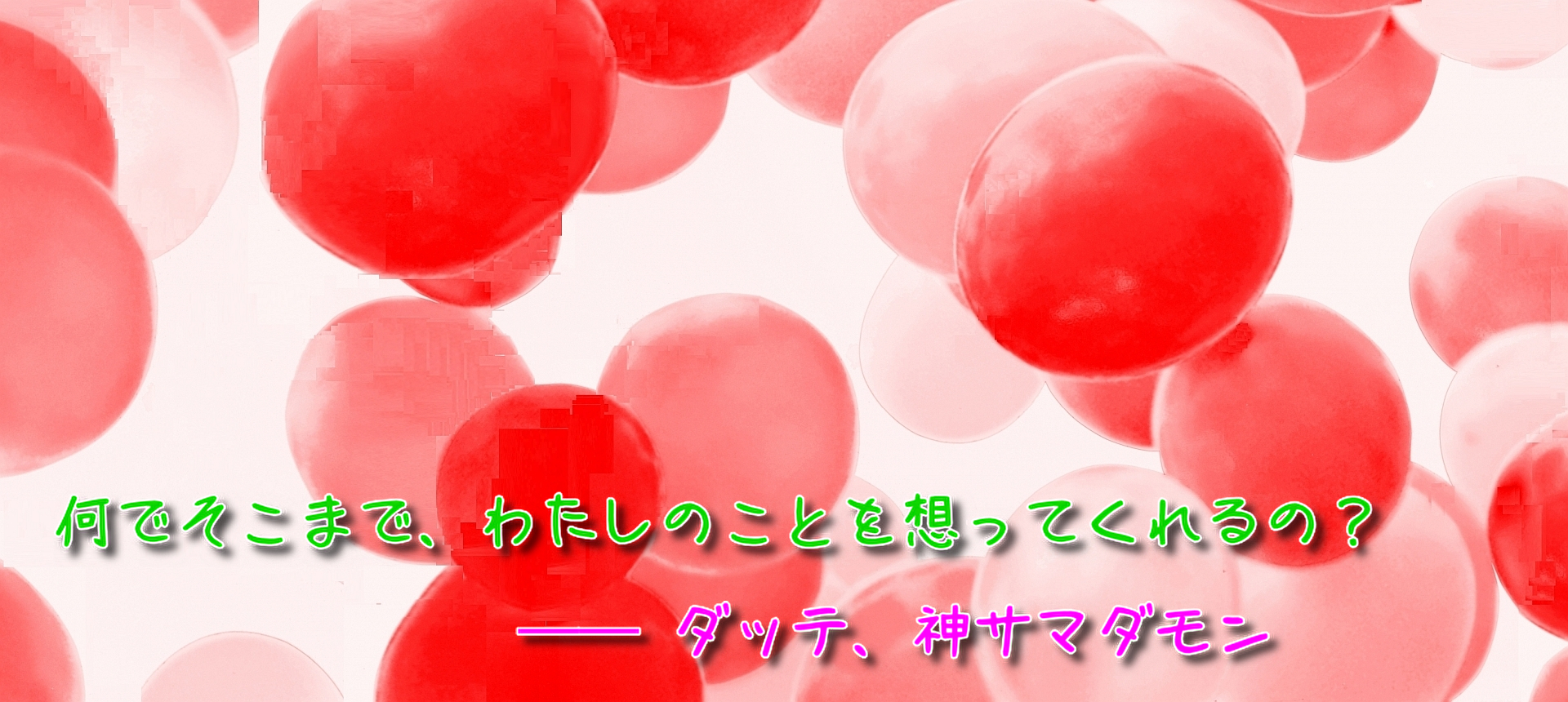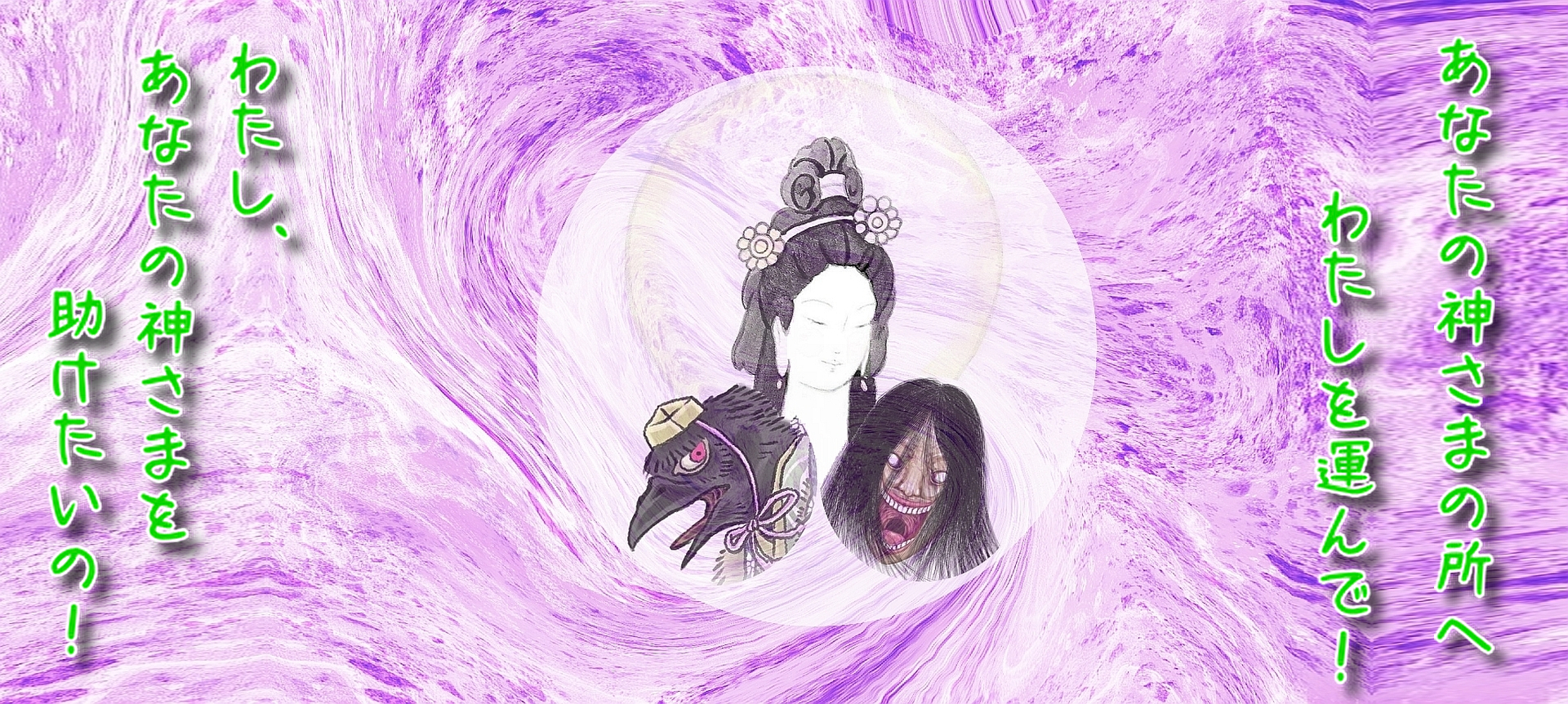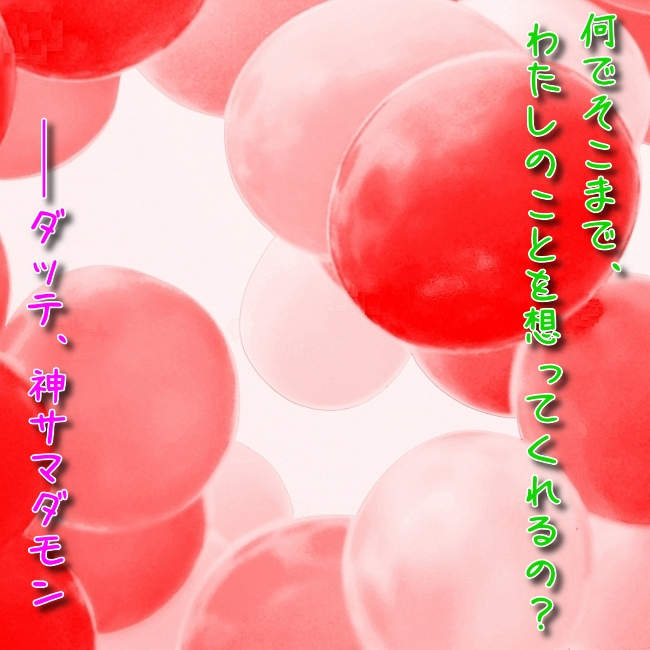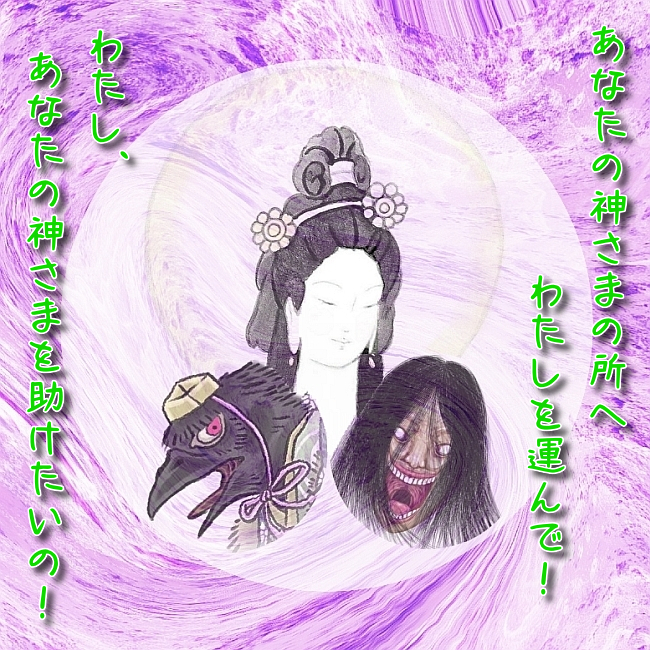風船たちの神さま 目次
風船たちの神さま
気がつけば、わたしは赤い風船がいっぱい浮かんでいる所にいた。
ここはどこだろうと思うこともなく、わたしは自分に向かって飛んで来る風船たちを、じっと眺めていた。
風船と言っても、よくある端っこに紐を結びつけたような風船ではない。縛ったような所はどこにもない、まん丸の風船だ。風船と言うよりは、大きなゴム鞠と言った方がいいかもしれない。
だけど、わたしにぶつかったときの感触は、やっぱりゴム鞠と言うより風船かな。大きさは両腕で抱えるほどあって、結構大きいけど、すごく柔らかくて、当たっても全然痛くない。あんまり柔らかくて、ぶつかった勢いでぺちゃりと平たくなって、わたしの体に張りつくみたいになる。
ここには強い風があり、風船たちは風に吹かれるだけでも、丸い座布団みたいにへしゃげてしまう。その風は何故か一定のリズムで吹いていて、風船たちは風が吹くたびに座布団に変身しながら前に進んでいる。
そんな風船たちが遥か上空から地面近くまで、ひしめきあって浮かんでいる。まるで野鳥の大群の中に入り込んでしまったみたいだ。
人はいないし、生き物らしきものもいない。白っぽい薄緑色の地面は、どこまでも真っ平らだ。草木は生えていないし石ころも落ちていない。
上を見上げると、風船たちの隙間から見える空も、地面と同じような薄緑色だ。
太陽は見当たらないけど、曇り空のような明るさはある。あの薄緑色に見えるのは、たぶん空いっぱいに広がった雲で、太陽はその向こうに隠れているのだろう。
音は何も聞こえない。ただ風が吹くたびに、小さなビリビリするような振動が伝わってくる。この振動が体に伝わるたびに、何故かはわからないけど、わたしの胸の中は物悲しさでいっぱいになる。
だけど風船がわたしにぶつかると、わたしの中に爽やかな力が湧き起こる。風に物悲しくさせられたわたしに、風船が元気を注入してくれているみたいだ。
いったいここはどこなのか。この風船たちの正体は何なのか。何もわからないけど、元気をくれる風船たちは、わたしの味方にちがいない。こんなに数え切れないほどの風船たちが、わたしの味方だと思うと、それだけで胸がいっぱいになってしまう。
よく見ると赤い風船たちの間に、小さな黄色い手毬みたいなのが交じってる。赤い風船と比べると数は少ないようだ。
見た目は丸っこいけど、近くに飛んで来た手毬を観察すると、表面が金平糖みたいにぼこぼこしている。
硬いのか柔らかいのかは触ってみないとわからない。すぐ近くに来た手毬に手を伸ばしてみたけれど、もう少しの所で指が届かなかった。
ふと顔を上げると、かなり遠くの上空に、透明のしぼみかけたビーチボールみたいなのが飛んでいた。周りの風船たちと比べると、何倍もの大きさがあるようだ。
他にもいるのかなと思って、あちこちを眺めてみたけど、どこを見ても風船ばかりだ。
もう一度上空に目を戻してみると、さっきのビーチボールもわからなくなった。
あれだけ大きいから、近くを飛んでいたならすぐにわかりそうだ。でも全然いないようだから、黄色い手毬よりもさらに少ないみたい。
それにしても、ここはまったく奇妙な所だ。何だか前にも来たことがあるような気がするけど、それがいつのことかは覚えていないし、本当に来たかどうかもわからない。それでも、ここには親近感がある。風船たちもわたしを歓迎してくれているみたいだ。
わたしはぶつかって来た風船を抱きとめた。なんだかとても愛おしい。わたしの中に風船から元気が注ぎ込まれるのがわかる。
次の瞬間、わたしは驚いた。抱いていた風船が青くなってしぼんでいるのだ。
見ると、わたしにぶつかった風船たちは、みんな青くしぼんで飛んで行く。どういうことだろう?
私は少し考えて理解した。風船たちはわたしに元気を与えた分、自分はしぼんでしまうのだ。色が青くなったのは、元気がなくなったということなのだろう。
「あなたたち、自分の元気をわたしにくれてたんだね」
わたしは抱いていた青い風船に話しかけた。話が通じると思ったわけではないけど、感激と申し訳なさがわたしにそうさせた。
そのとき、わたしには自分の声が奇妙に思えた。口に出して喋っているつもりなのに、なんだか頭の中で喋っているだけのような気がする。
自分の声のことはともかくとして、わたしは風船に、ごめんねと謝った。すると突然、頭の中に子供の声が聞こえた。
――イイノ。
どこから聞こえたのかはわからない。小さな女の子の声だ。小学校の低学年か、ひょっとしたら幼稚園児かもしれない。そんな女の子たちが何人も、一斉に喋ったように思えたけど、一人で喋ったようにも聞こえた。
わたしは周りをぐるりと見回してみた。だけど、どこにも女の子の姿はない。風船たちが邪魔で見えにくいから、わたしは地面に腹ばいになって女の子の足を探した。でも、やっぱり女の子はいなかった。
声はわたしが青い風船に謝ったときに聞こえた。もしかしてと思い、わたしはもう一度腕の中の風船に声をかけてみた。
「今の声、あなたなの?」
問いかけに対する返事は、すぐに頭の中に返って来た。
――ソウダヨ。
わたしは興奮した。この風船たちは生きている! 人間と同じように心があって、話ができるんだ!
わたしは気持ちを落ち着かせながら風船にたずねた。
「ねぇ、あなたたち、どうしてわたしに元気をくれるの?」
――好キダカラ。
思いもしなかった言葉に、わたしは泣きそうなくらい感激した。こんな言葉を誰が言ってくれるだろう? わたしは感動を抑えながら言った。
「だけど、わたしに元気をくれたら、あなたたちの元気がなくなるでしょ?」
――イイノ。
「何でそこまで、わたしのことを想ってくれるの?」
――ダッテ、神サマダモン。
「神さま? え?」
はっとなって目を開けると、もう朝だった。
頭の中で、さっきの子供の声が余韻となって残っている。
――ダッテ、神サマダモン。
それは声のようで本当の声ではない。実際に耳で聞く声と比べると、とても曖昧な感じがする。だけど、わたしが自分で妄想した声じゃない。本当に話しかけて来た声だった。
「なんで神さま? なんでわたしが?」
わたしはベッドに横になったまま、一人でつぶやき考えた。
わたしが風船たちの神さまならば、あの世界を創ったのはわたしということになる。だけど、あの世界を創った覚えなどないし、そもそもわたしにそんな力はない。
ひょっとしたら、憧れの意味で神さまという言葉を使ったのだろうか。それだったらまだわかるけど、それでもなんで風船がわたしに憧れたりするんだろう? みんなと姿が違うから?
手毬やビーチボールたちは、わたしのことをどう思ってるんだろう? やっぱり神さま? それとも手毬たちには別の神さまがいるのかしら。
出し抜けにベルが鳴った。びっくりして飛び起きたわたしは、それが目覚まし時計のベルだとは、すぐには気づかなかった。
ベルの原因がわかると、わたしは腹立たしさを込めて乱暴にベルを止めた。
「もう起きてるんだから、鳴ることないでしょ? まったく!」
時計はセットされたとおりにベルを鳴らしただけだ。なのにわたしに怒鳴られて乱暴な扱いを受けるなんて、気の毒としか言いようがない。だけど、このときのわたしにはそんなことを考える余裕などなかった。
わたしは黙り込んだ目覚まし時計をひとにらみすると、さっきの夢のことをもう一度考えようとした。しかし、どんな夢を見たのかが思い出せない。時計のベルに気を取られたために、夢の記憶が消えてしまったらしい。
必死になって思い出そうとすると、誰かに何かを言われたような、そんな気がした。それは嫌な言葉じゃなく、むしろうれしくなるものだったように思える。だけど、それ以上のことは何も思い出せなかった。
せっかくの夢を台無しにされてしまったことで、わたしは目覚まし時計に八つ当たりの枕を投げつけた。可哀想に、目覚まし時計はひっくり返ってしまった。
だけど、どんなに時計に文句を言ったところで、消えた夢は戻ってこない。わたしは夢のことはあきらめて起きることにした。
体は起こしたものの気分は優れない。できれば今日は学校へは行きたくなかった。だって、今日は運動会だから。
小学校の頃からわたしは運動が苦手だ。特に駆けっこは大嫌いだ。それなのにクラス対抗男女混合リレーの選手に選ばれてしまった。女子の一人は足の速い子に決まったけど、あとが決まらずくじ引きになった。そのくじで、わたしははずれを引いてしまったのだ。
他の選手はみんな足が速いのに、わたしのせいで負けてしまったら、わたしはみんなに顔向けができなくなってしまう。
だから、運動会が雨で中止になるよう祈ってたのに、カーテンを通して明るい光が部屋に差し込んでいる。今日は間違いなく晴れだろう。
わたしはカーテンを開けた。やはり思ったとおりにいい天気だ。いつもであれば気持ちがいいはずの青空が、今日はとても無慈悲に見える。また、そこに白い雲が運動会なんか他人事だと言わんばかりに、ぷかぷか気持ちよさげに浮かんでいる。
雲に向かって、イーッとしたわたしは、恨めしい気持ちで勢いよくカーテンを閉めた。
隣のクラスの転校生
「おはよう。今日は朝ごはん、ちゃんと食べて行きなさいよ」
二階から降りて顔を洗うと、台所にいた母が声をかけて来た。
テーブルの上には、トーストと目玉焼きとサラダが用意され、その横には牛乳が入ったマグカップが置いてある。
先に席に着いていた高校生の兄貴は、自分の分をほとんど平らげていた。あとは口にくわえているトーストだけだ。兄貴はかじった分を、急いで飲み込んで立ち上がった。
「母さん、遅くなるから、オレ、そろそろ行くわ」
「もう行くの? あら、ちょっと翔太郎! まだ食べ終わってないじゃないの!」
母はむっとなったけど、兄貴はそんなことはお構いなしだ。トーストの残りをくわえ直すと、さっさと自分の食器を重ねて母に手渡した。
「お弁当は持ったの?」
「もう鞄に入れてある」
トーストを手に取った兄貴は、口をもぐもぐさせながら言った。母は何か言いたげだったけど、気をつけてね――としか言わなかった。
兄貴はわたしに向かって意気揚々と片手を上げると、わたしの横をすり抜けて行った。
「わたしも、もう行く!」
わたしが兄貴のあとを追いかけようとすると、後ろで母が怒る声がした。
「だめよ、ちゃんと食べて行きなさい」
「お兄ちゃんだって、食べてないじゃない!」
「お兄ちゃんは食べました。春花は今日は運動会でしょ? 食べないと倒れちゃうよ」
「平気だって。いつも食べなくたって大丈夫だもん」
「だめ! 食べなさい!」
いつもより強い口調で言われたので、わたしは渋々テーブルに着いた。
母はいつだって兄貴に甘くて、わたしにきびしい。最近ずっと朝ごはんを食べていないから、目玉焼きを食べたら胸焼けしそうになった。
「ごちそうさま」
わたしが席を立つと、ほとんど残った朝食を見て母がにらんだ。仕方なくマグカップを手に取って、立ったまま牛乳を飲んだ。でも、半分飲むとお腹がいっぱいになった。
「もういいでしょ? じゃあ、行って来ます」
飲み残しのカップをテーブルに置き、用意された水筒を持つと、わたしは逃げるように玄関へ向かった。すると母が追いかけて来たので、玄関に降りて大急ぎで靴を履いた。
早く外へ逃げようとドアノブに手をかけたとき、後ろで母が呼び止めた。
「これ、持って行きなさい」
振り返ると、母は小さな包みを持っていた。
「それ何?」
「お弁当よ」
「え? もしかして今日、来ないの?」
胸の中がキュッとなった。母は申し訳なさそうに弁解した。
「ごめんね。昨日まで行くつもりだったんだけど、今朝、急に店長から連絡があってね。午前中だけでいいから、どうしても出て来て欲しいって言われたのよ」
「どうして? 今日は運動会だって言ってあるんでしょ? なんで断らなかったの?」
「だってさ、店長とこの娘さんが怪我をして、病院へ連れて行かないといけないって言うんだもん。断れないじゃない。それに、あなたが出るリレーは午後からでしょ? それには間に合うと思うんだけど、お昼に間に合うかはわかんないからさ。万が一のためよ」
母は弁当の包みを差し出した。わたしは母をひとにらみすると、その包みを引ったくった。
兄貴が中学生のときには、運動会にはいつだって開会式前から行っていた。なのに、わたしが中学生になって初めての運動会には来てくれないなんて最低だ。
母は弁当屋で働いている。朝の暗いうちから仕事に出たり、夕食時間より遅く帰ることもしょっちゅうだ。わたしはやめて欲しいけど、兄貴の学費のためだと言われたら何も言えなくなる。
日曜日に母親とショッピングに行ったことを、学校で友だちが楽しそうに喋っても、わたしはいつも話を聞くだけ。わたしがどんな気持ちなのか、母はちっともわかってない。
今日だって、午後のリレーを見て欲しいんじゃない。見て欲しいのは午前の終わりにある創作ダンスだ。
「午前だって競技はあるんだからね」
「ほんとに、ごめんなさい。でも、リレーには絶対間に合うように行くからね。がんばるのよ」
わたしは返事をせずに玄関を出ると、後ろを振り返らないままドアを閉めた。バタンとドアがやかましい音を立てたとき、自転車に乗った兄貴が、まだ少し残っているトーストを口にくわえたまま、目の前をサーッと通り過ぎて行った。
兄貴の高校は、この辺りではちょっと名の知れた進学校だ。わたしなんか逆立ちしたって入れない。だけど日曜日の今日に兄貴が学校へ行くのは補習じゃない。部活のためだ。兄貴は中学校でバスケットボールをやってたけど、高校でも一年生でレギュラーだ。
門を出ると、駐車場のゲートが開けっ放しになっていた。いつものことだけど、兄貴はゲートを開けたまま行ってしまう。開けたらちゃんと閉めるようにと、母からしょっちゅう言われてるのに、返事ばかりで同じことを繰り返す。それでも許されているのは、勉強ができるからだ。でも、いくら頭がよくたって、ルールはちゃんと守るべきだ。
兄貴への憤りを覚えながら、わたしは駐車場のゲートをガラガラ閉めた。駐車場には、母の可愛らしい赤の軽自動車があるだけだ。わたしが乗る自転車はない。
わたしが住んでいる家は古い分譲団地だ。お年寄りが多くて、子供の姿はあまり見かけない。あまり活気のない所だけど、安いという理由で父が中古物件を、わたしが小学校へ入るときに購入した。あの頃で築四十年になるって言ってたから、今は築四十七年か。大きな地震が来ればひとたまりもないだろうけど、お金がないそうだから仕方がない。
家のすぐ近くには林があって、田んぼに水を引く用水路もある。夏になったらセミがうるさいほど鳴くし、蚊もたくさん出て来るへんぴな所だ。東京都内だなんて信じられないほど、ここは都会の匂いがしない。
でも、ちょっと出た所には立派な高層マンションが建ち並んでいる。わたしたちが住んでいる所とは別世界だ。そこの子たちは持っている物も上等で、何だか気品があるように見える。
それに大抵みんながスマホを持っていて、いろんな情報を知っている。うちはお金がないので、兄貴が高校に入学したお祝いに、やっとスマホを持たせてもらっただけだ。
学校へ向かって歩いていると、時折自転車が追い抜いて行く。兄貴みたいな高校生が多いけど、わたしと同じ中学生もいる。いつもは制服姿だけど、今日はみんな運動服だ。
上級生たちは黙って追い抜いて行くけれど、同学年の一年生は小学校で一緒だった子が多く、みんな声をかけてはくれる。でも自転車を降りて一緒に歩いてくれる子はいない。
小学一年生のときに、わたしは自転車を買ってもらった。だけど、そのときにひどく転んで以来、怖くて自転車に乗れなくなった。
学校へ行くには、自転車があった方が便利だと思う。だから、もう一度挑戦してみたい気持ちもないわけじゃない。でも、両親はわたしが自転車嫌いだと思い込んでいる。それに自転車を買うには、結構お金がかかる。だから、今更自転車に乗りたいとは言えなかった。
しばらく歩いていると、途中の高層マンションから、同級生の女子生徒が二人現れた。山上真弓と本田百合子だ。ここからだと学校も近いので、真弓たちは歩いての通学だ。
二人はわたしに気がつくと手を上げた。わたしは手を振り返して駆け寄った。
「おはよう。真弓も百合子も、ちゃんと朝ご飯食べて来た?」
いつもは食べないことが多いけど、今日は目玉焼きと牛乳半分をお腹に入れた。それで少し偉くなった気分で尋ねたけど、二人ともわたし以上にしっかり食べていた。
「春花こそ、ちゃんと食べてんの? 最近痩せたように見えるけど」
「まさか、ご飯を抜いてるんじゃないよね?」
二人の言葉にどきりとしたけど、まさか――と笑ってごまかした。
以前、真弓たちは他のクラスの太った子を笑って馬鹿にした。当時、わたしはぽっちゃり体型だったので、痩せなければと減量を決意した。でも食事を減らしたなんて言えば、自分が太っていたと認めたことになる。それは馬鹿にされた子と同じという意味だ。
母にいろいろ言われながら、食事を減らしてずいぶんになる。最初の頃は、かなりきつかった。空腹がひどくて、授業なんて頭に入らなかった。元々頭が悪いのに授業がわからないから、尚更テストでは点数が悪くなった。体調もよくなくて風邪を引きやすくなった。お陰で母には叱られたけど、それでも食べないようにがんばった。
その甲斐あって、鏡に移した姿が少しは痩せたように見えた。それでも真弓たちは何も言ってくれなかった。それが今日、ようやく認めてもらえたと言うわけだ。
「そんな不健康なこと、してませんよーだ」
わたしは喜びを抑えながら言い返した。
「じゃあ、何で痩せたの? 病気?」
真弓が疑わしそうに言うと、百合子もじろじろとわたしを見た。
「やめてよね。実は兄貴と一緒に、夜、歩いてるの」
「お兄さんと夜に? ほんと?」
嘘だ。昼間バスケットボールに熱中している兄貴が、夜に歩くはずがない。歩くにしたって、わたしなんかと一緒に歩いたりはしない。
「いいよねぇ、春花は素敵なお兄さんがいて」
「ほんとよ。妹と一緒に歩いてくれる兄なんて、どこにもいないよ」
二人の関心が、わたしではなく兄貴に移った。わたしはほっとしたけど、少し面白くない気分でもあった。
真弓と百合子には、それぞれ二つ年上の兄と姉がいる。今は同じ中学校の三年生だ。一緒に通学しないのは、お互い友だちといるのがいいからみたいだけど、真弓も百合子も自分たちの兄や姉は冷たいのだと言う。
二年前、中学一年生だった兄や姉の応援のために、真弓たちは初めて中学校を訪れた。わたしたちは別々の小学校だったから、このときはまだお互いを知らなかった。
この運動会で、うちの兄貴はいくつもの競技で大活躍した。その姿に真弓も百合子も夢中になったそうだ。その上、兄貴と言葉を交わす機会もあったらしい。二人はすっかり兄貴のファンになり、自分たちの兄や姉を通じて、うちの兄貴の情報を仕入れていた。そのときに真弓たちは、妹であるわたしの存在を知ったそうだ。
中学校に入学してわたしと同じクラスになると、早速二人はわたしに近づいて来た。もちろん目的は兄貴だ。
わたしにすれば、あの高層マンションに住む真弓たちは憧れの世界の人だった。おまけにどちらも美人だ。その二人から声をかけてもらって仲間にしてもらえたのだ。それは、何の取り柄もないわたしにとって驚きであり、とても誇らしいことだった。
わたしは真弓たちにもっと気に入られようと努力をした。また真弓たちの話には何でもうなずいた。二人に逆らって機嫌をそこない、仲間外れにされるのが怖かった。二人は気に入らない相手のことを見下すので、それだけは何があっても避けたかった。
兄貴にはいつも反発するけれど、真弓たちと親しくなれたことでは感謝していた。だけど結局、真弓たちが本当に関心があるのは、わたしではなく兄貴だった。それを思うと、とても空しくなる。それでも、二人との関係が壊れることが怖いから、本音を口にすることはできなかった。
そもそも、あんな兄貴のどこがいいのだろうかと、わたしは思う。真弓たちはいい所のお嬢様だけど、きっと男を見る目はないに違いない。
真弓たちが思うほど、兄貴は優しくない。わたしは気遣いなんか見せてもらったことがない。
わたしが食事を減らしているのをいいことに、わたしが好きなおかずがあっても、兄貴は平気でそれを横取りする。テレビを見ていても、自分が好きな番組があれば、断りもなくチャンネルを変えてしまうし、妹の前でも平気でおならをする。それがまた臭い。
真弓も百合子も兄貴の本当の姿を知らないだけだ。それでも兄貴がいるから、二人はわたしを大切に扱ってくれる。わざわざ兄貴のイメージを壊すようなことを口にして、自分の立場を悪くする必要はない。だから、わたしは真弓たちに好きなように喋らせている。
真弓たちは時々わたしの家に遊びに来る。でも、わたしの部屋には面白いものや見せるものが何もない。だから、二人はすぐに退屈してしまう。それで何だかんだと理由をつけては、隣にある兄貴の部屋をのぞいて、兄貴とお喋りしようとする。て言うか、それが二人の本当の目的だった。わたしは兄貴に会うためのお約束のようなものだ。
兄貴も兄貴で妹ではない女の子の前では、かっこよくて気さくな高校生を装う。そんなことをするから、真弓たちはますます兄貴に夢中になった。
わたしの家にいる間、二人がわたしと一緒にいる時間よりも、兄貴と喋っている時間の方が遥かに長い。そんなときは、さすがにわたしは悲しくなってしまう。
「ねぇ、お兄さんの学校って、運動会はいつなの?」
真弓が尋ねると、百合子も目を輝かせた。
「高校は春だったと思うよ」
わたしは素っ気なく言ってやった。すると二人は、えー!――と声を揃えて叫んだ。
「それじゃあ、あたしたち来年まで応援に行けないじゃない!」
「あたしたち、お兄さんが活躍するとこ、見たかったのに!」
「しょうがないよ。もう終わっちゃったんだもん。それにね、高校の運動会は生徒だけでするから、どこの家も家族は応援に行かないらしいよ」
わたしは少しうんざり気分で話をした。二人はぶつぶつ文句を言い続けたけど、こればかりは本当のことだからどうしようもない。
そのとき、わたしたちの前方に見慣れない女子生徒が現れた。と言うより、追いついたという方が正しいか。その生徒は一人で歩いているのに足取りが遅く、できれば学校へ行きたくない雰囲気だ。わたしと一緒で運動会が嫌いなのかもしれない。見慣れないと言うのは、わたしたちと着ているものが違うということだ。
その女子生徒が着ている体操服は、ネックが紺色だ。わたしたちのネックは青だから、似ているけど少し違う。でも服よりもっと違うのはズボンだ。わたしたちのズボンは緑色だけど、その子のズボンは紫色だ。
違う学校の生徒だろうかと思ったけど、この辺りを歩いているのだから、そうではないだろう。もし違う学校なのだとしたら、ここから歩いて行くには遠過ぎる。
「あの子、確か隣のクラスの子よね?」
真弓が女子生徒を見ながら、眉をひそめた。そうね――と百合子はうなずいた。
「今学期、転校して来た子よ。名前は知らないけど」
一年生は三クラスある。わたしたちは一組だから、隣のクラスと言えば二組だ。夏休み明けに転校して来たということか。
一組には転校生がいなかったから、転校して来た者がいたとは思いもしていなかった。体育の時間が二組と一緒だったら、もっと早くにわかっただろうけど、そうじゃないから気がつかなかった。
「何で紫のズボンをはいてんだろ?」
「たぶん、新しいズボンを買うお金がなかったんだよ」
「気の毒に。貧乏な家には生まれたくないよね」
「教科書も前の学校のを使ってるのかもよ」
「お金がないって、ほんと可哀想」
何も事情を知らないくせに、二人は転校生が貧乏な家の子だと決めつけて馬鹿にした。
距離から言えば、真弓たちが何を喋っているのかは、転校生には聞こえないだろう。でも、大袈裟にアハハと笑う大きな声は聞こえているに違いない。
いつもだったら、わたしも二人に合わせて一緒に笑うところだ。だけど、何故かわたしは、転校生を笑う気にはなれなかった。本当にお金がなくて大変だったとしても、それはうちだって同じだから。でも、それとは別に、わたしは真弓たちに同調したくなかった。
わたしが黙ったまま笑わないので、どうしたの?――と真弓が言った。
百合子も怪訝そうにじっと見ている。わたしは慌てて笑顔を繕うと、ちょっと考えごとをしていたと言った。
「考えごと? 何を考えてたの?」
「何って……、別に大したことじゃないよ」
「大したことないのなら、教えなさいよ。何を考えてたの?」
わたしは困った。転校生のことを何もそこまで馬鹿にしなくてもいいじゃないかと考えていた。そんなことを二人に言えるわけがないけど、他に何と言っていいのか思いつかない。
二人の視線が、わたしの心の中にまで入り込んで来るみたいだ。耐えられなくなったわたしは、二人が喜ぶことを言うことにした。
「実は、今度の兄貴の誕生日にね、二人を招待しようかなぁって考えてたんだ」
「え、ほんとに?」
「あたしたちを呼んでくれるの?」
二人は手を取り合って跳び上がった。その様子を眺めながら、どうしよう?――とわたしは思った。後悔先に立たず。口は禍の元とはこのことだろう。
これまで兄貴の誕生日に人を呼んで祝ったことなんかない。夕食後に家族でケーキを食べるだけだ。それに兄貴の誕生日は先月で、もう終わっている。
「ねぇねぇ、お兄さんの誕生日っていつ?」
「今月? それとも来月?」
真弓と百合子は、わたしの手を片方ずつつかんで言った。わたしはほとんど考えずに、思いつくまま答えた。
「十二月だよ。十二月十八日」
「えぇ? 三ヶ月も先じゃない!」
百合子ががっかりしたように口を尖らせた。でも真弓は、それでも構わないと言った。
「じゃあ、約束だよ。でも、十二月十八日って平日?」
「わかんないけど、平日だったら一番近くの日曜日にするから大丈夫」
口が勝手に適当なことを喋ってしまう。真弓たちは何をプレゼントにしようかと、打ち合わせを始めた。
怖くなったわたしは、真弓たちから顔を逸らして前を向いた。すると、先を歩いていたはずの紫色のズボンの転校生は、いつの間にか見えなくなっていた。自分が笑われていると気づいて逃げたのだろうか。
兄貴のことではしゃぐ真弓たちの横で、わたしの胸は小さな罪悪感でチクリと痛んだ。
目撃
ピストルの音が鳴り響き、一〇〇メートル走が始まった。走るのは各クラスの男女二名ずつ。一年生は三クラスだから一度に走る選手は六名で、みんな足の速い者ばかりだ。
各クラスの応援席から懸命な声援が送られる中、一年生男子の選手たちが後ろへ土を蹴り上げながら、ゴール目がけて走って行く。一位は二組。二位と三位は三組だ。
続けて一年生女子。うちの男子は四位と六位に終わったけど、我らが山田早紀は陸上部所属で、一年生女子では一番足が速い。一組では一番期待の星だ。他のクラスも強者を出して来るだろうけど、早紀に勝てるわけがない。
スタートラインに立った女子選手たちを眺めたとき、おや?――とわたしは思った。六名の選手たちの中に一人だけ、紫色の体操ズボンをはいている選手がいる。
――あの転校生だ。
わたしは転校生に注目した。真弓たちには馬鹿にされたけど、一〇〇メートル走の選手に選ばれるとは大したものだ。
一人で登校していた様子から、友だちがまだいないように思えたけど、みんなに認められたということは、友だちができたのに違いない。ひょっとしてクラスで浮いているのだろうかと気になっていたので、わたしは何だかほっとした。
「位置に着いて。用意――」
パン!――とピストルが鳴ると、みんな一斉にスタートした。思ったとおり、早紀はいきなり他の選手たちの前に飛び出した。その上、さらに加速してみんなを引き離す。少し遅れて他の選手たちが、団子状になりながら早紀を追いかける。と思ったら、一人だけ集団からぐんぐん引き離されて行く。紫色の体操ズボンをはいた、あの転校生だ。
「え? なんで?」
足が速いはずじゃなかったの?――と思っているうちに、早紀が一番でゴールし、続けて他の選手たちもゴール。それから、あの転校生が一人遅れてゴールした。
他の選手と比べると、転校生は明らかに足の回転が遅かった。わたしのすぐ横で真弓と百合子が、転校生のことを思いきり馬鹿にして笑っている。でも、わたしは笑う気持ちになれなかった。
あれは明らかに人選ミスだ。だけど、転校生が自分から走りたいと申し出たとは思えない。わたしもそうだからわかるけど、足が遅い者は自分が選ばれないよう祈るものだ。
わたしみたいに、くじ引きではずれくじを引いたのだろうか。それとも、早くクラスに馴染めるようにと、担任の先生が決めたのかもしれない。でも、この結果ではどうなんだろう? よくがんばったねと言ってもらえたらいいけれど、真弓たちが笑ったように、みんなから馬鹿にされる原因にもなりかねない。
あれこれ考えているうちに二年生の競技が始まり、すぐに三年生の出番となった。
自分で走ると一〇〇メートルは、とても遠くて時間がかかる。だけど、他の人が走るのを見ていると、あっと言う間に終わってしまう。転校生のことを気にしていたので、二年生や三年生の結果がわからないまま、一〇〇メートル走競技は終了した。
このあとはダルマをかぶって走るダルマ競争や、二人三脚など遊び半分の競技が続く。
こういうのは真剣に走る競技と比べて人気がある。当然希望者が多いから、大概はくじ引きで決める。これについてはわたしは当たりくじを引き、二人三脚の選手になることができた。しかも一緒に走る男子が、何とクラスで一番人気のある谷山健一郎だ。
兄貴ほどではないにしても、谷山はなかなかのイケメンだ。だけど兄貴と違って、わたしにも優しくしてくれる。勉強はそこそこできるけど、上位クラスというほどではない。それでもテニスは上手らしくて、テニス部でも先輩たちから期待されているそうだ。
わたしは谷山とペアになれてよかったと思った。でも、別に谷山が好きなんじゃない。ふざけてばかりいるやつや、わたしに美人じゃないと文句を言うやつと組むのは御免だった。
だから相手が谷山とわかったときには喜んだけれど、女子生徒たちからはブーイングされた。それでちょっと困惑したけど、要は羨ましがられているわけだ。そう考えると気分がいい。
ダルマ競争が始まった。二人三脚はこのあとだ。
ダルマ競争には百合子が出場した。顔が見えなくていいというのが出た理由だけど、それは周りがよく見えないということでもある。それにかぶり物は重いし、足も動かしにくい。予想どおり百合子は転んでしまい、起き上がったあとに全然違う方向へ走ったので、みんなに大笑いされた。
百合子も笑われるのは覚悟の上だったろうけど、相当恥ずかしかったようだ。二人三脚に出るわたしは、入場門で待機していたので直接は聞いていないけど、応援席に戻った百合子は、二度とダルマ競争には出ないと怒りながら宣言したらしい。気位が高いっていうのもなかなか大変だ。
だけど、わたしたちだってどうなるかわからない。男女のペアでやるので、みんな恥ずかしがって一度も二人三脚の練習はしなかった。全員がぶっつけ本番だ。気位が高くなくても、あんまりひどい姿は人に見せたくない。転ばないことを祈るばかりだ。
出番を待つ間に、ペアは互いの足首をはちまきで結んで固定する。それだけでも気恥ずかしいのに、立ち上がって転びそうになり、谷山に抱き支えられたときには、顔から火が出そうなほど恥ずかしかった。
いよいよ出番になって、わたしたちはスタートラインの所まで移動した。二人の足が固定されているので、谷山と歩調を合わせなければ歩けない。バランスを崩しそうになるので、互いの肩を組み合って身体を密着させ、声をかけ合いながら進んで行く。
谷山とは小学校のときからの付き合いだし、谷山のことなんかこれまで何とも思ったことがない。なのに、何だか胸がどきどきする。
あちこちから声援や冷やかしの声が飛んで来る。がんばろうな――と言う谷山の声は他の誰かに言ってるみたい。谷山の笑顔がまぶしくて、わたしは下を向いたままうなずくだけだった。
ピストルの音と同時に、選手たちが一斉に走り出す。競争のはずなんだけど、そんな感じがしない。
一、二! 一、二!――と声をかけ合って走っていると、谷山と一つに溶け合ったみたいになって、頭がぽーっとなった。ゴールに着いても気づかないまま、どんどん走ろうとしたので、谷山が止まろうとしたときにつんのめって転んでしまった。
二人の足ははちまきで縛られていたので、わたしが転ぶと、谷山も引っ張られるようにして転んだ。谷山がわたしを抱くようにかぶさって来たので、わたしは慌てて起き上がろうとした。恥ずかしくて何も考えられない。だけど足が固定されているから、二人一緒に動かないと起きられない。無理に立とうとすると互いの足が痛くなる。
痛ててと言いながら、谷山はわたしを落ち着かせようとした。それから固定された二人の足を伸ばし、きつく結ばれたはちまきを苦労して解いた。
やっとはちまきが外れて自由になったとき、わたしは何だか悲しくなった。
「痛かったか? 悪かったな、急に止まったりして」
しょんぼりしていたわたしの顔を、谷山は心配そうにのぞき込み、わたしに謝ってくれた。悪いのはわたしの方なのにそんな優しい声をかけられて、わたしは本当に泣きそうになった。
すべての選手が走り終えて全員が退場するまでの間、わたしはずっと谷山の隣に座っていた。この競技がずっと続けばいいのにと思っていたけど、二年生も三年生もあっと言う間に走り終えた。こうして谷山と一緒にいる時間は終わってしまった。
午前の部の終盤には借り物競走がある。これには真弓が参加する。足の速さを競うものではないから、真弓は自分から手を上げた。負けたとしても、これも遊びみたいなものなのでお気楽な競技だ。幸い希望者が少なくて、真弓はすんなり選ばれた。
男女とも選手は二名ずつだ。女子で真弓と一緒に出場するのは、わたしの小学校の同級生の宮中満里奈だ。
男子が終わり、いよいよ真弓と満里奈の登場だ。
スタートラインに並んだ選手たちは、みんな本気で競争するつもりはないみたい。男子たちもそうだった。にこにこしながら隣の選手と何か喋ったりしている。
と思ったら、ピストルが鳴った途端、みんな借りる物を書いた紙を目がけて、全力疾走で突進した。男子と違って、女子は全員が本気のようだ。
満里奈はそれが初めからわかっていたようで、スタートはよかった。だけど、真弓は置いてけぼりを食ったみたいに、みんなよりスタートがワンテンポ遅かった。それで紙を拾うのは一番最後になったし、紙を開く動作がもたもたしていた。
他の選手たちはすでに借り物内容を確かめて、自分たちのクラスの応援席へ向かっている。満里奈も大急ぎでわたしたちの所へ来ると、広げた紙を見せながら叫んだ。
「誰か鉛筆持ってない? 鉛筆よ!」
鉛筆?――みんなは互いの顔を見た。普段ならともかく、運動会の応援に鉛筆なんか必要ない。満里奈が足踏みをしている間、みんな持っているはずのない鉛筆を探し始めた。その間にも他の選手たちは、次々に目的の物を手に入れてゴールに向かっている。
しびれを切らした満里奈はクラスメイトの助けを諦めて、先生たちが控えるテントへ走って行った。すると、そのテントから校長先生の手を引いて来る選手がいた。お腹の突き出た校長先生がよたよたと走っている。気の毒に、その生徒は一位は絶対に無理だろうけど、満里奈よりは早くゴールできるだろう。
それにしても真弓はどこへ行ったのだろうか。全然こっちへ来ないところを見ると、早くに先生たちのテントへ向かったのかもしれない。
競技終了の合図が鳴った。満里奈が鉛筆を持ってゴールした姿は見えた。だけど、真弓がどうなったのかわからない。応援してよと頼まれていたのに、見ていなかったとは言えない。わたしは焦った気持ちで真弓を探した。
探し物が見つからない真弓が、しょんぼりゴールへ向かうのかと思ったけど、真弓はどこにもいない。他の仲間たちも真弓はどこだと探していた。
一人が指差しながら、あそこにいたと叫んだ。それはゴールを終えた選手たちの集団の中だ。真弓はみんなが見ていないうちにゴールしていたようだ。
しかも奇妙なことに、真弓は一位の選手の場所に腰を下ろしていた。そんなの有り得ない話だけど、誰も真弓の場所を変えないし、文句を言う者もいないようだ。
本当に一位だったのなら、その勇姿を見たかった。それに見ていなかったなんて言ったら、どんな反応を返されるかが怖かった。
それでも真弓がゴールしたところは、誰も見ていない。百合子でさえも気がつかなかったみたいだから、わたしはちょっぴり安心した。
三年生の借り物競走が終わると、全学年の女子による創作ダンスの時間だ。わたしたち女子は男子を残して入場門へ集まった。退場門から出た借り物競走の選手たちのうち、女子選手はそのまますぐに入場門へ戻って来て、他の女子生徒たちと合流した。
「ねぇねぇ、見てくれた? あたし、一位取ったんだよ!」
興奮した様子で戻って来た真弓は、開口一番に自分の一位を自慢した。だけど、すぐに入場が始まった。それで真弓の話を聞くことはできなかったし、みんなも見たかどうかの返事はしないままだった。
創作ダンスは全学年で行うけど、普段の練習はそれぞれの体育の授業のときにやった。だから、全体の合同練習が二度予定されていた。そのうち、一度目は雨で中止になった。二度目はできたようだけど、わたしは風邪を引いて休んでしまった。だから、わたしが女子全員と踊るのはこれが初めてだった。
全体でどんな風に踊るのかは説明されたけど、緊張して失敗するかもしれない。でも、どうせわたしを見てくれる人はいないんだ。
このダンスを母に見てもらおうと、わたしはひそかに考えていた。兄貴と違って運動も勉強もだめだけど、それでもこれぐらいはできるんだってところを、母に見せたかった。それなのに急な仕事で来られないなんて最悪だ。
パートなんかやめたらいいのにと思うけど、いずれ兄貴が進学する大学のお金は、今以上にかかるそうだ。だから、その分も今から蓄えておかないとだめらしい。
うちの古くておんぼろの家だって、銀行でお金を借りて買ったから、そのローンもこれから何年も払い続けないといけないそうだ。
父は転勤族で、お盆とお正月以外はめったに帰って来ない。もう何年もそんな感じなので、うちの家はほとんど母子家庭と言っていい。甘えられるのは母しかいないけど、母の頭の中は兄貴のことと、お金のやり繰りのことばかり。
わたしなんか頭が悪いから、大学へは行かないで働けって言われるだろう。下手すれば高校だって行かせてもらえないかもしれない。
いろいろ考えながら入場すると、どこからか赤い風船がすっと浮かび上がった。
風船は風に吹かれて、わたしの頭上を飛んで行った。家族と一緒に来た子供が手放してしまったのだろう。風船を見送りながら、わたしは何かを思い出しそうな妙な気分になった。
音楽が始まり、みんなが一斉に踊り始めた。踊り出すと緊張感はなくなった。その代わり空しい気分がわたしを泣かせようとしていた。そんな気持ちに耐えながら懸命に踊り続けていると、近くで踊る紫色の体操ズボンが視界の端に見えた。
このときは輪になった者たちが、輪の外を向いたまま後ろに下がり、輪の中心へ背中合わせに集まるところだった。
後ろ向きに移動するので、みんなが同じ速度で同じ場所に集まるのはむずかしい。だから何度も練習を繰り返し、お互いにどうすればいいのか教え合って来た。悲しんでいる暇などない。後ろに下がって身体が左右の者と同時に触れた瞬間、わたしはほっとした。
隣のグループも同じように背中合わせで集まったけど、紫色のズボンの転校生がみんなより少し遅れたようだ。わたしは心の中で転校生にエールを送った。
いったん集まったあとは、リーダーの子がそこから離れて、隣の者がそれに続く。その隣の者がさらに続き、順々にらせんを描きながら、外へ向かって大きく広がって行く。
わたしは一番最後に離れることになっていたので、それまでのわずかな間、隣のグループを眺めていた。向こうでも次々に生徒たちが移動して行き、転校生が動く番になった。そのときに、わたしは見てしまった。
すぐにわたしが動く番になったから、じっと見ていることはできなかった。だけど、転校生が隣の人に続いて走り出そうとしたとき、その後ろに続くはずの女子の足が、転校生の足を引っかけたのだ。気の毒に、転校生は大舞台の真ん中で無様に転んでしまい、後ろの女子から口汚く罵られていた。
――あれは間違いなんかじゃない。絶対にわざとだ。
踊りながらわたしは胸がどきどきした。あの転校生はいじめられている。きっと一〇〇メートル走を走らされたのだって、足が遅いのがわかっていて、無理やり走らされたのに違いない。
わたしは自分がどう踊っているのか、わからなくなった。身体が勝手に動いているだけで、頭の中はずっと転校生のことを考えていた。
担任の先生はわかっているのだろうか? 二組には誰も助けてくれる人はいないのだろうか? どこにいるのかはわからないけど、転校生の家族は今のを見てどう思ったのだろう? それにあの転校生は、どんなに情けなく悲しい気持ちになっただろう?
憤りでいっぱいになったわたしは、ダンスが終わって退場門へ向かう間、二組の連中の所へ行って、あの女子を怒鳴りつけてやろうと考えていた。
だけど、それは頭の中の妄想だった。実際には、わたしはクラスメイトたちと一緒に、自分たちの応援席へ戻っていた。
すぐ隣が二組の応援席だ。可哀想な転校生は後ろの方に、独りぼっちでしょんぼり座っていた。声をかけてあげたい衝動に駆られながら、わたしは何もしてあげられなかった。頭の中では一生懸命慰めてあげるのだけど、実際には横目で見るだけだ。
次は全学年男子の騎馬戦で、男子たちは入場門へ移動していた。応援席は女子だけだ。早速みんなは真弓を取り囲み、どうやって一位になったのかとようやく説明を求めた。
誰も見ていなかったことに、真弓はがっかりした様子だったけど、すぐに得意げに喋り始めた。
「残り物に福ありって言うけど、あれ、ほんとね。あたし、運がよかったのよ。あたしが一番最後に拾った紙にはね、イケメンって書いてあったの」
イケメン?――みんなが口を揃えて聞き返すと、そうよと真弓は澄まし顔で答えた。
アナウンスが聞こえ、全学年の男子が入場門から走って出て来た。うちのクラスの男子たちの中に、谷山の姿が見えた。嫌な気分だったわたしは少しだけ胸が熱くなった。
「イケメンって誰?」
百合子が尋ねた。
「誰だと思う?」
真弓がもったいをつけると、焦らさないでとみんなが文句を言った。その不平を心地よさげに聞いたあと、借り物競走に出た一年生男子だと真弓は言った。
みんなは驚いて互いに顔を見交わした。いったい誰が出ていたのかと確認し合ったり、果たして本当にイケメンがいたのかと議論したりで、とても男子の応援どころではない。
始まっている競技の方へ目を向けても、それは競技を見ているのではない。借り物競走に出た選手の顔を確かめるためだ。でも、わたしはちゃんと谷山の姿を見つめていた。
騎馬戦は三人が組んで騎馬になり、敵とはちまきを奪い合う者を上にかつぐ。谷山は騎馬の先頭だから、すぐに見分けがつくし、何よりかっこいい。
「イケメンって、うちのクラスじゃないよね?」
誰かが尋ねた。それはそうだろう。うちのクラスでイケメンと言えば、谷山に決まってる。だけど、谷山は借り物競走には出ていない。つまり、他のクラスの男子ってことだ。
でも、そんなことはどうでもいい。谷山の騎馬が他のクラスの騎馬と争っている。そこへ別の敵の騎馬が加わって、谷山の騎馬はピンチだった。手に汗握るとはこのことだ。
「ちょっと春花、あんた、人の話を聞いてないの?」
真弓が不機嫌そうに、わたしに声をかけた。わたしは慌てて真弓に微笑んだ。
「ちゃんと聞いてるよ。目は男子を見てるけど、耳は話を聞いてるから」
「じゃあ、言ってみてよ。あたしが選んだイケメンが何組の子か」
「え? えっと、二組だっけ、三組だっけ?」
「ほら、聞いてないじゃないのよ。どうせ、谷山に見とれてたんでしょ?」
「え? な、何言ってんの? 違うって」
そう言いながら、わたしは顔中が熱くなった。他の女子たちはわたしをからかったり、谷山くんは女子全員のものだからね――と釘を刺したりした。
わたしは何度も真弓の言葉を否定しながら、下を向くしかなかった。横目で競技を見ると、谷山たちがかついだ男子が、敵にはちまきを取られたらしい。谷山たちはうなだれながら、運動場の端へ移動して行った。
わたしは自分が応援できなかったから、谷山たちが負けたと思った。でも、みんなは谷山のことなど、どうでもいいみたい。真弓が指差す三組の騎馬グループを、必死で見つけようとしていた。
それは前田健二という男子をかついだ騎馬で、最後まで残るために争いを避け続けているようだ。真弓が言うイケメンとは、この前田のことらしい。
わたしは前田も小学校から知っている。でも、とてもイケメンという感じではない。ただ前田の名誉のために言うけれど、前田は決して変な顔をしているわけじゃない。そうではなくて、前田はイケメンかと言われると、首を傾げたくなるだけだ。
他の女子たちも、どうして前田がイケメンなのかと真弓を問い詰めた。
真弓は両手を上げて騒ぐみんなを静かにさせ、それから得意げな顔で説明した。
「あのさ、誰がイケメンかって、そんなの見る人の好みでしょ? だからね、誰を連れて行ったところで、あたしがこの人はイケメンだって言い張れば、それで通るのよ。あの子がさ、たまたまゴールの一番近くにいたから声をかけたの。あなた、イケメンだから一緒に来て――てね。そしたら敵なのにさ、あの子、喜んで来てくれたってわけ」
みんな口をあんぐり開けたまま声も出なかった。ただ百合子だけが大きくうなずいた。
「なるほどね。その手があったか。さすがは真弓ね」
感心する百合子に、でしょ?――と真弓はうれしそうに笑った。
確かに、真弓の咄嗟の判断には感心するしかない。だけど、頭の中から可哀想な転校生のことが離れない。それにもう一つ気になったのは前田のことだ。
前田はわたし同様、高層マンションに憧れていた。そのマンションに住む真弓は、多くの男子生徒から人気があり、前田もその中の一人らしいのだ。
前田はイケメンじゃないけど、結構純粋でいいやつだ。だから今回のことで、妙なことにならないかとわたしは心配だった。
屋上でのお弁当
運動会も午前の部が終わり、昼の休憩時間になった。生徒たちはそれぞれの家族の所へ散って行った。家族の応援席や体育館など、あちらこちらに分かれての昼食だ。親しかった生徒たちも、このときだけはバラバラだ。
朝に持たされた弁当箱と水筒を手にさげて、わたしは母の姿を探して回った。だけど、どこにも母はいなかった。母は万が一と言ったけど、ほんとはお昼に間に合わないとわかっていたに違いない。だから、わたしに弁当を持たせたのだろう。
わたしはがっかりしながら、弁当を食べる場所を探した。独りぼっちで食べているところなんか、誰にも見られたくない。なのに、どこへ行っても誰かがいた。
いくら朝ごはんを食べないことに慣れたって、お昼になればお腹が空くし、今日は身体をいっぱい動かした。お腹はぐぅぐぅ言っている。でも、このままでは弁当を食べられずに、午後の競技を迎えることになってしまう。
困ったなと思って校舎を眺めたわたしは、いいことを思いついた。今は教室の中には誰もいないはずだ。
わたしはそっと校舎に忍び込むと、教室へ向かった。
外は賑やかだけど、校舎の中は別世界みたいにひっそりしている。ひんやりした廊下を歩いて一年一組の教室へ行くと、思ったとおり誰もいない。
だけど一年生の教室は一階なので、窓から中が見える。おーいと誰かに呼びかけながら走る男子生徒の姿が窓の向こうに見えると、わたしは教室から廊下に出た。
一階はだめだ。だけど、さすがに他の学年の教室に無断で入るわけには行かない。どうしようと思いながら、足が勝手に階段を上がって行った。途中の薄暗い二階と三階の廊下は、やっぱりわたしを拒絶しているようだったので、足は自然と屋上へ向かった。
でも、屋上に出る扉は鍵がかけられているかもしれない。いや、絶対にかけられているはずだ。
屋上の入り口に着いたわたしは、試しに扉のノブを握って回してみた。すると、驚いたことに扉はガチャリと開いた。
気持ちのよい青空が目に飛び込むと、ようやく居場所を見つけた喜びが、わたしの胸に広がった。
わたしは胸を弾ませて、屋上へ足を踏み出した。だけど次の瞬間、その喜びは凍りついた。何と、そこには先客がいた。でも、すぐにわたしは気を取り直した。
先客の女子生徒は、運動場からは見えない側のフェンスに、背中をもたせかけて一人でパンをかじっていた。はいているズボンは紫色だ。
この子は二組でいじめを受けている。そのことに気がついたとき、わたしは憤慨したはずだった。でも、結局はこの子を助ける勇気がなかった。
ちょっと谷山に気持ちが惹かれたりもしたけれど、あれは自分の責任から逃げていたんだと気がついていた。そんなわたしに神さまは、もう一度責任を果たすチャンスを与えてくれたに違いなかった。
扉の音が聞こえたからだろう。転校生は驚いたようにこっちを見ていた。目が合ったわたしは覚悟を決めた。静かに扉を閉めると、前に出ながら明るく声をかけた。
「ごめんね。誰もいないと思ったんだ」
転校生は慌てたように食べかけのパンを袋に仕舞い、黙ってわたしの横をすり抜けた。わたしは振り返って、扉のノブに手をかけた転校生に話しかけた。
「ねぇ、よかったら一緒に食べない? わたし、独りぼっちで食べないといけないからここへ来たんだけど、やっぱり一人より二人の方がいいからさ」
転校生はノブを握ったまま動かない。わたしはもう一声かけた。
「お願い、一緒に食べて。助けると思ってさ」
転校生はノブから手を離さないまま、怪訝そうな顔だけをこちらへ向けた。
「助ける?」
初めて聞いた声は、わたしたちの言葉と少しイントネーションが違う。でも、そんなことは気にしないで、わたしは話を続けた。
「今日ね、ほんとはお母さんが見に来てくれるはずだったんだ。だけど仕事の方が大事みたいで、やっぱり来られないって、今朝になって言われたの」
転校生はノブから手を離すと、真っ直ぐわたしの方を向いた。
「わたしには高校生の兄貴がいるんだけどさ。両親は兄貴のことばっかり大事にしてね、わたしのことなんか、一つも大事に思ってくれないんだ。かっこ悪い話だよね。あれ? 何で初めて会った子にこんな話するんだろ。誰にも言ったことないのに……」
それは本当のことだった。真弓たちだけでなく他の友だちの前でも、自分の弱味になるような話はしてこなかった。それなのに、この転校生には口が勝手に喋ってしまう。
おまけに悲しい気持ちが込み上げて来て、涙までこぼれてしまった。そんな自分に焦りながらも、わたしは出始めた涙を止めることができなかった。
転校生は扉から離れ、うなだれるわたしの肩を抱いてくれた。
「泣かいでもええよ。うちでよかったら、話聞くけん」
初めて聞く言葉だった。西の方の言葉みたいだけど、何だか温かい響きがある。
転校生は辺りを見回したけど、屋上だから椅子なんてない。それでフェンス近くに座ることになって、わたしたちは互いに向き合って腰を下ろした。
泣いてしまったことが恥ずかしく、弁当と水筒を下に置くと、わたしは両手で涙を拭った。そのあと何を喋ればいいのかわからず黙っていると、向こうから話しかけて来た。
「うちは一年二組の兵頭久実って言うんよ。愛媛から転校して来たん」
「愛媛? 愛媛って――」
「やっぱり、わからんか。愛媛はな、四国にあるんよ。四国はわかるやろ?」
わたしは日本地図を思い浮かべながら、どこが四国だったっけと考えた。久実は苦笑して、わたしたちが座っている所に、指で日本地図を描いた。
「日本て、ここが北海道で、ここが本州じゃろ? ここが九州でな、ここが四国や」
土の上じゃないから、コンクリートを指でなぞっても地図は描けない。わたしは久実の指の軌跡を目に焼きつけて、実際にはない地図で、久実が指差す四国の位置を確かめた。
久実はもう一度四国を指で描いたあと、九州と本州が接する部分と、海を挟んで向き合った所を指し示し、そこが愛媛だと教えてくれた。
うなずくわたしに、久実は愛媛はミカンで有名だと言った。なるほど、それなら聞いたことがある。わたしがもう一度うなずくと、久実はうれしそうに笑った。
その笑顔がとても可愛いくて、わたしは久実が好きになった。それに、さっきまではいじめられて落ち込んでいただろうに、その久実が笑顔を見せてくれたことは、わたしには何よりうれしかった。
「わたしは白鳥春花。一年一組なんだ」
「じゃあ、お隣のクラスなんじゃね」
「うん、お隣。クラスは違うけど、たった今からわたしたちは友だちだね」
「友だち?」
久実はちょっと戸惑ったのか、返事を返してくれなかった。
「迷惑……かな?」
わたしが困ると、久実は慌てた様子で首を横に振った。
「ううん、迷惑なんかやないけん。ただな……」
「ただ?」
「ただ、うちなんぞが友だちで構んのじゃろかて思たけん……」
久実の言葉はわからない所もあるけれど、何を言いたいのかは理解できた。
「あの……、あなたのこと、久実って呼んでもいい?」
久実はちょっとだけ驚いた顔を見せたけど、こくりとうなずいた。わたしは久実に、自分のことは春花と呼ぶよう頼んだ。
久実は遠慮がちに、春花――とわたしに呼びかけ、わたしは明るく返事をした。うれしそうな久実に、今度はわたしが、久実――と呼びかけた。久実は丁寧に、はい――と答えた。
二人の心の間に、見えない橋が架かったみたいな気がした。運動会より仕事を優先した母に、わたしは感謝したい気持ちになった。
「わたしね、久実が初めてなんだ。さっきみたいに本音の話ができたのは」
「何で、うちに?」
「わかんない。わかんないけど、こんなこと、初めてなの。他の人と喋るときは、こんなこと言ったら何て言われるかな、こう言ったら嫌われるかなって、気を遣ってばっかりでね。楽しそうなふりはするけど、ほんとは楽しくないって言うか、何か自分が思ってる友だちっていうのとは、ちょっと違うかなって思ってたんだ」
久美は真剣な顔でわたしを見ながら言った。
「わかるよ。春花のその気持ち、うち、わかる」
「ほんとに? ほんとに、わかってくれる?」
「うん。うちもね、同しこと思いよった」
気持ちが通じ合うって、何てうれしいんだろう。そう、わたしはこんな友だちが欲しかったんだ。
わたしは家のことや自分の友だちのこと、自分が何も取り柄がなくて自信がないことなんかを、夢中になって久美に喋った。
久実は何度もうなずきながら話を聞いてくれて、自分だって何もできないし、本当の友だちなんかいなかったと言った。
「ところで、久美はどうしてこっちの学校に転校して来たの? やっぱりお父さんの仕事の関係?」
わたしの問いかけに、久美は困ったような顔を見せたが、すぐに笑顔で言った。
「まぁ、そがぁなとこかな。ほんでも、うっとこもお父ちゃん忙しいけん、ほとんど母子家庭なんよ」
「ほんとに? じゃあ、わたしと似たようなもんだね」
「ほうじゃねぇ」
はにかんだように笑う久美に、今日はお母さんは一緒じゃないのかとわたしは尋ねた。
久美は笑みを消すと、母親は昨日から熱を出して寝込んでいると言った。
「せっかくの運動会だけど、それどころじゃないね。でもお母さん、運動会を見に来られなくて残念がってたんじゃない?」
「まぁね。ほんでも、お母ちゃんに見せられるほどのもんやないけん」
少し目を伏せがちに久美は言った。久美が言ったのは一〇〇メートル走や創作ダンスのことだろう。自分が活躍できる競技なら親にも見て欲しいけど、悲惨な結果がわかっているものは見せたくない。ましてや、いじめられているところなんか、絶対に見られたくない。
わたしは久美がいじめられていることには触れず、転校して来たばかりなのに、あれだけできたのはすごいと久美を褒めた。
久美は出たくないのを無理に出されたと言ったけど、それでも出たことはすごいとわたしは褒めまくった。
「わたしだったら仮病になって休んじゃうよ。それを出たんだもん、久美は偉いよ」
「そがぁ言うてくれるんは春花ぎりやで」
「ぎりって?」
少し困ったように笑うと、何々だけという意味だと久美は言った。
「ほやけん、春花ぎりじゃて言うんは、春花だけやていう意味なんよ」
「なるほど、ぎりか」
うなずくわたしに、久美は言った。
「うち、最初は運動会休むつもりやったんよ。ほんで、お母ちゃんにそがぁ言うたら、休んだらいけんて怒られてな。しょうことなしに来たけんど、ほんでも来てよかったわい。こがいして春花と知り合うことができたんやもん」
やっぱり久美の言葉は少しわかりにくい。それでもわたしは一生懸命に耳を傾け、久美の気持ちを喜んだ。
「そう言ってもらえたらうれしいな。ねぇ、つい喋ってばっかりになったけどさ。そろそろお昼ご飯を食べようよ。久美はお母さんが熱出しちゃったから、コンビニでパンを買ったんでしょ? よかったら、わたしのお弁当を半分こしようよ」
「え? ほんなん悪いわ」
「悪くなんかないよ。それに久美が持ってたパン、わたし好きなんだ。だから、そのパンを半分くれたら、交換したことになるじゃん。ね、そうしよ?」
「ほやかて、食べさしやで?」
「いいじゃん、友だちなんだから」
わたしにうながされて、久美は食べかけのパンを袋から取り出した。
「ほんまに、こんなんで構んの? さらのパンがあったらよかったけんど、うち、これしか買うてなかったけん」
「さらのパンって?」
「あれ? こっちではそがぁ言わんの? まだ食べとらん新しいパンのことや」
「へぇ、新しいことを、さらって言うんだ。面白いね」
笑うわたしの顔を、久実はじっと見つめた。
「何? どうしたの?」
「うちの言葉、変?」
「変じゃないよ。こっちの言葉と違うだけでしょ? そんなの、住んでた所が違うんだから、当たり前じゃん」
もし喋った相手が久実でなければ、慣れない言葉を変だと思ったかもしれない。でも、久実のお陰でそんな風には思わないで、方言を面白いと受け止めることができた。それでも久実は、まだ半信半疑の様子だ。
「ほやけど、変な感じがするやろ?」
「だから、変じゃないってば。面白いねって言ったのも、そういう意味で言ったんじゃないよ。同じことを表現するのに、違う言い方があるって面白いと思わない?」
「ほれは、ほうやけんど……」
「二組の子たちは、久美の言葉、変って言うの?」
久美はうなだれるようにうなずいた。わたしは久美の肩をポンとたたいて、気にしないの――と励ました。
「言いたい人には言わせておけばいいよ。わたしは久美の言葉、柔らかくて温かい感じがするから好きだな」
「ほんまに?」
「ほんまほんま」
久美の言葉を真似て答えると、久美はようやく笑ってくれた。
「それじゃあ、そのパンもらうね。代わりに、こっちのお弁当を半分食べて」
わたしは久美から食べかけのパンを受け取ると、自分の弁当箱を久美に渡した。弁当の蓋を開けた久美は、美味そうや!――とうれしそうな声を上げた。特に久美が注目したのは、毎度お馴染みのタコさんウィンナーだ。
「このタコさんウィンナーな、うち、憧れよったんよ」
「こんなもの、どこの家だって作るでしょ? 久美の家では違うの?」
「うっとこのウィンナーは、ただ切れ目を三本ほど入れて炒めるぎりなんよ。ほやけん、他の人の弁当にこれが入っとるん見よってな、食べてみたいなぁて思いよった」
「お母さんに作ってって言えばよかったのに」
「言うたんやけどな。ほんときはわかった言うんよ。ほやけど、いざこさえるときには、いつものウィンナーなんよ。ほやけん、いつか自分でこさえよて思いよったけど、まだこさえとらんのよ」
「うちの親もそんなとこある。よかったら、タコさんウィンナーは全部食べてもいいよ」
「全部もらうわけにはいけんよ。半分この約束やけん」
久美はタコさんウィンナーを一つ口に頬張ると、よく味わうように口を動かした。
しばらくしてウィンナーを飲み込んだ久美に、わたしは感想を聞いてみた。久美はウィンナーの味だったと答えた。それはそうだとわたしが笑うと、当たり前やったね――と久美も笑った。
他のおかずは定番の卵焼きと、昨夜の残りの鳥の唐揚げ。それにミニトマトとブロッコリーだ。わたしは野菜が嫌いなので、ブロッコリーは全部久実に食べてもらった。それだけでも、今日久実と友だちになれたのはラッキーだ。
ブロッコリー以外を半分食べた久実は、ごちそうさまでした――と満足そうに両手を合わせた。
「ああ、美味しかった。春花のお母ちゃんに会うたら、お礼を言わないけんね」
「だめだよ。そんなことしたら、ブロッコリーを食べてもらったってわかっちゃうよ」
「あ、ほうか。ほら、いけんね」
久美が笑い、わたしも笑った。
わたしは卵焼きを食べたあと、残っていたタコさんウィンナーを箸に取り、久実の顔の前に持って行った。
「ほら、あげるよ」
「いけんよ。自分で食べや」
「いいから食べなよ」
「ほんまに、ええの?」
「ほんまほんま」
久実はにっこり笑うと、パクリとウインナーを食べた。うれしそうな久実の顔を見ていると、少しも惜しいと思わない。
わたしは唐揚げとご飯をパクパク食べると、最後にミニトマトを口に放り込んだ。噛んだ瞬間、ガシュッと口の中に甘酸っぱい汁が弾けた。いつもは大して美味しいと思わないトマトだけど、今日のは甘くて美味しかった。
今何時だろうと思ったけど、時計なんか持っていない。校舎の壁には大きな時計があるけど、屋上からではわからない。それに下手にのぞいて、屋上にいるのを誰かに見られたら大変だ。屋上には勝手に出入りしてはいけない決まりがあるから、先生に大目玉を食らってしまう。
だけど出入り禁止のはずの屋上の扉の鍵が開いていて、久実が一人でここにいたなんて偶然とは思えない。そのことを久実に話すと、久実も同じ気持ちだと言ってくれた。
きっとわたしたちは出会う前から何かで結ばれていて、ここでこうして出会う運命だったに違いない。そう言うと、久実は喜んでくれたけど、少し悲しそうな顔になった。
「どうしたの? 何でそんな顔するの?」
「ほんまは、うちなんか春花の友だちにはなれんのに」
「なんで? なんでそんなこと言うの?」
「ほやかて……」
久美が黙ってしまったので、わたしは久美が初めてできた本当の友だちだし、久美と友だちになれたことが、ほんとにうれしいと熱く語った。
久美は目を伏せたまま、だんだん――と言った。
「だんだんって?」
「ありがとて言う意味や。丁寧に言うたらな、だんだんありがとうて言うんよ」
「そうなんだ。じゃあ、あたしも言うよ。久美、あたしと友だちになってくれて、だんだんありがとう」
久美はようやく笑顔に戻って、さっきの言葉のことを謝った。
「妙なこと言うて堪忍な。春花と友だちになれたこと、うち、ほんまにうれしいんよ」
「よかった。それじゃあ、約束だよ。今日からわたしたちは親友だからね」
わたしが右手の小指を出すと、久実はちょっとだけ戸惑い、それから自分の小指を出した。
「指切りげんまん。二人は親友だよ」
わたしたちは互いの小指を絡めた手を、何度か小さく振った。わたしは満足したけど、久実は立てたままの小指を悲しげに見つめていた。
でも、わたしが見ていることに気がつくと、久美は慌てたように指を引っ込めてにっこり笑った。
鏡の中のわたし
「今日はがんばったね。あなたがリレーに出るなんて、お母さん、鼻が高いわ」
スーパーで買ったお寿司をつまみながら、母はわたしを褒めてくれた。だけどわたしには、運動会を見に来るのが遅くなった言い訳をしているように聞こえた。
それでもリレーは見てもらえたのだ。文句を言うのはやめにしよう。正直、走る姿を母に見てもらえたことは、わたしもうれしかった。
驚いたのは、兄貴までもが駆けつけてくれたことだ。何でも、部活の練習が午前中で終わったので、同じ中学校の卒業生たちと一緒にのぞきに来たそうだ。
いつもの兄貴はわたしなんかに関心がない。だから来てくれるとはこれっぽっちも思っていなかった。だけど朝食のときに、わたしが午後の部でリレーに出ると母から聞かされて、絶対に見に行くと母には言ったらしい。
そんなこと、わたしはちっとも知らないから、リレーが終わってクラスの席に戻ったとき、兄貴が仲間と声をかけに来てくれたので、びっくりしたしうれしかった。
だけど家に帰って来ると、兄貴はいつもの素っ気ない兄貴に戻っていた。
兄貴は三つ目のマグロを口に放り込むと、口をもぐもぐさせながら言った。
「ほんと、大したもんだ。どん亀のお前がリレーに出るなんてな。それにしても、なんでお前なんかがリレー選手に選ばれたんだ?」
昼間の兄貴はどこへ行ってしまったんだろう? 自分が運動が得意だからって、偉そうに上から目線で言わないで欲しい。それにマグロは一人二つのはずだ。忘れているのか、わかった上で食べているのか。兄貴のことだから、絶対にわかって食べている。
わたしは急いで自分のマグロを確保すると、くじ引きだと言った。
口の中身を飲み込んだ兄貴は、驚いた顔をした。
「くじ引き? お前のクラス、みんな勝ちたくないの?」
兄貴の言い分は当然で、わたしだってそう思ってた。だけど、山田早紀以外は誰も手を上げなかったから仕方がない。それでも当たりくじを引いたときには、人生終わったと思ったほど気分は落ち込んだし、わたしに決まったことで、もうだめだと言うやつもいた。
だけど、走ってみたら楽しかった。あれだったら、もう一度走ってもいいくらいだ。それは走るのが好きになったということではない。楽しかったのには理由があった。
男女混合リレーは男女が交互に走る。選手は五人で、わたしは第四走者だった。
第一走者の男子は三位だったけど、第二走者の山田早紀の活躍で、第三走者の男子は、なんと一位で走って来た。だけどバトンを渡されたときに、わたしはバトンを落としてしまい、おまけに足が遅いから一番びりになった。
それでも、最後の走者である谷山健一郎が猛ダッシュで走り、二位の二組を追い抜いて、一位の三組とデッドヒートとなったのはすごかった。
結局、うちのクラスは二位に終わった。わたしがバトンを落としてなければ、一位になれたのにという非難の視線が、何人かの女子からわたしに向けられた。それで、とても肩身の狭い思いをしていたところに、兄貴が来てわたしをねぎらってくれたわけだ。お陰で女子たちの雰囲気もガラリと変わった。これについては兄貴に感謝するべきだろう。
だけど本当はそれほどには落ち込んではいなかった。
競技が終わったあと、谷山がわたしをかばって慰めてくれた。何人かの女子がわたしをにらんだのは、それに対するやきもちもあったのかもしれない。
もっとうれしかったのは、二組の第四走者が久実だったことだ。
足が遅い久実が一〇〇メートル走に出されたのは、二組の生徒からの嫌がらせだ。でも、リレーにわざわざ足の遅い者を選ぶとは思えなかった。
最初は久実もわたしみたいに、偶然くじ引きで決まったのだろうかと思っていた。だけど久実から話を聞くと、本当は別の子が出る予定になっていたらしい。ところが、その子が昼休み中に走り回って転んでしまい、足を挫いたために先生の指名で久美が急遽出場することになったと言う。
それにしても、先生までもが久実に恥をかかせようとしたのかと、わたしは心の中で憤慨した。でも事実はそうじゃなくて、急なことで誰も競技に出たがらず、困った先生が仕方なく、一〇〇メートル走に出場した久実に頼んだらしい。
もちろん久実は初めは辞退したそうだ。だけど、先生に何度も頭を下げられて断れなかったみたい。それで、負けても構わないという約束で出たところが、隣にわたしがいたというわけだ。
屋上で一緒にお弁当を食べたときには、お互い他の話に夢中だったので、午後のリレーに出ることを、わたしは久実には話していなかった。だから、久美もとても驚いていた。
競技前に入場門に集まったとき、お互いの存在を知ったわたしと久実は、手を取り合って喜んだ。それを見た周囲の他の子たちは、一様に妙な目をわたしたちに向けた。それでもわたしたちはそんなことは気にせず、一緒になれたことや、お互いに足が遅いことではしゃぎ続けた。
わたしはバトンを落としたけど、久実はバトンを落とさなかった。だけど、ちゃんと受け取るのに手間取ってしまい、わたしと久実は、ほとんど同じような位置関係で走ることになった。でも正確に言えば、久実の方がちょっとだけ速かった。それで、わたしはビリだったわけだ。
最終走者にバトンを渡したあと、わたしと久実は互いの健闘を讃え合った。走るのがこんなに楽しかったのは初めてだと久実は言ったけど、わたしもまったく同感だった。
でも、ライバルであるはずの久実とはしゃいでいたことは、他の選手たちには面白くなかったらしい。競技が終わったあと、もっと真面目にやれと早紀に文句を言われた。だからわたしは、久美が転校生でまだ新しい学校に馴染んでいないからと説明した。
すると、お前はいいやつだな――と谷山が褒めてくれた。谷山の方こそ、ほんとにいいやつだ。
そんな経緯は母にも兄貴にも話していない。でも二人とも見るものはしっかり見ていたらしい。わたしが親しくしていた紫色のズボンの生徒は誰なのかと、母は興味深げに聞いた。兄貴も寿司に手を伸ばすのをやめて、わたしの言葉を待った。
わたしは久実のことを説明し、二人で一緒に屋上でお弁当を食べた話もした。すると母は、これからも力になってあげるようにと言ってくれた。
兄貴もわたしを褒めてくれた。それはわたしたちが出入り禁止の屋上で、勝手にお弁当を食べたということに対してだ。さすがはオレの妹だと兄貴は言うんだけど、久美のことは褒めてもらうようなことじゃないから、まぁいいか。
ところでさ――と兄貴はわたしのマグロに手を伸ばしながら言った。わたしがマグロを避難させると、兄貴は隣にあったハマチを取った。それもわたしの取り分だ。
「ちょっと、お兄ちゃん。それ、わたしのハマチでしょ?」
「お前がマグロしか取らないから、いらないって思ったんだよ」
兄貴は惚けながらハマチを口に放り込んだ。そのままもぐもぐしている兄貴に、何がところでなの?――と母が言った。
兄貴はハマチを飲み込むと、にらんでいるわたしに言った。
「お前がバトンを渡した最終ランナーさ、あいつ、お前に気があるんじゃないのか?」
「え? なんで?」
「オレ、お前に声をかける前に見てたんだけど、あいつ、お前のことを慰めてただろ? 他のやつらがいる前であんな風に慰めるのって、そうはいないぜ。たぶん、あいつ、お前に惚れてるな。間違いない」
わたしは顔がカーッと熱くなった。熱は頭の中にも浸透し、焦げつきそうになった思考回路が、反射的にわたしに言い返させた。
「何があいつよ。そんな上から目線で言うなんて、谷山くんに失礼でしょ!」
「何、むきになってんだよ。もしかして、お前もあいつに惚れてるのか?」
「何でわたしが、あんなやつに惚れないといけないのよ。あいつはね、誰にだって優しいの。だから、クラスの女の子には一番人気があるし、わたしなんかが好きになったって、その――」
「お前、自分が何喋ってんのか、わかってる? 支離滅裂だぞ」
まあまあ、いいじゃないの――と母が二人の間に割って入った。
「いいわよね、青春って。そんな風にしてられるのも、今のうちだけよ。現実はきびしいんだって、大人になって社会に出たらわかるから」
母はもっと食べろとうながした。
それでわたしがハマチにしようか、サーモンにしようかと迷っていると、パッと兄貴がわたしのサーモンをつまんで口に放り込んだ。あっと思っていると、兄貴は頬を大きく膨らませたままハマチも取った。さっきも取ったから、もうわたしのハマチはない。
「もう怒った!」
わたしは立ち上がると、兄貴の前に残っていた寿司を、三つまとめてつかむと、そのまま口に詰め込んだ。もう何を食べてるのかわからない。これは戦争だ。
ところが兄貴はやり返さなかった。口の周りを飯粒だらけにして、ふぐみたいになったわたしを見て、腹を抱えて笑った。
「これがお年頃の娘かよ……、その顔……、谷山ってやつに見せてやれ……」
「二人とも好い加減になさいね!」
母が怒りながら噴き出した。ひどいよ、お母さんまで!
わたしは二人の前から逃げて洗面所へ行った。だけど、口に入れた物を吐き出すわけにはいかず、そのまま鏡を見ながらもぐもぐ食べた。急いで飲み込みたいけど、喉に詰まりそうになるから、少しずつしか飲み込めない。
鏡に映った自分を見ると、確かにおかしい。自分でも笑いそうになったり泣きそうになったりしながら、わたしは何とか口の中の物を飲み込み終えた。
わたしが洗面所にいる間に、笑いが収まった兄貴は母と喋っていた。兄貴は父と母がどこで知り合ったのかと聞き、お見合いをしたと母は言った。
「こっちで暮らしてた伯母が世話好きな人でね、この人なら絶対に間違いないからって言うから、あんまり深く考えないままお見合いして、その流れで結婚したのよ。その頃は、周囲の人たちが次々にお見合い結婚してさ。そうするのが普通なんだって思ってたの」
わたしが洗面所から戻っても、兄貴は関心がないみたいに母との会話を続けた。
「その結果は? 伯母さんの言うとおりだった?」
母は質問に答える前に、わたしにお寿司は一つずつ食べるようにと釘を刺した。
わたしの前には、兄貴に取られたはずのハマチとサーモンがあった。母が自分の分を置いてくれたようだ。
「お母さん――」
「いいから食べなさい。これは、がんばったあなたへのご褒美よ。だけど、一つずつよ」
もう一度母が念を押すと、さっきのわたしの顔を思い出したのか、兄貴がまた笑い出した。
わたしは兄貴をにらんだあと、お見合いの話?――と母に尋ねた。
うなずいた母は兄貴に顔を向け、伯母さんの言うとおりだったと言った。
「あなたたちのお父さんは、ほんとにいい人よ。あなたたちのために、身を粉にして働いてくれてるでしょ?」
この言い方が少しわたしを刺激した。あなたたちのためにじゃなくて、兄貴のためなのに。わたしはちょっと皮肉を込めて母に聞いた。
「ねぇ、お兄ちゃんは大学へ行くんでしょ? わたしも大学に行ってもいい?」
「何言ってんのよ。まだ高校も入ってないのに、なんで大学なの? その前に高校へ入んないといけないでしょ? ちゃんと勉強してるの?」
兄貴が一緒になって偉そうに言った。
「そうだぞ。お前の成績だと入れる高校だって限られるぞ。て言うか、入れないかもな」
「あ、お兄ちゃんまでそんなこと言う?」
「お兄ちゃんだから言ってんの!」
母は笑いながら、わたしたちをなだめた。
「まあ、学校がすべてじゃないからね。大学なんか行かなくたって、生きて行く道はいくらでもあるから」
「それって、わたしなんか大学へ行かなくてもいいってこと?」
「無理に行く必要はないって言ってるの。大学に入るのは大変でしょ?」
「そうそう。他に好きなことができるかもしれないし、好きな男ができるかも――」
あ、もう好きな男はいたか――と兄貴はわざとらしく自分の頭をたたいて笑った。
わたしは兄貴をにらみつけ、兄貴の前にあった寿司を二つ取った。それは兄貴の好物のイカとウニだ。
「あ、やりやがったな!」
イカとウニを続けて口に入れたわたしは、兄貴を挑発した。
「だまぁみど、ブヮーカ!」
「ちょっと、春ちゃん。女の子なのに下品よ」
「母さん、これはそういう問題じゃない!」
兄貴がこちらの寿司に手を伸ばそうとするのを、わたしは両手でブロックした。
「何だよ、こいつ。ダイエットしてたんじゃねぇのかよ!」
はっとしたけど、もう遅い。でも、たまにお寿司ぐらい、たくさん食べたって大丈夫だろう。それに今日はめでたい日だ。久美という親友ができたのだから。久美は今、どうしてるんだろう? お母さんの熱は下がったのかな?
わたしは兄貴を警戒しながら、ゆっくりと口の中身を飲み込み考えた。
もし久美のお母さんの熱が下がっていなければ、せっかくの日なのに久美たちはコンビニ弁当かもしれない。それでも久実はきっと、運動会が楽しかったとお母さんに報告しているだろう。そのことは、何よりお母さんを喜ばせたに違いない。
ダイエットなんかするもんじゃない。この夜は食べ過ぎて具合が悪かった。だって、母の分まで食べてしまったのだから。いくらご褒美だからって、母への配慮が欠けていた。それでバチが当たったのだろう。
わたしは布団の中でお腹をさすりながら、何度も身体の向きを変えた。
どうしても眠れないので、わたしはベッドの上に起きると、枕元の電気をつけた。すぐ横の机の上に、小さな鏡が置いてある。それを手に取り、わたしは自分の顔を映した。
薄暗い部屋の中に、ぼんやりと浮かび上がった顔。痩せたようでも、やっぱり丸い。もしかしたら、お寿司を食べすぎたから、顔が元に戻ってしまったのだろうか?
こんなことでは、真弓たちに何を言われるかわからない。それに谷山だって、やっぱりスラッとしたきれいな子がいいんだろうな。
久美と友だちになれたことや、谷山と一緒に二人三脚とリレーに出られたことで、少し有頂天になっていた。よく考えてみれば、わたしは何も変わっていない。
わたしはちっとも可愛くないし、勉強も運動もだめだ。
兄貴も谷山もイケメンで女の子たちから人気だし、真弓も百合子も美人だから、何をやっても許される。だけど、わたしはそうじゃない。
わたしは顔の角度を変えながら、鏡に映った顔を眺め続けた。下から照らす明かりのせいで、鼻や顔の窪みが大きな影を作り、昼間見ても変な顔が余計に変に見えて来る。もう口にお寿司は詰め込んでいないのに、あのときと同じみたいな顔だ。
「ブス」
わたしは鏡の中の自分に悪態をついた。
――あなた、わたしが嫌いなの?
悲しそうな顔をした鏡の中のわたしが言った。本当は自分の独り言だ。
「嫌いだよ、お前なんか。何で、もっと可愛く産まれて来なかったのさ。可愛かったら、勉強ができなくたって、運動が苦手だって、みんなが優しくしてくれるのに」
――本当にそう思ってるの?
一瞬怒ったように見えた鏡の中の顔が、泣き出しそうな顔になった。
ただの鏡遊びのはずなのに、胸の中に悲しみが込み上げて来る。それで却ってわたしは意地になり、鏡の中の自分に文句を言い続けた。
「本当だよ。お前なんか嫌いだよ。ブスだったらブスなりに、何か取り柄があればよかったんだよ。だけど、何もないじゃん。もっと勉強できるとか、運動神経がいいとか、何か人より優れたものがあればいいのにさ。お前なんか、いいとこ一つもないじゃんか!」
鏡に怒りをぶつけながら、わたしは悲しくなって下を向いた。
――ごめんね。でもね、あなたはこの世でたった一人の、わたしの神さまなのよ。
え?――わたしはギクリとして顔を上げた。鏡の中の自分も驚いた顔をしている。
「今のは何? 今の、わたしが自分で喋ったんだよね?」
自分の問いに自分でうなずきながら、何だかすっきりしない。確かに、今のは自分で喋ってたとは思う。だけど、自分で考えて出て来た言葉じゃない。まるで、誰かがわたしの口を借りて喋ったみたいだ。いや、本当にこの口が喋ったのだろうか?
それに、神さまと言う言葉が引っかかる。前にも誰かに言われたような、そんな気がするんだけど、それがいつのことなのか思い出せない。
もしかしたら、これって魔法の鏡なのだろうか? そう思って、わたしは鏡をひっくり返したり、透かしたりして調べてみた。だけど、別に気になる所は見当たらない。そもそも百円ショップで買った鏡だから、魔法の鏡であるわけがない。
もう一度鏡の中をのぞいてみたけど、そこに映っているわたしは、何も喋ってくれなかった。
「わたし、あなたの神さまなの?」
尋ねてみたけど、やっぱり何も答えてくれない。いろいろ変な顔をしてみたら、鏡の中でも同じことをやっている。結局、全部わたしの一人芝居で、思わず出て来た言葉はただの妄想なのだろう。
わたしは鏡を机に戻すと、枕元の電気を消した。
今日はいろいろとうれしかった一日だったのに、締めくくりは切ないものになってしまった。
本当の友だち
この日は運動会でつぶれた日曜日の代休だ。だけど、母も兄貴も休みじゃない。
いつもだったら母の仕事が早番でなければ、わたしと兄貴が母に見送られて家を出る。でも、今日はわたしが二人を送り出す形になった。とは言っても貴重な休みなので、朝は布団の中でゆっくりしていたい。
結局、兄貴には挨拶もしないで、自転車が出て行く音を窓越しに確かめただけだった。
行って来るね――と下から声をかけた母は、さすがに無視ができない。布団の中から大きな声で、行ってらっしゃいと返事をした。
玄関に鍵をかける音がした。間もなくすると、駐車場のゲートが開く音が聞こえて、母の車のエンジンがかかった。いったん車が表に出たあと、今度はゲートが閉まる音。それから母が車に乗り込む音がして、車のエンジン音は遠ざかって行った。
辺りが静かになると、二度寝をしようと、しばらく布団の中で横になっていた。でも、カーテン越しの陽射しで部屋の中は明るい。それに、母に大声で返事をしたのがいけなかった。すっかり目が覚めてしまって、ちっとも眠くならなかった。仕方なく身体を起こして一階へ下りたけど、誰もいない家は何だか居心地が悪い。
今日は誰とも何の約束もしていない。わたしはスマホを持っていないから、誰かに連絡をしようと思ってもできないし、呼び出しがかかって来ることもない。
昨日の運動会が終わったあとは、みんながんばったな――と先生から褒めてもらって解散となった。真弓と百合子から一緒に帰ろうと誘われたけど、ちょっと用事があるからと言って、わたしは二人を先に帰した。だから、真弓たちと遊ぶ約束はしていない。
二人を先に返したのは、久美と一緒に帰る約束をしていたからだ。
真弓たちを先に帰した手前、久実と一緒にいるところを二人に見られるとまずい。それで、教室で少し時間をつぶしてから、わたしたちは家路に就いた。
教室でも帰り道でも、喋ったのは他愛のない話ばかりだった。それでもわたしは楽しかったし、久実も楽しかったと思う。
別れ道になってもなかなか互いに離れがたくて、どうでもいいような話を、その場に立ったまま延々と続けた。久実がお母さんのことを思い出さなければ、暗くなるまで喋っていたかもしれなかった。それほどずっと喋り続けていたのに、今日どうするのかは相談しなかった。
ほんとは今日、久実と遊ぶ約束をしたかった。だけど、久実のお母さんが具合が悪いから、久実を誘うのは遠慮した。
久美もそう思ったから、今日のことを何も言わなかったのだろう。だから、お互いの家の電話番号も教え合っていない。でも今になって、わたしは後悔していた。今日のお母さんの具合を電話で確かめてから、どうするかを決めればよかったのだ。
食堂のテーブルには、母が朝食を用意してくれていた。トーストとベーコンエッグと、わたしが嫌いなブロッコリーだ。だけど昨夜、お寿司を食べ過ぎたし、普段食べないから朝は食欲がない。
わたしは冷蔵庫から牛乳を取り出すと、コップに注いで一口だけ飲んだ。まだ寝ぼけた様子の胃袋が、冷たい牛乳が流れ込んで来て驚いているようだ。
コップを持ったまま隣のリビングへ行くと、わたしはソファーに座って、テレビのリモコンをつけた。だけど、どのチャンネルも面白い番組なんかやっていない。退屈だ。
プチンとテレビの電源を切ると、わたしはリモコンをポイッと横に投げた。するとリモコンが何かにぶつかる音がした。何だろうと思って目を遣ると、ソファーの隅に一冊の本が無造作に置かれていた。タイトルは「産まれたときの記憶」だ。
手に取ってみると、誰かが図書館で借りた本のようだ。背表紙の所に本の記号と番号が書かれたシールが貼られてある。
裏表紙をめくると、図書カードを差し込む紙ポケットがあった。その下には、兄貴の学校の判が押されてある。どうやら兄貴が学校から借りた本らしい。今日返すつもりだったのを忘れて行ったのだろう。頭はいいのに、こういうところは抜けている。
小説かなと思ってめくってみると、どうもそうではないようだ。何か科学的な本みたいで、ちょっと文章がこむずかしい。
パラパラと適当にページをめくって見ているうちに、話し言葉で書かれてある所があった。そこの少し前の方にページを戻して読んでみると、それは産まれたときのことを覚えているという人の体験談だった。
この部分は読みやすい。書かれてあるのは、母親のお腹の中にいたときのことを覚えている人や、産まれて来たときに、笑顔で迎えてくれた人たちのことを覚えているという人の話だ。とても信じられない話ばかりだけど、まだ母親のお腹の中に宿る前から、自分を産んでくれる人の様子を、宙に浮かんで眺めていたという話まであった。
わたしは馬鹿馬鹿しくなって本を閉じた。子供が読んでもわかるような作り話を、よくも真面目に取り上げるものだと、わたしは呆れながら著者を確かめた。著者は外国人のようで、名前が片仮名で書かれてある。日本人は外国人に弱いから、外国人が書いた本というだけで信じそうだ。この本を日本人が書いていたら、誰も読まないに違いない。
わたしはリモコンの隣に、本を投げ捨てるように置いた。
――こんな本を読むなんて、お兄ちゃんは頭がいいと思ってたけど、本当は大したことないんだな。
めったに味わうことのない優越感に浸ったわたしは、ソファーにもたれながら手に持った牛乳を一口飲んだ。だけど、いくらかっこをつけても、わたしが頭が悪いという事実は変わらない。
現実に戻ると、退屈がわたしにのしかかって来た。わたしは天井を見上げ、久実の名前を呼んだ。
「若草マンション。ここだな……」
わたしは四階建てのこぢんまりした古びた建物を見上げた。
結局、我慢ができずに久実の家まで来てしまった。
ここは真弓たちがいた小学校の校区になるけれど、校区の建物が全部高級マンションというわけではない。この建物にもマンションという名前がついているけど、真弓たちの家とはずいぶん違う。
見たところエレベーターはない。建物の左の端にあるらせん階段で、上がり下がりするみたいだ。久実の家があるのは三階だそうなので、わたしは階段を三階まで上がった。
三階の廊下は何にもなく、殺風景でひっそりしている。四つか五つの扉があるけど、どこも部屋の番号が書いてあるだけだ。どの表札にも名前が入っていない。久実の家が三階だとまでは聞いたけど、部屋の番号までは聞いていなかった。
わたしは何度か廊下を行ったり来たりした。そのうち誰かが出て来るんじゃないかという期待があった。だけど、どの家も留守みたいに物音一つしなかった。このどれかの扉の向こうに、久実がいるだろうにと思うと悔しかった。でも、呼び鈴を押して間違っていたら大変だ。せっかくここまで来たのにと思いながら、わたしは階段を下りた。
一階へ下りると、小さな郵便受けが並んでいる所があった。だけど、そこにも名前は一つも書かれていなかった。それに部屋の番号すら、書かれていない郵便受けもあった。
下から建物の三階を見上げたけど、久美は出て来ない。他の人でもいいからと祈ったけど、やっぱり誰も出て来なかった。わたしは久実に会うのを諦めるしかなかった。
とぼとぼと歩きながら、真弓の家にでも行ってみようかと思った。このままでは、今日一日独りぼっちで退屈だ。真弓に約束はしてないけど、行くだけ行ってみることにした。
真弓が暮らす高級マンションに着くと、わたしは下からマンションを見上げた。真弓の家は十五階。上の方だ。やっぱり、わたしとは住んでいる世界が違う。
わたしはマンションの入り口へ向かった。
真弓の家には何度か呼んでもらったことがある。だから、どこが真弓の家なのかは知っている。でも突然訪ねたりしたら、驚かれるかもしれない。もしかしたら、呼んでもないのに来るなんてと、図々しく思われる可能性もある。それに、家族で出かけて留守ということも考えられる。
不安な思いで玄関に着くと、わたしははっとなった。ここは外の人間が勝手に中に入れないよう、セキュリティがきびしいのだ。住人の許可がなければ、入り口の扉は開かないようになっている。
扉の脇を見ると、数字が書かれたボタンが並んだ機械があった。機械にはマイクとスピーカーがある。これで住人の部屋の番号を押して、中の人に許可をもらうのだ。
前にここへ遊びに来たのは、何週間か前のことだ。そのときは部屋の番号を覚えていたけど、忘れてしまった。確か初めは十五なんだけど、そのあとの数字が思い出せない。違う番号を押してしまっては大変だ。でも、番号が押せなければここから先へは進めない。
わたしはがっかりしたけど、まぁいいやと思い直すことにした。
真弓の家には百合子の他にも、同じマンションに暮らす似たような女の子たちも遊びに来る。そんな中にいれば、わたしは一人浮いてしまう。
わたしはみんなが喜ぶような話題を提供することができない。いつも誰かが何かを言い出すのを待って、それに合わせてうなずいたり、はしゃいだりするだけだ。でも、本当に楽しいと思うことはめったにない。
でも、今のわたしには久美がいる。今日は久美に会えなかったけど、だからと言って、わざわざ自分から気疲れするような所へ出向く必要はない。
わたしはマンションの玄関から外へ出た。一度だけ真弓の家を見上げたあと、わたしは自分でも驚くほど清々しい気分で自分の家に向かった。だけど歩いているうちに、だんだん退屈な気持ちが蘇り、足は次第に重くなった。
しょんぼりしながら家の近くまで戻ると、辺りをきょろきょろしている女の子がいた。久美だ!
「久美!」
わたしはうれしさに駆け出した。振り返った久美も笑顔になって駆け寄って来た。
久美はわたしの手を取ると、ほっとしたように言った。
「春花、外におったんか。うち、春花んとこに遊びに行こ思て来たけんど、どこが家なんかさっぱりわからんで往生しよったんよ」
「ほんとに? わたしも久実と遊ぼうと思って、久実のマンションまで行ったんだよ。だけど、どこの家も表札に名前が出てなかったから、わからなくて帰って来たんだ」
「ほうやったん。ほれは悪かったね。ほやけど、いつ来たん? 全然すれ違わなんだね」
真弓たちのマンションに立ち寄ったことが後ろめたくて、わたしは本当のことが言えなかった。
「帰って来る前にちょっと寄り道してたから、その間に久実が来たんだよ」
「ほうなんか。ほんでも春花が寄り道してくれたけん、よかったわい。春花が真っ直ぐ家に戻んとったら、うち、どこが春花の家かわからんまま諦めて去ぬるとこやったわ」
去ぬるとは帰るという意味だ。古風な言い方を面白く思いながら、わたしは言った。
「ほんとだね。危ないとこだった。間一髪ってやつだね」
久美は女の子なのに親父みたいな言葉を使うのがおかしかった。それで、つい喋りながら笑ってしまった。だけど、久美はそれを二人が無事に再会できて、わたしが喜んでいると思ったみたい。わたしと一緒に笑いながら、久美は二人の運のよさを喜んだ。
「へぇ、ここが春花の部屋なん……」
ベッドと机でほとんどいっぱいの狭い部屋を、久美は物珍しそうに見回した。
壁には流行の男性アイドルのポスターや、好きなアニメのカレンダーを飾ってある。でも真弓や百合子とは好みが違うみたいで、こんなのがいいのかと二人して馬鹿にされた。
果たして久美はどう反応するのだろう? どきどきしていると、久美はポスターを見つけるや否や、うれしそうに駆け寄った。
「うち、この人の大ファンなんよ。優しそうでええよね」
「やっぱり久美とわたしは気が合うんだね。この人のよさをわかる人って少ないんだ」
わたしはすっかり安心したし、うれしかったけど、カレンダーに目を移した久美は、さらにわたしを喜ばせてくれた。
「うちもこれ、大好きやった。毎週見よったよ」
「ほんと? うれしい!」
ちょっと待っててと言うと、わたしは台所へジュースとお菓子を取りに行った。こんなことは今までなかったと思うほど胸が弾んでいる。
いそいそと冷蔵庫からジュースを取り出してグラスに注ぎ、戸棚に隠していたお菓子と一緒にお盆に載せると、わたしは二階の部屋へ上がって行った。
お待たせ――と言って部屋に入ると、久美は窓の外を眺めていた。振り返った久美は、何だか暗く硬い表情に見えた。でも、それはほんの一瞬だけだった。お盆のジュースとお菓子を見た久美は、はしゃいで喜んだ。
ベッドにお盆を載せて、その両脇に二人で座った。その拍子にジュースがこぼれそうになったので、わたしは慌てて二つのグラスを手に取り、一つを久美に手渡した。
「だんだん」
久美はにっこり笑って言った。
「だんだんって、確か、ありがとうって意味だったよね」
「覚えてくれたんか。うれしいな」
「愛媛では、みんな、だんだんて言うの?」
「今は誰も言わんな。これは古い方言でな、田舎のおばあちゃんがよう使いよったけん、ほれがうちにも移ってしもたんよ」
久美は恥ずかしそうにしながら、ジュースを飲んだ。
「愛媛弁て、何かいいよね」
「だんだん。あ、また言うてしもた」
二人でくすくす笑ったあと、久美は自分の言葉は愛媛弁ではなく、伊予弁だと言った。
「いよべん?」
「うん。昔の言い方で、愛媛のことを伊予て言うんよ」
「なるほど。伊予弁ってさ、何か温かくて、気持ちが籠もってる感じがするね」
「そがい言うてくれるんは、春花ぎりやし」
久実は沈んだ顔になると、悲しそうに言った。
「こっちでは伊予弁は珍しいけん、喋ったら小馬鹿にされるんよ。ほじゃけん、普通の言葉を喋ろとしてもな、やっぱし喋り方が違うみたいなけん、余計にからかわれるんよ」
二組の生徒たちのことだろう。わたしは聞いていて腹が立った。
「でもさ、こっちの人だって愛媛に行けば、よそ者でしょ? どっちの言葉を使う人が多いかってだけの話だから、そんなに気にしない方がいいよ。だいたい言葉の違いのよさがわからない人なんて、全然大した人間じゃないからさ。相手にすることないよ」
久実を慰めながら、自分でもなかなかいいことを言うなと思った。でも、久実は元気を取り戻すどころか、余計にしゅんとなったようだった。
「そうだ、久実が好きなことを教えてよ。久実って何が好きなの?」
ここは話題を切り換えるのが一番。わたしは思いきり明るい声で久実に尋ねた。久実はしょんぼりしたまま小首を傾げた。
「花かな……」
「花? どんな花が好きなの?」
「桜とかチューリップとか、ヒマワリとかコスモスとか、誰でも知っとるような花も好きやけんど、道端にひっそり咲いとる、名前もわからんような、こんまい花も好きなんよ」
「こんまいって小さいってことでしょ?」
「ほうよほうよ。小そうてな、誰の目にも留まらんような花が好きや」
「何で、そんな花が好きなの?」
「ほやかて一生懸命咲きよるやろ? 誰っちゃ見てくれんし、誰っちゃ世話してくれんのに、一生懸命咲いとるやんか。ほれが健気でいじらしいんよ……。ほれに、そのこんまい花に顔近づけてよう見てみたらな、結構珍しい形しよったり、愛らしい姿をしよるんよ。あれに気づかんのは損やで」
喋っているうちに、久実は元気を取り戻したようだった。わたしの名前が春の花というのも何かの縁だと言い、あとで一緒に花を探すことになった。
「ところで、春花は何が好きなん?」
「え? わたし?」
久実を元気づけるために聞いただけなので、自分が答える番になるとは考えていなかった。好きなものがないわけじゃないけど、いきなり聞かれると急には思いつかない。
「えっと……、絵を描くことかな」
「絵ぇ? 春花、絵ぇ描けるん?」
「自慢できるようなもんじゃないけどさ。これでも一応は美術部に入ってんだ。でも、最初に美術部に入った動機はね、運動部に入りたくなかったから。わたし、運動苦手だからさ。でも文化部って美術部の他は、吹奏楽部と手芸部と英会話サークルしかなくてね。どれも向いてないみたいだけど、絵だったら、まだましかなって思ったの」
「よう言うわ。絵ぇなんてそがい簡単に描けるもんやないで。なぁ、春花が描いた絵ぇ、うち、見てみたい。何ぞあったら見せてや」
ほんとだったら恥ずかしくて人に見せたりしないけど、久実の頼みだから断れない。
わたしは家に持ち帰っていたデッサンやクロッキーを、ベッドの下の整理箱から取り出した。ほとんどが一学期に描いた練習の絵で、自分で見ても何だこれはと思うようなものばかりだ。
それでも久実はわたしの絵を一枚一枚眺めながら、感動の声を上げてくれた。
絵を一通り見て満足した様子の久実は、輝いた目をわたしに向けた。
「なぁ、うち、春花にお願いがあるんよ」
「お願い? 何?」
「一枚ぎりでええけん、うちに絵ぇ描いてくれん?」
「え? 今? ここで?」
久実は子供のようにうなずいた。久実だから特別に絵を見せたけど、頼まれて描くほどの腕じゃない。
わたしは絵を描くための画用紙も鉛筆も、学校に置いてあると言い訳をした。でも、久実はそれで諦めはしなかった。広告の裏でもかまわないし、普通の鉛筆でもボールペンでもいいからお願いと言い、両手を合わせてわたしを拝んだ。
普通の鉛筆しかないから上手く描けないかもと言うと、久実はそれでも構わないと言って喜んだ。
わたしは仕方なく無地の便せんに、普通の鉛筆で絵を描くことにした。
「じゃあ、そこにいてね」
わたしは久実をベッドに座らせたまま、自分は机の椅子へ移動した。
「ひょっとして、うちを描いてくれるん?」
「絶対に期待しないでよ。できた絵を見て、何これ?――なんて言わないこと!」
「ほんなん言うわけないやん! だんだんな、春花」
どういたしましてと言う代わりに、ちょっとだけ笑ってみせたあと、わたしはじっと久実を見つめて絵を描き始めた。
わたしが目を向けるたびに、久実は恥ずかしそうに微笑んだ。でもモデル役なので、じっと身動きせずに座っていた。
そのうれしそうな笑顔はほんとに素敵だった。仕方なく始めたはずなのに、手に持った鉛筆が勝手に動いて行く。
いつの間にか夢中になって描いた久実の姿は、自分で言うのも何だけど、結構上手に描けていると思う。ほら、紙の中で久実の分身が、こんなにいい顔で笑っている。
わたしの様子を見た久美が、できたん?――と期待の顔で尋ねた。
「できたのは、できたんだけど……」
「見せてや!」
立ち上がろうとする久実を、わたしは制してもう一度座らせた。
一応描けはしたけど、まだ未完成だ。わたしはこの絵に久実の雰囲気を出したかった。だけど、どうそれを表現したらいいのかわからない。ぼんやり久実を眺めていると、久実の周りに花が見えた。
これだと思ったわたしは、目に浮かぶままいろんな花の絵を描き足した。知っている花もあれば、思いついたまま描いた知らない花もある。本当にそんな花があるのかどうかもわからない。それでもわたしには、久実が花に囲まれているイメージがあった。
描いているうちに、なんでか久実の頭や肩に小鳥が乗っているように見えた。これはいいやと思って、小鳥も描き足した。すると、今度は膝の上にウサギが乗っている。面白いなと思って、これも描いた。
「久実ってさ、花が好きだって言ったけど、小鳥や動物も好きじゃないの?」
「うん。好きやけんど、ほんなことわかるん?」
「顔にそう書いてあるのよ」
久実が驚いた様子で両手で顔を押さえると、頭や肩に乗っていた小鳥たちが、驚いて飛んで行ってしまった。代わりに、いつの間にか現れた子犬が二匹、久実の足にじゃれついている。ん? 一匹はちょっと変わってるな。もしかして、これってタヌキ?
何でこんな物が目に浮かぶんだろうと、自分でもおかしくなった。久実が気にするのでこらえていたけど、どうしても顔に笑みがこぼれてしまう。
「何、笑とるんよ? もしかして、妙な顔を描きよるんやなかろね!」
我慢しきれず立ち上がった久実から、絵を隠しながら何とか描き終えた。
「はい、完成しました!」
久実は疑いの眼差しをわたしに向けながら、わたしが差し出した絵を受け取った。だけど、そこにある絵を見ると、大きく目を見開いた。
同じように開かれたままの口からは、しばらくしてから、嘘や――というつぶやきが漏れた。
「これ、ほんまにうちなん?」
「そうだよ。今回のは自信作だな。ちゃんとした画用紙に描けなかったのが残念」
少し誇らしげに言うと、久実はぼろぼろ涙をこぼし始めた。やっぱり花や動物は余計だったかと、わたしはうろたえた。
「ごめん。でも、それね、別にふざけて描いたわけじゃないんだよ」
久実は黙って首を横に振りながら、絵をそっと胸に抱きしめ、だんだん、春花――と言った。
わたしはほっとして、涙のわけを聞いた。でも、久美は何も教えてくれなかった。
学校の屋上で初めて久美と喋ったとき、わたしは久美の前で涙を見せた。あのときのわたしと同じように、久美も長い間、何かを胸の奥に隠し続けていたのだろう。それは学校でのいじめかもしれないし、もっと他のことかもしれない。友だちだから話して欲しい気持ちはあるけれど、無理に聞き出すのはよくないことだ。
わたしは立ち上がると、黙って久美を抱きしめてあげた。久美は絵を胸に抱いたまま、わたしの肩に頭を載せて泣いた。
しばらくして泣きやんだ久実は、わたしから離れて恥ずかしそうに笑った。
わたしは安心したけど、次に何と言えばいいのかわからなかった。代わりにお腹がぐーっと鳴って、久美に笑われた。何だかいい雰囲気だったのに、お腹のせいでぶち壊しだ。
「なぁ、今何時やろか?」
久美が辺りを見ながら尋ねるので、わたしはベッドの枕元にある、目覚まし時計を指差して、もうお昼過ぎだと言った。すると久美は慌て出した。
「うち、そろそろ去ぬらんと」
「もう帰るの? まだ来たばっかりじゃない。それに、一緒に花を探すんでしょ?」
「ほうなんやけんど、うち、スーパー行かんといけんのよ。お母ちゃん、まだ治っとらんけん、お母ちゃんが食べられそうな物、買いに行くんよ」
「じゃあ、わたしも一緒に行く!」
「え? ほんなん悪いし」
「いいのいいの。どうせ、することなくて暇なんだもん。一緒に行くよ」
久美はうれしそうに笑うと、もう一度わたしが描いた絵を眺めた。
「なぁ、なんでうちの周りに、こがいな花とか小鳥とか動物、描いてくれたん?」
「なんでと言われてもなぁ。何となくそんな感じに見えたんだ」
ほんまに?――と驚く久美に、それが久美の雰囲気なんだとわたしは言った。すると久美がまたちょっと泣きそうな顔になったので、わたしは久美を買い物へうながした。
スーパーへ向かう道中、わたしたちは道端に咲く小さな花を探した。これまでそんな物を気にしたことがなかったので、意外にいろんな花があることにわたしは驚いた。
久美は花の名前を一つ一つわたしに説明してくれた。その中に、わたしが想像して描いたのと似た花があった。
久美はそれをうれしそうに指差すと、この花の花言葉は、『喜びも悲しみも共に』だと教えてくれた。それは、まさにわたしたちにぴったりだ。
偶然とは言え、そんな花の絵を描いたことに、わたしは不思議なものを感じていた。それは久美も同じようで、春花と知り合えてほんまによかった――と何度も言ってくれた。
三人の仲間
わたしはふわふわ浮かんでいた。目の前には女の人が一人立っている。わたしのお母さんになる人だ。とっても優しそうな人で、その温もりがわたしに伝わって来る。まるで早く生まれておいでねって言われてるみたい。
お母さん、わたしを産んでくれるお母さん。わたし、早くお母さんの子供に産まれたいよ。ねぇ、お母さん。いつ、わたしを産んでくれるの? わたし、待ってるよ。お母さんがわたしを産んでくれるの、待ってるからね。
わたしがお母さんの子供になったなら、わたし、お母さんのこと、いっぱいお手伝いするからね。お母さんのためだったら、わたし、どんなことだってしてあげる。約束だよ。
お母さんはわたしに気づいたように振り返り、にっこり微笑んでくれた。お母さん、わたしのこと、わかってくれたんだ。大好きだよ、お母さん。お母さん……。
「お母さん……」
半分目を覚ましながら、わたしはつぶやいた。母の優しそうな笑顔が、まだ閉じたまぶたの内側に見えている。
突然、部屋の扉をドンドンとたたく音がした。わたしはびくりとなって目を開けた。
「おい、まだ寝てんのか? 今日は休みじゃないんだぞ! 早く起きろ!」
「うるさいなぁ、起きてるよ!」
わたしは扉に枕を投げつけた。階段をトントンと下りて行く兄貴の足音が憎らしい。足音が聞こえなくなると、代わりに兄貴の大きな声がした。
「じゃあ、行って来るよ。急がないと、今日は遅刻だ!」
「気をつけて行ってらっしゃい。急いでも事故しちゃだめよ」
玄関で兄を見送る母の声だ。わたしは慌てて目覚まし時計を見た。七時四十分を回ってる。いつもならとっくに家を出ている時間だ! わたしはベッドから飛び降りた。
「もう、何で鳴らないのよ!」
わたしは着替えながら目覚まし時計に悪態をついた。時計は確かに七時に合わせてあったけど、鳴ったのには気がつかなかった。いや、きっと鳴ったのを消して二度寝をしたに違いない。それでも起きるまで鳴り続けろと、わたしは勝手な文句を時計に言った。
急いで着替えを済ませたわたしは、鞄をつかむとドタドタと階段を下りた。食堂にいた母が呆れた顔でわたしを見た。
「いくら呼んでも返事をしないと思ったら、ほんとに寝てたのね?」
わたしは何も答えず急いで顔を洗い、牛乳も飲まずに家を出た。母が後ろで文句を言ってたけど、そんなの聞いてる暇なんてない。今日は久実と待ち合わせをしてるんだ。
おはよう!――道角で待っていた久実に、わたしは大きく手を振って駆け寄った。
「ごめん、待たせちゃった」
息を弾ませるわたしに、はにかんだような笑みを浮かべた久実は、おはよう――と小さな声で言った。
「走って来たん?」
「朝寝坊しちゃってね。運動会より速く走ったよ」
二人で笑うと、わたしたちは並んで歩き出した。他の生徒たちはみんな先へ行ってしまったようで、わたしたちの近くには誰もいない。
「昨日はいろいろありがとね」
「どういたしまして。それより、お母さんの具合はどう? よくなったみたい?」
「もう、だいたいええみたい。今日から仕事に出るて言いよった」
昨日、わたしは久実の買い物に付き合った。そのあと、いったん別れてそれぞれの家に戻り、それから久美はもう一度遊びに来た。そのときに、久美はお母さんがわたしを今度家に連れて来るようにと言っていたと教えてくれた。わたしも久美の家に遊びに行きたいと思っていたので、久美のお母さんの言葉はとてもうれしかった。
また、そのときに久美は自分の家の話を、わたしにいろいろ聞かせてくれた。
うちと同じように久美の家も共働きで、お父さんは休みにも仕事をするほど忙しい人らしい。だから一人っ子の久美は鍵っ子で、家に帰っても独りぼっちのことが多いそうだ。
うちの親が共働きをしているのは、兄貴の進学と家のローンのためだけど、久美の家では何のためにそんなに働いているのだろうと、わたしは思った。それとなくそれについて聞いてみると、新しい家を買うための資金を貯めるためだそうだ。
その話をするときの久美は、寂しさを無理に我慢しているように見えた。それはそうだろう。大人には大人の事情があるんだろうけど、子供にだって子供の望みがある。それを口にしたくてもそうできないのはつらいものだ。
特に兄弟がいない久美は本当に一人なんだから、そこは両親も考えてやればいいのにと思う。
せめて弟か妹でもいればいいのにねと言うと、久美は黙り込んで涙ぐんだ。やっぱり久美は必死に寂しさを我慢していたようだ。
わたしは久美を慰め、自分の父親の悪口を言った。久美の親のことは言えないからそうしたんだけど、久美は父親のことを悪く言ってはだめだと言った。
泣くほどつらい想いをしているのに、父親をかばおうとするなんて、久美はとても父親想いのようだ。それで、久美はお父さんが大好きなんだねと言うと、久美はうなずきながら涙をぽろぽろこぼした。
久美ってなんていい子なんだろうと思いながら、これからは二人でいっぱい楽しいことをしようとわたしは言った。
そのあと互いの祖父母の話になったけど、わたしはできれば祖父母の話はしたくなかった。
わたしの父の実家はそれほど遠くない。だから、たまに祖父母が訪ねて来る。でも、二人の関心は兄貴だけだ。いつも兄貴の学校の話や、大学受験の話ばかりする。
わたしのことは思い出した感じで、ちょっとだけ聞いて来る。それに答えると、またすぐに兄貴の話題だ。だから、わたしは父方の祖父母があまり好きじゃない。
一方、母の実家は北海道で、こっちの祖父母はわたしを可愛がってくれる。とは言っても、直接会ったのは小学校の一年か二年の頃に遊びに行ったときだ。遠いからめったに訪ねることはできないし、向こうから遊びに来ることもない。たまに電話で喋るぐらいがせいぜいだ。
お盆やお正月に訪ねるのは、いつも父の実家の方ばかりだ。どうして北海道へ行かないのかと母に尋ねると、お金がかかるし、自分はもう白鳥の人間だからというのが返事だった。母がそんなことを言うのは、絶対にこっちの祖父母のせいだと思う。普段の様子を見ていると、絶対そうに違いない。
そんな話をすると、久美はわたしや母を気の毒がった。
久美の方は、父方のおばあちゃんが一人いるだけだそうだ。母方のおじいちゃんとおばあちゃんは、久美が生まれる前に亡くなったらしい。
久美のお父さんは瀬戸内海の漁師町の人で、こちらのおばあちゃんは今もそこの家に暮らしているらしい。
おじいちゃんは漁師だったけど、二年前に事故で亡くなったそうだ。それからは、おばあちゃんは一人で暮らしているので、久美はおばあちゃんのことを心配していた。
おばあちゃんたちの子供は、久美のお父さんと伯母さんの二人だけだそうだけど、久美のお父さんは町に働きに出たので、おじいちゃんの後を継ぐ人はいなかったらしい。
おじいちゃんが亡くなったあと、お父さんがその家に戻るかという話があったそうだけど、そこにはお父さんの仕事がないので、戻ることにはならなかったそうだ。また、おばあちゃんもその町を出ることを望まなかったので、おばあちゃんは一人で暮らすことになったようだ。
それでも伯母さんという人が近くにいるそうだから、まったくの独りぼっちじゃないよねと言うと、久美は少しだけ笑って、ほうじゃねと言った。
おばあちゃんはどんな所に住んでいるのかと尋ねると、すぐ前が海だと、久美は懐かしそうに話してくれた。
瀬戸内海を日本地図で確かめてみると、本州と四国、九州に囲まれた海だということはわかった。だけど地図では、そこがどんな所なのかは全然わからない。そこを知る久美から説明されて、わたしは初めて瀬戸内海という海を思い浮かべることができた。
青空の下、右から左へずっと広がる水平線。あちらこちらに浮かぶ島々と、のんびり動く船。広い空には、やっぱり白い雲がのんびりと流れている。
青に緑が交ざった色の海と、釣りを楽しむ人たち。その近くをカモメが飛んでいる。
後ろの山にはパラグライダーの乗り場があって、時々パラグライダーに乗った人が砂浜に降りて来る。
ここは水平線に沈む夕日が絶景で、その夕日を見るためだけに訪れる人も多いそうだ。もう話を聞いているだけで、よだれが出そうなほど行きたくなってしまう。
いつか必ず訪ねてみたいと言うわたしに、久美はおばあちゃんから聞かされたという言葉を教えてくれた。それがまた、とても素敵な言葉だった。
「ねぇ、久美。昨日教えてくれたおばあちゃんの言葉、もう一回言ってくれる?」
「え? もういっぺん言うん?」
「お願い。伊予弁で聞きたいの」
久実は少し照れていたけど、何度も頼むと、夕日を眺めるように前を見つめて言った。
「夕日見てきれいじゃて思うんはな、あんたの心がきれいなけんよ。花見て素敵じゃて思うんはな、あんたの心が素敵じゃてことなんよ」
「それよ、それ! やっぱり伊予弁じゃないとね。それに何べん聞いても、いい言葉!」
わたしはほんとにこの言葉が好きだった。久美は照れ笑いをしながらもうれしそうだ。
「何か、春花と一緒におったら、うち、自信が湧いて来るわ」
「わたしも久美のおばあちゃんに会ってみたいなぁ」
「ほうじゃね。会えたらええね」
久美は微笑んだけど、もう会えないと思っているのかもしれない。何だか笑顔が寂しげに見える。それで、わたしは話題を変えることにした。
「そう言えばさ、わたし、今朝変な夢を見たんだ」
実は、ずっと喋ろうかどうしようかと迷っていた。わたしが見た夢は、兄貴が借りた本の馬鹿馬鹿しい話と同じだ。まさか自分がそんなものを見るとは思わなかったし、話して笑われるのが心配だった。
「変な夢?」
「自分が産まれる前の夢なの」
「産まれる前の? へぇ、面白そうやね。どがぁな夢やったん?」
久美は目を輝かせて話を聞いてくれた。
真弓たちだったら馬鹿にされたと思うけど、やっぱり久実は違う。不思議な夢じゃねぇ――と首を捻りながら、夢の意味を一緒に考えてくれた。でも、いくら考えても答が出るわけがない。結局、わたしたちは夢の意味を見出すのは諦めた。
久実は残念そうにしながらも、これまでにも何か不思議なことはなかったかとわたしに尋ねた。別にそんな経験はないはずだけど、わたしも真面目に考えてみた。それで思い出したのは、まだ幼稚園に行ってた頃か、その前か、とにかくわたしがとても幼かった頃、わたしはスーパーの中で迷子になった。
覚えているのは、人がたくさんいる広いお店の中で、母の姿を見失ったことだ。わたしは心細くて半べそをかきながら、あっちこっちを走り回って母を探していた。
喋っていると、さらに思い出した。そもそも、そんなことになったのは兄貴のせいだった。お店の中で一緒に鬼ごっこをしていた兄貴が、わたしを置いていなくなったのだ。
母も兄貴も見つからず、わたしが声を出して泣きそうになったとき、こっち――と言う誰かの声が不意に聞こえた。でも、こっちと言われても、どっちなのかがわからない。
どっち?――と姿の見えない相手に尋ねると、後ろ――と声がする。
そっちへ行って商品棚の角まで行くと、そこから左だの右だのと声が続き、最後には兄貴がわたしを見つけてくれた。
何かに気を取られてわたしを見失った兄貴は、母にかなり叱られたみたいだった。わたしの所へ駆け寄って来ると、勝手にどこかへ行くなよと文句を言った。
そんなこと、今の今まで忘れていたし、あのときは、あれが誰の声なのかなんて考えもしなかった。それほど、あのときのわたしは幼かったのだろう。
久実は興奮した様子で、他にはないかと言った。わたしは額に指を当てながら考えたけど、他には何も思い出せなかった。
「春花、今日は遅かったじゃない」
「ぎりぎりセーフってとこね」
真弓と百合子が寄って来て、わたしの様子をうかがった。じろじろ見られるので、何よと言うと、二人は口を揃えて、別に――と言った。
わたしが構わず自分の席に着くと、二人は後ろについて来てわたしの机の横に立った。
「ねぇ、春花は昨日は何をして過ごしたの?」
真弓が意味ありげな顔で聞いた。
「昨日? 別に何もしないよ」
「ふーん、じゃあ、何でうちのマンションに来たのに、そのまま帰っちゃったの?」
やばい。見られてたんだ。わたしは焦ったけど、できるだけ何でもない顔をした。
「見てたのか。だったら声をかけてくれたらよかったのに。あれはね。ちょっと家に忘れ物を取りに帰ったの。だけど見つからなかったから、もういいやって諦めたんだ」
「忘れ物って何よ?」
今度は百合子が言った。わたしの話なんか信用してないみたい。もしかして久実といるところを見られたのかと、ちょっと心配になった。でも、ここは強気で行くしかない。
「兄貴がね、日曜日の夜にクッキーを焼いたんだ。だから、それをお裾分けしようと思って出たのに、肝心のクッキーを忘れてしまったからさ」
「ほんとに? お兄さん、クッキーなんか焼くの?」
百合子の声に、他の女子生徒たちも集まって来た。真弓も身を乗り出して、ほんとに?――と迫って来た。どうしようと思ったけど、もう嘘をつき通すしかない。
「初めて焼いたの。それで真弓たちの分を取っておいたのに、帰って戸棚を見たら、置いてあったクッキーがなくってさ。あとで聞いたら、兄貴が学校へ持って行ったんだって」
「あんた、それはあたしたちにくれるクッキーだって、お兄さんに言ってなかったの?」
真弓は本気で怒ってるみたい。百合子も顔が引きつっている。
「ごめん。まさか、兄貴がわたしの分を持って行くとは思ってなかったから……」
「ごめんじゃ済まないよ。ああ、あたし、お兄さんの焼いたクッキー食べたかった」
「あたしも食べたかった」
二人して襟首を絞めるので、わたしは咳き込みながら、わかったからと言った。
「次は絶対に持って行くから。それでいいでしょ?」
「次って、いつよ?」
にらむ二人に、わたしは近いうちにと言った。だけど、それじゃあ許してもらえず、今度の日曜日に真弓の家に、クッキーを持って行くことになった。
本鈴が鳴った。先生が教室に入って来ると、みんな慌てて自分たちの席に戻った。
真弓と百合子は椅子に座ってからも、必ずだからね――と目で訴えて来た。わたしは小さくうなずいたあと、すぐに嘘をついてしまう自分を呪った。
よく考えれば、真弓の部屋の番号がわからなかったと、正直に言えばよかったのだ。それを咄嗟に嘘をついてしまったのは、真弓たちとは遊ばず久美と遊んだことの、後ろめたさがあったからに違いない。わたしは嘘をついた後悔と今後の不安でいっぱいになった。
休憩時間になっても真弓たちの目が気になって、わたしは久美に会いに行けなかった。すると、廊下に出て来た久美が、窓越しにわたしを探す姿が見えた。
すぐに出ようと思ったけど、真弓たちに引き留められて、わたしは教室を出ることができなかった。久美は残念そうにしながら、自分の教室へ戻って行った。
次の休み時間も、久美がわたしの方を見ながら廊下を歩いて行くのが見えたので、わたしはトイレに行くと言って教室を出ようとした。そしたら真弓たちもついて来たので、久美には小さく手を振るしかできなかった。
その次の休み時間になると、わたしはすぐさま教室を飛び出した。二組の前に行くと久美の姿が見えたので、わたしは外にいると手で合図した。
校舎の玄関へ行くには、もう一度一組の前を通らなければならない。でも、それでは真弓たちに見られてしまうから、わたしは三組の前を通り過ぎ、そのまま突き当たりの戸口から外へ出た。本当は上履きで出てはいけないのだけど、そんなことは言ってられない。
すぐに久美がやって来たので、わたしは手招きして久美を外へ出した。
怪訝そうな久美にわたしは言い訳をした。
「いつもわたしをつかまえて放さないのがいるから、ここまで逃げて来ちゃった。私に会いに来てくれてたのに、ごめんね」
「ほれは構んけんど、春花、人気者なんじゃね」
「いや、人気者っていうんじゃなくって……」
わたしが言葉を濁すと、久美は一度は見せた笑みを引っ込めた。
「じゃあ、何?」
「人気者の下っ端」
「何ほれ?」
「だから言ったでしょ? わたし、相手に合わせてばかりだったって。ほんとはそうしたくなくっても、相手の言うことになかなか逆らえなくってさ。向こうは人気者だし」
「春花も大変なんじゃねぇ」
苦笑する久美に、わたしはきっぱり言った。
「だけどね、それはこれまでの話。わたしには久美がいるから、今までの自分とはおさらばするんだ」
「ほやけど、大丈夫なん? うちのせいで春花が気まずいことになったら、うち困るし」
「大丈夫だって。でも、あんまり突然なこともできないから、またさっきみたいなことになるかもしんないけど、そのときはごめんね」
久美は笑顔で手を振った。
「構ん構ん。うちのことやったら気にせんでや。うち、春花に会えんでも、うちには春花がおるて思うぎりで元気出るけん」
「ありがとう! 久美、大好き!」
わたしは久美の両手を握ると、久美を抱きしめた。
「ところで、今日は誰かに意地悪されなかった?」
「まだ、そがぁにはされとらんよ」
「もしひどいことされたら、わたしに言ってね。わたし、クラスは違うけど、怒鳴り込みに行くから」
「だんだん。ほやけど、大丈夫。今も言うたけんど、前と違て、うちには春花がおる。そがぁ思たら、他の誰かに何ぞ言われたかて平気やけん」
何とうれしいことを言ってくれるのだろう。わたしはもう一度久美を抱きしめた。
昼休みになると、わたしは急いで昼食を済ませて外へ出ようとした。もたもたしていたら、真弓たちがついて来る。
まだ食べ終わっていない真弓と百合子は、そんなに急いでどこへ行くのかとわたしに声をかけた。わたしは部活の準備だとだけ言うと、教室を出て二階にある美術教室へ向かった。そこは誰もいないし、わたしは美術部だから誰にも不審に思われない。
教室の中で待っていると、しばらくして久美がやって来た。久美もこの教室は知っているはずだけど、こんな時間に入るのは初めてだった。きょろきょろしながら、秘密基地みたいだと言って喜んでいた。
わたしは昨日見せられなかった自分の作品を久美に見せた。久美はそれらを眺めて感心しながら、自分も美術部に入ればよかったと言った。
久美はテニス部だけど、ほんとはテニス部でなくてもよかったらしい。前の学校でテニスをしていたと言ったら、担任の先生にテニス部へ入れられたと久美はぼやいた。入部はつい先日のことだったそうで、わたしともう少し早く知り合っていれば、絶対に美術部にしていたと久美は残念がった。それはわたしにしても、とても残念なことだった。
放課後、部活動の時間になると、わたしは美術教室の窓際に陣取った。そこからだとテニスコートが見える。
テニス部は男子と女子に分かれていて、隣り合ったコートで練習する。テニス服に着替えた生徒たちが、ぞくぞくとコートに集まって行く。その中にみんなと違う紫色のズボンの女子生徒がいた。久美だ。
久美が前の学校のズボンをはいているのは、注文した新しい体操服とズボンが、業者の手違いでまだ届かないからだそうだ。テニス服については、まだ入部して間もないから買ってないと久美は言っていた。
前の学校で使っていたテニス服はないのかと尋ねたら、松山では一年生部員は全員が、体操服で練習をしていたらしい。
テニス服をまだ購入していないのなら、テニス部をやめて美術部に鞍替えするチャンスだけど、そんなことはなかなか言い出せるものではない。それでも、いずれは久美が美術部に移って来ると期待して、わたしはテニスコートを眺めていた。
遠いから一人一人の顔まではわからないけど、体型や大きさなどから谷山健一郎はわかる。クラスが違うのに、久美に向かって手を上げている。なんだ、谷山のやつ、久美のことを知ってたんじゃないか。
ちょっと複雑な気持ちで眺めていると、白鳥!――と先生の声が飛んで来た。
「さっきからよそ見ばかりして。いつになったら始めるんだ?」
すみませんと頭をすくめると、わたしは体を前に向けた。そこにはデッサン用の彫像が置かれてある。他の部員たちは、すでにデッサンを始めている。今日は気が乗らないが、やるしかない。
わたしはデッサンをしながら、時々先生や他の部員たちの様子をうかがった。
これまでもみんなを眺めているときに、何かが目に浮かんだことは一度もない。こうして改めて眺めてみても、やっぱり何も浮かんで来ない。目に見えるのは、みんなの普段どおりの姿だけだ。
昨日、久美の絵を描いたときに見えたものは、気分がとても高揚したために思い浮かんだだけに違いない。それでも、久美があれだけ感激してくれたから、ちょうどよかったと言うか、あんな絵が描けてラッキーだったと思う。もう一度描けと言われても、描ける自信はない。
それにしても、あのとき久美はどうして泣いたんだろう? まだ理由は聞かせてもらっていないけど、とにかくこれからも久美の力になってあげなくっちゃ。
夕方になり、壁の時計を見ると、五時になるところだ。
「そろそろ終わりにしよう」
先生が声をかけると、みんなは道具を片づけ始めた。
ちらちらとテニスコートを見ていたので、今日のデッサンはまるでだめ。のぞきに来た先生も、何も言わなかったけど渋い顔をしていた。絵に集中できていなかったのは、ばればれに違いない。
窓から外を見ると、テニス部はまだ練習を続けている。片づけを終えたあとも、久実たちの様子を眺めていると、高橋早苗が声をかけて来た。
「白鳥さん、帰らないの?」
早苗は美術部員であると同時に、クラスメイトでもある。将来は漫画家になりたいそうで、教室にいるときはノートに落書きをして楽しんでいることが多い。
この落書きが可愛らしくて本当に上手い。わたしなんかと違って、早苗には絶対に絵の才能があると思う。
だけど、早苗は引っ込み思案で目立つことが好きじゃない。運動会でも百合子と同じ理由で、選んだ競技はダルマ競争だった。それで、百合子と同じように素っ転んでしまい、思いきり目立ってしまった。そのことを早苗は今日も大いに恥じていた。
早苗は真弓たちと同じ小学校にいたけれど、昔から真弓や百合子が苦手だったと言う。だから真弓たちと仲よくしているわたしに、敬意を払ってくれているようだった。
そのせいなのか、早苗がわたしを呼ぶときは、名前で呼ばずに白鳥さんという言い方をする。でもわたしは逆に早苗のことを、サッチーと愛称で呼んでいる。ちなみに、早苗をサッチーと呼ぶのはわたしだけだ。
うん、帰るよ――と言いながら、わたしの目はテニスコートに向いたままだった。
テニス部はようやく練習が終わったようだ。部員たちがコートに集合して、先生の話を聞いている。あれではいつ解散するかわからない。
解散したあと、部員たちは汗を拭いたり、服を着替えたりしないといけないから、久実が解放されるのはまだまだ先だ。
早苗の家は久実のマンションより、もう少し離れた所にある。だから、早苗は自転車で通学している。朝の登校は一緒じゃないけれど、部活が終わったあとは、わたしと別れる所まで自転車を押しながら一緒に帰るのがいつものパターンだ。
わたしは窓辺から離れると、部室の入り口で待つ早苗の傍へ行った。
早苗と一緒に校門を出たあとも、わたしは久美のことが気になった。部活のあとに一緒に帰るという約束はしていないけど、きっと久美はそのつもりに違いない。
何度も後ろを振り返っていると、どうかしたの?――と早苗が尋ねた。
わたしは迷いながらも、久実のことを話してみた。すると早苗は、久美が出て来るのを待っていようと言ってくれた。
わたしは早苗のことを見直した。これまでは同じ部活動をしているクラスメイトぐらいの感覚しかなかった。でもこのときから、早苗はとても近い存在になった。
久実を待つ間、わたしは早苗にも今朝見た夢の話をしてみた。すると、早苗もとても興味を持ってくれた。そして、自分も母親のお腹の中にいたときのことを覚えている気がすると、早苗は言った。
驚くわたしに早苗が語ってくれたのは、ザーザーという心地よい音が聞こえていて、時々誰かの話し声がしたり、温かい気持ちが伝わって来た記憶があるという話だった。
まだ言葉なんかわからないはずなのに、話し声が自分にかけられたものであることや、大好きだよとか、早く産まれておいでねと言われているのが、早苗にはわかったそうだ。
こんな話をすれば頭がおかしいと思われるだろうから、誰かに聞いてもらいたくても話せなかったと、早苗は言った。それで、わたしと話ができたことを喜んでくれた。
しばらくすると、運動部の生徒たちがぞろぞろと校門から出て来た。帰る方向が別の者たちは、ここで互いに別れの声をかけ、それぞれ同じ方へ帰る者同士で行ってしまう。
中にはうちのクラスの者もいて、校門にいるわたしと早苗を見ると、こんな所で何をしているのかと言った。どうでもいいお喋りだと答えると、大概がふーんと訝しげにしながら帰って行った。でも谷山は違った。
谷山はわたしたちに声をかけると、絵のことを聞いて来た。早苗は恥ずかしがって喋らないので、仕方なくわたしが谷山の話相手になった。
そこでわたしは久実のことを知っていたのかと、少し責めるようにして谷山に確かめてみた。谷山はどぎまぎした様子で、まぁなと言って笑った。その笑顔は何だかわたしの胸に突き刺さった。
そろそろ久実も出て来る頃だと思っていると、真弓と百合子が現れた。それで谷山が、じゃあな――と帰って行ったので、わたしは真弓たちが憎らしくなった。
二人とも運動が苦手なくせに、自分たちだけでバトミントン部を立ち上げた。でも、ほとんど遊びみたいな練習で、堂々と体育館を使わせてもらうほどではない。運動場の隅っこで、二人で羽根を打ち合う程度だ。
そんな二人だから、運動部員としては全然目立たない。それでわたしの頭の中から、二人の存在がすっぽり抜け落ちていた。
突然の二人の登場に早苗もひどく驚いたようで、早苗はそっとわたしの後ろに隠れた。
何を喋っているのかと尋ねられ、わたしは絵の話だと答えた。真弓たちが早苗を見て、漫画ね――と言うと、早苗が困ってわたしを見た。
文化祭で展示する絵のことだと、早苗に代わって話しながら、わたしは校門の中に目を遣った。すると、服に着替えた久実が一人でとぼとぼやって来る。このまま久実がここへ来たら、面倒なことになりそうだ。
わたしは、そうだ!――とわざと大きな声を出した。
「わたしね、ちょっと忘れ物して来ちゃった」
「な、何を……?」
一人置いて行かれると思ったのか、早苗は不安げな目をわたしに向けた。
「ちょっとね。でも、すぐ戻って来るから待ってて」
泣きそうな早苗を残し、わたしは走ってその場を離れた。すると、久実がわたしに気がついて手を上げた。
わたしは口の前に指を立て、校舎へ戻るよう指で示した。久実はきょとんとしていたけど、わたしが横を走り抜けると、黙って後をついて来た。
校舎の中に入ると、わたしは早苗と二人で久実を待っていたことを告げた。ただ、ちょっと話が合わない者もいるので、その人たちがいなくなるまで待って欲しいと頼んだ。
人気者の人たちかと久美が聞くので、そうだと答えると、久美は笑って、わかったと言った。そして、わたしが呼ぶまで校舎に隠れていることになった。
わたしは急いで早苗の所へ戻った。早苗は小さくなって真弓たちと喋っていたが、わたしに気づくと怒ったような目を向けた。
「ごめん、ごめん」
「あんたってほんとに忘れんぼだね。今度は何を忘れたの?」
百合子が呆れ顔で言った。隣の真弓も渋い顔だ。
だけど、部活中に描いたクッキーのデザインだと言うと、途端に二人は目を輝かせた。
見せて欲しいとせがまれたけど、そんな物などあるはずがない。わたしはまた適当な説明をして、部室は鍵がかかっていたから、描いた用紙を取り戻すのは明日だと言った。
それは自分たちがもらえるクッキーかと真弓が言った。もちろんと答えると、真弓たちは残念がりながらも、兄貴のクッキーをもらえることを早苗に自慢した。だけど早苗がきょとんとしているのでつまらなくなったのか、そろそろ帰ると言った。
二人が行ってしまうと、早苗はわたしに文句を言った。
「ひどいよ、白鳥さん。わたしを一人にするなんて!」
「ごめん。さっき、そこまで久実が来てたのよ。でも、真弓たちは久実のこと、よく思ってないみたいだからさ。わたしが呼ぶまで校舎で待ってるよう、久実に伝えて来たの」
「そうだったの。でもね、嘘をつくのはよくないと思うよ」
「嘘って?」
「さっき、あの二人に嘘ついたでしょ?」
「ああ、そのことか。でも仕方がなかったんだ。勘弁して」
いつもは引っ込み思案で、自分の意見をなかなか言わないのに、このときの早苗は違っていた。それでも、それ以上は何も言わなかった。
わたしは校舎へ戻って久実を連れて来た。紹介された早苗はがちがち状態で、久実にぺこりと頭を下げた。久実の方も少し緊張してるようだった。
でも、早苗は漫画家になる予定だと教えると、久実は興味深げに早苗に話しかけた。それで二人はすぐに打ち解けたようだったので、わたしはほっと安堵した。
三人であれこれ喋っているうちに、実は自分で描いた漫画の作品が家にあると、早苗が言った。そんな話はクラスの誰も知らない。
わたしと久実が見たい見たいとせがむと、早苗は恥ずかしそうに笑って、今度家に来てくれたときに見せると言った。
早苗は絵を描くことではクラスの人気者だった。でも、それ以外では影が薄くて目立たない。部活のあとにわたしと一緒に帰るときだって、こんなに話で盛り上がることはなかった。
早苗ってこんなに笑顔を見せるのかと思うほど、早苗はとてもうれしそうだった。家に人を呼ぶのも初めてらしい。わたしも久実も、その光栄に大はしゃぎをし、今度部活がない日の放課後に、そのまま早苗の家にお邪魔すると約束をした。
早苗が加わったことで、久美に新たな仲間ができた。早苗の家にお邪魔できるのもうれしいけど、わたしには久美に仲間が増えたことが何よりうれしかった。
言霊
「お前さぁ、それって、その転校生にめっちゃ失礼なんじゃねぇの?」
口の中の物を飲み込んだあと、兄貴は箸の先をわたしに向けて言った。
「どうして失礼なの? わたしは久美に嫌な思いをさせないようにしただけだよ? 久美だってちゃんとわかってくれたんだから」
言い返したわたしは、母に同意を求める目を向けた。だけど、母は黙って食事を続けるばかりで、何も言ってくれない。
兄貴は軽蔑するような顔をしながら言葉を続けた。
「わかってくれたって言うけどな、お前にそんな風に言われて、そこでその子がへそを曲げられるか? お前だけが頼りなのに、そのお前の言うことに逆らえるわけねぇだろ?」
「違うもん!」
兄貴はため息をつくと、あのな――と言った。
「逆の立場になって考えてみろよ。お前が愛媛に転校したとしてだな、そこで初めてできた友だちが、お前と一緒にいるところを誰かに見られないよう、こそこそしてたらさ、お前、どんな気分になる?」
「わたし、こそこそなんてしてないもん! ちゃんと早苗に紹介して、三人で一緒に帰ったんだからね」
「そいつの話をしてんじゃねぇんだ。お前と普段仲よしのあの二人に、その転校生を会わせようとしなかったんだろ? そのことを言ってんだよ!」
普段仲よしという言葉には反発したくなった。だけど、真弓や百合子と一緒にいることが多かったのは、事実だから言い返せない。そこは聞き流してわたしは反論した。
「だって真弓たち、久実のことを馬鹿にするんだもん。久実を会わせたら、久実が嫌な思いをするじゃないよ!」
「お前が本当にその転校生のことを大事に思ってんなら、隠したりしないで、堂々と会わせりゃいいんだよ。それで、その子が馬鹿にされるような人間じゃないってことを、あの二人に教えてやればいいんだ」
「二人に話が通じなかったら、どうすんのよ?」
「そんときはしょうがねぇだろ。お前が大事に思う方を取ればいいじゃん」
「勝手なこと言わないでよ。こっちの苦労も知らないくせに!」
わたしがにらむと、兄貴はふっと笑った。
「要するに、お前の苦労って言うのは、あっちにもこっちにもいい顔したいってことなんだろ? 結局、それってきれいごとを言ってるだけじゃん。お前がやったことは、その転校生のためじゃなくて、自分のためだな。お前、自分を守ろうとしただけなんだろ?」
「違うもん!」
わたしが大声を出すと、ようやく母は口を開いた。
「そんなに大きな声を出さないの。それより、二人とも早く食べなさい。せっかくのハンバーグが冷たくなっちゃうじゃないの。これ、高かったんだからね」
兄貴は矛を収めて、言い争うのをやめた。だけど、わたしの方は収まらない。気持ちが高ぶったままで、食事をする気にもならない。
「オレ、高い冷食のハンバーグもいいけどさ。やっぱ、母さんの手作りのハンバーグがいいな。安物の肉でもね」
「最後の一言が余計よ」
母が注意しながら笑うと、兄貴も一緒になって笑った。二人の笑顔がわたしをさらに腹立たしくさせた。我慢ができなくなって、わたしは勢いよく立ち上がった。
「ごちそうさま」
「あら? ほとんど食べてないじゃないの。ちゃんと最後まで食べなさい!」
「お腹空いてないの!」
「それじゃあ、これ、いただき!」
兄貴は反省することもせずに、わたしの皿に手を伸ばした。思わずわたしが兄貴をにらむと、何だよ?――と兄貴はわたしをにらみ返した。
「お前、もうごちそうさまなんだろ? だったら、オレが食ったっていいじゃんか」
「どうすんの、食べるの? 食べないの?」
母の口調は叱られているみたいだった。
「食べない」
わたしは横を向いて席を離れ、兄貴の後ろにあるドアへ向かった。それが二人への精一杯の反抗だった。
兄貴はわたしの皿を引き寄せながら、あのさぁ――と母に言った。
「母さん、クッキーの焼き方知ってる?」
ドアノブに手をかけていたわたしは、思わず動きを止めた。
「知ってるけど、どうしたの、急に?」
「実はね、オレの友だちがさ。自分が焼いたクッキーを学校に持って来たんだよ」
「友だちって、女の子?」
わたしのこめかみ辺りが勝手に引きつった。
「男だよ、男」
「男の子がクッキーを焼いて来たの? へぇ、それは珍しいわね」
「そいつね、食べることが好きでさ。将来はケーキ屋になりたいって言うんだ」
「じゃあ、ケーキも作るの、その子?」
「そうなんだって。でも、ケーキは持って来れないから、代わりにクッキーを持って来たんだけどさ。これがまた美味いんだ。それで、うちのクラスではちょっとしたクッキーブームになっててね。男子も女子もいろいろ作って持って来るようになったんだ。だから、オレもちょっと作ってみようかなってね」
「へぇ、そうなんだ。時代は変わったものね。お母さんが学生だった頃は、男の子がクッキーを焼いて持って来るなんて、有り得なかったわよ」
「まぁ、そういうわけでさ、今度暇があるときにクッキー作るの手伝ってよ」
「いいわよ。じゃあ、今日は無理だけど、明日の晩にでも作ろうか」
「ほんとに? やった!」
わたしは両手で顔をこすって顔の筋肉をほぐすと、くるりと兄貴たちの方へ向いた。
「どうしたのよ、何笑ってんの? 部屋へ戻るんじゃなかったの?」
わたしの様子をずっと見ていたであろう母が、からかうように言った。気恥ずかしさが笑みを浮かべる手助けをしてくれる。
「お兄ちゃん、クッキー作るんだって?」
わたしは兄貴の肩越しに明るく声をかけた。兄貴はあからさまに嫌そうな顔を見せた。
「お前にゃ関係ねぇだろ? 食い終わったんだから、さっさと部屋へ行けよ」
「お兄ちゃーん」
わたしが甘えた声で抱きつくと、兄貴は面食らったように慌てふためいた。
「こら、やめろ。気持ち悪いんだよ!」
「そんなこと言わないで、わたしにもクッキー焼いてくんない?」
「何でオレがお前にクッキー焼かねぇといけねぇんだよ? クッキー食いたいんなら、自分で焼いたらいいだろ?」
「お兄ちゃんのクッキーが食べたいの。お・ね・が・い」
パチパチさせた目で見つめながら、顔を近づけると兄貴は悲鳴を上げた。
「わかったから離れろ! 離れろってば!」
「ほんとね? 約束だよ?」
兄貴は死にそうな顔で、わかったよ――と答えた。わたしは自分の席に戻ると、兄貴の前にあった自分の皿を引き戻した。
「おい、何だよ。さっき食わないって言っただろ?」
「気が変わったの。女心と秋の空って言うでしょ?」
わたしがハンバーグにかぶりつくと、兄貴は悔しそうに母を見た。母は笑いながら、これにて一件落着!――と言った。
木曜日の今日は部活がない。放課後になると、わたしは早苗の所へ行った。真弓と百合子が声をかけて来たけど、今日は早苗と帰るから先に帰ってて欲しいと言った。この日は久実と一緒に初めて早苗の家に行き、早苗が描いた漫画を見せてもらうのだ
運動会が終わってから、わたしは久実と一緒に通学を始めた。今ではそこに早苗も加わり、わたしたちは仲よし三人組になった。
休憩時間には、わたしは大概早苗のそばにいるようになった。早苗と一緒だと、廊下に出て久美と会うのも不自然さがないように思われた。久美もうれしそうで、早苗にはほんとに大感謝だ。
ただ、真弓や百合子と過ごす時間が少なくなったことが気にはなっていた。日曜日にあげるはずだったクッキーを今日二人にあげたから、今のところは大丈夫だと思う。でも、いつかそのうち二人が怒り出すのではないか、という不安があった。
それでも早苗の家に着いたら、そんな気持ちも一気にどこかへ消え失せてしまった。
決して広くはない早苗の部屋には、本棚が二つあった。そのどちらの本棚にも、漫画の本がびっしり並んでいた。わたしと久実は思わず声を上げて、自分がお気に入りだった本や、まだ読んでいない有名漫画家の本を夢中で手に取った。
一方、早苗の机には描きかけの漫画があった。とてもハイレベルな絵で、紙の横には専門的な漫画の道具がある。それを見ると、改めて早苗は特別な人間だと感心させられた。
ひととおり本棚の漫画を吟味したあと、わたしと久実は本命である早苗の漫画を見せてもらうことになった。
早苗は待ってましたとばかりに、机の引き出しを開けた。中にはこれまでに描いた、いくつもの漫画が入っていた。早苗はその漫画の原稿の束を取り出すと、二つに分けてわたしと久実に手渡してくれた。
最初に描いたという漫画は短い恋愛もので、ちょっと絵のタッチやストーリーが素人っぽいように思えた。でも、そのあとの漫画は描き重ねるにつれて、絵もストーリーも上手くなっていた。
「サッチー、絶対に漫画家になれるよ。わたし、断言する」
「うちも断言する。高橋さん、ほんまにすごいわ。中学生とは思えんで」
二人で絶賛すると、早苗は大喜びした。
早苗の話では、両親は早苗が漫画を描くのを認めてくれてはいた。でも、漫画家なんかになれるはずがないから、他の人たちみたいに高校や大学を受験して欲しいと願っているらしい。それで早苗は漫画家の夢を諦めていたそうだ。
だけど、わたしと久実がべた褒めしたので、諦めるのはやめると宣言した。
そのとき、部屋のドアをノックする音が聞こえた。早苗が声をかけるとドアが開いた。
「いらっしゃい」
顔を見せたのは、早苗のお母さんだ。
早苗がわたしたちを紹介したので、わたしも久実も立ち上がってお辞儀をした。お母さんは、にこにことうれしそうにしながら言った。
「この子の部屋を見てびっくりしたでしょ? この子ったら勉強もしないで、漫画ばっかりだから」
「でも、さっき見せてもらったんですけど、すっごく上手に描けてますよ」
わたしが早苗をかばうと、久実も一緒にうなずいた。お母さんは、わたしたちの反応がわかっていたみたいで、ほんとに?――と笑顔を崩さないまま早苗を見た。
早苗も援軍がいるからか、ほらねと言う顔でお母さんを見返した。
お母さんは何かを言い返す様子もなく、あのね――と言った。
「お茶とお菓子を用意してあるんだけど、よかったらこっちで食べない? おばあちゃんがね、あなたたちの話を聞きたがってるのよ」
わたしと久実は顔を見交わした。早苗からは漫画の話しか聞いていない。おばあちゃんがいるとは初耳だった。前に聞いていたとすれば、すっかり忘れていたことになる。
「無理にとは言わないけど、どうかしら?」
お母さんがうながすように言うと、早苗は困惑顔をわたしたちに向けた。だけど、わたしも久実も笑顔でうなずき、お母さんの誘いを受けることにした。
「まぁまぁ、素敵な娘さんたちだこと」
小さなテーブルでわたしたちを迎えてくれたのは、六十過ぎと思われるお洒落な感じのおばあちゃんだった。こざっぱりした格好で笑顔がとても愛らしい。一目見ただけで、お話好きだとわかる雰囲気がある。
「さぁ、どうぞ」
お母さんに勧められて、わたしと久実はおばあちゃんと向き合うように並んで座った。テーブルは四人がけで、早苗はおばあちゃんの隣に座り、お母さんは台所から持って来た踏み台を、テーブルの横に置いて腰かけた。
テーブルの上には、それぞれの席にお茶と大福もちが置かれてあった。
おばあちゃんへの挨拶が終わると、食べながら話しましょうとお母さんが言った。
だけど、わたしも久実も遠慮してなかなか手をつけられない。おばあちゃんが大福を頬張るのを待って、それからようやく食べることができた。
大福は上品な甘さのあんこがたっぷりで、わたしと久実は思わず顔を見交わして、美味しい!――を連発した。
わたしたちが喜んだので、お母さんもおばあちゃんも満足気な様子だった。
おばあちゃんはお茶を一口すすったあと、わたしに話しかけた。
「白鳥さんは、早苗と同じ美術部なんだってね」
わたしは小さくうなずいた。でも、早苗と絵の上手さを比べられているようで、気恥ずかしかった。
すると、久美がわたしが描いた絵のことを挙げ、わたしには他の人にはない感覚があると言った。わたしは慌てて否定したけど、早苗もおばあちゃんたちも、その絵が見てみたいと言った。
わたしは全然大したことないからと、久美の言葉を打ち消そうとした。だけど早苗はわたしには不思議なところがあると言い、わたしが見た産まれる前の夢の話を、おばあちゃんやお母さんに聞かせた。二人がうなずきながらわたしに興味深げな顔を向けると、わたしは気恥ずかしさでいっぱいになった。
「サッチーだって、お母さんのお腹の中にいたときのこと、覚えてるって言ってたじゃない!」
つい早苗の秘密事を喋ってしまったので早苗は慌てた。だけどお母さんもおばあちゃんも、へぇと驚いた様子を見せただけで、早苗を笑ったり否定するようなことは言わなかった。
逆に、どんなことを覚えているのかと二人が尋ねるので、早苗はぎこちなく説明した。
話を聞き終わったお母さんは、おばあちゃんとうなずき合ったあと、真面目な顔で早苗に言った。
「おそらく早苗が言うことは本当よ。お母さんはもちろんだけど、お父さんもおばあちゃんも、私のお腹の中にいるあなたに向かって、毎日のように声をかけてたんだから」
早苗は驚いた顔でわたしと久美を見ると、本当に?――と、お母さんたちに言った。
お母さんとおばあちゃんが声を揃えて、本当だよと答えると、早苗の目からみるみる涙があふれ出た。
「あらあら、どうしたの? 泣いたりして」
お母さんは、微笑みながら早苗に声をかけた。
「わたし……、自分がそんなに望まれてたなんて知らなかった……。わたし、自分なんて認められてないって思ってたの……。だから、今の話もね……、本当は愛されてたんだよって……、自分に言い聞かせるために……、勝手に妄想してたんじゃないかって……」
「何言ってんの。お母さん、なかなか子供に恵まれなくてね。何度もお父さんやおばあちゃんと一緒に神社へ行って、子供を授かりますようにってお願いしたのよ。それで、やっと産まれた子供があなたなの。だからね、あなたは神さまからの授かりものよ。そんなあなたを大事に思わないわけがないじゃない」
お母さんは涙ぐみながら言った。おばあちゃんの目にも涙が光ってる。
「お前のお父さんが漫画の道具を買ってくれたのだって、お前を大事に思っているからこそじゃないのかい? ただ趣味でやるのと、それを商売にするっていうんじゃわけが違うからね。そこをあたしたちは心配してるんだよ」
早苗は下を向いたままだった。わたしは早苗に代わって、お母さんたちに言った。
「サッチーは漫画家になりたいんです。だけど、漫画家なんかになれるわけないって、お母さんたちに言われて自信をなくしてたんです」
「高橋さんの絵ぇは、ほんまに上手やと思います。高橋さん、いくつも漫画描いとって、絵ぇも上手やし話もとっても面白いです。ほやけん高橋さん、きっと漫画家になれると、うちは思います! 絶対なれます!」
久美も一緒になって早苗を支持してくれた。
わたしは心強い気持ちで、お母さんとおばあちゃんを見つめた。二人は少し困ったように互いを見たけど、お母さんはわたしたちの方を向くと、わかったわ――と言った。
「そのことについては、あとでお父さんと相談してみましょう。ただね、わたしたちはそういう世界を知らないから心配なのよ。だから大学はともかく、せめて高校ぐらいは出て欲しいな」
お母さんの言葉におばあちゃんもうなずいた。
「絵が上手っていうだけじゃ、いい漫画は描けないんじゃないのかい? 漫画を描くためにも、いろいろ経験することは必要だと、あたしゃ思うけどねぇ」
わかったと早苗を言うと、涙の顔を上げた。
「高校は行く。でも漫画部のある高校がいい」
「そんなのがあるのかい?」
おばあちゃんが驚いたように言った。
「わかんないけど、漫画が描ける学校がいい」
「もし漫画部がなかったら、自分で作ればいいじゃん」
「ほうよほうよ。ないなら、自分でこさたらええんよ」
わたしと久美が応援すると、そうかと早苗の顔が輝いた。
「なければ自分で作ればいいんだよね。白鳥さんや兵頭さんの言うとおりだ。わたし、そうする。漫画部がなかったら自分で作る」
「他にも漫画が描きたい言う人らが集まって来たら面白いで」
「確かさ、まんが甲子園っていうのがあるんだよね。あんなのも参加すれば楽しそう」
ほんとだ――と早苗の顔はますます明るくなった。まだ中学一年生なのに、すっかり高校で漫画を描くつもりになったみたいだ。
「世の中ってやつは、どんどん変わって行っちゃうんだねぇ。あたしたちの頃には考えられないようなことを、今の人たちはやろうと思うんだねぇ」
おばあちゃんはやっぱり不安みたいだった。でもおばあちゃんの言葉は、早苗の希望を認めてくれたように聞こえた。
よかったね――と久美が早苗に言った。早苗は涙に濡れた笑顔で大きくうなずいた。
わたしは自分が、こんな場面に関われたことがうれしかったし、ちょっぴり誇らしかった。わたしと微笑み合った久美も、きっと同じ気持ちなのだと思う。
「あとで早苗が描いた漫画を、あたしにも見せておくれ」
おばあちゃんが言うと、早苗はうれしそうにうなずいた。
しばらく早苗の漫画の話が続いたあと、おばあちゃんは久美の話がまだだったと、思い出したように言った。
急に自分の出番になった久美は、少し言いにくそうにしながら、愛媛から移って来たことや、家庭の状況を説明した。
お母さんやおばあちゃんは、慣れない土地での久美の暮らしをねぎらいながら、愛媛の話をして欲しいと言った。二人とも愛媛はもちろん四国のことも、よく知らないらしい。
久美が愛媛の名所を教えると、道後温泉は有名だとおばあちゃんが言った。何でも三千年の歴史がある温泉らしい。
どこが一番のお勧めかと聞かれると、久美は伊予灘の夕日だと答えた。それはどこかと言う二人に、久美はわたしに聞かせてくれたのと同じ説明をし、そこで見る夕日は最高ですと言った。すると、お母さんやおばあちゃんもそうだけど、早苗までもが行ってみたいと言ったので、久美はうれしそうだった。
わたしは黙っていられなくなって、伊予灘には久美の素敵なおばあちゃんがいると言った。そうなんだとお母さんに言われて、久美がうなずくと、どんなところが素敵なのかとおばあちゃんが尋ねた。
久美は困って、とても優しいおばあちゃんですとは言ったものの、あとの説明ができなかった。そこでわたしは、あの言葉をみんなに教えてあげてと言った。
久美は戸惑った様子だったけど、どんな言葉か聞きたいとお母さんもおばあちゃんもせがむので、久美は覚悟を決めたように姿勢を正し、おばあちゃんのあの言葉を披露した。
「素敵なことを言ってくれるおばあちゃんだね」
早苗がうっとりした様子で言うと、お母さんも感想を述べた。
「いいわよねぇ、土地の言葉って。それに、おばあちゃんの言葉、ほんとに素敵だわ」
おばあちゃんもうなずくと、真面目な顔で言った。
「今の言葉は、あなたのおばあさまの人生がぎゅっと詰められているみたいだね。言葉に魂が籠もってるよ」
「魂……ですか?」
久美が遠慮がちに尋ねると、そうだよ――と言って、おばあちゃんはわたしにも目を向けた。
「昔の人はね、どんなものにでも魂があるって考えてたんだよ。山を神さまに見立てて拝むのだってそうだし、いつも使っている道具だって、自分の相棒だと思って大切にしたものさ。それと同じで、人の口から出て来る言葉にもね、その人の魂の一部が含まれてるって思ってたんだ。だからね、それを言霊って言うんだよ」
考えたこともなかった説明に、わたしは感心した。久美も神妙に話を聞いている。だけど、早苗は普段からこんな話を聞かされているようで、当然という顔でわたしに言った。
「だからね、嘘をつくって、よくないことなんだよ」
「嘘って何の話?」
お母さんがわたしと早苗の顔を見た。わたしが焦ると、一般的な話だと早苗は言った。
おばあちゃんはうなずくと、嘘はよくないと言った。わたしは穴があったら入りたかった。
「嘘ってやつはね、人を欺こうっていう思いが言葉になったものなんだ。だけどね、嘘は相手だけでなく、自分自身をも欺くんだよ。人っていうのは、本来正直な生き物なんだ。でも、嘘をつくのはね、自分は不正直な人間なんだって、自分に言い聞かせるようなものなのさ。本当は真っ当な正直者の自分にね」
「嘘を繰り返すと、どうなんの?」
早苗が調子を合わせるように尋ねた。きっと答を知っているだろうに、わたしに聞かせるために聞いたに違いない。ちらりと早苗を見てから、おばあちゃんは言葉を続けた。
「人から信用されなくなっちまう。それはわかるだろ? 人を騙すやつは誰からも信じてもらえなくなるんだよ。でもね、気をつけなくっちゃいけないのは、悪意のない嘘だよ」
「悪意のない嘘?」
顔を見交わしたわたしと久実に、いいかい?――とおばあちゃんは言った。
「誰かを騙すつもりがなくっても、本当の気持ちと違うことを言っちゃうことってあるだろ? 本当のことを言うとひどい目に遭うとか、馬鹿にされるとか、惨めな気持ちにさせられるとかさ。だけど、いくら嘘を続けたって、いつかは嘘だってわかってしまうものなんだ。そうなったら、おしまいだよ。悪気がなくたって、大嘘つきって言われちまう」
わかるだろ?――とおばあちゃんは、わたしたちの顔をのぞくように眺めた。まるで心の中を見透かされているみたいだ。
「そのときに素直にごめんなさいって言えれば、まだいいんだよ。でも言えなかったら、どこにも居場所がなくなっちまう。そうなったら悲しいし腹も立つだろ? その気持ちを人にぶつけたら余計に孤立しちまうし、自分にぶつけりゃ、せっかく生まれて来た人生を捨てることになっちまうよ。もう自分なんかどうだっていいやってね」
お説教をされてるみたいな気分になって、わたしの目は机の上の湯飲みを見ていた。それに気づいたのか、今度はお母さんが慰めるような声で言った。
「悪気がない嘘なんて、あたしたちだって、つい口にすることがあるからね。そんなに気にすることはないのよ。おばあちゃんが言いたいのはね、嘘をついたかどうかってことよりも、自分の本当の気持ちを大事にしてるのかってことなのよ」
おばあちゃんもまずかったと思ったのか、さっきより明るい口調で喋った。
「嘘はともかくね、人を責めるような言葉も慎まないといけないよ。褒める言葉はいいけどさ。誰かを責めるような言葉は、相手に呪いの言葉を投げかけるのと同じなんだ。だから誰かに何かを伝えるときには、言葉に気をつけなきゃいけない。そうは言っても、あたしたちもつい余計なことや、人を傷つけるような物言いをすることがあるんだけどね」
「ほんとよね。あたしたち、さっちゃんのことをあんなに傷つけてたなんて、さっきまでわかってなかったもの。ごめんね、さっちゃん」
さっちゃんというのは、早苗のことらしい。早苗はその呼び方が恥ずかしかったのか、もういいよ――とうるさそうに言った。
「とにかくさ、兵頭さんのおばあさまは素晴らしい人だっていうことさね」
おばあちゃんのこの言葉で、言霊の話は終わりになった。
「サッチーのおばあちゃん、面白い人だったね」
帰りがけ、わたしは久美に言った。そう言うことで、自分が平気だと見せたかった。
もう日が暮れかけていて、辺りは薄暗くなり始めている。夕暮れ時の寂しさのせいなのか、笑顔でうなずいた久美は、何だか少し沈みがちにも見えた。
「ねぇ、もしかしてわたし、調子に乗って余計なこと言ったかな?」
心配になって尋ねてみたけど、久美は微笑んで首を横に振った。
「春花は何も悪いこと言うとらんよ。春花のお陰で、うちのおばあちゃんのこと、みんなに喜んでもらえたし、高橋さんのおばあちゃんからええ話を聞けたんやけん、春花にはお礼を言わんとね。だんだんな」
わたしはほっとしたけど、やっぱり久美は寂しそうだ。
「ねぇ、わたしたち親友だからね」
「どがぁしたん、急に?」
久美は戸惑ったように笑った。
わたしは寂しそうな久美を励ましたかった。だけど、何と言っていいかわからなくて、思わず出た言葉だった。
「わたしと久美とサッチーの三人は、これからもずっと親友だって、今日思ったんだ」
「高橋さんも、そがぁ思とるやろか?」
「思ってるよ。でなきゃ、わたしたちを家に呼んだりしないよ。それに今日はサッチーにとって、特別の日になったんだもん。わたしたちは特別な関係だよ」
久美は微笑みながら小さくうなずいた。だけど、やっぱり何だか悲しそうに見えた。
雨に濡れた涙
「あのさぁ、春花、最近あたしたちと付き合い悪いんじゃない?」
一時限目の授業が終わると、百合子がそばへ来て唐突に言った。
わたしはどきりとした。真弓や百合子と遊ぶ時間が減ったのは事実だ。だから、いつそのことを言われるかと、ずっと冷や冷やしていた。その心配がついに現実になったらしい。驚いた心臓が胸の中で慌てふためいている。
「付き合いが悪いって、どういうこと?」
わたしが惚けると、百合子は面倒臭そうにため息をついて、わかってるくせに――と言った。
いつの間にか真弓も百合子の隣に来ていて、嘘つきは泥棒の始まりだと言った。
実は先週、真弓たちから久しぶりに、今度の日曜日にわたしの家に遊びに来たいと言われた。その日曜日というのは昨日のことだ。
もちろん二人の目的は兄貴に会うことだ。だから、わたしは兄貴の都合が悪いと言って断った。
だったら真弓の家で遊ぼうと誘われたけど、これも用事があると言って行かなかった。久美や早苗と映画に行く約束をしていたからだ。
付き合いが悪くなったのは本当だけど、嘘をついたわけじゃない。かちんと来たわたしは、真弓に言い返した。
「嘘って何よ? 昨日、兄貴が部活で忙しかったのも、用事があったのも全部本当だよ」
「そのことは、いいの」
真弓が言うと咄嗟に百合子が、よくないでしょ?――と真弓を見た。
だけど真弓は、そのことはあとにしようと言って取り合わなかった。それで百合子は渋々口をつぐんだ。
百合子が言った話じゃなくて、別のことでわたしが嘘をついたと、真弓は言いたいみたいだ。それが何のことなのか、わたしには皆目見当がつかなかった。
だけど、何だか嫌な予感がする。胸の中で心臓が、やばいよ、やばいよ――としきりに訴えている。
真弓はわたしに顔を戻して言った。
「あんたさ、あたしたちをお兄さんの誕生日に呼んでくれるって言ったよね?」
その話かと、わたしはうろたえた。そのことはすっかり忘れていたし、あれは口から出任せに言ったことだ。でも、それは昨日ではなかったはずだ。
「ああ、そのことだったら大丈夫。ちゃんと兄貴には言ってあるから」
真弓の顔色をうかがいながら、少しだけ笑顔を見せて、わたしはごまかそうとした。すると真弓は、嘘つき!――と言って、わたしをにらみつけた。
「あんた、ほんとに大嘘つきね」
真弓と言いたいことが違っていたはずなのに、百合子も真弓に口を揃えて言った。
二人してここまで怒っているということは、二人を兄貴の誕生日に呼ぶということが、嘘だったとばれたに違いない。だけど、何で嘘がばれたのだろう? 確かめたいけど、それは嘘を認めることになる。白を切っている今、それは墓穴を掘ることになってしまう。
「あんた、お兄さんの誕生日、いつって言った?」
真弓が追い立てるように言った。でも、あれは適当に喋ったことだったから、いつだったかが思い出せない。確か、年末辺りだったような気がするけど。
「わかんないの? 自分のお兄さんの誕生日でしょ?」
「兄妹だって誕生日を忘れることってあるでしょ? 兄貴なんか、わたしの誕生日を覚えてくれてたことなんか、一度もないんだから」
精一杯言い返しながら、いつと言ったか必死に思い出そうとした。だけど、全然思い出せない。どうしよう?
「ねぇ、いつよ?」
わたしは真弓たちの表情を読みながら言った。
「十二月……」
「何日?」
「二十日」
真弓の顔が鬼みたいな形相になった。両手の拳が小刻みに震えている。
「こないだよこしたクッキーだって、お兄さんが焼いたんじゃないんでしょ?」
わたしは絶句した。
先日真弓たちにあげたクッキーは、実は兄貴じゃなく、わたしが焼いた物だった。
兄貴と一緒に焼いたんだけど、真弓たちにはちゃんと兄貴のクッキーをあげるつもりだった。
なのに、前に真弓たちに喋った嘘のとおり、兄貴はわたしにくれるはずのクッキーまで学校へ持って行ってしまったのだ。それで仕方なく、真弓たちには自分のクッキーをあげただんだけど、これは別に二人を騙すつもりでやったことではない。
それでも、兄貴が焼いたクッキーだと言って渡した以上、わたしは嘘をついたことになるし、そのことは自分でもわかっていた。
それにしても、そのことを真弓たちはどこで知ったのだろう? どこかで兄貴に会う機会があったのだろうか? きっと、そうだ。兄貴が余計なことを喋ったに違いない。
観念したわたしは弁解しようとしたけど、口が動くばかりで言葉が出なかった。
絶交よ――真弓はわたしを見下ろしながら、冷たい口調で宣言した。
「今日限り、あんたとは絶交よ。これからは友だちでも何でもないから忘れないでね」
真弓は返事を待たずに、くるりと背を向けて自分の席へ戻って行った。百合子は真弓の背中とわたしを見比べると、あたしも絶交だからね――と言って真弓の後を追った。
一人残されたわたしを、クラスメイトたちが黙って見つめている。
隣の席にいた宮中満里奈が、心配そうにわたしを見ていたけどそれだけだ。何があったのかと尋ねてくれる者は一人もいない。聞かれたところで、嘘をついたのは事実だから言い訳のしようもない。それでも周囲の沈黙は、責められているようでつらかった。わたしはその雰囲気に耐えきれずに教室を飛び出した。
足はトイレに向かっていた。一人きりになりたくて、トイレの個室に入ろうと思っていた。だけど、トイレには他の生徒たちがたくさんいたので、わたしは向きを変え、階段を駆け上った。屋上へ行くつもりだった。
息が切れるほどの勢いで階段を駆け上り、屋上の扉の前に着いた。だけど、今度はしっかり鍵がかけられていて、扉を開くことはできなかった。何度も扉のノブをガチャガチャしたあと、わたしはその場にうずくまった。
久実や早苗と親しくなれたことで、わたしは有頂天になっていた。それで真弓たちとの距離が遠くなっても構わないと思っていたし、むしろ、そうなることを願っていた。だけど、こういう形で自分の願いが叶うことになるとは思ってもみなかった。
涙がぼろぼろこぼれて床を濡らした。
早苗のおばあちゃんの言ったとおりになってしまった。真弓たちだけでなく、クラス全員がわたしのことを、大嘘つきの信用ならないやつだって思ったに違いない。きっと、早苗だってそう思っている。あの谷山だって……。
誰かに話を聞いて欲しい気持ちはあった。だけど今更何を話したところで、それさえも嘘だと思われるだろう。どうすればいいのかわからず、わたしは泣き続けた。
休憩時間の終わりを告げるチャイムが鳴った。教室へは戻りたくなかったけど、戻らないわけにはいかない。
重い身体を引きずるように、わたしはゆっくり階段を下りて行った。どの学年も生徒たちは教室へ戻り、どこの階の廊下もひっそりしている。
一階まで下りたわたしは、教室の後ろの戸をそっと開けて中に入った。みんなはすでに席に着き、先生が教壇に立っている。
「白鳥、遅いぞ!」
先生に注意されたわたしは返事も挨拶もせずに、うなだれたまま自分の席に戻った。
周囲からの視線を感じる。男子も女子も、みんながわたしのことを見ている。
わたしは誰とも目を合わせないようにして、自分の机の上に意識を集中しようとした。すると、机の上に置かれた紙が目に入った。
『うそつき! 死ね!』
真弓か百合子が書いたのだろう。わたしはすぐに紙をぐしゃぐしゃにすると、二人の方を見た。二人とも、じっとわたしのことをにらんでいる。
わたしは真弓たちをにらみ返してやった。でもそのとき、こっちを向いた谷山と目が合った。わたしは慌てて目を逸らすと下を向いた。谷山にだけは、今の惨めな姿を見られたくなかった。
谷山はわたしのことを、大嘘つきだと思っただろうか?
谷山は誰にでも優しい。その谷山にさえ嫌な目で見られるようになったら、わたしはもうここにはいられない。
この日、わたしは針のむしろに座らされているみたいだった。誰も声をかけてくれず、話しかけることもできず、この苦痛にひたすらじっと耐えるしかなかった。
休憩時間には机に突っ伏して何も見ない、何も聞かないようにしていた。だけど、どうしても周りの音や声は聞こえてしまう。
真弓たちがわたしの様子を眺めながら、他の誰かにわたしの悪口を言っている。それに反応して驚く声や笑う声が聞こえると、わたしは両耳を手でふさいだ。
早苗だけでも味方になってくれたらと、ちょっとだけ期待はあった。だけどこの状況では、気の弱い早苗が傍へ来られるわけがない。
久実だって廊下からわたしの様子を見たかもしれないけど、違うクラスの部屋に勝手に入っては来られない。
四時限目の授業が終わり、昼休みの時間になった。わたしはお弁当とお茶を抱えると、黙って教室を出ようとした。
「勝手に外で食べるやつがいる!」
真弓の声がした。わたしは無視して廊下に出た。
ちらりと早苗の方を見たけど、前の方に座っている早苗は、わたしに気がつかないのか、机の上に弁当を広げているところだ。
そっと隣の教室をのぞいてみると、久実がいた。だけど、久実は独りぼっちじゃなかった。他の女子生徒たちと机を並べ、一緒に弁当を食べようとしていた。
どうやら相手はみんな同じテニス部員らしい。部活動を通して仲がよくなったに違いない。だけど、わたしはそんな話は聞いていなかった。
「何よ、わたしと同じ美術部がよかったって言ってたくせに!」
わたしは久実をにらんだけど、久実はこちらに気がつかない。まさかこの時間に、わたしが廊下にいるとは思ってもいないのだろう。だけど、気持ちがつながっているのなら、気づいてくれてもよさそうなものだ。
わたしはしばらく待っていたけど、久実が仲間たちと笑う姿を見ると、その場を離れて校舎の外へ出た。
誰にも見られない所を探すうちに、わたしは校舎の端にある体育道具の倉庫へ来た。すぐ横には、大きなイチョウの木があって感じがいい。
わたしはイチョウの木の根元に腰を下ろすと、何でこんなことになったのだろうと考えた。
わたしはつまらない人間だ。だから真弓たちと一緒にいることで、自分だって特別なんだってところを、みんなに見せようとした。
実際、早苗がわたしに一目置いてくれたのだって、真弓たちと付き合っていたからだ。
家に遊びに来た真弓たちを母に紹介したときも、わたしは鼻が高かった。自分がどれだけ学校で認められているかを、母にアピールできたからだ。
でも真弓たちが関心を持っていたのは、わたしじゃなく兄貴だった。わたしはただの兄貴へのパイプ役に過ぎない。それがわかっているから、わたしの方も真弓や百合子を、本当の友だちだなんて思ったことがない。本当の友だちにしてもらえるとも考えていなかった。
真弓たちと友だちのふりをして周囲を騙しながら、自分が魅力のない人間だということを、わたしは自分の目からも隠そうとしていた。だけど、全部嘘だとみんなに知れてしまい、自分自身にも現実を突きつけることになった。
結局、わたしは惨めなピエロだった。
昼食が終わったようで、校舎の中が騒がしくなった。外に出て来た者もいて、わたしはお弁当を開かないまま立ち上がった。もう食べる場所はないし、何かを食べたい気分でもない。行く所がないわたしは、とぼとぼと教室へ向かった。
大勢の男子生徒たちが騒いでいる玄関に入り、教室がある廊下へ行くと、二組の前に谷山がいるのが見えた。
どきっとして、わたしは近くの階段の陰に隠れた。そこからそっと顔を出してのぞいてみると、谷山は二組の誰かを呼び出してもらっているようだった。
わたしは谷山と顔を合わせたくなかった。谷山があそこに立っている限り、わたしは教室へ入れない。困ったなと思いつつ、無理に教室に戻る理由もないから、わたしはその場で谷山の様子を見続けた。
上から下りて来た上級生二人が、妙な顔でわたしを見ながら職員室の方へ行った。ちょっとだけ上級生を見送ったあと、谷山に目を戻したわたしは驚いた。
谷山が呼んだのは久実だった。谷山は右手で頭の後ろを掻きながら、照れ臭そうに何かを言った。久実も恥ずかしそうに下を向いている。
ヒューヒューと二人をはやし立てる声が、教室や廊下から聞こえた。困惑した谷山は、久実の手を引いてこちらへやって来た。
わたしは慌てて階段を上がり、踊り場の陰から谷山たちが来ないか確かめた。
しばらくすると谷山と久実の姿が見えた。いつでも上に逃げられるようにしながら見ていると、二人は階段を通り過ぎて玄関の方へ行った。後ろから冷やかしの男子たちがついて行く。
付いて来るな!――と言う谷山の怒ったような声が聞こえ、他の生徒たちは階段近くから動かなくなった。
わたしの心臓は破れそうなぐらいドキドキしている。頭は何も考えられない。真弓や百合子を怒らせたことや、教室で恥をかかされたことなど全部どうでもいいように思えた。わたしは大声で叫びたかった。ただ、叫びたかった。
冷やかしの者たちがいなくなるのを見計らい、わたしはそっと教室に戻った。みんながわたしに目を向けたと思うけど、わたしの頭にあるのは、谷山と久実のことだけだった。
泣きそうになるのをこらえながら、席に戻ったわたしは帰り支度をした。
「もしかして、家に帰るの?」
隣から満里奈が声をかけて来た。満里奈とは小学校から一緒の仲だ。でも真弓たちと付き合い出してから、昔ほどは喋らなくなった。
だけど、満里奈は心配してくれているようだ。つい甘えたくなったけど、今更だった。
帰る――と一言だけ返して顔を上げると、真弓と百合子がわたしをにらんでいた。わたしは二人には構わず黙って廊下に出た。
「白鳥さん、待って!」
早苗が後ろからわたしを呼び止めた。振り返ると、話があるのと早苗は言った。
「わたしに近づいたら、サッチーまでひどい目に遭わされるよ」
味方になれない早苗に皮肉を言ったわけじゃない。その逆だ。
わたしは早苗が心配だった。早苗までが巻き添えで嫌な思いをすることになれば、申し訳ないでは済まされない。
だけど早苗は思い詰めたような顔で、わたしから離れなかった。
わたしは周囲を見回し、玄関ホールの隅っこへ早苗を誘った。早苗は怯えたような様子で、わたしに謝らないといけないことがあると言った。
「わたしに謝る? 何のこと?」
説明を求めながら、わたしは身体がゾクリとした。それは何かとても悪いことで、今回のことと関係があると、わたしの直感が告げていた。
「わたしね、今日は日直当番だったから、先に学校へ来たでしょ? それで、あとから来た山上さんと本田さんがね、わたしの所へ来て、昨日のことを聞いて来たの」
今日はわたしは久実と二人だけで登校した。わたしたちがいつものようにゆっくり登校している間に、早苗は真弓たちから話しかけられたということらしい。
「あの人たちも、昨日、商店街へ遊びに出てたらしくて、そこでわたしたちのことを見かけたって言うの。それで何をしてたのかって聞かれたから、わたし、いろいろ喋ったの」
それで百合子が付き合いが悪いと文句を言ったのかと、わたしは納得した。百合子は早苗と久美がわたしを奪ったと受け止めたのかもしれない。
「何かひどいことを、二人から言われたりされたりしなかった?」
早苗は首を横に振った。でも、早苗は今にも泣きそうだった。
「本当のことを言って。あの人たちに何か言われたんでしょ?」
早苗は下を向いたまま黙っている。返事をうながすと、早苗は顔を上げずに言った。
「白鳥さんは大嘘つきだから、付き合うのはやめた方がいいって。あんたも今に騙されるよって言われた……」
ほら、やっぱり――とわたしは思った。
「それで、何て答えたの?」
「そんなことないって言った」
「あの二人は、何て言ったの?」
「勝手にすればいいって笑ってた」
近くでは他の生徒たちの声が飛び交っている。だけどわたしと早苗の間には、息苦しい沈黙が漂っていた。
それにしても、早苗が謝らねばならないというのは何だろう。昨日のことを二人に喋ったことだろうか? それとも、早苗もわたしのことが信じられなくなったのだろうか?
わたしは早苗の手を取ると、自分の気持ちを伝えた。
「信じてもらえるかどうかわかんないけどね。わたし、サッチーと仲よしになれてうれしかったし楽しかったよ」
早苗は下を向いたまま泣きそうな声で言った。
「わたしも楽しかった……」
「サッチーが漫画家になれると思うって言ったのも嘘じゃないよ。本当のことだから」
「嘘だなんて思ってない……」
早苗の目から涙がぽろぽろこぼれた。
「わたし、白鳥さんが嘘つきだなんて思ってない。でも、白鳥さんがあの人たちに悪く言われたのはね、わたしのせいなの」
「どういうこと?」
尋ねながら、わたしはまさかと思った。早苗はうなだれながら、あのね――と言った。
「わたしね、嘘つけないから、聞かれたことをいろいろ喋ったの」
「映画とかカフェに行った話じゃなくて?」
「それもだけど、三人で喋った話もあの二人に話したの」
昨日は三人でカフェに行き、一つのパフェを分け合いながらお喋りを楽しんだ。
そのときに真弓たちにあげたクッキーが話題になり、わたしは兄貴のクッキーが手に入らなかったから、仕方なく自分のクッキーを渡したと説明した。
その苦労話を早苗は久美と一緒に笑っていたけど、まさか、その早苗から真弓たちに話が伝わるとは思わなかった。
あのときには、八月の兄貴の誕生日に買ったケーキの箱を、わたしが誤って落としてしまい、中のケーキがグチャグチャになってしまった話もした。これも大笑いだったけど、この話も早苗はあの二人に喋ったということらしい。
わたしは言葉が出なかった。ここだけの話だからと念を押したわけではない。だからと言って、そんな話まで馬鹿正直に真弓たちに喋るだなんて、わたしは早苗が信じられなくなった。
早苗は泣きながら、ごめんなさいと謝った。だけど、その言葉は遠くで聞こえる知らない人の声みたいだった。わたしの耳も頭も言葉の意味が理解できなかった。
ただわかったのは、早苗が余計なことを喋ったせいで、真弓たちに嘘がばれてしまい、わたしは学校にいられなくなったということだ。
不思議に怒りは湧いて来なかった。だって、一度は親友だと信じた相手だから。
わたしは、いいよ――と言った。それが精一杯で、それ以上は言葉が出ない。無理に喋ろうとすると涙が出そうになる。
わたしは早苗に背を向けると、下駄箱の方へ向かった。
後ろで早苗が何度も謝るのが聞こえた。でも聞こえないふりをして靴を履き替え、そのまま外へ出た。さっきは青空が出ていたのに、いつの間にか雲が広がっている。
ふと横を見ると、さっきまでわたしがいた体育道具の倉庫の横に、谷山と久実が向き合い立っていた。何を喋っているのかはわからない、でも、ふざけた話をしているのではなさそうだ。真面目な顔で話す谷山の言葉に、久実が何度も小さくうなずいている。それから驚いたように首を横に振った久実は、迫る様子の谷山に大きくコクリとうなずいた。
その雰囲気に、わたしの胸はカーッと熱くなった。早苗に対して抱いた感情は、悲しみだけだった。でも今、わたしの身体を震わせているのは怒りだった。
そのとき、教室の窓から身を乗り出してこっそり二人の様子を眺めていた、二組の男子生徒たちが冷やかしの声を出した。
驚いて振り向いた二人と、わたしは目が合った。二人がいる場所は離れていたけれど、その時の二人の表情は何故かよく見えた。二人とも見られてはいけない所を見られたという顔だった。
わたしは反射的に走り出した。そのまま校門を飛び出すと、家に向かって走り続けた。走っている間は、とにかく逃げることしか頭になかった。だけど、とうとう息が切れ、足が言うことを聞かなくなった。
走るのをやめると一気に悲しみが込み上げて来た。わたしは肩で息をしながら泣いた。
初めて本当の友だちができたと思っていた。久実や早苗の力になれたことが、本当にうれしかった。これからずっと三人は親友なのだと信じていた。だけど、馬鹿を見たのはわたし一人。わたしだけが責められて、本当の独りぼっちになってしまった。
時折車が横を通っても、歩いて来た人が怪訝そうな顔をしても、涙は止まらなかった。
やがて、ぽつりぽつりと雨が降り出した。
雨は次第に強くなり、わたしの身体も荷物もぐちょぐちょになった。
だけど雨はわたしの涙を隠してもくれた。冷たい雨はわたしを打ち続けたけど、雨だけが今のわたしを黙って慰めてくれているようだった。
光の存在
今日で何日になるだろう。わたしはあれからずっと学校を休んで、自分の部屋に引き籠もっている。
母も兄貴も心配して、何があったのかと聞くけれど、そんなの説明できるわけがない。学校の先生も様子を見に来たみたいだけど、わたしは一度も顔を出さなかった。
部屋の扉越しに聞いた母の話では、先生も何があったのかをちゃんと把握できていないらしい。自分で説明してくれないと誰も何もわからないと、母は懇願するように言った。
それでもわたしは沈黙を貫いた。先生が事情を知らないはずがない。母はわたしが嘘つきなのをわかった上で、わからないふりをしているだけだ。
食事もほとんどしていない。下に降りるのはトイレに行くときだけで、あとは部屋の中だ。母が心配して食事を運んで来るけど、そのほとんどはゴミ袋行きだ。液体は窓から外へ流して捨てた。この三日に口にした物と言えば水だけだ。
こんなことをしていれば当たり前だけど、とても具合が悪い。身体が衰弱しているのが自分でもわかる。だけど、別に死んでもいいと思っていた。もうこの世のすべてと縁を切り、一人で消え去ってしまいたいという気持ちになっている。
早苗はたぶん怖いのだろう。わたしの様子を見に来ることはなかった。
でも、久美は二度訪ねて来た。一度目は学校を休んだ翌日。二度目は昨日だ。
どちらの日も、家にはわたし以外誰もいなかった。呼び鈴が鳴ったとき、わたしは二階の部屋のカーテンの隙間から、そっと門の外を見た。そこには久美が立っていた。
久美はしばらくそこにいたけど、そのうち諦めて帰って行った。そんなことが二回あった。
久実は電話もかけてくれた。母がそう伝えてくれたけど、わたしは誰とも喋りたくなかった。それに、今のわたしには久実が別世界の人間みたいだった。だから電話には出なかった。
わたしなんかがいなくたって、久美はみんなと仲よくやっていけるだろう。それに久美には谷山がついている。あいつ以上に頼りになる者もいないから、久美は安心だ。わたしが久実を心配する必要がなくなったのだから、よかったと言えばよかったのだと思う。
久実や早苗と楽しく過ごしていたのは、ほんの前のことだ。久美の家にも呼んでもらって、久美のお母さんにも気に入ってもらえた。わたしも久美や早苗を母に紹介した。わたしは三人の絆が深まったと思ったし、それがとてもうれしかった。だけど、今ではそんなこともずっと昔のことのような気がしている。
二人に対する怒りや悲しみはすでに鎮まり、今はただ遠くから二人の幸せを願う気持ちがあるだけだ。悪いのはわたしであって、久美も早苗も悪くない。わたしが一人で勝手に泣いたり怒ったりしていただけで、こうなった責任のすべてはわたしにある。
真弓や百合子には悪いことをしたなと思う。でも、それ以上は何も思わない。
初めの頃は、何もあんな言い方をしなくたってとか、みんなの前で晒し者にすることないのにと反発していた。でも、元々あの二人とは合わなかったんだと考えると、どうでもよく思えた。
クラスのみんなにしたって同じだ。みんな友だちのようでいたけれど、本当の友だちとなると、いないも同然だった。
顔や名前を知っていて、その時の気分で適当にお喋りをする。それだけの人たちであって、何でも話し合えるような者はいない。ただの友だちごっこだ。本当の友だちだったら、あのときにわたしの話を聞こうとしてくれたはずだ。
何もかもがどうでもいい。考えるのも面倒だ。だけどその一方で、やっぱりみんなと仲よくしたかったし、認めて欲しかったという気持ちが、思い出したように頭をもたげてくる。
どれが自分の本音なのかが、わたしにはわからなかった。ただ他の人たちのように、もっと魅力的な女の子に生まれていればと、悲しく思う気持ちがあった。
もっと美人だったら、もっと頭がよかったら、もっと運動が得意だったら……。子供の頃から、そんなことを思うことはよくあった。だから、わたしは自分が嫌いだった。何かで失敗したり笑われたりするたびに、わたしは自分を呪った。そんな恥をかいたときの感情が蘇り、わたしはますます自分が嫌いになった。
こんな自分に生んだ両親を恨んだこともある。て言うか、認めてもらえないことに腹を立てていたのだと思う。わたしだって兄貴みたいに認めて欲しかったから。でも、もうそれも無理。
あれも嘘、これも嘘。そもそも真弓たちが友だちだということ自体が嘘だった。わたしみたいな大嘘つきは、親にとって恥以外の何でもない。わたしはクラス中から白い目を向けられただけでなく、大好きな親に大恥をかかせてしまった。なんでこんな子を産んでしまったのかと思われるに違いない。
兄貴にしたってわたしのとばっちりで、真弓たちから悪く見られるかもしれない。それどころか、兄貴の学校でもわたしのことが話題になって、兄貴も学校に居づらくなってしまうことも考えられる。そうなったら、わたしはどうすればいいのだろう、兄貴にも兄貴に期待を寄せている両親にも顔向けができない。
わたしは鏡に映る自分に、毎日のように悪態をついた。
お前なんかいない方がいい。なんで産まれて来たりしたのさ。嘘をつく以外何もできないブス。お前なんかに生きる価値はない。お前なんか死んじまえ。死んでこの世から消えればいいんだ。そうすれば、きれいさっぱり忘れられるし、わたしだって嫌な想いをしなくて済む。
鏡の中から同じ言葉を言い返すわたしは、脂ぎった髪がぼさぼさだ。やつれた顔の目の下には、黒いクマができている。皮膚はがさがさで唇の色も悪い。不細工な顔がさらに醜くなっている。きっと、もうすぐ死ぬんだろう。
言い争っていると、最後には鏡の中のわたしが泣き出してしまう。ざまあみろだ。だけど、なんでか勝ったはずのわたしも泣いている。
今日、母は仕事に行くかどうか迷っていた。だけど、これ以上お荷物にはなりたくないし、今更心配なんかして欲しくない。兄貴の学費を稼がないといけないのだから、さっさと働きに行けばいい。だから、構わないでとわたしは母に怒鳴った。
だけど母が出かけてしまうと、母はわたしをそれほど大切に想っていないのだと、悲しい気持ちになった。理不尽で自分勝手な考えなのはわかってる。でも、どうしてもそんな風に考えてしまう。たぶん、頭がどうにかなっているに違いない。
ベッドでぼんやり天井を眺めているうちに、うとうと眠って夢を見た。
学校の教室で自分の席に座ったわたしを、クラスのみんなが取り囲み、わたしを指差しながら、嘘つき、ブス、役立たずと、罵倒したり嘲笑したりする夢だ。ここ何日も同じ夢を見てしまう。
夢の中のわたしは、自分を認めてもらおうと必死になって、言い訳したり懇願したり泣きわめいたりする。
でも、早苗と久実は廊下からわたしを見ているだけ。助けてはくれない。そのうち久実は谷山に誘われて姿を消し、早苗も迎えに来た家族と一緒に行ってしまう。
みんなは死ねと言って、わたしに唾を吐きかける。
気がつけば、先生が教壇に立っている。でも、わたしがみんなから罵られているのを見ていながら、少しも止めようとしない。一人で黒板にいろいろ書きながら授業を進め、時折、誰かの名前を呼ぶ。だけど、それはわたしへのいじめを止めるためじゃない。授業の質問に答えさせるためだ。
先生の質問に答え終わった生徒は、再びわたしを罵倒し始める。先生は誰も見ていない黒板を指差しながら、独り言のように授業を続けている。
何でか廊下を母と兄貴が歩いていて、わたしの教室を探しているみたいにきょろきょろしている。だけど、ここだよと叫んでも、わたしの声は二人には届かない。この教室の中の出来事も、わたしが中にいることも、二人は気づかない様子で行ってしまう。
わたしは独りぼっち。誰も助けてくれない。誰も気づいてくれない。そんな思いに脳みそがつぶされそうになりながら、気がついたら部屋の天井を見上げて泣いていた。
悲しみから逃れようと、ふらつく身体で台所へ行きテレビをつける。だけど、少しも面白くない。
テーブルの上のお菓子を一つだけ口に入れ、カップに入れた牛乳を少し飲む。それからテレビを消して部屋へ戻ろうとしたけど、階段の途中で何度も息切れで動けなくなった。
咳をしながらやっと部屋に戻り、だるい身体でお気に入りの漫画や本を広げてみる。でも、全然話が頭に入って来ない。結局、わたしはぐったりとベッドに横になった。
退屈という感じはない。退屈を感じる神経回路が麻痺しているのだろう。うとうとするまで、ぼーっと過ごす。
このぼーっという感じも、初めは何も考えないでぼんやりしていたのだけど、今日は頭の中が溶け始めているのではないかと思うような、ちょっと異常なぼんやり加減だ。身体も日に日にだるくなり、やつれているのに重い感じが強くなっている。
喉の痛みや咳が始まったのは数日前からだ。寒気もひどく、測ってはいないけど熱があると思う。咳は日増しにひどくなり、黄緑色のどろっとした痰が出るようになった。
母にも兄貴にも身体の状態については話していない。でも隣の部屋の兄貴には、わたしの咳が聞こえていたのだろう。母はわたしに病院へ行くよう説得したけど、わたしは部屋の扉を閉めたまま、頑として母の話を聞こうとしなかった。薬を飲んだ方がいいとは思うけど、意固地さの方が勝っていた。
心の奥底では母に助けを求めていた。でもそれができないまま、わたしは部屋に籠もり続けた。だけど、今日は咳が一段とひどくて息苦しい。それに咳をするたびに胸が痛くなる。なんだか部屋の空気が薄いみたいで、いくら息を吸っても吸えてないみたいだ。
わたしは身体に鞭打ち、もう一度下へ降りて風邪薬を探した。そのとき、引き戸が開けられたままの両親の部屋が何となく気になり、わたしはそこへ足を踏み入れた。
普段はめったに入ることがない八畳間の中を、わたしはぼんやりした目で見回した。
本当なら父も一緒のはずなのに、ずっと母はこの部屋に一人でいる。寂しげなその姿が目に浮かぶと、わたしは居たたまれない気持ちになった。
もう出ようと身体の向きを変えたとき、足下の畳の上にアルバムが二冊、無造作に積まれているのに気がついた。
しゃがんでアルバムを開いてみると、それは兄貴が生まれてからの写真集と、両親が若い頃の写真や、家族で撮った写真を集めたものだった。
タンスの上には写真好きの父が出張先で撮った、風景なんかの写真のアルバムが並んでいる。そこを片っ端から調べたけど、わたしだけのアルバムはどこにもない。
わたしは勝手にタンスの引き出しや、押し入れを開けて自分のアルバムを探した。だけど、どこにもなかった。
やっぱり、そうなんだ。わたしは両親にとって、少しも大切な存在じゃなかった。きっと、望まれないで生まれて来たに違いない。早苗と違い、わたしは望まれていなかった。夢で見た産まれる前の母の姿は、わたしの妄想に過ぎなかった。
わたしは兄貴のアルバムを蹴飛ばすと、息苦しいのもかまわず二階へ駆け上った。そのままベッドに倒れ込むと、枕に顔を押しつけて泣いた。
声を出して泣いたせいか、ひどく大きな咳が出た。とても泣くどころではない。咳が続いて息ができないし、胸の痛みも半端じゃない。だけど、どうすることもできない。
しばらくすると、ようやく咳は治まった。だけど、わたしは疲れ切ってぐったりしていた。このままだと本当に死んでしまいそうだ。
やっぱり病院へ行くべきなのか。そうだ、さっきは風邪薬を取りに行ったはずなのに、忘れて上がって来てしまった。何か薬を探さないと。
わたしは枕から顔を外した。すると、わずかではあったけど、白い枕カバーに小さな紅い染みがいくつもついていた。顔を近づけて確かめてみると、咳で出た唾しぶきで濡れたと思われる跡がある。紅い染みはその中にあった。
「血だ」
怖くなったわたしは、机の上のティシューを何枚も引っ張り出すと、それで枕カバーを拭いた。だけど、拭いても拭いても紅い染みは取れない。
また咳が出た。思わず手に持ったティシューを口に当てたら、そのティシューにも紅い斑点がついた。
わたしは、もうおしまいなのだと思った。死んでもいいやと思っていたのに、いざ死が目の前に迫ると、恐ろしさに身体が震えた。
わたしみたいな役立たずは、誰にも大事に思ってもらえない。だけど……。
「お父さん……、お母さん……、怖いよ……。死ぬのは嫌だよ……」
涙が再びあふれ出した。でも泣くと咳が出るので泣けなくなる。咳が止まると、また涙は流れ落ちるけど、声を出して泣くと咳が始まる。
朦朧とする頭の中は悲しみと絶望でいっぱいだった。泣いていると、またもや咳が出始めた。今度の咳はかなりひどく、息を吸う間を与えてくれない。かろうじて吸えた息はほんの少しで、すぐにまた胸の中の少ない空気を搾り出すような咳が続いた。辺りに咳と一緒に出た血が飛び散っている。
息ができず気が遠くなって行く。頭の中で誰かが囁いている。
――思い出しなさい……、思い出しなさい……。
言葉の意味を理解できないほど、頭の中はぼやけていた。
きっとこのまま死んでしまうんだという思いが、わずかに後悔の余韻となって、わたしの意識は消えようとしていた。
だけど不思議なことに、誰かの声はさっきよりもはっきり聞こえるようになっていた。そして、わたしはその声を聴くだけの存在になっていた。
――思い出しなさい……、思い出しなさい……。
わたしは一人の女性の近くに浮かんでいる。その女性はお母さんだった。
わたしは子犬のようにお母さんの周りにまとわりついて、早くお母さんの子供になりたいと思っていた。
お母さんは慈愛とユーモアに満ちた人で、お母さんの子供として生まれて来ることを、わたしはお母さんと約束していた。
まだ身体を持たないわたしは、今のお母さんには見えない。それでもわたしはお母さんにわかってもらいたくて、何度もお母さんに声をかけた。だけど、全然お母さんは気づいてくれない。
でも、ほんとは気づいてくれていると、わたしにはわかっていた。だって、お母さんの優しさや温もりが、わたしをしっかり包んでくれているから。
あれ? お母さんのお腹に何かが見える。はっきりした形はないけど、何かがいるみたい。あなたは誰? わたしを待ってたの? うれしい。それに、ありがとう。会いたかったよ。あなたと一つになることで、わたしはお母さんの子供になれるんだね。
いつの間にか、わたしは違う所に浮かんでいた。ここはどこだろう?
浮かんでいるのは、どこかの部屋の天井近くだ。ぶら下がった蛍光灯が横に見える。蛍光灯の傘の上は埃だらけだ。全然掃除をしていない。
汚いなぁと思いながら周りを確かめる。壁が見えるけれど、頭がぼんやりしているみたいで、今ひとつしっくり来ない。まるでテレビの画像をのぞいているようで、自分がここにいるという実感がない。
だけど、ここはどこなんだろう?
壁に貼られたポスターやカレンダーが見えた。どこかで見たような気がするけど、上から見下ろしているせいか、よくわからない。
わたしは視点を変えて、もっと下を見た。すると、机やベッドが見えた。ベッド脇の床の上に、誰かが横を向いて倒れている。パジャマ姿の女の子だ。
わたしは女の子の顔をよく見ようと思った。すると、すっと床全体が迫って来て、女の子との距離がなくなった。それで、わたしは女の子の顔を間近で見ることができた。
ぼさぼさの髪は、何日もお風呂に入っていないみたい。油でべたべたした感じだ。肌も汚いし顔色も悪い。ご飯をちゃんと食べていないのか、頬が少しこけたように見える。
閉じられた目は涙で濡れ、紫色の唇に血がついている。もしかして、死んでるの?
わたしは女の子に触れようとして、初めて自分に手がないことに気がついた。驚いて身体を確かめると、そこにあるはずの身体がない。どこを見ても身体がない。あるとしたら頭だけか、あるいは目玉だけに違いない。
パニックになって周囲を見渡したとき、わたしはようやくそこが自分の部屋だと気がついた。
じゃあ、この倒れている女の子は誰? わたしはもう一度女の子を見た。
女の子が着ているのは、わたしのパジャマだ。え? と言うことは、この子は――
わたしは悲鳴を上げた。でも、上げているつもりの悲鳴が、実際には声に出ていない。叫び声は耳ではなく、頭の中で聞こえるだけだ。もし、頭があったならだけど。
――嘘! 嘘だ! わたしは死んでない! わたしはまだ生きてるよ!
訴える相手などどこにもいないのに、わたしは周囲に向かって叫んだ。でも、やっぱりそれは、頭の中での叫びだった。
わたしは泣いた。だけど、泣き声なんか誰にも聞こえない。涙だって出ているかどうかわからない。
わたしは自分の身体の上に、浮かんだまま泣き続けた。やがてその悲しみは、次第に怒りへと変わって行った。
倒れている自分に向かって、わたしは罵声を浴びせた。
――何で死んだりしたのよ! この役立たず!
わたしは自分の身体をたたこうとした。だけど、手がないからたたけない。そのことが余計にわたしをいらいらさせた。
――この馬鹿! 死んだふりなんかやめて、さっさと起きなさいよ。ほら、起きろ!
倒れているわたしの身体はぴくりとも動かない。
悲しみに打ちひしがれたわたしは、こうなってしまったことへの腹立ちを、倒れている自分の身体にぶちまけた。
――いいよ、もう。そうやって勝手に死んでれば? あんたにはその姿がお似合いよ。ブスだし馬鹿だし、何の取り柄もない、ただの八方美人の嘘つきだもんね。あんたのせいで、これまでわたしがどれだけつらい想いをしたのかわかってんの? あんたなんか、あんたなんか……。
大っ嫌い!――と叫んだとき、倒れているわたしの目から涙がこぼれるのが見えた。一瞬はっとなったけど、わたしはそっぽを向いた。すると、そこに光が見えた。
何か光輝くものが、わたしと同じように浮かんでいる。眩しいぐらいの光だけど、少しも眩しくはない。
このまばゆい光が何なのかはわからない。ただ、その光からは優しさといたわりが伝わって来る。もしかして、これが神さま?
突然、頭の中で声が聞こえた。
――あなたは、まだわからないのですね。
どうやら喋ったのは、この光らしい。それに、これはわたしに何かを思い出すよううながしていた、あの声だ。
光が話しかけているのはわかったけれど、わたしはすっかり圧倒されていて、光への返答ができなかった。何を言われているのかもわからないし、思考自体が停止してしまったようだ。何も考えることができず、わたしはただ光を見つめていた。
そんなわたしに対して、光が怒る様子はなかった。光はいたわりを放射しながら、淡々とした口調で言った。
――あなたは思い出さねばなりません。
思い出す? 何を思い出すって言うの?――独り言なのか、光に言い返しているのか、自分でもわからないままわたしはつぶやいた。
すると、光の輝きがさらに強くなり、部屋中が光でいっぱいになった。そのあまりの輝きに、わたしは自分がどこにいるのかわからなくなった。
熱くもなければ眩しくもない。だけど、光以外は何も見えない。しばらくすると、光の強さが和らいで行き、視界に何かが見えて来た。
まばゆさがすっかりなくなったとき、そこには見覚えのある眺めが広がっていた。
不思議な世界
わたしはパジャマ姿で薄緑色の空間にいた。
そこは赤い風船の大群で埋めつくされた所だ。風船たちは風に吹かれながら、同じ方向に向かって進んだり止まったりしている。何故か、ここに吹く風はリズミカルだ。
わたしはこの光景を見たことがある。だけど、いつ見たのかは覚えていない。
風船たちは赤いけれど、少し黒っぽくくすんだ感じで張りがない。前に見た風船は鮮やかな赤色で、もっと張っていたような気がする。
赤い風船の中には、青くてしぼんだ風船もたくさん交ざっている。だけど、これも前にはあんまりなかったように思う。
他には黄色い手毬みたいなのと、透明のつぶれた大きなビーチボールみたいなのも飛んでいる。このビーチボールみたいなのがやたら目につくけど、前にもこんなにいただろうか?
それに吹きつけて来る風が異様に熱い。いや、ちょっと待って。これって風なの?
ドッドッと忙しないリズムで、ぶつかって来る風のような流れ。だけど、肌に触れるその感触は風とは違う。わたしは腕を動かして確かめてみた。うん、やっぱり違うようだ。
この抵抗感は空気じゃない。でも、だとしたら息ができないはずだ。わたしは慌てて呼吸をした。息苦しさはあるけど、息が吸えないわけじゃない。と言うことは、やっぱりこれは空気だろうか? だけど、どうも何だか液体のような気がする。
きっと神経がどうにかなっているのだろう。頭はぼんやりしているし、身体もだるくてふわふわしている。流れの勢いは強くないけど、気をつけないと飛ばされそうだ。
そもそも、この流れは何なのだろう? 何だか誰かが怒鳴ったり泣き叫んだりしているみたいだ。
唸るような音が聞こえるわけじゃない。流れが身体にぶつかるたびに、怒りや悲しみの感情がわたしの心に侵入して、中を無理やりかき回すような感じがする。
それに対して、赤い風船たちはわたしを少し爽やかな気分にしてくれる。だけど、よく覚えてはいないけれど、前はもっと爽やかだったような気がする。それに青くしぼんだ風船は、ぶつかって来ても少しもいい気分にしてくれない。
とにかく熱くて息苦しくて、頭も身体もはっきりしない。そこに嫌な感情が勝手に湧いてくる。一言で言えば、とても具合が悪い。
それにしても、ここはどこなんだろう? 何で、わたしはここにいるのだろうか?
わたしは自分がどこの誰なのか思い出せなくなっていた。誰かに聞きたいけど、ここには誰もいない。わたしは泣きそうになった。でも、待って。そうだ、思い出した。
わたしは飛んで来た赤い風船を捕まえて抱きかかえた。赤い風船はわたしに爽やかさを与えると、青くしぼんでしまった。
「ねぇ、あなた、わたしが誰か知ってる?」
わたしは青くなった風船に話しかけた。わたしの記憶が正しければ、ここの風船たちには心があって、人間のように会話ができるはずだ。
――神サマ。
頭の中で女の子の声が聞こえた。やっぱりと思って、わたしはうれしくなった。どうしてわたしが神さまなのかはわからないけど、前にもそう言われた記憶がある。何かの間違いだとは思うけど、神さまと言われて悪い気はしない。
「ここはどこなの?」
――ワカンナイ。
「わかんないって、あなたたち、自分がいる所のこと知らないの?」
――知ッテル。
「じゃあ、ここがどこなのか教えてよ」
――ワカンナイ。
声は少し怯えているように聞こえた。
わたしは風船を手放すと、別の風船を捕まえた。だけど問いかけに対する答えも、怯えている様子も、さっきの風船とまったく同じだ。
その風船を手放して新たな風船を捕まえてみたけど、やっぱり反応は同じだった。
どうしてわたしを怖がるのかと、その風船に聞いてみると、風船は泣きそうな声で答えた。
――ダッテ、神サマ、ミンナノコト、嫌イナンダモン。
わたしは驚いた。同時に、ちょっと腹が立った。
いったい、わたしが何をしたって言うの? わたしはここがどこなのかと尋ねているだけだ。風船たちが嫌いだなんて一言も言っていない。そもそもここのことを知らないのだから、好きか嫌いか以前の話だ。
「何でそんなこと言うの? わたし、あなたたちのこと、嫌ったりしてないよ?」
――嫌ッテルモン。
「嫌ってないってば。ねぇ、何でわたしがあなたたちを嫌ってるって思うわけ?」
――ダッテ……、ソウナンダモン。
これでは埒が明かない。わたしは違うことを聞くことにした。
「じゃあね、どうしてわたしのことを神さまって言うの?」
――神サマダカラ。
「だからさ、何でわたしが神さまなの?」
――神サマダカラ。
わたしは頭がおかしくなりそうだった。ただでも具合が悪くて、頭がぼーっとしているのに、こんなわけのわからないのは嫌だった。
ここがどこなのかわからない。何でここにいるかもわからない。神さまじゃないのに神さまにされて、嫌ってもいないのに嫌っていると言われる。嫌な感情は勝手に湧いて来るし、何でこんな目に遭わなければならないの?
わたしは風船を抱いたまま泣いた。
――神サマ、泣カナイデ。
風船が心配そうに言った。だけど、わたしは泣き続けた。すると、他の風船たちもわたしにぶつかりながら、同じように慰めてくれた。
――神サマ、泣カナイデ。神サマ、泣カナイデ。
「どうして、わたしを慰めるの? みんな、わたしが嫌いでしょ?」
――神サマ、大好キダヨ。
――神サマ、大好キナノ。
「わたしがみんなを嫌いだって言うくせに、わたしのことは好きだって言うの?」
――神サマ、ミンナ嫌イデモ、ミンナ、神サマ大好キ。
「だから、わたし、みんなのこと嫌ってないよ? わたしだって、みんなが大好きだよ」
――嫌イジャナイノ?
「言ったでしょ? わたし、みんなが大好きなの。みんな、自分の元気がなくなるのに、わたしに元気をくれようとするのだって、わたし、感謝してるんだから」
――ミンナノコト、好キ?
「大好き!」
わたしは抱いている青い風船に頬ずりした。
そこへ次々に、他の風船が張りついて来たので、わたしは抱けるだけ風船たちを抱いてやりながら、大好きだよ――と言った。それで風船たちは、ようやくわたしの言葉を信じてくれたようだった。
「ねぇ、もういっぺん聞くけど、わたしがみんなのことを嫌いだって、何で思ったの?」
――聞コエルノ。
「聞こえる? わたしの声が聞こえるって言うの?」
――ウン。
「その声、今も聞こえてるの?」
――聞コエテルヨ。
わたしは耳を澄ませた。だけど、わたしには何も聞こえなかった。だいたいここには音と呼べるものがない。風船たちの声だって、耳で聞いているんじゃなくて、頭の中で聞こえている。わたしが喋る声だって、口を動かして喋ってはいるけど、本当に声が出ているのかどうかはわからない。
風船たちの声と、風船たちがくれる爽やかさ以外では、わたしが感じているのは、流れが運んで来る熱気と、怒りや悲しみの感情だけだ。
この感情の正体はわからないけど、ひょっとしてこの感情を、風船たちはわたしの言葉と受け止めているのだろうか?
「ねぇ、あなたたちが言ってるわたしの声って、この流れから伝わって来る、怒ってるような泣いてるようなもののこと?」
――ウン。
やっぱりそうなのか。わたしは納得すると同時に怒りを覚えた。流れが運んで来る怒りではなく、本当の怒りだ。具合が悪いから余計に腹が立つ。
なんで風船たちが、わたしを神さまと呼ぶのかはわからない。でも何者かが神であるわたしを貶めようと、わたしを偽って嘘の言葉を広めているに違いない。
自分たちを運ぶ流れにそんな言葉を載せられては、風船たちが怯え悲しむのは当然だろう。お前なんか嫌いだって、絶え間なく聞かされ続けているわけだから。
それなのに風船たちは、わたしを大好きだと言う。自分たちがこれほど傷つけられていると言うのに、わたしを無条件に慕ってくれている。それだけに、わたしは偽の神が許せなかった。
また、風船たちの純粋な気持ちにわたしは感激した。この喜びは具合の悪さも忘れさせてくれそうだ。
「ありがとう、みんな……。わたしを慕ってくれて、ありがとう」
――神サマ、喜ンデクレタヨ。
――デモ、オ前ナンカ嫌イダッテ声、聞コエルヨ。
風船たちは喜んだり、困惑したりしていた。
「ねぇ、この流れはどこから来てるの?」
――アソコダヨ。
「あそこって、どこ?」
――アソコ。
わたしはがっくりした。でも、相手は子供だ。気を取り直して聞き直した。
「あなたたち、どこから来たの?」
――ワカンナイ。
「じゃあ、どこへ行くの?」
――イロンナ所。
「そこへは何をしに行くの?」
――ミンナニ、元気ヲアゲルノ。
「わたしにくれたみたいに?」
――ウン。
「でも元気をあげたら、あなたたちの元気がなくなっちゃうじゃない?」
――イイノ。マタ、取ッテ来ルカラ。
「元気を取って来る? どこから取って来るの?」
――アソコ。
もう、わたしはがっくりしなかった。風船たちは場所の名前を知らないのだろう。わたしは違う尋ね方をした。
「そこはどんな所なの?」
――トッテモ、キレイナ所。
「へぇ、わたしも行ってみたいな」
――イイヨ。ダケドネ、壊レテ、ナクナリソウナノ。
「壊れてなくなりそう? そうなったら、困るんじゃないの?」
――困ルケド、仕方ガナイノ。
「何で、そこは壊れそうなの?」
――悪イノガ、壊シチャウノ。
この世界はわたしの想像を超えている。悪いのと言われても、それがどんな姿をしているのか、思い浮かべることができない。それが余計にわたしを怖い気分にさせる。
「その悪いのを、やっつけられないの?」
――ヤッツケヨウトスルケド、ダメナノ。
「どうして?」
――ダッテ、神サマガ……。
風船はそこで言葉を切った。おそらく、わたしの偽物が関係しているに違いない。
わたしに遠慮しないでいいから教えて欲しいと頼むと、風船は話を続けた。
――神サマガネ、ミンナノコト嫌ウカラ、ガンバレナイノ。
思わずわたしはムッとなった。
風船はわたしが怒っていると思ったようだ。小さな声で、ゴメンナサイ――と言った。わたしは慌てて声をかけた。
「いいのよ。気にしないで。さっきも言ったけど、わたしはあなたたちを嫌ってないし、大好きだよ。だけど、その悪いのと戦う人は、わたしが嫌ってるって信じてるのね?」
――ウン。死ンジャエッテ言ワレルカラ。
「そんなことまで言うの?」
――ゴメンナサイ。
わたしの口調が強かったからだろう。風船は、また謝った。人間の子供だったら、頭をすくめて小さくなっていたに違いない。わたしは風船を慰め、怒ってないからと言った。
「それにしても困ったね。わたしの偽物がみんなにひどいことを言うから、みんな力が出せなくなって、そのきれいな所も壊れそうになってるんだね。そこが壊れちゃったら、どうなるの?」
――ミンナ、死ンジャウノ。
「そうなの? じゃあ絶対に何とかしなくっちゃ!」
――ドウスルノ?
「この流れを作ってる人に会って、嘘を広めないように言うのよ」
――ウソッテ何?
「え? 嘘がわからない? 本当じゃないことよ」
――ホントウッテ?
わたしは面食らった。嘘も本当もわからないってどういうこと? だけど、風船たちの純粋さを考えると、そうかと思った。
この世界に暮らす者たちには裏表がなくて、純粋に思ったとおりに生きているに違いない。だから、嘘をつく者などいないわけで、嘘がないから本当もないわけだ。でも、だからこそ偽の神が広める偽りの言葉に、風船たちは反発することもなく、素直に打ちのめされてしまうのだ。
わたしは言い方を変えた。
「あのね、あなたたち、わたしをその人の所へ連れて行ってくれる?」
――一緒ニ行ケバ、ソコヘ行ケルヨ。
「その人って、どんな人なの?」
――トッテモ大キイノ。
「どのくらい大きいの?」
――ウーント大キイノ。
人間の子供だったら、きっと両手をいっぱい広げて表現するのだろう。とにかく途轍もなくでかい相手に違いない。そうでなければ、これだけの流れを起こすことなんてできやしないだろう。
「ところでさ、あなたたち、名前は何て言うの?」
――ナマエ?
「名前がわかんないの? あなたたち、わたしのことを神さまって呼ぶでしょ? わたしはあなたたちのことを、何て呼べばいいの?」
――ミンナ。
「それじゃあ、他の人たちと区別ができないじゃない。この流れを起こしている人と、あなたたちは違うでしょ?」
――ウン。
「この流れを起こしてる人や、あなたたちのことを、わたしは何て呼べばいいの?」
――ミンナ。
わたしは鼻から大きく息を吸って吐いた。
「何で、みんななの?」
――神サマハ、ミンナノ神サマダカラ。
なるほどと思ったけど、質問の答にはなっていない。でも、この世界では個別の名前はないのかもしれない。だから場所のことを尋ねても、わからないという返事になってしまうのだろう。
「じゃあ、行こうか」
わたしは抱いていた風船を手放すと、周りの風船たちに声をかけた。
流れを作る相手に会うのだから、わたしは流れが来る方を向いた。だけど、風船たちは流れに逆らえない。ふわふわ浮かびながら、流れに乗って移動している。仕方なく、わたしは流れの先へ向きを変えると、風船たちと一緒に歩き出した。
こんなに重力を感じるものかと思うほど、身体が異様に重い。でもその一方で、ふらふらふわふわと安定感がなくて浮いた感じもする。重心が定まらないと言うか、病気になって高熱が出たときに歩くような感じだ。
わたしは絶対病気に違いない。こんなに具合が悪いのは、病気だからに違いない。だけど寝る場所などないし、寝ている場合でもない。風船たちが苦しんでるのに、放って置くなんてできないもの。
少し歩いたあと、わたしはバランスを失って転びそうになった。そのまま地面に突っ伏すと思ったら、わたしの身体は流れに持ち上げられて、ふわりと浮かび上がった。
「うわわ!」
流れに身体を持ち上げるだけの力があるとは思ってなかった。わたしは驚きながら、身体のバランスを取ろうと必死に手足をばたばたさせた。だけど上手くコントロールができず、わたしの身体は上下左右に関係なく、くるくると回転し続けた。
それでもいろいろ手足の伸ばし具合や、身体の丸め具合などを調節するうちに、身体を真っ直ぐ前に向けたり、空中を上がったり下がったりするコツをつかんだ。
そうして上手く飛べるようになると、移動がとても楽になった。じっとしていても流れが勝手に運んでくれるのだから、これはいい。
ただ、この流れは相変わらず熱いし、嫌な感情を引き起こす。だから、自制を失わないように心の状態を確かめながら、気持ちを落ち着かせるのが骨折りだった。
わたしの顔のすぐ横に、あの黄色い手毬がいた。
「こんにちは」
手毬に声をかけたけど返事がない。無視されているのかと思っていると、近くにいた風船の一つが教えてくれた。
――ソノ子ハ寝テルヨ。
「寝てるの? 飛びながら?」
――スルコトナイカラ、眠ッテルノ。
ふーん――と言いながら、わたしは眠ったままの手毬を、両手で抱くように持って観察した。見た目は金平糖みたいな手毬なのに、さわって見るとゼリーみたいに柔らかい。指でぷにゅぷにゅ押してみたけど反応がない。
もしかして死んでるんじゃないの? そう思ったとき、わたしは何かを思い出しそうな気がした。死ぬという言葉が何だか引っかかる。だけど、結局は何も思い出せなかった。むず痒いような妙な気分だ。
そのとき、透明のビニールの塊みたいな物が、少し離れた所を飛んで来た。それはあのビーチボールのようだと思っていた物だ。
このビーチボールは風船たちの何倍もの大きさがあるけれど、しぼんでぺちゃんとつぶれたような形になっている。ちょうど柄のない傘が風に飛ばされているような感じだ。
風船たちは流れが止まると動きが止まる。でも、このビーチボールは流れが止まった瞬間、広げた胴体をヒュッとすぼめて、その勢いでさらに前へ進む。次の流れが来ると、また胴体を広げて流れに乗り、流れが止まると胴体をすぼめて前進する。流れのリズムに合わせてしゅっぽしゅっぽと進む様子は、巨大なミズクラゲが泳いでいるみたいだ。
でも、このクラゲには足がない。代わりに傘の窪んだ側の中心に、こんもり盛り上がるような形で、大きな目玉が一つあった。
クラゲがわたしを追い抜いて行くとき、その目玉がぎょろりと回転しながら、わたしを見た。わたしのことが気にはなるけれど、今は構っていられないって感じだ。
突然、目の前に大きな壁が現れた。壁と言っても、わたしたちの前に、立ちふさがっているのではない。風船の群れを二つに分ける仕切りの壁だ。
行く手は大きな二つの入り口に分かれていて、わたしは流れに押されるまま、右手の入り口へ飛び込んで行った。
何となく空や周囲が近くなったと思っていると、またもや二つの入り口が現れ、今度は左の入り口へ入って行った。
こんなことを繰り返すうちに、広かった空間はどんどん狭くなって行き、やがてわたし一人が通れるぐらいの狭い洞窟のような通路になった。流れの勢いは弱くなり、わたしは地面に降りて歩くことにした。
なんだか熱さが増して来ている。後ろから来る熱気よりも、前の方が熱く感じる。
と思ったら、目の前に巨大な大蛇が現れた。あまりにも大きくて、怪獣という言葉でも表せない。
その大蛇は宙吊りにされているのか、頭を下にして胴体が真っ直ぐ天に向かって伸びている。その姿は、わたしが知るどんなビルやタワーより、巨大で長く高かった。
逆さ吊りの大蛇は、あんぐり開けた口で白い山に咬みついている。その姿は山を呑み込もうとしているみたいだ。
大蛇の頭は山と同じように白いけど、空に伸びた胴体は真っ赤だ。その先にある空は真っ白で、大蛇の尻尾は空に突き刺さっているように見える。
一匹だけでも驚きなのに、ここは見渡す限り同じような大蛇が、空からいっぱいぶら下がっている。まるで大蛇の森だ。この異様な光景に、わたしは口を開けたまま固まった。
大蛇の中の大蛇
身体のだるさも忘れ、わたしはしばらく大蛇の森の入り口に佇んでいた。こんな世界があるなんて、いったい誰が知っているだろう。この大蛇たちは生き物なのだろうか? 生き物だとしたら、史上最大の怪物に違いない。
まったく動かないところを見ると、冬眠しているように思えるけど、ここはヒーターに囲まれているみたいに熱い。この大蛇たちは寒いときに眠るんじゃなく、熱いときに眠るのかもしれない。
とにかく今は動かないからいいけれど、動き出したら大変だ。もし見つかったら、逃げることは不可能だ。ここには隠れるところなんかないし、こんな大蛇の攻撃を避けられる者などいないだろう。
と思っていると、風船たちはどんどん大蛇の森に入り込み、群がるように大蛇たちに近づいて行く。わたしたちをここへ運んだ流れは、今はほとんど感じられないけど、わずかな流れがあるようだ。その流れが風船たちを大蛇たちの近くまで運んでいる。
「ねぇ、あなたたち、あの大蛇が怖くないの?」
わたしは近くに浮かぶ風船たちに尋ねた。だけど、風船たちはわたしの質問がわからないみたい。
――ダイジャ? コワクナイ?
「大蛇がわかんないの? ここにうようよいるでしょ? あのでっかくて、上ににゅって伸びてる生き物よ」
――コワクナイッテ、何?
「怖いかって聞いてるの」
――コワイ? 何?
「え? もしかして、怖いがわかんないの?」
――ワカンナイ。
なんと風船たちは怖いという感情がないらしい。まさに怖いもの知らずというやつだ。だけど、ああやって風船たちが近づいているところを見ると、この大蛇たちは危険ではないのだろうか。
「このでっかいのって、危なくないの?」
――ウン。
危ないという言葉はわかるらしい。それはともかく、風船の答えにわたしは半信半疑だった。危なくないと言われたって、こんな大蛇たちを目の当たりにしたら、怖さを知る者ならば、誰だってすくんで動けなくなるはずだ。
でも風船たちがこの森に入って行くのだから、わたしも行くしかない。とは言っても、この大蛇たちが偽の神だとしたら……。
わたしは踏み出そうとした足を止めて、横にいた風船に聞いた。
「ねぇ、わたしがみんなを嫌ってるって言いふらしているのは、この大蛇たち?」
――ダイジャ?
「だから、このでっかいのが、わたしがみんなを嫌ってるって言いふらしてるの?」
――違ウヨ。
「そうか。違うのか」
ほっとしたわたしは、ようやく足を踏み出した。それでも内心はびくびくだ。離れていたって巨大に見える大蛇に近づいて行くのだから、怖さを知るわたしが緊張するのは当たり前だろう。
だけど、周りにいる風船たちは誰も怖がっていない。怖いと思っているのは、わたし一人だ。大蛇が本当に危険でないのなら、一人で怖がるわたしは滑稽に違いない。
わたしたちはゆっくり一匹の大蛇に近づいて行った。近づくにつれて、巨大な大蛇がさらに巨大に見えるので、やっぱり怖くなってしまう。
そんなわたしを気にするでもなく、風船たちはまったく平気な様子で大蛇に近づいて行き、大蛇の目の中に吸い込まれていた。
大蛇の目は普通のヘビの目と同じで、瞳の部分が縦長の裂け目みたいになっている。風船たちはその縦長の瞳の中に、次から次へと入って行く。
大蛇は白い山に噛みついているので、歩いて行くなら山を登らなければならない。だけどそれは大変なので、わたしは跳び上がって宙に浮かび、風船たちと一緒に大蛇の傍まで行った。それでわかったのは、大蛇の瞳に見えたのは本当の裂け目で、縦穴の洞窟みたいになっている。風船たちはその洞窟の中へ入っているのだ。
では大蛇たちは生き物ではないのかというと、そうではない。瞳が洞窟になっているその目は、時々ぎょろりと動いて辺りの様子を窺っているみたいだ。
それでも大蛇が風船たちを攻撃することはなく、大蛇たちはじっと同じ姿勢のまま、風船たちが瞳の中に入るがままにさせている。
わたしが瞳の洞窟に近づいたとき、大蛇の目はぎょろりとわたしの方を向いた。ぎょっとなったけど、どうしようもない。流れはその瞳に向かっている。わたしは怖さで身体を縮こめながら、風船たちと一緒に瞳の洞窟に吸い込まれて行った。
洞窟の中は真っ暗だろうと思ったけど、どういうわけか薄明るい。それに、すごい熱気が奥から噴き出して来る。その熱気にわたしはたじろいだけど、風船たちはこの熱さが平気みたいだ。ゆっくりだけど何でもない感じで、どんどん奥へ進んで行く。
地面に足を下ろしたわたしは、気を取り直して風船たちについて行った。すると洞窟の奥で、またもや驚くべき光景を目にすることになった。
洞窟の奥は大蛇の口の中につながっているらしく、広がった空間の中に、大蛇が食らいついていた白い山の頂きがあった。その頂きに無数の大蛇が、外の大蛇と同じ格好で食らいついている。つまり、大蛇の中は大蛇だらけだったわけだ。
もちろんこの大蛇たちは、外の大蛇よりは小さい。それでも、神社やお寺のご神木よりも遥かに太くて大きい。動物園で見る大蛇なんか全然比べ物にならないし、恐竜よりも遥かにでかい。きっと恐竜なんか一呑みだろう。これ一匹だけでも、町が大騒ぎになるほどの怪物だ。そんな怪物たちが上からびっしりとぶら下がっている。
この怪物たちの頭もやっぱり白くて、胴体は赤い。見上げてみると、胴体のあちこちから火が噴き出ていた。どうやら熱さの原因はこの火柱らしい。この炎のせいで、尻尾の方がどうなっているのかはよく見えない。
また怪物の胴体には所々に、ぎょろぎょろ動く目玉がいっぱいついている。とても不気味な姿だ。
だけど風船たちは少しも怖がる様子がなく、火の中をくぐりながら上へ移動して行く。その途中で怪物の胴体に次々にへばりつくから、怪物に元気をあげているのだろう。この怪物たちも風船たちから見れば仲間であり、みんなであるのに違いない。
わたしはできれば大蛇たちに近づきたくなかった。だけど、先へ進むには風船たちについて行くしかない。
咬まないでねと言いながら、大蛇たちのすぐ傍へ行くと、わたしは跳び上がった。
宙に浮かんだわたしは、風船たちと一緒にふわふわと大蛇に沿って上昇した。すると、突然目の前に火柱が上がった。
わたしは慌てて大蛇の胴体にしがみついた。そのとき伸ばした手の先に目玉があった。驚いて手を引っ込めると、目玉はぎょろりとこっちを向いた。わたしは思わず後ずさりをしながら身体を起こした。
「あれ? わたし、立ってる?」
大蛇は柱のように上に伸びていたはずなのに、大蛇の胴体は地面のようにわたしの足の下にある。
振り返ってみると、大蛇がかぶりついている白い岩が壁のように見えた。本当は崖の下のように見えるはずだ。
洞窟の入り口はその白い壁の上の方にあって、そこから風船がどんどん入って来る。
前を見ると、目玉がたくさんある胴体が道のように伸びていて、数え切れない火柱が噴き上がっている。
ここの重力はどうなっているのだろうと思いながら、わたしは風船たちが動く方へ歩いた。浮かんでいる方が楽だけど、さっきみたいにいきなり炎が噴き上がると、浮かんでいては焼けてしまう。炎を避けるためには歩くしかなかった。
でも具合が悪いのに、炎や目玉を避けて進むのは酷だった。それに、たくさんの目玉に見張られているみたいで緊張するし、炎の近くは熱くてとても息苦しい。風船たちのためとは言っても、やっぱりつらい。
どこまで進むのかわからないままふらふら歩いていると、目の前に炎が噴き上がった。うわっと思ったら、突然足下が大きく動いた。でも、本当の地面じゃないから地震ではない。この怪物が動いたのだ。間違いなく、この大蛇は生きている。
怪物の胴体は大きく膨らんだように感じられた。足下からぐっと持ち上げられたみたいになって、バランスを失ったわたしは炎の中に転がった。
「うわっ、熱っ、熱っ!」
慌てて炎の中から這い出したわたしは、火傷をしなかったか身体中を触って確かめた。だけど幸いと言うか、どういうわけだかどこにも火傷はなかったし、パジャマも焦げたりしていない。
髪の毛だって、チリチリになったのではないかと心配したけど、ボサボサなだけで、どうにもなっていなかった。どうして火傷をしなかったのかはわからないけど、ようやくわたしはほっとした。それにしたって、この熱さはほんとに勘弁してもらいたい。
――敵ガイルゾ、火ヲ吐ケ!
小人が喋ってるみたいな、小さな早口の甲高い声が聞こえた。周囲を見渡したけど、敵とわかるようなものはいない。もしかして敵って、わたしのことだろうか?
わたしはしゃがむと、足元の赤い大蛇に声をかけた。大蛇の上を歩いていたし、火に焼かれても大丈夫だったからか、わたしの大蛇への恐怖はどこかへ行ってしまったようだ。
「ねぇ、敵ってどこにいるの?」
――知ラナイ。
大蛇と思われる声が聞こえた。だけど、さっき聞こえた声とは違う。若い女性みたいな声だ。その少々投げやりな言い方に、わたしは少しむっとした。
「敵がいないと、火を吐かないの?」
――ソンナコトナイ。
「どんなときに吐くの?」
――イツモハ少シダケ。敵がイタラ、タクサン。
「敵がここにいないなら、この火はどんな役に立ってるの?」
――知ラナイ。
大蛇の言葉は素っ気なかった。返事をするのが面倒臭いみたい。
――敵ガイルゾ、火ヲ吐ケ!
また小人の声がした。わたしはもう一度周りを見たけど、何もいない。
「ねぇ、さっきから誰かが火を吐けって言ってるけど、誰が言ってるの?」
――知ラナイ。
「知らない相手に言われて、火を吐いてるわけ?」
――ソウ。
嫌そうな喋り方に、わたしは腹が立った。威張るわけではないけれど、風船たちはわたしを神さまだと言って慕ってくれている。大蛇も風船たちの仲間だったら、少しはわたしに敬意を払ったっていいはずだ。
「あなた、わたしが誰だかわかってる?」
――神サマ。
小さな消え入りそうな声が聞こえた。
「あなた、わたしのこと、嫌いなんでしょ? だから、そんな風に喋るのね?」
――ゴメンナサイ。神サマ、大好キ。デモ、壊レソウデ喋レナイ。
「壊れそう? 死んじゃうってこと?」
――ソウ。
わたしは、どきりとした。こんな怪物のような大蛇が死にそうだなんて、それほど大変なことが、今この世界で起きているということなのか。
「何で壊れそうなの? 敵が来てるから?」
――食ベル物、ナイ。
「食べる物? 食べる物って、どんなの?」
――トッテモキレイデ、飛ンデ来ル。
「それが今は飛んで来ないの?」
――モウ、ズット来ナイ。ダカラ、体、小サクナッタ。
これでも体が小さいだなんて驚きだ。以前はどれだけ大きかったと言うのだろう?
――ソレニ、元気、モラエナイ。
「元気? 元気って、この子たちが分けてくれる元気のこと?」
わたしは風船たちを見回して言った。大蛇は、そうだと答えた。
確かに、わたしが記憶している風船たちはもっと真っ赤で、ぱんと張ったような感じがあった。でも、今の風船たちは赤黒くて張りも弱いし、青くしぼんだものもたくさん交ざっている。青い風船は分け与える元気がなさそうだし、赤黒い風船が分けられる元気は少ないのだろう。
――食ベル物、元気、ドッチモナイト、火ヲ吐ケナイ。
「火が吐けなくなると、どうなるの?」
――壊レチャウ。
これは大変だ。この大蛇たちの役割が何なのかはわからない。だけど、大蛇たちが死んでしまうことは、世界の滅亡とつながっているに違いない。
――敵ガイルゾ、火ヲ吐ケ!
また、あの声がした。見上げると、頭の上は天井だ。この天井は、外側の大蛇の体壁なのだろう。その天井から小さくて真っ白なヘビが、ぶらんとぶら下がっている。
――敵ガイルゾ、火ヲ吐ケ!
どうやら、声の主はこのヘビのようだ。太さはわたしの指ぐらい。長さは一メートルもなさそうだ。
「敵って、どこにいるのよ?」
わたしが尋ねても、白いヘビには聞こえないのか、同じ台詞を繰り返すばかりだ。
わたしは白いヘビと話すのは諦めて、風船たちに食べ物の場所を尋ねた。だけど風船たちの答は、ワカンナイ――だった。
場所の名前がわからないだけかと思って、そこへ連れて行けるかと聞いてみたけど、答はやっぱり、ワカンナイ――だった。
困った。このままでは世界が滅びてしまう。だいたいわたしの偽物は、何故この世界を呪うのだろう? 風船たちが元気を取りに行く所は、悪いものが壊そうとしているし、大蛇たちの食べ物も飛んで来なくなった。これらのことは無関係とは思えない。両者はどこかでつながっているはずだ。そして、それを操っているのは偽の神に違いない。
わたしは神さまと呼ばれているのに、この世界のことを何もわかっていない。それなのに偽の神の方は、世界を掌握していて思いどおりに操っている。
これでは、どちらが本物の神なのかわからない。悔しいけど、風船たちが誤解しているだけのことで、向こうの方が本物の神なのかもしれない。
だけど、たとえそうだとしても許せない。わたしを慕ってくれる者たちが、理不尽に滅ぼされてしまう。それを黙って見ているなんて、わたしにはできない。
とにかく世界を滅ぼそうとする偽の神の正体を暴くしかない。
わたしは大蛇を励ますと、先を急いだ。大蛇の胴体はとても長く、吐き出される炎は熱い。でも、それで燃えるわけではないのがわかったから、わたしは火の中に何度も飛び込みながら進んだ。
途中で天井からぶらさがる白いヘビに、何度も出くわした。白いヘビたちは同じ声、同じ口調で、敵ガイルゾ、火ヲ吐ケ!――と繰り返している。まるで録音テープを放送しているスピーカーみたいだ。
可哀想に、足下の赤い大蛇は、こんなちっぽけなヘビに言われるまま炎を吐き続けている。食べ物も元気も不足しているのに、こんなことが続いたら死ぬのは当たり前だ。
わたしは大蛇に同情したけど、自分もかなり具合が悪い。特にこの熱気が耐えがたい。ふらふらになりながら進んでいたけど、わたしはとうとう炎の中に倒れ込んだ。
熱くても通り過ぎる瞬間であれば我慢ができる。だけど倒れたままだと、身体が焼けなくても焼けそうだ。あまりの熱さに悶えながら炎から這い出したけど、もう限界だ。
ぼんやりした頭を上げると、前方に白い岩が迫っているのが見えた。その岩の上方には洞窟の入り口が見える。わたしは落胆の呻き声を上げてうなだれた。
ここは初めに入って来た場所だ。洞窟が縦長の亀裂みたいになっているのが、その証拠だ。あれは外側にいる大蛇の瞳の形だ。
きっと頭がぼんやりしてるから、何度も転びそうになっているうちに、進む方向を間違えて元の場所へ戻ったのだ。でも、もう一度長い大蛇の上を移動する力は残っていない。
朦朧としながら風船たちに目を遣ると、青くしぼんだ風船たちが、ゆっくり移動しながら岩の上の洞窟へ入って行く。洞窟からこちらへ出て来る風船は一つもいない。
おかしいなと思ったわたしは、力を振り絞って立ち上がった。ふらふらと白い岩の傍まで行くと、大蛇の白い頭が大きな口で岩に咬みついている。
やっぱり初めの所に戻ってしまったようだ。わたしはがっかりしながら、大蛇の頭に手を触れた。途端に大蛇の頭ごと身体が前に倒れ、わたしは大蛇の頭から岩の上に転げ落ちたような格好になった。
体をさすりながら立ち上がると、目の前に洞窟があって、青い風船たちがその中へ移動して行く。後ろを振り返ると、白い岩に咬みついた大蛇が真っ直ぐ逆立ちをしていた。
見上げると、初めに見た時よりも大蛇の胴体が太くなっていて、隣り合った大蛇との間が狭くなっている。それぞれが火を噴き出しているから、一番上の様子はわからない。
もう一度洞窟に目をやると、やっぱり風船たちは出て行くばかりだ。中に入って来る風船は一つもない。ここが出口なのは間違いないようだ。
わたしはしばらく考えて、ようやく結論にたどり着いた。それは、この大蛇には尻尾がなく、両端が同じような頭になっているということだ。それぞれが白い岩に咬みついていて、こっちと向こうの白い岩をつなぎ止めているのだろう。それにどんな意味があるのかはわからない。でも恐らく、それはこの世界にとって大切な役目なのだと思う。
洞窟を抜けると、外の大蛇の森に出た。どの大蛇も初めに見たときよりも、太くなっている。
上を見上げると、白い空がとても低く見えた。でも、あの白い空は本当は空じゃない。ここと同じ白い岩だ。さっきはあそこにいたのかと思うと、とても奇妙な気分になった。
そのとき、急に上の岩が遠ざかった。同時に大蛇たちの胴体が、細くなって伸びて行く。やっぱり思ったとおりだ。この大蛇たちは二つの岩を結びつけ、近づけたり遠ざけたりする。それには途轍もない力がいるはずで、その力を生み出すには大蛇が言った食べ物と、風船たちがくれる元気が必要なのだ。わたしは改めて、何とかしなければと思った。
大蛇の森を離れると、わたしたちは再び狭い通路に入った。周りは青い風船ばかりだ。赤いままの風船はいない。通路は徐々に広くなり、それに従って青い風船たちの数が増えて行く。流れも次第に強くなり、わたしの身体も再び浮かび上がった。
さっきまでとは違うのは、後ろから流れに押されているのではなく、前の方に吸い寄せられるみたいということだ。空間の色も薄緑色ではなく薄い青だ。
後ろからの流れがないからか、あの嫌な感情は湧いて来ない。だけど代わりに滅び行く世界の絶望が辺りに満ちている。
熱気は大蛇の森を訪れる前より強い。と言うことは、流れの熱はあの大蛇たちが出す炎の熱なのかもしれない。その熱が流れに乗って、世界中へ広がっているのだろう。
それはおそらく敵が現れたという警報の意味なのだろう。だけど、普段の炎にはどんな意味があるのだろう?
わたしは大蛇の炎がなかったら、世界はどうなるのかと考えた。それでわかったのは、きっと、世界は寒さで凍えてしまうということだった。きっと大蛇は世界の温度を調節しているのだ。わたしは納得して一人うなずいた。
そのとき、ずっと先の方に何かが動いているのが見えた。同じリズムで動いている。
近づいて行くうちに、それが途方もなく巨大な口だとわかった。空間全体が口になったようで、口の三方には鋭く尖った三枚の歯があった。それがリズムを刻みながら、すごい勢いで噛み合わさっている。もしあの歯に触れれば、真っ二つにされてしまうだろう。
いつの間にかビーチボールのクラゲたちが、青い風船たちにたくさん交じっている。何だか妙な雰囲気だ。
不安と恐怖に包まれながら、わたしはぐいぐい引っ張られて行く。すべての物が巨大な口の中に吸い込まれている。それはわたしも例外ではない。わたしは身体のバランスが取れなくなって、ぐるぐる回り出した。
巨大な口がどんどん迫って来る。三枚歯の動きに合わせて、シャキンシャキンという音が聞こえて来そうだ。その三枚歯がとうとう目前に迫ると、わたしは悲鳴を上げた。だけど、叫ぶだけで抗うことはできない。
強い力で引き寄せられたわたしに、すごい勢いで三方から歯が迫る。もうだめだ! わたしは目をぎゅっと閉じた。
壊れゆく虹の森
すぐ後ろから衝撃が伝わって来た。歯が噛み合わさった振動に違いない。間一髪で噛み切られずに済んだらしい。
と思ったら、今度は周囲からすごい圧力が襲って来た。絶対に死ぬと思うほど、わたしは押しつぶされそうになった。そんなわたしの中に、強烈な怒りと悲しみが四方八方から押し込まれる。身体は外から押しつぶされそうなのに、心は中から破裂させられそうだ。
身体がつぶれそうになる恐怖と、心が弾けそうな絶望でパニックになったわたしは、何が何やらわからないうちに、強い力で移動させられた。と思ったら、再び圧力と絶望感の攻撃がわたしに加えられた。その威力はさっきのよりさらに強くなっている。
わたしは自分が生きているのかわからないほど、放心状態のままぐるぐる回転しながら飛んでいた。どうやら外へ放り出されたらしい。
しばらくしてようやく我に返ったわたしは、がんばって身体の回転を止めると、後ろを振り返った。だけど、もうさっきの怪物は見えなくなっていた。見えるのは無数の青い風船たちと、そこに交じったクラゲや手毬たちだけだ。
怪物の姿は見えないけれど、わたしたちを押し出す流れには、わたしを破裂させようとした、あの絶望的な感情が載っている。と言うより、この流れはあの強烈な怒りと悲しみそのものだ。
おそらく間違いない。あの巨大な口の生き物こそが、偽の神の正体だ。
対決せねばと、わたしは流れに逆らって偽の神の所へ戻ろうとした。あんな怪物に勝てるわけがないけれど、風船たちを救うためにはあの怪物と戦うしかない。だけど、心も身体もぼろぼろのわたしは、どんどん押し流されて偽の神から引き離されて行った。
辺りは最初にいた所と同じ薄緑色になっていた。でも、風船たちはみんな青くしぼんだままで、クラゲたちもたくさんいる。みんな何も言わないけど、わたしと同じ目に遭ったはずだ。
「みんな、大丈夫?」
風船たちに声をかけたけど、なかなか返事は返って来ない。風船たちもかなりダメージを受けたのに違いない。
それでも、しばらくすると風船たちの方が、わたしを気遣い心配してくれた。何て優しい子たちだろう。わたしは切なくて泣きそうになった。
次から次にあの嫌な感情が、追い打ちをかけるように押し寄せて来る。わたしは少しでも対抗しようと、みんな、大好きだよ!――とできる限りの大声で叫んだ。
――神サマ、アリガト。
――神サマ、大好キ。
あちらこちらから風船たちのうれしそうな声が聞こえた。風船たちを元気づけるつもりが、自分の方が元気づけられた。
わたしは何としてもあの偽の神と戦わねばと、決意を新たにした。だけど、決心ばかりで方法が思いつかない。
あそこまで巨大な相手と、どうやって戦えばいいのだろう? 今回は噛み裂かれることなく無事に通り過ぎた。でも、あの歯に噛まれてはおしまいだ。
それに歯を避けられても、さっきみたいな目に遭わされて、あっという間に放り出されたのではどうしようもない。
しばらくして、行く手を二つに分ける壁が現れた。その先へ進むと、また道は二つに分かれる。そんなことを何度か繰り返すと、またもや道は狭い洞窟のようになった。そこを通り抜けると、わたしたちは透明な木が密生した、不思議な森に出た。
わたしの背丈の何倍もある森の木々は、どれも同じ種類の木だ。周囲にいっぱい伸ばした枝には、葉っぱが一枚もない。幹も枝もガラスでできているみたいに透明で、向こうが透けて見える。でも触ってみると、ビニールのように柔らかくて温もりもある。
最初に森を見たときには、何か透けて見える物がたくさんあるとしか思わなかった。
でも次の瞬間、森全体が七色の光のグラデーションに包まれた。わたしは驚いて言葉も出て来なかった。疲れも忘れ、ただ茫然とその美しさに見とれるばかりだった。
木の幹や枝は虹色の光の通り道だ。根元から幹の中を昇って来た七色の光が、すべての枝へと伝わって行く。枝の先まで光が届くと、そこに虹色の花が咲く。花はわたしの手ぐらいの大きさだ。
虹色の花というのは、七色の花びらがあるのではない。花が色を変えながら光り輝くのだ。花は赤から紫まで、虹の七色どおり順番に光って行く。最後の紫色に輝くと、花は細かく砕け散るように消えてしまう。あとには卵ぐらいの大きさの、雪のように真っ白な丸い実が残る。
風船たちは木に群がってこの白い実を食べる。とは言っても、風船たちには口がない。正確には食べると言うより、吸収すると言う方がいいのかもしれない。
とにかく風船たちは次から次に白い実を食べて、青い色から赤い色に変わって行く。
風船たちの数もものすごいので、せっかくできた実はすぐになくなってしまう。だけどその頃には、再び木の中を虹色の光が昇って来て、枝の先に新たな虹色の花を咲かせる。それがずっと繰り返されるから、白い実が足らなくなることはなさそうだ。
わたしは近くにできた白い実を、手に取ろうとして指で触れた。すると、それだけで実はすっと消えてしまった。同時に、実に触れた指先から全身に爽やかな感じが広がって来た。これは風船たちがくれる、あの爽やかさと同じだ。
きっと、この白い実こそが元気の素だ。風船たちはこの実を吸収して、他の仲間たちに分け与えるのだろう。
わたしはこの世界のことが、ほとんどわかっていない。でもあの大蛇たちのように、その場から動けない者たちが、他にもたくさんにいるのかもしれない。
風船たちはそういう者たちに代わって、この森へ元気を集めに来ている。それは何の見返りも求めない、優しく高貴な行いだ。
人間もこの風船たちを少しは見習うべきだと、わたしは思った。
わたしが虹の森に見とれていると、黒いとげとげしたイガグリのような物が、どこからか二つ並んでふわふわと飛んで来た。一つの大きさはソフトボールくらいだ。
二つのイガグリは互いの接点を軸にして、くるくるとゆっくり回転している。その回転があるからなのか、風船たちを動かす流れに逆らって動けるようだ。
次の瞬間、近くにいた風船にイガグリが接触した。風船はたちまち破裂して、ばらばらになった。驚くわたしの目の前で、イガグリは次々に風船たちを破壊し続けた。
イガグリが壊すのは風船たちだけではない。森の木の枝にイガグリが触れると、枝はガラスが割れるように砕け散った。幹に触れると、木全体が砕け散った。
きっと、これがあの白いヘビが警告していた敵に違いない。
イガグリは次第にわたしの方へ近づいて来る。まるでわたしに狙いを定めたみたいだ。でも、わたしは恐れよりも強い怒りを感じていた。大切な風船たちを殺し、みんなの森を破壊するなんて絶対に許せない。
わたしに攻撃手段はない。せいぜい威嚇の大声を出すぐらいだ。でも、そんなことでイガグリは止まらない。とうとう、わたしのすぐ近くまで寄って来たけど、わたしは逃げなかった。と言うか、本当は固まってしまって動けなかった。
目の前までイガグリが迫ったとき、わたしは自分が消え去ることを覚悟しなければならなかった。
そのとき、上から何かがにゅっと伸びて来た。それは、もう少しでわたしに触れそうになっていた、イガグリに覆いかぶさった。
固まっていたわたしは頭も身体も動かない。目だけ動かして上を見ると、そこにはビーチボールのクラゲが浮かんでいた。
何とクラゲには、ちゃんと足が生えている。中心にある目の周囲から、たくさんの足が出ていて、そのうちの一本が、わたしに迫っていたイガグリを捕らえて、自らの中に取り込んでいた。捕らえられたイガグリはクラゲの足の中で、外へ出ようと藻掻いているようだ。
イガグリを取り込んだ足は、しゅるしゅると縮んで胴体の中に隠れた。それで、足の中に取り込まれていたイガグリも、一緒にクラゲの胴体の中に移動した。
クラゲの胴体の中には、鋭い牙がたくさん生えた小さな口がいくつもある。それがイガグリを周囲から細かく食いちぎっていった。
見えるのは口だけだ。まるで透明の魚みたい。でも、噛み砕かれたイガグリの破片は、動く口と一緒には移動しないで、その場に漂ったままだ。つまり、動く口には体はなくて、本当に口だけのようだ。
よく見ると、他の所にもイガグリが出現していて、クラゲたちはあちらこちらでイガグリを捕らえていた。
クラゲの足の先には、マカロニの穴のような窪みがある。その窪みを素早く広げてイガグリを捕らえ、そのまま足の中へ取り込んでいた。
でも中には捕獲に失敗し、伸ばした足をイガグリのトゲでちぎられるクラゲもいた。ちぎれた足は縮んで小さくなり、最後にはガラスのように細かく砕け散ってしまった。
これが人間の戦いだったら、戦えない者は我先に逃げるだろう。だけど風船たちは、イガグリとクラゲの戦いなどお構いなしに、夢中になって白い実を食べている。仲間がイガグリにやられても騒いだりしない。
だけど、そのように風船たちが淡々とやるべきことをやっているのは、仲間への無関心からではなく、使命だからに違いない。風船たちが世界中に元気を運ばなければ、そこにいる他の仲間たちは死滅するだろう。風船たちも命懸けで働いているのだ。
わたしはイガグリがどこから来るのか、確かめてみることにした。
途中に現れるイガグリを避けながら、森の奥へと歩いて行くと、全体が真っ黒に変色した木を見つけた。他の木が虹色に輝いても、この木は輝くことなく、ずっと黒いままだった。
木の周りには、イガグリが群がるように浮かんでいる。集まっているクラゲたちは、忙しそうに足を伸ばして、次々にイガグリを捕らえていた。クラゲの中には、捕らえたイガグリの残骸で、全体が真っ黒になっている者もいた。
真っ黒になったクラゲは、イガグリを捕らえるために伸ばした足までが黒かった。イガグリを捕らえた足を、胴体の中へ引っ込めたそのクラゲは、そのまま固まったように動かなくなった。次の瞬間、クラゲは崩壊した。
崩壊したクラゲの表面部分はちぎれた足と同じように、ガラスみたいに粉々に砕け散った。でも、真っ黒になった中身は砕け散らずに、割れた卵のようにどろりとなって下へゆっくり落ちて行く。
飛び散ったクラゲの皮の破片は、きらきらと光りながら辺りを漂い、わたしの方まで広がって来た。よく見ると、漂っていると言うより、ひらひら舞っている感じだ。その様子は、とても小さな透明の蝶々のようで、見とれるほど美しかった。
だけど、じっくり見ている暇はない。それに、この蝶々たちはクラゲの死骸の一部であり、見ていて悲しいものだ。
数え切れないほどイガグリがいる状況は変わらない。他のクラゲたちは仲間の死を恐れも悼みもせずに、必死な様子でイガグリを捕まえている。それを続けると、自分がどうなるのかがわかっているだろうに、それでもクラゲたちは戦いをやめなかった。
そんなクラゲたちの奮闘にもかかわらず、イガグリの数は減っているようには見えなかった。むしろ、どんどん増えて来るようだ。
どういうことだろうと思い、わたしはじっと辺りを観察した。すると、黒くなった木の枝先から、次々にイガグリが出て来ていた。木をよく見ると、中にイガグリが密集していた。木の黒さの正体は、中に詰まったイガグリだった。
モゾモゾゴソゴソとうごめく無数のイガグリたちが、七色の光の代わりに透明の木の中を移動している。その数はここに集まっているクラゲたちの比ではない。
それに、イガグリたちを捕獲するクラゲたちの動きも、少し緩慢なようだ。懸命に戦ってはいるのだけど、足を効率よく動かしているようには見えない。十本あっても、二、三本しか動いていない。残りの足はすることもなく、ぶら下がっているだけだ。
イガグリを捕らえる足の伸ばし方も、素早く伸ばす者もいれば、疲れたように伸ばす者もいる。そんなのは逆にイガグリの餌食になって、伸ばした足をちぎられてしまう。
わたしはクラゲたちを応援しながら、どうしてこんなに動きが悪い者がいるのだろうと考えた。でも、すぐにその理由は推測できた。
わずかではあるけど、ここにも流れがある。この流れは、やはり偽の神の呪いに満ちている。恐らくそれがクラゲたちの動きを鈍らせているのだ。
クラゲたちは神のために戦っている。それなのに、その神から罵られるのだ。これではイガグリと戦うことが正しいかどうかもわからなくなるだろう。
それでもクラゲたちが戦うのは、神を慕っているからだ。世界を守ることが神のためだと、信じているからに違いない。
切なさの涙をこらえ、わたしはクラゲたちを鼓舞してまわった。
「みんな、がんばって! わたしはみんなのこと、わかってるからね! わたし、みんなのことが大好きだし、とっても感謝してるの! だから、絶対に負けないで!」
鼓舞した効果があったのか、クラゲたちの動きがよくなり出した。ところが、よかったと思ったのも束の間、わたしは驚きで声が出せなくなった。
音が聞こえる所ならば、パリンとガラスが割れるような音がしただろう。真っ黒だった木が壊れ、中に詰まっていたイガグリが、一気に外へあふれ出た。
もう、ここにいるクラゲたちだけではどうにもできない。しかも、壊れた木の根の部分から、次々に新たなイガグリが、湧き出るように出て来ている。
木が壊れて飛び出したイガグリの集団が、わたしの方へ向かって来た。近くにいた風船たちは、あっと言う間に破壊された。イガグリは上にも下にもいるし、横にも広がりがあって避けようがない。走ろうにも、わたしは身体が重くて素早くは動けない。
もうだめだ!――わたしは逃げるのを諦めた。
すると、わたしの前にクラゲたちが降りて来て楯になってくれた。
たくさんある足で、必死にイガグリたちを捕まえようとするクラゲたち。だけど、イガグリの数はクラゲの足より多い。クラゲたちは次々に崩壊して行った。
――逃ゲテ! 神サマ、早ク逃ゲテ!
クラゲと思われる声が、頭の中で叫んだ。次の瞬間、目の前のクラゲが崩壊した。
わたしのために――わたしは泣き叫びそうになった。だけど、イガグリはその暇を与えてくれなかった。もう守ってくれる者はいない。
そのとき、わたしはひどい咳に襲われた。それに合わせるかのように、突然つんざくような轟音が振動となって鳴り響き、森全体が大きく揺れた。
揺れと息苦しさでわたしは立っていられなくなり、地面に這いつくばった。イガグリが迫っているのに動けない。もうだめだ。
でも、一向にイガグリが襲って来る様子がない。それに何だか流れの勢いが強くなったようだ。イガグリたちは吹き飛ばされたのだろうか?
顔を上げると、少し先の地面に裂け目ができている。そこに風船たちやイガグリたちが、次々に吸い込まれていた。
見ていたわたしも吸い込まれそうになったので、必死に地面にしがみつこうとした。だけど、しがみつく物がなく、わたしの身体はふわりと浮いた。
裂け目に近づくにつれ、引き寄せる力が強くなる。藻掻いてもどうにもならない。
暗い裂け目が目前に迫って来た! そのとき、子供の声が聞こえた。
――神サマ、危ナイ!
わたしのすぐ前に黄色い手毬がいた。眠っていたはずのその手毬は、雨傘が開くようにバッと大きく広がった。その姿は八角形の凧のようだった。
そうやって広がった手毬は、穴をふさぐように裂け目に引っかかった。他にも近くにいた手毬たちが次々と体を広げて、同じように穴の上に覆い被さった。そのお陰で、わたしは裂け目に吸い込まれるのを免れた。
だけど、裂け目はその部分だけではない。すぐにわたしはその先へ引っ張られた。すると、次々に変化した手毬たちが、先回りをするように裂け目をふさいでくれた。
「助けてくれて、ありがとう」
裂け目が完全にふさがり、わたしは手毬たちにお礼を言った。でも、凧になった手鞠たちは返事をしない。妙に思って触れてみると、柔らかかった手毬たちは、硬い石になっていた。
「え? どうして?」
驚くわたしに、近くにいた青い風船が声をかけた。
――ミンナ、役目ヲ、果タシ終エタノ。
「果たし終えた? 死んじゃったってこと?」
――ウン。
「そんな……、わたしを助けるために……」
――アアスルノガ、役目ナノ。
近くにいたかなりの数のイガグリが、裂け目の中に吸い込まれたようだ。だけど壊れた木の根元から、別のイガグリが次々に出て来る。
ショックを受けたまま、わたしは顔を上げた。虹色に輝く木が数本立っている。でも、その向こうは――
「嘘でしょ?」
森の奥の方は、見渡す限り真っ黒で、上空はどんより曇っている。いや、曇っているように見えたのは、クラゲたちがびっしりと集まっていたからだ。
破壊された森の中では、クラゲとイガグリの死闘が繰り広げられていた。もはや風船たちが立ち入る隙はない。入ればたちどころに、イガグリに引き裂かれるだけだ。
この世界は崩壊寸前なのだと、わたしは悟った。
わたしは神さまなのに、何もできない役立たずだ。わたしは自分の無力を呪った。すると、それを嘲笑うかのように、偽の神が放った絶望の雰囲気がその濃さを増した。
わたしは走った。身体は重くだるいけど、風船たちが流れる方へ向かって力の限り走った。時折、咳き込んで息ができなくなった。そんなときは必ず轟音と地震が起こった。
新たにできた裂け目には、手毬たちが命を捨てて立ち向かってくれた。あそこに吸い込まれたらどうなるのだろう? 想像するのも怖いけど、木の根元からイガグリたちが現れたことを考えると、裂け目の中はイガグリたちの住処なのかもしれなかった。
咳が落ち着くと、わたしは立ち上がって走った。決して逃げるのではないと、必死に自分に言い聞かせた。
みんな、わたしのために死んで行く。そのみんなを見捨てて逃げるのではない。この世界を救うために走るのだ。そう、わたしは偽の神と対決しなければならない。どんなに強大な相手だとしても。
いつしかわたしは森を出て、薄い青色の空間にいた。
空間は次第に広くなり、赤さを増した風船たちと一緒に、わたしは宙を舞った。後ろから流れに押されているのではない。前方へ引き寄せる力で飛んでいた。
やがて空間いっぱいの巨大な口が現れた。今度の口は上下から、包丁のような歯が噛み合わさっている。でも、歯が二枚であろうと三枚であろうと、触れたら終わりなのは同じだ。
どんどん引き寄せる力が強くなり、目の前に巨大な口が迫って来た。
「ちょっと、あなた! 神さまのふりをするのはやめなさい!」
わたしはあらん限りの声を振り絞って、巨大な口に向かって叫んだ。だけど口の動きは変わらない。わたしの声など聞こえていないかのように、ガチャンガチャンと機械的に歯を動かしている。
わたしは叫びながら、歯が開いた口の中へ吸い込まれた。あとは前とまったく同じ。わたしは身も心もぼろぼろにされて、噛み終えたガムのように吐き出された。
無力感と絶望の中、わたしは怒りと悲しみの流れに運ばれるままだった。
枯れ草の原っぱ
たどり着いたのは、枯れ草だらけの荒れ地だった。空は土のような色をしていて、辺りは薄暗い。枯れ草以外に目につく物はなく、荒涼とした感じが薄ら寒い。
赤みの残っている風船は、枯れ草に元気を与えていた。でも、そんなことをしたって枯れ草は枯れ草のままだ。
「ここはどんな所なの?」
敗北感に耐えながら、近くの風船たちに尋ねると、みんなが口々に説明してくれた。
――ココデ食ベ物ガ、生マレルノ。
――デモ、ズット食べ物、生マレナイノ。
「あなたたちも食べ物が必要なの?」
――ウン。
風船たちは虹の森の実を食べても、完全には赤くならない。それは食べ物が足らないからに違いない。クラゲたちだって、飢えたまま必死にイガグリと戦っている。みんな、本当はぼろぼろなのに世界を守ろうとがんばっている。憎むべきはあの偽の神だ。
風船やその仲間たちが逆らわないのをいいことに、あんな乱暴で呪わしいことを続けるなんて絶対に許せない。
疲労は限界に来ていて、起きているのもつらいけど、世界を救わねばならないという気持ちが、わたしを奮い立たせている。
だけど、あんな怪物とどう戦えばいいのか。戦う以外にあの怪物を止めることができるなら、それが一番いいんだけど、相手のことが何もわからない今、わたしにはいい方法が全然思いつかない。まずは情報を集めなければ。
わたしは近くの風船に聞いた。
「ねぇ、さっき、大きな口に呑み込まれたでしょ? あれが偽の神さまなのよね?」
――ニセッテ?
「そうか。偽はわからないよね。さっきの大きな口が、あなたたちが言う神さまなの?」
――神サマジャナイヨ。
意外な返事に、わたしは驚いた。
「違うの? だって、みんなにひどいこと言うの、あの口でしょ?」
――神サマノ言葉ヲ、伝エテルダケ。神サマジャナイノ。
「それじゃあ、神主さんみたいじゃないの」
――カンヌシ?
「いいの。気にしないで。だけど、あの口は神さまに忠実だってことよね?」
――チュウジツ?
疲れがどっと襲いかかって来る。だけど、相手は子供と同じだ。わたしはゆっくり息をしてから言い直した。
「あの大きな口は、神さまの言葉がみんなを苦しめるのがわかってて、そのままあなたたちに伝えているのね?」
――ソレガ、役目ダカラ。
「あなたたち、腹が立たないの?」
――ハラガタタナイ?
そうか、風船にはお腹がない。て言うか、全部がお腹みたいだけど、やっぱりわからないか。
「あなたたち、あんなひどいことされても嫌じゃないの?」
――イヤ?
「嫌もわかんないか。じゃあ、何て言えばいいかな……。あなたたち、あんなひどいことされても何とも思わないの?」
――悲シイ。
「それだけ?」
――ウン。
わたしは切なくなった。風船たちは神にひどい目に遭わされても、悲しいとしか思わない。文句を言うこともなければ、あの大きな口の生き物を責めることもしない。それぞれはただ自分の役目を果たしているだけだと理解しているし、自分もまた危険を顧みずに役目を果たそうとする。どうして? 神さまが大好きだから。
わたしは泣きそうになりながら風船たちに言った。
「わたしね、あの大きな口に間違ったことを伝えないでって言いたいんだけど、どうすればいい? また、あそこへ行ける?」
――行ケルヨ。
「よかった。じゃあ、どうすればあの大きな口と話ができるかな? あそこへ行っても、すぐに放り出されちゃうから、話ができないでしょ?」
風船たちはすぐには答えてくれなかった。沈黙が続いたあと、誰かが言った。
――チョット、ムズカシイケド……。
「できるのね? どうすればいいの? 教えて!」
どの風船が喋ったのかわからず、わたしは風船たちを見回しながら言った。
――ピューッテ出タ、スグノ所ニネ、入ル所ガアルノ。
「そこに入れば、あの大きな口と話ができるのね?」
――ウン。
やっと方法が見つかった。わたしは世界の崩壊を救ったような気になった。
「そこには、どうやれば入れるの?」
また風船たちは黙ってしまった。今度は誰も答えてくれない。
「ねぇ、どうしたの? そこへは、どうやったら入れるの? 教えてよ」
――ワカンナイノ。
「だって、あなたたち、そこへ行ったことがあるんでしょ?」
――アルケド……。
そうだった。風船たちは自分の意志で進行方向を決めているわけではない。流れに乗っているだけだ。右へ行くか左へ行くかは流れ次第だ。あの口を出たばかりの所にある入り口に、入れるかどうかはまったくの運次第なのだろう。
わたしはがっかりした。だけど、諦めてしまってはおしまいだ。できることは何でもやってみるしかない。
突然、足下が動いた。また地震かと思ったけど、虹の森で起こった揺れとは違う。轟音は聞こえないし、ぐらぐらっという感じでもない。ゆっくり波打つような揺れ具合だ。実際、枯れ草だらけの地面は、上がったり下がったりしていた。
しばらくして揺れが収まると、風船たちがわたしを呼んだ。
――神サマ、ホラ!
――コッチ、コッチ!
声は聞こえるけど、どの風船が呼んでいるのかわからない。きょろきょろしながら歩いて行くと、ソッチジャナイヨ――と言う声。何度も方向を修正しながら進むと、前方に明るい色が見えた。わたしは歩調を早め、小走りになった。
色がある場所へ着くと、そこは一面の花畑になっていた。だけど、そこにある花は公園や花壇なんかで見かけるようなものではなかった。
丈は三十センチぐらいだろうか。多肉植物のように丸く膨らんだ、緑色の細長い葉のような物が、にょきにょきと地面から生えている。茎なのかもしれないけど、よく見る植物の茎と比べると、はるかに太くて瑞々しい。この葉っぱだか茎だかわからない丸い物の先っぽには、色とりどりの花が咲いていた。
花と言っても不思議な感じだ。蓮の花の形に似ているけれど、見ているうちに輪郭がぼやけて、きれいな色の光の塊になる。
下の葉っぱのようなものは、ゆらゆらと左右に揺れている。何度か揺れると、光の塊になった花はふっと宙に舞い上がる。そよ風に吹かれたタンポポの綿毛のような感じだ。
光の花が離れたあとも、葉っぱのような物はゆらゆら揺れ続ける。すると、その先に再び同じような花が咲く。
辺りにはいろんな色の花の光が、ふわりふわりと漂っている。その輝きは緩やかなリズムで、強くなったり弱くなったりしている。何色ものホタルが乱舞しているみたいで、とても幻想的だ。その数はどんどん増え続け、ゆっくりと同じ方へ流れて行く。
しばらくすると、地面に生えた葉っぱたちは、花を咲かせるのをやめた。と思ったら、次第にしぼんで茶色く変色し、ついには初めに見たのと同じ枯れ草になってしまった。
だけど宙に浮いた光の花たちは、ふわふわと浮かび続けて少しずつ動いていた。
わたしは光の花たちの後について移動した。もちろん、風船たちも一緒だ。
「ねぇ、もしかして、これがみんなの食べ物なの?」
近くにいる風船に尋ねると、ソウダヨ――と返事が返って来た。
わたしは浮かんでいる光に手を伸ばし、その一つを手に取ってみようとした。だけど、光は手の中を通り抜けてしまい、触っているのに触っている感覚がない。
わたしは諦めて観察するだけにした。すると、同じように見える光でも、大きさに違いがあるのがわかった。
光が強く輝いたときに、一番大きく広がって見えるのは紫色の光だ。
逆に一番小さく見えるのは赤い光。黄色や緑やピンクや青い光なんかはその間だけど、どれが大きいか小さいかという判別はつかない。その中で、赤い光だけが風船に触れると見えなくなった。
結局、光の花が咲いたのは、枯れ草の原っぱの限られた場所だけだった。それもわずかな時間だけで、花が咲いた辺りはすぐに元の枯れ草に戻ってしまった。
きっと本来は見渡す限りの光の花が咲くのに違いない。それはとても素晴らしい光景だろう。でも今の原っぱは、枯れ草だけの忘れ去られた寂しい場所のようだ。
あの虹色の森がイガグリに壊されていくように、ここもこのまま花が咲くこともなく、原っぱ全体が朽ちていくのに違いない。それはこの世界全体が滅びていくということだ。
広大な原っぱを出たあと、わたしたちは青白い空間を進んだ。歩くのも疲れるので、わたしは浮かびながら移動した。それでも長い間同じ状態でいると、ひどい気怠さと息苦しさばかりに気持ちが向いて、偽の神と戦う意思が薄れてしまう。おまけに、あの巨大な口が流す絶望的な感情が、わたしにすべてを諦めさせようとする。
それでも風船たちが声をかけて、わたしを励ましてくれるので、わたしは何くそと自分を奮い立たせた。そうして進んでいると、やがて前方に巨大な山が見えて来た。それは岩肌が剥き出しになった真っ赤な禿げ山だ。樹木らしきものは生えていない。
わたしは富士山をテレビでしか見たことがない。だけど、おそらく富士山よりも遥かに大きいと思える、見上げるような山だった。
わたしたちの先の方を飛んでいる光の花たちは、風船たちと一緒にその赤い山へ向かっている。あの山を登るのかと、へとへとのわたしは再び気持ちが萎えそうになった。
ところが空いっぱいに浮かんだ風船たちは、それぞれの高さのまま山に吸い込まれるように消えて行く。下の方にいる風船たちも、上に上がることなく山の中に消えるようだ。
山に向かう風船たちは、みんな青くしぼんでいるのかと思ったら、側面から山に近づく風船たちは赤いようだ。枯れ草の原っぱは通らずに、別の道でここへ来たのだろうか。でも、赤い風船と青い風船は混じることなく、それぞれが別の所から山に吸い込まれているみたい。
この吸い込まれる様子が遠くからだとよくわからなかったけど、近づいてみると岩山のあちこちに、中へ入る入り口のようなものがあった。
岩山の表面は、全体に亀の甲羅みたいな六角形の模様がある。そのそれぞれの六角形の中心に穴が開いている。無数にあるこれらの穴の中に、風船たちは次々に入って行った。
枯れ草の原っぱから移動して来た光の花たちも、風船たちと一緒にこれらの穴の中へ入って行く。もしあの原っぱ全部で光の花が咲いたなら、きっとこの山全体が七色の光に包まれたに違いない。だけど今は光の花が少ないために、七色の光を迎えられる穴は全体のごく一部だけだ。
わたしは光の花を追いかけて穴の一つに侵入した。中は薄暗いトンネルになっているけど、全体的に赤っぽく見える。交番の上についている、あの赤い電灯でぼんやり照らされているみたいだ。
――ヤット来タ。
うれしそうな声がした。同時に、大きな舌のような物が、右側からべろりとわたしの身体を舐めた。驚いて右を見ても、誰もいないし何もない。
――ヤット来タ。
また声が聞こえて、今度は左側から大きな舌が、わたしを舐めた。
「何よ、何なの?」
振り返っても、やっぱり誰もいないし何もない。
――ヤット来タ。
声と同時に、右側からまた何かが舐めた。そっちを見ると、今度は左。
パニックになったわたしは、両腕で自分の身体を抱くようにして守った。だけど、そんなことをしたって舐める舌は止まらない。わたしは大きな何かに舐められ続けた。でも目に見えるのは赤黒い通路の壁だけだ。
わたしは気持ちを落ち着かせると、絶対に相手の正体を見極めてやろうと思った。
身体の右側を舐められたとき、わたしは右を見ないで左側をじっと見た。すると驚いたことに、そちらの壁が舌のように伸びて来て、わたしの身体をべろりと舐めた。すぐに右を見ると、そっちの壁も舌になってわたしを舐めた。
前方を見ると、風船たちも舐められていた。だけど、慣れているのか平気なようだ。もしかして風船を舐めることで、元気を分けてもらっているのだろうか? でも、ここにいる風船たちは、さっきの枯れ草たちに元気を分けていたので、ほとんどの者たちが青くしぼんでいる。いくら舐めたところで、分けてもらえる元気は残っていないだろう。
「ねぇ、あなたたち、何でわたしたちのことを舐めるの?」
わたしが尋ねると、壁はわたしを舐めながら喋った。
――食ベ物……食ベテルダケ。
「わたし、食べ物じゃないよ!」
わたしは文句を言った。でも、すぐに光の花が食べ物だということを思い出した。
見ていると、左右から出て来る大きな舌は、確かに光の花を舐め取っていた。光の花は舌に張りついたまま壁の中へ取り込まれている。でも、光の花は数が減っている様子がない。食べられて見えなくなったと思っても、いつの間にかそこで光っている。
おかしいなと思って、わたしは観察を続けた。すると、光の花を舐め取った舌が引っ込んだあと、そこの壁の中から新たな光の花が、染み出るように外へ出て来た。
これでは食べたことにはならないだろうにと思ったけど、染み出て来た光の花は、原っぱで見ていた光の花とは、少しだけ違うような気がした。
一番大きかった紫の光は、少し小さくなったように見える。その色具合も、元の紫色と比べると、青みがかっていたり、赤みがかっていたりしているようだ。他の色の光も、前と同じように見えるけど、よく見ると、少し違っているみたいだった。
「ねぇ、あなたたち、食べた物を元に戻してるの?」
わたしは壁に尋ねた。壁はまたわたしを舐めながら答えた。
――全部ハ……食ベナイ。
「いらないのは戻すわけ?」
――ミンナガ……食ベヤスク……シテル。
「みんな? 他の人たちは、初めのままじゃ食べられないの?」
――一番小サイノ……食ベラレル……。他ノ……食ベラレナイ。
つまり、ここは加工工場ってことか。あるいは調理場なのかもしれない。そして、この壁の舌たちは、この世界のシェフってわけだ。わたしは少しだけ楽しい気分になった。
だけど、途中から壁が舐めなくなった。もう舐めないのかと尋ねると、食べ物がなくなったと言われた。もう加工すべき光の花がなくなったので、何もできなくなったらしい。
これで食べ物はみんなに足りるのかと聞いてみると、全然足らないと言う答が返って来た。それは、風船たちの仲間が飢え死にするということだ。
トンネルを抜け出ると、そこは薄い青色の空間だった。流れに押されるのではなく、前に吸い寄せられる感じだ。空間が広くなるにつれて、青い風船たちの数がどんどん増えて行く。まだこの世界のことがよくわかっていないけど、前へ引き寄せられるときに、あの巨大な口が現れたように思う。
どんどん宙を飛んで行くと、思ったとおり先の方に開いたり閉じたりしている、巨大な口が見えて来た。動いている歯は三枚ある。でも、もう一つの口は歯が二枚だった。どちらも呪いの言葉を発していたから、二匹とも偽の神の代弁者ということか。一匹でも戦うのは大変だろうに、双子の怪物とは困ったものだ。
とにかく吸い込まれて吐き出されたときに、入り口を見つけなければならない。出口のすぐ近くにあると言うから、よく注意していよう。
口の真ん中を通過したのでは、入り口を見つけたとしても、絶対そこへは行き着けないだろう。近づくこともできずに、通り過ぎてしまうに違いない。端っこにいた方が見つけやすいだろうし、入りやすいはずだ。
わたしは宙を泳ぎながら、風船たちの群れの端の方へ向かって、少しずつ移動した。でも空間はかなり広くて、端まで移動するのは容易ではない。
そうこうしているうちに、口がぐんぐん迫って来た。口の中を通り過ぎたあとのことばかり考えていたけれど、あの歯に噛み切られてはおしまいだ。
わたしは覚悟を決めると、自分でも宙を泳ぎながら口の中へ飛び込んだ。
これまでと同じように、すごい圧力で押しつぶされそうになりながら、心は絶望で張り裂けそうになった。この苦痛に耐えるのに必死で、入り口を探すことなど頭から抜け落ちてしまいそうだ。
外へ吐き出されたとき、わたしはぐるぐる回転しながら入り口を懸命に探した。でも、これはジェットコースターに振り回されながら、周辺の様子を確かめているのと同じだ。入り口が見えたかもしれないけれど、わたしには何もわからなかった。結局、わたしは入り口を見つけられないまま、虹の森へ押し流された。
不思議なことに、森には黒い木は一本もなく、すべての木が七色に輝いている。風船たちは夢中で白い実を食べていたけど、わたしはイガグリが現れないか心配で、警戒を続けた。だけど、一向にイガグリは現れない。ここはとても平和なようだ。
突然胸が苦しくなって、わたしは咳き込んだ。その時、森は轟音とともに大きく揺れ動き、わたしは近くの木にしがみついた。また地面が裂けるかと思ったけど、今度はそこまでにはならなかったようだ。それにしても、何で咳をすると地震が起きるのだろう?
奇妙に思いながら、わたしは近くにいた風船に、ここに敵はいないのかと尋ねてみた。
風船はウンと言った。どうやら虹の森は一カ所だけではないらしい。クラゲとイガグリの戦いは、こことは別の森で起こっているということだ。まだ無事な森が残っていたのはよかったと思う。だけど、ここだってどうなるかはわからない。
安堵と心配が入り交じる中、目指す入り口を見つけられなかったことを、わたしは悔やんだ。
入り口がどこにあったのかと、風船に聞いてみると、次に吸い込まれて出た所にあると言う返事が返って来た。要するに、さっきの所には入り口はなかったらしい。
わたしはがっくりしたけど、今度こそはと気合いを入れ直した。
風船たちの故郷
二枚歯の口に吸い込まれ、身も心もグチャグチャにされながら、わたしは吐き出される一瞬を待った。さいなむ苦痛の相手をせずに、必死に入り口のことだけ考え続けた。
ブシュッと吐き出されたとき、洞穴のようなものが一瞬目に入った。だけど身体は回転しているし、飛び出す勢いを制御できない。わたしはそのまま押し流されて行った。
あそこが風船たちが言う入り口だとしても、これではとてもたどり着けそうにない。あそこへ入るのは至難の業で、まさに運次第だ。自分の力だけでは無理だろう。
落胆しながら運ばれて来たのは、あの大蛇たちの森だった。
風船たちと一緒に、光の花が大蛇の瞳の洞窟へ吸い込まれている。中にいる炎を出す大蛇たちも、これでいくらかは安堵するだろう。
わたしは少しほっとしたけど、倦怠感が強い。最初の頃よりも、かなり具合が悪くなっている。疲労は極限で、何をするのもつらく億劫に感じてしまう。もう一度大蛇の瞳に入り、上空に見える向こう側へ行く自信はなかった。
ふと見ると、大蛇が咬みついている岩の陰に、大蛇の瞳とは別の洞窟があった。風船たちの多くは大蛇の方へ流れて行くけど、一部はこの洞窟へ入って行く。わたしはそちらへついて行くことにした。
岩の中に入ると、そこは広い空洞になっていた。鍾乳洞みたいな岩の柱が、何本も天井を支えるように立っている。鍾乳洞と違うのは、同じような柱が左右の壁を貫いていることだ。真横の柱もあれば、斜めの物もある。見ようによれば、巨大なクモの巣のようだ。
柱を避けながら奥の方へ進んで行くと、上の方でピンク色の風船が集団で大きな球になっている。ピンク色の風船は初めてだし、風船たちがぴったり集まって塊になっているのも初めて見た。
辺りを見回すと、地面近くにも同じようなピンク色の風船集団があった。そこへ行ってみると、このピンクの風船は赤や青の風船とは全然違っていた。胴体は透けていて、中に大きな目玉が一つある。この目玉は上下左右に向きを変えて、辺りの様子を眺めていた。
「あなたたち、誰?」
わたしが尋ねると、風船たちの目が一斉にわたしの方を向いた。
――誰? ワカンナイ。
同じ答がいくつも重なって聞こえた。その声は赤や青の風船たちのような小さな女の子の声だ。でも幼稚園児のようなとても幼い感じがする。
眺めていると、だんだん色がピンクから赤に変わって行く風船がいた。その風船は目玉が、胴体の奥の方へ移動していた。
やがてその目玉が見えなくなると、赤くなった風船はプチュンと集団から外れた。その姿はこれまで見て来た赤い風船たちとそっくりで区別がつかなかった。どうやらピンクの風船たちは、赤い風船の子供のようだ。
次から次に赤い風船が集団から外れて行くので、わたしは赤い風船が抜け出たあとの、空間をのぞいてみた。でもそこには何も見当たらないし、周囲のピンクの風船たちですぐに埋められる。
何度か観察していると、赤い風船が抜けた直後の一瞬に、残された目玉が確認できた。でも、それはすぐに奥の方へ吸い込まれるように消えてしまった。
奥で何やらゼリーのような物が動いているように思えた。でも小さな隙間だから、そこに何があるのかよくわからない。それに隙間は隣の風船たちに埋められしまい、それ以上は奥の方を確かめることができなかった。
「ここはあなたたちの家なの?」
近くにいた赤い風船に、わたしは尋ねた。だけど、家というものがわからないらしい。そうですと答える代わりに、ここで自分たちは生まれたと風船は言った。
どうして目玉がなくなるのかと聞いてみると、今度は目玉の意味がわからない。ピンクの風船の中にある、丸くて動く物だと説明すると、やっとわかってもらえた。
風船たちはそれを失う代わりに、より多くの元気を運ぶことができるのだそうだ。
それにしても、あれは目玉ではないのだろうか? 風船たちにとって、あの目玉みたいな物が何なのか尋ねてみると、昔の思い出と考える力だと風船は答えた。
「昔の思い出と考える力? じゃあ、あなたたちは昔のことを何も覚えてないわけ?」
――覚エテナイヨ。
「じゃあ、考える力は? あなたたちだって考えるんでしょ?」
――ムズカシイコトハ、ワカンナイ。
「だったら、あの子たちは昔のことを覚えてて、むずかしいことがわかるの?」
――タブンネ。デモ、ワカンナイ。
ピンクの風船集団を眺めながら、わたしは集団の後ろへ回った。するとピンクの風船より、何倍も大きな薄いピンク色の風船がいた。その風船にも大きな目玉があって、ぎょろぎょろと辺りを見回している。その目玉がわたしの方を向いて動きを止めた。わたしのことを見ているのかと思ったら、その目玉の瞳の部分が、ぷっくらと膨れ出した。
その目玉の瞳にできた瘤は、どんどん大きくなった。やがて胴体の外へ飛び出すほど膨らむと、その瘤は胴体の一部ごとプチンと風船の本体からちぎれて離れた。できたのは、あのピンク色の風船だ。元の大きな風船の方は、何事もなかったかのように、また大きな目玉をぎょろぎょろさせている。
新しく生まれたピンクの風船は、ふわふわと漂い始めた。その先には、新たなピンクの風船集団ができつつあった。その集団の中心にいたのは、あのビーチボールだ。クラゲのようなつぶれた姿はしてなくて、少ししぼみ気味の丸い形をしている。新しいピンクの風船は、ビーチボールに近づくと、そのままぴたりとくっついた。
既にくっついていたピンクの風船の一つが、目玉を後ろへ吐き出すように残して、ビーチボールから離れた。残された目玉はビーチボールに引っついたままだったけど、すぐにビーチボールの中に取り込まれた。そのあと、風船の目玉はイガグリと同じように、ビーチボールの中にある、たくさんの口に食べられてしまった。
わたしは元の大きな薄ピンクの風船の所に戻ると、声をかけてみた。
「こんにちは」
――コンニチハッテ、何デスカ?
年配の女性の声だ。
「挨拶の言葉よ」
――アイサツ?
「わかんなければ、いいの。ちょっと教えて欲しいんだけど、あなたの中にある、その目玉ね。それって本当は何なの?」
――メダマ?
そうだった。目玉じゃわからなかったんだ。わたしは正しい言葉に言い直した。
「あなたの中にある丸くて動く物よ。昔の思い出と考える力って聞いたんだけど」
薄ピンクの風船は、目玉らしき物をくるりと回転させた。
――コレデスカ?
「そう、それよ。それって何なの?」
――コレデ、方向ヲ理解シマス。
「方向って? どっちへ行くかってこと?」
――行イノ方向デス。
「行いの方向? 何それ?」
風船は上手く説明できないみたいで、目玉みたいな物をくるくる回した。
「自分がすべきことを、どんな風にするっかってこと?」
――ソウデス。スルカ、シナイカヲ、決メタリモシマス。
薄ピンクの風船が言いたいことはわかった。でも、この目玉みたいな物で、どうやってそんなことを理解するのかはわからない。
「あなたが産んだ子供たちは、行いの方向を理解できなくてもいいの?」
――コドモ? ワタシノ、分身ノコトデスカ?
「分身か。なるほどね。そう、その分身たちよ」
――何ヲ行ウカハ、決マッテイマス。考エル必要ハ、アリマセン。
「そういうことか。じゃあさ、昔の思い出っていうのは、どんなものなの?」
――ワカリマセン。
「え? だって、あなたの分身が言ったんだよ? それなのに、わからないの?」
――古イ記憶ガアルコトハ、ワカリマス。ドンナ記憶ナノカハ、ワカリマセン。
「じゃあ、記憶喪失ってこと?」
――記憶ソウシツ?
「昔のことを思い出せないってことよ」
――ムカシノコトハ、ワカリマセン。
「いいよ。ありがとう」
――神サマト、オ話シデキテ、光栄デス。
もう神さまと呼ばれることに慣れてしまい、わたしは気恥ずかしさを感じなくなっていた。
この風船をポヨンポヨンとたたくと、風船から困惑が混じった興奮が伝わって来た。神から嫌われているという思いと、神に認められたという喜びが入り交じった感じだ。
わたしにしても、今にも倒れそうな疲れが、風船たちと喋っていると、少し癒やされて元気になれるようだ。
少し行くと、今度はビーチボールの大きいのに出くわした。
このビーチボールは中心部分に、線状の窪みが縦に走っている。柔らかいおもちの真ん中を、紐でぎゅっと縛ったみたいな感じだ。その見えない紐が、どんどんきつく締まって行くように、ビーチボールの表面にできた窪みは、胴体の中心に向かって深く食い込んで行く。
胴体の真ん中には、例の目玉のような物がある。それも窪みの食い込みで、今にも左右にちぎれそうになった。と思ったら、ほんとにちぎれてしまった。当然、胴体の方も左右に分かれ、二つのビーチボールになった。
「あなたたち、こうやって増えてたのね?」
わたしが声をかけると、二つのビーチボールは同時に、ハイ――と言った。虹の森で仲間のビーチボールに助けてもらった話をし、感謝してることを伝えると、二つともうれしそうに、アリガトウゴザイマス――と喜んだ。
ビーチボールたちと別れてさらに行くと、今度はビーチボールの何倍もある、巨大なナメクジがいた。胴体は黄色がかった透明で、その中に大きな目玉がいくつも並んでいる。
わたしはナメクジは苦手だ。うえぇと思いながら眺めていると、突き出た角の先っぽがぶっくらと膨らんだ。それはあの黄色い手毬だった。
手毬は角からプチンとちぎれると、辺りをふわふわ漂い始めた。
手毬がちぎれたナメクジの角は、しゅるしゅると頭の中に縮んで戻った。すると、また頭の別の部分から、同じように二本の角がにゅるにゅると伸びた。その角の先は、さっきみたいに手毬となった。
どうやらナメクジは手毬の親らしい。わたしは親近感が湧いて来た。
「ねぇ、あなたはどうして体の中に、丸い物がいくつもあるの?」
――大キクナルノニ、一ツデハ足ラナインデス。
ナメクジは丁寧な言葉で答えてくれた。でも、やっぱり年配の女性みたいな声だ。
「何でそんなに、大きくならないといけないの?」
――小サイト、ダメダカラデス。
「どうして、小さいとだめなの?」
――大キクナラナイト、イケナイカラデス。
これでは堂々巡りになってしまう。
「あなたは昔のことがわかるの?」
――ムカシ?
「やっぱし、わかんないか。いいよ、ありがとう」
ナメクジと別れ、わたしは先へ進んだ。途中、ピンクの風船集団や、その風船たちを産む薄ピンクの風船、それに大きなビーチボールや、巨大ナメクジを何度も見かけた。だけど、そういう者たちとはまったく違う、不思議な生き物にわたしは出会った。
その不思議な生き物は薄ピンクの風船より一回り大きくて、色は全然ついていない。まったくの無色透明で、空気や水みたいだ。
それなのに何で気がついたかと言うと、それは大きな目玉のような物を一つ持っていたからだ。つまり、大きな目玉が一つだけ、ぽつんと宙に浮いていたわけだ。
宙に浮いた目玉は、真下を向いたまま動かなかった。何だろうと思って手を触れようとしたら、手前にガラスのような硬く透明の物があった。それで、この生き物が透明なのがわかったんだけど、ガラスみたいな冷たさはなかった。
わたしは両手で目玉の周辺を探りながら、この見えない生き物の形を確かめた。細かい所はわからないけど、触った感じでは上下につぶれた平べったい球のようだった。
眠っているのか死んでいるのか。声をかけても返事がない。下を向いた目玉も全然動かない。
だけど赤い風船たちは、この生き物にも張りついて元気を渡していた。ここにいる何かは生きているのかと尋ねると、眠っているだけと風船は言った。
そのとき、下を向いていた目玉のような物が、ぐるんと向きを変えてこっちを見た。ぎょっとしながら声をかけたけど返事はない。
透明だった生き物は少しだけ色を変え、透明ながらもその輪郭が見えるようになった。その姿はあのビーチボールそっくりで、大きなビーチボールと同じように、真ん中から分裂して二つになった。
この生き物の正体は、ビーチボールだったのかと思ったら、またもや変化が起きた。分裂した一方は、ビーチボールのままだったけど、もう一方は、薄いピンク色になった。
薄ピンク色の生き物は、中の目玉のような物がこちらへ突き出して来た。あれよあれよと言う間に、飛び出した目玉と胴体の一部は、ちぎれてあの薄ピンク色の風船になった。
後ろに残った元の胴体の方は、今度は黄色に変化した。さらに、胴体の中の目玉のような物に、たくさんの角が生えた。角はどんどん伸びて胴体の外へ突き出した。まるでウニのような姿だ。
巨大なウニのトゲの先は順番に膨らんで行き、かなり大きくなったところで、プチンとトゲの先からちぎれた。そうやって生まれた黄色い生き物は、中に目玉を持ったゼリーの塊みたいだ。そんなのが次から次にできて行き、水が入ったビニール袋みたいに、ポワポワしながら互いに寄り添い始めた。
そのうち、この生き物たちは一つに融合して、あの黄色いナメクジになった。
一方でウニの姿になっていた生き物は、伸ばしたトゲを体に戻し、目玉のような物から伸びた角も縮んでなくなった。体の色も次第に薄れ、元の見えない姿に戻ろうとしているようだった。中の目玉のような物も、ゆっくりと地面の方へ向いて行く。
「ちょっと待って! 寝る前に話を聞かせて!」
慌てて呼びかけると、ほとんど下を向いていた目玉のような物が、少しだけわたしの方を向いた。胴体はほとんど見えなくなっている。
「あなたが、みんなのお母さんなのね?」
――オカアサン? 何ダネ、ソレハ?
老婆のような、しゃがれ声が聞こえた。
「みんな、あなたの分身なんでしょ?」
――ココニイル者タチハネ。
「他の所にいる人たちは、あなたの分身じゃないの?」
――ソレゾレニハ、ソレゾレノ元ガイルンダヨ。
「そうなの? 他の所にも、あなたみたいな存在がいるのね?」
――ソウダヨ。
「あなたたちは、誰から生まれたの?」
――ミンナ、同ジ一ツノ存在カラ、生マレタンダヨ。
「じゃあ、昔はたった一つの、存在しかいなかったの?」
――ソウダヨ。昔ハ、タダ一ツノ存在ダケダッタ。
「それは、あなたの持つ古い記憶なの?」
――遠イ記憶ダヨ。
「その一番初めの存在って、今もどこかにいるの?」
――イルヨ。イツデモ、ドコニデモネ。
「よくわかんないよ。もうちょっと、わかるように言ってくれない?」
――ミンナ、一ツノ存在ノ、分身ナンダヨ。コノ世界ノネ。
この生き物の言葉はむずかしい。でも、大切なことを告げているのは間違いない。
「それって、世界そのものが一番初めにあった、ただ一つの存在ってこと?」
――ソノトオリダヨ。
「よくわかんないけど、みんなが生まれる前は、世界は空っぽだったってこと?」
――空ッポジャア、ナイヨ。世界ハネ、愛デ満タサレテイタンダ。三ツノ愛デネ。
「三つの愛?」
――一ツノ愛ダケデハ、世界ハ産マレナイ。存在スルニハ、二ツノ愛ガ必要ナンダヨ。
「二つの愛が、世界を創ったんだね」
――ダケドネ、二ツノ愛ダケデハ、生マレルコトハデキテモ、育チハシナインダヨ。
「育たないとどうなるの?」
――消エユクノミダネ。ソウナラナイタメニハネ、モウ一ツノ、愛ガ必要ナンダヨ。
「もう一つの愛?」
――ソウダヨ。神ノ愛サ。
「え? わたしの?」
思わずそう言って、わたしは少し恥ずかしくなった。でも、この生き物は気にする様子もなく話を続けた。
――カツテ、コノ世界ハ、アナタノ愛ニ満チテイタ。ダケド今ハ、憎シミシカナイ。
「ちょっと待って。わたし、この世界を憎んだりしてないよ?」
――今、世界ハ滅ビツツアル。ソレデモ世界ハ、アナタヲ……慕ッテイルヨ……。
目玉のような物が下を向き始めた。もう胴体の方は全然見えない。
「待って! 眠っちゃだめよ! まだ話は終わってないってば!」
伸ばした手が、硬いガラスのような胴体に遮られた。
目玉のような物は完全に下を向き、この不思議な生き物は、もう何度呼びかけても、眠りから覚めてくれなかった。
水晶の洞窟
また虹の森へやって来た。ここが前に訪れたのと同じ場所かはわからない。でも、目の前に広がる森は壊滅的だ。
真っ黒だったであろう木々は、どれも根元でポッキリ折れて砕け散っていた。その切り株のように残った根元から、続々とイガグリが出て来ている。
無数のクラゲたちが、壊れた森全体を覆うように集まっている。イガグリを森の外へ出すまいとしているようだ。
青くしぼんだ風船たちは、元気を手に入れることができないまま、クラゲたちの上方を空しく流れて行くばかりだ。下を流れてしまった者たちは、イガグリたちに殺される運命にあった。
白い洞窟の中では、たくさんのビーチボールが分裂して増殖していた。だけど、あそこで増える数よりも、ここで壊れて行く数の方が遥かに多いように思う。戦いはクラゲたちが劣勢で、このままだといずれイガグリはこの森を出て世界中へ広がるだろう。そうなれば間違いなく、この世界は破滅するに違いない。
一方で、わたしの息苦しさは強くなっていた。ひどい咳に襲われてうずくまるたびに、世界は大地震に見舞われた。まるでわたしの咳と地震は連動しているようだ。
それは、わたしがこの世界の神であることを示されているようで、神であるわたしの弱体化が、世界の崩壊とつながっているみたいに思える。
体のだるさは半端じゃなく、頭の中も何かを思考できる状態ではない。わたし自身が崩壊しそうな感じだ。
どうしてこれほど具合が悪いのか。その理由はわからない。でも、自分がこれだけ弱ったからこそ、偽の神がこの世界を手に入れたのだろう。
偽の神は世界を滅ぼそうとしているけれど、そうさせた責任がわたしにはある。
わたしを護ろうとして死んでいった者たちのことを思うと、どんなに具合が悪くても弱音を吐いたりはできない。これ以上、わたしを慕ってくれている者たちの命が奪われるのを、許すわけにはいかないのだ。
この世界を取り戻してみせる。その想いだけが、今のわたしを突き動かしていた。
咳と地震が落ち着くのを待って、わたしは急いで虹の森を離れた。
わたしなんかにこの世界を救えるなんて、信じているわけじゃない。そもそもわたしには自分がこの世界の神だという認識がない。それでもこれは自分の役目なのだと、わたしは強く感じていた。これをするべきなのは、また、これができるのは自分を置いてはいないと、心の奥にいる自分がわたしを鼓舞している。
巨大な口の生き物に会うための入り口は、この森の次に現れる二枚歯の口の向こうにある。問題はどうやってその入り口へ入るかだ。
わたしはぼんやりしがちな意識の中で、どうすればいいだろうかと必死に考えた。
あの巨大な口の生き物が偽の神でないならば、他の生き物たちのように、わたしを慕ってくれるはずだ。そうであるなら、わたしの言葉を聞いてくれると思うけれど、あの状態では会話などする暇がない。わたしは心も体もぐちゃぐちゃにされ、あっと言う前にあの生き物の中を通り過ぎてしまう。
あの口に呑み込まれる前に、こちらの言葉を向こうに届かせるにはどうするか。そう考えたとき、この世界では声で意思を伝えているわけではない、ということをわたしは思い出した。
風船たちの言葉は声を介さず、直接わたしの頭の中に伝わって来る。わたしは相手に口で喋っているつもりだけど、実際は声は出ないで、頭の中の想いだけを相手に伝えているのに違いない。
声であれば近くへ行かないと聞こえないだろうが、テレパシーのような伝え方なら、離れていても伝わるはずだ。
そうだ、あの口に呑み込まれる前に、あの生き物に話しかけてみよう。だめかもしれないけど、やってみる価値はあるし他に方法はない。
前方の遠くに巨大な口が見えると、わたしは口に向かって大声で話しかけた。と言っても、やはり実際の声ではなく頭の中で叫んでいるようだ。
「ねぇ、わたしのことがわかる? わたし、あなたと話がしたいの。これからあなたの中に入るけど、そのままわたしを吐き出さないで、あなたの所へ行かせてちょうだい!」
声が届いていないのか、相手からの返事はない。ただ、戸惑っているような感じだけは伝わって来た。
わたしは巨大な口に引き寄せられながら、何度も同じことを叫び続けた。そうして目の前に二枚歯が迫ると、わたしはあっと言う間に口の中へ吸い込まれた。
中の様子はこれまでと変わらない。圧力と絶望で痛めつけられたあと、わたしは外へ吐き出された。やっぱり話は通じなかったのかと、わたしはぐるぐる回転しながら落胆していた。
でも、何だか周りの様子がこれまでとは違うみたい。今までは広い空間に放り出されていたけど、今回は狭い空間の中に押し込められたようだ。
これはもしやと考える間もなく、気がつくとわたしは巨大な赤い大蛇たちの上に降り立っていた。
大蛇の上に立ったのは初めてじゃないけど、わたしはびっくりして逃げようとした。だけど自分で跳び上がる前に、わたしは勢いよくうねった大蛇に大きく跳ね上げられた。
そのまま宙に浮かんで下を眺めてみると、大蛇たちは一団となって大きくリズミカルに上下に動いていた。その様子は大きな赤い絨毯が風にたなびいているようだ。
前に見た炎を出す大蛇は頭が二つあって、長い胴体に目のような物がたくさんあった。でも、この大蛇たちは頭は一つで胴は短く、胴体の目のような物は一つだけだ。
一匹がもう一匹の尻尾に咬みつき、咬まれた大蛇は別の大蛇の尻尾を咬んでいる。そうやってできた長い大蛇の列がびっしりと横に並ぶことで、大蛇を編み込んだ絨毯が作られている。
でもこの大蛇の絨毯は、部屋に敷く絨毯のように平らにはなっていない。一見平らに見えても、上から見下ろすと、全体がとても巨大な球体を形成しているのがわかる。その球体がリズミカルに拍動し、大蛇たちは順番に上下運動を繰り返していた。
大蛇の球体周囲には白い霧が広がっていて、霧の中に入ると球体が見えなくなる。
この霧は奇妙な感じで、あまり奥深く入ろうとすると、クッションのように押し戻されてしまう。だから、うんと離れた所から球体全体を眺めることはできなかった。
尻尾を咬まれた大蛇の列の先頭はどうなっているかと思い、わたしは一番先にいる大蛇を求めて移動した。
すると、大蛇の列の群れは二手に分かれて、霧の中へ消えていた。球体の端が二本の管になったわけだが、その先は霧の中なのでどうなっているのかはわからない。
球体の大蛇たちが拍動して動くと、管を構成している大蛇たちも、球体の大蛇たちに合わせて動く。球体で作られた拍動の波は、そのまま二本の管にも伝わっていた。
この二本の管のうち、片方の管の付け根辺りに洞窟が見える。そこから次々に赤い風船たちが出て来るので、そこがこの場所への入り口に違いない。よく覚えていないけど、わたしもその洞窟を通り抜けてここへ出て来たのだろう。
と言うことは、あの洞窟はこの管の内側に通じているわけだ。だとすれば、この球体があの巨大な生き物で、管は呑み込まれた者たちが放り出される所なのだろう。
三枚歯の口から出ると、必ず虹の森へ行き着くけど、二枚歯の口から出たあとは、どこへ向かうのかはわからない。それぞれ出たあとの行き先が違っているのは、通る管が違うからだと私は納得した。
わたしはこの球体が一つの生き物だと思っていたけど、実際は数え切れない大蛇の集団だった。
誰がボスなのかがわからないので、わたしは上空から大蛇たち全体に向かって声をかけた。
「わたしが呼びかけてたのは、あなたたちなのね? そうでしょ?」
――ソウデス。神サマ。
頭の中で泣いているような震えた声が聞こえた。男なのか女なのかはわからないけど、大人のような声だ。
声は一つだけでなく、大勢の声が同時に聞こえている。声の様子から、この大蛇たちはわたしを恐れているようだった。
「あなたたち、どうしてみんなを苦しめるようなことするの? あなたたちが広めてるのはね、わたしの言葉じゃないの。わたしの偽者の声なのよ」
――ニセモノ?
「わたしじゃない誰かの声を、あなたはわたしの声だと勘違いしてるってこと」
――ワタシ、ワカリマセン。
大蛇たちは全体で一匹のような受け答えだ。見た目はたくさんだけど、全体で一匹と考えた方がいいのだろうか? わたしは迷いながら大蛇たちに言った。
「わからないって、何が?」
――ワタシ、神サマノ言葉、ミンナニ、伝エテイルダケデス。
「わたしがこんなひどい言葉を、あなたに伝えるわけないでしょ?」
――ワタシ、神サマノ言葉、伝エルダケ。
「あなた、こんな言葉広めたら、みんながどうなるかわからないの?」
――ワタシ、神サマノ言葉、伝エルダケ。
「そうだとしても、この言葉はおかしいぞって思わないの?」
――ワタシ、神サマノ言葉、伝エルダケ。
「あなただって、わたしに嫌われてるって思ったら悲しいでしょ?」
――悲シイデス。ダケド、神サマノ言葉、仕方アリマセン。
「自分も悲しいのに、その言葉をみんなに伝えるってわけ?」
――神サマノ言葉、伝エルノガ、ワタシノ役目デス。
「自分が死ぬかもしれないのに?」
――神サマノ言葉、伝エルノガ、ワタシノ役目デス。
頭が固いと言うのか、考える頭がないのか、大蛇たちは同じ言葉ばかりを繰り返して、ちっとも埒が明かない。
「あなたが言う神の言葉って、どうやってあなたに伝えられるの?」
――囁カレルノデス。
「囁く? その神さまがあなたの所に来て囁くの?」
――神サマ、イツモ一緒デス。
「いつも一緒って、今もその神さまは、ここにいるの?」
――アナタ、神サマ。アナタ、ココニイマス。
「そうじゃなくって、あなたが言う神さまよ。みんなにひどいことを言う神さまのこと」
――神サマ、一緒デス。
「一緒じゃないの! わたしはみんなを苦しめるようなことなんか言わないよ」
大蛇たちは黙ってしまった。こちらの話が理解できないのだろうか。
わたしは話をやめて、球体の上方を移動した。
球体はかなり大きいので、全部を見るのは大変だ。ずいぶん移動した頃に、初めに見たのとは別の太い管が現れた。管はやはり二本ある。でも拍動はせず、球体の拍動に合わせて小さく振動していた。その管の先は、やっぱり霧に隠れて見えない。
この管があるのは、大蛇たちの尻尾の側だ。よく見ると、列の一番後ろにいる大蛇たちの尻尾が伸びて合わさり、この二本の管を作っているようだ。
こちらも片方の管の付け根に洞窟があり、大蛇たちに元気を渡して青くなった風船たちが、ゆっくりと入って行く。たぶんここが出口なのだろう。
二つの管の間を見ると、そこから白い紐のようなものが霧の中へ伸びていた。
これは何だろうと思って、わたしは紐に近づいてみた。すると、紐はいくつにも分岐して、赤い大蛇たちのそれぞれの尻尾に引っ付いていた。
その部分にさらに近づいてみると、突然声が聞こえた。
――コノ役立タズメ。オマエナンカ、死ヌノガ、オ似合イジャ!
わたしは驚いて辺りを見回した。だけど、声の主は見当たらない。それでも罵倒する声が、あちこちから聞こえて来る。
――貴様ノセイデ、ワタシハ、ドレホド、ツライ思イヲ、サセラレタコトカ。
――何ニモデキヌ、ロクデナシメ。貴様ナンゾ、オラヌ方ガマシジャ!
――嫌イジャ、嫌イジャ! ワタシハ、貴様ガ、大嫌イジャ!
――オ前ナンゾニ、何ガデキル? 貴様ニ、何ノ価値がアルンジャ?
――ドウシテ、サヨウニ、不細工ナノジャ! 何故、モット美シク生マレナンダ?
怒りでムカムカしながら、わたしは声の主を探した。そして、ついに見つけた。
いくつもに分かれた白い紐は、赤い大蛇たちの尻尾に絡みつきながら、それぞれが一匹の小さな白いヘビになっていた。その白いヘビたちは、赤い大蛇たちの尻尾に喰らいついたまま、赤い大蛇たちに口汚く罵り続けていた。
「あんたたちだったのね?」
わたしはすぐ近くにいる白いヘビをにらんだ。
この白いヘビは、炎を吐く大蛇たちの所にもいたあのヘビだ。
あのヘビたちと同様に、目の前にいるヘビたちも、わたしの言葉など聞こえていないみたいだ。録音テープが喋るように、ずっと罵声を繰り返している。
「ちょっと、あんたたち。好い加減にしなさいよね!」
わたしは白いヘビにつかみかかった。だけど白いヘビの頭をつかんだ途端、つかんだ両手を伝って強烈な怒りと悲しみが、衝撃波となってわたしの中にぶち込まれた。それはこの赤い大蛇の球体の中で、詰め込まれたものより強力だった。
わたしはショックで弾き飛ばされ、胸の中で感情が暴れるのを抑えることができなかった。心を制御できないわたしは、いつの間にか白いヘビと同じ言葉を叫び続けていた。
――神サマ、ヤッパリ、ミンナガ嫌イナノ?
わたしに張りついた赤い風船が、わたしに元気を与えながら悲しげに言った。
はっと我に返ったわたしは、両手で胸を押さえて叫んだ。
「わたしはこの世界が大好き! わたしはこの世界にいるみんなが大好きなの!」
わたしは叫び続けた。すると、わたしの中であれだけ暴れ回っていた、狂気の渦が弱まった。
そのあとも同じ言葉を繰り返し叫び続けると、心の中の狂気は次第に鎮まっていった。そうして、わたしはやっと落ち着きを取り戻すことができた。
赤い大蛇に罵り続ける白いヘビは、霧の中から出て来ている。このヘビの本体、あるいはこのヘビを使う黒幕が、この霧の向こうにいるに違いない。
わたしは白ヘビの尻尾を追って、霧の中へ入ろうとした。だけど霧に跳ね返されて、奥へ進むことができなかった。
わたしは白ヘビの言葉に苦しむ、赤い大蛇たちをねぎらった。それから、白ヘビがどこから来ているのかと、大蛇たちに尋ねた。
大蛇たちは、それがどこなのかは答えられなかった。だけど、わたしをそこへ送り届けることはできると言った。
わたしは絶対にあの声を止めてみせると、大蛇たちに約束した。それから、大蛇たちの言葉に従って、青い風船たちが入って行く洞窟へ向かった。
洞窟を抜けると、わたしはすぐに三枚歯の口に呑み込まれた。それから虹の森へ運ばれた。白ヘビの場所へ行くのはそのあとだと、赤い大蛇たちが言っていた。
このときに見た虹の森は、さらにひどい状態になっていた。
木がほとんど折れてなくなった森には、クラゲや風船たちの残骸が霧のように漂っていた。その中を数え切れないイガグリが、我が物顔で浮かんでいる。
生き残っているクラゲは戦意喪失した感じで、近くにイガグリがいても捕まえようとしない。流れ込んで来る風船たちは青くしぼんだまま、次々にイガグリの餌食になった。
わたしは具合が悪いのも忘れ、急いで森の上空を抜けると二枚歯の口へ向かった。
「お願いね! あの声の主の所へ、わたしを運んで!」
迫る巨大な口に向かって、わたしは叫んだ。
口の中へ飛び込んだわたしは、これまでと同じように扱われ、これまでのように吐き出された。
飛ばされて移動している間は、どこへ向かっているのかはわからない。途中の道は、どれも同じように見える。本当に頼んだ場所へ行けるのだろうかと不安になったが、やがてたどり着いたのは白いトンネルだった。でも風船たちの故郷のように、クモの巣みたいな柱はない。
何故トンネルが白いのか。それはこのトンネルが白ヘビの胴体でできているからだ。白ヘビの長い胴体がすだれのようにびっしりと並び、筒のようになったのがこのトンネルだった。
胴体ばかりで頭はないので、あの罵倒する声は聞こえない。でも、白ヘビの胴体から狂気が滲み出ていて、触れればどうなるかは予想がついた。
わたしは白ヘビに触らないよう、バランスを取って浮かびながら前に進んだ。
風船たちが心配になったけど、この白いすだれのような壁には、どの風船も触れていない。近づくことはあっても、ある程度までしか近づけないようだ。
わたしは恐る恐るすだれの壁に手を伸ばしてみた。ぎりぎりの所まで指を近づけてみるつもりだった。
風船たちが近づけない距離になると、わたしの指は透明の膜のような物に触れた。手のひらでその膜を押してみると、柔らかい感触で少し向こう側に近づけた。だけど、それ以上は手を押しやることができないので、壁に触れることはない。
わたしはほっとすると、流れに乗って先へ急いだ。
白ヘビのトンネルを抜け出ると、足場のない広い空間に出た。そこは辺り一面が色とりどりの水晶だった。まるで虹の七色でできた宝石が散りばめられているようだ。
浮かんでいるので地面がなくても平気だけど、重力を感じないこの場所では、どっちが上でどっちが下かはわからない。白ヘビのトンネルは絶壁のような所にぽっかり口を開けていたけど、身体の向きを変えれば、トンネルの出口が地面に開いているように見える。
トンネルを構成していた白ヘビの胴体は、トンネルの出口から周囲の水晶に向かって放射状に伸びている。それで地面に見えた絶壁は、白ヘビの胴体が敷き詰められた絨毯のようだった。でも、この白ヘビの絨毯も透明の膜で覆われているので、地面に降り立っても直接触れることはない。
そうは言っても、一度はひどい目に遭った白ヘビだ。わたしはできるだけ浮かんだまま、白ヘビの地面には足を降ろさないようにした。そのとき、近くで叫び声が聞こえた。
――敵ガイルゾ、火ヲ吐ケ!
どきりとしたわたしは緊張しながら身構えた。この声は大蛇の森で聞いた白ヘビだ。ここは白ヘビたちの巣に違いないから、わたしは白ヘビが襲って来ると思った。だけど、白ヘビは攻撃して来ないし、炎が出てくるわけでもない。
それでもわたしは警戒を解かないまま、辺りをよく観察した。わかったのは七色の水晶たちにも、例の目玉のような物がそれぞれ一つあるということだ。それは、水晶たちも風船たちの仲間ということであり、風船たちは他の所と同じように、水晶たちにも元気を分け与えてやっていた。
あの枯れ草の原っぱで見つけた赤い光の花が、数は非常に少ないけれど、風船たちに交じって漂っていた。水晶に触れた赤い光の花は、そのまま水晶の中に溶け込んで消えた。
それとは別に、何かきらめく小さな物がわたしの前を横切った。よく見ると、それはひらひらと舞う小さな透明の蝶だった。
このガラスのような蝶はクラゲの死骸の一部だ。何でこんなものがここに?――と思っていると、蝶は赤い水晶の上にとまり、小さな声で囁いた。
――敵デス。危険デス。
それだけ伝えると、蝶はそのまま塵となって消え去った。そのとき、水晶の赤い目が明るく輝いた。
――敵ガイルゾ、火ヲ吐ケ!
赤い目が放つ光でその水晶全体が赤く輝き、そこから出ている白ヘビの胴体が震えた。
そうか、そうだったのか。わたしは理解した。あの白いヘビを通して言葉を発していたのは、この水晶だったんだ。と言うことは、球体の赤い大蛇たちに呪いの言葉を発しているのも、ここの水晶に違いない。
敵がいる警報を発するのは、世界を護るためだ。だけど、世界に暮らす者たちを呪うのは、世界を滅ぼすのと同じことだ。
この二つの動きは矛盾している。きっと、一部の水晶が狂っているのに違いない。その水晶を探し出して狂った指示をやめさせれば、世界を救うことができるだろう。
洞窟には無数の水晶が所狭しと並んでいて、それぞれの水晶から白ヘビの胴体が伸びている。それでも叫んでいるのは赤目の水晶たちだけで、他の水晶たちは黙ったままだ。
わたしは洞窟をどんどん奥へ進んで行った。途中に、白ヘビのトンネルの出入り口がいくつかあった。だけど、世界を呪う水晶はまだ見つからない。あちこちで聞かれていた、赤目の水晶たちの叫び声も次第に遠ざかり、ついには何も聞こえなくなった。
どのくらい進んだだろう。前方で金色の光が輝くのが見えた。あの呪いの声も聞こえて来る。偽の神に違いない。わたしは光の場所へ急いだ。
そこは金色の水晶と銀色の水晶に囲まれた巨大な空間だった。前方の壁は金色の水晶、そして後方の壁は銀色の水晶でできている。
光りながら騒いでいるのは金色の水晶たちで、銀色の水晶は光らずに沈黙している。
――コレマデ貴様ニ、マトモニ、デキタコトガ、アロウカ?
――何ト恥知ラズナ、何ト情ケナイ奴ジャ。
――貴様ナンゾ、産マレテ来ネバ、ヨカッタンジャ!
みんな、世界を護ろうと必死に戦っているのに。大好きな神さまのために、懸命に生きているのに。そんなみんなに向かって、どうしてこんなひどいことが言えるの? 狂っているにしても許せない!
「あんたたち、さっきから、何ひどいことばかり言ってんのよ! あんたたちのせいで、この世界は滅びそうになってるのよ!」
わたしが叫んでも、ほとんどの水晶たちはわたしの声を無視して、同じような呪いの言葉を繰り返した。ただ、わたしの正面にいる水晶だけが、わたしの言葉に反応した。
――コレハ、神サマノ言葉デス。
呪いの言葉でない水晶の声は抑揚がなく、機械が喋っているみたいだ。
「その神さまって、どこよ?」
――コノ中デス。
「そんな出任せ言って! 神さまなんて、ほんとはいないんでしょ?」
――デマカセ? ワカリマセン。
「みんな、わたしが神さまだって言ってんのよ? それなのに、その中に神さまがいるって、どういうこと?」
――アナタニハ、神サマノ気ヲ、感ジマス。デモ、アナタハ、神サマデハアリマセン。
「どうして、そう言い切れるの?」
――神サマハ、世界ト一ツデス。世界が生マレタトキカラ、ズット、コノ中ニイマス。
「その神さまが、どうして世界を壊そうとするの?」
――神サマノ意思、ワカリマセン。我々ハ、神サマノ言葉ヲ、伝エルダケデス。
「世界が滅びるのよ? あなたたちだって、死んじゃうんだよ? それでもいいの?」
――ソレガ、神サマノ意思ナラバ、従ウノミデス。
「わたしはこの世界を救いたいの。この子たちを助けたいのよ!」
わたしは周りにいる風船たちを見回して言った。だけど、水晶の反応は変わらない。
――世界ヲ救エルノハ、神サマノミデス。
「だから言ってるでしょ? わたしが神さまだってば!」
――アナタガ、神サマナラバ、何故ココニ、イルノデスカ?
わたしは言葉に詰まった。水晶は淡々と言葉を続けた。
――アナタガ、神サマナラバ、ココニハ、イマセン。コノ中ニ、イルハズデス。
何と言う愚かな頑固者だろう。話にならない。わたしは無理やり中へ入ろうと、水晶を押しのけようとした。だけど、水晶はびくともしない。
それにここまで来たけど、今度こそもう力の限界だ。わたしは力を失い膝を折った。
そのとき、後ろに並ぶ銀色の水晶たちが、稲光の閃光が走るように光った。同時に、洞穴中に響くような大きな声が聞こえた。
「春ちゃん、しっかりして! 何で、こんなことに……」
「お母さん? お母さんだ!」
それは母の声だった。母の声によって、わたしは自分が誰なのかを思い出した。わたしは白鳥春花。中学一年生の女の子だ。
「お母さん、どこ? わたしはここにいるよ?」
通路に出て周囲を見渡しても、母の姿はない。代わりに銀色の水晶たちが稲妻のように光り、懐かしい声が辺りに響いた。
「まだ息がある。大丈夫よ、待っててね。すぐに救急車を呼ぶからね!」
救急車? そうか、わたしは部屋で倒れて死んだんだ。いや、そうじゃない。お母さんは、まだ息があるって言ってた。それに救急車を呼ぶということは、わたしはまだ生きてるってこと?
わたしは混乱した。生きているのなら、ここにいるわたしって何? この世界って何?
もし、わたしの身体が生きていたとしても、わたしがここにいる以上、身体が本当に生き返ることは有り得ない。よくて植物人間。悪ければ、やっぱり助からないだろう。
今すぐ戻れたら、わたしは助かるかもしれない。だけど、どうすれば元の世界へ戻れるんだろう?
どうやってここへ来たのかわからないから、ここから出る方法もわからない。それに、戻れる方法がわかったとしても、滅びかけてるこの世界を見捨てて、一人だけ逃げるなんてわたしにはできない。
自分が本当にこの世界の神なのかはわからないけど、みんながわたしを慕ってくれている。それなのに、みんなを放って行くなんてできないよ。
わたしは泣いた。世界も救いたいけど生き返りたい。元の世界に戻れなければ、助かるかもしれないわたしの身体は、今度こそ本当に死んでしまうに違いない。
わたしの身体……。わたしの大切な身体……。
真弓たちと揉めて学校にいられなくなり、わたしは自暴自棄になっていた。本当は自分が悪かったのに、それを認めることができず、何もかも身体のせいにしてしまった。
勉強ができないのも、運動が苦手なのも、身体が悪いわけじゃない。努力をしない自分が悪かっただけだ。自分の顔にブスって言ったけど、ほんとは案外可愛いって思ってた。
それなのに自分が死ぬって思ったとき、取り返しがつかないって思ったとき、わたしは自分の身体を罵ってしまった。お母さんがわたしのために産んでくれた身体なのに……。産まれたときから、ずっとわたしを支えてくれた身体だったのに……。
そう、わたしは思い出した。この体はわたしが生まれるために、先にお母さんのお腹の中で、わたしを待ってくれていたんだ。わたしと一つになりたくて、ずっと待っていてくれたんだ。
それからわたしと体は、何をするにも一緒だった。体はわたしの一番の相棒で、どんなことでもわたしと一緒に経験したんだ。
いや、そうじゃない。体はわたしが望むとおりに動いてくれて、わたしにいろんな喜びを経験させてくれた。
体がこうして欲しいって、わたしに訴えて来ても、わたしはそれを無視することがあった。それでも体はわたしを裏切ったりしないで、いつもわたしのために動いて、わたしを支えてくれていた。
わたしがお母さんから生まれることができたのも、家族でいろいろ楽しむことができたのも、絵を描くことができたのも、谷山と二人三脚ができたのも、全部体が手伝ってくれたからだ。久美と知り合えたのも、早苗に漫画を見せてもらえたのも、体が一緒にいてくれたから。
転んで怪我をしたって、体はがんばって傷を治してくれた。風邪を引いたときだって、一生懸命風邪を治してくれたんだ。
わたしが具合が悪いのならば、体だって具合が悪かったはずだ。それなのに体はわたしのために、ずっとがんばってくれていた。それなのに……。
倒れたままわたしに罵倒され、涙をこぼしたわたしの身体の姿を、わたしは思い出していた。
あなたは何も悪くないのに、あんな姿になるまで追い詰めて、挙げ句の果てに罵って死なせてしまうなんて。わたしは何て馬鹿だったんだろう。ごめんね、わたしの身体。ごめんね……。許してなんて言えないけど、それでもあなたはわたしを責めないんでしょ? ごめんなさい……、どうか、わたしを許して……。
涙ぐむわたしの頭に、鏡に映した自分の姿が浮かんだ。鏡の中のわたしが囁いている。
――あなたはね、この世でたった一人の、わたしの神さまなの。
わたしは、はっとした。そうだ、あのとき鏡の中のわたしは、確かにそう言った。
――ミンナ、一ツノ存在ノ、分身ナンダヨ。コノ世界ノネ。
不思議な生き物の言葉が、わたしに考えさせた。
わたしを神と慕う風船たちは、この世界の分身だ。でも、この世界って?
――あなたはね、この世でたった一人の、わたしの神さまなの。
鏡の中のわたしが囁き続けている。
――カツテ、コノ世界ハ、アナタノ愛ニ満チテイタ。
不思議な生き物が語りかけてくる。
突然すべてがわたしの中でつながり、わたしはようやく理解した。風船や大蛇たちは、みんなわたしの身体の分身で、この世界は、わたしの身体の心そのものだった。
そして、わたしは思い出した。
不思議な生き物が語った二つの愛とは、父の愛と母の愛だ。
二つの愛が一つになって母の中に宿り、そこにわたしの愛が加わった。それがわたしの身体であり、この世界だった!
そのとき、洞穴中のすべての水晶が金色に輝いた。わたしは光に包まれ、気がつくと洞窟とは違う場所にいた。だけど、ここはどこなんだろう?
偽の神の正体
わたしが佇んでいたのは、光の霧の中だった。
ここには風船たちも水晶たちもいない。不思議なことに、ずっと続いていた身体のだるさも消えていた。
ここはどこだろう。霧の中で頭をめぐらせていると、どこからか罵声が聞こえて来た。
「こうなってしまったのは貴様のせいじゃ。何もかも貴様が悪いのじゃ。出来損ないの貴様なんぞ、このまま消えるがいい!」
光の霧で視界が妨げられ、周りで何が起こっているのかが全然わからない。
わたしは両手を伸ばして霧の中を探りながら、声が聞こえる方へ近づいて行った。すると次第に光の輝きが弱まって、辺りはだんだん薄暗くなった。その暗さは一歩進むごとに濃さを増して行く。
「貴様のせいで、今までどれほどつらい思いをしたことか。貴様なんぞに、この悲しみはわかるまい」
白黒の世界の中で、着物姿の女が背を向けて立っている。
その女の前に誰かが倒れていた。罵声はこの着物の女が、倒れている誰かに向かって発しているものだ。
怒鳴っている女に気づかれないようにしながら、わたしは女の横へ回ろうとした。そのとき、倒れている人物の顔が見えたわたしは、思わず驚きの声を上げた。そこに倒れているのは、わたしだった。
わたしの声に気づいて、怒鳴っていた女が後ろを振り返った。その女の顔を見たわたしは、二度目の驚きの声を上げた。
髪を振り乱した女の額には、二本の角が生えている。赤い口元からは牙がのぞき、両手の指の爪は鋭く伸びていた。女は般若だった。
この般若こそが偽の神に違いない。と言うことは、般若の前に倒れているのは、身体のわたし?
般若は怪訝そうに目を細めると、小首を傾げながら二人のわたしを見比べた。
「貴様は誰ぞ?」
恐ろしくてすぐには声が出なかった。それでもわたしは気持ちを落ち着けると、精一杯平気な顔を装った。
「神よ。この世界のね」
「神とな?」
般若は目を大きく広げると、後ろに仰け反りながら大笑いをした。
「この暗い世界の神じゃと申すか。かような牢獄ごとき所にも神がおるのか」
般若はわたしを馬鹿にした。だけど、それは般若がこんな狭い所しか知らない無知であることの表れだ。お陰でわたしは少し気持ちに余裕を持つことができた。
「あんたが知らないだけだよ。すぐそこまで行けば、眩しいくらいに明るいんだから」
般若は笑うのをやめると、ずいっと前に出た。わたしは思わず後ずさりをした。
「面白いことを言う。ならば、そこへ案内してもらおうか」
「じゃあ、わたしの後について来ればいいよ」
般若に背を向けるのは怖かった。だけど仕方がない。わたしは般若の先に立って歩き始めた。それでも気になってちらりと後ろを振り返ると、般若は黙ってついて来ている。
ともすれば恐怖が込み上げようとする。だけど、わたしは神だ。わたしの身体の世界の責任者だ。風船たちを助け、身体のわたしを救うという使命が、わたしの恐怖心を抑え込んでいた。
しばらく歩いたけど、どういうことか、どこまで行っても暗闇ばかりだ。いつまで経っても光のある所に行き着かない。さっきまでいたあの場所はどこなのだろう。
「まだか? まだ明かりのある所には着かぬのか?」
いら立ったような般若の声が、後ろから責め立てる。
もう少しだからと言って、さらに歩いたけれど、やはり暗闇から出られない。光の場所からこの闇に入るまで、こんなに時間はかからなかったはずなのに。
どうやら迷ってしまったようだと焦っていると、前方に誰かが倒れているのが見えた。近づくと、それはさっき見た身体のわたしだった。
「元に戻ってしまったようじゃな」
後ろで般若が勝ち誇ったように言った。わたしは般若を振り返って言い訳をした。
「待ってよ、本当なんだから。本当に光がいっぱいあったんだってば!」
「何が光じゃ、この大嘘つきめが! 貴様もそこな女と同じように死ぬがいい!」
般若が身構えながらにじり寄って来る。わたしは般若を見ながら後ろへ下がった。だけど、後ろに倒れていた身体のわたしにつまずいて、わたしは尻餅をついた。
その拍子に身体のわたしは小さく呻き声を出した。よかった。まだ生きているようだ。
「ねぇ、しっかりして!」
わたしが揺り動かすと、身体のわたしはうっすらと目を開けた。
「あなたは……」
身体のわたしが蚊の鳴くような声を出したとき、般若が呪いの言葉を放った。
「まだ生きておったか、この役立たずめが。さっさと死なぬか、この屑め!」
身体のわたしは目に涙をいっぱい浮かべると、がくりと頭を落とした。声をかけて揺さぶってみても、ぴくりとも動かない。わたしは無性に腹が立って、般若をにらみつけた。
「あんたは何で、そんなひどいことを言うの? この子があんたに何をしたのよ!」
般若はぎょっとしたような顔で、わたしをじっと見つめた。
「貴様……、何故平気でおれるのじゃ?」
「何言ってんの? わけわかんないこと言ってないで、ちゃんと説明してよ! 何であんたはこの子に意地悪をするの?」
般若の耳にはわたしの言葉なんて入っていないみたい。般若はわたしを無視して再び呪いの言葉を吐いた。
「貴様は頭が悪く、動きも鈍い。真の友もおらぬ上に、身内にとっての厄介者め!」
今度の言葉はわたしの胸にぐさりと突き刺さった。わたしが怯むと、般若は勢いを取り戻したようだった。さらなる悪態をつきながら近づいて来た。
「さぞかしつらかろうの。友と信じた者に裏切られ、惚れた男を奪われたのじゃ」
「な、何であんたが、そんなことを知ってるのよ?」
「気の毒にの。醜女でなければ、男を奪われずに済んだものを」
やっぱり谷山のことを言われるのはつらい。わたしは唇を噛んだ。
「申してみよ。貴様に如何ような価値がある? さぁ、申してみよ! 申せぬか。申せんわな。貴様なんぞに生きる価値なんぞあろうものか。そもそも産まれて来たのが誤りぞ」
言い返せないわたしは、いつの間にかうなだれていた。悔しさに涙がこぼれ、その涙が倒れているわたしの頬に落ちた。すると、わたしが小さな声でつぶやいた。
「神……さま……、ごめんなさい……」
やっぱりこのわたしは、身体のわたしだ。わたしの闘志に再び火がついた。このわたしのために、あの風船たちのために、こんなことでへこたれてどうする?
わたしは身体のわたしを抱きかかえると般若をにらんだ。
「あんたが言ったことは全部本当だよ。わたしはブスだし、勉強も運動も苦手なの。やっとできた本当の友だちだって関係が壊れちゃった。でもね、こんなわたしでも慕ってくれる者たちがいるんだよ。それも、数え切れないぐらいいっぱいね!」
「貴様を慕う者がおるとな? さような者がどこにおると申すのか」
「この子よ」
わたしは抱きかかえた身体のわたしを見つめた。痩せ細って痛々しい姿だけど、ちっとも醜いなんて思えない。愛おしくて愛おしくてたまらない、わたしの大切な身体の心。
「この子はね、わたしの身体なの。この子の中には数え切れないぐらいの、この子の分身がいるのよ。その子たちはね、どんなにつらくたって、どんなに悲しくたって、みんな、わたしを慕ってくれてるのよ!」
「何を戯けたことを……」
「だいたい、何よ。さっきから人のことばっかり言って! あんた、自分はどうなの? あんたは何ができるの? 言ってごらん? そんな恐ろしい顔してるんだから、さぞかし恐ろしい化け物仲間がいっぱいいて、あんたのことを大事にしてくれるんでしょうね?」
般若はわたしをにらみながら口をもごもご動かした。だけど反論はできない様子だ。それにしても、この般若は何者なんだろう?
「ほら、言ってごらん。あんだけ人のことをぼろっかすに言ったんだから。あんたはさぞかしすごいんでしょうね? ほら、言ってよ。あんたは何ができるわけ? 黙ってないで言いなさいよ!」
わたしが立ち上がって前に歩み出ると、般若はじりじりと後ずさりをした。もう般若に対する恐怖心はなくなっていた。
「そんな姿してたって、ちっとも怖くないよ! そんな角を生やして、そんな牙や爪を見せられたって、全然怖くないんだから!」
本当に襲いかかられたら大変だけど、何故か般若は襲って来ないという確信が、わたしにはあった。
わたしに言い返せない般若はその場にへたり込み、うなだれてしくしく泣き出した。思ってもみなかった般若の姿に、わたしは思わず般若に駆け寄った。
般若の肩に手をかけようとしたとき、般若は泣きじゃくりながら言った。
「だって……おとうさんもおかあさんも、いっつもおにいちゃんのことばっかりだもん」
え?――驚いたわたしは、般若をまじまじと見下ろした。
さっきまでの般若の声は恐ろしい女の声だった。でも、今のは幼い女の子の声だ。
「おにいちゃん、おべんきょうもできるし、走るのもはやいの……。でもね、わたし、おべんきょうもできないし、走るのおそいから、ほめられるのは、いっつもおにいちゃん」
「ちょっと、どうしちゃったの?」
「自転車だってね、ほんとは乗りたかったの……。だけど、こわかったし、おにいちゃんに笑われたから、乗れなくなっちゃったの……」
「あんた、もしかして……」
「おとうさんはおしごとばっかり……。おにいちゃんも遊んでくれないし……、おかあさんのこともね、がっかりさせてばっかり……。わたしね……、悪い子なの……。できそこないなの……。わたしなんか、だぁれもだいじに思ってくれないの……。だからね、だからね……、わたし、わたし……、鬼になるしかなかったの……」
わたしは般若を抱き寄せた。着物の下に隠れた般若の体は、驚くほど小さくて着物はぶかぶかだった。ぽとりと落ちた般若の面の下にあったのは、泣きじゃくる幼い女の子の顔だった。そう、この子は幼い頃のわたしだった。わたしは幼い自分を抱きしめた。
「いいのよ。もういいの……。あなたは悪くないよ。あなたは悪い子じゃないし、鬼でもないの。あなたはね、そのままでいいんだよ。あなたのことは、わたしがわかってる。だから、もう泣かないで」
まだ泣き止まないわたしに、わたしは喋り続けた。
「あなたはね、世界でたった一人の素敵な女の子なんだよ。あなたはお母さんのことが大好きで生まれて来たんでしょ? お母さんだってそのこと、ちゃんとわかってるし、お母さんもあなたが大好きなのよ。ただね、お母さんもいろいろ大変で、あなたに構って上げられなかったの。でも、そんなお母さんを助けるために、あなたは生まれて来たんでしょ?」
語りかけた言葉は、自分自身に言い聞かせるものでもあった。
泣くのをやめて顔を上げた幼いわたしを、わたしは励ました。
「思い出してごらんよ。悪いことばかりじゃなかったでしょ? ほら、わたしも今、思い出した。お父さん、動物園に連れて行ってくれたじゃない。ゾウさんやキリンさんやライオンさんと一緒に、写真を撮ってくれたの覚えてない? お父さん、あなたの写真ばっかり撮ってたからさ、お兄ちゃんむくれてたでしょ?」
幼いわたしは涙でいっぱいになったつぶらな瞳で、わたしを見ながらこくりとうなずいた。
「幼稚園で食べたお弁当。毎日美味しそうなおかずだったでしょ? あれだってね、お母さんが疲れてるのに、朝早く起きてあなたのために作ってくれてたんだよ。そうそう、あなたが風邪引いて寝込んだとき、お母さん、ずっとあなたの傍にいてくれたでしょ? わたし、知ってるよ。お母さん、あなたが心配で全然寝なかったんだから」
「おぼえてる……」
「ほらね? お父さんもお母さんも、あなたのこと大好きなの。お兄ちゃんだってさ、お友だちの所でもらったお菓子、あなたのために持って帰って来てくれたよね?」
小さくうなずく幼い自分の頭を撫でてやりながら、わたしは思い出せる限りの家族との楽しい思い出を話してやった。そうしていると、自分が癒やされて行くような気がした。
わたしは幼い頃から自分を責め続けていた。それなのに、今もまた幼い自分を責めてしまった。わたしはひどい言葉をぶつけたことを、幼いわたしに謝った。
幼いわたしは首を振り、いじわるをしてごめんなさい――と言った。
そのとき、闇の中に閃光が走った。同時に、母の叫び声が辺りに反響した。
「春ちゃん、今、救急車を呼んだからね! 死んだらだめよ! あなたが死んだら、お母さん……、お母さん……どうして生きて行けばいいの……? だから、お願い。死なないで!」
声を絞り出した母の嗚咽が響く。
やっぱり母はわたしを愛してくれていた。それはわかっていたはずのことだった。だけど、心のずっと奥の方には拗ね続けていた自分がいた。その自分が泣いているのを感じたとき、幼いわたしが涙ぐみながらつぶやいた。
「おかあさん……、おかあさん……」
幼いわたしはつぶやきながら、わたしの腕の中で光になった。その光はわたしを包み、いつの間にか辺りは光の霧に戻っていた。
幼いわたしは姿を消していた。だけど、わたしにはあの子がどこへ行ったのかわかってる。あの子はわたしの中に戻ったのだ。
わたしはかがむと、倒れているもう一人のわたし――身体のわたしを助け起こした。
「しっかりして! お願い! もう二度とあなたのこと責めたりしないから、目を覚まして!」
身体のわたしは目を開けると、微笑みながらわたしの手を取った。
「うれしい。わたしのことを思い出してくれたんですね」
「今までごめんね。わたし、あなたのことをすっかり忘れて、自分一人で生きてるって思い込んでたの。本当にごめんね」
「わたし、あなたに思い出してもらいたくて、これまで何度もわたしを見てもらおうとしてたんです」
「それじゃあ、今までわたしをあそこに招いていたのは……」
「わたしです。でも今回はあなたの方から来てくれたんですね。ありがとう」
わたしは感激でいっぱいになり、身体のわたしをしっかりと抱きしめた。涙が勝手にあふれて止まらない。
相手を想う互いの気持ちが、溶け合って一つになっていく。同時に、わたしとわたしは一つに重なった。
はっとなって目を開けたわたしの顔に、何かがかぶせられている。すぐ横に母がいて、涙を浮かべた目でわたしを見ていた。
「春ちゃん、気がついたのね? よかった!」
母が喜びの声を上げると、母の傍にいた男の人が、わたしの顔をのぞきこみながら話しかけた。
「春花さん、わかりますか? もうすぐ病院に着きますからね」
どうやらわたしは救急車に乗せられているようだ。ぶら下がった点滴の管が、わたしの腕につながれている。
「お母……さん……」
わたしが弱々しい声で呼びかけると、母は泣きそうな顔で言った。
「何? どこか痛いの? 苦しいの?」
「お母……さん……、大好き……だよ」
母が号泣したのは覚えている。でも、そのあとのことは覚えていない。次にわたしが目を覚ましたのは病室の中だった。
ベッドの横には母と兄貴がいた。その隣には、遠い出張先にいるはずの父がいた。父は笑顔を見せたけど、その目は泣き腫らしたみたいに真っ赤になっていた。
わたしは体力が落ちているところへ肺炎にかかってしまい、病院に担ぎ込まれたときには、かなり危険な状態だったらしい。それで、父は仕事も放り出して戻って来たそうだ。
とは言っても、今もまだ具合は悪く、頭はぼんやりしているし息苦しさがある。一番の危機を脱しただけのことで、絶対安静なのは変わらない。それでもせっかく家族全員が揃ったから、何か話がしたかった。
酸素マスクをしているのと、倦怠感で喋るのが億劫だったけど、耳を近づけてくれた兄貴を通して、わたしはみんなに心配をかけたことを謝った。父も母もそんなことはいいからと言ってくれたし、兄貴さえもが余計なことは考えるなとわたしをいたわってくれた。
わたしは父を呼んで、自分の子供の頃の写真が欲しいと言った。思い出した記憶では、父には写真をたくさん撮ってもらっているはずだった。
父が少しうろたえると、母が笑いながら父の弁解をした。
父はわたしが可愛くて仕方がなく、こないだのお盆に家に戻ったときに、わたしのアルバムを持って行ったのだと言う。
父は真っ赤になりながら惚けていたけど、最後にはわたしをそっと抱いて、本当はずっと一緒にいたいと言ってくれた。わたしには大学の話をしないのも、お金の問題ではなくて、わたしを家から出すのが心配だったからだそうだ。
慌てた様子のお年寄りが二人、病室に入って来た。父方の祖父母だ。二人はわたしの手を握り、何でこんなことにと言って泣いていた。
わたしは幸せを感じていた。バラバラになっていた心と身体が一つになったばかりか、ようやく家族と一つになれたのだ。きっと、わたしの中で風船たちも喜んでいるにちがいない。
久実からの手紙
熱が下がり、酸素マスクも取れた頃、わたしは一人部屋から四人部屋へ移された。
その部屋には、わたしの他に二人の患者がいた。だけど一人が昨日のお昼過ぎ、もう一人が今朝退院して、部屋はわたしの貸し切りになっていた。
そんなところに宮中満里奈と山田早紀が見舞いに来てくれた。二人ともわたしの姿を見るなり泣き出した。わたしが死ぬかもしれないと思っていたらしい。
満里奈はクラスのみんなが心配していると言い、早紀は早く学校へ戻って来て欲しいと言ってくれた。
二人が来てくれたことは素直にうれしかったけど、意外でもあった。わたしは信用ならない大ボラ吹きだったはずだ。
そのことを言うと、二人はそのようには思っていないと言った。その理由は、自分たちが嘘をつかれたわけではないし、真弓たちの言い分をそのまま信じたりもしていないかららしい。
ただ、あのときにわたしに声をかけなかったのは、事情がよくわからず、自分たちが関わるべきかどうか迷ったからだそうだ。
それでも満里奈は何があったのかを、昼休みにわたしから聞くつもりだったらしい。ところが、わたしがさっさと帰ってしまい、そのまま学校へ出て来なくなったので、話を聞きそびれたのだと言う。
早紀も自分も同じだと言い、ずっとわたしのことを心配していたそうだ。
中には真弓たちの言い分だけを聞いて、わたしを悪く見た者もいたらしい。でも、わたしが嘘をつくことになった理由を、早苗がみんなに説明してくれたそうで、それでわたしを悪く見ていた者も見方を変えたということだった。でも真弓と百合子にとっては、それは逆風が吹き出したという意味になる。
満里奈たちはその話をわたしに伝えたかったそうだけど、わたしは部屋に閉じ籠もって母の話さえ聞こうとしなかった。それでその話を聞かないまま、わたしは重傷の肺炎になって入院した。
実際、わたしはかなり危ない状態だったようで、満里奈たちはわたしが死ぬのではないかと、気が気でなかったと言う。真弓と百合子はみんなから責められたらしいけど、それでも自分たちは悪くないと強気を見せていたそうだ。
ところが、そのあと事件が起きたと満里奈たちは言った。
心配したとおり、三組の前田健二が真弓に恋文を渡しに来たと二人は言った。
前田は真弓を人がいない場所へ誘ったそうだけど、用があるならここで言ってと、真弓は教室を出ようとしなかったそうだ。それで前田が真弓に手紙を渡したら、なんと真弓はその手紙をその場で広げて読み上げたと言う。その上で真弓は前田に、自分はあんたには全然興味がないと言い放ったそうだ。
真弓がそんなことをしたのは、わたしのことで旗色が悪くなっていたからじゃないかと思うと早紀は言った。どういうことかと言うと、自分は何も悪くないから責められても平気だし、こんな人気者なのだと、みんなにひけらかしたかったのだろうということだ。
本当のところは本人から聞いてみないとわからないけど、確かにそうかもしれないとわたしも思った。真弓の気位の高い性格を考えると、誰かを見下すことはあっても、自分が低く見られることは受け入れられないに違いない。
前田にすれば、相当な勇気を出して手紙を書いたのに、みんなの前で大恥をかかされたわけだ。その前田に真弓は借り物競走で前田を選んだ理由を説明し、自分に気があると思い込んだ前田を馬鹿にして笑ったと言う。
前田はそのまま学校を飛び出して行方を眩まし、三組の生徒たちが手分けして探したのだと、早紀は腹立たしげに喋った。
わたしが真弓と百合子に嘘をつくことになったきっかけは、二人が転校生の久美を馬鹿にしたからだ。その話を早苗から聞いていた早紀も満里奈も、真弓に嘲笑された前田と久美が重なって見えたと言った。そして、こんな真弓たちに同調するのが嫌で、わたしが嘘をついたのだと改めて理解したそうだが、他の者たちも同じことを口にしていたらしい。
結局、前田は体育倉庫の裏で一人で泣いているところを見つかった。
三組の生徒たちは前田を教室へ連れ戻したあと、怒って真弓の元へ押しかけて来たと言う。それは大変な騒ぎで、下手をすればクラス同士の大喧嘩になりかねない状況だったようだ。ところが一組の生徒で真弓をかばおうとする者は、一人もいなかったそうだ。百合子でさえもが、前田を晒し者にした真弓の行為を、やり過ぎだと言ったらしい。
三組の生徒たちから吊し上げを食った真弓は、泣き出しはしたものの、前田への謝罪は頑として拒否したと言う。それで頭に来た三組の生徒たちは、真弓につかみかかったそうだ。谷山が止めようとしても、騒ぎは収まらなかったようだ。
「そこにね、真弓たちが馬鹿にしてたっていう二組の兵頭って子がね、やめや!――て言いながら割って入ったの。それで、その子が真弓を抱きかかえてかばったのよ」
満里奈が言葉を切ると、早紀が興奮気味に言った。
「あのときは、みんな驚いたよ。だって、全然関係ないはずの二組の子がさ、たった一人でそんなことするなんて、誰も思ってなかったからさ」
「て言うか、あの子だって真弓たちから馬鹿にされてたんでしょ? そのことに気がついてたんだとしたら、信じられないことだよね」
付け足して喋った満里奈の言葉に、早紀も大きくうなずいた。
わたしも驚いた。どうして久美がそんなことをしたのかわからなかったし、久美の中にそんな強い勇気があったとは知らなかった。
わたしが話の続きを求めると、早紀が話してくれた。
「それであの子ね、大勢で一人の人間を寄ってたかって責め立ててどうするんだって、みんなに言ったのよ。そしたら誰かが、こいつが悪いんだって言い返したわけ。そしたらあの子、やるなら一人でやれって言って譲らなかったんだ」
すごかったよねと早紀は真弓とうなずき合った。谷山でさえ止めることができなかった騒ぎを、女子の久美が一人で止めたことに、早紀たちは感動を覚えたと言う。
そしたらさ――とわたしに顔を戻した満里奈が言った。
「あれだけ謝らないって言ってた真弓がね、前田くんに謝るって言い出したんだ」
「ほんとに?」
「ほんとよ。あたし、あの子、すごいなぁって思ったんだ」
満里奈の言葉に早紀もうなずいていたけど、でもね――と言った。
「すごい騒ぎだったから、二組の子たちも見に来てたんだけどね。その中の女子でさ、何を偉そうに!――て、その子のことを悪くいうやつがいたんだ」
満里奈も続いて言った。
「あの子、転校生でしょ? その女子が言うにはね、あの子は前の学校でいじめ問題を引き起こして、それで学校にいられなくなって、こっちへ逃げて来たそうなの。向こうの学校で喧嘩して、何人も怪我させたんだって」
「何よ、それ! そいつ、何を根拠にそんなでたらめを言うわけ?」
そんなことを言うのは、創作ダンスで久美に足を引っかけて転ばせたあの女子に違いない。頭に血が昇ったわたしは、自分がその場にいなかったことが腹立たしかった。
憤るわたしを二人は慌てたようになだめた。興奮すると、また病状が悪化すると思ったようだ。
わたしが落ち着くと、満里奈が言った。
「今、スマホで何でも調べられるじゃない。その子、それで調べたらしいのよね」
わたしがまた興奮しそうになると、早紀がもう一度わたしをなだめて言った。
「あたしたち、何も確かめてないから、本当のことはわかんないけどさ。とにかく、あの子はあの騒ぎを収めてくれたんだから、それはそれでしょ?」
久美をかばっているつもりかもしれないけど、早紀の言い草にわたしはカチンと来た。
「久美はそんなことする子じゃない! スマホにどんな情報があるのか知んないけど、そんなの全部でたらめよ。そんなのを鵜呑みにする方が馬鹿なのよ!」
今度は満里奈がまぁまぁと両手でわたしを制して、とにかくさ――と言った。
「問題は真弓が前田くんを晒し者にしたってことだからね。誰も二組の女子のピンボケた話なんか相手にしなかったよ」
早紀も笑顔で、そうそうと言った。
「結局さ、その女子は二組のテニス部員に連れて行かれて、それでおしまい。そのあとも兵頭って子の噂が出ることもなかったからさ。何も気にすることないよ」
そうは言っても、わたしは久美が心配だった。それで、そのあと久美はどうしたのかと尋ねたが、早紀と満里奈は顔を見合わせて、わからないねと言った。それから早紀が弁解するように言った。
「その女子に何も言い返さなかったし、いつの間にかいなくなってたからさ」
「二組でも何も問題はなかったの?」
「隣のクラスのことだからさ。あたしもよくわかんないよ」
当惑する早紀に代わって満里奈が言った。
「でも、何かあったって話もないから、おそらく何もなかったんじゃないかな」
二人はこの話を切り上げたいようで、いつ退院できそうなのかと話題を変えた。わからないけど近いうちだと思うと話すと、もう中間テストが始まるから、学校へ出て来るのはそれが終わってからがいいよと早紀が言った。
中間テストと言われて、わたしはぎくりとした。元々勉強ができていないところに、学校を長く休んでしまったから、今テストを受ければほぼ0点なのは間違いない。
このままテストを逃れたとしても、勉強が遅れた分はこれからがんばって取り戻さなければならない。そのことを考えると、このままずっと入院していたくなる。それでもやはり久美のことは気になった。
学校を飛び出したとき、わたしは久美と谷山の仲を疑った。だけど、今はそんなことはどうでもよかった。
わたしは今回のことで相棒である身体のわたしはもちろん、家族の大切さを知った。それと同じように、わたしにとって久美は大切な存在だ。
久美と谷山が好き合っていたとしても、久美が大切であることには変わりがない。そのことにも今回の体験はわたしに気づかせてくれた。わたしは久美が笑顔でいてさえくれればそれで満足だ。
早く久美に会いたいけど、久美はまだ見舞いには来てくれていない。わたしの回復を耳にしたなら、一番に会いに来てくれそうなものだけど、わたしは家に訪ねて来てくれた久美を無視したし、久美がくれた電話にも出なかった。そのことで久美が気を悪くしていたなら、そのことを謝りたかった。そして前のような関係に戻りたかった。
満里奈と早紀が帰ってしばらくすると、今度は早苗と谷山が来てくれた。
思いがけない取り合わせに驚いていると、谷山が照れながら、早苗と一緒に来たわけではなく、たまたま下で一緒になったのだと弁解した。
早苗が来てくれたことには、わたしは驚かなかった。でも谷山が見舞ってくれるとは、夢にも思っていなかった。
初めに早苗が顔を見せたときには、自然に笑顔が出た。でも、その後ろに谷山が姿を現すと、わたしは驚きを通り越して、頭の中の配線が切れたようになった。
でも、谷山も緊張していたみたいだった。もう大丈夫なの?――と早苗は聞いたけど、谷山は突っ立ったまま、わたしが早苗と喋るのを横で黙って聞くだけだった。早苗が気づいて声をかけなければ、谷山は最後まで喋らなかったかもしれなかった。
早苗は小さな花束をわたしにくれた。わたしはお礼を言ったあと、満里奈たちから聞いたよと言った。
「サッチー、みんなの前でわたしのこと、かばってくれたんだって?」
「え? いや、だって、元はと言えば、わたしが悪いから……」
下を向いた早苗に、そんなことないよとわたしは言った。
「ほんとに悪いのはわたしなの。サッチーじゃないよ。わたしが自分を悪く見られたくなくて、ほんとの気持ちを相手にはっきり伝えなかったのが悪かったんだ。だからね、サッチーは悪くないんだよ」
「だって、わたし……」
「まぁ、馬鹿正直っていうのは、ちょっと考えた方がいいかもしんないけどさ」
わたしが笑うと、早苗も泣きそうな顔で笑った。その横で話がよくわからない谷山が、重そうな袋を抱えたまま当惑している様子だ。
「谷山とは関係ない話をしちゃった。ごめんね」
わたしが謝ると、いいよいいよと谷山は笑顔を見せた。
「ところで、その袋は何? もしかして、わたしへのお見舞い?」
わたしに聞かれると、谷山は待ってましたとばかりに、その袋をベッドの上に載せた。その重みでマットがずんと沈むと、わたしは何だろうと言って早苗と顔を見交わした。
「これさ、オレのお気に入りの漫画なんだ。落ち込んだときなんかさ、これ読むと元気が出るからさ、白鳥にもいいかなって思って持って来たんだ」
漫画と聞いて目を輝かせた早苗が、どんな漫画かと尋ねると、谷山は袋の中から一冊を取り出して、冒険物だと言った。それから物語についての谷山の熱い説明が始まった。興奮した早苗は、わたしが読み終わったあとは自分に貸して欲しいと谷山に懇願した。
谷山はうれしそうに笑うと、いいぞと言った。それから二人は漫画談義をして、それぞれの好きな漫画の話に夢中になった。まったく、ここへ何をしに来たのやらだ。
話が一段落したところで、ずっと心配してたんだぞ――と谷山はわたしに言った。
あのとき、谷山も何があったのかがわからないまま、わたしに何と声をかければいいのか悩んだらしい。それで、わたしと仲がいい久美が何か知っているのではないかと思い、昼休みに久美から話を聞いていたら、わたしが学校を飛び出したのが見えたと、谷山は申し訳なさそうに言った。
久美と谷山の関係を誤解していたわたしは、自分の愚かさが許せなかった。せっかく家まで訪ねてくれたり電話をくれた久美を、無視してしまったことが改めて悔やまれた。
気持ちが顔に出たようだ。谷山と早苗が大丈夫かとわたしに聞いた。わたしは笑顔を繕って、ちょっと疲れただけで大丈夫と言った。
早苗はわたしを気遣い、そろそろお暇しようかと谷山に言った。わたしは慌てて、大丈夫だからもう少しいてと、二人を引き留めた。谷山は迷っていたけど、結局話を続けた。
「オレさ、さっさとお前から直接話を聞くべきだったって、ずっと悔やんでたんだ」
「ありがとう。だけど、何で谷山が悔やむの?」
「え? だって、そんなの当たり前だろ? 同じ一組の仲間が大変なことになったら、誰だって何とかしようって思うじゃん」
そうじゃないから、学校を飛び出すことになったんだってば。だけど、まぁいいか。
「谷山って優しいね。男子でお見舞いに来てくれたの、谷山だけだよ」
「え? そうなのか? まぁ、みんな恥ずかしがり屋だからな」
谷山は照れたように笑ったが、何だかうろたえているみたいでもあった。
「白鳥さん、検温です」
若い女性の看護士が入って来た。早苗と谷山はわたしから離れて、看護師に場所を譲った。
看護士はてきぱきとわたしの状態を確かめ、明日のレントゲン検査と、血液検査で異常がなければ、退院の許可が出ると思うと言った。
看護士が出て行くと、谷山もそろそろ帰ると言った。
もう少しいて欲しかったけど、これ以上は恥ずかしくて言えない。来てくれてありがとうと言って、持って来てもらった漫画は退院しても必ず読むからと約束した。
谷山は病室の戸口まで行くと、もう一度戻って来た。それで、元気になったら絶対に学校へ戻って来いよ――とわたしに約束を迫った。
拒むことができず黙ってうなずくと、谷山は安心したように笑った。
「待ってるからな」
谷山はそう言い残して帰って行った。
「谷山くん、白鳥さんのことが好きなんだね」
谷山を見送った姿勢のまま、早苗がぽそりと言った。
「ちょっと、何言ってんのよ!」
わたしは思わず否定したけど、顔が熱い。きっと真っ赤になっているに違いなかった。
早苗は振り返ると、絶対にそうだよ――と楽しそうに言った。せっかく熱が下がったと言うのに、早苗はわたしの退院を長引かせるつもりらしい。
「それよりさ、久実はどうしてるの? 元気にしてるかな?」
わたしは急いで話題を変えた。それに早苗なら久美のことを知っているんじゃないかと思っていた。
ところが早苗は暗い顔になって、最近兵頭さんには会っていないと言った。理由を尋ねると、自分のせいでわたしが学校に出られなくなったから、久実に顔を合わせられなかったと言う。
わたしは満里奈たちから、真弓と前田の騒動のことを聞いたと話し、そのときに久美が真弓をかばったそうだねと言った。
早苗はうなずくと、兵頭さんはとても勇敢で立派だったと言った。
二組の女子が久美を貶めるようなことを言ったらしいねと聞くと、ひどい人だと早苗も思ったそうだ。それでもその女子が言ったことが気になって、早苗は自分でもスマホで調べてみたと言う。そう、早苗はわたしや久実と違って、スマホを買ってもらっていた。
「そしたら、本当にそんな書き込みをしている所があってね。わたし、兵頭さんに何て声をかけたらいいのかわかんなくって……。ただでも顔を合わせにくいのに、余計に話ができなくなっちゃったの」
「そんなこと、わざわざ調べたの?」
「だって、気になったから……」
沈黙が続いたあと、わたしはそんな話は信じないと言った。
「人の悪口言う人なんて、平気で勝手なことを言うからね。そうやって、騒ぎが大きくなるのを隠れて見るのが楽しいのよ。だから、わたしはそんなの信じない」
「わたしも信じたりしてないよ」
早苗が訴えるように言った。早苗が嘘をつくはずがないから、わたしは早苗を信じると言った。だけど、久実のことが心配だ。
「久実、どうしてるんだろう? 大丈夫かな?」
「本人から直接聞いたわけじゃないから、本当かどうかわかんないんだけど……」
早苗はさっき谷山から、ちらりと話を聞かされたと言った。
「わたしも兵頭さんのことが気になったからね。それとなく谷山くんに聞いてみたの。そしたらね、田舎のおばあちゃんが倒れたみたいだって。谷山くん、ここ何日か兵頭さんの顔を見てないから、もしかしたら、おばあちゃんの所へ行ってるのかもしれないって」
わたしは驚いた。久実のおばあちゃんと言えば、あの夕日の言葉を久実に語った、久実が大好きなおばあちゃんだ。わたしもいつか会ってみたいと思っていた、あのおばあちゃんが倒れたなんて、とても他人事には思えない。ましてや久実にすればこれは一大事だ。
「おばあちゃん、大丈夫かなぁ?」
わたしが心配すると、早苗は明るく言った。
「きっと大丈夫だよ。うん、絶対大丈夫!」
早苗も久実のおばあちゃんのファンだった。わたしを安心させるみたいに喋ってるけれど、本当はそうやって自分を安心させようとしているのだろう。
久美やおばあちゃんのことは心配だけど、ここにいてはどうすることもできない。それでわたしは話を変えて、自分が死にかけていた間に経験したことを早苗に話した。
早苗は半分開けた口を閉じるのを忘れたまま、わたしの話に聞き入っていた。でも、途中で思い出したようにメモをバッグから取り出すと、わたしが話す生き物たちや、世界の様子を懸命に書き留め出した。
わたしが話を終えると、いつかこの話を漫画にさせて欲しいと早苗は言った。わたしは喜んで承諾した。
このメモは宝物だと言って、早苗はメモをバッグに仕舞った。それから早苗は自分の両方の手のひらを見つめ、その手で自分の身体を抱いた。
「わたし、今の今までこの身体が自分だって思ってた」
早苗は自分の身体に、いつも一緒にいてくれてありがとう――と言った。
早苗って本当に素直な子だなって、わたしはうれしくなった。
早苗に刺激されて、わたしも改めて自分の身体に感謝して、大好きだよと伝えた。早苗は身体の中が温かくなった気がすると言ったけど、わたしも同じだ。きっと風船たちが喜んでくれているのだろう。
早苗は人差し指で鼻を押さえながら、それにしても――と言った。
「白鳥さんが見た光って、何だったんだろう?」
それはわたしも考えていたことだ。天使だろうか、本当の神さまだろうかなどと、二人で言い合ったけど、結局、答は出て来なかった。
「わたしも白鳥さんみたいな経験がしてみたいなぁ」
早苗が羨ましそうに言った。
「死にかけたいわけ?」
わたしが笑いながら言うと、早苗は首を横に振った。
「そうじゃなくて、不思議な体験がしてみたいなって思っただけ」
「わたし、思うんだけどね。あの光はわたしに大切なことを思い出させてくれたけど、それは、わたしが好い加減なことばっかりしたまま死にそうになったからだよ。もし、わたしがいろんなことに感謝することを忘れないでいたら、自分がこの身体の神さまだってことを覚えていなくても、あの光は出て来なかったと思うんだ」
「どういうこと?」
「つまりね、本当に思い出すべきことっていうのは、何に対しても感謝の気持ちを持つってことなのよ。感謝できるってことは、相手とのつながりを感じてるってことでしょ? それは相手にとっても自分にとっても幸せなことなのよ。わたしはその幸せがわからなくなってたから、そのことを光の存在が思い出させてくれたって思ってるんだ」
「だけど、わたし、光の存在に会ってみたいな」
「いつか会えるよ。すぐには会えなくてもね、早苗の光の存在は、いつでも早苗の傍にいてくれてると思うよ。それで、つらいことがあってもね、早苗がそれを乗り越えるのを、じっと見守ってくれてるのよ」
早苗はわたしの顔をじっと見つめて言った。
「何だか白鳥さん、前とずいぶん変わったみたい」
「変わったのよ。何も知らなかったわたしから、いろいろ学んだわたしに変わったの」
わたしは自分が成長したと自覚していた。物事を一段高い所から見ているような気分だった。以前ならそれを得意に思っただろうけど、何故か今は特別なことに思えない。
夕方になると、母と兄貴が来てくれた。
これが来てたよ――と母は封筒をわたしに手渡した。表にはわたしの名前と住所が書かれ、裏には久美の名前があった。家に届いたのは一昨日の金曜日だったそうだけど、持って来るのを忘れていたらしい。
わたしは急いで封を開けた。中には手紙が入っていた。
手紙はわたしを気遣い心配するものだった。谷山から事情を聞かされて驚いたことや、わたしの家を二度訪ねたけれど、会うことができなかったことも書かれていた。
わたしが真弓たちから吊し上げられたことを、久実は自分のせいだと悔やんでいた。わたしが久美と友だちになったから、真弓たちとの関係こじれて、こんなことになったと久美は考えていたらしい。
わたしが重症の肺炎になったと知ってから、久実はわたしが元気になるよう、毎日祈り続けてくれていたそうだ。でも、おばあちゃんが突然倒れて危篤状態になったので、わたしの回復を確認できないまま、母親と二人で愛媛へ戻ることになったとあった。
今は新幹線の中にいるので、おばあちゃんの状態はわからないけど、おそらくだめなのではないかと久実は書いていた。この文面を見ると、悲しそうな久実の顔が目に浮かぶ。
久実はわたしの見舞いをできないことを詫び、この手紙が届く頃には、わたしが回復に向かうと信じているとあった。でも本当は不安と心配でいっぱいに違いなかった。
手紙の最後の方には、自分なんかを親友と言ってくれて、素敵な絵まで描いてくれたことを感謝してるし、このことは死んでも忘れないと綴られていた。読んでいて、わたしは何だか嫌な気持ちになった。
春花、今までだんだんありがとう――これが締めくくりの言葉だった。この言葉に、わたしはひどく違和感を覚えた。これは感謝を示しつつ、別れを示唆しているように見える。久実はわたしが助からないと思ったのだろうか?
直接連絡を取って、肺炎がよくなったことや、学校へ戻ることなどを、わたしは久実に伝えたかった。だけど、久実はわたしと同じで携帯電話を持っていない。久実のおばあちゃんの家の住所も知らないから、連絡の取りようがない。
「その子、あなたが仲よくしてた子でしょ?」
わたしが手紙を読み終えるのを待って、母が声をかけた。
わたしは母に手紙を見せて、久美がわたしのことで自分を責めているから、何とかして連絡を取りたいと訴えた。だけど母には、久実が戻るまで待つしかないと言われた。
兄貴に意見を求めても、どうしようもねぇだろ?――とこっちも素っ気ない。でも、そう言いながら、手紙を回された兄貴は、封筒の切手に押された消印を確かめた。
「伊予灘郵便局って書いてあるな。その子は、この郵便局の近くにいるのかもな」
兄貴の言葉は一筋の光明だった。わたしは退院したら、その足で四国へ行くと言った。すると、母がすかさずわたしの言葉を否定し、兄貴をにらんだ。
「翔ちゃん、余計なこと言わないでちょうだい! やっとこの子が退院できて、学校にも戻れるようになったのに、何言ってんのよ!」
思いがけず母に叱られた兄貴は、口を尖らせて言った。
「オレはただ手紙の消印が、伊予灘郵便局って書いてあるって言っただけじゃん。何も春花にそこへ行けって言ったわけじゃねぇよ」
「そこへ行けって言ってるのと同じでしょ? 屁理屈こねないの!」
「お母さん、お願い! わたしを四国へ行かせて!」
わたしは母に頼み込んだ。だけど、母の態度は変わらない。
「春ちゃんね、あなた、今回のことで、どれだけみんなに心配かけたのかわかってる? あなた、もうちょっとで死ぬとこだったのよ?」
「それはわかってる。でも、このままだと久実が危ないの!」
「何が危ないのよ? おばあちゃんが危篤だから、お母さんと一緒に四国へ戻っただけでしょ? いずれは帰って来るんだから、そのときまで待ってればいいことじゃない!」
母の言うことは尤もだ。でも、この手紙には文字には表れていない、久実の想いが書かれてある。それが母にはわからない。
わたしは早紀たちや早苗が言ったことも気になっていた。久美が前の学校でいじめ問題を引き起こしたなんて、わたしはこれっぽっちも信じていない。だけど、前の学校で久美に何かがあったのだとは思う。そして今回のことだけでなく、そのことも久美を苦しめているように思えていた。
母さんの言うとおりだな――と、兄貴は他人事のように言った。
わたしは兄貴から手紙を奪い取ると、胸に抱いて泣いた。妹の涙にうろたえたのか、兄貴は言い訳をした。
「さっきの伊予灘郵便局ってさ、その子のばあちゃんの家の近くの郵便局とは限らないよな。ひょっとしたら、大阪とか松山の郵便局かもしれないぜ」
「そんなの、調べてみないとわかんないじゃないの!」
「そりゃ、そうだけどさ」
わたしの剣幕に兄貴は口ごもった。でも、母は頑として聞く耳を持ってくれなかった。
「とにかくお母さんは許しませんからね。そんな病み上がりの体で四国へ行くだなんて、とんでもない話よ。それにあなたが元気だったとしても、今の家にはそんなお金はありません。わかったら、この話はおしまい。今晩ちゃんとご飯食べないと、退院の話だって取り消しになっちゃうからね!」
わたしには反論できなかった。兄貴も黙って肩をすくめただけだ。わたしはうなだれるしかなかった。
不吉な夢
わたしは暗がりの中にいた。久実がスポットライトで照らされたように、闇の中に浮かび上がって立っている。
春花、ごめんな――久美は泣きながらわたしに謝った。
「久美は悪くない! 久美は何も悪くないんだからね!」
わたしはそう叫びながら、久美のそばへ駆け寄ろうとした。だけど、どういうわけか身体が重くて思ったように動けない。
「二枚舌!」
誰かの声が聞こえた。その瞬間、後ろから何かがヒュンと、わたしの頭のすぐ左を通り過ぎた。それは矢だった。
久実を見ると、久美の右の胸に一本の矢がぐさりと突き刺さっていた。
「久美!」
わたしは久美を助けようとしたけど、やはり身体が異様に重くて動けない。
よろけて倒れそうになった久美は、刺さった矢をつかみながら何とか踏みとどまって立っている。わたしに向けられた久美の目は、許しと救いを求めているように見えた。
「疫病神!」
再び声が聞こえた。わたしの頭の右をかすめた別の矢が、久美の左胸に刺さった。久美は苦しそうに口を開いたまま、わたしに何かを言おうとしていた。しかし、二本の矢のせいで声が出ないようだ。
わたしは必死に久美の元へ行こうとした。だけど焦れば焦るほど、身体はどんどん重くなる。足だけでなく腕までもが、おもりをつけられたように重い。まるで見えない何かに身体が押しつぶされそうだ。
久美は両手で胸に刺さった矢をつかみ、よろけながらつぶやくように言った。
――春花……、こがぁな、うちの……、友だちになってくれて……、ありがとう……。
「この偽善者め!」
罵りと同時に、わたしの頭上をかすめて矢が飛んだ。矢は久美の額を貫き、久美は後ろへゆっくりと倒れていった。
「久美!」
わたしは大声で叫んだ。久美は倒れたまま動かない。
わたしは矢を射た者を見定めようと、後ろを振り返った。だけど後ろは真っ暗闇で、人の姿は見えない。ただ、久美を馬鹿にして笑う大勢の声が遠くの方で聞こえた。
「お前たちは何だ、この卑怯者! そんな所でこそこそしてないで姿を見せろ! 姿を見せて、わたしと戦え! わたしが久美の仇を取ってやる!」
わたしは闇に向かって怒鳴った。でも相手にはわたしの声が聞こえていないのか、わたしには何の反応もないまま、久美を嘲笑い続けている。
わたしは身体の向きを戻すと、久美の傍へ行こうとした。まだ身体は重いけど、さっきよりは幾分動けるようだ。
わたしはカメが移動するみたいな速度で、じわじわと久美の方へ向かった。だけど、どれだけ進んでも、久美との距離は縮まらない。そうしているうちに、久美の身体は闇の中に溶け込むように消えていった。
「久美!」
わたしは叫びながら目を開けた。辺りは真っ暗だけど、さっきの闇とは違うようだ。身体はやっぱり動きにくかったけど、重いと言うのではなく、何かが身体に巻きついているみたいだ。その何かと格闘しているうちに、わたしは自分が病室のベッドで寝ていたことを思い出した。わたしは自分で布団を身体に巻きつけていたらしい。
闇の中で四苦八苦しながら、わたしはようやく布団を身体から引き離した。
急いで枕元の明かりをつけると、ベッドを囲むカーテンが、暗がりの中に照らし出された。暗い病室の中で、ここだけが別の空間のように見える。
今のが夢だったとわかったことで、わたしは気持ちがいくらか落ち着いた。それでも完全に落ち着いたわけではない。本当に久美が殺されたような想いが残っていて、胸の中では今も怒りと悲しみが渦巻いている。
それにしても嫌な夢だった。あんな不吉な夢なんか二度と見たくない。でも一方で、今すぐ夢の中に戻って久美を助けたいとも思っていた。
どうしようもない憤りとやるせなさで、わたしは拳で枕を何度もたたいた。それで少しは怒りが収まると、どうしてあんな夢を見たのだろうという想いが浮かんで来た。
満里奈たちや早苗から聞かされた久美の話や、久美の手紙の文面に抱いた不安が、こんな夢を見させたのは間違いない。それでも、本当にそれだけが夢を見た理由なのだろうかと、わたしは考えた。と言うより、わたしには今見た夢が、久美が送ってよこした念のような気がしてならなかった。
久美と谷山の関係を疑ったとき、久美はわたしから遠い存在になっていた。だけど、今は改めて久美を近くに感じている。そう、久美とわたしは特別な関係なんだ。
前はなんとなくそう感じていた。だけど、今は絶対そうだと確信している。
光の存在によって体験させられた様々なことが、わたしを大きく変えた。わたしは以前のわたしではない。わたしは自分というものが、みんなが考えているようなものではないと理解しているし、生まれる前というものがあったのだと知っている。
わたしがお母さんの子供になったのも、偶然そうなったんじゃない。生まれる前から、そう約束していたからだ。それはおそらく、お父さんや兄貴との関係においても言えることだろう。同じように、わたしと久美は生まれる前から、親友になる約束があったのだと思う。
いや……違う。約束なんかじゃない。もっと深くて強い関係だ。初めからずっと一緒にいたような、そんな感じがする。それは有り得ないことではないだろうし、きっとそうだと強く感じている。だからこそ、久美の想いがあんな夢となって、わたしに伝わったのに違いない。
だとすれば間違いない。久美はわたしに助けを求めている。わたしに謝りながら、助けてって叫んでいるんだ。
わたしは居ても立ってもいられなくなった。でも今は入院中だし、久美の居場所もわからない。お母さんはわたしが久美を探しに行くことを許してくれないし、探しに行かせるお金もないと言った。
不安はどんどん募っていくけど、今のわたしには何もすることができない。だけど、このままでは本当に久美がどうにかなってしまいそうな気がする。あぁ、どうすればいいんだろう。
しばらく悶々とした気持ちで座っていたけど、わたしはもう一度横になって、枕元の明かりを消した。途端にカーテンに仕切られた空間は、再び闇の一部になった。
わたしは真っ暗な天井を見つめながら、あの光の存在に訴えた。
「お願い、力を貸して! 久実が危ないの!」
きっとあの光の存在なら何とかしてくれる。そう期待して訴え続けたけど、光はちっとも現れてくれない。こちらの都合で呼んでも、だめなのだろうか?
わたしは光の存在のお陰で、自分と身体の関係や家族の愛を思い出し、自分自身を受け入れることができた。だから、もう光の存在は現れる必要がなくなったのだろうか?
あるいは久実は他人だから、久実の問題は久実が自分で解決しないといけないのだろうか? それとも、久実には久実自身の光の存在がいるということなのか?
たとえそうだとしても、何とか言ってくれたらいいのにと思う。黙ったまんまなんて、久実のことなんかどうでもいいみたいだ。
でも、わたしはすぐに思い直した。あの優しさといたわりに満ちた光の存在が、久美のことをどうでもいいだなんて思うわけがない。
それに、わたしと久美は生まれる前から一緒だった。それは光の存在だってわかっているはずだ。だから、光の存在が久美に対して知らんぷりをするとは思えない。だけど、だったらどうして出て来てくれないのだろう?
わたしは自分が早苗に言ったことを、ふと思い出した。
つらいことがあっても、それを乗り越えるのを光の存在は見守っている。そうか、今は光の存在は、わたしたちのことを見守っているってことか。それは逆に考えれば、今の状況はわたしが一人で乗り越えられるということだ。
なるほど、そうなんだ。わたしは納得してうなずいた。普通に考えれば、乗り越えられるはずがないように思えるけど、きっと何かいい方法があるに違いない。
わたしは懸命に考えた。だけど、やっぱりいい考えが浮かんで来ない。
そもそも久美がどこにいるのかを知らないし、一人で四国へ行くためのお金も手段も持ち合わせていない。
体力もない病み上がりのわたし一人に何ができるのか。何にもできない。そう、わたしは無力な役立たずだ。
気持ちが泥沼に沈んで行きそうになったわたしは、大きく首を横に振った。だめだ、だめだ。これじゃあ、前のわたしと同じだ。
あの幼いわたしが同じように落ち込んだなら、絶対無理だからあきらめなさいって言うのか。そんなことを言うはずがない。きっとうまく行くから、あきらめちゃだめよって言うはずだ。
――だけど、どうすればいいの?
闇の中から、幼いわたしが途方に暮れた目をわたしに向けている。
「どうするかは、これから一緒に考えよう。とにかくあきらめないこと。それに、わたしたちには相棒がいるでしょ?」
わたしの気持ちが伝わったのか、幼いわたしはにっこり笑うと姿を消した。
わたしは身体を起こすと、また枕元の明かりをつけた。再びベッドの上が闇から切り取られて別の空間になった。
わたしはベッドの横にある棚の引き出しを開け、中から手鏡を取り出した。これは母が家から持って来てくれた手鏡だ。
わたしは鏡に自分を映した。そこに映っているのはわたしだけど、正しく言えば、これはわたしの身体だ。鏡の中のわたしは、にっこり微笑んでいる。
――あなたが望むようにして下さい。わたしはいつでも一緒です。
身体のわたしが囁いてくれているような気がした。わたしはうれしくなって泣きそうになった。
そうよ、あなたはわたしの一番の相棒なの。わたしの身体さん。あなたがいる限り、わたしは何でもできる。できないとすれば、それは自分がやろうとしないから。自分でやると決めたなら、あなたはわたしに従って動いてくれる。
わたしは自分の身体を抱いて、ありがとう――と感謝した。失いそうになっていた自信が再び戻って来た。
きっとできる。きっと久美を助けられる。わたしの胸に希望が広がった。
わたしは改めて考えた。でも、漠然と考えるのではない。自分がどうしたいのかを整理して、そこで何が問題なのかを見極めるんだ。問題をはっきりさせなければ、答えは見えて来ない。
わたしの望みは、久実に会いに四国へ行くことだ。向こうでどうするかは別に考えることにして、まずはどうやって四国へ行くかだ。
わたしは腕組みをして考えをめぐらせた。だけど、どんなに気合いを入れ直したところで、やっぱり問題はお金だ。お金がないと始まらない。
自信を取り戻したはずのわたしは、再び心が折れそうになった。そのとき、どういうわけか棚の上に載せてあった本が、ばさっと床に落ちた。ちゃんと載せておいたのにと文句を言いながら、わたしはベッドから手を伸ばして、落ちた本を拾い上げた。
明かりの下に置かれた本は、クイズの本だった。わたしが退屈するだろうと、兄貴が買ってくれた物だ。
わたしは何を考えるでなく、その本を手に取ってページをめくった。中には、いろんな面白い問題や変わった問題が載っている。
わたしが問題が解けずに本を放り出すたびに、兄貴はわたしができなかった難問を難なく解いてみせた。そのときの得意げな兄貴の顔が目に浮かぶ。
久美のことを心配しているはずなのに、頭の中で兄貴が偉そうに喋り始めた。
――お前な、諦めるのが早えんだよ。どんな問題だって、必ず答はあるもんだぜ。
病み上がりの妹を励ますのが兄だろう。なのに、うちの兄貴は妹をからかう対象としか見ていない。
思い出したいわけじゃないのに、思い浮かんだ腹立たしい記憶はなかなか頭から離れてくれない。わたしは今四国へ行く方法を考えているんだぞ。邪魔すんなよ。
わたしは兄貴を追い出そうとして頭を振った。でも、頭の中で兄貴は同じ言葉を繰り返す。
――お前な、諦めるのが早えんだよ。どんな問題だって、必ず答はあるもんだぜ。
あぁ、うるさい、うるさい! そんなことはわかってるってば。わかってるけど、わかんないの。お兄ちゃんみたいに答えがすぐにわかったら、誰も苦労なんかしません! わたしとお兄ちゃんとは違うの!
心の中で兄貴に反論しながら、わたしはふと思った。兄貴には答えがわかって、わたしにはわからない。同じ兄妹なのに何が違うんだろう?
兄貴は頭がよくて、わたしは馬鹿だから。違う、そうじゃない。それは問題が解けない言い訳だ。わたしと兄貴は何が違うのか?
――発想の転換だって。こうに決まってるっていう思い込みを捨てるんだよ。
頭の中で、兄貴がわたしに説教をする。だけど、それはクイズの話だ。今わたしが抱えている問題は、そんな遊びじゃない。お金も何もない病み上がりの中学生に、何ができるかっていう真面目な話だ。
妄想の中の兄貴に文句を言いながら、でも、これだって思い込みかもしれないと、わたしは思った。考えてみれば、思い込みに遊びも真面目もないだろう。
わたしは座り直すと、もう一度考えてみた。
今の問題が解決できないのは、わたしの思い込みのせいだとすれば、何が思い込みなんだろう? だって、お金がなければ何もできない。それは常識だ。
だけど、それこそが思い込みじゃないのかと、わたしは考え直した。
よく考えれば、世の中にはいろんな人がいる。お金がなくたって、すごいことをやってのける人だっていた。でもそんな人は特別であって、自分にはそんなことは無理だと思ってた。そもそも自分もそんなことをやってみたいと考えることもなかった。
でも、今はお金がなくても四国へ行けるなら、それがどんなことだって挑戦してみたいと思ってる。自分には無理だなんて考えるつもりもない。
「お金がなくても四国へ行ける。そんなのは絶対無理だって思ってたけど、これは思い込みだ。そうなんだ。お金がないと何もできないっていうのは、わたしの勝手な思い込みなんだ。うん、きっとお金がなくても四国へ行く方法はあるし、それを探せばいいんだ」
わたしはうなずいた。何だか、わたしの前に一筋の光が降りて来たみたいだ。後ろで光の存在が笑っているような気がする。
そうだ。最悪どうしようもなかったら、歩いて行けばいい。絶対に行けないなんて有り得ない。
だけど、それは最悪の場合だ。それに歩くのは時間がかかる。お金をかけずにもっと速く行ける方法はないだろうか。
少し考えて、そうだとわたしは思った。ヒッチハイクだ。
いつだったかテレビの番組で見たことがある。お金がほとんどない外国人が、ヒッチハイクで旅行をしていた。もちろん、そんな簡単に車を出してくれる人はいないけど、それでもゼロじゃない。待っていれば必ず親切な人が現れて、車に乗せてくれるんだ。そればかりか食べる物を分けてくれたり、家に泊めてくれたりもしていた。
これだ、四国へ行ける!――わたしははしゃいだ。思わず大きな声を出してから、ここが病院だと思い出し、わたしは慌てて両手で自分の口を押さえた。
幸い部屋がわたし一人の貸し切りになっていたからよかったけど、隣の部屋の患者さんは起こしてしまったかもしれない。
その患者さんに心の中でごめんなさいと謝りながら、わたしは喜びを抑えきれずに、ベッドに座ったまま跳びはねた。
ヒッチハイクなんか恥ずかしいとか、乗せてもらえないかもという考えは、微塵も浮かんで来なかった。
事情を説明すれば、きっと助けてくれる人はいるだろう。途中までだって構わない。そこからまた親切な人を探せばいいんだ。でも、どうせならトラックがいいかも。トラックだったら遠い四国まで一気に運んでもらえるかもしれない。
目指す場所は、手紙の消印にある伊予灘郵便局だ。伊予の海という意味だろうから、久実のおばあちゃんの家がある所だと思う。郵便局の人に聞けば、きっとおばあちゃんの家を教えてもらえるに違いない。
わたしは気がついた。これまで自分は何もできないと思っていた。でも、それは本気でやろうとしていなかっただけなんだ。
久美については、わたしは本気だ。だから何があっても、わたしは久美の所へ行くつもりだし、絶対に行ける。行ってみせるから。
問題はお母さんだ。お母さんがどれほど、わたしを愛してくれているのか、わたしはよくわかっている。お母さんを心配させたり悲しませたりすることは、何より苦痛だ。
学校で何があったのか、これまでわたしが何をして来たのか、わたしは何もかもお母さんに話した。だけど、お母さんはわたしを叱ったりせず、わたしの気持ちがわからなかったことを謝ってくれた。
お母さんが四国行きを反対するのだって、わたしのことを心配しているからだ。そんなお母さんを裏切るように思えることだけが、わたしを躊躇させた。
でも、お母さんならわかってくれる。久実が本当に危ないということが、おかあさんは理解できていないだけだ。それがわかれば、お母さんはわたしを許してくれるだろう。お母さんはそういう人だ。
わたしはお母さんを信じている。それに万が一にも久美に何かがあったなら、お母さんまでもが悲しみに打ちひしがれるに違いない。
わたしが久美を助けに行くことは、お母さんを助けることにもなる。わたしは大きくうなずいた。
退院して家に戻ると、わたしは真っ直ぐ自分の部屋へ向かった。部屋の中は、倒れたときのまま時間が止まっているような感じだった。
わたしは自分が倒れていた場所に立ち、あのときのことを思い出していた。
あのとき、わたしは自分の身体を離れて宙に浮かんでいた。そして、下で倒れている自分の身体に、すべての責任を押しつけて悪態をついた。
どうしてあんなひどいことができたのか。わたしは自分の身体を両腕で抱くと、ごめんね――と言った。
身体が温かくなった。身体のわたしが、わたしに愛を送ってくれたのだろう。同時に、うれしそうな風船たちが、イイノ!――と叫ぶ声が聞こえる。
みんな元気? わたし、みんなのこと大好きだよ。これからもずっと、みんなのこと大切にするからね。
風船たちや手毬たち、クラゲたちが楽しそうにわたしの周りを泳いでいる。真っ黒になっていた虹の森も復活し、わたしが呼吸をするたびに、美しい七色の光に輝いている。
枯れ草だらけだった原っぱも、今は一面にきれいな花が咲き乱れ、辺りは七色のホタルが飛び交っている。
わたしを舐めた壁も忙しそうに舌を動かし、赤い大蛇たちも力強く動いている。だってほら、わたしはこんなに動いているんだもの。
そして、あの大きな球体の大蛇たちも、今は喜びに満ちている。あの大蛇たちに咬みついている白いヘビは、わたしの愛を大蛇たちに伝えているの。それを大蛇たちはわたしの世界中に広めている。
みんな、大好きだよ。みんなのこと、いつまでも愛してるからね。
わたしの声に応えるように、わたしの身体のすべてが活き活きと活動しているのがわかる。あぇ、生きているって何て有り難くて素晴らしいことなんだろう。わたしは一人じゃない。みんなが支えてくれているんだ。
そうだ、わたしはもう一つ大切なことを思い出した。
わたしの喜びは誰かが喜ぶこと。だからこそ母を喜ばせたいと思っているし、久美や早苗のことも喜ばせたい。わたしがこの世界に生まれたのは、みんなを喜ばせたいからだ。
自分に何ができるのかはわからない。でも、ちょっとしたことで構わない。相手が喜んでくれさえすれば、それでいいんだもの。すごいことや目立つこと、認められたり褒められることが目的じゃない。人を喜ばせることが目的なんだ。
それはきっと久美だって同じだろう。久美の無事を確かめられたなら、わたしはすべてを久美に話し、喜びを広げる計画を一緒に立てよう。考えただけでわくわくする。でも、そのためにまずやるべきなのは、久美の所へ行くことだ。
夕食はわたしの退院祝いで、赤飯やら鯛やらとずいぶんご馳走だ。普段、倹約ばかりしている母だけど、この日だけは奮発してくれたみたい。
それにこの日は、さすがの兄貴もわたしに遠慮して、先にご馳走に手をつけようとはしない。そんな風にできるんだったら、最初からそうしろよな。
母はわたしが元気になったことを本当に喜んでくれていた。そんな母を再び心配させるのは、やはり心苦しい。でも、もう後戻りはできない。母と兄貴が眠ったら、わたしは家を忍び出るつもりだ。
四国なんか行ったことがないし、愛媛のこともわからない。唯一の頼りは久美の手紙にあった消印の郵便局だけだ。そこにさえ行けば何とかなる。わたしはそう考えていた。
父はわたしが退院する前に仕事に戻ったので、今は母と兄貴とわたしの三人だけのお祝いだ。それでも父は電話をくれて、今後のことは何でも力になるから、いろいろ深く考え過ぎないようにと言ってくれた。
わたしは以前とは違う居場所を手に入れたうれしさでいっぱいだった。その一方で、頭の中は四国へ行くことばかり考えていた。
いつから学校へ戻るかという話になると、今週は中学校も高校も中間テストだと、兄貴が言った。早紀たちもそんなことを言っていた。それで学校への復帰はテストが終わった来週に決まった。兄貴はテストをしないで済むことを喜んでくれたけど、半分はからかっているのだろう。母は笑いながら服の袖で目頭を押さえている。
もしまた学校で嫌なことをされたなら、オレが怒鳴り込みに行ってやるからな――と兄貴は言ってくれた。兄貴も前と比べると、とても優しくなった。
でも、今はクラスのみんながわたしを待ってくれている。そう話したら、兄貴は安心したし、母もうれしそうだった。
真夜中が過ぎ、母が寝たと思われる頃、わたしは向かいの部屋にいる兄貴の様子を窺った。
わたしと兄貴の部屋は二階にある。階段を上がった突き当たりの右がわたしの部屋で、左が兄貴の部屋だ。
扉越しに兄貴の部屋から音楽が聞こえて来る。兄貴は夜更かしするのが日常だ。特に今は試験勉強をしているはずだから、いつもより遅くまで起きているかもしれない。
「もう、勉強なんかやめて早く寝ろよな」
わたしは小声で兄貴につぶやき、ベッドの上に横になった。
下着の着替えなどを詰め込んだリュックは用意してある。母と兄貴に当てた手紙も書いた。出かける前に、食堂のテーブルに置いて行く予定だ。
準備は万端でいつでも出られる。だけど、出発は兄貴が寝るまで待たねばならない。兄貴に見つかれば計画は台無しになるからだ。
わたしは寝転びながら日本地図を広げた。スマホもパソコンもないわたしは、兄貴に適当なことを言って、伊予灘郵便局の場所を調べてもらった。
思ったとおり郵便局は愛媛県の海辺で、松山市より西の方だ。おそらくその近くに久美のおばあちゃんの家がある。
わたしは愛媛までの道のりを指でたどり、途中にある大きな街の名前を頭にたたき込んだ。
郵便局を調べてもらったとき、わたしが何か企んでいるんじゃないかと、兄貴は訝しんでいる様子だった。でも、わたしに何ができるのよ!――とわざと反発したら、それはそうだと兄貴も納得した。
ほんとは何だってできる。それをできないふりをするって結構大変だ。
ふと枕元の時計を見ると、もう一時を回っている。わたしは部屋の扉の所へ行って耳を澄ませた。すると、兄貴の部屋からまだ音楽が聞こえて来る。まだ起きてるみたいだ。
あぁとわたしは頭を掻きむしり、さっさと寝ろよと小声で兄貴に悪態をついた。
それからまたベッドに戻り、兄貴が早く寝るようにと、いらいらしながら祈っていたけど、ひょっとして――と急に心配になった。
もし兄貴が音楽を流したまま机に突っ伏して寝ていたなら、わたしは家を出ることができずに朝を迎えることになる。それでは計画は失敗だ。
日中にヒッチハイクをしようとしても、警察に見つかって補導されるような気がする。やるなら今しかないのだけど、兄貴が寝たのがわからなければ、計画を実行できない。
わたしは枕に顔を押しつけて、うーっと唸った。そして、そのままうとうとしてしまったらしい。はっと目を覚ましたわたしは、しまったと思って飛び起きた。時計を見ると、もう二時になる。
わたしはベッドから飛び起きると、そっと扉の傍へ行って耳を近づけた。兄貴の部屋の音楽は――止まってる?
わたしはそっと扉を開けて確かめた。やっぱり兄貴の部屋からは何も聞こえない。
――やった!
わたしは心の中で叫びながら小躍りをした。いよいよ出発だ!
用意したリュックを背負ったわたしは、二人への手紙を手に持った。それから改めて兄貴の部屋の様子を確かめたけど、何も聞こえないし、中の明かりも漏れ出ていない。間違いなく兄貴は寝たようだ。
わたしは部屋の電気を消すと、代わりに階段の電気をつけた。すると、階段のスイッチがパチンと鳴った。いつもなら気にならない音が、やけに大きく響き渡る。
わたしは慌てて電気を消した。すると、またもやパチンと音が鳴り、わたしは声を殺して呻いた。
暗闇の中で、わたしは兄貴が起きなかったかと物音を探った。息を殺し、同じ姿勢のまま待ったけど、何も音は聞こえない。よかった、兄貴は目を覚まさなかったみたいだ。
ほっとしたわたしは、もう一度電気をつけようとした。でも、音が鳴るすんでのところで、スイッチを押すのをいったんやめた。それから音がならないよう、慎重にゆっくりとスイッチを押した。
それでも少しは音が鳴ったけど、さっきみたいな音じゃない。一応は聞き耳を立てて兄貴の様子を確かめ、それから静かに階段を下りた。すると、今度は階段がギシギシ音を立てる。古い家だからあちこちが軋むんだけど、このときだけは静かにして欲しかった。
お兄ちゃんが起きるじゃないの!――と心の中で階段に文句を言ったが、やっぱり階段は踏まれるたびにギシリと音を出す。
わたしは階段が軋まないよう、できるだけ階段の端っこを踏むことにした。うん、今度は大丈夫みたい。音はほとんどならないぞ。
喜び勇んでゆっくり階段を下りていると、がらりと上で戸が開く音がした。
背筋が凍って固まったわたしに、後ろから兄貴の声が呼びかけた。
「おい、待てよ。オレも一緒に行くからさ」
四国へ
やっぱり伊予灘郵便局の場所を調べてもらったことで、兄貴はわたしを怪しんでいたらしい。それで、わたしがトイレに行った隙に、兄貴はこっそりわたしの部屋をのぞいて、リュックや手紙を用意していたのを確かめたと言った。
部屋を勝手にのぞいたことを、わたしは怒った。だけど、一緒に四国へ行ってくれると言うから、感謝の気持ちの方が強かった。正直言えば、やっぱり一人は心細い。
でも今週は高校はテスト期間のはずだ。そのことを聞くと、可愛い妹のためだと兄貴は言った。
わたしのことなんかちっとも構ってくれなかった兄貴が、わたしのためにテストを受けないとは思えない。病み上がりのわたしを心配しているのであれば、わたしの行動を止めようとするはずだ。
本当の理由を問い詰めると、兄貴は笑いながら、先生の言葉に従っているんだと胸を張った。
先生というのは兄貴のクラスの担任で、勉強を教えるより人生を語ることに熱心なのだそうだ。よく授業を脱線しながら面白い話をしてくれるそうだけど、その先生が口癖のように言う言葉が、人生は冒険だ、冒険を恐れるな――というものらしい。
その言葉を兄貴は真面目に受け止めていたそうで、今がその冒険の時だと兄貴は強調した。だけど、これは先生が言う冒険とはちょっと違う気がする。
とは言っても、兄貴が同行してくれるのは、わたしにはとても心強かった。
兄貴はスマホを持っているからいろいろ調べられるし、いざと言うときに母と連絡を取ることもできる。また夏休みにバイトをしたお金も、結構残っているそうだ。
それに比べて、わたしが頼みにしていたのは久実の手紙だけだ。兄貴は呆れながら、どうやって行くつもりだったのかと聞いた。それで、ヒッチハイクで行こうと思っていたと答えると、兄貴の目が輝いた。
兄貴は四国まで鈍行列車で行こうと考えていたそうだけど、ヒッチハイクの方が経済的だし、何より冒険的な響きが兄貴の気を引いたようだ。
だけど頭で考えるのと、実際にやってみるのとでは大違いだった。
初めは四国へ向かうトラックは、簡単に見つかると考えていた。でもトラック自体が見つからない。仕方なく大きな通りまで出たけれど、病み上がりの身体で歩き続けるのは、かなりきつかった。
それにこんな真夜中過ぎの時間だと、トラックどころか乗用車だってめったに来ない。やっと来たと思ったら、暴走族と思われるようなやかましい音を鳴り響かせる車だった。危ないので、兄貴と街路樹の陰に隠れてやり過ごすと、あとはまた静寂だけが残った。
きれいなお月さまが煌々と照らす夜道は、寂しい冷気に満ちている。わたしが両手で身体を抱きながら肩をぶるっと震わせると、来たぞ、来た来た!――と兄貴が叫んだ。
見ると、車のライトが近づいて来る。トラックだ! わたしたちは待ち構え、トラックが近くに来ると手を大きく振って声をかけた。でもトラックはわたしたちの前を素通りした。だめかと思ってがっくりしていると、少し先の方でトラックが止まった。
兄貴はトラックの方へ走って行き、身振りを交えて懸命に運転手に訴えた。でも、なかなか反応がないようだ。
やっぱりだめかと思ったら、兄貴がわたしに向かって両腕で大きな丸を作ってみせた。信じられない気持ちで駆け寄ると、兄貴は得意げに言った。
「乗せてくれるってさ。でも四国までじゃなくて、仮眠をとるトラックが集まってる、高速道路のサービスエリアまでだって。それでいいだろ?」
「四国まで運んでやれりゃいいけどよ。あいにく目的地が違うんでな。四国行きのトラックがいそうな所まで乗っけてってやるよ」
助手席の窓越しに声をかけてくれたのは、運転席に座ったかなり年輩のおじさんだ。結婚が遅かったそうで、わたしたちと同じ年頃の子供がいるんだって。
おじさんが荷物を片づけてくれた助手席に、兄貴と一緒に乗り込むと、そこまで友だちを想う子供も、今どき珍しいとおじさんは言った。
また兄貴のことも、こんな妹想いの兄貴はいないと褒めてくれた。それで気をよくした兄貴は、担任の先生に冒険をしろと言われた話をした。だけど、それはちょっと違うかもな――と、おじさんに笑われてしまった。
トラックを走らせながら、おじさんはこれまでの苦労話や家族の話を聞かせてくれた。移動の時間は結構あったと思うけど、話を聞いていると、あっと言う間にサービスエリアに着いてしまった。
おじさんはわたしたちをトラックから降ろすと、四国へ向かいそうなトラックを、自分も降りて探してくれた。
でも、残念ながら四国行きのトラックは見つからなかった。それに最近は三人乗りのトラックは少なくなっているらしくて、わたしたちを乗せられる上に、西へ向かうトラックを探すのは一苦労だった。
それでも、大阪までなら運んでもいいと言ってくれる運転手さんが見つかった。もちろんトラックは三人乗りだ。それで、わたしたちは大阪で別のトラックを探すことにして、そのトラックへ乗せてもらうことになった。
親切なおじさんは、わたしたちが新しいトラックに乗り込むのを確かめると、がんばれよ――と言って自分のトラックへ戻って行った。
兄貴と一緒にお礼を言って手を振ったわたしは、おじさんの親切に感激しながら、やってみるものだと心の中で自分の行動を称賛した。
兄貴も興奮した様子で、冒険の出だしに満足しているようだ。
「それじゃあ、トラックを動かすぞ」
わたしたちに声をかけた新たな運転手の人は、さっきのおじさんより若かった。歳を尋ねてみると、四十五だそうだ。
この人もわたしたちの話に驚きながら、無茶なことをするもんだなと笑っていた。
兄貴はこの人にも担任の先生に言われた冒険の話をした。だけどやっぱり、ちょっと違うんじゃないかと言われてしまった。
大阪までどのくらいかかるのかと尋ねると、かなり遠くて何時間もかかるらしい。それで、向こうに着いたら起こすから、それまで眠ればいいと運転手さんは言ってくれた。
そんなことは申し訳ないと思ったけど、わたしも兄貴もいつの間にか爆睡したようだ。気がついたら、外はすっかり明るくなっていた。
兄貴が寝ぼけ眼をこすっていると、スマホが何度か鳴ってたぞ――と運転手さんは言った。
兄貴はごそごそと荷物からスマホを取り出すと、履歴を見て裏返った声を出した。
「母さんだ!」
兄貴は慌てて母に電話をした。呼び出しの音が聞こえ、すぐに母が出た。
兄貴は謝ろうとしたけど、その前に母の怒鳴り声がわたしの耳にも飛び込んで来た。
兄貴が亀みたいに首をすくめ、わたしも思わず同じ仕草をすると、運転手のおじさんは噴き出した。
兄貴は懸命に母をなだめつつ、兄妹で家を出たことを詫びた。それで、絶対に危ないことはしないと言って、母を安心させようとした。
母はしばらく怒り続けていたけど、どうしようもないと諦めたのか、わたしの声を聞かせるようにと兄貴に言った。
わたしが恐る恐る電話を替わると、母は心配そうな声で、わたしの体調を聞いた。
わたしは元気なことを伝え、心配をかけたことを謝った。
母はとにかく身体に気をつけて、頻繁に連絡して来るようにと言った。それから、運転手さんにお礼を言いたいと言ったけど、運転手のおじさんは照れたような顔で、運転中だからと電話に出るのを断った。
トラックがサービスエリアに停まると、自分の役目はここまでだと、運転手のおじさんは言った。ここなら四国行きのトラックも結構あるらしい。わたしたちが降りると、運転手のおじさんも次のトラックを一緒に探してくれた。そうして何台かのトラックを回ったあと、見つかったのは何と愛媛のトラックだった。しかも運転手は女性だ。
わたしたちは運転手のおじさんに、何度もお礼を述べて別れた。そのあと女性の運転手さんに挨拶をして、次のトラックへ乗せてもらった。
運転手さんは越智という人だった。越智さんはまだ三十代だそうで、独身だけどバツイチでもあると、カラカラ笑いながら話してくれた。
「これからの女は何でもばんばんやって、男なんぞに負けんようにせんといけんで!」
越智さんは気合いを込めて言うと、じろりと兄貴を見た。兄貴が戸惑ったように下を向くと、また越知さんはカラカラ笑った。
「お兄さんみたいな妹想いの男の子は、女性の味方やけんな。あたしは大好きやで」
口元に笑みを見せた兄貴は頬を少し赤らめて、また下を向いた。こんな兄貴の姿を、わたしはこれまで見たことがない。
越智さんは横目で兄貴を見て、可愛いねぇ――とますますテンションが上がった。一方の兄貴はますます小さくなった。
四国へ渡るには海上の橋を通る。海の上を走るなんて生まれて初めてだ。兄貴も目の前に広がる絶景に、学校にいたんじゃこの景色は見られなかったと興奮気味に言った。
それで調子が出たのか、兄貴は越知さんにも先生から言われた冒険の話をした。すると越智さんはうなずいて、素敵な冒険だと言ってくれた。兄貴はうれしそうに笑い、そのあともずっと喋り続けた。
松山に着いたのは夕方だった。どこかで一晩明かさねばならないけれど、どうやって宿を探せばいいのかわからない。
兄貴が必死にスマホで宿を調べていると、荷物を降ろし終わった越智さんがわたしたちの所へ来て、これからどうするのかと聞いてくれた。
今の状況を正直に話すと、それならうちへ来ればいいと越智さんは言ってくれた。こんなにラッキーなことになるなんて信じられない。
驚きのあまり二人で返事もできずにいると、お兄さんのこと襲たりせんけん――と越智さんは兄貴の顔をのぞき込んだ。兄貴が慌てて、そんなことは心配してないと言うと、それじゃあ決まりと越智さんは笑った。
越智さんの家は、久美の家のような古いマンションだった。
わたしたちはリビングで寝かせてもらうことになった。わたしがソファーで、兄貴は床の上に敷いた布団の上だ。
越智さんはわたしたちに、郷土料理をご馳走してくれた。その上、温泉にまで連れて行ってくれた。
兄貴は大喜びだったけど、久実のことを思うと、わたしは心の底から楽しむことはできなかった。そんなわたしを越智さんは励ましてくれて、明日は何があるかわからないのだから、そのために身体を休めて力を貯めるのは必要なことだと言ってくれた。
「ほんじゃあ、しっかりやりや!」
翌朝、駅まで車で運んでくれた越智さんは、わたしたちを降ろすと行ってしまった。
わたしは越智さんを見送ったあとも、しばらく松山の街並みを眺めながら感慨に浸っていた。
ほんの一昨日まで、わたしは東京の病院に入院していた。それが今はここにいる。
普通に考えれば、わたしがここまで来るのは到底無理なことだった。だけど、いろんな人が力を貸してくれて、こうしてここに立っている。それがとても不思議だったし、涙が出るほどの感動だった。
「おい、何やってんだよ! 早くしろよ!」
いつの間にか切符を購入していた兄貴が、乱暴に手を動かしながら、大声でわたしを呼んだ。周りの人たちが何事かという目で見ている。せっかくの感動が台無しだ。空気が読めない馬鹿兄貴!
わたしは兄貴をにらむと自分の切符を奪い取り、兄貴を押しのけて改札口へ急いだ。だけど、どこにも切符を入れる自動改札機がない。続いて来た兄貴も、あれ?――ときょろきょろしている。
兄貴と二人でオロオロしていると、端っこの方にある窓口から女性の駅員さんが、こっちですよ――とにこにこしながらわたしたちを呼んだ。
駅員さんは切符にハンコを押すと、わたしたちを駅のホームへ入れてくれた。恥じ入りながら入ったホームは閑散としていて、列車はまだ一つも来ていない。
しばらくそこに立っていると、兄貴が左手から来た列車を指差した。
「おい、見てみろよ。あれ、一両しかないぜ」
ホームに入って来る列車を見ると、確かに一両だけしかない。
松山駅の前の道路は路面電車が走っていた。路面電車も珍しいので、兄貴と一緒に眺めていたけど、あれはどれも一両だけだった。だけど、駅の線路を走る一両だけの列車があるとは思いもしなかった。しかも、この列車はパンタグラフがない。
列車イコール電車だと思っていたわたしは、地下鉄でもないこの列車が、どうやって電気を取っているのだろうと兄貴に尋ねた。でも物知りの兄貴も知らないみたいで、兄貴は近くにいた駅員さんをつかまえて聞いた。
駅員さんから返って来た答えはディーゼルで、軽油を燃やして動くエンジンで走っているということだ。要するに車と同じなわけだ。
へぇとわたしたちが驚いているうちに、この一両だけの列車は少し離れた所に停まり、中から乗客たちが降りて来た。
兄貴は面白がって列車に近づき、しげしげと眺めていた。
わたしは久美の所へ行くことを考えていたので、自分たちの列車に乗るには、どこにいればいいのかを駅員さんに尋ねた。すると駅員さんは、兄貴が眺めている列車がその列車だと教えてくれた。
そのことを兄貴に伝えると、兄貴は大喜びで列車に乗り込んだ。乗り込み口は車両後部に一つあるだけで、わたしもそこから兄貴に続いた。
中は窓を背にして座る椅子が、通路を挟んで向き合っている。乗務員は運転士さん一人で、乗客はわたしたちを含めて数名だけ。
前へ進もうとすると、近くにいた乗客の男性が、そこの整理券を取れと言う。見ると、小さな四角い機械から小さな紙切れが顔を出している。それを取ると、紙には番号と松山という文字が書かれていた。何だかバスに乗るみたいだ。
二人で空いている所に腰を下ろすと、兄貴は地図を広げた。
地図によれば、進行方向の右側に海がある。普段、海から遠い所に暮らすわたしたちには、海が見えるというだけで特別な感じがする。
前方の右側に空席を見つけた兄貴は、そちらへ移動しようとわたしをうながした。そこからだと海だけでなく、運転席からの景色もよく見えた。
目的地である伊予灘駅までは約一時間。いよいよ久美のいる所だと思うと、何だか身体に力が入る。相棒のわたしも気合いが入っているようだ。
でも兄貴にとっては、これはただの冒険だ。兄貴は腕時計を何度も見ながら、出発の時間を今か今かと待っていた。
ジリリンとベルが鳴って扉が閉まると、列車が動き出した。兄貴は身体を後ろに捻り、子供みたいに窓に顔を張りつかせた。
ここには都会のような高層ビルはない。それでも駅周辺にはビルと呼べる建物が並んでいた。だけど、列車が進むにつれてビルは姿を消し、辺りは民家ばかりになった。
やがて、水があまり流れていない川幅ばかりが大きな川を渡ると、景色はがらりと変わった。民家さえもがばらけてしまい、線路の周りには田んぼや畑が広がった。前方には山があり、その山へ近づいて行くと、右手にある町並みの向こうに海が現れた。
「おい、春花。海だぞ!」
兄貴が興奮した様子で叫ぶので、他の乗客たちの視線が集まった。ところが兄貴はまったく意に介さず、海を指差しながら、ほらあそこだ!――とわたしに教えた。
「わかってるから、静かにしてよ!」
恥ずかしいわたしは小声で兄貴を制したけれど、兄貴には全然通用しない。船だとか島だとか叫びながら窓に張りついている。くすくす笑う乗客もいたけど、わたしは何も聞こえないふりをして下を向いた。
行く手に山が迫ると線路は二手に分かれ、わたしたちの列車は右手の線路を進んだ。
列車はしばらく山裾の木々の中を走っていたけど、右手の視界が開けると、すぐそこに海が見えた。これでまた兄貴が感嘆の声を上げたので、乗客の何人かがまた笑った。
わたしは兄貴の背中を引っぱたいてやった。だけど兄貴は、何すんだよ?――と状況がわからない。ほんとに頭がいいのか悪いのか。とにかく兄貴は変わってる。
そのあと海は何度も土手に隠れたけど、ついにその姿を窓いっぱいに現した。兄貴にうながされて顔を上げてみると、右から左まで全部が海。わたしも思わず窓に張りついた。
確かにここの夕陽は素晴らしいだろうなと思いながら、兄貴と海を眺めていると、不意に列車が止まった。
振り返ると列車は駅に停まっていて、伊予灘駅の文字が見えた。わたしたちは慌てて棚から荷物を降ろすと、前方の出口から列車を降りようとした。
そのとき運転士に切符を求められ、初めてそこが無人駅なのだと気がついた。
でも兄貴が言うには、これまで通過した駅はすべて無人だったらしい。わたしは下を見てばかりだったし、久実のことを考えていたから、ちっとも気がつかなかった。
少ない乗客の半分がここで降りた。ほとんどが観光客のようだ。
駅にはすでに人がいたけど、みんな車で来た人らしくて、乗車はしないで写真を撮っている。久実から夕日を見に来る人が多いと聞いていたけど、夕日がなくても人気のある駅らしい。
ここが有名な駅だとわかっている兄貴は、海を眺めながら駅の端まで歩いて行った。自分がいる場所を、記憶に焼きつけているみたい。
だけど、ここには久美に会いに来たのであって、観光で来たわけじゃない。時間が惜しいわたしは兄貴を追いかけて、早く行こうと言った。
兄貴はここまで来れば、ほんの数分楽しんだところで何も変わらないだろうと、スマホで海の写真を撮り始めた。ムカッと来たわたしは、兄貴の手をつかんで無理やり駅の出口へ連れて行った。
観光客が多いからなのか、列車はすぐには出発しないで停まったままだった。すると兄貴は、今度は列車が入った駅舎の風景を撮り始めた。
海を背景にしたこの駅の写真は、ネットでもよく見られるらしい。でも列車が一緒の写真は、列車が来たときでなければ写せない。それを自分で撮れるものだから、兄貴は浮き浮きだ。一方のわたしはいらいらしたけど、兄貴が動かなければどうしようもない。
わたしは仕方なく兄貴が写真を撮り終わるのを待つしかなかった。ため息をつきながら海を眺めたけど、確かに駅のすぐ向こうに海が広がる風景は素敵だと思う。でも、今のわたしにはせっかくの風景を楽しむ余裕はない。
いらだちを抑えながら兄貴を待つ間、することがないわたしは改めて駅を見渡した。
目に映るのは、あちらこちらで兄貴のように写真を撮る人たちばかり。停車中の列車の中の乗客は、わたしたちが降りたときとほとんど変わらない。新たに乗車したと思われるのは、手前の席に座る女の子一人だけだ。外の人間には人気スポットのこの駅も、地元の人にはあまり利用されないみたい。
ようやく写真を撮り終わった兄貴は、わたしに文句を言われながら、スマホで郵便局の場所を調べてくれた。これだから兄貴に腹は立てても、あまり強くは言えない。
幸いなことに、郵便局はこの駅からそれほど遠くなかった。方角を確かめたあと、わたしは急いで歩き始めた。なのに、横を見ると兄貴がいない。後ろを振り返ると、兄貴は自然を満喫しながらのんびり歩いていた。本当ならば学校でテストを受けているはずが、こんな所にいることが楽しくて仕方がないようだ。だけど、そんなの私には関係ない。
「もう、お兄ちゃん! 早くしてよ!」
一秒でも早く久実の無事を確かめたいわたしは、大声で兄貴を呼んだ。わかったよといいながら兄貴は足を速めたけど、気がつけばまた同じようにのんびり歩いている。
そんなことを繰り返しながら十分ほど歩くと、わたしたちは伊予灘郵便局に着いた。
伊予灘郵便局は小さな郵便局だ。それでも町自体が小さなこの辺りでは、みんなが頼りにしている所なのだろう。小さな駐車場には車が三台止まっていて、もう一台が駐車場が空くのを待っている。
他の人たちがいる所では、久美の話をしづらいので、わたしは車がいなくなるのを待った。何分待ったのかはわからないけど、待ちくたびれた兄貴は、またもやスマホで辺りの風景を撮影し始めた。そうしながら兄貴はどんどん郵便局から離れて行く。
心細くなったわたしが呼んでも、兄貴は駐車場に車があるのを見ると、まだ大丈夫だと言って散策を続けた。
しばらく経ってようやく最後の車が出て行ったとき、兄貴はかなり遠くまで行ってしまっていた。
「お兄ちゃん、早く戻って来てよ!」
中の人に聞かれるのではないかと心配しながら、わたしは大声で兄貴を呼んだ。兄貴はやれやれといった感じで戻って来たけど、それでも悠々と歩いてる。早くしないと、次の車が来るじゃないのよ、馬鹿兄貴!
わたしが急かすと、兄貴はようやく小走りを始めた。だけど、それだって本気で走っているとは思えない。
わざとらしく肩で息をしながら、悪ぃ悪ぃと兄貴は悪びれずににやついた。わたしは兄貴をにらみつけると、郵便局の入り口の前に立った。だけど、そこで急に緊張感が膨らんで来た。もしここで久実の居場所がわからなかったら……。そう思うと、中へ入るのが怖かった。
「おい、何やってんだよ。中に入るんじゃねぇのか?」
扉の前から動けずにいるわたしは、さっきとは逆に兄貴に急かされた。
「わかってるよ! 今、気持ちを落ち着けてんの!」
声を荒げて言い返したものの緊張は解れない。わたしは大きく深呼吸をすると、覚悟を決めて足を踏み出した。自動扉がすっと開き、こぢんまりとした中の様子が目に入った。心臓がばくばくしてるけど行くしかない。そのために、ここへ来たんだから。
わたしは入り口を入ったところで足を止めた。勇気を出して踏み込んだけれど、誰に話を聞けばいいのかがわからない。そんな所で止まるなよ――と後ろから兄貴に言われ、少しだけ前に進んだけれど、そこでまたわたしは立ち止まった。
途方に暮れた様子のわたしに、いらっしゃいませ――と窓口の女性が声をかけた。後ろの兄貴に背中を押され、わたしは窓口の前に進み出た。
「あの、ちょっとお尋ねしたいことがあるんですけど」
はい、何でしょう?――と微笑む女性に、わたしは久実からの封筒を見せ、この消印がここで押されたものかを、まず確かめた。
確かにここですと、その女性がうなずくと、わたしは封筒の裏に書かれた久実の名前を見せ、この子のおばあちゃんの家を知りたいと訴えた。
突拍子もないことを尋ねられて、窓口の女性は当惑した様子だった。他に客がいなかったので、隣の窓口にいたもう一人の女性や他の局員たちも集まって来て、代わる代わる久実の名前を見た。
「これぎりじゃ、わからんぜ……」
頭にゴマをふったような年配の男の人が、封筒を見ながら首を捻った。
「あの、最近おばあちゃんが倒れて入院したそうなんです。危篤だって言うんで、それで久実はおばあちゃんのお見舞いに来たんです!」
ちゃんと説明になったか自信はない。でも、わたしは久実との関係や久実のおばあちゃんについて、持っている限りの情報を伝えた。
「おばあちゃんの名前はわからんかな? 兵頭さん言うたら何軒もあるけんなぁ」
ゴマふり頭の局員の言葉に、わたしは首を横に振った。すると、初めの女性とは別の窓口にいた女性がわたしに言った。
「ほれにしたかて、なんでわざわざこの子に会いに来たん? この子は用事が済んだら東京へ戻るんやないん?」
その言い方が少し冷たく聞こえたので、わたしは手紙の中身を見せて、この文面にはすごく嫌な感じがすると訴えた。
それがどういう意味なのかは伝わったみたいだけど、わたしの言い分を素直に受け取ってもらえたわけではないようだ。女性は他の局員たちと困惑の顔を見交わしている。
このまま相手にしてもらえなかったら、すべてはおしまいだ。わたしの中で不安が大きくなって行く。兄貴を振り返っても、兄貴も何も言えない様子だ。
そのとき、初めの女性がみんなに声をかけてくれた。
「この兵頭久美いう子が、実際のとこどがぁなんかはわからんけんど、この子ら、こがぁして遠いとこから、わざわざここまでおいでたんやけん、何とかしちゃろや」
女性の言葉で雰囲気が変わり、どうしたものかとみんなが考え始めてくれた。わたしはこの女性を拝みたくなった。とは言っても、すぐに名案が浮かぶわけではない。次の客が来てしまえば、そこまでになってしまいそうだ。
そのとき恰幅のいい男の局員が、ひょっとして――と言った。
「先日亡くなった総子さんやなかろか? 確か、昨日が葬式やったと思うけんど」
わたしは顔から血の気が引くのを感じた。その人が久美のおばあちゃんだとしたら、きっと久実は深く落ち込んで泣いているに違いない。
初めの窓口の女性がうなずいて言った。
「ほうじゃねぇ。ほうかもしれんね。入院しよるばあちゃんやったら、他にもおるかもしれんけんど、危篤やった言うんなら、亡くなった総子さんがほうなんかもねぇ」
「そこの家の場所、教えてもらえますか?」
わたしはその窓口の女性にお願いし、後ろにいる他の局員たちの顔を見た。
「ほやけど、個人情報やけんなぁ」
恰幅のいい局員が顎に手を当てながら言った。すぐさま窓口の女性が後ろを振り返り、局長!――と叫ぶように言った。
「さっきも言うたけんど、この子ら遠いとこから、学校休んでまでして友だちを探しに来たんで? ほれやのにそげなこと言いよったら、伊予の人間の恥になるで!」
どうやらこの恰幅のいい人は局長らしい。でも、ここで一番強いのは、この女性のようだ。頬を膨らませながら局長が口をつぐむと、女性はわたしたちの方に顔を戻した。
「兵頭さんとこは、こっからちぃと離れとるけんど、あんたら、車で来たん?」
わたしが首を振ると、わたしに代わって兄貴が、列車で来ましたと答えた。
女性はふーむと唸り、歩いて行けんこともないけんど――と思案げに言った。
「歩いて行きますよ。どのくらいかかるんですか?」
兄貴が尋ねると、三十分ぐらいかなと女性は言った。それから女性はまた後ろを向き、ゴマふり頭の男性に声をかけた。
「中村さん、今、手ぇ空いとろ? 悪いけんど、この子らを車で運んでやってくれん?」
「何ぜ、その言い方は。まるでわしがぶらぶらしよるみたいやないか。まぁ、車やったら大した時間はかからんけん、行ってやっても構んがな」
「じゃったら、運んだってや」
女性に言われた中村さんは、素っ気ない様子でわたしたちに外を指差すと、裏口から外へ出て行った。
「ほら、あんたらも外に出ぇや。中村さんが車出してくれるけん」
女性が笑顔でわたしたちをうながした。
二人でお礼を言ったあと、わたしと兄貴は急いで外へ出た。そこへ中村さんが現れたけど、中村さんの車は軽トラックだった。
軽トラックが珍しい兄貴は目を丸くして、これに乗るんですかと中村さんに尋ねた。
おうよと中村さんがぶっきらぼうな声を出すと、すげぇと兄貴は喜んだ。それで気をよくしたのか、中村さんはにやりと笑って言った。
「普段はバイクで来よるんよ。局長もバイクやし、窓口の姉やんらは自転車よ。ほんでも今日はバイクの調子がいけんかったけんな。しゃあなしにこれで来たんぜ」
「でも、三人は乗れないんじゃ……」
わたしは思わずつぶやいた。見たところ、座席は運転席と助手席だけだ。助手席はトラックみたいに広くない。
「姉やんが助手席ぜ。兄やんは荷台でよかろ。何、ちぃとの距離やけん構ん構ん」
そんな乗り方をしてもいいのだろうかと、わたしはちょっと心配になった。
でも、兄貴は荷台に乗ることが刺激的なようだった。中村さんが荷台の後ろの衝立みたいな部分を手前に倒すと、兄貴はそこから荷台の上にひらりと飛び乗った。
「ほぉ、兄やんは身軽じゃな」
「そうですか? これぐらい誰だってできますよ」
そう言いながら、兄貴の鼻の穴は得意げに膨らんでいる。中村さんは笑っていたけど、その笑みを消して兄貴に言った。
「ひょっとパトカーが来たら、そこにべたっと横になって見えんようにしよってくれよ。見つかったらめんどいけんな」
やっぱり、これはまずいことらしい。だけど、もう乗るしかない。兄貴はパトカーと聞いて目を輝かせている。
わたしの気持ちを見透かしているのか、中村さんはこちらを向いて口元を少しだけにやりとさせると、荷台の後ろの衝立を元に戻した。
いなくなった久美
普通の乗用車と比べると、軽トラックは乗り心地がいいとは言えなかった。でも、荷台の兄貴のことを思えば文句は言えない。
道は比較的真っ直ぐで、それほど揺れはしなかった。それでも座席のない兄貴は、荷台にへばりつくように坐って、必死に身体を支えていた。
しばらくすると軽トラックは、とても古そうな家に着いた。家の前には車が一台も止まっていない。中もしんと静まり返っていて誰もいないみたいだ。本当にここが久美のおばあちゃんの家なのだろうか?
わたしは軽トラックを降りて表札を確かめると、玄関の呼び鈴を押した。中で呼び鈴が鳴っているのが聞こえる。だけど、それに対する反応のようなものが何もない。
「どうした? 誰もいないのか?」
後ろで兄貴が首や肩を回しながら言った。やはり軽トラックの荷台はこたえたらしい。兄貴の後ろでは、軽トラックの運転席から中村さんが様子を窺っている。
そうみたいと答えたわたしは、急に不安が募り出した。
郵便局から持ち続けていた久実の手紙を胸に押し当てながら、わたしは久美が出て来てくれることを祈った。だけど久美は現れないし、誰も出て来ない。この家ではないのか? それとも久実は入れ違いに東京へ帰ったのだろうか?
「どがいした?」
中村さんが声をかけた。わたしは中村さんの傍へ戻ると、誰もいないみたいですと説明した。すると、近くの民家から出て来た年配の女性が、不審そうにわたしたちを見た。
「あんたら、誰ね?」
わたしは慌てて説明しようとしたが、先に中村さんが女性に言った。
「わしは郵便局の中村いうもんやけんど、この子らが東京から兵頭久美いう女の子を訪ねて来たんでな。ほれで、ここへ連れて来てみたんよ。先日亡くなったここのばあさまが、その子のばあちゃんやないかと思たんでな」
久美やて?――と女性は顔をしかめた。
「あの子やったら、もう去んだろ。葬式は昨日終わったけんな」
「いんだって……」
こっちの言葉がわからない兄貴が、独り言のようにつぶやいた。わたしは構わず女性に言った。
「失礼ですけど、あなたは久美の親戚の方ですか?」
「うちはあの子の伯母や。言うても、血ぃはつながっとらんで。あの子の義理の父親が、うちの弟なんよ」
「義理の父親?」
聞き直したわたしに、女性はいらだったように言った。
「あんた、何も聞いとらんのかいな。あの子の母親はうちの弟と再婚したんよ。ほやけん弟はあの子の義理の父親じゃ。ほんでも、その弟も死んでしもたけどな」
「え? お父さんが死んだ? いつですか? まさか、おばあちゃんが亡くなったのと同じときに?」
久美の伯母さんという女性は、呆れたような顔を見せた。
「あんた、ほんまに何も聞かされとらんのやな。わざわざ東京から来た言うけんど、久美の方はあんたのこと、友だちやとは思とらんのやないんか?」
わたしは伯母さんの毒舌に圧倒されて返事ができなかった。代わりに兄貴が後ろから伯母さんに尋ねた。
「そんなことより、久美さんのお父さんが亡くなったのは、いつのことですか?」
伯母さんはじろりと兄貴を見てから、二年前の夏だと言った。
「弟はな、寝る間もないぐらい仕事が忙しかったんよ。ほんでも、あの子が海に行きたいて言うたけん、疲れた体に鞭打って、あの子を島へ連れて行ったんよ」
瀬戸内海は一見穏やかに見えるが、実際は複雑な潮の流れがあり、船の衝突事故もよく起こるらしい。
よく知らない海は危ないから、浜から離れないようにと、久美は父親から言われていたはずだった。しかし、久美は注意を守らず浜から離れ、沖へ流されてしまったと言う。
「弟はあの子を助けよとして、あの子を追いかけたそうな。ほんでも、体がへろへろやったけんじゃろね。途中で溺れて死んだんよ」
わたしは衝撃を受けた。久美から聞いた話では、久美は父親の仕事の関係で東京へ来たはずだった。
何故久美は本当のことを話してくれなかったのか。他にも話してくれていないことがあるのだろうか。久美は松山でいじめ事件を起こしたために東京へ逃げて来たらしいと、頭の中で満里奈が喋っている。
伯母さんは言葉を失ったわたしに構わず話を続けた。
「あの子がちゃんと言うとおりにしよったら、弟は死なずに済んだんよ。死ないでもええ弟を死なせといて、あの子はちゃっかり他の人に助けてもらいよった。うちの弟は犬死にや。わざわざ死ぬために、あの子の母親と一緒になったようなもんじゃ。歳が五つも離れた年増で、連れ子までおるような女に騙されてしもて」
「ほら、言い過ぎやろ。本人らがええ思て一緒になったんなら、他人がとやかく言うもんやなかろがな」
中村さんがたまりかねたように言った。しかし、伯母さんは悪びれずに言い返した。
「ほれこそ他人のあんたが口挟むことやなかろがね。弟は父親の後継いで漁師になるはずやったんよ。たった一人の後継ぎやったのに死んでしもたけん、父親は毎日呆けたようになってな。ほれで、車にはねられて死んでしもたんよ」
そこまで言ってから、伯母さんは今度はわたしたちに向かって言った。
「ほんでも、うちの母親はあの子を慰めて励ましよった。ほれやのに、あの子は中学校で騒ぎ起こして、事もあろうかPTAの会長さんの娘らに怪我させたんよ。ほれで、こっちにはおられんようになってしもて、東京へ逃げくさったんじゃ」
「それは確かなことなんですか?」
兄貴が尋ねると、当たり前じゃろがねと伯母さんは噛みつきそうな顔で言った。
「その話聞いたうちの母親は、ほれから血圧がえらい高なってしもてな。とうとう頭の血管が切れて死んでしもた。あの子はうちの弟ばかりか、父親と母親まで死なせたんよ。うちらにとって、あの子は疫病神以外の何でもないで」
疫病神という言葉に、わたしはどきんとなった。夢の中で矢が久美の胸を貫いたとき、誰かが叫んだのがこの言葉だ。
わたしは悟った。夢で見た矢は、久美を罵った者が放った言霊に違いない。そして疫病神という呪いの言葉を放ったのは、この伯母さんだ。
わたしの中で伯母さんに対する怒りがみるみる膨らんだ。
「久美は疫病神なんかじゃない!」
「何怒りよるんよ。うちは事実を話しとるぎりじゃろがね」
「久美のお父さんが亡くなったのは、久美のせいなんかじゃない! おじいちゃんやおばあちゃんだって久美は大好きだったんだから、久美が疫病神のはずがないでしょ!」
「あの子に好かれた者は死んでしまうんよ。ほれが疫病神でのうて何やて言うんよ?」
「わたしは死んでないし、死んだりしない! だから久美は疫病神なんかじゃない!」
伯母さんは当惑したように息を吐くと、この子たちを早く連れて帰れと中村さんに言った。それから伯母さんは憤った様子でわたしに言った。
「だいたい、なんでうちが初対面のあんたにそげなこと言われないけんのや? あんたはうちらにとって、まったくの赤の他人じゃろがね。東京の人間いうんは、そがぁに礼儀知らずなんか」
険悪な雰囲気の中、まぁまぁと中村さんが伯母さんをなだめて言った。
「とにかく、ここにはその久美いう子はおらんのじゃな?」
「おるもんかね。葬儀に呼んだわけでもないのに、母子で勝手に来よったんよ。そげな者らをここへ置いたりするわけなかろ?」
「わしにそがぁなこと言われても困らい。ほんでも、その子らがここに泊まったんやないんなら、昨夜はどこに泊まったんかな」
「従兄の政兄とこに泊めてもろたみたいな。母親のことをあの二人に知らせたんも政兄やけんな。まったく余計なことぎりしてくれる従兄じゃ」
「まさにいって?」
尋ねたわたしに、伯母さんは面倒臭げに言った。
「名前が政吉やけん、政兄や」
「ほの政吉いう人の家は、どこにあるんぜ?」
口汚く喋る伯母さんに、中村さんは穏やかに話しかけた。そうして政吉という人の家の場所を伯母さんから聞き出すと、行くぜ――とわたしたちに言った。
わたしは伯母さんをひとにらみしてから中村さんの後に続いた。でも兄貴は伯母さんにぺこりと頭を下げた。口が悪くても、一応は政吉という人の家を教えてくれたことへのお礼ということだろう。それと東京の人間が礼儀正しいというところを、示したつもりもあるに違いない。
軽トラックに乗り直したわたしたちは、少し離れた所にある集落へ移動した。もちろん兄貴は後ろの荷台の上だ。
伯母さんが言ったように、久美がわたしたちと入れ違いで東京へ戻ったのであれば、それはそれで構わない。向こうで久美はわたしの無事を知るはずだから。だけど、久美が東京へ戻ったということを確かめるまでは安心できない。わたしの胸の中では、不安が騒ぎ続けている。
ある家の前に軽トラックを停めた中村さんは、わたしたちより先に降りて、その家の呼び鈴を押した。あとから降りたわたしは、どきどきしながら出て来る人を待った。わたしの後ろでは、兄貴が首と肩を回しながら、やはり緊張した顔で中村さんを見ている。
中村さんは何度か呼び鈴を押したけど、誰も出て来ない。わたしの中の不安が、ざわっと大きく膨らんだ。
表札に出ている名前を確かめた中村さんは、おかしいなと言った。
「家は間違とらんみたいなけんど、誰っちゃおらん。誰ぞ一人ぐらいおってもよさそうなんやがな」
「もしかして、みんなで久美さんたちを見送りに行ったんじゃ……」
兄貴が遠慮がちに言うと、ほうかもしれんな、と中村さんはうなずいて腕時計を見た。
「松山方面の列車が来るまで、まだ一時間以上あるな。駅まで見送りに行くにしたら、ちぃと早過ぎると思うけんど、見に行くか?」
わたしたちがうなずくと、中村さんはわたしたちを軽トラックに乗せて、わたしたちが降り立った駅へ向かった。
ところが駅にいたのは、駅から海の写真を撮りに来た観光客たちばかりで、久美も見送りらしき人たちもいなかった。
「もう一本早い列車に乗ったんだろうか?」
兄貴が松山へ向かう線路を見つめながらつぶやいた。そのつぶやきを耳にした中村さんが、じゃったら兄やんらが見つけとらい――と即座に言った。
どういうことかと聞くと、もう一本早い列車というのは、わたしたちが乗って来た列車だと中村さんは説明した。それほどここは列車の数が少ないらしい。
もし久美がその列車に乗っていたのなら、松山駅で列車を降りた久美とわたしたちが、顔を合わせていたはずだと中村さんは言った。
確かに、一両編成で乗車口が一つだけしかない列車から、久美が降りて来たのだとしたら、わたしが見逃すはずがない。東京と違って降りて来た人の数も多くなかったから、久美が他の人に隠れて見えないということもなかった。
あの列車に久美は乗っていなかったし、次の列車に乗るわけでもなさそうだ。それは久美が東京へ戻ったわけではないし、戻るつもりもないということだ。では、久美はどこへ行ったのか。わたしは寒いものを感じた。
中村さんはわたしたちを軽トラックに乗せると、もう一度さっきの家に戻った。すると家の前でうなだれる女の人と、その人を慰めているような男の人がいた。
軽トラックに気づいたように二人が顔を向けると、わたしは急いで車を降りた。男の人の方は知らないけれど、女の人は久美のお母さんだった。久美の家に遊びに行ったとき、久美のお母さんと顔を合わせていたので、すぐにわかった。
「おばさん!」
わたしが駆け寄ると、久美のお母さんはとても驚いたようだった。
「春花ちゃん? 春花ちゃんか?」
「おばさん、久美は? 久美はいるんですか?」
わたしの言葉を聞いた久美のお母さんは、顔をゆがめて泣きそうになった。
「久美はおらんなってしもたんよ」
わたしの中の不安が絶望に変わろうとしていた。わたしは必死に気持ちを抑えながら尋ねた。
「いつからいなくなったんですか?」
「朝ご飯食べたときはおったんよ。そのあと、ぶらっと外へ出たきり戻んて来んのよ。帰りの列車はお昼やし、あの子の荷物はそのままやったけん、その辺におるもんやとばっかし思いよった。一時間ほど前になって、ようやっとあの子がおらんなったてわかってな、ほれでみんなで手分けして探しよったんやけんど、どこっちゃ見つからんのよ」
「まだわからんで。尚子らが見つけとるかもしらんけん」
隣にいた男の人が、久美のお母さんを慰めた。誰だろうと思っていると、久美のお母さんが、この人は夫の従兄の政吉さんだと言った。それからお母さんはわたしのことを男の人に説明したが、兄貴に気づいて、こちらは?――とわたしを見た。
「わたしの兄です。わたしが久美に会いに行くって言ったら、ついて来てくれたんです」
ほぉと政吉さんが声を出し、久美のお母さんも驚いた顔で照れ気味の兄貴を見た。
「春花ちゃんが久美に会いに来てくれたぎりでもびっくりやのに、お兄さんまでおいでてくれたやなんて……」
「いえいえ、いつもこんな感じなんですよ」
兄貴は少しうれしそうに言った。何がいつもこんな感じだ。兄貴はまったく調子のいいことばかり言う。
「ほやけど、学校があるんやないか?」
政吉さんが尋ねると、えぇまぁと兄貴は言葉を濁した。少し当惑したような顔の口元はにやついている。学校があるのに妹に付き添ってここまで来たのかと、感心してもらえるのを期待しているようだ。
でも、そのことを政吉さんが言う前に、久美のお母さんがわたしに言った。
「そがぁ言うたら、春花ちゃんかて入院しよったんじゃろ? ひどい肺炎らしいて久美から聞いたけんど、春花ちゃん、もう体はええんか?」
「はい。みんなに助けてもらって、何とか回復することができました」
「ほうなんか。ほれはよかったけんど、ほれにしたかて病み上がりじゃろ? こがぁにやつれてしもて……」
久美のお母さんはわたしの手を取りながら、病院はいつ退院したのかと言った。一昨日ですと答えると、お母さんは驚いたように目を丸くした。また隣の政吉さんも、同じような顔でわたしを見た。
「退院したばっかしやのに、そがぁな体でこがぁなとこまでおいでてくれたんか。お母さんはこのこと知っておいでるん?」
「はい、知ってます」
ね――とわたしは兄貴を振り返った。政吉さんの感心の言葉を遮られ、所在なげにしていた兄貴はびっくりした様子で、何が?――と言った。
「お母さん、わたしたちがここに来てること、知ってるもんね?」
「え? あ、あぁ、知ってます」
本当は黙って来たんだけど、それがばれてしまい、トラックの中で兄貴は母からこっぴどく叱られた。でもそれで事情を説明したし、そのあとも兄貴がこまめに報告しているみたいだから、母がわたしたちがここにいることを知っているのは本当だ。
「ほんまに? ほやけど、あんたらのお母さん、よう許してくれたもんじゃね。あたしじゃったら絶対に許さんで。あんたらはよっぽどお母さんから信頼されとるいうことなんじゃねぇ」
久美のお母さんが政吉さんに顔を向けると、まったくじゃと政吉さんもうなずいた。
「普通はそがぁなことは許さんぜ。しかも今聞いた話じゃ、姉やんはひどい肺炎で入院しよったばっかしなんじゃろ? いくら兄貴がついてくれとる言うても、そがぁな子を親はこがぁなとこまで来させたりすまい。ほれで、こっちには飛行機で来たんかな?」
すかさず兄貴が、ヒッチハイクで来ました――と言った。
「ヒッチハイク? 東京からここまで?」
政吉さんは驚いたというより、呆れたみたいに目を見開いた。わたしは慌てて言い足した。
「本当は今日の新幹線でってことだったんですけど、それじゃあ遅くなっちゃうから、親切なトラックの運転手さんにお願いして、昨日のうちに運んでもらったんです」
「全部で三台のトラックのお世話になりました」
兄貴が得意げに補足した。
久美のお母さんは驚いて政吉さんと顔を見交わすと、どうしてそこまでしてここへ来たのかとわたしに言った。
わたしは久美からもらった手紙を読んで、久美が心配になったからだと言った。久美のお母さんの目は、みるみる涙でいっぱいになった。
「春花ちゃんぎりじゃ……。あの子のことをそこまで想てくれるんは、春花ちゃんぎりじゃ……」
久美のお母さんはわたしの手を取り、わたしを抱きしめた。
「こがぁな体で、ようおいでてくれたね……。ありがとう……。ありがとう……」
わたしはお母さんの子供になりたくて、この世界に生まれて来た。それは久美だって同じはずだ。久美もこのお母さんの子供になりたくて生まれたのだし、久美のお母さんも久美と出逢えるのを待ち望んでいたはずだ。その久美がいなくなったことで、久美のお母さんがどれだけ心を痛めているかと考えると、わたしは胸が締めつけられた。
久美のお母さんはわたしから離れると、涙を拭きながら言った。
「ほれにしたかて、ようこの場所がわかったもんじゃね」
「郵便局の中村さんに連れて来てもらったんです。中村さん、お仕事があるのに、ずっとわたしたちに付き合ってくれて、一緒に久美を探してくれているんです」
「あの、久美さんの手紙の消印に伊予灘郵便局って書いてあったんで、それで取り敢えずここまで来てみたんです」
兄貴が付け足して言ったけど、久美のお母さんは兄貴の頭のよさには気づかず、ほうやったんかと中村さんに頭を下げた。それに合わせるように、政吉さんも頭を下げた。
二人に頭を下げ返した中村さんは、そろそろ仕事に戻るとわたしたちに言った。
「何や、えらいことになっとるみたいなけんど、わしもせんといけんことがあるけん」
ほんの短い間だったけど、もう中村さんはわたしたちの仲間みたいな感じだった。その中村さんの離脱はやっぱり心細かった。それでも無理なことは言えない。赤の他人の中村さんにここまでしてもらえただけでも感謝だ。
わたしと兄貴が中村さんにお礼を述べていると、女の人が一人焦ったような顔でやって来た。
「あんた、久美ちゃん、おらんで」
女の人はわたしたちを見ながら、まず政吉さんにそう言った。それから、この人らは?――とわたしたちのことを見ながら言った。
東京から久美に会いに来た友だちだと説明した政吉さんは、この女の人を女房の尚子だとわたしたちに紹介した。
そこへまた別の若い女性二人がやって来て、おらんわ――と政吉さんたちに言った。
政吉さんはまたわたしたちに自分の娘たちだと説明し、彼女たちにわたしたちを紹介した。二人は和美さんと八重さんと言い、どちらも近くの会社で働いているらしい。
わたしは挨拶もそこそこに、久美が見つからないのかとみんなに尋ねた。政吉さんの家族は黙ってうなずき、久美のお母さんは嗚咽した。
様子を見ていた中村さんは、ほんじゃあと申し訳なさそうに小声をかけると、軽トラックに乗って行ってしまった。
「とにかく警察に連絡しよや」
政吉さんはそう言うと、家の中へ入って行った。
娘さん二人がその後に続くと、硬い表情をしている久美のお母さんに、中へ入るよう尚子さんがうながした。それから尚子さんはわたしたちを振り返ると、お二人もどうぞと招き入れてくれた。
知らされた事実
家の中に入ると、政吉さんが早速警察へ電話をかけていた。その電話はずんぐりしていて真っ黒で、数字が書かれたボタンはない。代わりに丸い穴がいくつも開いた円盤が付いていて、それぞれの穴の下に数字が書かれてある。
政吉さんはこの穴に右手の指を入れて、ジーコジーコと円盤を回転させていた。それから左手に握っていた黒くて太い受話器を顔に押し当てた。
「もしもし、警察? うちの従弟の娘がな、行方知れずになったんよ。すぐに探してくれんかな」
政吉さんは大声で警察に喋り始めた。その様子を久美のお母さんたちが不安げに眺めている。
ところが兄貴は政吉さんの会話より、黒い電話に関心を向けているようだ。じっと電話を物珍しげに見つめている。
うちの家にも固定電話はあるけれど、もっと薄くてボタンで番号を打ち込むタイプだ。だから、わたしにしたってこの家の電話は珍しいけど、今はそれどころじゃない。それなのに兄貴ったら、今の状況が理解できているのだろうかと腹が立つ。
一方で政吉さんの娘さんたちは、わたしたちに興味が湧いたらしい。警察への連絡は父親に任せたという感じで、小声でわたしに話しかけて来た。それで久美との関係や、どうしてここへ来たのかということを聞き出すと、政吉さん同様に驚いた。また横で話を聞いていた尚子さんも目を丸くした。
「何べんも同しこと言わしなや。ほやけんな、東京からこっちのばあさんの葬儀に来よった従弟の娘が、急に行方不明になったんよ。みんなで手分けして探したけんど、どこっちゃ見つからんけん、警察でも捜してくれて言いよんじゃろがな!」
政吉さんが壁を見ながら受話器に怒鳴った。ぴりぴりした空気が、わたしたちを黙らせた。
そのあと政吉さんは、受話器の向こうの警察と何度かやり取りをしたあと、乱暴に受話器を置いた。
「すぐ来てくれ言うとんのに、ああだこうだ言うて、なかなか腰上げようとせん。あがぁなことやけん、世の中から事件がなくならんのぜ!」
政吉さんはわたしたちの傍に腹立たしげに腰を下ろした。でも、すぐに顔の険しさを消すと、心配せんでええけん――と久美のお母さんを慰めた。
「とにかく今は久美ちゃんの無事を信じよや。こがぁして東京の友だちもおいでてくれたんやけんな。絶対久美ちゃんは見つかるて」
久美のお母さんはしおれるようにうなだれて、自分がもっと気をつけておくべきだったと悔やんだ。
「うちの人が死んだんも、おじいちゃんが亡くなったんも、自分のせいやてあの子は思いよった。春花ちゃんが病気になったんも自分のせいやて言いよったあの子が、どがぁな気持ちでここへ来たんか、気ぃついてやれんかったあたしは母親失格や」
「ほんなことない。あんたは女手一つでようやっとらい。悪いんは里子ぜ。あの阿呆たれは自分が離婚して出戻りになったのに、自分と同しバツイチの初子さんが、忠志と一緒になって幸せそうにしよるんが面白なかったんよ」
政吉さんが久美のお母さんを慰めると、尚子さんも言った。
「里ちゃん、昔っから忠志くんのこと可愛がりよったけんねぇ。その忠志くんを初子さんに取られたいう気持ちもあったんじゃろな。ほうは言うても、あの人の初子さんや久美ちゃんに対する態度は異常なで。なんであそこまでひどいこと言うんじゃろか」
知らない名前が出て来たので、わたしは和美さんに誰のことかと、そっと尋ねた。
和美さんの説明によれば、里子というのがあの怖い久美の伯母さんで、忠志というのが久美の亡くなったお父さん、そして、初子というのが久美のお母さんのことだそうだ。
ようやく人間関係がわかったけれど、どうして久美が伯母さんに憎まれるのかが、わたしにはわからなかった。
それについて尋ねてみると、尚子さんが話してくれた。
「あたしもな、なんでそこまであの子を嫌うんかて聞いてみたことがあるんよ。ほしたらな、子供の頃に自分をいじめよった上級生に似とるけんじゃて言いよった」
「ほうなんですか?」
久美のお母さんが当惑した顔を尚子さんに向けた。今の話は初耳だったらしい。
うなずく尚子さんに、わたしは言った。
「わたし、久美はおばさんに似てるって思ってました。それは、おばさんもその人に似てるってことでしょうか?」
ほうじゃねぇと、尚子さんは久美のお母さんを見つめた。
「確かに初子さんも似とるとこはあるけんど、どっちか言うたら久美ちゃんの方が似とるかな。言うても、ほんまはどっちも全然似とらんのよ。誰が見たかて、里ちゃんをいじめた人と、久美ちゃんや初子さんは別人やてわかるけん。ほんでも、どっか似とるとこがあったら、全部似とるみたいに思てしまうんじゃろかねぇ」
誰のことかと政吉さんが聞くと、尚子さんはその人物がどこの誰なのかを説明した。もちろんわたしたちには誰のことかはわからない。でも政吉さんはわかったようで、あいつかと言いながら大きくうなずいた。
「そのいじめた人は、今もここにいるんですか?」
兄貴が話に交ざると、政吉さんが言った。
「どこぞへ嫁入りしたみたいでな、あとのことはわからんのよ」
「だとしたら、それもあの伯母さんが腹を立てる理由かもしれませんよね」
納得したようにうなずく兄貴に、わたしはどういうことかと尋ねた。
「つまり、自分をいじめた相手は離婚されていないのに、いじめられた自分は離婚されたっていうのが、面白くなかったんじゃないかってこと。自分をいじめたやつは幸せに暮らしてるのに、いじめられた方の自分がなんで不幸せなのかって考えるんじゃないかな」
なるほどと政吉さんがうなずき、尚子さんも感心したような目を兄貴に向けた。
「翔太郎くんって頭がえぇんじゃねぇ」
八重さんが言うと、ほんまほんまと和美さんも言った。
「ほれに、えらい妹想いやしねぇ。翔くん、女の子にもてるじゃろ?」
和美さんがからかうように言うと、それほどでもと兄貴は照れ笑いをした。
わたしは咳払いをすると、久美のお母さんに久美がどうして東京へ転校したのか尋ねてみた。
お母さんはしょんぼりしながら、いろいろあったんよと言った。
「あの子が幼稚園の頃にな、あの子の実の父親は、あたしらを捨てておらんなったんよ。ほれであの子は泣いてな、ちょっとしたことに腹を立てるようになってしもた。やけん、小学校に上がっても友だちはできんし、片親じゃいうことをからかわれたら、相手が男の子でも取っ組み合いの喧嘩をするほどじゃった」
今の久美からは想像ができないほど、子供の頃の久美は気性が激しかったようだ。だけど、その気性も新しい父親ができると、次第に落ち着いて行ったそうだ。
「新しい夫はな、まっことあの子に優しかったし、あの子も新しい父親のことが大好きじゃった。あの人のお陰でな、久美はようやっと本来の穏やかで優しい子に戻れたんよ」
久美のお母さんは懐かしそうな笑みを浮かべて言った。わたしにもその頃の久美の様子が目に浮かぶようだ。
ところがその大好きな父親が、沖に流された久美を助けようとして死んだのだ。その光景を見ていたであろう久美が、どれだけ悲しくつらいことだったのかは想像に難くない。
当時、久美のお母さんはお腹に新たな命を宿らせていたと言う。久美は自分の弟か妹ができるのが、とても楽しみだったらしい。
だけどこの事件がきっかけとなって、その子を流産してしまったと久美のお母さんは言った。それは久美が自分にとって大切な存在を、同時に二つ失ったということだった。そして、二つの命がなくなったのは全部自分のせいだと、久美はずっと自分を責め続けていたそうだ。
それなのに、そんな久美に追い打ちをかけるように、あの伯母さんが久美に呪いの言葉を吐いた。久美は学校にも行けなくなり、ずっと家に引き籠もっていたと言う。
「あの子は自然が好きな子でな、花言葉もようけ覚えよった。そんなあの子の慰め言うたら、庭に咲く花とか、飼うとった子犬とか、時々庭に遊びに来る小鳥やタヌキじゃった」
話を聞いていたわたしは、どきりとした。花、子犬、小鳥にタヌキ。それらはわたしが久美の絵に描き加えた生き物たちだ。
久美のお母さんは久美を学校へ行かせるため、それまで暮らしていた山の近くから松山へ引っ越しした。松山なら自分たちの状況を知る者がいないため、久美も学校へ行きやすいと考えたそうだ。
しかし、松山では庭がなかったので犬を飼うことができず、可愛がっていた犬は近所の知り合いにもらってもらうことになった。それは久美には悲しいことだったので、久美のお母さんは松山へ移ったあと、久美に部屋で飼うウサギを買ってやったそうだ。
転校してもすぐに友だちができるわけでもなく、久美は学校が終わると、ウサギの世話ばかりをしていたらしい。
わたしが久美に描いた絵には、そんな意味があったのかと、わたしは初めて知った。あの絵は久美にとって慰めであり、久美の本当の姿だったということだ。それに、失ってしまった大切な者たちへの想いも、あの絵に重なっていたに違いない。
あのとき絵を抱きしめて泣いた久美が思い出され、わたしの目から涙がこぼれた。兄貴は涙の理由を知らないけれど、しんみりと話を聞いている。
中学校になると、別々の小学校出身の者たちが一緒になるので、久美にも馴染みやすかったらしい。ようやく友だちができたようなので、久美のお母さんもほっとしたそうだ。
しかし、その中学校で事件が起きた。それが久美の伯母さんが言ういじめ事件らしいけど、事実は久美が事件を引き起こしたわけではなかった。
久美のお母さんの話によれば、事の発端は東京からの女子転校生だと言う。
その転校生は喋り方が松山の言葉とは違っていたので、気取っていると女子生徒たちにからかわれたらしい。それがやがては執拗ないじめになったとき、久美はいじめグループの生徒たちに、いじめをやめるように注意したと久美のお母さんは言った。
すると、そのいじめグループのリーダーが、どこから情報を得たのか、片親のくせにと久美を馬鹿にしたらしい。さらには何も知らない久美の父親のことまで嘲笑ったので、大喧嘩になったそうだ。
怒れば男子相手でも負けない久美だけど、なにしろ相手は複数だ。争いに気づいた男子生徒たちが両者を引き離すまで、久美は必死に相手を引っぱたいたり蹴飛ばしたりしたそうだけど、本人はそのときのことをよく覚えていないそうだった。それでもお互いが怪我をするほどの喧嘩だったので、久美はお母さんと一緒に校長室へ呼び出されたと言う。
校長は相手のことは咎めないまま、久美の暴力性は異常だと言ったそうだ。それで、病院で精神異常がないかを調べることと、怪我をさせた各生徒の家に行って謝罪することを求められたと、久美のお母さんは腹立たしげに言った。
普段はおとなしい久美が、どうしてそこまでしたのかを考えて欲しいとお母さんは訴えたそうだけど、校長はまったく聞く耳を持たなかったらしい。
この一方的なやり方に、久美のお母さんは納得が行かなかったし、久美も謝罪することを拒否した。その結果、久美は一週間の停学処分になった。
このいじめグループのリーダーというのがPTA会長の娘だったそうで、そのことと久美の処分は絶対に関係があると久美のお母さんは言った。
結局、停学処分が解けても、久美は学校へ戻ろうとしなかった。また、久美のお母さんもあんな学校へは行かせられないと思ったそうだ。
そんなとき、間の悪いことに久美が飼っていたウサギが死んだと言う。少し調子がよくなかったらしいけど、まさか死ぬとは思っていなかったので、久美には二重のショックとなったようだ。
久美はぼろぼろだった。それはそうだろうと思う。やること全部が裏目に出て、愛する者との間を引き裂かれてばかりだ。大好きだった父親を馬鹿にされて、久美が怒りを爆発させたからって、そんなのは当たり前だ。
四国から東京へ移って来たのは、不幸続きの娘を心機一転させるためだったと、久美のお母さんは言った。移動先に東京を選んだのは、東京だったら田舎のような権威主義はないだろうし、自分が働く先を見つけやすいと考えたからだそうだ。
だけどその新たな転校先で、久美は再びいじめに遭って居場所を失った。そのことを久美のお母さんが知っているのか確かめたかったけど、とてもそんなことは聞けなかった。
わたしは久美が父親のことを話してくれなかった理由がわかったような気がした。これまで久美は片親ということで嫌な想いをさせられて来た。だから、そんな話はしづらかったのに違いない。それに海で亡くなった父親の話など、誰にも喋りたくなかっただろう。わたしだって同じ立場だったら、絶対に誰にも本当のことは話さない。
「学校なんか無理に行かなくたっていいんだよ」
兄貴がぽつりと言った。
「人間、学校なんか行かなくたって生きていけるし、学校よりもっと大事なことが、世の中にはいっぱいあるんだ。オレは今回の旅で、それを学ばせてもらった。だから、オレ、久美さんにもそのことを教えてあげようと思ってんだ」
わたしは心底兄貴をかっこいいと思った。もう、ハンバーグを横取りされたって怒ったりしない。
兄貴の言葉には、そこにいるみんなが感動したようだった。特に久美のお母さんは目頭を押さえながら兄貴の手を取って、よろしくお願いしますと頭を下げた。
兄貴はどぎまぎした様子だったけど、わかりましたと言った。
表で車の音がした。と思ったら、間もなくして呼び鈴が鳴った。政吉さんが玄関に出ると、二人の警官が立っていた。政吉さんの電話に応じて来てくれたようだ。
尚子さんと久美のお母さんは玄関へ行ったけど、残ったわたしたちは廊下に隠れて、三人と警官たちとの話を盗み聞きした。
政吉さんたちは代わる代わる必死に事情を訴えていた。だけど、警官たちの方には少しも緊迫感がない。淡々と聞くべきことを聞きながら、遺書がないのであれば、そんなに心配しなくていいと、無理に三人をなだめようとしていた。
わたしは飛び出して、警官たちに久美の手紙を見せた。そして、この手紙の文面は別れを告げているように見えると訴えた。
手紙を読んだ警官たちは、わかりましたと言うと、パトカーを巡回させて辺りを調べてみると約束した。それから、その手紙を持って行こうとしたので、わたしは慌てて手紙を取り戻した。
警官たちが帰ると、政吉さんは納得できない様子で、こがぁなったら山狩りぜ!――と言った。
「久美ちゃんはな、たぶん山ん中へ入って行きよったんよ。ほんなん、パトカーで道路走ったかて見つかるわけあるかい。わし、町内会長ん所行って、みんなで山狩りするよう頼んで来うわい」
久美が一人で山に入る。それがどういうことかは誰にでもわかる。まさかと思いながらも、わたしは政吉さんの言葉を否定できずにいた。みんなも緊張が走ったように顔を強張らせている。久美のお母さんが泣き崩れると、政吉さんは困惑を見せたけど、そのまま言葉もかけずに出て行った。
尚子さんは久美のお母さんの傍へ行くと、あの人が言ったのは悪い意味ではないと慰めた。それから時計を見て、何か食べておこうと言った。
「こがぁなときやけん、食べる物はしっかり食べとかんとな。今からおにぎりこさえるけん、あんたらも手伝いや」
尚子さんが和美さんたちに声をかけて台所へ向かうと、二人ともその後に続いた。
本当は尚子さんだって動揺しているに違いない。だけど、わざと気丈に振る舞ってみんなを鼓舞しているのだろう。
久美のお母さんは涙を拭くと、わたしと兄貴を自分たちが泊めてもらった部屋へ案内した。それから自分もおにぎり作りを手伝いに行った。
悲しくても泣いてばかりはいられないし、じっとしているのもつらいに違いない。久美のお母さんの後ろ姿を見送ったわたしは、胸が締めつけられた。
部屋の隅に置かれた久美たちの荷物の傍で、わたしと兄貴は黙って座っていた。
間もなくすると、久美のお母さんがお盆におにぎりとお茶を載せて運んで来てくれた。尚子さんたちは急いでおにぎりを食べたあと、もう一度久美を探しに出るそうで、わたしたちにはここで待機するようにとのことだった。
わたしたち三人は黙っておにぎりを食べた。本当はおにぎりなんて食べる気分じゃなかったけど、何もしないでいると気が滅入ってしまう。
わたしは少しでも久美のお母さんの気持ちを和ませようと、久美がタコさんウィンナーを食べたがっていた話をした。お母さんは少し微笑むと、そんなことを言われてたような気がすると言った。でもすぐに涙ぐむと、おにぎりを口に頬張ったまま泣き出した。
わたしと兄貴はお母さんを慰め、きっと久美は見つかるからと励ました。だけど、本当はわたしだって不安でいっぱいだった。
おにぎりを食べ終わっても、わたしたちにはすることがなかった。見知らぬ土地で何をすればいいのかわからないし、未成年のわたしたちにできることなど何もなかった。
傍らに置かれた久美たちの荷物の中には、畳まれた久美のカーディガンもあった。昼間は暖かいので着なかったのか、そんなことを考える余裕もなかったのかはわからない。でもこのカーディガンには、久美の気配の余韻が残っていた。
「久美、戻って来てよ……」
わたしは久美のカーディガンを抱きしめてつぶやいた。
そのとき、わたしの目に留まった物があった。それは一本の長い髪の毛で、カーディガンの肩の辺りに絡まるようにあった。
きっと久美の髪の毛に違いない。その髪の毛を指で摘み取ると、わたしは無意識にその髪の毛に話しかけた。
「ねぇ、あなたの神さま、どこにいるの? 知ってるなら教えて」
「お前、何言ってんだ? 大丈夫か?」
兄貴が怪訝そうに言った。久美のお母さんも心配そうにわたしを見ている。だけど、わたしの目に二人は映っていない。わたしが見つめているのは、久美の髪の毛だけだった。
「わたし、あなたの神さまに会いたいの。お願いだから、神さまに会わせて」
わたしは必死だった。藁にもすがると言うけれど、髪の毛にもすがる想いだ。
同じ言葉を繰り返しつぶやいていると、急にひどいめまいがして、身体を起こしていられなくなった。倒れるように畳の上に横になっても、世界はぐるぐる回り続けている。
「おい、春花。どうした?」
「春花ちゃん、しっかりして!」
兄貴と久美のお母さんの声が聞こえた。二人がわたしの身体を揺らすのもわかった。だけど、わたしには二人がどんどん遠くなって行くように思えた。やっぱり病み上がりで旅を強行したのが悪かったのか。こんなときに、こんなことになるなんて最悪だ。
わたしは気持ちが悪くなって目を閉じた。それでも身体が回り続けているようで、わたしはひたすら具合の悪さに耐えるしかなかった。
突然、わたしは悲しみの中に放り込まれた。久美のことを悲しんではいたけれど、その悲しみが暴走したみたいに、わたしを涙の海に沈めようとしていた。
あんまりつらくて、わたしは目を開けた。すると、世界はまだ回っていた。いや、そうじゃない。回っているのはわたしの方?
部屋の畳に寝ていたはずなのに、わたしは宙に浮いている。もしかして、わたしはまた死にかけているのだろうか。
不安になって周りを確かめようとしたけど、ぐるぐる回っているのでよくわからない。それでも、さっきまでいた部屋ではなさそうだし、体のわたしはどこにも倒れていないみたい。それに兄貴や久美のお母さんの姿もない。代わりに赤い物がいっぱい見える。わたしはどうなってしまったのだろう?
手足を伸ばしてバランスを取ると、ようやく回転は止まった。だけど、わたしは悲しみの風に流されている。
わたしは涙をこらえながら辺りを見回し、え?――と思った。
無数の赤い風船たちが、わたしと一緒に風に押し流されている。わたしはまたもや身体の世界に入り込んだようだ。
見つけた!
「みんな元気みたいだね」
わたしは明るさを装いながら、風船たちに声をかけた。でも何だか様子がおかしい。
風船たちはわたしにぶつかるたびに元気を分けてくれるけど、いつもの親しみのようなものが伝わって来ない。まるで、ぶつかったから仕方なしに元気をくれているだけみたいな感じがする。
わたしはぶつかって来た風船を抱き留めると、わたしが誰だかわかるかと尋ねてみた。すると風船は素っ気なく答えた。
――ワカンナイ。
え?――わたしは面食らった。わたしはみんなの神さまなのに忘れちゃったの?
抱き留めていた風船を手放すと、わたしは次の風船をつかまえて同じ質問をした。しかし、返って来た返事はさっきと同じだった。
何度か同じことを繰り返したけど、やっぱり風船たちの返事は変わらない。みんな、わたしのことを忘れてしまったようだ。
わたしは自分の体が他の誰かに乗っ取られたのではないかと疑った。
兄貴や久美のお母さんと一緒にいた部屋で、わたしは突然めまいを覚えた。ひょっとしたらあのときに何者かが、わたしの体を乗っ取ったのかもしれない。それで身体のわたしがその危機を伝えようとして、わたしをこの世界に引き込んだのか。そうだとすれば、この大変なときにとんでもないことだ。
前にこの世界を支配していた偽の神の正体は、幼い頃のわたしの心だった。だから風船たちは、わたしのことも神として認めてくれた。でも今回は、わたしは神として認めてもらっていないようだ。それは新たにこの世界を支配した者が、わたしとはまったく別の存在ということになる。
わたしは焦った。久美を助けねばならないのに、体を乗っ取られてしまったのでは何もできない。久美どころか自分さえもが危険な状態にあるわけだ。
どうしようと思っていると、ふわふわとビーチボールが近づいて来た。わたしの傍まで来ると、ビーチボールはクラゲに姿を変えた。
――オ前、ヨソモノ。ドッカラ来タ?
「何言ってんの? わたし、あんたたちの神さまよ? 忘れたの?」
クラゲの失礼な態度に、わたしは思わず強い口調で言い返した。するとクラゲは足の一本を、わたしの方に向けた。
「ちょっと、やめてよ! わたしは――」
ひゅっとクラゲの足が飛ぶように伸びて来た。わたしは反射的に両手で足の先を払いのけた。前とは違って、身体は軽くて素早く動ける。周りも水と言うより空気みたいだ。
すぐに他の足が攻撃して来たけど、同じように避けられた。さらに続く攻撃をかわしながら、わたしは自分の動きのよさに驚いた。以前のわたしだったら、絶対クラゲに食べられていただろう。
わたしは水泳は苦手だったけど、宙を泳ぐようにしてクラゲから離れた。身体はスイスイ前に進み、あっと言う間にわたしはクラゲを後ろに引き離した。
以前に動きが鈍かったのは、わたしの身体が死にかけていたからだろうか? よくわからないけど、きっとそうだと思う。それにしても、みんなどうしたのだろう? それに、この風が運んで来る悲しみはどういうことなのか?
確かに、わたしは久美を心配して悲しんでいる。でも絶望してるわけじゃない。きっと救えると信じている。なのに、この風が伝える悲しみは絶望に満ちている。これはわたしの悲しみじゃない。やはり、わたしとは別の何者かが、わたしに代わってこの世界を支配しているのに違いない。
また水晶たちの所へ行って、その向こうにいる新たな偽の神と対決するしか、この世界を取り戻すことはできないだろう。しかし、どうすれば水晶たちの向こうへ行けるのだろうか。
前のように偽の神が自分の一部であったなら、わたしが神の座へ行くことは可能だと思う。だけど、今神の座に居座っているのが、わたしとはまったく関係のない者であれば、わたしはそこへ行き着くことはできないだろう。
わたしは途方に暮れた。偽の神と対峙できなければ、対決などできない。それはこの世界を取り戻せないということだ。それはわたしにとっては、生きたままの死を意味する。そして、ここまで来て久美を助けることができないということでもあった。
急がなければ。何とかしなければ。そう思っても、焦ったりうろたえたりするばかりで名案は浮かばない。とにかく水晶たちの所へ行かなければどうしようもないけど、そのためには球の大蛇たちに頼まなければならない。でも、あの大蛇たちにしたって、今のわたしは神さまじゃないだろうから、言うことを聞いてもらえるとは思えない。
それでも他に方法は思いつかない。とにかく急がないと、わたしには時間がない。
わたしは浮かび上がると、悲しみの風が向かう先へ泳いで進んだ。
風船たちをどんどん追い抜いて行き着いたのは、あの炎を吐く双頭の大蛇たちの所だ。声をかけてみたけど、やっぱり大蛇たちはわたしが誰だかわからない。だけど、わたしは気にせずに先を急いだ。まず会わねばならないのはこちらの大蛇ではなく、球になった大蛇たちだ。
前と違って、今回は大蛇の胴体を通過するのに、それほど時間はかからなかった。大蛇の森を出ると、いよいよ球の大蛇たちだ。
わたしは青くなった風船たちをかき分けるようにしながら先を急いだ。そして巨大な三枚歯が目に入ると、球の大蛇たちに向かって叫んだ。
「ねぇ、わたしのことがわかる? わたしをまた白ヘビたちの所へ送って欲しいの。神さまのいる所よ!」
三枚歯はどんどん近づいて来るけど、球の大蛇たちからの返事がない。やっぱり、わたしが誰かがわからないとだめなのか。
わたしは何度も球の大蛇たちに呼びかけながら、三枚歯をくぐり抜けた。途端にあの激しい圧力と絶望的な悲しみが、わたしに襲いかかって来た。
いつものようにぐちゃぐちゃにされたわたしは、外へ吐き出されると、落胆と動揺に揉まれながら虹の森に着いた。
七色の光に満ちた森はとても美しかった。イガグリなど一匹も見当たらず、まるで楽園のような雰囲気だ。だけど、わたしはもうこの森の神ではない。今のこの世界では、わたしは単なる侵入者に過ぎず、誰の協力も得られない。それどころか敵としてクラゲたちから攻撃されるのだ。
今も森の美しさに慰めを求めていたのに、いつの間にか現れたクラゲたちが、わたしに足を伸ばして来た。
間一髪でクラゲの足をかわしたわたしは、森の中を泳いでクラゲたちから逃げた。
その傍らで風船たちはわたしになど興味がない様子で、夢中になって木にできた白い実を食べている。だけど、まったく普通の状態かと言うと、そうではないと思う。だって、この世界は悲しみに満ちているから。
わたしはそのことに疑問があった。どうしてこの世界を支配している者は、悲しんでいるのだろう? この世界を奪っておきながら悲しんでいるというのだろうか。
そもそも神の座である水晶たちの向こう側には、神以外は入れないはずだ。神ではない者が神を押しのけてこの世界を奪うことなど不可能なのに、わたしはこの世界を奪われた。どうして?
謎に苦しむわたしの頭の中で、発想の転換だと兄貴が囁いている。発送の転換? わたしは何か思い違いをしているのだろうか?
そう考えたとき、まさかとわたしは思った。
わたしは自分がこの世界の神だと考えていた。だけど、それが思い込みだったとしたらどうだろう。
わたしと同じように、他の人にだって風船たちの世界があるはずだ。見た目が似ているから間違えただけで、ここは最初から他人の世界なのかもしれない。
そう考えると、風船たちがわたしをわからないのも納得が行く。わたしはただの侵入者に過ぎないからだ。じゃあ、だとしたら、この世界は誰の世界なんだろう? それに、どうしてわたしは他の人の世界に迷い込んだりしたのか?
わたしは気持ちを落ち着かせ、どうしてこうなったのかを考えた。
確か、わたしは兄貴と久美のお母さんと三人で、久美たちが泊めてもらった部屋にいたんだ。そこでおにぎりを食べたあと、何にもすることがないし何もできなくて、それでどうしたっけ? えっと……、そうだ。カーディガンだ。久美のカーディガンを見つけて、わたしはそれを胸に抱いて、久美に戻って来てって言ったんだ。
わたしは、はっとなった。あのとき、わたしは久美のカーディガンに一本の髪の毛を見つけた。そして、その髪の毛にあなたの神さまに会わせてってお願いした。そしたら急にめまいがして、そのあと、この世界に入り込んだんだ。
久美の髪の毛に、あなたの神さまに会わせてってお願いしたら、わたしはこの世界に来た。これって、もしかして……。
――久美の世界だ!
そうか、そうだったのか。
ここが久美の身体の世界であるということは、久美はまだ生きているってことだ。だけど、この絶望に満ちた悲しみは不吉だ。
わたしは久美に自分が無事であることを伝えねばと思った。それがわかれば悲しみはいくらか癒えるに違いない。
気配を感じて振り返ると、クラゲがいた。攻撃をしようとしているのだろう。足先をわたしの方へ向けている。わたしは逃げずにクラゲに言った。
「あなた、この世界の神さまが悲しんでるのわかってる?」
クラゲは黙ってわたしに足を伸ばして来た。その足を避けながら、わたしはもう一度言った。
「あなたは神さまのために動いてるんだろうけど、今本当にすべきなのは、神さまを悲しみから救ってあげることじゃないの?」
――ヨソモノガ、何ヲ言ウ!
クラゲはさらに攻撃を続けた。わたしは逃げながら周りにいる風船たちにも叫んだ。
「あなたたちもだよ! みんなの神さまがこれだけ悲しんでるのに、あなたたち何もしないの? このままでもいいの?」
――ダッテ、ドウスレバイイノカ、ワカンナイモン。
風船たちの声が返って来た。反応があるということは、何とかなるかもしれない。わたしは希望を感じながら話しかけた。
「だけど、神さまが泣いてたら、あなたたちだって悲しくなるでしょ?」
――悲シイヨ。
「神さまを助けたいって思わない?」
――助ケタイ。
「わたしも、あなたたちの神さまを助けたいの。だから、力を貸して!」
――ドウスルノ?
「この風でみんなを動かしてる人がいるでしょ? その人にね、わたしを神さまの所まで運ぶように、みんなでお願いして欲しいの」
――神サマ、助ケテクレルノ?
「そうよ。だって、あなたたちの神さまは、わたしにとっても大切な人だから」
突然ゼリー状の物が、わたしの上に覆いかぶさった。あっと思ったときには遅かった。わたしはクラゲの足に捕まってしまった。風船たちを説得してたから油断をした。
わたしは逃げ出そうと藻掻いたけれど、ゼリーの中は動きにくい。完全にわたしを呑み込んだクラゲの足はしゅるしゅると縮んで、わたしと一緒に胴体の中へ収まった。そこにはあの口だけの生き物がうじゃうじゃといた。
クラゲの体を通して、外の様子が見えた。ゼリーの中からだから、風船たちがゆがんで見える。そのゼリーの中を、口だけの生き物が集まって来た。
もうおしまいか。わたしは久美を助けられなかったし、自分もこのまま死んでしまうのか。
何故か恐怖はなかった。ただ悲しみだけがあふれ出して来る。そのときゼリーの外から声が聞こえた。
――助ケテ!
――神サマヲ、助ケテ!
風船たちの声だ。
――オ願イ、神サマ、助ケテ!
――オ願イ、助ケテ!
それは大合唱とも言えるものすごい声だった。近くの風船たちだけでなく、遠く離れた風船たちもが叫んでいるようだ。
――助ケテ!
――神サマヲ、助ケテ!
風船たちが懇願しても、わたしの命は風前の灯火だ。だけど、口だけの生き物は近くまで来たものの、一向に襲いかかって来ない。と思ったら、わたしを包んだゼリーが動き、わたしはクラゲの胴体から外へ向かって移動した。
わたしを包んでいたゼリーが服を脱ぐように上に外れ、外へ伸びていたクラゲの足は、再びしゅるしゅると胴体に収まった。
「わたしを助けてくれるの? どうして?」
わたしはクラゲに尋ねた。いや、今は足がないからビーチボールか。ビーチボールは丁寧な言葉で答えてくれた。
――アナタガ、神サマヲ、想ウ気持チ、ヨクワカリマシタ。
「ほんと?」
――ホント?
そうだ、この世界の生き物たちには嘘がないから、本当という言葉は意味をなさない。
「いいの。それより、助けてくれてありがとう」
わたしはビーチボールを抱きしめた。ビーチボールからもうれしい気持ちが伝わって来る。
――ワタシカラモ、オ願イシマス。ドウカ、神サマヲ、助ケテ下サイ。
わたしはビーチボールに改めて感謝を伝え、行こう!――と風船たちに呼びかけた。向かう先は球の大蛇たちの所だ。
宙に浮かんだわたしは、風船たちを追い越しながら先へ急いだ。それでもわたしを包む風船たちの声は変わらない。すべての風船たちが、わたしを応援してくれている。
――コノ人ヲ、神サマノ所ヘ!
――コノ人ニ、神サマヲ、助ケテモラウノ!
巨大な二枚歯が見えた。球の大蛇だ!
「お願い! わたしをあなたたちの神さまの所へ運んで! わたし、あなたたちの神さまを助けたいの!」
風船たちの大合唱の中、わたしは懸命に球の大蛇に叫んだ。だけど、やっぱり大蛇からの返事はない。
二枚歯をくぐり抜けたわたしは、例によってぐちゃぐちゃにされながら、自分を神の元へ運ぶよう大声で叫んだ。
球の大蛇から吐き出されたわたしは、自分で泳ぐ力もなく、ぐるぐる回転しながら流されて行った。周囲では風船たちが、神サマヲ助ケテ!――と叫び続けている。
やがて風船たちの声は小さくなり、わたしは白いトンネルに流れ着いた。そう、ここはあの白ヘビたちのトンネルだ。球の大蛇たちは返事もしてくれなかったけど、結局はわたしの願いを聞いてくれたようだ。風船たちの応援が効いたのか、大蛇たちも神さまを助けたいと思ったのか。たぶん、その両方なのだろう。
一緒にトンネルに入った風船たちに、この先に神さまがいるのかとわたしは確かめた。風船たちは声を揃えて、ウンと言った。あとは何も言わないけど、風船たちの期待がひしひしと伝わって来る。
だけど問題はこれからだ。久美がいるのは、あの水晶たちの向こう側だ。神でなければ入れないあの領域に、わたしが入ることはできない。それなのにどうやって久美と意思の疎通をはかるのか。
答えが見つからないまま、わたしは先へ進んだ。風船たちの期待がわたしを焦らせるけど、風船たちに関係なく、わたしは久美を助けねばならないのだ。
水晶の洞窟にたどり着いたわたしは、そのままどんどん先へ進んだ。
やがてわたしは金色の水晶たちの空間に着いた。後方には金色の水晶たちと向かい合うように、銀色の水晶たちが並んでいる。
金色の水晶たちを前にしたわたしは驚いた。目の前には巨大なスクリーンがあって、大きな映像が映し出されている。これはわたしの世界では見られなかったものだ。
どういうことかと言うと、ここの水晶たちの表面に映像が映し出されていて、それら全体が一つの巨大な映像を作っているのだ。
この巨大スクリーンに映っているのは、バスの中のようだ。細い通路を挟んだ両脇に座席が並んでいる。この映像を映しているカメラは、通路の右側にあるようだ。
後ろはわからないけど、前方の座席には五、六名の人が座っている。座席の先頭に運転席があって、運転手らしき人の姿が見える。
正面から横の窓にかけて、外の景色が後ろへ流れて行く。時々画面が揺れ動くのは、バスの揺れだろう。
長細い三本の羽根がある大きな風車が見えた。確か、あれは風力発電の風車だ。このバスはどこを走っているのだろう。それに、どうしてこんな映像がここに映っているのだろうか。
後方の銀色の水晶たちが静かに輝きながら、バスの音を響かせている。と思ったら、突然稲妻の閃光が銀色の水晶たちの間に走り、誰かの声が辺りに響き渡った。
――姉やんは、どこまで行くんかな?
映像が左へ移動して、この映像を映しているカメラの左横、通路を挟んですぐ隣の座席が映った。そこには老夫婦と思われる、にこにこ顔のおじいさんとおばあさんがいた。
声をかけたのは、通路側に座るおじいさんだ。正面におじいさんがいるので、まるでわたしが話かけれられているみたいだ。
――灯台です。
久美の声だ! だけど、久美の姿は映らない。ほうかなと楽しげにうなずくおじいさんたちが映っているだけだ。おじいさんは続けて喋った。
――ここいらではあそこが一番有名なけんなぁ。ほんでも、あそこは灯台以外、なーんもないとこぜ。
――灯台からの夕日が見たいんです。あそこからの夕日はまっこときれいじゃて、おばあちゃんが教えてくれたけん。
――おばあちゃんがおるんかな。
――夕日見たら、おばあちゃん所へ行くんです。
――姉やんのおばあちゃんは、あそこの傍におるんかな。
久美の声は聞こえず、画面が小さく上下に揺れた。
――あんたん所の学校は、今日はお休みなんか?
今度はおばあさんが身を乗り出すようにして話しかけた。どこにいるのかわからない久美は、はいと小さな声で返事をした。
――どこの学校に行きよるんぜ?
また、おじいさんが尋ねた。久美は東京の学校だと答えた。いつの間にかおじいさんたちの顔からは笑みが消え、不審さが見えている。
――他の家族はどがぁしたんね? あんた一人ぎりなんか?
おばあさんが尋ねると、また画面が小さく上下に揺れた。
――うちが先に来たけんど、じきに母親が来ますけん。
――お父さんは?
――一昨年に亡くなりました。
おばあさんは悪いことを聞いたという顔になり、もう聞くのをやめた。
――まぁ、一人は危ないけんな。気ぃつけなはいや。
おじいさんが言うと、おばあさんも言った。
――ほうよほうよ。世の中、悪いこと考える人間が多いけんな。油断したらいかんぞなぁし。
――だんだん。ご心配ありがとうございます。
だんだんという言葉を聞いたからか、おじいさんたちはまたにこやかな顔になった。
突然、わたしの身体がガクガク揺れた。映像も声も消えて真っ暗闇になると、兄貴の声が聞こえた。
「おい、しっかりしろ! 春花、春花!」
目を開けると、そこは久美が泊めてもらった部屋の中だった。兄貴がわたしの顔をのぞき込んでいる。その後ろで、久美のお母さんが心配そうにしていた。
「あれ? わたし……」
わたしが身体を起こすのを手伝いながら、兄貴がおろおろした様子で言った。
「大丈夫か? 病院へ行こうか?」
自分の状況が理解できたわたしは、兄貴に叫ぶように言った。
「お兄ちゃん、久美の居場所がわかったよ!」
「何言ってんだよ? やっぱり病院へ行こう! おばさん、この近くに病院は――」
「違うんだってば! わたし見たの。久美はね、どこかの灯台へ向かうバスの中にいるの。風車が見える所を走ってた!」
兄貴はぽかんとわたしの顔を見た。でも久美のお母さんは、藁をもつかみたい気持ちなんだろう。今のは本当なのかと、わたしににじり寄った。
わたしがうなずくと、それはきっと佐田岬の灯台へ向かうバスに違いないと、久美のお母さんは言った。
どういうことですかと兄貴が尋ねると、久美のお母さんは、この辺りで夕日で知られる灯台は、佐田岬の灯台だと言った。また岬がある佐田岬半島には、風力発電の風車がたくさんあると説明した。
それでも兄貴はまだ信じられない表情だ。
「それにしたって、何だってこいつがそんなものを見るんですか?」
「ほれはわからんけんど、春花ちゃんと久美の間には、何か特別な関係があるみたいなんよ。春花ちゃんが久美に描いてくれた絵ぇ、あたしも見せてもろたけど、あがぁな絵ぇが描けるんは、二人が特別な何かでつながっとるとしか思えんけん」
「春花が描いた絵? おい、春花。お前、どんな絵を描いたんだよ?」
わたしは兄貴に顔を向けずに言った。
「今はそんなこと説明してる暇はないよ。それより、おばさん。急いで久美を追いかけないと大変なんです」
「他にも何ぞ見えたん?」
顔を強張らせた久美のお母さんに、わたしは戸惑いながら言った。
「久美は……、久美は灯台で夕日を見たら、おばあちゃんの所へ行くって言ってました」
「おばあちゃんとこ? 久美はそがぁ言うたん?」
「わたしに見えたのは、久美が灯台へ行くバスの中で、一緒に乗ってたおじいさんやおばあさんと喋ってるところなんです。その会話の中で久美はそう話してました」
真っ青になった久美のお母さんは、尚子さんを呼びながら台所へ向かった。しかし、尚子さんたちは久美を探しに出ようとしていたようで、返事の声は玄関から聞こえた。
わたしが急いで玄関へ出ると、兄貴も後ろからついて来た。そこへちょうど久美のお母さんも来た。和美さんと八重さんは先に出たらしく、玄関には尚子さんだけがいた。
「尚子さん、久美がおった。久美が見つかったんよ!」
「え? ほんまに?」
尚子さんは驚いた様子で、どこで見つかったのかと尋ねた。久美のお母さんは興奮したまま、今はバスの中らしいと言った。
「あの子は佐田岬の灯台へ向ことるんよ。ほじゃけん、すぐに追いかけたいんよ」
「岬の灯台? なんでそがぁなことがわかるん?」
「春花ちゃんが見たんよ。あの子がバスで岬に向ことるんを、春花ちゃんが見たんよ」
「春花ちゃんが見た? どがぁして見たん?」
尚子さんがわたしに顔を向けた。
わたしは風船たちの世界のことは話さず、気を失っている間に久美がバスで岬へ向かうところが見えたとだけ言った。
風船たちの話をしなかったのは、そんな話など信じてもらえないだろうし、頭がおかしくなったと思われるからだ。でも、意識を失っている間に久美の姿を見たという話にしても、簡単に信じてもらえるものではない。
案の定、尚子さんはわたしの話を否定はしなかったが、受け入れてくれたわけではなさそうだった。うーんと難しい顔をしたまま、何と答えればいいのか悩んでいる様子だ。
久美のお母さんは、わたしと久美の間には特別なつながりがあるみたいだと言い、わたしが久美に描いた絵の説明をした。
兄貴はへぇと感心した様子で話を聞いていたけど、それぐらいのことでは尚子さんはわかってくれないみたいだった。ほうなんかと言ってくれはしたけど、やっぱり難しい顔は変わらない。
表で車の音がした。政吉さんが戻って来たようだ。
久美のお母さんが玄関へ向かったので、わたしたちも後に続いた。
しばらくして現れた政吉さんは、わたしたちを見るなり腹立たしげに言った。
「会長のやつ、まったく話にならん! そがぁなことは警察に任せときゃええんぜ――言うてな、ろくに話を聞こうとせんのぜ、あのくそダヌキめ!」
「政吉さん、車出して!」
いきなり久美のお母さんに懇願され、政吉さんはきょとんとなった。
「どがぁした? 車でどこ行くんぜ?」
「岬や! 佐田岬の灯台へ行くんよ! 久美はそこへ行こうとしよるんよ!」
「岬の灯台? なんでそがぁなことがわかるんぜ?」
「この子が、春花ちゃんが見たんよ!」
久美のお母さんは尚子さんに言ったのと同じ説明をした。だけど、政吉さんの反応も尚子さんと同じだった。
「気持ちはわかるけどな。そげな夢の話信じてどがぁするんぜ。あげな遠い所へ行ってしもたら、その間に警察から連絡が来ても困ろ?」
「ほやけど、あの子は岬におるんよ。夕日が沈んだら、あの子は、あの子は……」
泣き出して喋れなくなった久美のお母さんを、政吉さんと尚子さんは慰めた。それでも車を出すとは言ってくれない。
二人は困ったような目をわたしに向けると、久美のお母さんを台所へ連れて行った。残されたわたしは兄貴を見た。兄貴は何が何やらよくわからないという顔をしている。
「お兄ちゃんも、わたしのこと信じられない?」
「まぁ、そうだな。いきなりあんなことを言われたら驚くし、それを信じろって言われたって困るというのが正直なとこだな」
「やっぱり、お兄ちゃんもそうなんだ」
わたしがうなだれてべそをかくと、だけどな――と兄貴は言った。
「信じる信じないじゃなくってさ、面白いじゃないか」
「面白い? 久美が死ぬのが面白いの?」
わたしが顔を上げてにらむと、そういう意味じゃないと兄貴は言った。
「お前にとっては間違いないことであっても、他人にとっては不確かな話だろ? その不確かな話に乗るって言うのは冒険だ。しかも、今の状況だと一か八かってやつだ。まぁ、言ってみれば賭けだよな。そういう意味で面白いって言ったんだ」
「お兄ちゃんが言ってること、わかんない」
むくれるわたしに兄貴は続けて言った。
「わかりやすく言えばさ、オレはお前と一緒に岬へ行くってことだ。お前を信じるって言うより、お前が言うことに賭けてみるってことだ」
わたしは兄貴に抱きついた。兄貴はうろたえていたけど、そっとわたしを抱き返すと、お前、こんなに痩せちまったんだな――とぽつりと言った。
兄貴はわたしが病み上がりだったことを思い出したようで、わたしが離れたあとも神妙な顔のままだった。
「親友を助けるために、お前はそんな体でここまで来たんだな。思えば、あの子からの手紙を読んだときに、あの子が危ないって思ったのも、お前とあの子に特別な何かがあったからだろうな」
「お兄ちゃん……」
「春花、オレがお前の願いを叶えてやるよ。オレがお前を佐田岬へ連れて行ってやる」
お兄ちゃん、かっこいい。かっこいいよ。だけど、車もないのにどうやって岬へ行くつもりなんだろう。
そのことをたずねると、それだよなと兄貴は言った。
「そもそも佐田岬の灯台がどこにあるのか、オレたち知らないもんな」
兄貴は荷物から地図を取り出した。夕日を見るって言うから、佐田岬は伊予灘より西にあるはずだ。
二人で愛媛の地図を調べると、西の端に九州に向かって突き出した細長い半島があり、そこに佐田岬半島と書かれていた。つまり、佐田岬はこの半島にあるってことだ。
わたしたちは一緒に指を半島の先へ動かした。そこには灯台のマークがあり、佐田岬灯台と書かれてある。わたしと兄貴は顔を上げて微笑み合った。
問題はここから佐田岬までどうやって行くかということだ。兄貴は伊予灘から佐田岬までのおよその距離を測った。
「おおよそ六十キロか。車だったら一時間で行ける距離だけど、歩いたらどんだけかかるんだ? 一時間に四キロ歩いたとして……、十五時間?」
兄貴は無表情にわたしを見て言った。
「無理だな。絶対に無理」
「え? お兄ちゃん、オレがお前の願いを叶えてやるって言ったじゃん! あれ、嘘だったの?」
「嘘じゃない。あのときは、本気でそう思ってた。だけど、今は事情が変わった。オレたちに車はないし、列車もあそこまでは走ってない」
「久美はバスに乗ってたんだよ? 近くまで行けばバスがあるよ」
わたしが必死に訴えると、兄貴は列車の時刻を調べてくれた。
佐田岬に一番近い駅は八幡浜駅だ。列車でここまで行って、そこからはバスかタクシーで行けばいい。わたしはそう考えていたけど、次に八幡浜へ向かう列車の時刻は夕方の四時三十八分だった。これだと八幡浜に到着するのが六時四分になる。日が沈むのは五時半頃だ。間に合わない。
「お兄ちゃん、タクシーで行こう!」
「タクシー? ここから佐田岬までタクシー代がいくらかかるのかわかんないぜ」
「お兄ちゃん、バイト代あるんでしょ? それにここまでヒッチハイクで来たんだから、その分のお金も残ってるじゃない」
兄貴は少しお金が惜しそうな顔を見せたが、覚悟を決めたみたいだ。わかったよと言うと、スマホで近くのタクシー会社を調べた。
だけど、この辺りの地理がさっぱりわからないから、どのタクシー会社が近いのかがよくわからない。わかったのは、このすぐ近くにはタクシーはないということだ。
兄貴が悪戦苦闘しながらいろいろ調べた結果、伊予市という所のタクシーを呼ぶことになった。しかし、タクシー会社に電話をしても、どこへ迎えに行けばいいのかと聞かれ、兄貴は返答に困った。それで伊予灘駅と答えると、次に行き先を聞かれた。
佐田岬ですと言うと、灯台を見に行くのかと聞かれた。そうですと答えると、灯台の所までは車が入れないので、手前の駐車場で降ろすことになると言われた。灯台はそこから二キロほど歩かなければならないそうで、普通に歩けば三十分ぐらいはかかるようだ。
伊予灘駅から佐田岬の駐車場までは、どれぐらいで行けるのかと尋ねると、一時間半ほどだという答えが返って来た。歩く道を合わせれば、全部で二時間ということだ。それは兄貴の計算よりも一時間長かった。
兄貴はわたしを見た。わたしがうなずくと、兄貴はお願いしますとタクシー会社に言った。すると、タクシーが向こうからこっちへ来るまで三十分ほどかかると言われた。佐田岬までの移動時間を合わせると二時間半だ。
兄貴の時計を見ると、もう三時になろうとしていた。ぎりぎり日没の時間だ。どうなるかはわからないけど、ここは頼むしかなかった。
それで、お願いしますと改めて向こうに伝えた兄貴は、え?――と言った。少し相手の話を聞いたあと、兄貴は困った顔でわたしを見た。
「今、車が出払ってて、こっちへ来るのに一時間ほどかかるって言うんだけど、どうしようか」
「一時間?」
それでは佐田岬に着けるのは六時になってしまう。もう日が沈み終わったあとだ。
わたしが泣き出したので、兄貴はまた後で電話しますと言って電話を切った。それからわたしに申し訳なさそうに言った。
「岬までだいたい六十キロぐらいだったから、ぶっ飛ばして行けば一時間で行けると思ったんだけど、実際は違ってたみたいだな」
兄貴の言い訳なんか聞きたくなかった。列車もだめ。タクシーもだめ。もうわたしたちには日が沈むまでに佐田岬へ行く手段がない。
「久美が死んじゃう……。久美が死んじゃうよ……」
わたしは泣きながら家の外へ飛び出した。追いかけて来た兄貴はうろたえながらわたしを慰めようとした。だけど、久美が岬にいるのがわかっていながら、助けることができないのだ。いくら慰められても、その悔しさと悲しさが収まることはなかった。
そのとき、わたしたちの後ろで車が止まる音がした。振り向いた兄貴が、あ――と言った。
「どがいした? まだ見つからんのか?」
聞き覚えのある声に、わたしは顔を上げた。すると、そこには軽トラックが停まっていた。運転席から顔をのぞかせていたのは、中村さんだった。
久美を追って
わたしは中村さんに駆け寄った。
「お願いします! わたしたちを佐田岬の灯台まで連れて行って下さい!」
「岬の灯台? 何の話ぜ、ほれは?」
「岬の灯台に久美がいるんです。日が沈むまでにそこへ行けなかったら、久美が……、久美が……」
わたしがまた泣き出すと中村さんは困惑して、何があったのかと兄貴に尋ねた。それで兄貴が事情を説明したけど、やっぱり中村さんも何を言ってるのかという顔を見せた。
だけど、中村さんに連れて行ってもらうしか方法がない。この軽トラックで運んでもらったなら、灯台まで二時間で行ける。ぎりぎりで久美を助けられるかもしれない。
「お願いします! お願いします! わたし、中村さんの言うこと何でも聞きますから、どうか、わたしたちを灯台まで運んでください!」
「そがぁ言われても、わしはまだ仕事が残っとるんよ。ほれ、後ろに荷物積んどろ? ほれをな、これから届けないけんのよ」
申し訳なさそうな中村さんに兄貴がたずねた。
「それは何ですか?」
「配達せんといけん物よ。配達行くやつが持って行くんを忘れよったんよ」
「じゃあ、それを届けたあとでもいいから、春花だけでも佐田岬の灯台まで運んでやってもらえませんか?」
「えぇ? これを届けたあとにか?」
「お願いします」
兄貴も必死になって頼み、わたしも一緒になって頼んだ。こうしている間にも、時間は刻一刻と過ぎて行く。
中村さんは何度も腕時計を見ながら、弱ったのぅ――と言った。
わたしは涙に濡れた目で、じっと中村さんを見つめた。中村さんはわたしの視線に耐えられなくなったようで、わかったわい――と言った。
「姉やんらと知り合うたんも何かの縁じゃろ。わしは縁を大事にする人間やけんな。岬まで運んだらええんじゃな?」
「信じてもらえたんですか?」
「信じたわけやないけんど、そがぁに真剣に頼まれたら、力貸さんわけにいくまい。ほんでも、ちぃと待ってくれよ。一応、職場に連絡しとかんといけんけんの」
「ありがとうございます! ありがとうございます!」
地獄に仏とはこのことだろう。わたしは感謝の気持ちでいっぱいだった。兄貴も喜びに顔を輝かせ、何度も中村さんに頭を下げた。
中村さんは照れながら職場に電話をし、急に熱が出て来てインフルエンザかもしれないから、荷物を届けるのはやめて、このまま病院へ行くと話していた。
電話を切った中村さんは笑顔を見せて、ほんなら行こわい――と言った。
軽トラックは後ろの荷台に荷物が載っているので、兄貴はわたしと一緒に助手席に乗せてもらった。と言っても、先に乗った兄貴の左足の上に、わたしの右のお尻を載せた格好で無理やり乗り込んだ形だ。それでもわたしが病気でやつれていなければ、きっと車のドアは閉まらなかっただろう。
本当はこんなことはしてはいけないと、わたしたちもわかっているし、中村さんもわかっている。だけど中村さんが時計を見て、悠長な走り方では間に合わないからと、兄貴にも助手席に乗るように言った。荷台に乗ったのでは危ないということらしい。
二人がぎゅうぎゅう詰めの状態だから、シートベルトも締められない。何かがあったら絶対に危険だし、警察に見つかったら捕まるのは間違いない。
「警察に捕まったら、ほれまでやけんの。そがぁならんよう祈っといてや!」
こんな状態なのに、中村さんはにこやかに言うと、軽トラックを発進させた。
軽トラックは海沿いの道をエンジンを唸らせながら走って行く。前をゆっくり走る車があると、中村さんは構わずその車を追い越した。
車体がガタガタ振動するので、車がこのままバラバラになってしまうんじゃないかと、わたしは心配になった。だけど兄貴はすっかり興奮してしまい、子供のようにはしゃいでいた。これは遊びじゃなくて、久美の命が懸かっていることなのに、何考えてんだか、まったく。
「オレ、ほんとだったら、今頃は中間テストの勉強をしているはずだったんです。それなのに、ここでこんなことしてるなんて信じらんないや!」
車の振動やエンジンの唸り声に負けないように、兄貴は大声で中村さんに話しかけた。
中村さんは笑いながら、お前は日本一の悪ガキだと言った。
「けんど、わしにしたかて、自分がこがぁなことしよるんが信じられんぜ。普通に考えたら、絶対にせんもんなぁ」
「中村さん、今日初めて会ったばかりのオレたちに、どうしてここまでしてくれるんですか?」
お前がそれを言うのかとばかりに、中村さんは横目でじろりと兄貴を見た。
「兄やんや姉やんが必死で頼むけん、仕事放っぽり出して兄やんらを運びよるんじゃろがな」
「それはそうなんですけど……、普通はどんなにお願いしたって、こんなこと引き受けてくれないじゃないですか。実際、さっきの家のおじさんたちには、全然相手にしてもらえなかったんです」
「まぁ、ほれはほうじゃろ。ほれが普通ぜ」
「でも、中村さんは引き受けてくれたじゃないですか。それはどうしてなんですか?」
ほうじゃなぁと中村さんは前を見ながら言った。
「さっきも言うたように、友だちのために東京から来た兄やんらが、あんだけ必死に頼んだいうんが一番の理由なけんど、わしはな不思議な話を信じる質なんよ」
「春花のことですか?」
兄貴がわたしを見ると、ほうよほうよと、中村さんも横目をちらりとわたしに向けた。
「さっきは仕事中やったけん、よしわかったとは言えなんだけんど、本音言うたら、兄やんらの話には大いに興味がそそられよったかい」
何だかうれしくなって顔を見交わすわたしたちに、中村さんは話を続けた。
「こがぁな話、テレビや雑誌じゃったらお目にかかることはあるけんど、自分の身近にゃあめったにないけんな。ほやけん、さっきのわしは大けな葛藤の中におったんぜ」
「佐田岬に行くべきか行かぬべきかってですか?」
兄貴が尋ねると、ほうよほうよと中村さんは言った。
「言うても、わしの中では答えは決まっとったがな」
「だったら、初めからそう言ってくれればよかったのに」
わたしが口を尖らせると、ほうもいくまいと中村さんは言った。
「一応、郵便局で雇てもろとる身やけんな。そがぁ簡単に仕事を抜けるわけにはいかんじゃろ? ほんでも、人の命が懸かっとるんじゃけん、知らんぷりはできまい。わしとしては職場への義理立てをした上で引き受けたわけよ」
「でも、オレたちが諦めてたら、どうしたんですか?」
「ほんときゃあ、お前ら友だちを見捨てるんか!――て活を入れとったぜ」
喋りながら中村さんは笑った。
兄貴はかなりの変わり者だけど、中村さんも相当な変わり者のようだ。でも、お陰でわたしたちは佐田岬まで運んでもらえる。変わり者万歳だ。
「ところで姉やんは、今回みたいな不思議なことはよくあるんかな」
急に話を振られて、わたしはうろたえた。
「え? それは……、よくではないんですけど……」
「よくではないけど、あるんか?」
はいとわたしがうなずくと、ほぉと中村さんは目を輝かせ、その話を聞かせて欲しいと言った。兄貴も驚いたような顔で、それは初耳だと言った。
わたしは風船たちのことを話そうかと思った。だけど、それは妄想だと言われるような気がしたので他の話をした。子供の頃にスーパーで迷子になったときの話や、久美の絵を描いたときの話、それと自分が生まれる前に母に会いに来たときの話だ。
中村さんは興味深げに話を聞いてくれた。でも、幼い妹を放ったらかしにしたのかと中村さんに言われた兄貴は、自分は妹とスーパーで遊んだ覚えはないとうそぶいた。
久美に描いた絵の話は、中村さんは驚いていたが、兄貴は先に聞いていたので、特に反応はなかった。だけど、生まれる前に母に会いに来たという話には、本で読んだのと同じだと兄貴は興奮して、中村さんにその本の説明をした。面白いことがあるもんぜと中村さんがうなずくと、他の連中はこんな話を馬鹿にすると兄貴は愚痴を言った。
中村さんは笑うと、そがぁなやつらは放っておけと言った。常識と言われることしか頭にない者たちは、自分で考えることができない可哀想なやつらだそうで、中村さんの意見には兄貴も強く同意した。
病院で見た久美の夢も、二枚舌などの声が聞こえたことを伏せて話すと、二人とも絶対にその夢は久美からのメッセージだと思うと言った。そして久美が佐田岬にいるという話も、絶対に間違いないと口を揃えて断言してくれた。
兄貴と中村さんの支持が得られたことはうれしかった。だけど、西に傾いた太陽を見ると不安が募った。
間に合うだろうかと心配すると、中村さんはわたしを励まし、さらにアクセルを強く踏んだ。
エンジンの唸りは悲鳴のように聞こえ、車体はさらにひどく振動した。もし何かにぶつかってしまえば、わたしたちの方が死んでしまう危険があった。さすがの兄貴も言葉が出せず、わたしを抱きかかえる腕がわたしを締めつけた。
わたしもとても怖かったけど、絶対助けに行くからねと、心の中で久美に念じ続けた。
しばらくすると軽トラックは海辺の道から山の道に入った。すると車が増えて来て、海辺の道にはほとんどなかった信号で、道路が少し混み始めて来た。
ただでも時間はぎりぎりなのに、前が詰まっているから中村さんもどうしようもない。軽トラックは勢いを失くして、ゆるゆる進んだ。わたしはいらいらし、兄貴もしきりに腕時計を確かめた。だけど、中村さんはこんなものだという顔だ。
それでも、しばらくして半島への道へ入ると、道路はスカスカになった。佐田岬へ向かう車はほとんどないようだ。元気を取り戻した軽トラックは再び唸りを上げ、武者震いを続けながら走り始めた。
車は山の中を走っているようだったが、時折きれいな海が眼下に広がった。兄貴は少しだけ感動の声を上げたけど、わたしには景色を眺めている余裕はなかった。
わたしが気にしているのは、正面に見える太陽だ。あの太陽が沈みきる前に灯台まで行き、そこにいる久美を捕まえなければならない。美しい夕日は命の砂時計のようだ。
兄貴が前方を指差して、あ――と言った。見ると、丘の上に風車があった。わたしはそれが久美がバスの中から見た風車ではないかと思った。だけど中村さんが言うには、風車があるのは一カ所じゃないらしい。それでもこの同じ道を久美が通ったに違いないと、わたしは確信した。
やがて軽トラックは海辺の町へ入った。ここは三崎町という所で、佐田岬半島の残りの部分がまだ西の方へ伸びている。太陽はかなり下がっていて、半島の丘陵に隠れそうだ。
心配するわたしに、あと三十分ほどで佐田岬の駐車場に着くと中村さんは言った。そのとき、突然サイレンが鳴った。
「うわっ、しもた。お巡りに見つかってしもた」
通り過ぎた交差点の陰に、ミニパトカーがいたようだ。わたしと兄貴の二人が助手席にいるのが見つかったらしい。
『そこの軽トラック、直ちに止まりなさい!』
マイクで喋る女性警察官の声が、後ろから攻撃を仕掛けるように飛んで来る。だけど、ここで止まったらおしまいだ。
わたしと兄貴は中村さんを見た。中村さんは困惑のいろが隠せない。それでも中村さんは心配するなと言った。
「前をふさがれん限り大丈夫ぜ。岬の駐車場までは絶対に運んじゃるけん」
「だけど、逃げたら中村さんの罪が重くなるんじゃ……」
兄貴が心配そうに言ったが、中村さんは平気な顔で応じた。
「人を犯罪者みたいに言いなや。軽トラの助手席に二人乗せたぎりの話じゃろが。あとでお巡りに捕まるんは一時の恥やが、今捕まって姉やんの友だちを救えんかったら、一生の恥ぜ」
何ていう人なんだろう。今日初めて会ったばかりなのに、わたしはこの中村さんという人の気概に頭が下がるばかりだった。
思えば、久美を救いたい一心で、普通じゃ誰もやらないようなことを始めたら、いろんな人が力を貸してくれた。トラックの運転手さんたちもそうだし、兄貴だってそうだ。みんな自分とは関係のないはずのことに、こんなに一生懸命になってくれる。
わたしは感激しながら、自分が不思議な力に導かれているような気がしていた。だから絶対に久美は大丈夫だという気持ちがあるけれど、夕日が沈むまでの時間はあまり残されていない。それを考えると、本当に大丈夫なのかと不安になった。
車が丘陵に近づくと、太陽は丘陵の陰に隠れて見えなくなった。でも西の空は茜色に染まっている。あの空を久美は灯台の近くから眺めているのだろう。だけど、夕日が沈んでしまったら――
泣きそうになるのをこらえながら、わたしは自分の想いが久美に届くよう願った。あの光の存在にも、どうか久美を助けて欲しいと頼み続けた。それでも不安なわたしは懐に仕舞った久美の手紙に手を当てた。手紙には、久美が泊まった部屋で見つけた、久美の髪の毛を挟んである。
わたしは髪の毛にもう一度、神さまの世界へ連れて行って欲しいとお願いした。久美の様子が知りたかったし、久美と一緒にいたかった。
だけど車はガタガタ揺れるし、後ろでは停車を求めるミニパトカーの大きな声が続いている。不安げな兄貴はそわそわしながら前を向いたり後ろを向いたりするから、そのたびにわたしは体を押されて気持ちを集中できない。
町を抜けると道が急に狭くなった。その道を中村さんは慣れたように軽トラックを素っ飛ばして行く。道にはカーブも多く、わたしは何度もひやりとさせられた。とても久美の世界へ誘ってもらうどころではない。前から対向車が来たらどうなるかと思うと、気が気でなかった。ジェットコースターが大好きな兄貴も、わたしに抱きついて固まっている。
夕日は隠れて見えないけれど、さっきよりも下へ移動しているはずだ。光が当たっている所は暮色に包まれ、影になっている所はどんどん薄暗くなっていく。
もしかしたら間に合わないのだろうか。泣きそうになったわたしの中で、幼いわたしが叫んでいる。
――あきらめたらだめ! がんばれ!
その隣にいる、体のわたしもわたしを励ました。
――わたしもお手伝いします。だから、あきらめないで。
急に眠気に襲われたわたしは、周りの騒ぎが気にならなくなった。ぼんやりして来た頭で、わたしは久美の髪の毛に、もう一度あなたの神さまの世界へ誘って欲しいと願った。
すると、頭の中が次第にぐるぐると回り出し、わたしは自分がどこにいるのかわからなくなった。
回転は頭の中だけでなく、わたし自身が回り出していた。わたしは回りながら風にどこかへ運ばれているみたいだ。
やがて風が静かになったとき、わたしの回転も止まった。目を開けると、わたしは水晶の洞窟にいた。後ろを振り返ると、地面に白ヘビたちのトンネルがあった。どうやら、久美の世界に入り込むことができたらしい。
いきなり水晶の洞窟に着いたのは、きっと久美の髪の毛も、自分の神さまを助けたいに違いない。あるいは久美の身体が、わたしをここまで導いてくれたのかもしれない。久美の世界全体が久美を助けたいと願っているのだと、わたしは感じていた。
今度こそ久美に会う。会ってみせる。わたしは決意を新たに前を向いた。
わたしは金色の水晶たちの所へ急いだ。洞窟をどんどん進んで行くと、先の方で光っている所が見えた。金色の水晶たちだ。
光り輝く空間に入ると、水晶たちが創り出した巨大なスクリーンに、今にも沈みそうな夕日と海、そして灯台が映っている。灯台は白いのだろうが、夕日を浴びてオレンジ色に染まっている。
灯台の向こうに広がる海は変わっていて、左側は波が荒いのに、右側はぺったりした水面だ。水平線に浮かぶ黒い陸地は九州に違いない。その陸地の陰に夕日が隠れようとしている。
近くに人影は見えず、人の話し声も聞こえて来ない。後ろの銀色の水晶たちが閃光を放つたびに聞こえるのは、久美がむせび泣く声だけだ。
「久美! 今行くから死んじゃだめ!」
わたしはスクリーンに向かって必死に叫んだ。だけど、わたしの声は久美には届かないようで、久美はずっと泣き続けている。
時折金色の水晶たちが金色の光を放つと、むせび泣く声とは別の声が洞窟に響いた。
――この疫病神! お前のせいで、みーんな死んでしもたわい。
――二枚舌にしてもひどいよね。親友にまで嘘をつくなんて最低だよ。
――ほんとは意地悪なのに善人ぶっちゃってさ。恥ずかしくないのかえ、この偽善者!
誰か久美じゃない者たちがこの中にいる。そして、みんなで久美を責め立てているようだ。
わたしは水晶のスクリーンをたたきながら、久美の名を呼んだ。しかし久美の返事はなく、深い悲しみが染み出して来るばかりだ。
その悲しみを糧にしているような気味の悪い者たちの声が、久美を責め続けてもわたしは何もできなかった。
「ねぇ、この中に入れて!」
わたしは水晶たちに頼んだ。だけど水晶たちは素っ気なく、この向こうは神さまだけの領域だと言った。
自分の身体の世界では、わたしが神さまだったから中へ入ることができた。だけど、この世界の神さまは久美であり、わたしに中へ入る資格はない。
それでも久美を助けるためには、中に入って久美を責める者たちを、何とかしないといけない。久美が命を絶とうとしているのは、きっとこいつらのせいに違いないのだ。それを必死に訴えても、頑固な水晶たちはロボットのような声で、同じ言葉を繰り返すばかりだった。
水晶と押し問答をしている間にも、スクリーンに映った太陽はどんどん下がって行く。もう下の端が陸地の陰にかかっている。
わたしは両手の拳で水晶をたたきながら、久実の名前を叫んだ。無駄なのはわかっていても、それしかわたしにはできなかった。
そのとき、どこからか光の存在の声が聞こえた。
――思い出しなさい。あなたと久美のつながりを。
辺りを見回しても、光の存在はどこにも見えない。
「どこにいるの? わたし、急いでるの! 早くしないと、久実が死んじゃう!」
――あなたと久美のつながりを思い出すのです。
ふざけないで!――と言いたいところだった。だけど相手は光の存在だ。言い争える相手ではない。それに光の存在がふざけるとは思えない。今がどんな状況にあるのかは、わかっているはずだ。だとすれば、光の存在はわたしを助けようとしているのに違いない。
冷静に考えたわたしは、光の存在が伝えていることが理解できないまま、その指示に従ってみることにした。だけど、わたしと久美のつながりを思い出す?
――あなたはわかっているはずです。自分と久美との関係を。
そうだった。わたしたちは生まれる前から、特別な関係にあったんだ。だからこそ、いろんなことが起きている。だけど、それがどんな関係なのかなんて思い出せない。どうすれば思い出せるの? それに、それを思い出したところでどうだと言うの?
――あなたは久美。久美はあなたです。あなたたちは一つの光でした。
やっぱり、そうだったのか。でも、どうやってそのときのことを思い出せばいいの?
――わたしを感じなさい。わたしを受け入れて感じるのです。
「あなたを? でも、あなたはどこにいるの?」
――わたしはここにいます。いつもあなたの中に、わたしはいます。あなたの中に、わたしを見つけて。
わたしの中に光の存在がいる? それは驚きだったし、とても心強かった。
久美のことが気になったけど、わたしは光の存在の言うとおりにしようと思った。目を閉じて気持ちを落ち着けながら、わたしは自分の心の中に光の存在を探った。
初めは何もわからなかった。気にしないようにしても、やっぱり久美のことが心配になるし、焦ってしまうと意識が集中できない。
――あなたは光。あなたは愛。あなたの中にある愛に触れてみて。
光の存在が心の中で話しかける。まるでその声は磁力のように、わたしの心全体を引き寄せて収縮させていく。
わたしの心は光の存在の心に、次第に取り込まれるように重なっていった。それは言葉では表せないような安らぎであり、喜びだった。あまりの感激にわたしは涙がこぼれた。そして、わたしは思い出した。
わたしは光……。わたしは愛……。わたしは……わたしは……、わたしは光の存在だった。そう、あの光の存在は本来のわたし自身。そして今を生きるわたしはその分身だ。
わたしはこの世界に生まれて来るときに、二つの心に分かれた。その一方が春花で、もう一方が久美。風船たちが身体の心の分身であったように、わたしと久美は同じ光の存在の分身だった。わたしたちは新たな可能性や喜びを求め、互いの再会を約束して、それぞれの両親の元に産まれたんだ。
わたしは春花としての意識を保ちながら、光の存在の意識も感じていた。そして、光の存在の意識を通して、久美の意識も感じることができた。
体が離れていても、わたしたちの心はつながっている。わたしの心はいつだって久美の心と一緒なんだ。久美……。久美を感じる……、久美を……感じる……。感じる……。久美……。
気がつけば、わたしは水晶の洞窟ではなく金色の霧の中にいた。その霧の中を感じるままに歩いて行くと、霧が晴れた場所に出た。そして、そこに久美が向こうを向いて立っていた。
「久美!」
わたしは久美の傍へ駆け寄り、久美の肩に手をかけた。すると、久美がゆっくり振り返った。
こちらを向いた久美を見たとき、わたしはぎょっとして立ちすくんだ。何と、久美には頭が四つもあった。
三匹の化け物
久美の右胸と左胸、そして額には小さな頭が生えていた。
右胸の頭はくちばしがあって、カラス天狗みたいな顔だ。
このカラス天狗は、相手を小馬鹿にしたような顔でにやにやしている。そのくちばしから、しきりに舌が顔をのぞかせているが、その舌は二枚あるようだ。
左胸にある頭は、青白い死人のような女だ。焦点が定まらないような女の目は白く濁っていて、どこを見ているのかわからない。髪はぼさぼさ、皮膚はぼろぼろで、顔の肉は腐っているようだ。
額に生えた頭は、優しげに微笑んだ女性だ。髪もきれいに整えて、一見すると、天女か仏さまのような顔立ちをしている。だけどよく見たら、その目は冷たく策略に満ちているようだ。
一方、本物の久美はぼんやりしていて、わたしを見てはいるけれど、わたしが誰なのかがわからないみたいだ。
「おや、誰だい、お前さんは?」
額の天女が警戒しているような目を向けた。それでも口元は微笑んだままだ。
「久美、わたしだよ。春花だよ。しっかりして!」
わたしが声をかけても、久美はぼーっとしたままだ。
「春花と言うのかえ。つまんない名前だね」
クックッと天女が笑うと、カラス天狗もケケケと笑って言った。
「君の名前さ、つまんないけど素敵だよ。それに君、不細工だけど可愛いよね」
死人の女はホホホと笑い、臭い息を吐きながら言った。
「うちは見たらわかるんよ。あんた、人に厄介ぎりかけよる疫病神じゃろ?」
三つの頭が喋っても、久美は人形のように何も言葉を発しない。久美はこの化け物たちに取り憑かれ、自分がわからなくなっているに違いなかった。
わたしは気味が悪いのも忘れ、死人の女に飛びかかった。女の髪をつかんで久美から引き離そうとしたけれど、久美の服を破って生えていた女の首は、しっかりと久美の胸につながっていた。女の頭を引っ張ると、久美が手前によろけて倒れそうになった。
女の首を絞めると、女は笑いながら、人殺し!――と叫んだ。
隣のカラス天狗がくちばしでわたしの手を突いた。痛くて女から手を離すと、カラス天狗はカカカと笑った。
「無駄なことはおやめ。あたしたちはこの子と一心同体なんだよ」
額の天女が微笑みながら言った。わたしは天女をにらんで言い返した。
「勝手なことを言うな! 久美を食い物にしている寄生虫のくせに!」
「寄生虫? 失礼なことをお言いでないよ。あたしたちだけが、この子と想いを共にできるんだ。どっから来たのか知らないけどさ。野良猫のお前さんとは違うんだよ!」
「そうそう。君は知らないだろうが、久美はね、本当は君のことが嫌いなんだってさ」
カラス天狗はへらへらしながら、わたしを気の毒がった。
「せっかく四人で楽しいにしよったんやけん、邪魔せんでくれん? 疫病神さん」
死人の女は文句を言うと、久美を見上げた。女は左目でわたしを見ながら、長い舌を出して久美の頬をぺろりと舐めた。背筋がぞっとしたけど、久美は無表情のままだ。
この化け物たちを何とかしないと、久美を助けることはできない。だけど、この連中は何なんだろう? いつの間に久美の心に食い込んだんだろう?
頭の中に、ふと夢で見た光景が浮かんだ。久美の両胸と額に突き刺さった言霊の矢。そうか、こいつらは言霊だ。二枚舌と疫病神と偽善者。それがこの化け物たちの正体だ!
「あんたたちの正体、見破ったからね!」
わたしが叫んでも、三匹とも少しも意に介さない様子でケラケラ笑っている。天女は笑いをこらえながら、聞いてあげるから見破った正体を言ってごらんな――と言った。
「あんたたちはみんな、誰かが久美に言い放った言霊だ!」
天女は白けたような顔を見せた。
「何を言うのかと思ったら……。もっと面白いことを言うと思ったのにさ」
カラス天狗と死人の女もうなずきながら言った。
「残念。二十点だな。でも、次は期待してるよ」
「ほんでも、どうせ、またがっかりさせられるぎりじゃろ。人に迷惑かけることしか能がないんやけん」
わたしは構わず死人の女を指差した。
「まず、あんたよ! 人のこと疫病神呼ばわりするけど、あんたこそが疫病神よ!」
「うちが疫病神? 自分のことを棚に上げて、よう言うわいねぇ。あんた、自分のことぎり言うて、相手のこと傷つけとるんやないんか? あんたがおるぎりで迷惑しよる人がおるやなんて、考えたこともなかろ?」
死人の女はわたしをにらみながら言った。だけど、わたしは負けない。何故なら、わたしは死人の女が誰が飛ばした言霊なのかを知っているから。
「そうやって相手に罪の意識を持たせることで、自分が偉くなったみたいに思ってるんでしょ? 自分では何もできないから、他の人を陥れて自分の立場を高く見せようとしてるだけじゃないの! あんたみたいなのをね、本当の疫病神って言うのよ!」
「この小娘が偉そうに。あんたこそ、自分が上じゃて思いたいんじゃろがね」
「あんた、馬鹿じゃないの? 人間に上も下もないでしょ? その顔と同じように、あんたの心は腐ってるのよ。その目だって、本当のことなんか何も見えてないんでしょ?」
「失礼なこと言いなや! うちの心は腐っとらんし、ちゃんとほんまのことが見えとるわいね」
「じゃあ、わたしが誰に迷惑をかけたのか言ってごらんなさいよ。あんた、わたしがいるだけで人に迷惑かけてるって言ったでしょ? それは誰なの? 言いなさいよ!」
死人の女は口をもごもごさせて言った。
「う……、お前の親じゃ」
「残念でした! わたしの両親はどっちもわたしのことを、とても大切に想ってくれてます」
「ほれじゃったら、お前の友だちじゃ」
「ほんとに、あんたって頭が悪いのね。でも腐ってるんだからしょうがないか。あのね、わたしのことを迷惑に思うような人は、わたしの友だちじゃないの。わかる? 本当の友だちっていうのは、相手のことを迷惑に思ったりしないものよ。そんなこともわからないってことは、あんたには本当の友だちがいないってことよね? そうでしょ?」
死人の女と言い合いながら、わたしは他の二つの言霊が黙っていることに気がついた。
三匹の化け物たちは仲間なのかと思ってたけど、どうやらそうでもないらしい。死人の女がわたしに言い負かされているのを、他の二匹は面白そうに聞くばかりで、加勢するつもりはないようだ。
言い返せずに口ごもる死人の女に、わたしは畳みかけるように言った。
「何でも人のせいにして、自分はいつだって正しいって思いたいのがあんたよ。そのために相手を傷つけて、自信をなくさせようとする厄介な意地悪女! それがあんたの正体であり、あんたの主人の正体よ!」
死人の女は憎々しげに歯を剥くと、食ってかかるように言い返して来た。
「このくそガキが! あんたみたいな子供にゃわかるまい。世の中いうんは、つらいことばっかしなんよ。ほんなん、誰ぞ不幸なやつがおらんとやってられんがね! 悪いんはうちやない。世の中や! 文句言うなら、世の中に言いや!」
わめく疫病神に、わたしの口が勝手に動く。
「そう思うのは、あんたが物事を一面からしか見てないからでしょ? 愚痴ばっかり言ってないで、ちっちゃなことでもいいから喜びを探してごらん。つらいと思うこともね、見方を変えれば喜びへの道しるべなのよ!」
「世の中知らん者が、きれい事ばっかし言うんやないわ! ほんまのつらさなんぞ知らんくせに!」
「つらさに本当も嘘もないのよ。人によって、つらさは様々なの。自分だけがつらさを知ってるって思うのは間違ってるよ。つらいと思うのなら、そこから抜け出すための工夫をするの。自分は不幸だって決めつけないで、幸せになることを自分に許してあげるのよ」
「何を偉そうに!」
「いいから聞きなさい。つらさっていうのはね、優しさに変えられるんだよ。自分がつらい分、人に優しくして励ましたり祝福してあげてごらんよ。そうすれば、自分が幸せだってわかるから」
わたしの話を聞きたくないのだろう。死人の女は首を大きく振りながら叫んだ。
「うるさいうるさい! うちは幸せじゃ!」
「幸せな人はね、他の人のことを悪く言わないものだよ。誰かのことを疫病神だなんて言ってるうちは、幸せとは言えないよ」
「黙れ黙れ、この疫病神が!」
「ほら、また言った。それ、ほんとは自分のことを言ってるんでしょ? あんたは自分のことが嫌いなのよ。その気持ちを他人にぶつけて疫病神って罵ってるの。違う?」
「違う! うちは疫病神なんぞやない!」
「じゃあ、自分のことが好き?」
死人の女は言葉に詰まった。
「言ってごらん。わたしは自分が大好きだって」
「うちは……、うちは……」
死人の女は白い目に涙を浮かべた。それから悔しそうに歯を剥くと消えてしまった。
わたしはちょっと驚いた。死人の女を言い負かせたとは思ったけど、それで消えるとまでは思っていなかった。これはいけると、わたしの中で自信が膨らんだ。
次の相手はカラス天狗だ。わたしが目を向けると、カラス天狗はぎょっとした様子で、何だよ――と言った。
「この嘘つきカラス。あんたの主人は大嘘つきの二枚舌ね。人を騙して喜ぶ嫌なやつよ。それも、自分のことはわからないようにしながら、陰でこそこそ人の悪口を流す小心者の卑怯者よ!」
わたしの指摘にカラス天狗はむっとなった。
「好い加減なことを言うな! 嘘つきは君だろ? 僕は嘘なんかついたことないぞ!」
「あんた、人の気を引きたいだけでしょ? 本当は構って欲しいけど、馬鹿にされるのが怖いんだよね?」
カラス天狗は、またにやにや顔になった。
「君が言ってることは、僕には関係ないからよくわからないけどさ、一般論として聞こうか。もし堂々と喋って馬鹿にされたり無視されたら、そんときはどうすんだい?」
「本当に言うべきことがあるのなら、何があっても言うべきよ。でもね、喋る相手や使う言葉は選ばないとね。人のことを馬鹿にするやつなんか、相手にしなけりゃいいのよ」
カラス天狗の眉間に皺が寄った。
「簡単に言うな! 本当に気兼ねなしに喋れるやつなんかいるもんか!」
「あれ? 一般論を喋ってるんじゃなかったの? 何、興奮してるわけ?」
はっとなったように、カラス天狗はにやにや顔に戻ったけど、くちばしの端が引きつっているみたいだ。
「わたし、あんたの気持ち、わかってるよ。あんた、本当は友だちが欲しいだけなんでしょ? 友だちって言っても、ただの知り合いじゃなくって、本当にあんたのことをわかってくれる人だよ」
「ぼ、僕は友だちなんかいらない。友だちなんか面倒臭いだけじゃないか」
「だから、そんなのは本当の友だちじゃないんだってば。あんたがいちいち気を遣わなくたって、あんたのことをわかってくれる友だちだよ」
「そんなやつ、いるわけないだろ?」
明らかにカラス天狗は自分のことを喋っている。わたしの敵意は同情に変わった。
「知らないようだから教えてあげる。わたしと久美は元々一つだったのよ。だから離ればなれに育っても、ちゃんと心はつながってるの。何の気遣いもいらないし、いつだってお互いのことを想い合ってるの」
「それこそ出任せだろ? 僕を騙そうったって、そうは行かないからな」
「わたしの目を見てごらん。わたしが嘘をついてるかどうかわかるから」
カラス天狗はちょっとだけわたしの目を見たあと、慌てたようにそっぽを向いた。
「ぼ、ぼくにはそんなことわからないよ」
「いいから見なさい!」
わたしが声を荒げると、カラス天狗はびっくりしたようにこっちを向いた。
わたしと目を合わせたカラス天狗は、ヘビににらまれたカエルみたいに、わたしから目を逸らせなくなったようだ。
わたしは笑顔を見せると、穏やかに話しかけた。
「いい? 嘘は言わないから、よく聞いてね。あんたにだってね、心がつながった人が必ずいるんだよ。だからね、人を騙して憂さ晴らしなんかしてないで、その人との出会いを探しなさい。そうすれば必ずその人と出会えるから」
笑みが消えたカラス天狗は、目を伏せがちに言った。
「僕にそんな相手なんかいない。誰も僕のことなんかわかってくれないよ」
「そんなことない。あきらめちゃだめよ。わたしに久美がいたんだから、あんたにだって絶対誰かがいるはずよ。向こうもね、あんたが現れるのを泣きながら待ってるんだよ」
カラス天狗は顔を上げてわたしを見た。
「僕を待ってる? 泣きながら?」
「そうだよ。あんたと同じように、自分には誰もいないって思って泣いてるの。だから、早くその人を見つけてあげないと可哀想でしょ?」
「だけど、どうすれば見つけられるんだよ?」
「自分なんてって思うのをやめて、自分を認めてあげるの。自分に素直になって、自分が本当に楽しいって思うことに夢中になるのよ。でもね、人を騙して楽しむのは、本当の楽しさじゃないよ。誰かを騙すときって、裏に悔しさとか腹立ちとか悲しみが隠れてるじゃない。そんなのじゃなくて、喜びだけの楽しみだよ」
カラス天狗はしょんぼり下を向いた。
「そんなの、誰もわかってくれないよ」
「誰にでもわかってもらう必要はないでしょ? 自分とつながっている人だけが、わかってくれればいいんだから。だけど、向こうだってあんたが何もしてなかったら、あんたのことがわからないじゃない。だからね、あんたがほんとの姿を見せていれば、あぁ、ここにいたんだって、あんたのことを見つけてくれるよ」
カラス天狗はくちばしを閉じ、何かを思案するような顔になった。そして、そのまま消えた。
やった。カラス天狗も消し去ることができた。
ほっとしながらも、わたしは外のことが気になった。夕日はどうなったのだろう。かなり時間が過ぎたような気がするけれど、久美が変わらずここにいるということは、久美はまだ生きているということだ。だとすれば、外とここでは時間の流れが違うのだろうか。
何にしても久美を助けるためには、最後の言霊である天女を倒さなければ。
「残るは、あんた一人ね。偽善者の天女さん」
わたしは久美の額の天女をにらんだ。天女は口元は笑っているけど、目は怒っている。
「なかなかやるじゃないか。それで、あたしをどうしよってんだい?」
「決まってるでしょ? さっきの二人みたいに、あんたにも消えてもらうから」
「ずいぶんな言い草だね。正義の味方にでもなったつもりかえ?」
「そっちこそ、何を威張ってんのよ。久美を殺そうとしてるくせに!」
「おやおや。あたしゃすっかり悪者扱いだね。言っとくけどね、久美が自分をどうするかは、久美が自分で決めてるんだ。あたしがいようがいまいが関係ないことさ」
惚ける天女を指差して、わたしは言った。
「言ってあげる。あんたの主人は人前では善人の顔を見せるけど、本当は誰が傷つこうがどうでもいいの。善人のふりをするのは我が身を守るためで、自分が傷つかないことだけ考えてるのよ。本当の自分が見せられないからいい子ぶってるけど、そんな自分が大嫌いで憎みさえする孤独で寂しい人。それが偽善者であるあんたの主人の正体よ!」
喋りながら少し前の自分を思い出したわたしは、情けない気持ちになっていた。死人の女にしてもカラス天狗にしてもそうだったけど、天女に対する言葉はまるで自分に投げかけているみたいだ。
だけど、今のわたしは昔のわたしじゃない。だからこそ言霊たちの考え方が理解できるし、こうして諫めることができるのだ。
天女は黙ったままわたしを見つめている。何も言わないところが不気味だ。わたしの言葉は天女に効いたのだろうか。ちょっと心配になったわたしは、さらに続けて言った。
「あんたみたいな偽善者はね、正体が知れたらおしまいだよ。そうなったら誰もあんたのことなんか相手にしてくれないんだから! まぁ、そもそも誰のことも信じてないんだから、他の人に相手にしてもらおうなんて思わないか」
無表情だった天女が、目を細めて笑った。
「言ってくれるじゃないか。小娘なのに大したもんだよ。恐れ入ったね。そうだよ、お前さんが言うとおり、あたしゃ孤独な偽善者さ」
「自分の正体を認めたのね?」
「だけどさ、やっぱりお前さんは尻の青い小娘さね」
「どういうこと?」
「経験が浅いってことだよ。何でもわかったつもりでいるみたいだけどさ、人間は謙虚さってもんが必要なんだ。そこがまだわからないところが小娘だって言ってんのさ」
この期に及んで小馬鹿にする天女に、わたしはむっとなって言い返した。
「あんたみたいな偽善者に、謙虚にする必要なんてないでしょ?」
「そうだよね、お前さんが言うのは尤もな話さ」
思いがけず、天女はしょんぼりした顔を見せた。だけど、これはわたしを油断させようとしているに違いない。わたしは天女をにらみ続けたが、天女は悲しげな目でわたしを見つめながら、でもね――と言った。
「こんなあたしにだってさ、たった一人だけね、信じたい、信じてもらいたいって思った人がいたんだよ」
「へぇ、そんな人がいるの。だけど、その人だってあんたが偽善者だってわかったら、さぞがっかりするでしょうね」
「確かにそうだね。がっかりするだろうね」
天女は寂しそうに目を伏せた。お芝居に決まっているだろうから、わたしは警戒しながら言った。
「そう思うんだったら、心を入れ替えたらどうなの?」
「いいんだよ。これがあたしなんだし、もうその人の本心っていうのがわかったからね」
「あきらめちゃうの?」
天女は顔を下に向けたまま、じろりとわたしを見た。
「あきらめるも何も仕方ないだろ? 相手が自分をどう思うかなんて、相手が決めることであって、あたしが決めるわけじゃないからね」
「神妙なこと言っちゃって。そう思うんだったら、その人に悪く見られる前に、早く偽善をやめて本当の善人になったら?」
天女はため息を一つついてから言った。
「誰もさ、初めから好きで偽善者になるわけじゃないんだよ。いつの間にかそうなっちゃって、自分でもどうにもできなくなっちまうもんなのさ」
天女の言葉はわたしの胸に突き刺さった。まるで自分のことを言われてるみたいだ。そのせいで、わたしの天女に対する言葉は少し優しげになってしまう。
「そんな風に決めつけないの。今だったらまだ間に合うから、偽善をやめるのよ」
「もう間に合わないさ」
「そんなことないって」
「そんなことあるんだよ。あたしはその人に本当の姿を見られちまったんだ。その人だけが、あたしの最後の心の支えだったんだけどね。もう何もかもおしまいさ」
死人の女もカラス天狗も本音を隠せなくなって消えた。二匹の言霊が消えたのは、自分の本音を認めて救いを求めようとしたからだと、わたしは思っていた。だけど天女は本音を認めながらも、救いを求めることをあきらめているようだ。これでは天女は久美に取り憑いたままで、久美を解放できない。
もう時間がないと思うけど、外の様子はわからない。とにかく急がなければ、取り返しがつかないことになってしまう。焦ったわたしは口調が荒くなった。
「おしまいだって思うんなら、他の二匹みたいに、あんたもさっさと消えなさいよ」
天女はまたわたしをじっと見つめ、ふっと笑った。
「そうだね。そうするよ。正直言えばさ、今までおばあちゃんの所へ行くのを迷ってたんだよ。だけど、お前さんが消えろって言うんだもんね。もう消えるしかないさね」
天女の言葉に、わたしはぎくりとなった。どうして天女の口から、おばあちゃんの話が出て来るのか? わたしの言うとおりに消えるって、どういうこと?
「ちょっと、何言ってんの? 何であんたがおばあちゃんの所へ行くわけ? て言うか、あんたにもおばあちゃんがいるの?」
天女は笑みを浮かべたままだったが、やはりその目は悲しげだった。それがさらにわたしの心にさざ波を立てる。
「まだわかんないみたいだから、最後にあたしが信じたいって思ってた人が誰なのか、お前さんに教えてあげようね」
「え? それって、わたしが知ってる人なの?」
「そうだよ。お前さんがよーく知ってる人間さ」
「わたしがよく知ってる人? 誰なの、それは?」
「その人はね――」
天女は迷ったように口をつぐむと、じっとわたしを見つめた。うろたえたわたしは、強気を装って天女をにらんだ。
「何よ? もったいぶらないで早くいいなさいよ!」
寂しげに笑った天女は、じゃあ言うよと言って、またわたしを見つめた。
「その人の名前は――」
白鳥春花って言うんだよ――と天女は言った。
「え? わたし?」
一瞬どきっとしたわたしは、すぐに怒りを覚えた。
「何でわたしなのよ! 好い加減なこと言わないでよ!」
「お前さんがそんな風に言うのは、お前さんがあたしの上っ面しか見てなかったからさ」
「何わけのわかんないこと言ってんのよ! わたし、あんたなんか知らないよ!」
「お前さんの態度や言葉は、今のあたしに向かって投げかけたものだろ? お前さんが知らなかった、本当のあたしに対するあんたの気持ちがこれなのさ」
「やめて! そんなこと言って、わたしを混乱させるつもりなんでしょ?」
天女がこんなことを言うなんて思いもしなかった。だけど、どうして天女はわたしの名字まで知っているのだろう? 一抹の不安が過ったわたしに天女は言った。
「あたしはね、もしかしたらお前さんだったら、本当のあたしを見ても、あたしから離れないかもしれないって、ちょっぴり期待してたんだ。だからさ、日が沈んだあとにおばあちゃんの所へ行くのをためらってたのさ。だけど……、結局はお前さんも他の連中と一緒だった。でも恨んだりはしないよ。悪いのは偽善者のあたしなんだからね」
「ちょっとあんた、何言ってんの? 変なこと言わないでよ! それじゃあ、まるであんたは――」
そうだよ――と天女はしょんぼりして言った。
「あたしを言い放ったのはね、この兵頭久美自身なのさ。だから、あたしは言霊だけど兵頭久美でもあるんだよ。そして、あたしが信じたかった、たった一人の人間っていうのはね。白鳥春花、お前さんだったんだよ」
わたしはぞわっとした。だけど、そんなこと信じられるわけがない。
「嘘をつかないで! あんたも二枚舌があるんでしょ?」
腹を立てたわたしに、天女は静かに言った。
「あたし、つまり兵頭久美は偽善者なんだよ。お前さんがこのことを受け入れられなくたって、それが真実なんだ」
「何とでも言いなさい。わたしは絶対信じないから」
天女は構わず話を続けた。
「何であたしが偽善者になったか知りたいだろ? あれはこっちの中学校でのことさ。あたしたちのクラスに、東京から来た女子がいてね。今のあたしみたいな言葉で喋ったもんだから、みんながその子を馬鹿にしたのさ。もちろんあたしも一緒にね」
「久美はそんなことはしない! 久美はとっても優しい子なんだから」
ありがとう――と天女は言った。
「だけどね、どんなに優しくたって、意地悪な気持ちはあるものさ。それが人間ってもんなんだ。春花だってそうだろ?」
天女はわたしを春花と呼び、のぞき込むように私を見た。わたしは圧倒されて何も言えなかった。
顔を上げた天女は昔を思い出すように横を見上げた。
「あたしはね、片親ってことでずっと肩身の狭い想いをして来たんだ。だから中学校ではそのことを隠してさ、クラスの友だちに気に入ってもらおうと、何かにつけてみんなに合わせて生きて来たんだよ。そうしなけりゃ、また嫌な想いをさせられちまうからね」
「それでみんなと一緒に転校生を馬鹿にしたって言うの?」
「そのとおりさ。だけどね、誰かを馬鹿にしてるときの自分って、いつもの自分と真逆だろ? だからさ、なんか気分がよくってさ。気がついたら、自分からその子のことを馬鹿にするようになっちまったんだ」
自分にだって思い当たることはある。だけど、天女の話を受け入れてはおしまいだ。
「そんな嘘、わたしは信じないからね!」
「信じようと信じまいと、それは春花の勝手だけどさ。事実はそうなのさ」
「久美はその子をかばって、みんなから攻撃されたんだよ? その久美がその子を馬鹿にするわけないでしょ?」
「どうしてあたしがみんなから責められたのか。それは単にその転校生をかばったからじゃないんだ。あたし自身がその子を馬鹿にしてたからこそ、お前は偽善者だって責められたんだよ」
「じゃあ、どうして馬鹿にしてたはずの相手をかばったりしたの? そんなことしたら、みんなから責められるのはわかってたはずでしょ?」
そうなんだけどさ――と天女はため息をついた。
「あたしは知ってしまったのさ。その子も父親がいなかったんだって。それで、みんながそのことでその子を馬鹿にしているのを、黙ってられなくなっちまったんだよ。お陰であたしも片親だってことがばれちまってね。何も知らない連中に、死んだ父親のことを馬鹿にされたもんだから、もう大喧嘩さ」
天女の話は筋が通っている。わたしが聞いている話とも矛盾がない。違うのは、わたしが知らない部分だけだ。そこが天女の作り話なのかどうかはわからない。わたしは天女が作った話だと思いたかったけど、本当のことのようにも思えてしまう。
だけど、そうなっては天女の思う壺だ。好い加減に作り話はやめろとわたしは言った。だけど天女の話は続いた。
「みんなから偽善者って言われても、あたしはそれを否定できなかった。だって、そのとおりなんだからね。それで、あたしは学校にいられなくなったんだよ」
「違う違う! 久美が学校にいられなくなったのは、怪我させたのがPTA会長の娘だったからよ」
天女はふんと言うと、あのくそ娘と顔をしかめた。
「確かに、あの馬鹿をとっちめたことは影響しただろうさ。だけどね、一番の理由はあたしが偽善者で、一人だけいい子ぶろうとしたと見られたからなんだ」
「久美がその転校生をかばったのは、いい子ぶろうとしたからじゃないでしょ?」
「それはそうだけどさ。もしあの子に父親がいないってわからなかったら、あたしは他の連中と一緒に、あの子のことをからかい続けただろうね。みんな、それがわかってるからさ。それで、いい子ぶるんじゃないよってなったわけ」
「だけど……」
「一番つらいのは、そんなあたしをおばあちゃんだけは信じ続けてくれてたってことさ。あたしは大好きなおばあちゃんを欺き続けた、ひどい孫娘なんだ」
わたしは何も言えなかった。天女の話を否定する言葉を探したけど、見つけることができなかった。
「松山にいられなくなって、あたしは自分のことを誰も知らない東京へ、母親に勧められるまま移って来たんだ。だけど来てみれば、今度は自分の方が田舎者って馬鹿にされる側になっちまった。あたしさ、ほんとにもう何もかも投げ出したくなってね。それで運動会のあの日、屋上へ上がったんだ。そこへ突然現れたのが、春花だったってわけなんだよ」
わたしは天女の話を疑う気持ちがなくなっていた。初めて久美に出会ったときのことを思い出すと、あのときの久美の気持ちが思い遣られ、わたしは涙ぐんだ。
「春花はやっぱり優しいねぇ。あたしさ、春花が声をかけてくれて、あたしのこと親友だって言ってくれたとき、ほんとにうれしかったんだよ。あたし、春花だけは信じられるって思ったんだ」
気がつけば、天女の声は喋り方は違っていても久美の声だった。わたしには天女の言葉が久美の言葉のように聞こえていた。
「だけどさ、あたしは偽善者だからね。春花に本当の姿を見せることはできなかった。そんなことをしたら春花を失うんじゃないかって思ってさ。ずっと本当のことが言えなかったんだよ」
わたしの目から涙がこぼれた。久美の気持ちは痛いほどわかる。わたしだって同じだ。
わたしは八方美人だった。だけど、それを久美に知られたくないから、真弓たちから久美を隠そうとしていた。自分の本当の姿を見られたくなかったのは、わたしだって同じだった。そう叫ぶと、そうじゃないよと天女は言った。
「あたしは東京から来た転校生を、みんなと一緒になって馬鹿にしたのに、春花はそうはしなかったよね。聞いたよ、春花、あの子たちに嘘をついたのは、あたしをかばうためだったんだね。あんなことになるのはわかってただろうにさ。あたしとは大違いさ。学校に出て来なくなった春花が肺炎になったって聞いたとき、あたしは心底自分を憎んだよ」
「わたし、そんないい子じゃない。だから――」
「もういいよ、何も言わなくったって。もう全部ばれちまったんだから。あたしは偽善者なんだ。善人面して、ほんとは人のことなんかどうだっていい人間なんだよ。春花が言うとおり、あたしは自分が傷つくのが嫌で、それでいい子ぶってたのさ。だから本当の友だちなんかできないし、どこへ行っても独りぼっちなんだ」
「そんなことない。久美にはわたしがいるよ!」
「もういいって言ってるじゃないか。春花があたしを親友だって言ってくれたのは、ほんとのあたしを知らなかったからだもんね。でも、それでいいんだよ。春花は何も悪くないんだよ」
わたしは必死になって弁解した。心の中は焦りと後悔でいっぱいだった。
「今みたいにほんとのことを話してくれてたら、わたし、久美の力になろうとしたよ。久美から離れようなんて考えないから。だってわたしたち、心がつながってるんだもん」
「泣かせることを言ってくれるじゃないか。だけど、今更さ。あたし、春花に全部喋って何だか清々した気分だよ。他の誰にも話せなかったことを、春花には話せたんだ。あたしの大事な春花。あたしの大好きな春花。あたしの話を聞いてくれてありがとう」
「よくない! 話はまだ終わってないから! 聞いて! わたしだって偽善者なの。わたしも人の陰口言ったことあるし、自分が傷つきたくなくて、何でも人のせいにしてたんだよ! 久美のことを親友だって言っておきながら、真弓たちから離れられなかった八方美人だったの。久美と谷山とのことを疑ったりもしたよ。だから一緒なの! 同じなの!」
天女は涙ぐみながら言った。
「やめておくれよ。一度は決心した気持ちが揺らいじまうじゃないか。ほら、夕日が……夕日がもう沈む。あぁ、なんて切なくて悲しい夕日なんだろ。あれが沈みきったら、春花ともお別れだ。あたしはおばあちゃんの所へ行くね」
わたしは周りを見た。だけど、そこに見えるのは金色の霧だけだ。水晶たちのスクリーンはここにはない。それでも天女には外の景色が見えているらしい。何かをじっと見つめならが涙ぐんでいる。
「だめよ! おばあちゃんの所へ行っちゃだめ! そんなことしたって、おばあちゃんは喜ばないよ!」
天女は何も言わないし、わたしの方を見ようともしない。遠くを見つめながら独り言のように、あとちょっとだとつぶやいている。
わたしは取り返しがつかないことをしてしまったと、パニックになっていた。死人の女とカラス天狗をやっつけたことで、調子に乗っていたようだ。
天女は悲しげな目をわたしに向けた。
「春花、お別れだよ。一時ではあったけど、こんなあたしの友だちになってくれてありがとね」
「だめ! 死んじゃだめ!」
わたしは久美に抱きついた。だけど本物の久美はぼーっとしたままだ。
「久美が死んだら、風船たちもみんな死んじゃうよ! わたしだって……、わたしだって生きていけなくなっちゃうよ!」
わたしが必死に呼びかけても、久美は反応してくれない。代わりに天女が、さぁ行くよ――と言った。
そのとき、わたしは久美の胸で何かが光っているのに気がついた。それは沈みゆく夕日のような赤と金色の混ざった光で、小さいけれど温もりがある。わたしは直感で、これは久美のおばあちゃんの言霊だと思った。おばあちゃんが久美に聞かせてくれた、あの言葉が久美の胸に残っているのに違いない。
「久美、おばあちゃんのことを思い出して! おばあちゃんは何て言ってた?」
「久美はおばあちゃんの所へ行くんだ。春花は黙って見送っておくれ」
天女が言った。だけど、久美はぼんやりしたまま何も言ってくれない。
わたしは天女をにらんで言った。
「あんたは久美の本心なんかじゃない! 久美が自分を偽ろうとする想いよ! あんたは自分自身を偽って、自分が久美の本心なんだって思い込んでるだけよ!」
天女は反論せずに、にやりと笑った。もう何を言っても無駄ということか。だけど、ここであきらめるなんてできない。わたしは久美を揺さぶりながら叫んだ。
「久美、おばあちゃんの言葉を思い出して! おばあちゃんは夕日を悲しいなんて言わなかったでしょ? おばあちゃんはこう言ったはずだよ! 夕日見てきれいじゃて思うんはな、あんたの心がきれいなけんよ。花見て……、えっと、花見て――」
もうだめだ。肝心な所で続きの言葉を忘れてしまった。どうすることもできず、わたしは久美を抱きしめた。無駄なこととはわかっているけど、そうするしかできなかった。
「花見て素敵じゃて思うんはな、あんたの心が素敵じゃてことなんよ」
久美の声が聞こえた。
え?――わたしは顔を上げて久美を見た。久美が涙に濡れた笑顔でわたしを見つめている。
額の天女は微笑みながら、すっと姿を消した。久美はわたしを抱き返しながら、うれしそうに言った。
「春花、うちの春花。だんだんな。だんだんありがとう」
おばあちゃんの夕日
「ほら、着いたぞ。急げ!」
突然兄貴に揺り起こされたわたしに、運転席から中村さんが叫んだ。
「ここはオレたちで何とかする。お前は早く行け!」
わたしは自分がどうなっているのかがわからなかった。だけど、兄貴は手を伸ばして助手席のドアを開けると、わたしを放り出すように外へ出した。そのとき後方に停まっていたミニパトカーから、男女の警官が降りて来るのが見えた。それで、ようやくわたしはどんな事態になっていたのかを思い出した。
「急げ! もう日が沈むぜ!」
もう一度中村さんが叫んだ。だけど、どっちへ行けばいいのかわからない。
「どこへ行けばいいの?」
きょろきょろするわたしに、中村さんは道がある場所を指差すと、ドアを開けて外へ出た。兄貴も出て来ると、わたしの肩をたたいて、時間がない、走れ!――と言った。
わたしが言われた方へ走り出すと、待ちなさい!――と警官が叫んだ。だけど、止まってなんかいられない。走りながら後ろを振り返ると、兄貴と中村さんが警官たちの方へ歩いて向かっているところだった。
すると、男性警官がわたしを追いかけようとした。それを兄貴が捕まえて格闘みたいになった。それを見た女性警官がわたしの方へ駆け出そうとしたけど、それも中村さんが両手を広げて阻止してくれた。
――お兄ちゃん、中村さん、ありがとう。
心の中で二人に感謝しながら、わたしは鬱蒼とした木々のトンネルの中に飛び込んだ。
夕闇に包まれている中での木々の陰は、もう夜が来たみたいに暗かった。そのことはわたしを不安にさせた。天女は消えたけど、久美がどうなったのかまではわからない。
久美が最後にわたしに言った言葉が、わたしへの別れの言葉だったように思えて、わたしは走りながら泣いた。
病み上がりで体力がない上に、呼吸も完全に元には戻っていないけど、わたしは止まることができなかった。暗くて足下が見えにくいところを、息を切らせながら走るので、わたしは何度もつまづきそうになった。足も思ったように上がらないし、苦しくて気が遠くなりそうだ。
だけど、それは体のわたしが必死になって、わたしのためにがんばってくれているってことだ。わたしは体のわたしに感謝しながら、もう少しだからがんばってと声をかけた。するとその声が届いたのか、心なし苦しさが楽になったような気がした。
どれぐらい走っただろう。こんなにがんばって走ったのは生まれて初めてだ。だけど、それで自分を褒める気にはならない。だって、だって……、木のトンネルを抜け出ても明るくないもの。海を見ても太陽はどこにも見えない。もう沈んでしまったんだ。
わたしは間に合わなかった。夕日が沈む前に、久美を見つけることができなかった。久美は……久美は……。
わたしは泣きながら走り続けた。走ると言っても、ほとんど足が動いていない。木のトンネルを抜けたあとも、誰もいない細い道がくねくねと曲がりながら続いている。どこまで行けばいいのだろう。灯台はまだ見えない。
「久美……、久美……」
わたしは倒れそうになりながら、久美の名前を呼び続けた。悲しみに沈みながら灯台を探すわたしの頭には、久美が見ていた風景があった。久美は灯台のすぐ傍ではなく、少し離れた所から、灯台と海と夕日を一緒に眺めていた。
ついに灯台を見つけたわたしは、久美がいたであろう場所を探し求めた。だけど、その場所へ行くのが怖くもあった。
海を見渡しても、水平線のどこにも太陽は見えない。余韻のような茜色の空があるばかりだ。やはり夕日は沈んでしまった。
終わった。すべては終わったんだ。わたしは間に合わなかった。ようやくここまで来たのに、わたしは久美を助けることができなかった。
わたしは子供みたいに泣きじゃくりながら、久美の名を呼び続けた。そして、久美がいたと思われる方へ、よろよろと歩いて行った。すると――
「春花? 春花なん?」
夕闇の中から久美の声がした。
「久美? 久美なの?」
わたしはどこにいるかわからない久美に向かって、力の限り叫んだ。
「春花! やっぱし春花や!」
再び久美の声が聞こえたと思うと、前方の薄闇の中から、誰かが駆け寄って来るのが見えた。その誰かは近づいて来るにつれて、姿がはっきり見えて来た。
息を弾ませながらわたしのすぐ前まで来たその誰かは、紛れもなく久美だった。もう死んだと思っていた久美だった。わたしの親友であり、わたしの分身である久美だった。
「春花、入院しよったはずやのに、こがぁなとこまでうちを探しに来てくれたんか」
わたしはうなずくと、久美を抱きしめて号泣した。何を言おうとしても、出て来るのは涙ばかりだった。
久美もわたしを抱き返し、泣きながら何度もわたしに、ありがとうと言った。
久美に自分の上着を着せてやったあと、わたしは夕日の名残の西空を眺めた。
「きれいだねぇ。わたし、こんなにきれいな夕焼け見たの、初めてじゃないかな」
夕日は沈んでしまったけれど、茜色に染まった空が薄闇の中に浮かび上がっている。その様が本当にきれいだった。
「ほれは、春花の心がほんだけきれいいうことや」
久美が微笑みながら言った。わたしもにっこり笑うと、久美に言った。
「と言うことは、久美の心もそれだけきれいってことだよね?」
「なんで?」
「だって、わたしたちの心はつながってるからさ。わたしと久美はね、元々一つだったのが、二つに分かれて生まれたんだよ」
「ほうなん? そがぁなこと考えもせんかったけんど、なんで春花はそげに思うん?」
「いろいろあったんだ。ほんと、いろいろね」
わたしは家で死にそうになってからの、様々なことを思い出していた。風船たちや体のわたし、そして光の存在……。
「ほれは、学校に出て来んようになってからのこと?」
「そうだよ。自分でも信じられないようなことをね、いっぱい経験させてもらったの。それでわかったことが、わたしたちは元々は光の存在だったってことと、わたしも久美も風船たちの神さまだってことなんだ」
「光の存在? 風船たちの神さま? 何ほれ?」
「詳しいことは、またあとで話すけどさ、わたしが久美がここにいるのがわかったのも、風船たちや光の存在が助けてくれたからなんだよ」
久美は頭に手を当て、うーんと呻いた。
「もうさっぱりわからん。早よ説明聞きたいけんど、話すと長なるんじゃろ?」
「そうだね。だから、お楽しみはあとに取っといて」
「しゃあないな。ほんでも、今春花が言うてくれたことは、うちには何よりや」
久美は笑顔を見せたあと、しんみりと言った。
「たぶん、わかっとると思うけんど……、うちな、ここで死のて思とったんよ。夕日が沈んだら、死んでおばあちゃん所へ行くつもりやった……」
わたしが黙っていると、久美は夕焼け空を見つめながら話を続けた。
「ここは四国の最西端やけん、夕日に一番近い所なんよ。うちにとって、夕日はおばあちゃんじゃった。ほじゃけん、おばあちゃん追っかけるつもりでここまで来たんよ」
「そうだったの」
「うちな、自分は疫病神やて思いよったんよ。ほれに二枚舌の偽善者や。そげな自分が嫌やったけんど、春花とおばあちゃんがおったけん、これまで生きて来られたんよ。ほやけど、おばあちゃんが死んで、春花までもが死んだら生きてられんけん……」
少しの沈黙を挟んで、わたしは尋ねた。
「二枚舌って、お父さんのこと?」
「こっちで、うちのお母ちゃんから話聞いたん?」
わたしがうなずくと、久美はため息をつき、ごめんな――と言った。
「うち、お父ちゃんがおらんことで嫌な目に遭うて来たけん、お父ちゃんのこと聞かれたら適当なこという癖がついてしもとるんよ。春花はうちのこと親友じゃて言うてくれよったのに、つい嘘言うてしもて……。ほんでも、ほれは春花を信じとらんことになるけん、うち、ほんまのことを言おうて思たんやけんど、言いそびれてしもて……」
そんなこと――とわたしは言った。
「言いたくないことは言わないでいいんだよ。親友だからって、何でもかんでも喋る必要はないから」
「うち、黙っとるんやのうて、嘘ついてしもた」
「無理に喋ろうとするから、違うことを言っちゃったんでしょ? そんなこと、わたしなんかいくらでもあるから」
「ほやけど……」
「ほんとじゃないことを言ったとしても、相手を貶めるつもりで言ったわけじゃないんだから、それは二枚舌とは言わないんだよ」
「ほうなん?」
「それにさ、わたしだって真弓たちの機嫌取るために嘘をついてたの。真弓たちからすれば、わたしこそが二枚舌だったわけ」
「真弓って?」
「わたしがいない間に、うちのクラスと三組の間で騒動があったんでしょ? そのときに久美がかばってくれた子よ」
あぁ――と久美はうなずいた。
「あの子かいな。春花、あの子らがうちのこと馬鹿にするけん、うちから気ぃ逸らそ思て嘘ついたんじゃろ? 高橋さんから聞いたで」
「それだけじゃないよ。わたし、適当な人間だったから、他にもいろいろあったの」
「うち、春花が学校出て来んなって、そのあとえらい肺炎になったけん、うちのせいでそがぁなったて思いよった」
「わたしが部屋に籠もっちゃって久美とも会わなかったから、久美を誤解させちゃったんだね。親友なのにごめんね」
久美は首を横に振ると、ほれはええんよと言った。
「うちも引き籠もりやったけん、春花の気持ちはわかるよ」
「久美もいろいろつらいことばっかりだったもんね」
久美は小さくうなずくと、夕焼けを眺めながら言った。
「うち、お父ちゃんが死んで、お母ちゃんのお腹におった子も流れてしもた。ほれからおじいちゃんが死んで、おばあちゃんまでが死んでしもた。ほやけん、うちは疫病神やて思いよった」
「それ、伯母さんに言われたんでしょ? あんな人、相手にすることないよ」
「ほんでもな、うちが好きになった人が次々死んでいったんは事実やけん」
「だから、わたしも死ぬって思ったの?」
うなずく久美にわたしは笑顔で、でも生きてるよ――と言った。
「久美のお母さんだって生きてるじゃない。久美、お母さんのこと、好きじゃないの?」
「大好きや」
「でしょ? だったら、久美が好きになった人が死ぬってことにはならないよね?」
ほんでも――と久美は下を向いた。
「お父ちゃんが死んだんはうちのせいや。お母ちゃんのお腹におった子が流れてしもたんも、うちのせいや。うちが沖に流されたりせんかったら、お父ちゃんが死ぬことなかったんよ。お父ちゃんが生きとったら、お母ちゃんのお腹の子も、おじいちゃんも死ぬことなかったし、おばあちゃんかて死なんかったじゃろ」
「気持ちはわかるけど、おじいちゃんやおばあちゃんのことまで、自分のせいだっていうのは考え過ぎだよ。それにお父さんのことだって事故なのよ。だから、そのことで自分を責めるのはやめないとね。そうじゃなきゃ、お父さん、悲しむよ」
ほやかて――と言いながら久美は涙をこぼした。
「お父ちゃん、うちを助けよとして沈んだんで……。沈みながらな……、まだうちのこと……助けよとしよったんよ」
絞り出したような声で喋ったあと、久美は声を出して泣いた。わたしは久美を抱いて慰めながら、それでも元気を出すようにとうながした。
「逆の立場で考えてごらん。久美がお父さんを助けようとして死んでね、生き残ったお父さんがずっと悲しんで自分を責め続けるの。久美はそんなお父さんに何て言うの?」
まだ泣き続ける久美に、わたしはもう一度同じことを尋ねた。久美は鼻をすすりながら小さな声で言った。
「お父ちゃんが悪いんやないけん……、自分を責めたらいけんて言う」
「でしょ? 久美のお父さんもそう思ってるよ。お母さんのお腹にいた子だってね、久美が泣いたら悲しむよ。それに、きっと久美に会いたかっただろうから、絶対もう一度別な形で生まれて来て、久美の前に現れるから」
久美は涙で濡れた顔を上げた。
「ほんまに?」
「わたしたち、生まれる前から存在してるんだから、死んだあとも消えるわけじゃないんだよ。そうやって何度も生き死にを繰り返して、いろんなことを学ぶの。お父さんたちだって何かを学んでるし、久美や久美のお母さんだって学んでるの。話を聞かせてもらったわたしもね」
わたしから離れた久美は手で涙を拭きながら、だんだんなと言った。
「やっぱし春花はすごいわ。うち、春花と知り合えてほんまによかった」
「それはわたしも同じ。久美と知り合えてほんとによかったと思ってる。でもね、わたしたち、こうやって出会うことを約束して、それぞれの家に生まれたんだよ」
「ほうなん?」
「言ったでしょ? わたしたちは元々一つだったんだって」
またそこかと、久美は苦笑した。
「その話、早よ聞かせて欲しいで。ほんでも、うち、春花が言うとることわかるような気ぃする」
「ほんと?」
「さっきも言うたようにな、うちはここで死ぬつもりやった。うちのせいで春花を死なせてしもたて思いよったけん、夕日を見終わったら、死んでおばあちゃん所へ行こて考えよったんよ。。言うたら、そこは春花がおる所でもあるんやけんど。ほしたらな――」
もう夕日が沈むというときになって、何故か急に胸の中に春花を感じたと、久美は興奮気味に言った。
「ほんまに突然や。春花が胸ん中に飛び込んで来たみたいで、うちの心の中から、自分は二枚舌じゃいう気持ちと、疫病神じゃていう気持ちを取っ払ってくれたんよ」
「どうやって?」
「どうやってかはわからん。ほんでも春花が出て来たら、疫病神いう気持ちも二枚舌じゃいう気持ちも、すっと消えてしもたんよ。春花にほんまのこと言えんかったんは悪かったて思とるし、お父ちゃんらが死んで悲しいのは同しやけんど、自分を二枚舌とか疫病神て思う気持ちはのうなってしもたんよ」
わたしは久美の話に興奮した。あの死人の女やカラス天狗との戦いを、久美は感じてくれていたのだ。
「ほんでもな、偽善者いう気持ちぎりは残っとった。春花はこれも除けよとしてくれよったみたいなけんど、うちがほれに抵抗しよったんよ」
「どうして抵抗したの?」
「ほやかて、春花にうちが偽善者じゃていうんは知られとなかったけん」
わたしは久美に自分を偽善者だと思う理由を聞いた。すると、久美は天女が語ったのと同じ話をした。
「今はこがぁして話せるようになったけんど、ほんときは絶対春花に知られとなかったんよ。知られたらおしまいやし、知られるやったら死んだ方がええて思いよった。ほしたら心ん中の春花がな、うちの心を抱くみたいに包んでくれたんよ。うち、もう泣きそうになったけんど、偽善者いうんを知られまいと悪あがきしたんよ」
その悪あがきというのは崖から飛び降りることだったと聞かされ、わたしは今更ながら冷や汗を感じた。あのときはほんとに危機一髪だったようだ。
「もうほとんど発作的いうか衝動的やった。ほんときはちょうど夕日が沈んだとこで、おばあちゃん所行くいうときでもあったけん、うちは柵に手ぇかけたんよ。ほれで、そこを乗り越えよとしたんやけんど、ほんときよ。ほんときにな、聞こえたんよ」
「何が? 何が聞こえたの?」
どきどきしているわたしに久美は言った。
「おばあちゃんのあの言葉や。あの言葉がな、うちの頭ん中ではっきり聞こえたんよ」
「夕日見てきれいじゃて思うんはな、あんたの心がきれいなけんよ――ていう、あの言葉?」
「ほうよほうよ。ただな、ほれを喋っとったんは、おばあちゃんやなかった」
「違うの?」
久美はわたしをじっと見つめて言った。
「春花や。春花がな、おばあちゃんのあの言葉を言うてくれたんよ。あのときの声、今でもはっきり覚えとる。柵に手ぇかけて夕焼け空見たときにな、春花があの言葉を言うてくれたんよ。ほしたら、夕焼け空がおばあちゃんみたいに思えてな。胸ん中が温こなって、久美、がんばるんやで――ておばあちゃんが言うてくれとるような気ぃがしたんよ」
あのときの正気を取り戻した久美の笑顔を、わたしは思い出していた。新たな感動がわたしの目を濡らした。久美も笑っているけど涙ぐんでいる。
「うちな、春花が描いてくれた絵ぇ、懐に入れとったんよ」
「あの絵を持っててくれたの?」
うんと久美はうなずき、その絵をわたしに見せてくれた。もう暗くてよくわからないけど、じっと目を凝らすと、確かにわたしが描いた絵だった。
「その絵ぇ見たらな、これがほんまの久美なんやで――て春花に言われとるみたいじゃった。気ぃついたら、自分は偽善者じゃいう気持ちはのうなっとって、心ん中は春花でいっぱいになっとった。春花はほんまのうちを知りながら、うちを優しく抱き続けてくれとった。今の春花みたいに、ずっとうちの傍におってくれたんよ」
久美は感激しながらも、春花がこんな形で現れたのは、きっと春花が死んだに違いないと思ったそうだ。死んで魂になった春花が、自分を助けに来てくれたのだと思い、日が沈んだあとも、ずっと春花を想って泣いていたのだと言う。
「ほしたら、また春花の声がするやんか。初めは頭の中で聞こえとるんかて思たけんど、今度はちゃんと耳で聞こえとった。春花が泣きながらうちを呼ぶ声が近づいて来るけん、うち、春花の幽霊かて思たんよ。ほしたら、ほんまもんの春花やった。死んだて思いよった春花が、うちの居場所も知らんはずの春花が、うちを探してこがぁな所まで……」
久美は顔を崩して唇を震わせた。わたしも久美と再会できたときの感動が蘇っている。
「わたしもね……、わたしも夕日が沈んじゃったから……、久美はもう死んだんじゃないかって……、だからね……久美の声を聞いたとき……、うれしくてうれしくて……」
わたしたちは手を取り合うと、もう一度抱き合って泣いた。
「春花ぁ! おーい、どこにいるんだ?」
兄貴の声がした。それでわたしは兄貴と中村さんを駐車場に残して来たことを思い出した。
振り返ると、辺りをすっかり包み込んだ薄闇の中に、懐中電灯らしき明かりが見えていた。兄貴の声はそちらから聞こえて来る。
「お兄ちゃん、ここだよ、ここ!」
向こうから見えるかどうかわからないけど、わたしは大きく手を振りながら、明かりに向かって叫んだ。すると、明かりの方からまた兄貴の声がした。
「春花、そこか! 友だちはどうした? 見つかったのか?」
「うん。見つけたよ。もう大丈夫だから!」
「そうか! よかったな!」
「ありがとう、お兄ちゃん。中村さんもそこにいるの?」
「わしもおるぜ。友だち見つかってよかったな!」
「ありがとうございます! 中村さんのお陰です!」
叫んだあと、わたしは久美に東京から兄貴と二人で来たことと、伊予灘郵便局の中村さんが仕事も放って、わたしたちをここまで軽トラックで運んでくれたことを話した。そして、その軽トラックが警察に追いかけられて、そこの駐車場で兄貴たちが捕まったことを話しているところに、兄貴たちがやって来た。
来たのは兄貴と中村さんだけではなく、警官たちも一緒だった。懐中電灯を持っていたのは警官たちだ。
思いもしない者たちがぞろぞろ現れたことで、久美は緊張しているようだ。
警官たちはわたしと久美を見ると、どちらが妹さんですか?――と兄貴に尋ねた。
こっちですと兄貴がわたしを指差すと、男性警官がわたしに、あなたが白鳥春花さんですかと言った。
わたしが返事をすると、その警官は久美に顔を向け、それではあなたが兵頭久美さん?――と尋ねた。
はいと久美が答えると、男性警官はここにいる理由を久美に聞いた。でも、久美が返答に困った様子を見せると、女性警官が答えにくければ言わなくても構わないと言った。
すると久美は、ここへは死のうと思って来ましたと答えた。その言い方はきっぱりとしたもので、わたしには久美が胸を張っているみたいに聞こえた。
それでも女性警官は、答えにくいことを答えてくれてありがとうと、久美をねぎらい、今度はわたしに質問をした。
「あなたは久美さんがここで死のうとしてるって、どうしてわかったの?」
「それは――」
わたしは久美を見てから、自分と久美は心がつながっているからですと答えた。
思ったとおり、警官たちは当惑したように互いを見た。だけど、わかってもらえようともらえまいと、それが事実なのだから仕方がない。わたしと久美も顔を見交わし、くすっと笑い合った。
気を取り直した様子の男性警官は、わたしたちに言った。
「およその経緯は、こちらのお二人から聞かせてもらいましたけんど、久美さんのご家族から捜索願いも出とりますので、お二人には署へご同行願いまして、そちらで改めてお話を伺わせてもろても構んですか?」
久美が小さな声ではいと答えると、警察官はわたしを見た。どきっとしたわたしは、ちらりと兄貴や中村さんを見てから言った。
「あの、わたしたちは逮捕されるんでしょうか?」
「逮捕? いやいや、逮捕はしません。あなたはお友だちを助けんさったぎりですけん。感謝状は出ると思いますけんど、逮捕状は出んでしょう」
よかったぁとわたしは思わず声を漏らしてから、同行することに同意した。すると、ほんでも――と男性警官は言い足した。
「中村さんについては、切符を切らせていただきます」
「切符?」
「二人乗りの軽トラックに三人乗って運転しましたけんね。事情はどうあれ、道路交通法違反ということで対応させてもらいます」
「え? だって中村さんは――」
「ええんやて。わしは姉やんらの力になれたけん、他のことはどがぁでもええんよ」
中村さんはわたしに微笑みかけて言った。
「だけど……」
「別に犯罪で逮捕されるわけやないけん。ほれより、姉やんの友だちが無事じゃったことが何よりよ。わしにとっては、ほれこそが誇りぜ」
わたしは胸がいっぱいになり、中村さんに抱きついた。中村さんはおたおたしながらわたしを抱き返し、病み上がりやのにがんばったな――と言ってくれた。
「あの――」
久美が中村さんに声をかけた。顔を向けた中村さんに久美は言った。
「見ず知らずのうちのために、こがぁなご迷惑をおかけしてしまいました。ほんまに、ほんまに申し訳ありませんでした。ほれと、ほんまにありがとうございました」
久美は深々と頭を下げた。中村さんは兄貴を見てにんまり笑うと、まっことええ役柄ぜ――とうれしそうに言った。
兄貴が中村さんに尊敬の眼差しを向けていると、久美は兄貴にも頭を下げた。
「お兄さんにも、うちのためにこがぁなことをしていただき、ほんまにありがとうございました」
わたしは中村さんから離れると、今度は兄貴に抱きついて、ありがとうと言った。
兄貴はにんまりしながら中村さんを見て、ほんとにいい役柄ですねと言った。ほうじゃろうと中村さんが返すと、病みつきになりそうですと兄貴は笑った。
「ほれじゃあ、中村さんらにもご同行願って構んですか?」
男性警官の言葉に中村さんはもちろんと答えた。ほんなら――と警官は、久美とわたしはミニパトカーに乗って、兄貴は中村さんの軽トラックに乗せてもらうようにと言った。
駐車場まで移動すると、中村さんは家に電話をさせて欲しいと警官たちに言った。どうぞどうぞと言われた中村さんは、ポケットからスマホを取り出して家に電話をかけた。
出て来たのは奥さんみたいだけど、仕事を抜け出したことがバレたのだろうか、中村さんはかなり叱られたみたいだ。スマホを耳に当てたまま何度も深く頭を下げている。
それでも中村さんは自分が何をしていたのかの言い訳はしないまま、この埋め合わせは必ずするからと謝り続けていた。埋め合わせということは、奥さんと何かの約束があったのだろうか。だとしたら、二人には申し訳ないことをしてしまった。
「大丈夫ですか?」
電話を終えた中村さんに、男性警官が心配そうにたずねた。中村さんは照れ笑いをしながら、実は今日は女房の誕生日だったと言った。
ほれは大事じゃと女性警官が言った。何、ええんよ――と中村さんは言ったけど、警官たちは中村さんに同情していた。
「姉さん女房で、いっつもかっつも世話になりっ放しやけんな。今日ぐらいはて思いよったんやが」
「ほんでも、あなたが何をやんなはったんかを説明したら、きっと奥さんもわかってくんなはらい」
「ほやけど、切符切られたことは黙っとりんさいや。また叱られるけん」
本当に警察に捕まったのだろうかと思うほど、警官たちは中村さんに親身だった。何だかすごくいい感じで、中村さんに迷惑をかけてしまったことを忘れそうだ。だけど、絶対忘れるわけにはいかない。だって、奥さんの誕生祝いを犠牲にしてまで、中村さんはわたしたちのために動いてくれたんだもの。
わたしと久美は何度も頭を下げて中村さんにお詫びした。
すみませんでしたと兄貴も中村さんに謝ったけど、兄貴は中村さんの姿勢に大いに感激したらしい。オレは中村さんみたいな男になる!――なんて言って中村さんを喜ばせた。でも警官たちからは、交通ルールは守ってよと釘を刺されていた。
西の空は夕日の名残の明かりもほとんどなくなり、辺りはすっかり闇に包まれていた。だけど、わたしたちの心は明るかった。
兄貴が大声で中村さんと喋りながら、軽トラックに乗り込んだ。その様子を見ると、すべてがうまく行ったんだと、改めて思えて来る。
わたしは久美の手を握ると微笑み合った。
よかった。今の気持ちは、ただそれだけだ。
青空と白い雲
佐田岬半島の付け根に、八幡浜という町がある。そこの警察署でわたしたちは事情聴取を受けた。
連絡を受けた久美のお母さんは政吉さんの車で警察署まで来た。久美と面会したお母さんは、何も言わずに久美を抱きしめた。久美は何度もごめんなさいと謝りながら泣いた。
久美は政吉さんにも頭を下げ、迷惑をかけたことを詫びた。
すでに事情聴取が終わっていた中村さんは、政吉さんが迎えに来たのを確かめると帰ろうとした。わたしたちは何度もお礼を言ったが、久美のお母さんと政吉さんも中村さんの手を握り、繰り返して感謝を告げた。
こうして中村さんは帰って行った。中村さんから話を聞いた奥さんは、どんな顔をするのだろう。中村さんが奥さんから叱られないことを祈っているけど、きっと奥さんも中村さんが無事だったことが一番うれしいと思う。
政吉さんは久美の無事を喜んだけど、わたしが言ったとおりに、久美が佐田岬で見つかったことを、とても不思議がっていた。
それは警察でも同じことで、改めて久美の居場所がわかった理由を問われても、わたしは同じことしか言えなかった。どうしてそうなのかと聞かれると、上手く説明できないと言うしかなかった。風船たちや光の存在の話をしたところで、わかってもらえないだろうし、話が長くなるのは避けたかった。その話を聞かせたいのは久美だけだから。
結局は不思議なことということで聴取は終わった。久美は二度と死ぬだなんてことは考えないと約束し、警官たちに励まされながら解放された。
兄貴は母に電話で連絡し、これまでのことを報告していた。だけど、わたしたちが警察に捕まったことを話すと、周囲の人たちにも聞こえるほどの母の叫び声が、スマホから飛び出して来た。
兄貴が母をなだめながら、警察に捕まった理由を説明すると、さらに大きな叫び声が飛び出した。兄貴は大慌てで、お巡りさんたちが驚くから大声を出さないよう母に言った。
そこへ久美のお母さんが兄貴と交代して母に挨拶をし、わたしと兄貴が久美の命を救ってくれたと、泣きながら礼を述べた。そして、わたしたちのことを叱らないようにと頼んでくれた。
続いて久美も電話に出て、みんなに迷惑をかけたことを母に詫びた。もう母は落ち着きを取り戻したようで、周囲に声は聞こえなかった。でも、うなずく久美の様子を見ていると、母は久美を励ましてくれているようだ。
わたしも電話を代わると、母はわたしの体を心配してくれた。また、今回のことは大目に見るけれど、今度からは自分だけで行動しないようにと言った。
それと、どうして久美の居場所がわかったのかと聞かれたけど、やっぱり説明ができなかったので、家に帰ってから話すと言った。
最後にもう一度電話に出た兄貴は、母の怒りが収まったと思ったのか、すっかり安心した様子だった。だけどそれは誤解だったようで、スマホを耳に当てた兄貴は、何度も謝りながらどんどん小さくなった。
久美はお兄さんに申し訳ないと言いながら、兄貴の仕草や表情を見ながら笑っていた。久美も兄貴という人間をつかみかねているらしいけど、それが面白いみたいだ。
警察を出ると、政吉さんがみんなに晩ご飯をご馳走すると言った。ずっと緊張の連続で食事のことなど忘れていたけど、食事と聞いたら急にお腹が空き出した。兄貴は声を出さずに、満面の笑みをわたしに見せた。
食欲はどうかとお母さんに聞かれた久美は、ぺこぺこだと言った。食欲が出たなら安心だなと兄貴は笑ったけど、まったくそのとおりだとわたしも思う。
政吉さんはわたしたちをファミリーレストランへ連れて行ってくれた。普通の夕食の時間はとっくに過ぎていたと思うけど、お店の中は結構なお客さんが入っていた。
お店の人に席を案内され、それぞれが好きな物を注文すると、さて――と政吉さんが言った。
「姉やん――やのうて、春花ちゃんに改めて聞くけんど、久美の居場所は夢の中で見たいうことじゃったな」
はいとわたしがうなずくと、そんなことはちょくちょくあるのかと政吉さんは言った。
あのときが初めてだったと答えると、久美のお母さんがまた久美の絵の話を出した。この話は政吉さんは聞かされていたはずだったけど、そのときは大して関心を示してくれなかった。だけど久美を見つけた今は、その絵を見てみたいと政吉さんは言った。
久美が懐からその絵を出して政吉さんに見せると、上手な絵ぇじゃなと政吉さんは言った。それで、この絵のどこが不思議なのかと改めて尋ねるので、久美と久美のお母さんが代わる代わるに、絵に描かれた生き物たちについて説明した。
「こがぁな絵を描けるのに、久美と春花ちゃんの間に特別な関係がないんじゃったら、春花ちゃんは超能力者いうことにならい」
久美のお母さんが真顔で言うので、わたしは咄嗟に否定した。
「わたし、超能力者なんかじゃありません。こんな絵を描いたのも、夢の話も、他の人ではありませんでした」
「ということは、やっぱしこの子らの間には、特別な関係があるいうことで」
久美のお母さんが政吉さんを見ながら強調すると、兄貴が付け足すように、わたしが病院で見た久美の夢の話をした。その声が大きかったので、わたしは兄貴に小さな声で喋るよう注意した。
兄貴はむっとした顔になったあと、自分の感想を述べた。
「その夢は、そのときの久美さんの気持ちが春花に伝わったんだと、オレは思います。それも二人の心がつながっている証拠じゃないでしょうか」
兄貴はちらりと久美を見た。しかし、久美は兄貴の演説を聞いていないみたいで、兄貴の方は見ないまま、ほんとにそんな夢を見たのかとわたしに尋ねた。
わたしはうなずいたけど、久美を貫いた矢が言霊だったことは黙っていようと思った。また、久美に取り憑いた三匹の化け物たちのことも、今は言わないでいることにした。だって、そんな話をしたら久美が嫌な気持ちになるだろうし、わたしが久美を助けたという自慢話みたいになってしまう。そんなのは絶対に嫌だ。
なるほどな――と納得した様子の政吉さんは、わたしと久美を見比べながら、これからもその関係を大事にするようになと言った。それから兄貴に顔を向けた政吉さんは、久美を助けるために東京からどうやって来たのかを、久美に説明してやってくれと言った。
兄貴はさっきのことで少し元気がなくなったみたいだったけど、政吉さんの頼みで復活した。それこそ水を得た魚のように、わたしが一人で家を出ようと考えたことを見抜き、妹のために学校も休んで、トラックをヒッチハイクして来たと説明した。途中、わたしから何度も声が大きいと注意されたけど、まったく気にする様子はなかった。
久美の手紙には住所が書かれていなかったので、消印にあった伊予灘郵便局を目指して来たということも、兄貴は得意げに話した。
わたしはすぐに郵便局の人たちが親切だったと話し、特に中村さんがいなければ、久美を迎えに行けなかった言った。すると久美も、本当にあんな人がいたとは信じられないと感慨深く言った。
政吉さんや久美のお母さんも、中村さんには改めてお礼をしなくてはいけないと言い、今日が誕生日だった奥さんと揉めなければいいけれどと心配した。
忘れられたかのような兄貴は、しばらく途方に暮れていたみたいだった。でも気を取り直して中村さんの話に混じると、軽トラックで猛スピードで走ったときの様子や、警察に追いかけられたときのことを喋った。
みんなが話に聞き入ると、兄貴はまた調子に乗って、ぶっ飛ばす軽トラックの中で、わたしが兄貴にしがみついていたとか、声をかけても言葉も出なかったなどと言った。
軽トラックが怖かったのは事実だけど、わたしにしがみついて声も出せずに固まっていたのは兄貴の方だ。わたしが猛抗議をすると、オレはずっと中村さんと喋っていたと嘘ばっかり。
挙げ句の果てには、警察に追われているときに、わたしが気を失ったと言うから、わたしは頭に来た。あれは気を失っていたんじゃなく、久美に取り憑いた言霊たちと戦っていたんだから。だけど、それを言えないわたしは、悔しさを呑み込むしかなかった。
すると、それはいつ頃のことかと、久美が兄貴に尋ねた。
えっと――と兄貴は鼻を指で押さえながら、日がほとんど暮れかけていた頃だったと思うと答えた。
「そのあとすぐに駐車場に着いたから、ちょっとの間だけなんだけどね」
少しは悪いと思ったのか、兄貴はわたしに気遣うような目を向けた。
久美はわたしを見ると、感動したように言った。
「やっぱし春花やったんじゃね」
「え? 何が?」
「春花がうちを助けに来てくれたってことや。お兄さんの話聞いて、うちはそがぁ確信したんよ」
何のことかと兄貴はきょとんとしていた。政吉さんも久美のお母さんも、久美の話がよくわからない様子で、何を今更という顔をしている。
だけど久美は構わずわたしの両手を握ると、改めてお礼を言わせて欲しいと言った。
「春花。春花がおらんかったら、うちは今頃死んどった。うちの心にずっと刺さっとったトゲを、春花が抜いてくれたんよ。だんだんな。だんだんありがとう」
久美はわたしを抱きしめた。久美が何のことを言っているのか、わたし以外は誰もわからない。だけど、政吉さんが拍手をし、久美のお母さんも拍手をした。兄貴は何が何やらわからないまま、政吉さんたちに続いて拍手をした。
久美の言葉はわたしの胸を打った。言葉では何も説明はしていないけど、わたしの涙が久美の言うとおりだと伝えただろう。久美もわたしを抱きながら涙ぐんでいた。
そこへ注文した料理が運ばれて来た。わたしたちは涙を拭いて微笑み合い、テーブルは祝いの席となった。笑顔と楽しい話にあふれ、つい数時間前に久美が命を絶とうとしていたとは思えないほど、賑やかで明るい食事となった。
何をしに来たのかと言われるかもしれないのに、兄貴は自分がスマホで撮った写真をみんなに披露した。そのうちの一枚を見た久美のお母さんが、あれ?――と言った。
それは伊予灘駅に着いたときに、兄貴がわたしに怒られながら撮影した駅と列車の写真だった。その列車の手前の席にこちらに背を向けて座る少女を指差し、これは久美じゃないかと久美のお母さんは言った。
兄貴が驚いてその少女の部分を拡大すると、絶対にほうよと久美のお母さんは言った。
「ほんまじゃ。これ、うちやし」
写真をのぞき込んだ久美は、わたしと兄貴を見た。
「春花とお兄さん、うちが乗ったんと対の列車に乗りよったんか。これはびっくりや」
警察で聴取を受けたときは、久美とわたしたちは別々に話を聞かれたので、久美がどうやって佐田岬へ向かったのかは、まだ聞いていなかった。
ところが何と、久美はわたしたちが乗って来た列車で八幡浜へ行き、そこからバスとタクシーで佐田岬へ行ったらしい。あのとき、馬鹿兄貴が駅の端まで歩いて行かなければ、わたしは駅で久美と出会っていたはずだった。
わたしたちの目が兄貴に集まった。うろたえる兄貴に、政吉さんがむすっとした顔で言った。
「何じゃい、今回のことは兄やんのせいじゃったかい」
「いや、ですからこれはですね、その、えっと……」
大慌ての兄貴を見て、政吉さんは笑い出した。
「終わりよければ、すべてよしぜ。兄やんは久美を助けるために、がんばってくれたんやけんな」
「いや、まぁ、はぁ」
返す言葉が見つからない兄貴に、みんなが笑った。
翌日、政吉さんがわたしたちを松山まで車で運んでくれた。そのとき、尚子さんや和美さん、八重さんが見送ってくれたのはもちろんだけど、久美を疫病神と罵っていた伯母さんまでもが見送りに来てくれた。
久美が死のうとしていたことを聞かされて、伯母さんは深く反省したそうで、これまでの態度を久美や久美のお母さんに詫びた。二人は伯母さんの謝罪を受け入れ、また遊びに来ることを約束した。
途中、久美のおじいちゃんやおばあちゃん、そしてお父さんのお墓参りもした。
前はお墓参りがつらかったけど、今はみんなが自分を見守ってくれているような気がすると、久美は言った。久美の言葉に、久美のお母さんもほっとしているみたい。もちろんわたしもよかったって思ってる。
お墓参りのあと、わたしたちは伊予灘郵便局に立ち寄った。局員の人たちは中村さんから話を聞いていたようで、わたしたちが顔を見せるなり、よかったなとみんなが喜んでくれた。窓口にいたお客さんは、何の話かわからずきょとんとしていたけど、あの女性の局員さんは立ち上がり、大きな声でおめでとうと言ってくれた。
久美も久美のお母さんも戸惑いながら、いろいろお世話になりましたと感謝を述べた。政吉さんも後ろで一緒に頭を下げた。
中村さんが拍手をすると、他の局員の人たちも手をたたき、小さな郵便局の中はすっかりお祝いムードになった。
「中村さん、昨夜は大丈夫だったんですか?」
兄貴が恐る恐る尋ねると、フライパンで殴られたと中村さんは言った。わたしたちが驚くと、冗談ぜと中村さんは笑った。
「女房も喜んでくれた。今晩、改めてお祝いするんよ」
「それはよかった。オレ、安心しました」
「向こうへ戻んたら、試験がんばれや。追試があろ?」
「え? そうかな」
「ほら、あるじゃろが。兄やんぎり試験なしで済ましてくれるはずがなかろ。ほれと、勝手に学校休んだことで、先生から大目玉を食らわい」
兄貴が困ったように頭を掻くと、中村さんはカラカラと笑った。
「姉やんらも元気でな。またいつか二人で遊びに来たらええぜ。ほんときは、わしが美味い物食わしちゃるけん」
「あの、オレは?」
恥ずかしげもなく自分の存在をアピールする兄貴に、わたしは顔が熱くなった。でも中村さんは明るく兄貴に応じてくれた。
「兄やんもぜ。将来はわしみたいな男になるんじゃろ?」
「それはもう絶対に!」
中村さんは局員の仲間を振り返って言った。
「聞いたか? この兄やんはな、学校卒業したら、この伊予灘郵便局で働くんぜ」
ほれはええとみんなが手をたたくと、兄貴は慌てふためいた様子でわたしたちを見た。
わたしは笑いながら、がんばってねと兄貴を励ましてやった。それからわたしたちは改めて中村さんたちにお礼を述べて、伊予灘郵便局を後にした。
待ちよるぜという中村さんの声が、後ろから追いかけて来ると、兄貴は頭を抱えて、どうしようと言った。久美はくすくす笑いながら、お兄さんて面白い人じゃねと言った。
「兄やんはえらい純情なんじゃな。みんな冗談言いよるぎりぜ」
政吉さんがにやにやしながら兄貴を慰めた。そうでしょうかと兄貴が真面目な顔で聞くと、中村さんは本気かもしれんと政吉さんは言った。
兄貴がまた頭を抱えると、可哀想だからもういじめてやるなと、久美のお母さんが政吉さんに言った。だけど久美のお母さんもおかしくて仕方がないらしい。喋りながら笑っている。
松山にはお昼前に着いた。東京へは松山駅から夜行バスで帰ることになっている。それまで時間があるので、久美はわたしたちを松山城へ案内すると言った。それで政吉さんはみんなでお昼ご飯を食べたあと、わたしたちを城山の近くで降ろして伊予灘へと帰って行った。
東京から松山へ着いたとき、兄貴はできれば松山城を見てみたいと言っていた。そのときはわたしに怒られたけど、まさかのお城見学に兄貴は大喜びだ。
城山にはリフトとケーブルカーがあった。でも、それで頂上まで行けるわけではなかった。リフトもケーブルカーも山の中腹までしかなく、あとは歩いて登るらしい。
急な登り坂は病み上がりのわたしには体力的にきつかった。それなのに兄貴は全然わたしのことは放ったらかしで、自分が興味を引かれた方へさっさと歩いて行く。
久美はわたしを心配して、休憩しながら登ろうと途中で足を休めた。そして、よくそんな体で助けに来てくれたものだと、また泣きそうになった。
すると兄貴は急いで戻って来て、大丈夫かとわたしを気遣った。だけど、その仕草がわざとらしい。わたしの額に手を当てて、熱はないなと言ったり、全然その気なんかないくせに、おんぶしようかとしゃがんでみせた。
だからわたしは、じゃあお願いねと言って、いきなり兄貴の背中に飛びついてやった。兄貴は見事につぶれてカエルみたいになった。
「お前なぁ、いきなり飛び乗るなよ!」
わたしの下で藻掻きながら、早く降りろと兄貴は怒鳴った。わたしが笑いながら降りると、兄貴はぷんぷん怒りながら立ち上がった。でも、大丈夫ですかと久美に声をかけられると爽やかな笑顔になって、これぐらいどうってことないっスと胸を張った。
その変わり身の早さに久美は戸惑っていたが、久美のお母さんは声を出して笑った。
お城には観光客だけでなく、地元の人たちも遊びに来ているようだった。山頂まで登っても天守閣には行かずに、街の眺めを楽しんでいる人たちも大勢いた。
その中に、中学生と思われる数名の男子のグループがいた。そう言えば、今は中間テストの時期だ。試験のあとの気分転換に遊びに来ているのだろう。みんなで海の方を眺めながら騒いでいる。
そのうちの一人がふとこちらを振り返ると、兵頭?――と久美に声をかけた。
「え? 石田くん?」
久美が驚くと他の生徒たちも振り返り、兵頭だと口々にうれしげな声を上げた。久美が石田くんと呼んだ男子生徒が駆け寄って来ると、仲間の生徒たちもこれに続いた。
「やっぱし兵頭や。わしら心配しよったんぞ」
「心配? うちのことを?」
「当たり前やないか。お前、停学なったあとも学校戻んて来んで、そのままおらんなってしもたろ? ほやけん、わしらお前に声もかけられんままやったんぞ」
「え? ほれって、どがぁな?」
「田中が橋本らにやられよったんを、わしらはわかっていながら止めよとせんかった。ほれをお前は体張ってやめさせよとしたろ? わしらな、自分が恥ずかしなってしもて、お前が戻んて来たら謝ろて思いよったんよ。ほしたら、学校やめたて聞いたけん」
元気やったかと、他の者たちも久美に声をかけた。
思いがけない昔の仲間との出会いに、久美は動揺した様子だったけど、安心したようでもあった。誰が誰なのかはわからないけど、何の話をしているのかは、わたしにもわかった。久美は一人悪者にされて学校を追い出されたみたいな形だったけど、実際は味方になってくれる者たちが大勢いたということだ。
久美は仲間たちのねぎらいに感謝をしたあと、わたしと兄貴とお母さんを紹介した。
一緒にいたのが母親だとわかり、石田くんと仲間たちは恐縮したみたいだ。でも、石田くんたちの言葉を聞いて、久美のお母さんがとても喜んだので、少し緊張は解れたようだった。
それから久美は彼らを一人一人わたしたちに紹介した。兄貴は高校生なので少し遠慮されたみたいだったけど、わたしは同じ中学生なので彼らの気を引いたようだ。はにかんだ様子で何かを言いたげな彼らを見ていると、わたしもまんざらでもないのかもと、鼻の穴が少し膨らんでしまう。
一通りの挨拶が終わると、あれからは田中へのいじめはなくなったと、石田くんが久美に言った。
「あとでわかったことなけんど、そもそもの原因は仲田やったんよ」
「仲田くん? なんで仲田くんなん?」
「あいつがな、田中のことをあることないこと、橋本らに言うとったみたいな。ほんで、橋本らが田中に腹立てたんよ」
「ほんまに? ほんでも仲田くん、なんでそがぁなことを……」
「あいつ、ほんまは田中に気があったみたいでな。ほんでも田中の言葉が素っ気なかった言うか、そがぁ聞こえてしもたんやろな。ほれで、なんぞて思たみたいなで」
新たに登場した名前が誰なのかは、当然わたしたちにはわからない。でもこの仲田という男子が、いじめグループを焚きつけたらしいことは理解できた。しかも、その嘘の出所が久美だと、この仲田という生徒はいじめグループに話していたようだ。だからこそ、いじめをやめさせようとした久美に、いじめグループは猛反発したのだろう。
男子生徒たちによって争いを止められたとき、この仲田という生徒は久美に向かって、お前は二枚舌だなと言ったらしい。
わたしはあのカラス天狗の主は、この仲田という生徒だったのかと理解した。聞けば、この生徒も小学校のときに他県から転校して来たそうで、独りぼっちでいることが多かったようだ。
それにしても、どうしてこの生徒は久美を貶めようとしたのだろう。わたしはそのことを尋ねたが、石田くんたちにも理由はわからないようだし、久美にもわからなかった。
だけど、わたしは思った。きっと仲田という生徒は、久美が仲間に合わせて本音を隠していることを、見抜いていたのではないだろうか。自分と同じ匂いを久美に感じたからこそ、久美に意地悪をしたくなったのだろう。それはこの生徒が自分自身にうんざりしていたということに違いない。
「そがぁなわけやけん、もういじめは起こらんと思うけんど、またあったら、今度こそわしらがやめさすけん。ほれと田中にも、お前が元気やったて伝えとこわい。あいつもお前のこと気にしよったけん」
「だんだん。ほれで、仲田くんはどがぁなったん?」
「そがぁなことしてしもたけんな。二学期なったら、どこぞへ転校してしもとった」
何とも後味の悪い話だけど、わたしはその仲田くんが新しい学校で、本当の友だちを見つけられるように祈った。
少し沈黙があったあと、石田くんは言った。
「兵頭はもうこっちへは戻らんのか?」
「そがぁに簡単に、あっち行ったりこっち行ったりはできんし。ほれに、うち、ようやっと自分の居場所見つけたけん」
久美は微笑みながら、ちらりとわたしを見た。
ほうかと石田くんたちは残念がった。でもすぐに気を取り直したように、今日はここに何をしに来たのかと尋ねた。
久美はわたしと兄貴を振り返り、親友の兄妹に松山を見せていると言った。それは久美が松山を悪くはとらえていないということになる。
石田くんたちはうれしそうに、松山のお勧めの所を口々にわたしたちに教えてくれた。また、わたしにメールアドレスやラインの話をするので、わたしはスマホを持っていないと言った。
もちろん久美にも尋ねたけど、やっぱり久美もスマホがない。石田くんたちはがっかりしていたけど、ないものはしょうがない。ほんじゃあ元気でなと、それぞれが明るく久美に声をかけ、わたしたちにも手を上げたり頭を下げたりしてくれた。
みんなもね――と返した久美は晴れ晴れとした笑顔だった。久美のお母さんもほんとにうれしそうだったけど、わたしだって最高の気分だ。久美が愛媛を訪れたのは、本当はこのためだったのではないかと思うほど、すべてが上手く動いているようだ。
天守閣の上から見た眺めは素晴らしかった。街が一望できるし、すぐそこに山や海がある。ここは松山で一番の観光スポットで、天守閣の中は多くの観光客で賑わっている。
それにしても、こんな近くに自然があるのは本当に羨ましい。それに自然が近いというのは、人にとって大切なことだと思う。だって、人間も自然の一部のはずだから。
わたしから少し離れた所で、兄貴が久美と久美のお母さんを相手に、道後温泉とか石手寺という有名な場所についての知識を披露している。自分が説明を聞く立場だってことを忘れているらしい。
二人ともそんなことは知っているって言ってやればいいのに、黙って話を聞いているから、兄貴の口はいつまでも止まらない。
久美はちらりとわたしの方を見るけど、兄貴が喋っているのを無視するわけにもいかないようだ。気にしなくていいからと微笑みで応じると、わたしは一人で景色を眺めながら考えた。それは、あの風船たちのおばあさんみたいな生き物が教えてくれたことだ。あの生き物が語ってくれた、三つの愛の話は今でもわたしの頭から離れない。
人が三つの愛から生まれるならば、他の生き物たちもみんな同じだろう。つまり、すべての生き物は愛から生まれ、愛で満たされているということだ。
みんな自分が何者かを覚えていないけど、誰もが愛の化身なんだ。悪いことをする人だって、その本当の姿は愛に違いない。だって、生まれて来たときは、みんな同じはずだから。悪いことをするようになるのは、自分が何者かがわからないまま、満たされない気持ちが積み重なるからだろう。
だけど、こんな話は誰にでもできるものじゃない。だって愛って言うだけで、みんな気恥ずかしい気持ちになって、真面目に話さなくなってしまうもの。
でも本当の愛っていうのは、みんなが思い浮かべるようなものじゃない。
わたしは自分が光の存在だったことを思い出したとき、愛が何かを知った。いや、正しく言えば、これも思い出したと言う方がいいだろう。
愛とは自分とすべてがつながっているという感覚的かつ感情的な理解だ。そう感じているときには、心の底から純粋な喜びが湧き上がって来て、心は最高の喜び一色になる。
人間の世界には男女の愛や家族愛、友情や人類愛など、いろんな形の愛がある。これらはみんな、純粋な愛が人間関係という形で制限されたものなのだと思う。
一番の基本的な愛っていうのは、無条件に相手を受け入れ、自分も受け入れられるというものだ。相手とのつながりを感じ、自分と相手が一つなんだって思い出すから、そこには嘘もなければ批判もない。相手や自分を高く見たり低く見ることもなく、互いのそのままを受け入れ合う。だから他人を悪く見なくなるし、自分が大好きになる。
そんな愛の中にずっといられたならば、どれほど幸せだろうと思う。それなのにわたしたちはわざわざそこを離れて、愛が見えにくいこの世界に生まれて来る。それにはどんな意味があるんだろう?
わかっているのは、忘れていたことを思い出すときに、感動するということだ。きっとこの世界には、愛が様々な所に様々な形で散りばめられているのだと思う。
それをわたしたちは一つ一つ確かめ、愛を見つけて回りながら、最後には純粋な愛の世界に戻って行くのだろう。
おそらくそれは、愛の世界にずっといたのではわからない喜びの発見に違いない。自分が暮らしている所の本当のよさは、そこから離れてみないとわからないというけれど、それと同じだろう。ただ愛の世界にいただけでは、愛の本当の価値は理解しにくいのかもしれない。
そう考えると、光の存在の自分よりも、何もできない今の自分の方がすごいような気がしないでもない。何だかこそばゆいような誇らしさが、わたしの鼻を通り抜けている。
「逃げて来てしもた」
久美がわたしの隣に来て舌をぺろりと出した。向こうでは兄貴が久美を気にしながら、まだ久美のお母さん相手に喋っている。久美のお母さんも気の毒だけど、お願いします。もう少し辛抱して、わたしと久美の時間を作ってね。
「ごめんね。うちの兄貴、空気読めないから」
「ええんよ。ほれより、あそこ見てみ。海の左側を陸地がずっと伸びとろ? あの辺が伊予灘でな、あのずっと先が佐田岬なんよ」
へぇと言って、わたしは久美が指差す辺りを眺めながら、昨日のことをいろいろと思い出していた。
兄貴と列車で伊予灘駅へ向かったことや、伊予灘郵便局を訪ねたこと、中村さんに軽トラックで海沿いの道をぶっ飛ばしてもらったこと、そして警察に追われながら、夕闇の中で久美を探して涙の再会を果たしたこと。そんなことが走馬灯のように頭に浮かぶけど、今は本当にそんなことがあったのかと思うほど、遠い昔のことのように思えてしまう。
「うち、あがぁな所まで行きよったんじゃね」
遠くにかすんで見える佐田岬半島を眺めながら、久美がぽつりと言った。
「春花が来てくれんかったら、今ここにうちはおらんかった。ほれを考えたら、怖い気持ちになるけんど、えらい不思議なことでもあったて思えるで」
「わたしもね、普通だったらこんなことできないよなって思ったよ」
「じゃろ?」
「だけど、こうしてできたんだもんね。だから、久美が言うように不思議に思えるけど、でもこれは全部こうなるように決まってたんじゃないかとも思うんだ」
「全部決まってた?」
わたしはうなずくと、だってさ――と言った。
「わたしが学校にいられなくなって肺炎で死にかけたから、わたしは光の存在にも会えたし、風船たちのこともわかったんだよ」
「あぁ、光の存在に風船。早よ、その話聞かせて欲しい」
焦れったそうな久美をなだめて、わたしは話を続けた。
「もし、わたしが真弓たちと揉めなかったら、あるいは、わたしが肺炎で死にかけたりしなかったら、わたしは久美を助けることができなかったんだよ」
「うちの居場所を光の存在とか、風船が教えてくれたけん?」
「そう。だからね、今回のことはたまたまこうなったんじゃなくて、こうなるべくしてなったんだと思うんだ」
久美は少し考えて言った。
「うちにこれまで起こったことも対?」
「そうだよ。全部が必然的に起こったんだよ。お互いにつらいことが多かったけどね。でも、二人ともそこからいろんなことを学んで強くなったの」
ふーんと久美は言った。わたしの話を受け入れるには、時間が必要なのかもしれない。久美が経験して来たことは、それだけつらいものだから。
「強なってどがぁするん?」
「それが人間の成長ってやつだよ。それにさ、強くなったら苦しんでる人とか、悩んでる人に手を差し伸べられるじゃない」
「まぁ、ほれはほうじゃね」
久美はうなずいた。ちょっとはわかってもらえたかな。
「わたし思うんだけどさ。この手を差し伸べるっていうのは、結局は喜びを伝えるって言うか、喜びを広げるってことなのよ」
「喜びを広げる? 何かええね」
久美の顔に笑みが見えた。わたしも思わず微笑んだ。
「でしょ? わたしね、久美と一緒にそんなことができたらいいなって思ったんだ」
「春花と一緒に喜びを広げるん?」
「そ」
久美はまた伊予灘の方を眺めると、明るい声で言った。
「うち、なんか自分の道が見えて来たような気がすらい」
「ほんと? うれしい!」
わたしが喜ぶと、久美の笑顔が振り返った。わたしたちをそよ風が撫でて行く。気分は爽快だ。
「ところでな、風船の神さまとか光の存在の話やけど、ちらっと触りぎりでも言うてくれん? うち、話聞くの東京まで待ち切れんけん」
周りの観光客を気にしながら、久美が小声で言った。
「ここで話すの?」
久美は目を輝かせてうなずいた。わたしは隣にいる観光客をちらりと見てから、久美に顔を寄せた。
「わたしを助けてくれた光の存在はね」
やはりわたしに顔を近づけた久美は、うんうんとうなずいた。
「実は、わたしたちだったの」
え?――と久美が思わず大きな声を出したので、わたしは慌てて人差し指を口の前に立てた。久美は自分の口を手で押さえると、どういうことかと言った。
「わたしたちは元々一つの光の存在だったの。その光の存在がね、わたしたちを助けてくれたんだよ」
「自分が自分を助けたってこと?」
「えっと、そういうことになるのかな」
わからんと言いながら、久美は額に手を当てた。でも、すぐに気を取り直したように言った。
「まぁ、ええわ。ほれについては、向こうに戻んてから聞かせてもらお。じゃあ、今度は風船や。風船の神さまて何のこと?」
「風船のって言うか、風船以外にもいろいろいるんだけどさ」
「何が?」
「手毬とか、ビーチボールとか……、いや、ビーチボールじゃなくてクラゲか」
わたしが喋っている間に、久美の眉根がどんどん寄っていく。
「また、訳のわからんことぎり言うて!」
「いや、だってほんとなんだよ。他にもね、山よりでっかい大蛇とか、枯れ草みたいなのとか、大きな舌でべろって舐めるのとか……」
あぁと言いながら、久美は首を大きく横に振った。
「もう、さっぱりわからん」
「とにかくさ、そんな生き物たちの神さまがね、わたしや久美なんだよ」
久美がため息をついていると、兄貴が久美のお母さんと一緒にやって来た。この話もおしまいだ。
「二人で何喋ってんだ?」
お邪魔虫の兄貴が、わたしたちの間に割り込んだ。むっとしたわたしは言った。
「お兄ちゃんの噂」
「え? オレの噂? 何だよ、それは」
顔を赤らめる兄貴を、わたしはからかいたくなった。兄貴の程度を確かめてやるんだ。
「お兄ちゃん、今回のことで何が一番大切かわかった?」
「何が一番かって?」
冒険することだって、兄貴は答えるに決まってる。それはそれで面白いけど、わたしの正解はそれじゃない。
兄貴はちらりと久美を見てから、そんなのは決まってるだろうと言った。
「何?」
「愛だ」
えぇ?――とわたしが大声を出したので、周りの人たちがびっくりして振り返った。わたしは恥じ入りながら、ごめんなさいとみんなに頭を下げた。それにしても、何だって正解を言うわけ? 兄貴は馬鹿だと思ってたけど、やっぱり頭がいいのかな?
「お兄さんてロマンチストなんですね」
久美がお愛想を言うと、ほんまじゃねと久美のお母さんもおかしそうにうなずいた。素直な兄貴が照れまくって、それほどでもと言ったら久美たちが笑ったので、兄貴もよくわからない様子で一緒に笑った。
「あ、風船!」
観光客の一人が叫んだ。見ると、窓の外を赤い風船が一つ、すーっと空へ昇って行く。下の広場で子供が手放してしまったらしい。風船が!――と叫びながら風船を見上げる子供が見えた。
目を風船に戻すと、風船の向こうにある白い雲が目に入った。真っ青な空をのんびりぷかぷかと浮かんでいる。わたしはその雲と心が通じ合った気がした。
うれしくなったわたしは、思わずみんなを振り返った。
「ねぇ、今ね、雲が笑ったよ。あそこの雲がね、わたしたちを見て笑ったんだよ」
兄貴と久美のお母さんはもちろん、久美までもが眉間に皺を寄せている。
わたしは久美の手を引いて青空を見せた。久美にだけはわかって欲しかった。でも、さっきの雲がどれだったのかがわからない。
うろたえるわたしを見て、久美は笑った。
「構ん構ん。春花はうちをびっくりさせてばっかしやけん、うちは春花を信じよわい。ほれにうちにもな、雲も青空も全部が笑とるみたいに見えるで」
「ほんとに?」
久美はうなずくと、今自分は生きているんだという実感があると言って、一つの雲を指差した。
「なんかな、おばあちゃんがあの雲に乗って、うちに話しかけとるような気ぃするんよ」
「へぇ。それでおばあちゃん、何て言ってるの?」
久美はうれしそうな顔でわたしに言った。
「雲が笑ろとるように見えるんはな、あんたの心が笑顔やけんよ――て」
きっと久美の言うとおり、あの雲には久美のおばあちゃんがいて、久美に話しかけたのだろう。おばあちゃん、今の久美を見て喜んでいるんだろうな。
そして、わたしもまた最高に幸せに違いない。だって、青空も白い雲も全部が笑ってるもの。
(了)